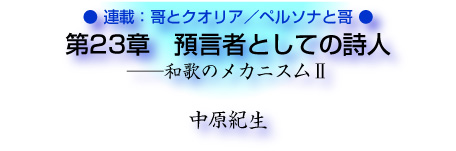|
■宇宙音声が飛び交い、アラベスクのごとく文字が立ち上がり絡まる場所
司馬遼太郎は『十六の話』に収められた「アラベスク──井筒俊彦氏を悼む」で、井筒俊彦の学問をめぐって、「古今東西の万巻の古典をそれぞれの言語で読み、それをつきあわせつつ、個人や集団がもっている無意識下の深層に入り、その混沌の本質をつかまえ、体系化した」と書いています。
《井筒さんの思索には、軸がある。古代インド哲学における最高価値である「空」(あるいは「無」)である。が、その軸が、場合によってセム的な人格を帯びたヤハウェやアッラーにかわることがある。
両者を往来する方法としてギリシャ哲学を、いわば道具として用いられた。道具が軸になって、ギリシャのソクラテス以前の自然神秘主義を、“宇宙音声”に似たようなすばらしい表現で体系づけられた。
ついには東西の思想が暗喩、もしくは明示した深層のなかに入りこみ、“通人類的”な深層を確認し、そこに普遍的な体系を構築された。》(中公文庫『十六の話』)
そういう人への、つまり、「東西の古典的神秘思想をあつかいつつも、その思想はつねに明晰」であり、また「言語を信じ、すべてを端正な日本語によって完璧に表現」した故人への誄詞[るいし]の表題に、司馬遼太郎は、豊子夫人が井筒真穂の筆名で発表した短編小説の題名を借用しています。「希代の哲学者の博捜と構築と表現を考えるとき、その鮮明さと流麗さ、さらには高度の形而上性とリズム感が、アラベスクということばにふさわしいようにおもえる」。
司馬遼太郎がくりだす言葉の数々、それらは、井筒俊彦の思想的営為がよってたつ方法論と、それがもたらす生理的感触のごときもの、そしてその成果物が放つ香気にいたるまで、過不足なく伝え、存分に讃える、まことに見事な評言になっています。とりわけ、「ギリシャのソクラテス以前の自然神秘主義」を歌うように叙述した名著『神秘哲学』の文体、というか抒情的昂揚感にうらうちされたその思想的息吹にあたえられた(「五大にみな響きあり」という語句を想起させる)呼び名は、「井筒さんの学問のしかたは、すべての思想的古典を、その国のその時代の言語で読むということである。/たとえばコーランを読むために、コーランが成立した時代のことばで読もうとし、当初は模索した。」と語られていることともあいまって、井筒俊彦の言語観(そして、翻訳観)の全貌を端的に指し示しているように、私には思えます。
さて、その井筒俊彦に、「哲学的意味論」という小文があります。第36回エラノス会議(1967年)に初めて(日本人としては、鈴木大拙についで二人目の)正式講演者として招かれた際、主催者から専門の領域を「哲学的意味論(Philosophical Semantic)」としてよいかと尋ねられ、最初はびっくりしたが、やがて、このレッテルへの意味付けの仕方いかんで、最近胸にいだいてきたイデーを他のどんな名称にもましてよく表現している、と思えるようになった。井筒俊彦はそう書いています。
《全然歴史と伝統を異にする哲学者たちを人為的に対面させ、語り合い理解し合わせるためには、先ずそこに共通した哲学的言語が成立しなければならない。諸国の哲学者たちの思想を、その精神の深みにおいて分析的に把握した上で、彼らに共通の言語を互いに語らせる知的操作がなければならない。このような哲学的共通言語を作り出すこと、それを私は哲学的意味論と呼び、その仕事を自分に課したいと思う。》(「哲学的意味論」、『読むと書く 井筒俊彦エッセイ集』)
ここでいわれる「精神の深み」、それは同時に(井筒俊彦の著書のタイトルにも使われた)「意味の深み」であり、また、司馬遼太郎の「通人類的な深層」につながり、そして、中井久夫がいうところの「言語の深部構造」もしくは「二つの言語のミーティング・プレイス」に通じているものでもあります。以前(第19章で)言及した中井氏の「訳詩の生理学」から、いまいちど引きます。
《私のいわんとするところを一言にしていえば、二つの言語、特に二つの詩──原詩とその訳詩──の言葉は、言語の深部構造において出会うということである。ここにしか、二つの言語、特に詩の訳のための二つの言語のミーティング・プレイス(出会いの場所)はない。もっぱら表層構造において出会いの場を作ろうとするから、翻訳は不可能かどうかという不毛な議論が生れてしまうのである。
私のいう「深部構造」とはチョムスキーの概念とはちょっと違っている。文法の深部構造だけが問題ではない。音調、抑揚、音の質、さらには音と音との相互作用たとえば語呂合わせ、韻、頭韻、音のひびきあいなどという言語の肉体的部分、意味の外周的部分(伴示)や歴史、その意味的連想、音と意味との交響、それらと関連して唇と口腔粘膜の微妙な触覚や、口輪筋から舌筋を経て舌下筋、咽頭筋、声帯に至る発声筋群の運動感覚(palatability とは palate 口蓋の絶妙な感覚を与えるものであって私はこの言葉を詩のオイシサを指すのに使っている)、音や文字の色感覚を初めとする共感覚がある。さらに非常に重要なものとして、喚起されるリズムとイメジャリーとその尽きせぬ相互作用がある。》(「訳詩の生理学」、『アリアドネからの糸』)
中井氏のいう「深部構造」もしくは「ミーティング・プレイス」、それはバベル崩壊後の詩人たちの(死後の)住み処であり、かのソシュールがアナグラム研究にうちこんだ領域でもあるにちがいない。私はそうにらんでいるのですが、それはともかく、この「深み」は、井筒氏がいうところの「言語アラヤ識」につながっていきます。『十六の話』の文庫版に附録として収録された、司馬遼太郎との対談「二十世紀末の闇と光」から、関連する井筒氏の発言を引いておきます。(「二十世紀末の闇と光」、『十六の話』)
◎阿頼耶識のどん底というか、西田哲学では「無底」といっていますけれども、「無底の底」というような世界を考えてみると、どろどろした本当のカオス的な世界で、無じゃない。無じゃなくて有なんだけれども、何ひとつ‘もの’が形をなしていない。そういう全体が無定形の言語的意味志向性のみの渦巻く世界で、神がそこに君臨している。
◎まず正確に観察するんです。そうすると、そのどろどろした無定形の意味志向性の「種子」がだんだんはっきりした存在イメージに転変しながら意識の表層領野に登っていき、現実の経験的な世界になってあらわれてくる過程が見えてくる。だから、唯識すべてが「識」であるということは、すべてが阿頼耶識の転換したものだということなんですね。
◎私にいわせれば、阿頼耶識とは、第一義的には、意味が生まれてくる世界なんです。意味というのは、存在じゃない。存在じゃなくて、「記号」なんですね。つまり、記号が生まれてくる場所。それが言葉と結びつくと言語阿頼耶識になる。言語阿頼耶識になる前に、言語以前の、純粋意味性の世界というものが「種子」の世界であって、それを唯識では名言種子[みょうごんしゅうじ]といっているんです。
◎結局すべてコトバだということですね。まだ言語そのものではないんだけれども、言語化されるべきものである。言語すなわち名称性を志向している浮動的流動的な意味単位の群れが自己顕現しようとして、いつも動いている内的場所。自己顕現して、たまたま因縁が合えば経験的な存在の世界になってあらわれてくる。それを、外的な世界だと思ったら、間違いになる。というのが、ごく簡単にいえば唯識の哲学的立場ですね。
ここにでてくる「どろどろした本当のカオス的な世界」や「どろどろした無定形の意味志向性の種子」といった言い回しは、東方ギリシア語圏のキリスト教神学で、神の三つの位格を示す「ペルソナ」にかえて使われた「ヒュポスタシス」(ラテン語 substantia の語源)に、「液体の中の沈澱物、固体と液体の中間のようなどろどろしたもの」という古い意味があったとする、坂口ふみ著『〈個〉の誕生──キリスト教教理をつくった人びと』の議論を想起させます。
(あるいは、坂部恵著『ヨーロッパ精神史入門──カロリング・ルネサンスの残光』の議論。いわく、西欧中世の普遍論争で、スコトゥス派(実在論)とオッカム派(唯名論)の対立は通常、個と普遍のプライオリティをめぐるものとされるが、パースは、「定まらないもの」(the unsettled)が最初の状態であるとするスコラ的実在論者の側に真実があるとして、その論争点をずらした。対立は個と普遍のいずれが先かではなく、それに先立ち「確定されないもの」と「確定されたもの」のどちらを先なるものと見るかにあるのであって、問題は、「むしろ、(パースはそこまで明言していませんが)、個的なものをどう捉え、ないしはどう規定するかにかかわるものである」。すなわち、実在論と唯名論の対立の因ってくるところは、「個的なものを、元来非確定で、したがって(ここが肝心のところですが)汲み尽くしえない豊かさをもち普遍者や存在をいわば分有するものと見なすか、それとも、まったく反対に、それを、いわば第一の直接与件として、しかも単純で確定された規定を帯びた、世界と思考のアトム的な構成要素と見なすか」という考え方のちがいにある。)
ここではこのことについて深追いすることはせず、「哲学的意味論」と「翻訳」の関係について、若松英輔氏が『井筒俊彦──叡知の哲学』で、「コーラン入門としてはもとより、井筒哲学の基礎的構造が論じられた「井筒俊彦入門」としての役割を持っている」と評した著作を通じて、(宇宙音声が飛び交い、アラベスクのごとく文字が立ち上がり絡まる場所、いわば共感覚的な言語フィールドにおいて)、考えをめぐらせてみたいと思います。
■言語事件としての啓示─コーランを読む1
井筒俊彦著『コーランを読む』の第一講に、啓示の記録であるコーランを「読む」とは、いったいどのようなことなのかをめぐる議論がでてきます。たかだか六頁ほどの短いもので、語られている内容もきわめて平易なのですが、(その表層にあらわれた外見にかかわらず)途方もなく深く濃い内容をはらんでいると思うので、すこし丁寧にフォローしておきます。
啓示とは一つの発話行為(ソシュールのいわゆるパロール)にもとづく「れっきとした、まぎれもない言語現象」である。ただしそれは通常の場合と違う一方交通の言語的コミュニケーション。一方向であるがゆえに、神のコトバの聞き手=ムハンマドという名の個人(B)が話し手=アッラーという名の神(A)に「語り返す」ことは決してない。
この神のコトバを受ける人のことを「預言者」(ナビー)という。イスラームの根本的な考え方によると、「預言」が起こったとき、神のコトバが預言者に届いて了解されそのままそこに停止してしまう場合と、預言者が自分の預かった神のコトバをそこにとどめてしまわないで他の人に伝達する場合とがある。この後者、「第二次的言語主体としての資格における預言者」のことをイスラームでは特に「使徒」(ラスール)と呼ぶ。コーランの考え方では、預言者であり同時に使徒でもある人の典型はモーセやイエス・キリストで、ムハンマドは人類の歴史に現われた最後の預言者にして使徒である。
神が預言者に語りかける度ごとに発話行為(パロール)が一つの「言語事件」として起こる。それらの積み重ねがコーランに記録されている。しかし、コーランはたんなる発話行為の集積であるだけではない。なぜならそうした「言語事件」がエクリチュール、文字言語、書記言語の次元まで引き上げられているから。文字に書かれているということは決して些細なことではない。発話(パロール)が文字に書かれ、書記言語(エクリチュール)のレベルに入って一つの言語テクストになると、コトバの性質が変わってしまう。言語的コミュニケーションの直接性がなくなり、発話行為特有の具体的な状況(シチュエーション)から切り離されてしまう。
エクリチュールとしてのコーランは「神が預言者に語りかけたという具体的な言語行為の場」から切り離されているから、「最初の発話の状況に居合わせなかった人々」でも自由に解釈できる。事実、イスラーム文化はいい意味でも悪い意味でもコーランを自由に解釈し、それを積重ねることによって成長してきた。だが、私=井筒はそのようなコーランの「創造的解釈」とは逆の方向に進めてみたい。
「つまり、エクリチュールとして与えられている『コーラン』のテクストを、もとの状況[シチュエーション]まで引き戻して、神が預言者に親しく語りかけるという具体的な発話行為[パロール]の状況において、『コーラン』のコトバをまず理解する。そして、そのような原初的テクスト了解の上で、さらにもう一歩進んでその奥にあるものを探ってみたい。神(A)が語りムハンマド(B)がそれを了解する、その第一次的言語コミュニケーションの底に伏在し、それを下から支えている根源的世界了解、存在感覚、気分的世界像、とでも呼ぶべきものを探り出してみようというのです。」
自由な創造的解釈とは逆の方向でコーランを読む(解釈する)。つまりエクリチュールとしてのコーランのコトバをパロールとしてのコトバの「濃密な状況性」のなかに引き戻し、パロールの底に働いている下意識的意味聯関まで掘り下げていって、そこに『コーラン』特有の世界観や存在感覚のようなものを浮かび上がらせる。いいかえると「『コーラン』のリアリティとの同時代性を我々が自分の中に、文献学的に再構成する」。これらの事柄の意味、とりわけ後段の「存在感覚」探求の意味合いについては、第二講の「『コーラン』の解釈学」の項で、(井筒言語哲学の基本フォーマットの呈示とともに)より詳細に語りなおされます。
ある具体的な状況においてパロールが生起するためには、話し手Aと聞き手Bの両者に共通する言語記号のコードがなければならない。言語学ではそれをラング(langue)と呼び、私=井筒は「内的言語」と呼ぶ。言語記号のコードとか体系などというとすっきり整理された組織体みたいな感じだが、それは表面の事態であって、その深みに入ってみるとたちまち混沌として捉えどころのないものにつき当たってしまう。
そのような「下意識的領域」もしくは「人間の言語意識の深層領域」に拡がる「意味」の次元では、コトバで固定された意味と、「コトバできっちり固定されていないが、しかし今にもコトバを生み出しそうになっている、つまり本格的な意味になりそうな状態にある、半意味体とでもいうべきもの」や「自分を表現してくれるコトバを手探りしつつあるような、いわば現に生みの苦しみをなめつつあるとでもいえるような、意味の可能体」とが混在しており、それらが縦横無尽に錯綜する糸で結ばれて連鎖をなしている。
《日本の連歌、俳諧の付合の技法などに極端にまで押し進められた形で現われていますように、意味の連鎖関係というものは実に不思議なものです。一人が句を出す(前句)と、その次の番に当たる人がそれにつながる句を付けていく(付句)。前句と付句とは基本的につながっているのですけれど、そのつながりの屈曲が実に微妙で面白い。連歌の出来ていく過程を見ていると完全にでき上がった意味ばかりじゃなくて、半分出来かけた意味みたいなものが、一座の人たちの間主観的意識の底にあって、それが不思議な連鎖の流動体をなして働いている有様がよくわかる。といっても、決して日本の連歌、継句だけに特有な事態なのではありません。いつでもどこでも、人間の言語があるかぎり、その意味構造はそうしたものなのです。》(『コーランを読む』)
このような「意味聯関のつくり出す下意識的領域」を私=井筒は「潜在的意味空間」とか「言語アラヤ識」と呼ぶ。それはラングという言語記号の体系の意味論的底辺にあたるもので、すべての発話はその発現である。表面に出ているコトバの底には「不思議なドロドロした流動体的な意味エネルギーみたいなもの」が強力に働いている。人間の下意識の薄暗いところにひそみ、いちいちの発話を通じて発動してくるそうした複雑な意味連鎖のことを「一種の存在感覚、あるいは原初的な世界像」といったらいいと思う。
そういう観点からコーランを見てみると、一つ一つの発話の底に非常に特殊な存在感覚が伏在していることに気付く。コーランの個々の発話としてのコトバは断片的、切れぎれで有機的全体性に欠けているが、その底には全体的な世界了解がある。「気分的には、それは漠然たる存在感覚であるかも知れませんが、本当は一つの複雑な意味聯関的全体構造なのです。」
■意味論的解釈学と存在感覚─コーランを読む2
井筒氏は、第三講でもくりかえし、コーランを「読む」という解釈学的操作、すなわち「意味聯関の深みから発話行為の表面に現われ出てくる意味を捉え分析する方法」を語っていて、そこでは、「『コーラン』に限らず、一般に古典的言語テクストを解釈する方法」に対して「意味論的解釈学」の名があたえられます。
それでは、その井筒氏が提唱する意味論的解釈学によってあぶりだされるところの、コーランの「存在感覚」とはなにかというと、それこそまさに『コーランを読む』という書物の全篇にわたって追究されるテーマであって、「あらゆるものが、天にあるもの、地にあるもの、すべてがただそこにあるということで神を賛美している」という「存在即賛美」や、「もう何を見、何を聞いても、ありとあらゆる事物、事象についてそれがしみじみ深い喜びとして経験される本源的な実存感覚」(159頁)、等々の切れぎれの言葉を抜き書きするだけで、神による「創造」や第二の創造としての「復活」といった出来事にたいする(身体的といってもいい)リアリティの感覚がおぼろげながら浮かびあがってくるのではないかと思います。
そしてそれは、第九講で語られる、預言という宗教現象がそこにおいて成立する「底の知れない闇のような実存の世界」、すなわち「存在の夜」の「感触」をめぐる叙述(そこでは、「存在感覚」は「世界感覚」といいかえられている)のなかでクライマックスに達します。
《イスラームの宗教性を底辺部で支えている一種独特の世界感覚なるものを考えてみると、「存在の夜」という形象が浮んでくるのです。存在の昼じゃない、夜です。近代人なんかには想像もできないような一つの不思議な現実がそこに開けてくるのですね。(略)
しかし、遠い昔の書物、いわゆる古典、を読むためには、そのテクストが成立した現場といいますか、生きたシチュエーションが、読む人のなかに再現されなければいけないと思う。これは、いちばん最初にお話しましたパロールのシチュエーションに当たります。『コーラン』の場合には、神がムハンマドに話しかけるそのパロール、発話行為を取り囲んでいるシチュエーションがはっきりつかめないと困る。それを私は『コーラン』の世界感覚という表現で定着させようとしているわけです。
そこで、『コーラン』的パロールのシチュエーションを具体的につかまえようとしてみると、それが暗い夜の世界だということがすぐわかってくる。我々には、ちょっと想像もできないほど陰湿な世界で、それはあるのです。陰湿とか暗いとかいうと、何だか嫌がっているみたいですけれども、別に否定的価値評価をしているわけじゃない。客観的事実なのです。『コーラン』を読むためには、暗い夜の感覚といったものが我々にどうしても必要になってくるのです。》(『コーランを読む』)
議論は続きます。
興味深いものをとりあげるならば、コーランの表現形態をレトリック的にみると、「レアリスティック/イマジナル/ナラティヴ」の三重構造をなしていて、それは、コーランのテクスト発展史を言語主体の意識と関連させた場合の、初期=巫者(シャーマン)的イマージュ、中期=物語、後期=歴史的事実・法律の規定、に対応していること。そして、このようなレトリックの三つの層からなるコーランの全体を渾然たる統一体に保つものが、「長短さまざまの文あるいは句を脚韻の繰り返しで…ちょうど太鼓の拍子、ドンドン打っていくその打ち方のように、リズミカルにコトバを区切っていく」散文形式、「サジュウ調」と呼ばれる神託の文体であったこと。
ちなみに、若松英輔氏は、前掲書第七章「天界の翻訳者」で、井筒俊彦の二度にわたるコーラン翻訳の試みを、「「意味の深み」における「読み」の追究」であり、「野心的なといってよい「哲学的意味論」の実践」であったとしたうえで、「サジュー調はコーラン全編を貫いている。井筒はこのサジューの言葉を、今、発せられたコトバとして蘇らせようとしている。古く千四百年ほど以前にムハンマドに降下したという歴史的事実から、言葉を再び今に解き放とうとしている。」(『井筒俊彦』)と書いています。(司馬遼太郎が、「コーランを読むために、コーランが成立した時代のことばで読もうとし」た、と言っていたのが、このサジューのことでしょう。)
いまひとつ引きます。『コーランを読む』の最終、第十講「啓示と預言」では、神の啓示がアラビア語で下されたことをめぐって、次のような議論が展開されています。それは、「神のコトバ」が神のもとで原初的にアラビア語だったことをしめしているのではない、それが具体的にどんなコトバだったかは誰にもわからないが、ムハンマドというアラブの預言者を通じてアラブ民族に伝達されたときに、アラビア語として啓示されたのだ、と。
《神のもとから、何語だか知らないけれども、永遠のコトバで書かれているものを、アラビア語にしながら。──今のコトバでいえば、アラビア語に翻訳しながら──ムハンマドに伝えたのは誰だったのか。啓示についての普通の考え方でいきますと、神が‘直接’語りかけたということになるのでしょうが、イスラーム本来の考え方では、天使ガブリエルが、仲介者として、神のコトバを預言者のところへもってくるということになっている。普通のコミュニケーションとちがって第三者が入っているのです。
(略)ですから、これは普通の言語のように話し手と聞き手だけの問題ではなく、そのあいだに仲介者、第三項が入ってくる。三項関係のパロール構造です。二項関係じゃない。》(『コーランを読む』)
翻訳者ガブリエル、あるいは、啓示とは翻訳である。ここには、なにか深甚な領界への思索の手がかりがひそんでいるように思います。ここで私が考えてみたいのは、古典和歌を「読む」ということの意義についてです。井筒氏の議論を参照すると、それは次のようなものになるでしょうか。
……古典和歌を読むこと、すなわち、和歌をめぐる意味論的解釈学の操作とは、エクリチュールとしての和歌を原初のパロール=〈聲〉のうちに、すなわちカミ(迦美)のギフト(純粋贈与)としての〈哥〉の到来や発生をめぐる濃密な具体的状況性のなかに引き戻し、そのパロールの底に働いている下意識的意味聯関にまで掘り下げたうえで、そこから和歌に特有の存在感覚や世界感覚のようなもの、たとえば、「もののあはれを知る」といった和歌的体験の実質を浮かびあがらせることである。
(ちなみにいえば、こうした王朝和歌のコトバの最低部にうごめくドロドロした意味連鎖の流動体が、歌の詠出をめぐる作法や規範(たとえば、上句と下句のあいだの転換の重さ)の弛緩とともにあからさまに噴出するようになったのが、和歌の滅びの後に猖獗を極めた連歌、俳諧の類であった)……。
ここで想起されるのが、和歌の言葉(仮名文字)は偽装された日本語音であり、和歌は紙上のパロールだとする神田龍身氏(『紀貫之──あるかなきかの世にこそありけれ』)の議論です。そこに、「やまとうた」は声にだしてうたわれる「和歌」ではなく、文字によって書かれる「倭詩」として成立したとする『中世の文学伝統』の議論を(表面的に)むすびつけると、さきに述べた原初のパロールとしての〈聲〉や〈哥〉といった観念そのものが、(ひいては、「もののあはれを知る」といった和歌的体験なるものもまた)、貫之を代表格とする王朝和歌の高度に洗練された言語技術の遣い手たちによって偽装されたフィクションである、といった事態がなりたっているのかもしれません。(俊成が、「かの古今集の序にいへるがごとく、人のこころを種として、よろづの言の葉となりにければ、春の花をたづね、秋の紅葉を見ても、歌といふものなからましかば、色をも香をも知る人もなく、何をかはもとの心ともすべき」と書いていたように。)
そして、そのようにとらえてこそ、貫之以後の王朝和歌を純粋詩として、すなわち、西脇順三郎がいうところの「メカニスム(機械)」(純粋意識から来る魂の喜びを直接に表現するのでなく、ただ実感ゼロの純粋意識の世界を起すメカニスムを与える純粋芸術)としてみる根拠が鮮明になるのかもしれません。が、私の立場は折衷的です。(かつて、第15章、第16章で、神田前掲書にあらわれた貫之像と、山田哲平氏が「日本、そのもう一つの──貫之の象徴的オリエンテイション」で描いた、もう一つの貫之像とを比較考察した際、論じたように。)
かんたんにいってしまえば、詞が先か心が先かといった、「やまとうたは、人のこころをたねとして、よろづのことのはとぞなれりける」の貫之歌論がもつ両義性を受け入れて考えたいということです。いわば、和歌的体験を実数、和歌のメカニスムを虚数とみた複素数、あるいは、詞の論理と心の論理(感覚、感情、思ひの論理)との複論理のもとで貫之の和歌の世界を考えていきたいということです。
■意味論の根本原理
すこし寄り道をします。
井筒俊彦に「意味論序説──『民話の思想』の解説をかねて」という文章があります。「畏友」佐竹昭広の著作の文庫解説として、この書物の「思想を構造的に分析し、その底流に伏在する学的原理を解明するという、興味深い、しかしまたすこぶる困難な役割を担う」ために書かれたものです。そこで、井筒氏は、佐竹昭広の学問とその独創的な思考を特徴づける「学的原理」を、「全ての言語現象を、表層・深層の別なく、統轄する凝視の姿勢」あるいは「あらゆる対象にたいする意味論的アプローチ」と名づけたうえで、『民話の思想』に伏在する「潜在的意味論」を曳き出し、それを顕在的状態における「意味論的構造分析のテクニーク」として解明しているのですが、実は、それらは井筒俊彦自身の意味論の「序説」もしくは「根本原理」の粗筋を叙述したものになっています。
以下、「有機的フィールド構造説」とでも名づけるべき井筒意味論のエッセンスを、箇条書きのかたちで抜き書きします。
1.ソシュール革命に始まる
考察は、次の「最も基本的な一点」から始まる。「「意味するもの」と、「意味されるもの」との結び付きとしての意味現象とは、そもそもどのような基礎構造をもつものであるのか。」(310頁)この問いに対する、「ある革命的な──言語学だけでなく、より一般に哲学的にも、革命的な──立場」を宣言したのが、かのソシュールの「意味現象内在化」の説である。
《それは、簡略化して言えば、「意味」なるものがそっくりそのまま内的事態である、ということである。「意味するもの」と「意味されるもの」との両側面を合わせて、全体を心内の事態、意識内部に起る事態、に還元してしまうのだ。全ては言語主体の意識の内面だけに生起する事柄であって、いわゆる外的世界、我々の外[ソト]に客観的に実在する世界(本当はそんな世界が‘実在’するかどうかが哲学上の大問題なのだが、いわゆる外的世界の実在性・非実在性はここでは問わないことにして)は完全に「意味」の柵外に追い払われてしまう。ここでは、‘外的’事物は全て、言語意識が己れのまわりに織り出す主体的意味連関の網目の一環になってしまうのだ。》
ソシュール以前の言語学では、「リンゴ」という語は目の前の一個のリンゴ(物的対象)を指示する。これに対してソシュールは、語が物(外在的対象)を指すのではなく、機能的複合体としての語の一部(意味する側、語の音的側面、シニフィアン)が同じ語の他の部分(意味される側、意味内実的側面、シニフィエ)を指示する、つまりシニフィアン、シニフィエはともに「心的形象」(心象、心的イマージュ)なのであり、「全てが心の限界内での出来事であって、外的事物事象、外的世界は、少なくとも‘第一義的には’、意味現象の構造の中に入ってこないのだ」と考える。
ところが、ソシュールは『一般言語学講義』の中で、シニフィアンを「聴覚映像」(image acoustique)と名づけ、シニフィエを「概念」(consept)と呼んだ。「もともとソシュールの理解するところに依れば、シニフィアンもシニフィエも、それぞれ心象(image)であって、その点では両者のあいだに差異はない。それなのに、なぜソシュールはシニフィアンの方にだけ image という語を使い、シニフィエには concept のような曖昧な語を当てたのだろうか。」それは、この時期のソシュールが、言語なるものの観察をその表層だけに限っていたからだ。社会制度的表層において記号コード化された形で働く言葉の「意味」は、概念的一般者としての意味である。「例えばキというシニフィアンは「木」一般を意味し、ヒトは「人」一般、ウマは「馬」一般という具合に」。
議論は、表層的、社会制度的、社会学的見地からの一般的な「意味」とは異なる、意味論的な「意味」とはなにかへと進んでいく。
2.深層的、下意識的、意味論的見地からみた意味
意味論的「意味」は、東洋的言語論を代表する唯識学の伝統に従い、意味なるものを、「コトバの表層における社会制度的‘固定性’」に限定せず、「下意識的あるいは無意識的深層における‘浮動性’の生成的‘ゆれ’」(309頁)のうちに把捉する。現代西欧の思想界では、「無意識はコトバである」とするラカンの深層意識論が、唯識哲学の中核をなす「言語アラヤ識」論の系統に属している。
2-1.鈴生りの果実のギッシリ詰まった一房
意味論的「意味」は、「概念的・抽象的で一義的な一般者ではなくて、複雑に錯綜する浮動的な内部分節構造を持ち、個別的具体的状況に応じて柔軟に機能する一般者」である。「意味論的「意味」現象の成立においては、シニフィアンは一つだが、それに対応するシニフィエの方は、原則的に、一義的ではない。一義的でないということは、しかし、直ちに多義的ということでもない。通常の、いわゆる多義性とは本質的に形態を異にして、それは様々に異る意味構成要素の寄り集る一群である。鈴生りの果実のギッシリ詰まった一房とでも言おうか。互いに交錯し、多重多層に結び合う、多くの意味構成要素の、濃密な有機的全体である。(略)言い換えれば、ここでは「意味」はひとつの有機的フィールド構造としての内部分節的拡がりなのであって、それを構成する個々の要素、がシニフィアンに対応する「意味」、すなわちシニフィエ、なのではない。」
《ハナというシニフィアン。ソシュールなら、これに対応する一義的シニフィエとして、なんの花ともつかぬ漠然たる‘花一般’(それが一体、正確にはどんなものであるのか私には分らない)の図形を描くだろう、全ての草木に共通する「花」の概念的形象として。だが、そんな概念的一般者としての「花」は、日本語の意味論的「意味」から程遠いことを我々は知っている。博物学上の術語としてならいざしらず、我々日本人の生きた言語感覚では、ハナというシニフィアンに対応するシニフィエには纏綿たる情緒の縁暈がある──と言って言い過ぎなら、少なくともそういうことを非常にしばしば我々は経験する。特に「花」という語がパトス的言語主体の‘なま’の声である場合には。そしてそれこそ、いま一言した言葉の意味のカルマの働きを端的に示すものなのである。》
2-2.意味のカルマ的本性
たとえば、本居宣長のほとんど妄執というに近いあの烈しい桜花への情熱、あるいは鴨長明の歌論書「無名抄」の有名な一節(「桜をば尋ぬれど、柳をば尋ねず」云々)、さらに古くは古今集歌「しず心なく花の散るらん」(紀友則)の底知れぬ憂愁、春の夜の夢の幻想の中で散る桜(貫之歌「やどりして春の山べに寝たる夜は夢のうちにも花ぞ散りける」)、下ってはあまりに有名な西行歌「ねがはくは花のもとにて春死なむ」。
《このようなものは、全て遠い昔の話であって、現代生活を忙しく生きる今の我々の日本語にはもはやなんの関わりもない、と、もし言う人があれば、それは一般に言語なるもののカルマ的本性を知らない、あるいは敢えて無視する、ことから来る誤解であろうと思う。
言語のカルマ性、すなわち意味のカルマとは何か。意味のカルマとは、かつて言語的意識の表層において現勢的だった──つまり顕在的に機能していた──意味慣用が、時の経過とともに隠在化し、意識の深層に沈み込んで、そこでひそかに働いている力のこと。意識の深底に隠れて、表面にはほとんど姿を見せないが、しかしその反面、隠在的であればあるだけ、見方によっては、かつて現勢的であった時よりも、はるかに強力で、執拗に現在の我々のコトバの「意味」を色付け、方向付ける重要な要因となっているのだ。このように、心の不可視の奥底に累積されて、下意識的に生き続けている古い意味慣用、それを意味のカルマというのである。》
唯識派哲学は、意味のカルマの一々を「言語種子」と呼び、数限りない意味のカルマが蓄積される場所(トポス)を「アラヤ識」と呼んだ。「そこに集積された意味のカルマは、複雑に絡み合い縺れ合い、互いに反発し合い相互に融解し合いつつ、新しい「意味」を生成していく。(略)「言語種子」、コトバの、コトバへの、可能体。」
3.意味分節は存在分節である
意味とは、存在論的に、いかなるものであるか。われわれが通常、存在者および存在世界として感知している事物事象は、意味分節によってはじめて現象的に自己を開示する。「意味的な差異化と識別性がなければ、様々に異る事物事象から成る存在世界なるものは存在し得ない。私=井筒はこの事実を、「意味分節は存在分節である」(意味分節・即・存在分節)という基礎命題の形にフォーミュラ化して表現する。」かくして、「意味論的「意味」は、我々の言語生活の現場に溌剌と躍動する生命の流れを組み込んだ理論を要求する」。
《我々の普通一般の言語生活において、知覚・感覚的認識経験の基礎をなす生きた意味論的「意味」の場合は、むしろ分節の浮動性こそ原則的なのであって、この事態が、上述した意味構成要素の有機的集合体としての意味フィールドの拡がりを根本的に特徴づけるのである。意味論的「意味」を根本的に特徴付けるこの事態が、これまた上述した言語的「アラヤ識」の、より根源的な事態に基くことは言うまでもない。》
■コトバの神秘哲学、あるいは存在の風
議論を先に進めるための補助線を引きます。
若松英輔著『井筒俊彦──叡知の哲学』の第六章「言葉とコトバ」、「和歌の意味論」の項を中心に展開されている議論です。司馬・井筒の対談「二十世紀末の闇と光」のなかで、井筒俊彦が、「私は、元来は新古今が好きで、古今、新古今の思想的構造の意味論的研究を専門にやろうと思ったことさえあるくらいです」と語ったことをふまえ、若松氏は次のように書いています。
《「思想的構造」あるいは「哲学的」と彼が断るように、井筒俊彦がいう意味論とは、言語学の領域に限定されない。言語学は通常、事物を軸に、それを呼ぶ言葉、そして言葉の意味へと論を進める。しかし、井筒俊彦の意味論は遡源的に進む。すなわち、「コトバ」→意味→言葉→事象へと展開する。「コトバ」は意味へと自己を分節し、意味は言語を招き寄せ、エネルゲイアとしての言語はエルゴンとしての事象を喚起する。井筒にとっての言語哲学とは、言葉に「意味」を探るというよりも、「意味」に「存在」へと回帰する道を見つける営みである。私たちは万葉の歌を前に、意味の知的理解の以前に心動かされる。それは表層意識とは別な「意識」が、始原的境域から吹く「存在」の風を看取しているのである。》(『井筒俊彦』)
ひとつ、註釈を挿入します。
引用文にでてくる「コトバ」は、井筒哲学の最重要の語彙で、若松前掲書によると、「存在はコトバである」という一節(『読むと書く』に収められた講演録「言語哲学としての真言」が初出)に井筒俊彦の学問は収斂されます。いわく、「「存在」[=絶対的超越者の異名]が「存在者」を「創造」するとき、「存在」は「コトバ」として自己展開する。コトバとは事象が存在することを喚起する力動的な実在、すなわち存在を喚起する「エネルギー体」に他ならない。」「叡知[ヌース]も霊[プネウマ]も「心真如」も、彼には「コトバ」の姿をもって現れた。井筒俊彦の「コトバ」は、言語学の領域を包含しつつ超えてゆく。バッハは音、ゴッホは色という「コトバ」を用いた。曼荼羅を描いたユングには、イマージュ、あるいは元型が「コトバ」だった。」
エネルゲイアもしくはエネルギー体としての言語(「言語はエルゴン[=作品]ではなく、エネルゲイアである」というフンボルトの言葉に由来する)に関連して、いまひとつ、引用を重ねます。
若松氏は、井筒俊彦が『ロシア的人間』で、プーシキンの詩をめぐって、「この詩の稀有な、純粋な「調和」を成り立たせているものは、筋や意味ではなくて、意味の内容を遥かに超えたある‘言い難きもの’、ブレモン師が純粋詩(poe'sie pure)と呼ぶところの‘何ものか’なのだ」と書いたこと、そして、そこで言及されるアンリ・ブレモンが、純粋詩にあって言葉は啓示的に現象し、詩人の役割は言葉を探すことではなく自らを通過する何ものかの純粋な表現の場となることにある、つまり詩人は言葉を何ものかに託されるのであり、その究極態は祈祷の言葉となる、と論じたことにふれたうえで、次のように書いています。
《「純粋詩」が生まれるとき、人間は主体的受動態にならざるを得ないというブレモンの思想の背景には、創造における神の絶対性と、人間の限界についての明確な認識がある。私たちは、ブレモンの言葉を、詩は祈りにならなくてはならないという風に読むべきではないのだろう。彼は、祈りすら、人間は与えられなければ行うことはできないと考えている。「祈り」とは祈願ではない。言葉によって超越者を闡明することである。
そうした人間の典型として、私たちは預言者を想起することができる。あるいは、旧約聖書の預言者たちが、詩人だったように、「クロオデルもまた預言者にして詩人である」(「詩と宗教的実存」)という井筒の言葉がここに重なり合う。詩人たちは自分の言葉を持たない。「神」からのコトバを得ることによってのみ、十全に主体性を表現する。
「純粋詩」は純粋現勢態、エネルゲイアである。だから、理解されることで、使命を終えない。「己が死灰より甦り、今まで自からが在ったところに無際限に再び成るように、できている」(ヴァレリー「詩話」)。それを「絶対言語(le Verbe)」といったのはマラルメである。ヴァレリーは十九歳のとき師となるマラルメに出会う。『意識と本質』の読者は、井筒俊彦がマラルメをきわめて重要な人物として論じたことを思い出すだろう。》(『井筒俊彦』)
若松氏は、「和歌の意味論的研究が著作にまとめられなかったのは残念だが、『意識と本質』には、その一端を思わせる論述がある。」と指摘しています。それは、まさにマラルメとの、さらにリルケや芭蕉との対比のもとでみられた王朝歌人の歌の世界、そして、万葉の時代の共感覚的な「見ゆ」の世界との対比のもとでみられた、新古今の時代の「眺め」のはたらきを論じる文脈のなかにでてくる議論です。以下、稿をあらためます。
(20号に続く)
★プロフィール★
中原紀生(なかはら・のりお)1950年代生まれ。兵庫県在住。千年も昔に書かれた和歌の意味が理解できるのはすごいことだ。でも、本当に「理解」できているのか。そこに「意味」などあるのか。そもそも言葉を使って何かを伝達することそのものが不思議な現象だと思う。
Web評論誌「コーラ」19号(2013.04.15)
<哥とクオリア>第23章:預言者としての詩──人和歌のメカニスムⅡ(中原紀生)
Copyright(c) SOUGETUSYOBOU 2012 All Rights Reserved.
|