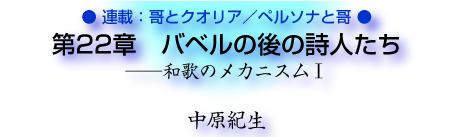|
|
|
Web評論誌「コーラ」 |
|
■創刊の辞 ■本誌の表紙(目次)へ ■本誌のバックナンバー ■読者の頁/ご意見・感想 ■投稿規定 ■関係者のWebサイト ■プライバシーポリシー |
|
<本誌の関連ページ> |
|
■「カルチャー・レヴュー」のバックナンバー ■評論紙「La Vue」の総目次 |
Copyright (c)SOUGETUSYOBOU |
|
|
|
これより先の数章は、ラカン三体とパース十体(さらには、貫之三体と定家十体)の錯綜した関係(もしくは、無関係)をめぐる挫折した論考の後始末、いいかえれば、余情というよりは未練の、倒錯した残心の構えでもって試みた落穂拾いの顛末記です。いわば、「ラカン三体とパース十体・残」の巻。
■和歌という意識
前章で、吉本隆明(『初期歌謡論』)による定家十体二重構造の説(定家十体を、幽玄様・長高様・有心様・事可然様・麗様という、「追いつめられた純粋詩」の世界に充てられる五つの歌体群と、見様・面白様・濃様・有一節様・拉鬼様という、「今様の歌曲俗謡の世界が、和歌的な声調に圧倒的な力で浸透してきたこと」がもたらす和歌形式の崩壊の危機への「何らかの意味での救抜(Erloesung)」のために設定された五つの歌体群とに二分する)をめぐって、純粋詩としての和歌を味わい、感銘を受けるためには、鑑賞者自らが作者となって、その当の歌をオリジナルな自作詠として「いひいだす」のでなければならない、といった趣旨のことを書きました。このことに関連する話題を二つ補います。
その一。風巻景次郞著『中世の文学伝統』は、聴覚を媒介とする「うたわれた歌」もしくは「音楽的詩歌」としての「歌謡」(楽器にあわせて詠ずる「歌」と無伴奏で詠ずる「謡」)、そして視覚を媒介とする「書かれた歌」もしくは「文字的詩歌」としての「創作詩」(文字にたよった「読む歌」)とを区分し、そのうえで、「和歌は、その伝統の確立するはじめにおいて、文字にたよる創作的詩歌であり、随ってまた、宮廷を中心として嗜まれる宮廷文学であるという性質を身に著けた」と断じています。以下、風巻氏の議論を引きます。
同書冒頭の一文、「草木のさやぎにも神の声が聞かれた遠い古の代から、歌は神や人とともにあった。」、にいうところの「歌」は、文字どおり口承されうたわれた「うた」だったのが、大化の改新の後、中国文化の輸入とともに本格的な漢字漢文の移植がすすみ、宮廷を中心に「からうた」(日本人が漢語でつづる漢詩)が日本列島の上に根をおろすようになると、それに対立して「やまとうた」(同様に、日本人が日本語でつづる和歌)の意識も宮廷を中心として成り立ってきた。
それでは、もうひとつの詩歌の類型、つまり聴覚を媒介とする「うた」の方はどうなっていったのか。
以上は、十八の節からなる『中世の文学伝統』の最初の節、いわば序説的部分からの抜き書き。(ちなみに、井筒俊彦は、『図書』が1987年におこなったアンケート、岩波文庫「私の三冊」に応えて、『善の研究』(西田幾多郎)、『旧約聖書 創世記』(関根正雄訳)とともに『中世の文学伝統』を掲げ、次の評言をそえている。「日本文学史の決定的に重要な一時期、「中世」、への斬新なアプローチを通じて、文学だけでなく、より広く、日本精神史の思想的理解のために新しい地平を拓く。」)
最後に、定家の時代、純粋詩の表現世界が俗謡の声調により追いつめられていった、とする吉本氏の見立てにかかわる議論を引きます。いわく、定家は「毎月抄」で十体に説き及び、中でも有心体を最上とするが、俊成が「恋せずば人は心もなからまし物のあはれもこれよりぞ知る」と歌ったといわれるように、物のあわれを知るのが「心有る」ことなのであって、定家が(麗様・長高様・濃様・見様などの多い新古今調がぴったりしなくなり)専ら有心ということを強くいうようになったのは、和歌は「詩」がなければ駄目だということの警告なのであった。ただ問題は、その「詩」が野生的な生活に結びついているものでなく、古典文芸、たとえば『白氏文集』の鑑賞によって培われる一種の雰囲気だったことにある。
■この不可思議なるパイプオルガン
その二。西脇順三郎は、『ボードレールと私』に収録された「超現実主義詩論」で、経験意識の世界(実感もしくは現実の世界)を作る「不純芸術」と、純粋意識の世界(実感ゼロの世界)を作る「純粋芸術」とを区分しています。(ちなみに、井筒俊彦は、追悼文「追憶──西脇順三郎に学ぶ」に、「西脇先生を生涯ただひとりの我が師と思っている」と書き、また、「西脇先生と言語学と私」では、「コトバにたいする、やむにやまれぬこの主体的関心の烈しさを通じて、結局、私は今でも西脇先生の門下生の一人なのだ」と書いている。)
いわく、「芸術は表現であるということは是等の世界[経験意識の世界と純粋意識の世界]を作る方法のメカニスムを表現すること」なのであって、「純粋芸術と不純芸術とが根本的に相違するところはそのメカニスムである」。すなわち、不純芸術においてはその作品に表現されている対象中に美感を構成するメカニスムが存在しているのに反して、純粋芸術の作品に表現されている対象中にはそのようなメカニスムは存在していない。
またいわく、純粋芸術とは「経験意識の世界即ちモア(moi)の世界を消滅せしめる一つのメカニスム」であり、「不純芸術より必然的に到着するところの芸術の形態」である。モアの世界の消滅とはすなわち自我の無限の拡大であり、自我と宇宙が合体し無限の形態を取ることである(ポール・クローデル『詩法』)。この純粋芸術のメカニスムは次の二つの構成要素からなる。第一に、「エステティクの世界[経験意識の世界]に於て二つの相異りたる経験意識を[神や美といったプラスの世界と、悪魔、悪、プロスティチューショオン及びグロテスクなるものからなるマイナスの世界という相反する二つの要素を]聯結すること。」第二に、「強烈なる生きんとする力。換言すれば美を求めんとする‘強烈すぎる力’が必要である。この力がなければ第一にあげたメカニスムは単にコミックな効果にのみ終るのである。」
さらにいわく、「純粋芸術の表現の対象は純粋意識を起さしむるメカニスムそれ自身」であって、ボードレールの詩に表現されているのは経験意識の世界に属する要素や心象だが、しかしこれらのものを純粋意識をもたらすメカニスムとしてとりあつかわないと、ボードレールの詩の批評を誤る。ポーが「マルジナリア」の附録で、ハムレットをドラマのメカニスムとして見るのではなくドラマからはなして一人の倫理的人物としてあつかう評論家を批判したのと等しく、ボードレールの詩と(常に詩という活動から出来ていたその)生活を一つのメカニスムとして見るのでなければ、ボードレール批評も一つの人生批評に終わってしまう。
和歌もまた、とりわけ、吉本氏が「追いつめられた純粋詩」の名のもとに区分した歌体に属する歌は、それを享楽し了解するためには、自らその歌を詠むのでなければならない。そして和歌を詠むとは、「世界中で最もデリケイトなる」メカニスム、つまり「不可思議なるパイプオルガン」を製造することにほかならない。そのように言ってもいいでしょう。
ところで、西脇順三郎がいう純粋芸術のメカニスムは、萩原朔太郎が「純粋詩としての新古今集」で、新古今集の和歌を「徹底的フォルマリズムの抒情詩」とよび、そこにはただ形式と内容しかなく、しかもその内容はそれ自身が形式なのだと書いたときの、その「形式」にあたるものとみることができると私は考えています。あるいは風巻景次郞が、新古今集以後の時代における「一首の歌に「詩」を打ち込まんとする芸術心の衰弱」を語った際、問題はその「詩」が古典文芸の鑑賞によって培われる一種の雰囲気だったことにあると論じたときの、その「詩」(有心体、有心様にいうところの「心」、あるいは端的に「詩心」)にかかわってくるのだろう(さらにいえば、かねてから私が考想している「哥の伝導体」という場・体(フィールド)にはたらく機制・機序(メカニスム)にもつながってくるだろう)と思います。
ここでは、吉本隆明氏が『初期歌謡論』で、「上句と下句のあいだの転換の重さ」を論じ(この、初期の短歌謡における上句と下句の「虚喩」的転換の関係は、純粋芸術のメカニスムの第一の構成要素、つまり相異なる二つの世界の連結を思わせる。ことのついでに、場所がらもわきまえずにつけくわえておくと、純粋芸術のメカニスムの第二の構成要素、「美を求めんとする」強烈な力は、かの貫之歌論における「いひいだす」ランガージュの力に通じている。)、あるいは、三浦つとむ著『日本語はどういう言語か』の文庫解説で、「わずか三十一文字といった表現が、めまぐるしいほどの、認識の〈転換〉からできあがっていること」や「作者が、意識せずにつかっているめまぐるしい認識の〈転換〉が、詩歌の美を保証している」と書いたときの、(いまひとつ引証をくわえるならば、『日本語のゆくえ』のなかで、「転換が極まるところは何であるかといえば、それは比喩です。(略)直喩とか暗喩といわれる比喩の仕方が転換のもっとも濃縮した場所になります。」と語り、また「比喩というのは転換なのです。」と語っているときの)、その「転換」に、より精確にいえば「場面転換」に通じているのではないか、そして、それはベンヤミンがいう「翻訳」のことだったのではないか、という仮説を呈示しておきたいと思います。
■西脇順三郎の最後の大仕事
四方田犬彦氏に「西脇順三郎と完全言語の夢」という論考があります。明治学院大学言語文化研究所の紀要「言語文化」第19号に掲載され、後に『翻訳と雑神 Dulcinea blanca』に収められたもの。純粋芸術のメカニスムが「翻訳」に通じているのではないかというアイデアは、この文章のなかにひそんでいました。以下、概略を引きます。
四方田氏はまず、晩年の西脇順三郎が心血を注いだ「ギリシャ語と漢語の意味音韻をめぐる比較研究」を紹介します。探求の現場にいあわせた中国文学者の回想を孫引きすると、その膨大な作業は、「ギリシャ語の音・義がのべられると、即座に『大字典』が開かれ、漢語の音・義がさがしもとめられる風景が続いた。ギリシャ語と漢語との音・義、それが単語と成語にわたって次々に合わさってくると、それはまるで両者の呼吸がぴったり合ったようで、互いに“この世の秘密を暴いているような戦きを感じる”などと言い合いながら、言葉は酔漢のように声高になった。」(小野田耕三郎「西脇順三郎の古代回帰──余談」、「言語文化」第1号)といった雰囲気のなかですすめられ、西脇八十八歳の誕生日を記念して刊行された『ギリシャ語と漢語の比較研究ノート』のあとがきによれば、その研究は大学ノート百二十四冊、さらに原稿用紙において七千四百枚を数えるといいます。(生前に発表した千二百五十篇の論文、一万二千枚に加え、未発表の草稿が少なくとも八万枚はあったというチャールズ・サンダース・パースには及ばないものの、ソシュールが残した約百五十冊のアナグラム研究ノート類には匹敵する規模で)、まさに四方田氏がいう「ラブレー的な数字」の言葉がふさわしいと思います。
問題は、この二十数年におよぶ「壮大な研究」が、はたしてラブレー的な奇行もしくは愚行(本論考で初めてこの企てを知ったときの、私の最初の素直な印象)と切って捨てることができるかどうかで、四方田氏は、ウンベルト・エーコが『完全言語の探求』で分類・提示した、完全言語の探求者が陥りがちな五つの罠と照らし合わせて考察したうえで、「西脇が生涯の後半にすべての情熱を注いで悔いなかった大作業が、今日の言語学の立場からすればアナクロニズムにしか映らないといった印象をあたえる」ことを認めながらも、「この「最後の仕事」に正当な照明を当て、西脇の意図と情熱の由来するところを正確に見極めるためには、どのようにすればよいのだろうか」と問いをたてるのです。
四方田氏は、西脇の最初の日本語による詩集『Ambarvalia』の巻頭を飾る「天気」という作品、「(覆された宝石)のやうな朝/何人か戸口にて誰かとさゝやく/それは神の生誕の日。」をとりあげて、その冒頭の一行に括弧がもちいられていることに注目します。「それは叙述が詩の語り手によって直接的になされたものではなく、どこか外側からの引用、他者の声の間接的な借用であることを示している。キーツが出典であるという指摘[新倉俊一著『西脇順三郎全詩引喩集成』によると、「( 覆された宝石)」は、ジョン・キーツの『エンディミオン』第三巻七七七行にある「like an upturn'd gem」に由来する。]が意味をもつようになるのは、この次元においてである。」
(ここに出てくる「複数の、互いに他者であるような言語の存在を前提とし、それを背後に認識したうえでポエジーに立ち向かう」という文章が含意すること、というか、この文章に触発されて考えたこと、たとえば、和歌や歌論が追究したのは、見える世界と見えない世界、人の世と神の界域、等々の異なる二つの世界=言語空間の間の概念や観念やイメージの翻訳の可能性であって、そのために和歌が駆使し洗練させていった技法が、かりに「映画的」と名づけてもいいところの「アナロジー」だったのではないかといったこと、等々については、後にとりあげる井筒豊子の和歌論三部作を考察する際、あらためてたちかえることになると思います。が、ここでは、このことは備忘録として書き記すにとどめて)、以下、西脇の英語翻訳者でもあるホセア・ヒラタの著書「The Poetry and Poetics of Nishiwaki Junzaburo: Modernism in Translation」(プリンストン大学出版局、1993年)に準拠した、四方田氏の議論を抜き書きすることにします。(ホセア・ヒラタ氏は、「言語文化」第19号に掲載された「西脇順三郎の詩と翻訳」のなかで、自著について、「海外で出された西脇の研究書としては未だに唯一のものだと思われる」と書いている。)
■戸口にてさゝやく者、あるいは翻訳者としての詩人
「ヒラタが出発点とするのは、これまであまたの西脇解釈者が言及することのなかった、きわめて微妙な細部、二行目にある「戸口」というわずか一語に隠された含意である。」どういうことかというと、それが、その「戸口」という語が、かの旧約聖書・創世記に記されたバベルの塔の物語を示唆しているということです。『オックスフォード英語辞典』は、「バベル」という語がいかなるセム語族の言語にも見当たらないという記述とともに、一説として、アッシリア語ではかつて「神の戸口」、「神々の戸口」が「バビル、バビリ」と呼ばれていたという事実を掲げている。「ここからヒラタは一挙に、ヴァルター・ベンヤミン[「翻訳者の使命」]が抱いていた独自の翻訳観と、ジャック・デリダ[「バベルの塔」、『他者の言語──デリダの日本講演』]によってなされたその解釈が織りなしている問題文脈のなかに、西脇の詩を導き入れてゆく。」
(ベンヤミンが「異質な言語の内部に呪縛されているあの純粋言語をみずからの言語のなかで救済する」というときの、その「救済」(Erloesung)は、吉本隆明氏が、俗謡の浸透によって崩壊の危機にさらされた和歌形式を「救抜」するために定家が設けた五つの歌体について論じていた、その「救抜」に文字どおり通じています。が、これもまた、ここでは指摘するだけにとどめおき)、引き続き、四方田氏の議論の抜き書きをつづけます。
いわく、こうしたベンヤミンの翻訳観が、完全言語論者の系譜の上にあることは説明を要しないだろう。このベンヤミンのテーゼをさらに発展させたところに、ジャック・デリダの薄気味の悪い哲学的思考がある。デリダによれば、神によるバベルの塔の破壊は、神聖にして不可侵であった神の固有名すらが翻訳されなければならないという状況をもたらしてしまった。「一方で神は翻訳をせよと命じ、また片方で自分のただひとつの名、父親としての唯一の固有名詞を人間たちに押しつけるのである。翻訳を課すると同時にそれを禁じるという矛盾したメッセージこそが、バベルという混乱の本質である。」
(文中の、「テクストの起源である作者の意図を超えて、テクストそのものが言語の網状組織のなかで展開してゆく、非人称的な運動」云々というバルト的表現は、私を惹きつけてやまない王朝和歌の世界の感触をいいあてて余すところがありません。とりわけ、それが「批評の地平においては」という限定のうえになりたつとされているところが、歌の詠出と評定評釈とが渾然一体となった多声的な和歌の場のありよう、というかあらかじめ批評という意識や営為がくりこまれた和歌制作の現場のありよう、あるいは編集という名の批評行為が先行するアンソロジーの世界の実質、さらには本歌取りという名の引用=翻訳行為の意義、等々といった「和歌のメカニスム」を考えるうえでなによりも大切なポイントをみごとについているように思います。
いま少し付言すると、和歌というテクストのなかで遂行される「メカニスム」を担う「非人称的な運動」は、ロラン・バルトがいう「映画的なもの」(ル・フィルミック)に、すなわち、情報伝達のレヴェルでもサンボリックな意味作用のレヴェルでもない、意味形成性(シニフィアンス)にかかわる第三の意味のレヴェルから(バルトが、それをもし叙述しうるとするなら日本の俳句というものになるだろう、「つまり俳句は、表意的な内容を持たない頭語反復的な身振り、意味(意味の希求)が抹殺された一種の傷跡なのである。」(「第三の意味」、諸田和治訳『ロラン・バルト映画論集』)と書いている、その映画における第三の意味のレヴェルから)現われてくるもの、「映画のなかにあって描写することのできないものであり、表出[ルプレザンテ]されえない表現[ルプレザンタシオン]」とされるものに通じているのではないか。あるいは、ヒッチコックが、トリュフォーの質問を受けて「わたしがずっと映画をつくりつづけてきて、何を学んだかというと、マクガフィンにはなんの意味もないほうがいいということだった」(山田宏一他訳『定本 映画術』)と答えた、その「マクガフィン」に通じているかもしれない。そんなことを私は考えはじめているのですが、これはまだ思いつきの域をこえない論件なので、ここでもまた、深追いせず素通りすることにして)、以上のことをふまえ、四方田氏は最後に、かの西脇晩年のギリシャ語と漢語の比較研究について、すなわち「詩人が生涯の情熱を捧げた」大仕事がなしとげようとした対象について、「完全言語への見果てぬ夢であった」と総括しているのです。
補遺として、個人的な回顧をはさみます。私はかつて、ベンヤミンの「翻訳者」を「使徒」になぞらえて考えたことがあります(「キルケゴールの伝導体」、『ポリロゴス2』)。それは、富岡幸一郎著『使徒的人間──カール・バルト』と「翻訳者の使命」とをかけあわせながら読んでいて、しだいに確信を深めていったアイデアでした。ここに、そのとき私の心をとらえた生の素材を二つ、記録しておくことにします。
富岡氏によれば、使徒とは「空洞を露呈する人間」(バルト『ローマ書』)のことです。「イエスについての知らせ、イエスの言動と奇跡、その十字架と死からのよみがえり、教会の存在と秩序についてのイエスの中で啓示された神の意志についての知識を、それら全てを最初に受けとめた人間の手から、忠実に、変えたり、減少させたりすることなく、次の人間の手へと、後代の者たちの手へと、順を追って伝えてゆくこと──自分のオリジナルな思想や自分の感情を語るのではなく、イエス・キリストにあって生起した出来事の本質だけを、後の者たちに宣べ伝えること──この使徒の奉仕の特徴を示す言葉として、新約聖書は「引き渡し」という用語を使う。使徒とは、まさにこの「引き渡し」を行なうために「空洞を露呈する人間」として、そこに立つ。この一点の活動において、歴史に関わる。」
また、富岡氏は、神学の思索とは後から[Nach]考えること[denken]であり、使徒的人間の思考は「追思考」のかたちをとると書いていました。そして、二十世紀において、この神学的な追思考の概念を、哲学のなかへ導入しようとしたのがマルティン・ハイデガーであるとも。「ハイデガーの追思考[ナッハ・デンケン]が追いかけるものは何か。いうまでもなく、それは彼の語る「存在」そのものである。存在の牧者といういい方に象徴されるように、形而上学の歴史のなかで失われた「存在」を追想すること──これが後期ハイデガーの思索のモチーフとなった。だが、この「存在」をめぐる思考は、神学における追思考とは似て非なるものではないか。たしかにハイデガーの哲学には「神学の遺産が満ちみちている」(スタイナー)。しかし、それは文字通り‘遺産’である。彼の問題にする「存在」とは、神学が対象とするものとは全く違っている。なぜなら、神学が対象とし、その思考が「追考する」ものは、決して隠され沈黙している「存在」ではない。それは、イエス・キリストにおいて地上の出来事として啓示された(啓示の語源は、隠されてあるものの覆いを取るという意味である)、人間にたいする神の具体的な語りかけであるからだ。」
■ベンヤミンと西脇順三郎、詩論を神学的に考えた人
最後に、ホセア・ヒラタの「西脇順三郎の詩と翻訳」(「言語文化」第19号)から、関連する文章をいくつか引いて、次章へとつなぎます。まず、ベンヤミンの「翻訳者の使命」をめぐって。
ヒラタ氏は、ベンヤミンの言語思想が西脇の詩論に非常に似通っていることに言及します。「西脇は「超現実主義詩論」において非常にユニークな詩論を表しているが、まず我々が気づくのが、西脇も詩論を神学的に考えた人だということだ。」
ここにきて、私の脳裡には、(貫之現象学の世界にあっては、「貫之が自然を詠んだものでもよし、自然が貫之を通して自己を詠んだものでもよい」といえる事態がなりたっていて、その定式中の「自然」を「言語」におきかえたときに出現する世界こそが、定家論理学の世界、すなわち「定家が言語を詠んだものでもよし、言語が定家を通して自己を詠んだものでもよい」と定式化できる世界なのではないか、あるいは、今ここに生まれつつあるポエジーとしての「神」は、啓示という言語メカニスムを介して、意味に捕らわれている動物を使徒的人間に、詩人=翻訳者に回心させるのではないか、といった思いつきとともに)、詩論を神学的に考えたもう一人の言語哲学者の名がくっきりとうかびあがっています。二篇のポール・クローデル論(「詩と宗教的実存──クロオデル論」「クローデルの詩的存在論」)を書き、神のコトバが記されたコーランを二度翻訳し、そして「存在はコトバである」と語ったその人こそ、井筒俊彦です。
(19号に続く)
★プロフィール★
中原紀生(なかはら・のりお)1950年代生まれ。兵庫県在住。千年も昔に書かれた和歌の意味が理解できるのはすごいことだ。でも、本当に「理解」できているのか。そこに「意味」などあるのか。そもそも言葉を使って何かを伝達することそのものが不思議な現象だと思う。
Web評論誌「コーラ」18号(2012.12.15)
<哥とクオリア>第22章:バベルの後の詩人たち──和歌のメカニスムⅠ(中原紀生)
Copyright(c) SOUGETUSYOBOU 2012 All Rights Reserved.
|
| 表紙(目次)へ |