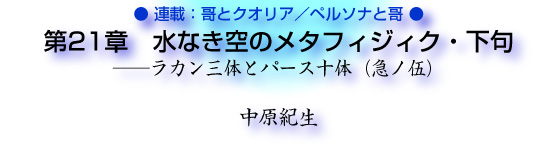�s�������u��Ə\�́v�̔��I�Ȋ�ł́A�Ñ̂̒P�������q���r��q���r�̐S�����������̂��悵�Ƃ���C���ƁA���l�̑O�q�I�Ȕj����A�����̏��i�̂d����C���Ƃ������ɂ��Ă���B���ꂪ�u���l�v�Ƃ����̑̂̃��j�[�N�ȗޕʂƁA���̂����܂������K�肵�Ă���B�����̗�̂���킩��悤�ɁA�ʎ����ꂽ�q�i���r�q���Ɓr�q���T��r�����\���Ă͂��邪�A�qꠂ̗t�ɖ��������̂ڂ�r�c�Ƃ������悤�ȁA�P���ȋ����ے��́q�i���r�����`����Ă��Ȃ��B�����ėތ^�I�ȁA����Ӗ��ł͂����炦����������p�^�[�����x�z���Ă���B���������q�i���r�̓T�^���́q�V�Í��I�Ȃ��́r�ɂ���Ă͂��߂ĉ\�ƂȂ����B���̉̑̂́q�V�Í��I�Ȃ��́r�̔��I�Ȋ���炢���A����Ӗ��ł͂��������̂������B�ǂ��ɂ��q�L�S�r��q�H���r�̉\���͂Ȃ������B�����q�V�Í��I�Ȃ��́r�̂Ȃ��ɁA���̉̑̂��͂��߂ēo�^����Ă���̂ɂ͂��ꂾ���̗��R���Ȃ���Ȃ�ʁB����͂��������ʑ��Łq�i���r�̃C���[�W�����肠���邱�Ƃ́A���i�̂̌n��͂܂������V�����o�����Ƃ����炾�B�����ł͏��i�Ə��S�Ƃ��A�\����̂ɂƂ��ē������������ɂ����Či�����r�܂�Ă���B�t
�@
�s���܁u�Z�l�v�Ƃ����Ӗ����m�����́n�u�ؗ�́v��u�]��́v�Ɍn���Â����Ɂu���l�v��u�ʔ��l�v�ƈ�ߑѐ��ɂ�����A�q�L�S�r��q�H���r��S�Ƃ��ĕۂ��Ȃ���A���p���̗w�̈ӎ��Ɛ����ɁA������������l�ɂƂĂ��߂Â������̂Ƃ��āA�u�Z�l�v���ʒu�Â��邱�Ƃ��ł��悤�B�u�Z�l�v�̂Ȃ��ɁA�a�̎j�I�ȊT�O��������������̊w�̔��I�ȋK���̎ς߂�ꂽ�q�S�r���݂�ƂƂ��ɁA�a�̌`�������āA�t�������Ɍ���Ȃ��߂Â��Ă䂭�p�������݂�ׂ����Ƃ�������B�������������́u�Z�l�v�ł͂�����ɒ[�ɂ�����Ă���B�t
�@
�X�D�L��߁i�ЂƂӂ�����j�l
�@
�@�@�䂽�̂ނȂȂ̎Ђ̗[�����������Ă��Z�݂̂��ɂ��ւ��ȁi���~�j
�s�����ȗw�m�w���o�鏴�x�́A���Ƃ��u���͂�Ԃ��̎Ђ̖ؖȎ��y�m��ӂ������n�A������N���|���ʓ��������n�Ƙa�̂Ƃ���������p�́A�a�̂����ǂ��Ă��������������悭�ے����Ă���B�q�Í�����r���߂��Ȃ������ɁA�a�̂ƍ��l�̑��w�Ƃ̍��Z�̌X�����͂��܂����B����͘a�̓I�Ȑ������A�������ɕ���č��l������Ƃ���ɏے�����Ă���B�܂��u��Ə\�́v�ɁA�悭���w�Ƃ��Ă̓����炵�����̂�����Ƃ���A���̘a�̕\���j��̕K�R�I�ȌX���Ƃ������ׂ����w�Ƃ̑��݉e���⍬���̖����A�ǂ��������邩�Ƃ����Ƃ���ɂ����ꂽ�B�u�ʔ��v�̂Ƃ��Ȃ��悤�ɁA�u�L��߁v�̂́A����Α��w�́q�����r���a�̂ɟ��������Ƃ���ɁA�s��I�ɐݒ肳�ꂽ�̑̂ł������B�����ɁA����͓���̂̉�̂���������h�g��̂ЂƂƂ��݂邱�Ƃ��ł���B�t
10�D�f�S�i������j�l
�@
�@�@�v�Џo�ł悽�����˂��Ƃ̖��Ȃ�ނ��̂ӂ̉_�̐Ղ̎R���i�����Ɨ��j
�s�u�f�S�v�̂Ƃ́A���t�������Ď��ɋ��������悤�ɉr����ꂽ���̂Ƃ݂Ȃ��ׂ��ł��낤���B�i���j
�i���j�����āu�ӂƂ݂ق��݂��Ȃ��A�Ȃт炩�ɕ����ɂ�����ʂ₤�ɂ�݂Ȃ��������͂߂ďd���v�Ƃ����Ƃ̉̎��_���炷��A�u�f�S�v�Ƃ������Ƃ͉̂̎p�̂������S�̂����Łu�Ȃт炩�v�Ȃ�ʂ��̂������Ă����B�������u�ʔ��l�v��u�L��ߗl�v�Ƃ������Ƃ���́A��Ƃ��u�f�S�l�v��{���I�ɂ́A���l�̑��w��ȗw�Ƃ܂������t�̕����ɂ����Ă������Ƃł������B�������܂���̂������邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B���������z���������ق����悢�悤�ȋC������B�i���j
�i���j���̂��_���Ƃǂ܂��Ă����R�̏�ɁA���傤�͉_�̋��������Ƃ̎R�����A�Ђ邪����悤�ɐ����Ă���B����͉_�ւ̖ł���̂��A����Ȗ����Ƃ��킵���悤�Ȏv���o������悤�ȋC������B����͐S���ł���悤�ȑz���ł���B�i���j��Ƃ́A�z���͂����������̂�������Ȃ����A�����̉̂���S�́u�f�S�v�Ƃ������Ƃ͂������ł���B�t
�@�Ȃ��A�g�{���́A��Ƃ́u���Ă��������N���t���ނ��ւT�Ȃ��߂Ȃ��߂ނ͂Ẳ���v���̑��̉̂������A�u�������Ƃ����S�́u�f�S�v�Ƃ������ǂ����킩��Ȃ��v�Ƃ��Ȃ���A���̂悤�ɂ��߂������Ă��܂��B�u�����u�f�S�v�̂Ƃ������Ƃ��q�v�������ĐS�����݂����Ă݂���̑́r�Ƃ����Ӗ��ɂ����Ƃ߂�A���̎�̉̂͒�ƂɂƂ��ĉ������ł������Ƃ������悤�B�v
�@
�����t���a���o�����Ƃ�
�@
�@�L�S�Ɩ��S�i����ɁA��O�̐S�Ƃ��āu���S�v�����Ă�������������Ȃ��j�ɕ���ꂽ���E�Ɉʒu�Â�����\�̉̂̋��n�A���Ȃ킿��Ə\�̂��A�u�ǂ��߂�ꂽ�������v�Ɓu���w�ɟ������ꂽ�̑́v�Ƃɕ�������A��d������邱�ƁB���̂��Ƃ̈Ӌ`�����ɂ߂邽�߂ɁA�����ň�{�̕⏕���������܂��B
�@
�@�g�{���́A�i��ɁA�w����ɂƂ��Ĕ��Ƃ͂Ȃɂ��x�Ƃ�����i�̂����ɁA������߂���v���̐��ʂ���������Ƃ���́j�u���w�̗��_�̖��v�ɂ��Ă��܂��܂Ȏv�����߂��点�Ă���Ƃ��A�O�Y�Ƃޒ��w���{��͂ǂ��������ꂩ�x�ɂ�������A���́A����߂č��x�ʼn���I�ȓ��e�������A���w��i����͂���̂ɂ��̏�Ȃ��D�ꂽ�������Ă���钘�����A�u���܂��A���w�̗��_�ɂ�����̂́A���Ԃ�A�킽���������낤�Ƃ������Ƃ��A�����ɒ��ς��ꂽ�v�ƁA�O�Y�{�̕��ɔʼn���ɏ����Ă��܂��B
�@�g�{�����A�u�O�Y����w�v����d���ꂽ����������͎����E�[���E�m���͓����܂��B�ЂƂ́A�u���w��i�̌��t���A�q�\���r�Ƃ��������Ɉʒu�Â��Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ��A�O��I�Ɏv���m�炳�ꂽ�v���ƁB���܂ЂƂ́A���{��̂�����u�Ăɂ��́v�ɂ��āA�O�Y�Ƃނ��u�b����̎����Ă����ϓI�Ȋ����ӎu���̂��̂��q�̂Ƃ��Ĉ������ƂȂ����ڂɕ\��������v�ƋK�肵�����ƁB�i�����ŏq�ׂ��Ă����̎����́A�����A���̌�A�i���̌�A�Ƃ́A���܂����߂Ă���u���J���O�̂ƃp�[�X�\�́v���߂����ƁA���邢�́A�r�܂ꂽ�̂̐��E�݂̍�l�Ɋւ���A�L�`�̊єV���ۊw���߂���l�@�Ɉꉞ�̂����������ɁA�Ƃ����Ӗ��ł��j�A������������ƁE�l�@�����݂����Ɨ\�肵�Ă���A���ɂ��\���̑��ɂ����ĂƂ炦��ꂽ�݂̂̍�l�Ɋւ���A���`�̊єV���ۊw�̍ŏd�v�̘_�_�ƂȂ�͂��̂��̂ł��B�j
�@��i�́A���}���L�̎d�������u�Ăɂ��́v�I�Ȍ��t�Ɋւ���c�_�͂����ł͊������A�O�i�́A�u�\���v���߂���g�{���̕��͂��ȉ��ɂ܂邲�Ɣ����������āA�i����܂ŁA���̂ق�̈�[���T�ς����ɂ����Ȃ��j�w�����̗w�_�x�ł̋g�{���̘a�̂̓lj����A���������ǂ̂悤�ȗ��_�I�w�i�������̂ł����������m�F���Ă��������Ǝv���܂��B
�s���t���A�a���o����Ă䂭���߂ɂ́A�����瑤�ɁA�F���̓������Ȃ���Ȃ�ʁB�ǂݎ肪�A���ǂ�̂́A�����瑤�Ɂq�\���r���ꂽ���t�����A��i��a���o���������瑤�ɂƂ��āA���t�́A�q�\���r���ꂽ�F���̓����̌��ʂł���B�������Ƃ���A�ǂݎ�́A��i�̌��t�����ǂ�Ȃ���A�����ɁA��҂̔F���̓�����ǂ��Ă���̂��B�܂��A���t���a���o���ꂽ�Ƃ��A�a���o������҂́A����A���t�ɂ���āA�t�ɂ��Ԃ�̈ʒu���͂�����ƌ��肳���B�����]���ƁA�����ɂ��ȒP�Ȃ悤�����A�ǂ�Ȍ���w�̒������A�ΏۂƔF���ƕ\���Ƃ̊W���A���ꂾ�������ɁA�w�E���Ă͂���Ȃ������̂ł���B�O�Y�Ƃނ̂��̊�{�I�Ȏw�E�́A�����ɗL���Ȃ��Ƃ��킩�����B
�@�킽���́A�����̌ÓT���̂̍�i���A�P���ȏ��i��A����ɂ�������炸�A��������������̂͂Ȃ����A�Ƃ������ƂɂЂ��������Ă����B�܂�A�Ӗ������ǂ��Ă݂�A�قƂ�ǁq�����ɔ������Ԃ��炢�Ă��܂��r�Ƃ����悤�ȁA�P���Ȃ��Ƃ����]���Ă��Ȃ��̂ɁA�ǂ����Ċ�����^����̂��A�Ƃ������Ƃ��^��łȂ�Ȃ������B����ɂ�������ߐ��Ȍ�̗����́A�����_����ł���B�܂��A�ߐ��ȑO�̗����̎d���́A�q�D�Ɂr�Ƃ��q���Ɂr�Ƃ��������z��]�̔�]�ꂵ�������Ă��Ȃ��B�������ꂽ��^�́A�\���I�Șg�g���A���̂̍�i�̉��l���A�g�g���̂Ƃ��āA�����Ă��邾�낤���Ƃ́A�킽���ɂ��킩���Ă����B����ǁA���ꂾ���ł́A�Ƃ��Ă��[���ł��Ȃ������̂ł���B�\�����ꂽ���t�́A�ނ������ɂ��邪�A�F���̓����́A���̓s�x�A�����瑤�ɂ���Ƃ����O�Y�Ƃނ̎����́A�킽���ɂ͌[���ł������B����ŁA���������ɍ�i�ɂ������Ă݂悤�Ǝv�����B�ߐ��Ȍ���A�ߐ��ȑO���A���̂̍�i�̊����̂��ׂĂ��A������Ӗ��������Ă��邾���łȂ����Ƃ́A���ϓI�ɂ́A�悭�킩���Ă���̂ɁA���̉��߂́A��`�̉��߂ƁA�����i���Y���Ɖ̕��m�����n�j�ƂɌ����āA����Ȃ�ɐ��k�ɂ͂Ȃ��Ă���B�����A�������������̑��̂ɂ͓��B���Ȃ��ŁA���߂��݂����˂��Ă��邾���ł���B����́A�r���́u�×����̏��v��A�钷�́u���Z�̉�䚁v�ŁA�T�^�I�ɏے������邱�Ƃ��ł���B�킽���́A���̂̍�i�̌��t���A�ɒ[�ɂ����A�ꎚ�A�ꎚ���ǂ�A���ꂲ�ƂɁA�w��ɂ����҂̔F���̓������A���ʂ��Ă݂邱�Ƃɂ����B�����ĈӊO�ɂ��A�킸���O�\�ꕶ���Ƃ������\�����A�߂܂��邵���قǂ́A�F���́q�]���r����ł��������Ă��邱�ƂɋC�Â����B�����Ƃ������������A���ĒN����������̖̂{���Ƃ��āA�w�E�������̂͂��Ȃ������̂ł���B��҂��A�ӎ������ɂ����Ă���߂܂��邵���F���́q�]���r���A���̂̔���ۏ��Ă���B�킽���́A����������ɁA�q��ʁr�A�q�I���r�A�q�]���r�A�q�g�r�̏������m�肵�A���̎l���A���݂܂ł̂Ƃ���A���t�ŕ\�����ꂽ��i�̔����A���藧�����Ă��邾�낤�Ƃ����A���_�̍������A�`�����邱�Ƃ��ł����B�Ώۄ��F�����\���Ƃ����O�Y����w�̊�{�I�ȍ��g�݂́A���镶�w��i���A�n��������̂̑����炽�ǂ�A������������n���̗��_�ɋ߂Â�����\�����������Ă����B�킽���͂��̓������ǂ����B�t
�@
���ڂ��J���Ă��Ȃ���Ό����Ȃ���
�@
�@���p���̑O�i�ɏ�����Ă��邱�Ƃ́A�u�����ɂ��ȒP�v�ǂ��납�A���t�ɐ旧���ĔF���̓������Ɨ��ɑ��݂��A���t�͂������̌��ʂ��L�q�i�\���j���邾�����Ƃ���A�f�p���}�f�ŌÂ߂���������ρi�\���ρj��\�����Ă�����̂̂悤�ɓǂ߂Ă��܂��܂��B���̓_�ɂ��ẮA�����T�m�����A�w��{�@����ɂƂ��Ĕ��Ƃ͂Ȃɂ��T�x�̕��ɔʼn���u���t�ɂ��āv�ɏ����Ă���A���̎w�E���Q�l�ɂȂ�Ǝv���܂��B
�s�������ɋg�{�́A������R�g�i�\���j�Ƃ����l���Ō��悤�Ƃ������߁A����̃��m�i�\���j�Ƃ��Ă̖��̈��s��ɂӂ����B���̂��߁A���Ƃ��\�V���[������w�̒B�����]���́u���ꖼ�̖ژ^���v�i�����̒���������̒����Ƃ͓Ɨ��ɁA����ɐ�s���đ��݂��A���t�͂��̖��̂ɂ����Ȃ��Ƃ�������ρj��Ŕj�����Ƃ���ɂ��邱�ƂɁA�\���ɗ����~�܂�Ȃ������B���̌��ʁA���E�̌���w�I�S�Ɣނ̌���w�I�B���Ƃ̊W�Â��Ƃ����d���͕��u���ꂽ�B���Ԃ�A�\�V���[���̌���w���o���n�Ƃ���f���_�̌���ς���́A�g�{�̕\�o�_�́A�\�o��p�̒��ɂ����̂ƌ���̐ؒf�̌_�@�Ղɂӂ����������S��`�I�Ȍ���ςƂ��āA�꓁���f�̂��Ƃɐ�̂Ă���ɈႢ�Ȃ��B�������A�\�V���[���̌���w�ł͋t�ɁA����̃R�g�Ƃ��Ă̕��ʂ�s��ɕt���Ă��邽�߁A�Ȃ������I�Ȍ���̍\���i�����O�j��������ӂ�ɂ�Đl�X�̌��ꊈ����ʂ��ĕω����Ă������Ƃ����₢���A������Ȃ���Ƃ��Ďc��B�f���_�̌���ςł��A����́u�Ӗ��v�́A���ꂪ�ǂ������\���������A�l����悵�Ă��邩�͌������Ă��i���Ƃ�����̓V�X�e���̍��ق̋Y��Ƃ��đ��݂���j�A���ꂪ�ǂ����痈�邩�A���ꂪ���Ȃ̂��́A�������Ă��Ȃ��܂܁A�c��̂ł���B�t
�@������u�R�g�v�Ƃ����l���Ō��邽�߂ɂ́A����������Ď��n�Ɂu�\���v���Ă݂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�u�����瑤�v�ɕ\�����ꂽ�u���m�v�Ƃ��Ă̌���A���Ƃ��ΌÓT�a�̂̍�i���߂����āA�������`�Ɛ����Ɋւ��鐸�k�Ȓ��߂��݂����˂Ă݂��Ƃ���ŁA�i���̂悤�ȕ��@�ł́A���̍�i�̈Ӗ��̍\����l�����������Ă邱�Ƃ��ł��Ȃ��̂͂������j�A���̉̂ɂ���Ă����炳��銴�����ǂ����痈�邩�A���ꂪ���Ȃ̂����������Ă邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�n�삷����́A�̂��r�ނ��̂́u�����瑤�v�̔F���̓�����Ǒ̌��i���邢�́A�ǎv�l�A�NJ��o�A�Ǒz�N�A���X�j���Ă݂�̂łȂ�������́B
�@�u�\�����ꂽ���t�́A�ނ������ɂ��邪�A�F���̓����́A���̓s�x�A�����瑤�ɂ���v�̂��Ƃ���A�̂̓ǂݎ�́A���̂Ƃ��A������炽�ȉr�ݎ�ƂȂ��āA�u�ނ������������瑤�v�Ɍ��t�Ƃ��ĕ\�����ꂽ�i���邢�́A���t�̂����Ɂq�\�ہr�Ƃ��Ă����ꂽ�j�u�߂܂��邵���قǂ́A�F���́q�]���r�v���A�u�����瑤�v�ɁA���Ȃ킿�A����́u�����ɔO���郁�^�t�B�W�J���ȁq�S�r�v�̂����ɁA���E�����ŁA���ɑ��ă��A���ɐ�������̃I���W�i���ȏo�����Ƃ��đ̌�����̂łȂ���A�i���ɓI�ɂ́A�����ő̌������u�R�g�v���u���m�v�Ƃ��ĕ\�����錾�t���A�������肻�̂܂���̌��t�Ƃ��Ėa���o���̂łȂ�������́j�A���̉̂���������u�����̑��́v�ɓ��B�����Ȃ��B�i�ނ���A���̂悤�ȐV���ȕ\����̂��A�������y���\�i�Ƃ��đn�����邱�Ƃ����A�ÓT�a�̂��߂��������ɂ̋��n�E���ʁE���U�ł������B�j
�@�������r�F���قǂ��������܂����B
�@���܂ЂƂf�ނ��N�W���܂��B�ȏ�ɏq�ׂ����Ƃ���Ɋ֘A���āA�O�Y�{�̑�ꕔ���͑��߁u��҂̑̌��Ɗӏ҂̒Ǒ̌��v�̋c�_�����p���܂��B���킭�A��҂̑̌���\���I�ɒǑ̌����悤�Ɠw�͂���Ƃ��ɁA�͂��߂Č|�p��i���ӏ܂��邱�Ƃ��ł���B���̒Ǒ̌��́A���ł��邱�Ƃ����o���Ȃ��猩�閲�A�ڂ��J���Ă��Ȃ���Ό����Ȃ����ł���B�Ƃ���ŁA�������Ă���Ƃ��A���̖������Ă��錻���̎����ƁA���̐��E�̒��̎����Ƃ͈قȂ��Ă���B
�s�ʂ̂�������������Ȃ�A��������ꍇ�ɂ́A�����̎��������̂܂܌����̎����Ƃ��đ��݂��Ȃ���A�������疲�̐��E�̒��̎������ϔO�I�ɕ��āA�����̎����ɂ͂ł��Ȃ��ϔO�I�ȑ̌������낢�����Ă̂���̂ł��B�i���j������w��I�ɂ́A�l�Ԃ̊ϔO�I�Ȏ��ȕ���Ƃ�т܂����A���̎��ȕ���͂ǂ�ȁu���v�ɂ����Ă܂����̂ŁA�G�ł��낤�Ɖf��ł��낤�ƌ���ł��낤�ƁA���邢�̓e���r�ł��낤�ƁA�\�����ӏ܂���ꍇ�̒Ǒ̌��͂��ׂāu���v�Ȃ̂ł�����A���ׂĊϔO�I�Ȏ��ȕ����܂Ƃ����̂ƍl���Ȃ���Ȃ�܂���B�t
����Ə\�̂̓�d�\���A���邢�́u�����瑤�v����u�����瑤�v�ւ̐S�̕ϗe
�@
�@���āA�ȏ�̑f�ނ����ƂɁA��Ə\�̂̓�d�\���̈Ӌ`���l���Ă݂܂��B
�@������S�ւƂ������̃��^�t�B�W�B�N�ɂ���Ă����炳�ꂽ�̂́u�S�v�A����������͌��t�i�\���j�ɂ���Ĕ}��ꂽ���̂ł����Ȃ��̂ł����A���́u�S�v���A���t�ɂ��\���i�C���j�̐����ɂ߂邱�Ƃł������ɕϗe���Ă����܂��B�����āA�i�u�����瑤�v�ɂ�����j�C������i�u�����瑤�v�ɂ�����j���n�ցA����������i�u���m�v�Ƃ��Ắj������i�u�R�g�v�Ƃ��Ắj�p�ւƂ������̃��^�t�B�W�B�N�ƂƂ��ɁA�u�S�v�͓��ʉ�����A�̂́A���̓��ʉ����ꂽ�u�S�v�̕\�ۂ��������́i���ʂɂ�����u�v�Ёv���ʂ����f�����ڂ����́j�Ƃ��čl������悤�ɂȂ��Ă����܂��B�i�u�p�v�Ƃ́A�u���p�v�Ƃ����C���̌����ɂ���u�������v�ł���Ɠ����ɁA�ڂ��J�����܂܌��閲�Ƃ��Ẳf��̃X�N���[���ɉf�����u�������v�ł���A⾉ɂ���ĈŖ�ɕ����т�����\����ʼn������鏊��Ƃ��Ắu�������v�̂��Ƃł�����܂��B�j
�@�����ł������ʉ����ꂽ�u�S�v�A���Ȃ킿�u�����ɔO���郁�^�t�B�W�J���ȁv�����Ȃ��u�S�v���A�u�ǂ��߂�ꂽ�������v�̐��E�ɏZ�܂����Ă��铖�̂��̂ɂق��Ȃ�܂���B���́u�S�v�̑f���͌���ł�����A���Ắu���v�i�N�I���A�j�Ƃ̌��E�����E�����̌_�@���������A�����Ɍ`���I�Ȃ��̂ւƏ�������Ă��܂��B�i�����Y���u�������Ƃ��Ă̐V�Í��W�v�ŁA���̂悤�ɏ����Ă���B�u�V�Í��W�ł́A���y�ɉ�����@���A���e�ƌ`���Ƃ��A�S����̕s���̂��̂ɂȂĂ�̂ł���B�����ł͕��w�ɉ�����@���Ӗ��ł́A�f�ނƂ��ӂ��̂��w��ǖ����B���ׂĂ̑f�ނ͎�菜����Ă��B�L����̂͂����u�`���v�Ɓu���e�v�����ł���B���������̓��e�́A���ꎩ�g�����Ɍ`���Ȃ̂ł��邩��A���ꂱ���O��I�t�H���}���Y���̝R��ƌ��Г��邾�炤�B�v�j
�@���������u�S�v��f�ނƂ��鏃�������u�ǂ��߂�ꂽ�v�ƌ`�e�����̂́A�������A�u���l�̉̋ȑ��w�̐��E���A�a�̓I�Ȑ����Ɉ��|�I�ȗ͂ş������Ă������Ɓv�ɂ��̌���������킯�Ȃ̂ł����A����ł͂Ȃ������Ȃ����̂��Ƃ����ƁA�����Ȍ`�����̂䂦�ɁA�̂̓ǂݎ�ɂ��i���ՂŊȕւȁj�Ǒ̌������ނ悤�ɂȂ��Ă���������ł͂Ȃ����B�ɒ[�ɂ����A�ӏ҂������҂ƂȂ��āA�܂��ɂ��̓��̉̂�����r�Ƃ��āA���j�[�N�ȃN�I���A�̌����r�I���W�i���ȉ̂Ƃ��āu���Ђ������v���Ƃł����A�i���ɓI�ɂ́A�������y���\�i�ƂȂ��āA⾉̓��ɏƂ炳��Ȃ���̂̐S�𐺂Ƃ��Ĕ����A�U�镑���Ƃ��ĉ������邱�Ƃł����j�A�������Ƃ��Ă̘a�̂𖡂킢�A�������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B���邢�́A�g�{���̌��t������āA�u�n���������̂̓��ʂ̈Â�����A����A�\�����ꂽ��i�Ƃ̓���ɂ����āA���ߍׂ����Č�����v�i�w���{��͂ǂ��������ꂩ�x���ɉ���j���Ƃł����A�������Ƃ��Ă̘a�̂𖡂킢�A�������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B����Ȏ��Ԃ������Ă��܂��Ă�������ł͂Ȃ����B���͂���ȉ��������ĂĂ��܂��B
�@�������Ƃ��Ă̘a�̂��ӏ܂���i�ڂ��J�����܂܌��閲�Ƃ��ĒǑ̌�����j�҂́A�������Ă��鎩���i�u���m�v�Ƃ��Ă̖����u�����瑤�v�Ɍo�����Ă��鎩���j�Ɩ��̐��E�̒��̎����i�u�R�g�v�Ƃ��Ă̖����u�����瑤�v�Ōo�����Ă��鎩���j�ƂɊϔO�I�ɕ��܂��B���̕�����A����r�̎�́i������g�́j�ƂȂ邱�Ƃʼn������邩�A���邢�͔�]�ƂƂȂ��ē��ꂷ��B����́A�}���̐g�ɂ͂ƂĂ����Ȃ�ʓ��ł��B�ł���Ȃ�A�����Ƃ��ēO��I�Ɋy���ނɂ����͂Ȃ��B�������āA�i���Ȃ藐�\�ȋc�_�ł����j�A�u���w�ɟ������ꂽ�̑́v�̐��E�́A�u���Ɖ���̂������̓]���̏d���v��Ô�������̂悤�ɂ������Ɏc�����ƂŁA���낤���āu��܂Ƃ����v�̔��e�ɂƂǂ܂����Ō�̉̑̂Ȃ̂ł����āA���̌�A�a�̂́u�������v�͕��A���Ɖ���́u�t�������v�Ƃ��āA�قȂ��̂ɂ���ĉr�܂�邱�ƂɂȂ��Ă������B
�@
�@�Ō�Ɉꌾ�A�g�{���́u�����ɔO���郁�^�t�B�W�J���ȁq�S�r�^�r�܂ꂽ�̂̂����Ɂq�\�ہr�Ƃ��Ă������q�S�r�v�ƁA�莁�́u�r�݂���S�^�r�܂ꂽ�S�v�Ƃ̈ٓ��ɂ��ďq�ׂĂ����܂��B
�@�~���Ҏ��́A�w���Ə@���̔����x�Ɏ��߂�ꂽ�u�p�������u�a�̑̏\��v�ɂ��āv�ŁA�������I�ȗH���̊T�O���߂����āA�u���ڂ�ł����������݂̌������������w�v�ł���A�u���݂̐[�������A���F�[���̂����瑤����A�������ɂ̂�������w�v�ł���Ƃ��A����A�����I�ȗH���̂̊T�O�ɂ��ẮA�u���{�̔��ӎ��̊���I�\���v�Ŏ��̂悤�ɏ����Ă��܂����B�u����́A�t��H�̐���̈����ł͂Ȃ��A�H�̗[�ׂ̂�т������̂��̂ł���A�߂��݂͐�]�ɂ܂Ő[�܂��Ă���B�������A�����ɁA���ȂƑΏۂƂ̊Ԃɂ��������́A�Ώۂ��̂��̂ɂ�����A�p���Ď�ς́A�����ϏƂ̎�̂Ƃ��ĒQ�������������̂ł���B���̔��w�������ɐ����B���̂悤�Ȕ��ӎ��́u�q�ω����ꂽ�߈��v�Ƃ���ׂ����̂�������Ȃ��B�����Ă��̔��ӎ����A�T�ƌ��т��A�\�ɂȂ�A���ɂȂ�A�o��ɂȂ�A�u��сv�u���сv�u�����v�ƕς��Ă䂭�̂ł��낤�B�v
�@���̔~�����̏������A��Ƃ́u�L�S�v�̊T�O���߂���g�{���̋L�q�A���Ƃ��A�u���̉̐S�̃��^�t�B�W�B�N���A�V���̏�y���̗��O���A�����I�ɂ��������B�i���j����̊����ɂ���Č������Ȃ��߂���q������r���u�L�S�v�ɂق��Ȃ�Ȃ������B�v�ƁA���邢�͂܂��A��Ə\�̂̂����́u�H���l�v���߂���L�q�A���Ƃ��A�u�����̕��ۂ̐��E�����ڂ�C�ɂ������m����Ȃ��x���ɉ����āA����̐��E�����݂Ă���̂��o�߂Ă���̂��A�����Ă���̂��͂�����Ƃ킩��Ȃ��B���������S�ۂɁu�H���l�v�̎��I�Ȑ��E�����Ƃ߂�ꂽ�B�����ɂ��������S�ۂ𔗂����w��ɂ́A�헐�A�Q���A���~���y���Ɗ�]�̂Ȃ������̕��i���������B�v��A�u�ꖇ�̔����т��ւ��Ă����E�A�n�Â�w�i�ɂ��āq�ق̂��r�ɓ������́A���������ފ݂̋��ʂ��C�����̂��̂ɂ���Ď��������B�܂�u�S�H���v�ƂƂ��Ɂu���H���v�����Ƃ߂�ꂽ�̂��B�������Ƃ���u�H���l�v�Ƃ́A���̂����ȋ�ۂ̒�ӂ���́A���̋ɒ[�������Ă���悤�ɂ݂���B�v�ƂЂ�����ׂċᖡ���Ă݂�ƁA���҂̋c�_�ɋ��ʂ��Ă���̂��A�����I�ȗH���̊T�O���������ϏƐ��ł���A��ۓI���E����i�ފ݂ցj�̏��ł���Ƃ������Ƃ��悭�킩��܂��B
�@�g�{�����u���^�t�B�W�J���ȁq�S�r�v�Ɩ��Â������́A����́A�����������̐����O�i���̐��j���璭�߂鎋���A���邢�́A�▋��\��������鎋�_�ł��邩�̂悤�ł��B����ɑ��āA�莁�������u�r�݂���S�v�́A�ϏƂ���鐢�E�A������鐢�E�̂����Ȃ��ɂ����߂��S�A����̂����ʼn�������Ȃ܂Ȃ܂����S�ł��邩�̂悤�ł��B���̊��o�ɂ������Ă����A�O�҂͍L�`�̊єV���ۊw�̐��E�ɑ����A��҂͋��`�̊єV���ۊw�̐��E������Ђ炭���̂��̂ɂ�����܂��B
�@
����Ə\�̂̎O�w�\���A���邢�̓p�[�X�\�̂Ƃ̊W���߂�����܂�������
�@
�@�ق�Ƃ��͂����ŁA��Ə\�̂ƃp�[�X�\�́i�ƁA��18�͂Ŏ����������Â��Ă������p�[�X�ɂ��L�����ށj�Ƃ̊W�ɂ��āA���݂���Ř_�������ł����B����������A�L�S�i�Ǝ��S�j�Ɩ��S�ɕ���ꂽ���I���E�ɂ�����\�̐S�̋��n�ƁA�����I�Ȑ��̐��E�Ɣ��I�ȋL���̐��E�Ƃɂ����킽��\�̋L�������^�̃N���X�Ƃ̊W���߂����āA�i�ł�������ɁA�O�c�p�������w���t�ƍ݂���̂̐��x�Ńp�[�X�\�̂Ɋ֘A�Â��Ę_�����A��C�̐^�������ɂ�����u�\�E�v���u���������ЂƂ̐��E�ɂ�����ݐ��̏\�̐����v��A�䓛�r�F�����w�ӎ��Ɩ{���x�Ő^�������̗��E�}���_���Ɠ���̂��́i�u���^�v�C�}�[�W���̍\���́j�Ƃ����A�J�b�o�[���[�̏\�́u�Z�t�B�[���[�g�v�\���́��u�_�̓��I�\���v���߂���c�_�A���X��D��܂��Ȃ���j�A�Ǝ��̗��_��W�J�ł���Ɩژ_��ł����̂ł����B
�@�����āA���̂��߂ɂ́A�p�[�X�\�̂��A���̐��E�̍����I�ȎO�d��������Ηݏ�I�ɓK�p���邱�Ƃɂ���āA�L���ߒ��ނ�����̂ł��������ƁA���Ȃ킿�A��ꎟ���A����A��O�����Ƃ����O�̌��ۊw�I�J�e�S���[�ɂ��敪�ƁA����ɁA����ɂ���ċ敪���ꂽ���ꂼ��̑��ʂ̓����ɂ�����O�̑��ݗl���̋敪�Ƃ��������킹�āA�L���ߒ��ނ�����̂ł��������Ƃ܂��A����Ɠ��l�̗ݏ扻���ꂽ�O�w�\�����Ə\�̂̂����Ɍ��������Ă������Ƃ��A�c�_�̑O����Ȃ��K�{�̍�ƂƂȂ�܂��B���A���ʓI�ɁA���ɂ͂��̍�Ƃ��܂��Ƃ����邱�Ƃ��ł��܂���ł����B
�@�������̃A�C�f�A�́A���ł������Ԃ��Ă��܂��B���Ƃ��A��X�͂ŏЉ���A�p�������̘a�̑̏\����߂���~���Ҏ��̋c�_�B�����ɏo�Ă����u�r���S���v�Ɓu�f���ΏۓI�����v�Ɓu�l���}��E���v�̎O�����A�u�L���ߒ��̑�ꎟ���I���ʁ��L�����ꎩ�݂̂̍���v�Ɓu�L���ߒ��̑���I���ʁ��L���Ƃ��̑ΏۂƂ̊W�ɂ�����L���݂̍���v�Ɓu�L���ߒ��̑�O�����I���ʁ��L���Ƃ��̉��ߓ��e�Ƃ̊W�ɂ�����L���݂̍���v�̎O�敪�ɂ��Ă͂߂Ă݂邱�ƁB������N�_�Ƃ��āA�a�̑̏\��Ƃ̔�r�_���D�肱�݂Ȃ���A��Ə\�̂̎O�w�\����E�o���邱�Ƃ��ł���̂ł͂Ȃ����B���邢�́A�O�͂Œ掦�����u�S�P�^�S�Q�^�S�R�v��u���i���R�̒����j�^�S�i�ϔO�̒����j�^���i�\���̒����j�v�̎O�w�\����g�ݍ��킹�邱�ƂŁA�p�[�X�\�̂ƒ�Ə\�̂̍\���I�ȓ��^�������邱�Ƃ��ł��邩������Ȃ��B����ɁA�����Ɂi�̘_�ɓ��L�́j�u�p�v�Ƃ�����l�̃J�e�S���[�����邱�ƂŁA��Ə\�̂����\���������o�����Ƃ��ł��邩������Ȃ��B
�@�����Ŏ����l���Ă���̂́A�u���p�v�Ƃ����C���̐��E�ɑ�����o�������A�������\���҂́u�p�v�̂����ɁA���Ƃ��A�V�́E���́E�R�́i�j�́j�Ƃ���������O�̂̂����ɋ�������i�����������j�Ƃ��������Ƃł��B����́A�����a�̂ɂ�����̘̑_�����������ɂ́A�q�ω����ꂽ�̂̎p�Ƃ��Ă̐g�̂ɁA���Ȃ킿�\���҂̏���E�U�镑���ւƂȂ����Ă����̂ł͂Ȃ����Ƃ����i���āA��V�͂ŏq�ׂ��j�����ɂȂ����Ă����܂��B�p�[�X�\�̂��A�������E�̂����ɔ��I�Ȍ���̐��E���͂����܂�邱�Ƃ�����킵�Ă���̂ɑ��āA��Ə\�̂͋t�ɁA����̐��E�̂����Ɏ������E���Y�o����邱�Ɓi�N�I���A�߂��̎����琶�����y���\�i�Ƃ��Ă̐S���C���L���x�[�g����A����ɂ́A���Ƃ��u�f��I�Ȃ��́v�Ɩ��Â��邵���Ȃ��A�u����ȈӖ��ł́u���v�̗̈�v�ɑ�����\���l�����a�����邱�Ɓj���������Ă���B����Ȃӂ��Ɍ����Ă�����������܂���B
�@
�i�P�W���ɑ����j
���v���t�B�[����
�����I���i�Ȃ��͂�E�̂肨�j1950�N�㐶�܂�B���Ɍ��ݏZ�B��N���̂ɏ����ꂽ�a�̂̈Ӗ��������ł���̂͂��������Ƃ��B�ł��A�{���Ɂu�����v�ł��Ă���̂��B�����Ɂu�Ӗ��v�Ȃǂ���̂��B�����������t���g���ĉ�����`�B���邱�Ƃ��̂��̂��s�v�c�Ȍ��ۂ��Ǝv���B
Web�]�_���u�R�[���v17���i2012.08.15�j
���F�ƃN�I���A����21�́@���Ȃ���̃��^�t�B�W�B�N�E���償�����J���O�̂ƃp�[�X�\�́i�}�m�ށj�i�����I���j
Copyright(c) SOUGETUSYOBOU�@2012 All Rights Reserved.