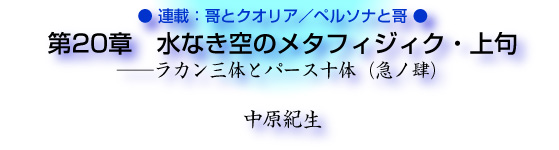|
|
|
Web評論誌「コーラ」 |
|
■創刊の辞 ■本誌の表紙(目次)へ ■本誌のバックナンバー ■読者の頁/ご意見・感想 ■投稿規定 ■関係者のWebサイト ■プライバシーポリシー |
|
<本誌の関連ページ> |
|
■「カルチャー・レヴュー」のバックナンバー ■評論紙「La Vue」の総目次 |
Copyright (c)SOUGETUSYOBOU |
|
|
|
■表現史としての和歌の歴史
ちくま学芸文庫版『初期歌謡論』のあとがきで、著者は、この本を書くことでいったい何をしたかったか、その二つののモチーフをみずから明かしています。
ひとつは、「『記』『紀』の歌謡からはじまり『古今』の成立によって確かになった和歌形式の詩を、発生の起源から形式の成立まで、歌謡という統一的な概念でたどってみたかった」というもので、この課題については、第Ⅰ章「和歌の発生」と第Ⅱ章「歌謡の祖形」、そして第Ⅶ章「和歌成立論」で論じられます。「歌謡の発生の起源から和歌形式の成立までを、初期の歌謡として連続させながら統一的に論ずるのが、わたしの願望だった。この方法は賀茂真淵と折口信夫に徴候を見つけだすことができる。この本の方法は両家にたくさんの恩恵をうけて、系譜の見方をすればこの系統をひいている。」
もうひとつのモチーフは、「わが国の詩の理論の書とみることができる初期の歌論書を、もっと理論化してみたかった」というもの。具体的には、「平安期の歌論書が説いている歌体の類別を解剖することと、歌枕とか枕詞のように景観と地名とのあいだや事物と冠辞とのあいだの固定した言葉の慣習(いわゆる「枕」)を解剖すること」の二点で、「かけねなしに難しい」これらの主題に、著者は、第Ⅲ章から第Ⅵ章まで、「枕詞論・正続」および「歌体論・正続」の論述を通じて、「できるかぎりの力能」をもって肉薄します。
これら二つのモチーフは、たとえば、同じあとがきの次の文章に記されているようなかたちで、縒りあわされ、「斬るとも刻むとも、離れ難き」(梁塵秘抄)関係を切り結んでいきます。
この、「わたしの著書で、研究書めかした体裁をもったただひとつの本」あるいは「わたしの本のなかでは、いちばん読者が少いという運命をたどった本」と語られる著書のなかで、吉本隆明氏は、和歌の歴史を「表現史」の観点から、つまり、文学表現の意識や秩序における内在的かつ必然的な契機とその変遷の、具体的な実例にそくした掘りおこしを通じて叙述していきます。「表現史はいつも表現の必然的な契機とその変遷だけを、たしからしい最後の核としてのこす。影響も余韻もそのまえでは消えてしまう。ただ内在的な契機からしかこの種の必然は掘りおこせない。」
私は、ここ数年、くりかえし本書を読みなおしてはそのたびに、随所にちりばめられた、賀茂真淵、折口信夫の系譜につながる「推し量り」の方法による着想の数々に感銘と刺激をうけ、また、驚きをあらたにしているのですが、それはまさに、吉本氏の、表現史を体現する詩人としての直観に裏うちされた方法であり着想であったからなのではないかと思っています。この章ではそのうち、もっぱら万葉集から古今集へといたる和歌形式の成立過程にかかわる議論を、要約や祖述ではない生の文章のかたちで抜きだし、次章での、定家十体をめぐる考察のための素材を蒐集していくことにします。
(「表現史」について、いまひとつ吉本氏の文章を抜き書きしておく。「…仮名文字の表現が成立してからあとでなければ『竹取』のような混淆文学体の物語が成立するはずがないなどという見解は、ばか気たものである…。文字の歴史の順序は、表現の歴史の順序とはちがう。表現史はそれを担った作者たち(説話、伝承の無名の群をふくめて)が知識的に多様な層でおなじ時代に存在しうるし、時代的に転倒して表現史的に新しいものが時代的には先に成立することもありうる。こういう文学の累層性をかんがえずに〈文学史〉という概念をつくりだしてもまったく無意味だといっていい。」)
■虚喩と畳み重ね
まず、先の引用文にでてきた、和歌形式の起源に関する「真淵、折口両家の考え方」をめぐって。
古事記中巻神武天皇記に、大久米命(おおくめのみこと)と伊須気余理比売(いすけよりひめ)とのあいだでとりかわされる応答歌が出てきます。「あめつつ 千鳥ま鵐[しとど] 何ど裂ける利目[とめ]/孃子に 直に逢はむと 我が裂ける利目」。賀茂真淵は「国歌八論余言拾遺」で、「…歌の始はことのはいと短くぞあるべき。さらば右のおほん唱和を、なほ歌の起りといはんにやとぞ、やつがれはおぼえ侍る。」と述べていて、吉本氏によると、この洞察は、折口信夫(「国文学の發生」第一稿)によって「さらに練られ、また修正されながら、もっと遡ってかんがえられた」。
ここでいわれる「歌謡の祖形でつきあたったとおなじ問題」に関連して、『初期歌謡論』の第Ⅰ章で論じられている、和語(上代語)に特有な律文化、韻文化の方法についてふれておきます。吉本氏は、「口太[くちふと]の尾翼鱸[すずき]」のような、古事記、日本書紀の時代にみられる同格同義の言葉をふたつ重ねた表現法(同一対象をより漠然と指した名詞+「の」(助詞)+同一対象をより具象的に指した名詞)のことを「畳み重ね」と名づけ、それは、和語の本質に根ざした普遍的な意義をもち、また「枕詞的なもの」の初原でもあったと指摘しています。
この「畳み重ね」もしくは「枕詞的なもの」は、吉本氏がいう「虚喩」的な関係に、すなわち、和歌形式の短歌謡の上句(前句)における客観的な叙景・叙事と、下句(後句)における主観的な叙心・叙情とのあいだになりたつ、共時かつ同型の意味論的構造に通じています。「ひろく枕詞的なものには、歌謡が自然描写の詩句と叙心の詩句との対比から成立っているとき、自然描写の詩句の部分をふくめることができる。つぎに上句と下句から成立っている短歌謡が、〈もの〉や〈こと〉を描写する詩句と、〈こころ〉を描写する詩句との対比から成立っているとき、〈もの〉や〈こと〉を描写している詩句のほうを、枕詞的なものとよぶことができる。」
たとえば、歌語としての「津のくにのなには」の意味は、「津の国にある難波」ではなく、津の国といえばすぐに連想されるところの「あの難波」というように解釈され、このあとの意味を重視すれば、「津のくにの」は枕詞の萌芽状態を象徴するものとなるが、では、あとのばあいはなぜ現われるのだろうか。吉本氏はそう問いをたて、次の解をあたえます。
畳み重ねや枕詞と虚喩の関係については、より直截に、「同格同義の〈畳み重ね〉は、もともとは一方の語が一方の語の〈虚喩〉となる関係にあり、なぜこの〈虚喩〉的な表現が律文化の過程でうまれたかについては、言語表現上の過程として説明されなければならない」とか、「枕詞を発生史的にあつかえば、まず〈虚喩〉の形がもっともはじめにやってくるのは疑いない」などと述べられています。
そのほかにも、枕詞には「言葉のトーテムのような呪意」もしくは「共同的な呪の意味」がこめられていた、あるいは、冠辞(枕詞)と受けの言葉のあいだには、現在ではわからなくなっている「共感」が介在していた、さらには、「枕詞的なものに〈もの〉や〈こと〉の描写以上の呪力がこめられていた時期から、まったく消滅してしまうまでの歌の歴史は、ある意味で、枕詞的[なもの]の在り方に凝結されているといってよい。」等々、「虚喩」的関係について考えるうえでも参考になる興味深い論点は多々あるのですが、ここではそれらの問題は素通りして、先を急ぎます。
■虚喩をめぐって、若干の余録
それでも、やはり(後の考察のためにも)書き記しておきたいことがいくつかある。以下は、個人的な備忘録として。
吉本氏は、「なぜ〈歌〉は直截に〈心〉の表現ではじまり〈心〉の表現でおわるところに成立しなかったのだろうか?」と問いをたて、そして、藤原公任が「新撰髄脳」に、「歌のありさま三十一字惣じて五句あり。上の三句をば本といひ、下の二句をば末といふ。」や「古の人多く本に歌枕をおきて末に思ふ心をあらはす。」と書いたことを踏まえて、ここでもまた、みずから解をあたえている。
吉本氏があげる実例は、折口信夫が「叙景詩の発生」で、神武天皇の「神風の 伊勢の海の大石[オヒシ]に 這ひ廻[モトホ]ろふ細螺[シタダミ]の い這[ハ]ひ廻[モトホ]り、伐ちてしやまむ」について、次のように書いていることだ。「主題の「伐ちてしやまむ」に達する為に、修辞効果を予想して、細螺の様を序歌にしたのではなく、伊勢の海を言い、海岸の巌を言う中に「はひ廻ろふ」と言う、主題に接近した文句に逢着した所から、急転直下して「いはひもとほる」動作を自分等の中に見出して、そこから「伐ちてしやまむ」に到着したのである。」
最近、その「叙景詩の発生」を巻頭に収録した『折口信夫古典詩歌論集』を眺めていて、「虚象」という、見慣れない語彙がつかわれているのをみつけた。それは、「短歌本質成立の時代─万葉集以後の歌風の見わたし」に、つごう二度でてくる。
ひとつは、「言いまわし一つで、物珍しく見せかけた」歌の実例として、九条良経の「桜さく比良の山風、吹くまゝに、花になりゆく 志賀の浦なみ」をあげ、「これは四句と五句との修辞上のかねあひから出る興味で、それが虚象を描く処に、価値が繋つている」と評しているところ。ふたつめは、新古今の恋歌をめぐって、「所謂幽玄体なる発想法」について述べられたところ。
吉本氏の「虚喩」、「虚辞」または「虚詞」を、折口信夫の「虚象」、そして埴谷雄高の「虚体」もしくは「創造的虚在」に(さらには、時枝誠記の、「虚記号」ならぬ「零記号」に)関連づけて考えてみる。ある時期から、そんな妄想じみたアイデアが浮かび、しだいにその内圧が高まっている。その際、虚喩が、和語特有の語法である畳み重ねや枕詞と関連づけられているからといって、それが和語表現に限定されるものではないことに思いをいたさなければならないと思う。以下は、講演録「喩としての聖書」(『〈信〉の構造2──キリスト教論集成』所収)での、吉本氏の発言。
■虚喩から喩の消滅へ
さて、(掛けあいという歌謡の初原の形をたもち、上句と下句の「共時的な意味の二重化」としてあらわれる)和歌形式の短歌謡における「虚喩」は、次の段階で、「もっとも短歌謡らしい喩」である「暗喩」に転じていきます。たとえば、万葉集巻三に収録された「瀧の上の三船の山に居る雲の 常にあらむとわが念はなくに」をめぐって。
上句(序詞)が直喩の機能をもつようになった歌、たとえば万葉集巻七、「樂浪[さざなみ]の志賀津の浦の船乗りに 乗りにし心常忘れえず」の歌をめぐって。
万葉復興をとなえた初期のアララギ派の歌人たちが、散文における写生文とおなじように、「客観描写の〈声調〉の卓抜さ」を読みとった歌、たとえば、万葉集巻十四の「信濃なる須賀の荒野にほととぎす鳴く聲きけば時すぎにけり」をめぐって、吉本氏は、「ありのままの叙事のようにみえるこの短歌謡の背後には、過ぎてはならぬ生々しい心があり、一首の表現はその潜在した心の〈喩〉だったとみられる。」と書き、そのような、叙事や叙景、枕詞や虚喩がもつ「象徴性」の役割を短歌謡の全体に拡げ、一首の短歌謡の意味の中心となるべき主観的な表現が言葉の背景におしかくされてゆく形を「全体喩」と名づけています。
■物から心へ─第一のメタフィジィク
それでは、和歌形式の短歌謡がおわり、「やまとうた」としての和歌が成立するためには、どのような条件が必要だったのか。吉本氏によれば、それは二つあります。いわく、「『古今集』における〈和歌〉の成立には、上句と下句のあいだの転換の重さをふりきることが必須の条件だった。そのためには〈自然〉との関係の仕方の変容と、叙情や叙心の内容の変化が、歌人たちになければならなかった。」
まず、「〈自然〉との関係の仕方の変容」をめぐって。
柿本人麻呂の「山の峡そことも見えず白樫の枝にも葉にも雪のふれれば」と、貫之が詠んだ「山の峡たなびき渡る白雲は遠き櫻の見ゆるなりけり」を比較して、吉本氏は次のように述べています。
これに対して、貫之歌「山の峡たなびき渡る」には、人麻呂歌の「叙景がもっている心騒ぎのようなものは、まったくなくなっている」。
「古今的なもの」を体現する貫之にあっては、短歌謡における「自然との交霊」が喪われ、もはや、「自然と心情の交歓と解放」であるように詠むことができなくなっている。このことを、吉本氏は、「歌が、景物をメタフィジィクによって書き改めているので、このメタフィジィクが全体を、持続するなめらかな曲線にしている」と表現しています。そして、貫之の秀歌や忠岑の「春日野の雲間をわけて生い出くる草のはつかに見えし君かも」などにみられる「古今的な」手法について、次のように指摘します。
もうひとつ、額田王の歌「三輪山をしかも隠すか雲だにも情[こころ]あらなむ隠さふべしや」と、貫之の歌「みわ山をしかもかくすか春霞人にしられぬ花やさくらむ」とを比較して。
かくして、「やまとうた」としての和歌が成立するための第一の条件「自然との関係の仕方の変容」がクリアされました。
■メタフィジカルな統覚作用
つぎに、第二の条件「叙情や叙心の内容の変化」をめぐって。
凡河内躬恒に「夏と秋と行きかふそらのかよひぢはかたへすゞしき風やふくらん」という歌があります。吉本氏による大意は、「今日で暦の夏がおわり秋がやってくる。あの空のみえない彼方のとおり路で、夏は去るがに秋は来るがにすれちがってゆくのか。そのとき秋が来るがのかよい路の、片側だけが涼しい風がふき、ここへもやってくるだろう」というもの。
自然という「おおきな容器」のうちにある短歌謡の「心」(感情)から、景物の世界を内在化し、自然にかたち(表現)を与える「メタフィジカルな統覚作用」としての和歌の「心」(思想)へ。ここで肝心なことは、その「メタフィジィク」そのものが「表現をとおして、はじめて実現される態のもの」であったことです。「まったくあたらしく、〈和歌〉の成立を告げる暗喩」であり、「しかもたんなる比喩ではなかった」とされる語句をふくんだ、「雪のうちに春はきにけりうぐひすのこほれる涙いまやとくらん」や「なきわたる雁の涙やおちつらん物思ふやどの萩のうへのつゆ」をめぐって、吉本氏の議論はつづきます。
さらに、「はやき瀬にみるめおひせばわが袖の涙の川にうゑましものを」や「しぐれつつもみづるよりもことのはの心の秋にあふぞわびしき」や「水のうへにうかべる舟の君ならばこゝぞとまりといはましものを」などの歌をめぐって。
■物・心・詞・姿
古今的なものの世界では、「物」と「心」が「詞」によってじかに結びつけられる。(物の構造と心の構造が同型だから、そしてまた、物と心の二つの世界にあいまたがる詞の構造がこれを反映しているから、そんなことが可能になるのだ、と言うことができる。むしろ、構造的には相容れない物と心を通底させるものとして詞の構造がなりたつからこそ、そんなことが可能になるのだ、とも言える。)そして詞は、(自然にかわる新しい容器となった)心による統覚作用を通じて、物と心に表現の秩序としての形態を与える。その形態(形象的なイメージ、もしくは音韻像)を「姿」とよぶならば、(「物=シニフィアン」と「心=シニフィエ」が結合して「詞=シーニュ」になるとして、その詞のかたちのことを「詞姿=フィギュール」とよぶことができるならば)、ここに、貫之歌「むすぶ手のしづくにゝごる」をめぐる俊成の評言、「ことばことのつゞき、すがたこゝろかぎりもなきうたなるべし」にあらわれた、「ことば」と「こと」(物)、「すがた」と「こゝろ」の四項がでそろうことになりました。
私の理解では(というより、私なりの語彙では)、『初期歌謡論』における和歌史の議論は、おおよそ次のように縮約することができます。
まず、自然、すなわち「物」の世界という大きな「容器」(プラトンの「コーラ」、西田幾多郎の「場所」に通じるもの)があって、そのなかで、(和語特有の畳み重ね、もしくは言語活動に普遍的な虚喩的表現を介して)、「心」がインキュベートされる。この「心」のことを「心0」(零次性の心、もしくは霊)と表記するなら、かくして、「物」の世界との交霊・交歓・交感を通じて、アニミズムやシャーマニズムにつながる(私の語彙でいえば、「哥というギフト」につながっていく)「心0」が定まる。(短歌謡、万葉集)
ついで、そうやって(虚喩的言語表現を媒介として)産出された「心0」群の集蔵体がひとつの領野をかたちづくり、それが、新たな「容器(コーラ、場所)としての心」(広義の貫之現象学の世界、あるいは「哥のパランプセスト」)となる。それまでの関係が逆転して、こんどはそこに「物」がとりこまれるようになる。この「物」の世界に秩序(かたち)をあたえるのが、「はたらき(メタフィジカルな統覚作用)としての心」(狭義の貫之現象学の世界をかたちづくる「いひいだす」力、あるいは「フィギュールとしての哥」)で、そのとき起動されるのが「心1」(一次性の心)である。(それは、実は、容器としての心のうちに内在化された「心0」が現働化したものである、といってもよい。あるいは、「やまとうたは、人のこころをたねとして、よろづのことのはとぞなれりける。」というときの、その、やがて詞へと生長していく「人のこころ」、もしくは「よろづ」のものが詞へと変成・編制されていくときの媒介、媒質となる「人のこころ」のことである、といってもよい。)この「心1」の立ちあがりによって、つまり「詞」による修辞的な表現活動を通じて、「見るものきくもの」(容器としての心にとりこまれた「物」)に付託して表現されるのが、「世の中にある人」が「心におもふこと」、すなわち「物」と同じ次元に属する事実としての「心2」(二次性の心)である。(和歌、古今集)
やがて、その、容器としての心のなかでインキュベートされた「詞」による表現の秩序を媒介にして、修辞的な表現物としての「姿」(歌に詠まれたイメージ、もしくは音韻・文字のかたち)が、象徴的な「心3」(三次性の心)として形象化される。すなわち、事実としての物=心の世界を表現の世界へと超出させる第一のメタフィジィクの徹底によって、(あるいは、「かの古今集の序にいへるがごとく、人のこころを種として、よろづの言の葉となりにければ、春の花をたづね、秋の紅葉を見ても、歌といふものなからましかば、色をも香をも知る人もなく、何をかはもとの心ともすべき」という、俊成的転回を介して)、いわば「容器としての詞」の世界がかたちづくられ、さらに、そのなかでインキュベートされた「姿」が、第二のメタフィジィクのはたらきによって、あたかもこの世を他界から眺めるがごとき「境地」として実在化される。(和歌、新古今集)
議論が先走り、混迷の域に達してしまいました。貫之現象学における「水なき空」に立ち騒ぐ「波」の十態、つまり定家十体における「心」の実相は、いったいどのようなものだったか。この(後段あるいは下句の)話題に転じるまえに、(前段あるいは上句の話題の締めとして)、第一のメタフィジィクがもたらしたものについて、壬生忠岑の和歌体十種をめぐる『初期歌謡論』の議論の一節を抜き書きしておきます。それは「写思体」を論じたもので、忠岑の註、「此ノ體ハ、志胸ニ在リテ顯シ難ク、事口ニ在リテ、言ヒ難ク、自ラ想フ心ヲアラハシ、歌ヲ以テ之ヲ写ス。言語ハ道フヲ斷チ、玄マタ玄也。況ンヤ餘情ト其ノ流レヲ混ジ、高情ト其ノ流レヲ交フ。」云々をめぐって、吉本氏はこう論じています。(私には、忠岑の註は、きたるべき定家の「有心様」を予見しているようにみえるし、吉本氏の評言が暗にいっているのも、そのことにほかならないと思える。)
★プロフィール★
中原紀生(なかはら・のりお)1950年代生まれ。兵庫県在住。千年も昔に書かれた和歌の意味が理解できるのはすごいことだ。でも、本当に「理解」できているのか。そこに「意味」などあるのか。そもそも言葉を使って何かを伝達することそのものが不思議な現象だと思う。
Web評論誌「コーラ」16号(2012.04.15)
<哥とクオリア>第20章 水なき空のメタフィジィク・上句──ラカン三体とパース十体(急ノ肆)(中原紀生)
Copyright(c) SOUGETUSYOBOU 2012 All Rights Reserved.
|
| 表紙(目次)へ |