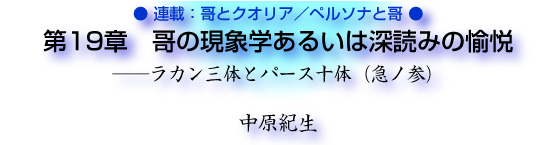|
|
|
Web�]�_���u�R�[���v |
|
���n���̎� ���{���̕\���i�ڎ��j�� ���{���̃o�b�N�i���o�[ ���ǎ҂̕Ł^���ӌ��E���z �����e�K�� ���W�҂�Web�T�C�g ���v���C�o�V�[�|���V�[ |
|
���{���̊֘A�y�[�W�� |
|
���u�J���`���[�E�������[�v�̃o�b�N�i���o�[ ���]�_���u�k�� Vue�v�̑��ڎ� |
Copyright (c)SOUGETUSYOBOU |
|
|
|
���~�[�e�B���O�E�v���C�X�Ƃ��Ă̐[���\���A���邢�͚F�̐����w
�@�O�͂ŁA���X�ؒ����w���Ɖi���x����A���̈�߂�����������v�v���́u�u�n���Ɩ��������v�����n��̐����w�Ɍ����āv�i�w�A���A�h�l����̎��x�����j�ɁA�u���̂̊l���v�Ȃ��ɑn��s�ׂ͂Ȃ肽���Ȃ��Ə�����Ă��܂��B
�@���䎁�͂Â��āA��\���I�㔼�̕��w�̐����́A�u���́v�T�O���u�e�N�X�g�v�T�O�ɒu���������Ƃɂ���i�u����ɂ���č\����`�͊����e�N�X�g�c�̐����ȕ��͂ɂ���������A��ꋉ�̕��w�Y����̂Ɏ��s�����B�v�j�Ƃ��A�܂��A���ӎ��͌���̂悤�ɁA���邢�͌���Ƃ��đg�D����Ă���Ƃ����Ƃ��A���J��������������ς�u�ے��E�v�ɑ�������̂Ƃ��ė������Ă������Ƃ�ɂ��݁A����ɁA���̊l���̌�ɂ͂��߂āA����͍�Ƃ̂Ȃ��Ŏl�Z�����������ƂɂȂ�̂��Ƙ_���A�������āA���炽�߂āu���́v�Ƃ͉����Ɩ₢�܂��B
�@�����ɏ�����Ă���̂Ɠ�����|�̂��Ƃ��A�i���m�ɂ́A�~�[�e�B���O�E�v���C�X�Ƃ�����b��p���A����̓��̓I�����⋤���o�I�A�^�����o�I�ȕ����A����Ƃ��Ă̈��u�A���X�Ɍ��y�������͂��j�A�u�̐����w�v�Ƃ����w�A���A�h�l����̎��x�Ɏ��߂�ꂽ�ʂ̘_�l�ɂłĂ��܂��B
�@�`�����X�L�[�̊T�O�Ƃ͈قȂ�u�[���\���v����́u�~�[�e�B���O�E�v���C�X�v�ł��邱�Ƃ̏؋��Ƃ��āA���䎁�́A�O���l����ɊO����ōs�����ʐڂ��A���̉�z�ɂ����āA�u�}�g�̎��R�ȁA��b�̂́A����ɐ��_��w�I�ʐڂɎg����ⓚ�̂̓��{��v�ɕϊ�����邱�Ƃ������܂��B
�@�`���ƓƑn�A�ӎ��Ɩ��ӎ��A���̑��A���̑��̑�������ΊT�O���o��~�[�e�B���O�E�v���C�X�B���Ȃ킿�A����̓��̂Ƃ��ẮA�����ē�̌��ꂪ�o��u���̐[���\�������̌��ꁁ�v������v�Ƃ��Ă̕��́B����́A�ǂ�������A�i��14�͂łƂ肠�����j�╔�b���́u���킢�v�ibetweenness-encounter�j�ɒʂ���ꏊ���v�킹�A�����āA�i��13�͂Ō��y�����j�x���N�\���́u�^���I�}���v��A�z������Ƃ��낪����܂��B
�@�܂��A���䎁�������u���u�v��u�����v�Ƃ�������b�́A�u�̂͂�����݂��������A�r����������ɁA���ƂȂ����ɂ����͂�ɂ�����鎖�̂���Ȃ�ׂ��B���Ƃ��r�̂Ƃ��ЂāA���ɂ��đP�������������������̂Ȃ�B�v�]�X�̓����r���i�×����[���j�̌��t��z�N�����A����ɁA�a�̂��u���Z�v�i�{���̋C������T�����߂�c�݂Ƃ��ẮA�����āA�{���̋C�����������̂��̂Ƃ��Ĉ����悤�Ƃ���w�͂Ƃ��Ẳ��Z�j�Ƃ����ϓ_���番�͂��A�����E�����E�|���E����E�{�̎�蓙�X�̘a�̂̃��g���b�N���A���Z�ɖ������ꂽ��Ԃ��Ȃ킿�u�V��I��ԁv���ĂыN���������ɂ����ĂƂ炦���A�n���ז����i�w�a�̂Ƃ͉����x�j�̋c�_���v�킹�A�Ō�ɁA�u���ۊw�ɂ���đΏې�������Ƃ����͉̂��o�Ƃ̎d���̂悤�Ȃ��̂ł��B���o�Ƃ͋r�{����̓I�ȏo�����ֈڂ��܂��B����o�������ŏI�I�ɕ���̏�ɏo�����A��Ɍ�����悤�ɂ��邽�߂ɂ́A���܂��܂Ȏd�|����ɍڂ��Ȃ�������Ȃ��̂ł��B�v�Ƃ��������B�i�X�̕��́i�w�\�͂Ɛ����x�A���c�����w�����B�i�X�ƈ��̌��ۊw�x����̑������j��A�z�����܂��B
�@�l�I�ȘA�z�̗�L�͂��̂�����Ŏ��l���邱�Ƃɂ��āA�����ł́A���䎁�̓�̘_�l�Ɏh���������āA����u�F�̐����w�v�̂悤�Ȃ��̂��\�z���A�u�����ꂽ���́v�Ƃ��Ă̘a�̂ɂ�������̓I�����A���Ȃ킿�~�[�e�B���O�E�v���C�X���[���\������̑̂��l�@����Ƃ��A�u�r�܂����́v�Ƃ��Ă̘a�̂ɂ�����u�N�u�v�ɑ���������̂���������Ƃ���A�u�[�ǂ݁v���������̓��̂��̂ɂق��Ȃ�Ȃ��̂ł͂Ȃ����A�Ǝw�E����ɂƂǂ߂Ă����܂��B
�@
���[�ǂ݂̖��x�A�ےJ�ˈ�̏ꍇ
�@�a�̖̂����݂́A�[�ǂ݂ɋɂ܂�B�������N�A�f���I���f�ГI�ɁA�Í��W����V�Í��W�܂ŁA�̐l�ł����A�єV����r�����o�Ē�Ƃɂ�����A�����a�̂̐��E�̈�[��`�����Ă��邤���ɁA�i�����āA�єV���r�u�e����Δg�̒�Ȃ�Ђ������̋��킽���ꂼ��т����v��u���o���鏼�ɂ͂���njÂ̐��̊����͂��͂炴�肯��v�Ȃǂ̎����f�ނɁA�[�ǂ݂Ƃ������͂ނ���A�ǂ݂������Ƃ������ɓǂ݂���ł����f�l�Z�̓lj���Ƃ��d�˂Ă��������j�A�������ɂ��̂悤�Ȏv�����Z���Ȃ��Ă��܂����B
�@���������a�̂ɋ����䂩��邫�������ƂȂ����A�ےJ�ˈ꒘�w�V�X�S�l���x�ɂ́A���l�Y�̈�ɂ������������ƃA�N���o�e�B�b�N�Ȓ���Z�I�Ƃł����ĉ����������ꂽ�A�[�ǂ݂̐^���A���̖͔͂Ƃ������ׂ��]�߂��ӂ�ɂ���߂��Ă��܂��B�������́A�L���Ȋw�B�Ƒn��̌��A�����ĂȂɂ������m�ȕ��@�ӎ��ɗ��ł����ꂽ���̂Ȃ̂ł����āA�u�[�ǂ݁v�ȂǂƂ����A�ǂ��������ȋ���������b�ŊےJ���̋Ɛт��`�e���ׂ��ł͂Ȃ��̂�������܂���B�i���m�ȕ��@�ӎ��Ƃ������ƂɊւ��āA�ꌾ����A�w�V�X�S�l���x�̕��ɉ����Ɏ��^���ꂽ�Βk�ŁA���҂́A���̒�ƂƂ̗���̈Ⴂ�ɂ��āA�u��Ƃ͕��w�ɋÂ�ł܂��Ă���l�����ǁA�l�͂����ł͂Ȃ��v�A�u�l�́A�P���u���b�W�w�h�̕����l�ފw�I�Ȍ|�p�����Ɛ܌��w�h�̖����w�I�ȕ��w�����̉e�����Ă��āA���w����p����W�J���Ă������̂Ƃ��đ����Ă��܂�����v�Ɣ������Ă���B�j
�@
�@���܂����ŁA��̗��������Ȃ�A�r���́u���[�̂Ƃ킽��M�̊��̗t�ɂ����H�����I�̂��܂Â��v����肠���ẮA���[�Ղ���߂��閯���w�I�D�~���X���i�ʖ�i�E�G�C�N�j�ɂ�����A�C�������h�̏K���ɂ܂Řb�肪�y�ԁj�A�܌��M�v�́u���̏��v���̑��̘_�l����c���j�̍l�@�ɂ��G��A���̏�ŁA�����`�Â����w�̉ؗ�ȉ���W�i���̑w�́A�u���[�v�u��i�Ɓj�v�u�n��v�u�M�v�u���i�E�E�D�j�v���X�̓V�̐�̌n��A���̑w�́A�u���̗t�v�i���̎��̔�͎��̌����j�v�u�����v�u�I�v�u���܂Â��i�莆�j�v�ƂÂ������̌n��j�ƁA���̉����I�����𒊏o����B�u�r���̈��́A�u���v�u�����H�v�u�����v�Ƃ��������肩�����Ȃ�����A�u���[�v�u�Ɠn��v�u�v�u�I�v�u���܂Â��v�Ƃ����̂��т���������������Ƃ��Ă��B���̈���[�������̘A���͐��̂������鉹�ł����B�F���̐��ł����͂̐����m�V�̐�̌n�����p�Ғ��n�́A�_�b�Ɠ`���ƍ��J�ɂ�āA�l�Ԃ̐��Ƃ��Ă̟��m�����̌n��Ɍ��т��n�Ɍ��т��Ă��B�v
�@�܂��A�r���̒�q�E���q�i�̂肱�j���e���́u�킪���͒m��l���Ȃ��������̟��m�Ȃ݂��n���炷�Ȃ��̏����m���܂���n�v���߂��镶�͂ł́A�����A�Ñ�l�ɂƂ��ĒP�Ȃ�Q��ł͂Ȃ���p�I�Ȃ��̂ł��������Ƃ��A���_���Ɠ��{�̎���A����ɂ́A�Ñ�l�ɂƂ��Ė��Ƃ͐_��A��A�����m�������܁n�̏h��Ƃ���ł������Ƃ���܌��M�v�̏Ȏ@��A�N���͍��A�}�i�^�j�͔��̂̂��߂̐ړ���Ƃ���ꌹ���ł����Ę_���A�u����������Ӊ����a�̂��ӏ܂���ɓ��ẮA���̖����w�I�Ȓm������ɉ��قǂ��S�ɂƂ߂Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̂��Ƃ�Y��A�P�Ȃ���̂Ƃ��ĉ��߂����̂ł́A�̂̏d�w�I�Ȗ��͂Ђ����͂�A��̐��̂ɂȂ邾�낤�B�v�Ɖ����A��̐Q���ŔE�ԗ��ɋ������������Ƃ߂�u���̏����v�́u���v���u���k�v�Ɓu�����v�ɂ�����͉̂����a�̂̏퓅�ŁA����͂��Ԃ�A��������E��؏�́u�������ɂ݂���̂ɂ��������m���Â�n�����̏����m�������n���_���Ԃ�܂Łv�̉e�����A�����Ȃ��Ƃ��r�����u�������Ƃ��̖��������Ăĕ��������Ȃ������̉����ȁv�Ɖr�̂͂���ɂ����̂�����A���̏r���̉e�����Ď��q���e���͈����r�̂��낤�Ƒz������B
�@
�@�����́A���O�́u���Â����������Q�������͂�C�̓s���H�◧���v�̑��w�I�ȍ�i���E����͂���������ł��傤�B���҂͂܂��A����u�������Q���v���ɕ����āu���Â����������^�Q�������͂�v�Ɠǂ݁A���̑O�i�́u�����v���܍s���ɂ��ƂÂ��u�H���v�ł��邱�ƁA�܂��A��i�́u�Q�̉����͂�v�͑�܋�u�H�◧���v�Ɗ֘A���A���̋�̔w��ɗ��H���r�����a�̂̒������j���Ђ���ł��邱�Ɓi�u�H���ʂƖڂɂ͂��₩�Ɍ����˂ǂ����̉��ɂ����ǂ납��ʂ�v�̏G�̂��A�Ă���H�ւ̕ω��̔����ȈႢ�̂����Ɍ��o�����{�l�̑ԓx��l���I�Ɍ��肵�A���ɂ́A���O�̂ɒ��ډe����^�����r���́u���H���H�₽����͐����͂�Ȃ�{���̉Y�g�v��u�{���̊ւ����̏��������Ă���~�Â̔g�̉����ς��v�ɉr���Ă���悤�ɁA�Q�̉��̕ς���ɐS�𗯂߂邱�ƂɂȂ�j�A���ŁA��l��ɂ����u�C�̓s�Ƃ͂��Ȃ͂����{�̂��ƂƂ��ӂ͓̂��{���w�̋v�����ɂ킽����v�ł��邱�Ƃ𖾂炩�ɂ��Ă����܂��B
�@�ȏ�̒i�������ŁA�ےJ���́A���O�̉̂��O�̑w���D�������܂��B���̑w�́A�w���ƕ���x�B�d�̉Y�œ�ʂ̓u�Q�̂����ɂ��s�̂��Ԃ�ӂ��v�ƈ����V�c�Ɍ����������ē�������u���g���v��A�����@���d�������ΉY�Ō������Ɂu�̂̓����ɂ͂͂邩�ɂ܂��肽�鏊�v��������A�����ɐ��i�����j���͂��߈��̌����a��l��������ł���̂����āA�u���͂��Â����v�Ɩ₤�ƁA��ʂ̓�炵���l���u���{��v�Ɠ�������u�Z���V�����v�̂�������Љ�A�ےJ���́A���O�̈��Ƌ��{�̉̂Ɍ����Ă܂��B�u���������Ƌ��{�͐��Ӓn�\�̑w�ɂ����Ȃ��B�v
�@���̑w�́A���{�`���B�����ň�߁A���̐��b���߂����D�~����I����A��O�́w��������x�̑w�ւƓ]���Ă����B�i��Ɉ������r���̏H�̓�A�{���ɗ����ꂽ��������ʉe�ɂ��Ă������Ƃ������āj�A���O�́A�{���̊��̖����Ō����������C�_�ɏ�����閲�ɂ��āA���̓����𗴐_�ɁA���̖��i�̂��̖��̏�j��L�ʕP�ɁA���̒n�𗴋{�Ɍ����Ă���߂̏�ɗ����āu���Â����v�̉̂��r�̂͊m���ŁA�����ł���Ȃ�A�s�֖߂������������̏�ɑ���u�Q���������̉Y�ɒ����̗���Ɛl���v�Ђ�邩�ȁv�̑����̂��A���t�W�́u�����������������킬�������V���̖��ɖO���܂����̂��v�����̂ɂ��Ă��邱�Ƃ���A���O�̉̂͒P�Ȃ�H�̂ł͂Ȃ��A���̓����͗��̂������̂ł���A�܂��A�����@�����{�̖��������̂����ł������̂́A���ƕ���̍�҂������w�����x�ɔ����Ă�������ŁA���O�́A�����������w�I�`���̂����Ȃ��ɂ����āA�u�������̕���ƕ��ƖŖS�̕���̑o���ɏo�ė��閾�����{�̃C���[�W�v��p�����̂��Ƙ_���A�Ō�ɁA���O�ɂƂ��āA��������ƕ��ƕ���Ƃ͕������������A���̂�������������M���̐����Ƃ������݂邽�߂̎肪����ł��������ƁA�����Ă����l����A�u�C�̓s�v�Ƃ́A�̓����p�ꂽ��A���\�̓s�����t�����ō�肠���A���̂Ȃ��Ő����Ȃ���Ȃ�Ȃ��j�̖��݂��u���w�I�ȏ�����v�ɂق��Ȃ炸�A�����Ȃ�A�C�̓s�̔w��ɂ͂����n���Ƃ��Ă̖��ȂǂȂ��Ă��悭�A�����̖��Ƃ��Ă̖����������ł悩�����̂��i�u�l���u�g��R�͂��Â�̍����v�Ɛq�ˎ���A�u���Ԃɂ͂悵�̎R�A���݂��ɂ͗��c��ǂނ��ƂƎv�Еt���āA�ǂݎ���v��ɂāA�ɐ��̍�����A�����̍����炸�v�Ƃ����֎���ׂ���B�v�j�Ɛ����B
�@�܂��Ƃɐ�i�A��i�A�L��̈�ɒB�����u�[�ǂ݁v�̋ɒv�A�T�^�Ƃ��ׂ��_�q�ł��B�������A�b����C�ɉ����a�̂̏I���ɂ܂ŋy��ł��܂��܂����B
�@
���̂̃A�X�y�N�g���L�q���邱�ƁA���邢�͚F�̌��ۊw
�@�a�̂́A�����悤�ɂł����߂��邱�Ƃ��ł���B��������ɁA���̂�����Ȃ��@�A�n�݁A�T�݂��v�邱�Ƃ͂����܂ł�����܂��A���̉����a�̂̈�ؓ�ł͂����Ȃ����`���A�d�w���̂���Ă�����Ƃ��낪�A���̕����ˑ����⋕�\���A�܂��A�O�\�ꕶ���A�������̕��������^�ɂ�鐧��Ƃ������A�\���̏�Ƌ@��A�Z�@����e��`���ɂ���������ɂ��邱�Ƃ́A�݂₷���������낤�Ǝv���܂��B
�@������������������ՓI�ȈӖ����������߂Ă���������ƁA���������u���I�Ȃ��́v���������ɂ͂��ł�����p���������͋V�琫�ƁA����炪����I�Ќ�I�����̉ʂĂɐg�ɂ܂Ƃ����ƂƂȂ����ے����������͗V�Y���̂䂦�ɁA�a�̂��r�݁A�܂��ǂނ��Ƃ��̂��̂��A�Ԓ���������̂�������ӂ��߂����R�ƁA����ɑΛ�����S�ƌ���̐��E�Ƃ��D��Ȃ����`�I�ŏd�w�I�ȊW���̂����Ȃ��ɐg�𓊂��Ă������Ƃɂق��Ȃ炸�A���������āA�̂ɂ����镨�ƐS�Ǝ��̈ʒu�Â����߂���u�̂̕��́v���邢�́u�̂̎v�z�v�̂���悤�ɉ����āA���̘a�̂͂����悤�ɂł��u�[�ǂ݁v���邱�Ƃ��ł���̂��A�Ƃ������ƂȂ̂ł��傤�B
�@
�@�[�ǂ݂��\�ɂ���̂̑��w���Ɋ֘A���āA�����ɁA���c�����w�����B�i�X�ƈ��̌��ۊw�x���́u��|�ϑz�I���ۊw�v�̋c�_��}�݂܂��B
�@���c���͂����ŁA�u���邱�Ɓv�i�ϑz���e�I���A�j���ӎ��̍����I�ȑԓx�Ƃ���t�b�T�[���́u���v�̌��ۊw�A���́u���w�I�Ό��v�ɑ��郌���B�i�X�̔ᔻ��c�q���A�����B�i�X���g�̔�ϑz�I�Ȍ��ۊw���u�Ӗ��v�̌��ۊw�Ƃ��āA�u�_�v��u���v��u�e�N�X�g�v�̌��ۊw�Ƃ��ĕ`�������Ă��܂��B
�@�u�߂����v���ƁA���Ȃ킿�u�����̑Ώۂ́A���̂ǂ́u�m�G�}�I�l���v�ɑ����Ă����^�����܂���B�t�b�T�[���́A�u�Ώۂ̂��̂ǂ̓���Ȍ�����v�������͂���Ώۂɂ��āu�Ӗ��I�ɔc�����ꂽ���́v���A�u�Ώۂ��̂��́v�Ƌ�ʂ��邽�߂Ɂu�m�G�}�v�ƌĂсA����A�u�m�G�}�v���u������ӎ��̂�����A�u�Ӗ��I�ɔc��������\��v���u�m�G�V�X�v�ƌĂт܂����B���F�i�m�o�j�A�z�N�A���^�A���X�̃m�G�V�X�̂�����ɉ����āA���̂ǃm�G�}�̌������A�A�X�y�N�g�i���j�͕ς���Ă����܂��B
�@�Ώۂ́A���̑S���̃A�X�y�N�g����C�Ɉ�]���Ղ����悤�Ȏd���ł͗^�����܂���B����ǂ��A���A�����ŁA���i�����j�Ɂu�\�S�I�Ȏd���ŗ^�����Ă��鑊�ȊO�̑����܂��ԐړI�Ɍ��O���Ă���A�Ƃ����d���ŁA�������͂��́u�S���m�G�}�v�ɒ��ϓI�ɐG��Ă���v�̂ł����āA���̒��ς́u���v�Ƃ��Đ��A����ƃt�b�T�[���͂����܂��B
�@�єV���ۊw�����̈ꕔ�Ƃ��đg�ݍ��ށA�F�̌��ۊw�Ƃ������̂����肤��͂��ł���B����́A�u���̂ǂ̃��j�[�N�Ȑڋߖ@�ɉ����āA���̂ǃ��j�[�N�ȃA�X�y�N�g���J������u�S���m�G�}�v�v�Ƃ��Ẳ̂̐S��p���u��������́i�����B�i�X�����ۊw�́u�V�����v�Ƃ��ċ���������_�����p����A�W�c�I�ɗ��������m�ł���A���҂ւ̉�H���m�ۂ��悤�Ƃ�����́j�ł���B�����a�̂�[�ǂ݂���Ƃ������Ƃ́A���������̂̃A�X�y�N�g���߂���m�G�}�I�l�����L�q���邱�Ƃɂق��Ȃ�Ȃ��B
�@����Ȃ��Ƃ�������̂ł͂Ȃ����ƁA���͍l���Ă��܂��B�����Ă܂��A�i�ȑO�A��T�͂ŁA���̎v�����̈�[���q�ׂ��A�����o�����L�q����l�̎��I����̘b��Ɋ֘A�Â��āj�A�u���A�����A���A����v�̂��ꂼ��ɑΉ�����u�Ӗ��A�m�o�A�_�A���v�̎l�̌��ۊw�������邱�ƂŁA�u�S���m�G�}�v�Ƃ��Ẳ̂̂��ׂĂ̑��e���L�q���ꂤ��̂ł͂Ȃ����Ƃ��B
�@
���[�ǂ݂̖��x�A�����r���̏ꍇ
�@�Ƃ���ŁA��ɁA�J�M���ʂ��ň������u�̂̕��́v��u�̂̎v�z�v�Ƃ�����́A�g�{�������w�����̗w�_�x��Y�́u���̘̑_�v�̖`���ɏo�Ă��錾�t�Łi���Ȃ݂ɁA�u���I�Ȃ��́v����������j�A�g�{���͂����ŁA�����̘a�̑̏\��ƒ�Ə\�̂̂������A���Ȃ킿�Í��W�ƐV�Í��W�Ƃ̂قړI���̍Ό��̂������ɁA�u�̂̕��́v�ɂ��Ăǂ������ϖe���������̂��A�u�̂̎v�z�v�ɂ��ĂȂɂ��N�������̂���₤�Ă��܂��B
�@�Z�̗w����a�̂ւ̕ϑJ��A�Í��W����V�Í��W�ւ́A����������A�u�ӊ����t���邢�͌Í������̘a�̂��u�É̑́v�Ƃ��ėޕʂ̊�ɂ����߁v���a�̑̏\�킩��A��y���I�Ȍ�������̊����ɂȂ���u�L�S�l�v����Ƃ����Ə\�̂ւ̓��s���A�����āA�����́u�����ɂ�����ϖ@�̋��U�v���A�r���ɂƂ��ẮA�V�䋳�w�i�w���d�~�ρx�j�ɂ����Ƃ���̋�E���E���̎O�ςł��������ƁA���X�̘a�̎j�I�Ȏ����ɂ��ẮA��ɁA���邢�͎��͂ł��炽�߂ĂƂ肠����Ƃ��āA�����ł́A�r�����u�×����[���v�ŁA�єV�́u�ނ��Ԏ�̂��Â��ɁT����R�̈�̂����ł��l�ɂ킩��ʂ邩�ȁv���A���������́u������݂���͂��R�̂قƁT�������ڂ��Ȃ����Ȃ��킽�邩�ȁv�ƂƂ��Ɂu�̖̂{�����v�ƕ]���������Ƃ��߂���A�g�{���̋c�_�����Ă��������Ǝv���܂��B
�@
�@�܂��A�єV�̂ɂ�������r���̕]���A�u���̉̂ނ��Ԏ�̂Ƃ����邠��A���Â��ɁT����R�̂�̂Ƃ��ЂāA�����ł��Ȃǂ��ւ�A���ق������ׂĂ��Ƃ��Ƃ̂U���A���������T�납������Ȃ������Ȃ�ׂ��B�����̖{�����͂��U���̉̂Ȃ�ׂ��B�v���߂����āB
�@�����ł��A����̏��S��U��������̏����I�\�������t�ӊ��ɂ͂�����͂��߂��A�]�X�̘a�̎j�I�L�q�ɂ��ẮA���͂ɂ䂾�˂邱�Ƃɂ��܂��B
�@�g�{���͂Â��āA�u�ΊԂ̂킫�����d���Ĉ������Ƃ����̂Ђ�̂���������A���ڂꂨ���鎴�ŁA�킫���������Ă������悤�Ɉ��߂Ȃ��B���̂킫���̂Ƃ���ł䂭��Ȃ��o���������Ƃ����ƌ��t�����킵�����̂ɂ������悤�Ɍ��t��s�������ɁA�S���c�����܂ܕʂ�Ă��܂������Ƃ��v�Ƃ����قǂ̈Ӗ��ɂȂ�A���́u�I�݂ł͂��邪�A�����Ɍ��肳�ꂽ�S���������Ă��邾���Ƃ�������v�̂̋��ʂɁA�Ȃ��r���͂������ȕ]�������������̂��Ɩ₢�����Ă܂��B
�@���ɁA�u������݁v�̉̂��߂����āA�I�F���́u�܌��J�ɕ��v�Ђ���Ίs����Ԃ������Ă��Â��䂭��ށv��єV�́u�s���l�܂�܂ɂȂ��Ȃ�Ή䂤�����ɂ��Ђ܂��肯��v�A�}�͓��Z�P�́u�s����Ƃ͂Ȃ��ɉK�̉Ԃ̂������̒��ɖ��킽���ށv�Ȃǂ̗މ̂Ɣ�r�����Ȃ���B
�@�����āA�Ō�ɁB
���̖̂{�̂��߂�����
�@�r���́u�̖̂{�����v�ɂ́A�@�،o�̓V�䋳�w�I�ȃ��^�t�B�W�b�N���A�Ƃ�킯�A�w���d�~�ρx�́u���v�̎O�ς������͎O���̐����ꗬ���Ă���B�g�{���͂��̂悤�Ɏw�E���A�r���ɂƂ��Ắu���v�́A�u�̂̋��n�Ƃ��Ă̎O�̒i�K�i���邢�͎O�̉̑̂̑��فj�v���Ӗ����邾���ł͂Ȃ��A�u�a�̗̂��j�I�ȕϑJ�̎O�̒i�K�v�A����������A�u�w���t�W�x�̒Z�̗w���w�Í��x�A�w���x�A�w�E��x�Ƃ����悤�Ɂw��ڏW�x�ɂ܂ł������Ă�����j���ے�����O�̒i�K�ł��������v�A�����āA�w���d�~�ρx�Ɂu�����̖@�́A�H���[ℂȂ�v�]�X�Ƃ���u�q���r�̍��_�ɁA�̑̂̌������̊j�S�Ƃ��Ắq�H���r�Ɨ��j�I�������Ƃ��Ắw��ڏW�x�I�Ȃ��́A���邢�͏����w�V�Í��x�I�Ȃ��̂̎p���������`�����Ƃ����Ă��悢�v�Ƙ_���Ă��܂��B
�@���茳�ɂ��钍�ߏ��i���{�ÓT���w�S�W�w�̘_�W�x�����A�L�g�ۍZ���E��j�ŁA�u��E���E���̎O���v�ɕt���ꂽ�����݂Ă݂�ƁA�u�V��Ŏ����̐^�������������B���ׂĂ̑��݂Ɏ��̂͂Ȃ��i����j�A��ł͂��邪���ɂ���ĉ���ɑ��݂��i�����j�A��E���͕s���@�ŁA�����͈�ʓI�ɂ݂Ă͂Ȃ�ʁi�����j�Ɛ����V��Ǝ��̋��@�B�v�Ƃ���܂��B�ȑO�i��12�͂Łj�g�����\�L���g���A�u���v�u�������ہv�u�����^���v�ƂȂ�ł��傤�B�܂��A�����Ɂu�p�[�X�O�́v�ɂ�������Ȃ�A�u��ꎟ���v�u��������v�u������O�����v�ƂȂ�ł��傤���B
�@�g�{���́A�єV�́u�ނ��Ԏ�́v�́u�����ł��l�ɂ킩��ʂ邩�ȁv���A�u���܂��ܓs�Œm�肠���Ă��������ƐΊԂ̂킫���̂Ƃ���ŏo�����āA�����ƌ��t�����킵�����S���̂����Ȃ���ʂꂽ�v�Ƃ����u�����Ɍ��肳�ꂽ�v�S���Ӗ��ƁA�u�l�Ɛl�Ƃ͂��̐��ł͂����S���c���Ȃ���ʂ����̂ł͂Ȃ����v�Ƃ������ՓI�ȈӖ��Ƃ̓�d�̊܂݂ŗ����i�[�ǂ݁j�����Ƃ��A�r���ɂƂ��āA�u���̉̂̐S�́w�~�ρx�̂�����u�]������v�Ɋ������̂Ƃ݂����̂ł͂Ȃ��������v�Ə����Ă��܂����B
�@��E���E���Ƃ����u�a�̗̂��j�I�ȕϑJ�̎O�̒i�K�v�̃A�C�f�A�̂��ƁA�u�q��r�ʂ���q���r�ʂ������q���r���̔ޕ��ɉ̂̋��ʂ��݂����߂悤�Ƃ���r���̉̂̎v�z�v����݂��Ƃ��A�єV�̉̂́A���������A���̐g�̂Ɍ���������u���̕��v�̂悤�ȁA���Ȃ킿�A�u�畆���m�o���Ȃ���A�q���̕��r�Ƃ����A���̐g�̂Ɍ����������B��̑Ώۂ͂Ȃ��B�����������������A���ۂ́u��O�����v�̂Ȃ��ɓ��荞�݁A�L���̕\�Ӎ�p�������Ƃ��ł���B�����Ȑ����Ƃ��Ă̕������ł͂��߂Ȃ̂��B���͐g�̂̒�R�ƂȂ�A��������A�q���̕��r�ɂȂ�Ȃ��ẮA�L���ւƏ��i���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�u��O�����v�́A�u����v���o�R���Ȃ��Ắu��Ԃ̐����v�ł���u��ꎟ���v����荞�ނ��Ƃ͂ł��Ȃ��B�v�i�O�͂ň������O�c�p�����̕��́j�Ƃ�����Ƃ��́A���̌������ꂽ�i�����Ɍ��肳�ꂽ�A���ۂƂ��Ắj����A�������͐��Ȃ���ɗ��������g�̂��Ƃ��A�̖̂{�R�̎p�𗧂����킵�߂Ă����Ƃ������ƂȂ̂ł��傤���B
�@���̂�����̃j���A���X�����݂Ƃ邽�߂ɁA���^��Z���w���d�~�ρx�i��g���Ɂj�����̒�����A�u�]������i���グ�ɂ������j�v�ƑΔ䂳���Ȃ���A�u�]������i���ギ���ɂ����j�v�ɂӂꂽ�ӏ����A�����������Ă����܂��B
�@�r���́u�̖̂{�����v�_���߂���g�{���̋c�_����A���́A���̓�̂��Ƃ��w�тƂ�܂����B
�@�ЂƂ́A���̘a�̂ɂ́u�̖̂��ӎ��v�i���邢�́A�̂̃~�[�e�B���O�E�v���C�X���[���\���j�Ƃ������ׂ��A��҂̈ӎ������[�������̈ł̋�i�����ԁj���͂�܂�Ă��āA���̐��ݓI�ȗ̈���A���݂Ɨ��j���������镁�ՓI�ȑ��i�w�j�ɂ����ĘI�o�����A���̉\�����Ђ��o���A����ɂ����ēǂ݂����Ă����i�[�ǂ݂���j���Ƃ��\�Ȃ̂��Ƃ������ƁB�����ЂƂ́A���̂悤�Ȑ��ݓI�ȁi�S���m�G�}�Ƃ��Ắj�u�̖̂{�����v�����݉����A������������̂��̘̑_�i���m�ɂ́A�̂̕��́A�̂̃A�X�y�N�g���߂���K�͂ƕ��ނɂ��Ă̎��o�I�ȁu�̂̎v�z�v�j�������炷���ʂł���A���̉̂̕��̂��\������̂́A�u���v�Ɓu���v�i���j�Ɓu�S�v�Ɓu�p�v�i�C���[�W�j�̎l���ł��邱�ƁB
�@���͂ł́A�w�����̗w�_�x���A���A�h�l�̎��Ƃ��āA�a�̎j�ƒ�Ə\�̖̂��{�ɂ킯����܂��B�����āA��������̋A�҂��ʂ�������A�����̖��ɂ��܂����Ǘ����Ԃ邱�Ƃɂ��܂��B
�@
�i�P�U���ɑ����j
���v���t�B�[����
�����I���i�Ȃ��͂�E�̂肨�j1950�N�㐶�܂�B���Ɍ��ݏZ�B��N���̂ɏ����ꂽ�a�̂̈Ӗ��������ł���̂͂��������Ƃ��B�ł��A�{���Ɂu�����v�ł��Ă���̂��B�����Ɂu�Ӗ��v�Ȃǂ���̂��B�����������t���g���ĉ�����`�B���邱�Ƃ��̂��̂��s�v�c�Ȍ��ۂ��Ǝv���B
Web�]�_���u�R�[���v15���i2011.12.15�j
���F�ƃN�I���A����19�́@�F�̌��ۊw���邢�͐[�ǂ݂̖��x�����J���O�̂ƃp�[�X�\�́i�}�m�Q�j�i�����I���j
Copyright(c) SOUGETUSYOBOU�@2011 All Rights Reserved.
|
| �\���i�ڎ��j�� |