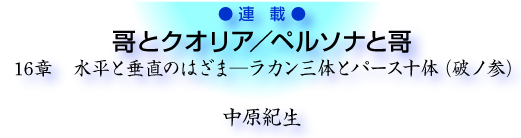|
|
|
Web評論誌「コーラ」 |
|
■創刊の辞 ■本誌の表紙(目次)へ ■本誌のバックナンバー ■読者の頁/ご意見・感想 ■投稿規定 ■関係者のWebサイト ■プライバシーポリシー |
|
<本誌の関連ページ> |
|
■「カルチャー・レヴュー」のバックナンバー ■評論紙「La Vue」の総目次 |
Copyright (c)SOUGETUSYOBOU |
|
|
|
■パラレル・ワールドと並行世界
前章で引いた神田龍身氏と山田哲平氏の議論を、いま一度とりあげて、貫之歌における鏡像、そして言語の位置づけはどのようになっているかという二つの切り口から、あらためて相互に比較してみます。第一の論点は、貫之歌に特徴的なモチーフである「水に映るもの」、すなわち鏡像のとらえ方や意義をめぐる両氏の見解の違いです。
貫之が詠んだ「二つ来ぬ春と思へど影見れば水底にさへ花ぞ散りける」について、神田氏は次のように論じていました。いわく、ここでは、パラレル・ワールドのごとくに、二つないものがもう一つあることの驚きが歌われている。貫之は、屏風絵に描かれた実像(岸辺に散る桜)と鏡像(水面に映じた桜)との間、いいかえると、まこととまことならざるものとの間で戯れているのだと。これに対して山田氏は、この歌には現実世界と、これに並行して存在するもう一つの自立世界が出現していると論じます。そして、貫之は、水面に映る鏡像がたんなる視覚上の写像ではなく、そこから全く別の世界が開いていることを明らかにするため、「水面」に替え、あえて奥行きを感じさせる「水底」という語をもちいたのだと。
共通するのは、貫之歌には二つの世界が詠みこまれているという指摘です。それを神田氏は「パラレル・ワールド」にたとえ、山田氏は「並行世界」と呼んでいるわけです。しかし、それらは言葉としては同義語であっても、その内実はまったく異なっています。
神田氏がいうパラレルな世界とは、かたや「まこと」としての実像であり、かたや「まことならざるもの」としての鏡像でした。リアルなものとフィクショナルなもの(鏡像との語の続柄からいえば、イマジナリーなもの)といってもいいでしょう。ただし、「二つ来ぬ春」の歌は、もともとが屏風絵というフィクションを媒介として詠まれたものなのですから、リアルといいフィクショナル(イマジナリー)といっても、それらは、いわば累乗化された高次元の世界での区分にほかならず、したがって、「まこと」がリアルなのか、それとも逆に、「まことならざるもの」こそがリアルであるのかは判然としないのですが、それはともかく、神田氏によれば、この実像と鏡像をめぐる貫之の詠法は、絵に描かれたもの(雪や光や桜)と絵に欠けているもの(匂いや音や皮膚感覚)、見えるもの(波)と見えないもの(風)、等々へと方法論的に拡張されていきます。
実像と鏡像、あるいはその拡張形としての、見えるものと見えないものとのパラレル・ワールド。さらに、この関係を時空間に拡張して、現に実現した出来事と実現しなかった出来事(もしくは、現にそうであった過去とあり得たかもしれない過去)、ひいては、今・ここにある知覚可能な「物」(res)にかかわるリアルな現実世界と可能世界とのパラレル・ワールド。このような、一つの平面(屏風絵)のうえで、(「雪降れば冬ごもりせる草も木も春に知られぬ花ぞ咲きける」の歌に詠みこまれた景物(雪と花)が、あたかも、一つのテレビのディスプレイで二つの異なったチャンネルが交互に入れ替わるごとく、「あるときは本当の花であり、あるときは雪の花である」といったかたちで表象されるように)、図(figure)と地(ground)が反転して相互に入れ替わる二世界の関係、すなわち「リアルな世界」と「フィクショナル(イマジナリー、ポッシブル)な世界」との関係は、山田氏の言葉を一部借用して、「水平(平面)的な二者交換」の関係と名づけることができるでしょう。
そうだとすれば、他方の「並行世界」における二世界、つまり「現実世界」と「もう一つの自立世界」との関係、もしくは、(「リアル」vs.「フィクショナル」との対比でいえば)、「アクチュアルな世界」と「ヴァーチュアルな世界」との関係は、同様に、「垂直(立体)的な二者並立」の関係と命名することができます。このことを、(「ヴァーチュアル」や「垂直(立体)的」といった語彙の出自も含めて)、貫之と印象派の画家モネとの類似性に説きおよんだ、山田氏自身の文章を引くことで確認しておきたいと思います。
末尾にみられる「伊勢の攻撃」とは、次のような事情をさしています。貫之の「水面の写像を水底の独自の世界として理解しようとする」歌にあっては、この写像に対して一切の行為がなされず、ひたすらそれを観照するに留まっているのに対して、伊勢の歌、たとえば「春ごとに流るる川を花と見て折られぬ水に袖や濡れなむ」にあっては、観照ではなく行為が写像に干渉し、水面に映った桜が本物の花ではないことが暴露される。
ここで、身体的行為(伊勢の攻撃)によって暴露されるのは、水面に映る鏡像(写像)から開かれるもう一つの「水中世界」、すなわち、三次元的な奥行きをもつ「独自の自立的宇宙」や、自立した意識による「自己意識の造形化」が、実は、「水底に喩えられた、実際には水面の写像に過ぎないヴァーチャルな世界」もしくは「単なるヴァーチャル世界」であるということでした。
しかし、いま引いた文章にでてくる「過ぎない」とか「単なる」といった否定的なニュアンスをおびた言葉遣いは、あくまで、今・ここにおける身体的な「行為」(actus)の場としてのアクチュアルな現実世界の側から見た、潜在的な「力」(virtus)が渦巻くヴァーチュアルな世界を形容するものです。リアルな現実世界の側から繰りだされるのは、「それは単なるフィクションに過ぎない」という批判であって、この場合、「それ」と名ざされた対象は端的にその存在を否定されます(二者交換)。これに対して、アクチュアルな世界とヴァーチュアルな世界は、アクチュアルなものがヴァーチュアルなものを模倣・表現・表出・引用するのであれ、後者が前者へと生長するのであれ(人の心が言の葉へと生長するように)、または一方が他方を包摂するのであれ、意味するのであれ、あるいはまったくの無関係であれ、とにかく、(「桜散る木の下風は寒からで空に知られぬ雪ぞ降りける」の歌において、蒼穹によって区画された空と、「桜穹」が区分けする木の下という「錯覚を超えたある種の非現実の空間」とが二重に成立していたように)、重層的に並び立つことができるのです(二者並立)。
■世界を創造する言語
神田氏と山田氏の議論を比較するための第二の論点は、貫之の歌の世界において、言語がどのように位置づけられるかをめぐるものです。
まず、神田氏は、実像(まこと)と鏡像(まことならざるもの)にかかわる作歌法が、絵に描かれたものと絵に欠けているもの、見えるものと見えないもの、等々の関係へと方法論的に拡張・深化され、さらには、存在とそのあらわれ(現象)、心とその外部へのあらわれ(言動)の関係をめぐる認識論的な屈折を経て、やがて貫之は、「ないものを現前させる」言葉のはたらきと、それが発動する根源には「不在」がある(鏡の裏には何もない)という認識に達したと論じていました。
私なりに要約すれば、屏風歌を詠む経験を通じて、貫之は、実像であれ見えるものであれ、もしくは存在であれ心であれ、いずれにせよ「まこと」の側に分類されるものはすべて、「まことならざるもの」すなわち鏡像としての言葉の力によって、「何もない世界」から出現するのだという鏡像(=言語)一元論に到達した。あるいはこれをいいかえて、実はそのような、根源的な「ない」の上にたちあがった世界こそが、そして、そこにおいて「ある」と「ない」とが図地反転する「あるかなきか」のパラレル・ワールドこそが、(その根源的な「ない」の世界をも含めて)言語の世界なのであって、貫之は、知覚可能な「実像」や「見えるもの」はもちろん、現象の背後に想定される「存在」や、言行を通じて外部にあらわれるとされる「心」もまた言葉の産物なのだとするフィクション(=鏡像=言語)一元論に到達したということなのでしょう。
この私なりの要約の後段、それは、(永井均氏が『西田幾多郎』で使った、ウィトゲンシュタイン哲学にかんする表現を借用すれば)、「言葉は体験と独立にそれだけで意味を持ちうる。「体験」もまたそういう言葉にすぎないのだ」とする定家論理学の世界に通じています。そして、俊成を経て定家へといたる、そうした後の世の歌論を包摂しうるものとして、(純粋経験の言語化を可能ならしめる場の創造にかかわる)「広義の」貫之現象学をとらえることができる、というのが私の仮説だったわけです。が、それはいまは措くとして、ここでは、(歌を「いひいだす」ことを課題とする)「狭義の」貫之現象学にかかわる話題、具体的には「フィギュールとしての哥」を構成する声と文字をめぐる神田氏の議論を、いま一度確認しておきます。
神田氏によると、貫之歌における「水面」もしくは(土左日記における)「海」は言語の比喩であり、目に見える「波」と目に見えない「風」は、それぞれ仮名文字と音声言語の比喩になっていました。そして、波のかたちに視覚化されることで初めて風の正体が見極められるように、「仮名という音声の視覚化によって、初めて言語の正体が対象化され得た」のでした。神田氏は、土左日記の仮名表記とその内容についての立ち入った分析をふまえて、貫之の仮名文は「紙上のパロール」もしくは「パロールを装ったエクリチュール」以外の何者でもなかったと論じています。
こうして、神田氏は、貫之にとって「仮名文字こそが偽装の日本語音という最大のフィクションだった」と結論づけます。
前章でも引いたように、その古今集を編纂する段階で、貫之は、「和歌の意味はコンテクストが決定すること、和歌の言葉は無限に引用可能であること」を認識していました。
■歌が歌を生みだすプロセス
以上のことを(前章で引いた神田氏の議論も組みこんで、再び)私なりに敷衍すれば、次のようになるでしょうか。
まず、貫之は、古今集仮名序で、アクチュアルな「(歌が声として出現するプリミティブな)はじまりの歌=やまとうた」とヴァーチュアルな「人の心」との並立関係を提示します。(神田氏にならって、それもまたひとつの「偽装」であったといっていいかもしれません。)これが音声言語やパロールにかかわる垂直的な二者関係だとすると、もう一つの、書記言語やエクリチュールにかかわるそれは、仮名文字・仮名文と漢字・漢文の二者関係となるでしょう。
ここに、貫之の「仮名文字=ピュアな日本語音」という「偽装」(より一般的には、文字は音声を映しだす透明な媒体であるという観念)と、同じく貫之による「本邦初の翻訳論」(「唐土とこの国とは言ことなるものなれど、月の影は同じことなるべければ、人の心も同じことにやあらむ」、すなわち、同じ「人の心」からみれば「漢字・漢文=仮名文字・仮名文」である)とが接合されて、その結果、「はじまりの歌/人の心」という描像が成立します。これは、一見、仮名序と同じ趣旨の思想を表現しているように見えますが、決定的に違うのは、「やまとうたは、人のこころをたねとして、よろづのことのはとぞなれりける」の「ことのは」(=仮名文字)が、透明なスラッシュ記号となって、アクチュアルなものとヴァーチュアルなものとを媒介していることです。
(この間のプロセスを詳述すると、まず、「仮名文字=ピュアな日本語音」の偽装を通じて、つまり仮名文字が「はじまりの歌=やまとうた」の透明な媒体となることで、パロールとエクリチュールがアクチュアルな相において部分的に接合される。しかし、その場合でも、人の「まこと」の心は漢字・漢文でしか表記されず、したがって、ヴァーチュアルな相においては、パロールにかかわる「人の心」とエクリチュールにかかわる「漢字・漢文」とは分離したままにとどまる。次に、「本邦初の翻訳論」によって、漢字・漢文と仮名文字・仮名文は、同じ「人の心」を根拠として、相互に交換可能なものとされる。いいかえれば、アクチュアルな仮名文字・仮名文とヴァーチュアルな漢字・漢文との垂直的な二者並立関係が、リアルなものとフィクショナル(イマジナリー、ポッシブル)なものとの水平的な二者交換関係におきかえられる。そして、「漢字・漢文=仮名文字・仮名文」の等式を介して、漢字・漢文の項が消去され、仮名文字・仮名文が、なかばパロール(音声)、なかばエクリチュール(漢字・漢文)として、「はじまりの歌=やまとうた」と「人の心」を媒介する「透明な」媒体として残される。)
かくして、「(歌が声として出現するプリミティブな)はじまりの歌=やまとうた」を今・ここで反復(引用)する、もしくは忠実に映しだす媒体として、水面や海面といった「質料零の非実体的な皮膜」になぞらえられる言語空間がしつらえられます。そして、その仮名文の世界では、(波と風とが、視覚対象物=波を「図」とし触覚の対象=風を「地」とするか、あるいはその逆の構図をとるかに応じて、図地反転するように)、文字(エクリチュール)と、その文字が指し示す音声(パロール)とが、かの「リアル/フィクショナル(イマジナリー、ポッシブル)」の水平的な二者交換関係のうちに繰りこまれ、さらに、歌を書記化することによって顕在化する「歌なるものに本来的に孕まれていた反復可能性」、つまり、一回性をもった歌の「コンテクスト」や詠歌主体や「歌の心」、ひいては「人の心」の反復(引用)可能性が、仮名文字という透明な媒体の水平的な交換関係(この場合は、「二者」ではなく「多者」ないし「無限」の交換関係)のうちに繰りこまれていきます。
その結果、「はじまりの歌/人の心」の左右両項が消去され、ただ「/」としか表記しようがない、仮名文字(=鏡像=フィクション)一元論が成立するわけです。しかし、これこそが貫之のしかけた最大の偽装なのであって、まず、仮名文字はピュアな日本語音を映しだす透明な媒体などではなく、偽装されたパロール(紙上のパロール)にほかならない。また、「鏡の裏には何もない」のではなくて、鏡(仮名文字・仮名文)の裏には漢字・漢文が潜んでいる。したがって、「はじまりの歌/人の心」の描像こそが、和歌を詠み・読み・編む体験のうちに(本当は)成り立っている関係、すなわち、アクチュアルな「紙上のパロール=仮名文字・仮名文」とヴァーチュアルな「歌の歴史性=漢字・漢文」との二重構造を隠蔽する「イデオロギー」でしかなかったことになります。
このあたりのところは、もはやとうに神田氏の議論を逸脱しています。とりわけ、いましがた論じた「隠蔽」云々は、後にとりあげる山田氏の立場、というより、(神田氏の場合と同様)、山田氏の議論を素材として私が仮説的に立ちあげたいと目論んでいるもう一つの立場からこそ、批判的に繰りだされる評言にほかなりません。(その場合、精確には、「はじまりの歌/人の心」の描像が、「仮名文字・仮名文/漢字・漢文」の二重構造を隠蔽すると同時に、実は漢字・漢文こそがアクチュアルで、仮名文字・仮名文は「単なる」ヴァーチュアルなものに「過ぎない」ことをも隠蔽している、と批判されることになるでしょう。)
神田氏自身は、「偽装」といい「フィクション」といっても、決して否定的な意味合いでそれらの語彙を使っているわけではありません。貫之本人はもちろんのこと、当代、後代の言語生活者(とりわけ、歌人)にあっても、貫之に発する偽装は自明のこととして暗黙の前提とされていたはずですし、たとえそれが初発において偽装されたフィクションであったとしても、永年、その偽装によってひらかれた言語空間のうちに住まいしているうち、(あたかも、かりそめに被った仮面が、もはや剥がしとることができないほど血肉化してしまうように)、それ自体がひとつの現実となりおおせるのは、みやすい道理ではないかと思います。
以下の文章は、そのような事情が日本文学史にもたらした「奇妙な捻れ」について語ったものです。貫之晩年の新撰和歌集という秀歌集に、仮名序ならぬ漢文序が付されていたこと、そして、この署名つきの漢文こそ、「貫之テクスト群の中で、ある意味でもっとも本音を吐露したものになっている」ことをふまえて、神田氏は次のように論じています。
新撰和歌集は、古今集から採録した二八○首を含む三六○首の歌を、春歌と秋歌、夏歌と冬歌、恋歌と雑歌といった「二首一組の連鎖」のかたちに編集したもので、ここには、既にある『古今集』を解体し、それを再構築することで何かを創出せんとする野心的な試みがなされている。しかし、それが何であるかは詳らかにし得ず、この「晩年のソシュールによる「アナグラム」研究のような、歌人貫之の謎の遺作」の実りある解読法が今後登場することを期待する。神田氏は、そう書いています。
私の仮説では、こうした貫之晩年の試みは、神田氏いうところの偽装によって切りひらかれた言語空間の内部において、当の貫之自身が、歌が歌を生みだすプロセスの探究に没頭していたことを示しているのであって、俊成、定家といった後代の歌人たちもまたこれと同様の試みに精励し、やがてそこから定家十体や心敬十体が、さらには、尼ヶ崎彬氏いうところの定家歌における「詠みつつある心」が、そして世阿弥の「花」が出現していきます。(「詠みつつある心」といっても、その実体は「詠まれた心」の一種にほかならず、ここには、貫之がしつらえた言語空間の内部において定家がしくんだもう一つの「偽装」が潜んでいる。そのような問題を提起することもできるでしょうが、しかし、これはまた別の機会にとりあげるべき論点です。)
■二つの世界と二つの言語
さて、次に、貫之歌における言語の位置づけをめぐる山田氏の議論を紹介する運びとなりました。
しかし、山田氏の論考では、貫之の言語観が主題的に論じられてはいません。そこで、以下、先の引用文の末尾にでてきた命題、「貫之の歌とは自己意識の造形化なのである」や、前章で引いた文章中の、「貫之は「水底」という語によってこれ[水面に映った花や月]は実像に従属する、単なる視覚上の写像ではない、そうではなくて、人間の単なる可視世界を越えたところの、純粋意識によって構成される、もうひとつの空間世界である、ということを暗に示したかった」云々の議論にでてくる「純粋意識」という語彙などを手がかりとして、私なりに、貫之における言語をめぐる「山田説」なるものを構成してみようと思います。その前に、これと対をなす「神田説」を、(くどいですが、もう一度)私なりに敷衍しておきます。
屏風歌や鏡像歌の詠歌体験を通じて、まこととまことならざるもの、リアルなものとフィクショナル(イマジナリー、ポッシブル)なものとの水平的な交換関係を発見した貫之は、この二項関係が、実はもう一段下位のフィクションの上に成り立つものであることを自覚していた。そして、その根源的なフィクション(何もないこと)を「地」として、「ある」と「ない」との水平的な交換関係が「図」として立ちあがるのか、あるいは逆に、「ある」と「ない」の交換を「地」として、「何もない」が「図」として透かし彫りにされていくのかはともかく、そのように二重化された交換関係こそが、森羅万象の世界を造形し稼動させる原理であり、かつ、言語というものがもつ根本的な構造にほかならないとの認識に達した。
貫之が、あくまで歌を詠む、あるいは編むという体験を通じて見出していった、この、世界と言語の構造的な相同性は、さらに高次元の交換関係を切り結んでいく。すなわち、言語の構造は世界の実相を反映する写像なのか(世界内存在としての言語)、あるいは逆に、世界のあり方の方が言語をなぞっているのか(世界の造形・稼動原理としての言語)、端的にいえば、「世界が先か言語が先か」をめぐる二つの立場が、対等の権利をもって成り立つことになる。この二者択一を前にして、貫之自身は、万象は言語の産物であり、「歌の心」(クオリアとしての)や「人の心」(ペルソナとしての)もまた、言語がかたちづくるコンテクストのうちに立ちあがってくるとする言語一元論の立場を採った。精確には、そのような「世界を創造する言語」へとつながる言語観を偽装し、かつ、自らが偽装した領域内において「歌が歌を生みだす(アナグラム的な)プロセス」を探究した。
これが、私なりの整理による神田説です。それでは、これと対になる立場、つまり「言語は世界の写像である」もしくは「言語は世界内存在である」とするのが山田説の立場なのかというと、それは違います。「世界が先か言語が先か」という二者択一的な問いが、山田説の立場では、そもそも成り立たないからです。詳説すると、次のようになります。
問題は「言語が先か世界が先か」ではない。「アクチュアル/ヴァーチュアル」の垂直的な二者並立関係において、「言語/世界」なのか「世界/言語」なのかということこそが、問われなければならない。(「言語/世界」や「世界/言語」がいかなる事態を表現しているかは、この際、措く。肝心なのは、いずれの描像にあっても、両者の「垂直的な」並立関係が表現されていることである。)
しかるに、神田説が、「言語が先で、世界は言語によって産出される」と主張するとき、言語の側がアクチュアルかつリアルである(言語の方が現実存在で、世界はその言語によって仮構される)とするか、逆に、世界がアクチュアルかつリアルである(世界の方が現実存在なのだが、それは、言語によってそのようなものとして制作される)とするか、そのいずれの場合にあっても、一方の側のヴァーチュアル性は否定され、リアルなものに対するフィクショナルなものの側へと繰りこまれてしまう。つまり、言語と世界の関係が、「アクチュアル/ヴァーチュアル」の垂直的な並立関係から「リアル/フィクショナル(イマジナリー、ポッシブル)」の水平的な交換関係におきかえられ、その結果、両者は同じ平面上で図地反転の関係を切り結ぶことになる。それは、「世界が先で、言語は世界の内部にあって世界を映しだす鏡像である」と主張したところで同断である。
それでは、山田説では、(貫之において)言語はどのようなものとして認識されるのか。このことを考えるためには、いったん、第一の論点にたちかえる必要があります。山田氏によると、貫之歌にあらわれた鏡像は、現実世界のたんなる写像ではなく、そこから現実世界と並行して存在するもう一つの自立世界が開いているのでした。つまり、貫之の鏡像歌において、世界は二つあったわけです。一つは、「中国」「仏教」という普遍的文明や世界宗教によってかたちづくられた(アクチュアルかつリアルな)「現実世界」であり、いま一つは、その現実世界に投げこまれ、そこにおいて「たゆたいながら、はかなげに映し出されるもう一つの」ローカルな世界、そして、「現実世界」からの自立や離反をめざす(ヴァーチュアルかつリアルな)「自立世界」です。
この二つの世界に対応して、言語もまた二つあります。いうまでもなく、貫之の場合、現実世界に対応するのが漢字・漢文であり、もう一つの自立世界に対応するのが仮名文字・仮名文です。そうだとすると、先の、言語と世界の関係をめぐる問いへの回答は、それが貫之における言語の位置づけをめぐるものであるかぎり、「言語/世界」でも「世界/言語」でもなくて、「ユニヴァーサルな世界(=中国)/ローカルな世界(=日本)」という垂直的な並列関係と、「ユニヴァーサルな言語(=漢字・漢文)/ローカルな言語(=仮名文字・仮名文)」というもう一つの垂直的な並行関係とが、それこそ並行的に成り立たなければならないというものになるはずです。ローカルな世界がユニヴァーサルな世界からの自立をはたすためには、ユニヴァーサルな言語に拮抗しうるローカルな言語を確立しなければならないということです。
山田氏が、「貫之の歌とは自己意識の造形化なのである」というときの「自己意識の造形化」とは、いま述べた「ユニヴァーサルな言語に拮抗しうるローカルな言語の確立」を通じて達成されるもののことであり、また、「人間の単なる可視世界を越えたところの、純粋意識によって構成される、もうひとつの空間世界」とは、同様に「ユニヴァーサルな世界からの自立をはたしたローカルな世界」(より精確には、ローカルな言語の確立を通じて、ユニヴァーサルな世界からの自立をはたそうとする不断の試みのうちに、ヴァーチュアルな次元において出現するローカルな世界)のことにほかなりません。それでは、山田氏がいう「意識」や「純粋意識」とは何かというと、それこそ、「(歌が声として出現するプリミティブな)はじまりの歌=やまとうた」のうちに表現されたヴァーチュアルな「人の心」(より精確には、そのようなものとして貫之によって偽装された「人の心」)のことです。
■意識をつくる言語、意識がつくる言語
これらをふまえて、以下、貫之の言語観をめぐる山田説なるものを、(紹介できなかった山田氏の議論を暗黙のうちにふまえつつ、いや、もはやとうに山田氏の議論を逸脱して)、私なりに敷衍してみます。
意識は、言語によってかたちづくられる。そうした力をもつ言語(意識をつくる言語)を「ユニヴァーサルな言語」と呼ぶならば、この言語が造形する意識によっては掬いとることができない残余の意識(たとえば、神仏由来の光が達しない、あやなき闇にうごめく「あるかなきか」の音や匂いや気配)、もしくは、そのような言語がかたちづくるコンテクストのうちにはすまいすることができない体験(たとえば、クオリアとしての「歌の心」やペルソナとしての「人の心」)が、ユニヴァーサルな言語に拮抗するものとしてつくりだす言語(意識がつくる言語)のことを「ローカルな言語」と名づけることができる。
一つの言語には一つの世界が対応する。ユニヴァーサルな言語には「ユニヴァーサルな世界」が、ローカルな言語には「ローカルな世界」がそれぞれ対応する。ところで、ユニヴァーサルな世界の住人にとっては、言語と世界(と意識)の関係はあまりに身近で自明なものであり、「世界が先か言語が先か」(あるいは、「意識が先か世界が先か」「言語が先か意識が先か」)といった問いは意味をなさない。そのような問いを意味あるものとして受けとめる(受けとめざるを得ない)のは、ローカルな世界の住人である。(「ユニヴァーサルな言語」や「ユニヴァーサルな世界」は、ここでの文脈でいえば、それぞれ「漢字・漢文」であり「中国」である。しかし、これを一般化して、それぞれ「母語としての○○語」、「○○語が母語として使用される世界」におきかえて考えてもよい。)
ローカルな世界の住人の立場から、言語と世界(と意識)の関係を、「アクチュアル/ヴァーチュアル」の垂直的な並立関係にそくして構成すると、まず最初に成立するのが、「ユニヴァーサルな言語/ユニヴァーサルな世界(意識)」である。この図式は、二つのことを同時に表現している。ローカルな世界の住人にとって、ユニヴァーサルな世界(とそこに住む人間の意識)の実質は(ともに)ヴァーチュアルでうかがいしれないものであり、ただその言語(文字や音声)だけがアクチュアルで知覚可能なものであるということと、ユニヴァーサルな言語を永年にわたって使用しつづけることで、やがて、そのような言語生活者のヴァーチュアルな心の次元に、ユニヴァーサルな世界の住人のそれと同等の意識が造形されていくということである。
意識は、言語によってかたちづくられる。このことを、ユニヴァーサルな世界の住人は自覚できないが、ローカルな世界の住人は痛切に自覚する(自覚せざるを得ない)。なぜなら、そこには残余の意識と、ユニヴァーサルな言語をもってしては表現できない体験がうごめいているからである。いや、そのような残余の意識や体験が、(たとえば、「からごころ」に対する「やまとごころ」のように)、ヴァーチュアルかつフィクショナル(イマジナリー、ポッシブル)なものとして仮構(制作)される、というのが精確かもしれない。しかし、たとえそうだとしても、残余の意識・体験は、いずれ、ヴァーチュアルな次元におけるリアルなものとフィクショナルなものとの図地反転を通じて、ヴァーチュアルかつリアルなものとしての地位を獲得し、やがて、あくまでヴァーチュアルな次元においてではあれ、ユニヴァーサルな言語に拮抗するローカルな言語をつくりだす。こうして、第二の図式、「ユニヴァーサルな言語/ローカルな言語(意識)」が成り立つ。
(ちなみに、ここで、ヴァーチュアルかつフィクショナルな「やまとごころ」が、ヴァーチュアルな次元での「リアル/フィクショナル」の水平的交換関係を介することなく、したがってユニヴァーサルな言語との拮抗関係を経ずして、直接的に「やまとうた」のうちに自らの表現を見出すのだ、といった議論を展開することも可能である。たとえば、「はじまりの歌(=やまとうた)/人の心(=やまとごころ)」という描像を「偽装」することで。
ところが、その場合、「やまとうた」は「やまとごころ」から受け継いだフィクショナルなものという身分を保持したままアクチュアルな次元に位置づけられることになり、すると今度は、アクチュアルな次元における「リアル/フィクショナル」の図地転換を通じて、アクチュアルかつリアルなものとしての地位を獲得するに至る。その結果、「ローカルな言語/ローカルな世界(意識)」という図式が得られることになる。
しかし、これは、かの第一の図式「ユニヴァーサルな言語/ユニヴァーサルな世界(意識)」と同型であって、その意味するところは、ローカルな意識(ユニヴァーサルな言語が造形した意識によっては掬いとられない残余の意識)が、自らに表現を与えるローカルな言語をつくりだし、そして、その言語こそがユニヴァーサルな言語(意識をつくる言語)であると主張しているに等しい。もちろん、そのような主張をするのは勝手だが、少なくともこれは貫之の歌論とは似て非なるものである。)
ローカルな言語は、「ローカルな世界(意識)」を造形する。すなわち、「ローカルな世界(意識)/ローカルな言語」。(この議論の最初からでてくる「ローカルな世界の住人」は、実はこの段階にいたってはじめて登場するものだった。)しかし、この図式は、たちまちのうちに、「ユニヴァーサルな世界(意識)/ローカルな世界(意識)」という第三の図式におきかえられてしまう。なぜなら、ユニヴァーサルな言語(意識をつくる言語)の方がローカルな言語(意識がつくる言語)よりも強力だからであり、したがって、ユニヴァーサルな世界とローカルな世界は、あたかも帝国と植民地の関係のように、一つの政治権力が統治する平面上で対等の関係をむすぶことはできないからである。
かくして、「ユニヴァーサルな世界/ローカルな世界」と「ユニヴァーサルな言語/ローカルな言語」が並行的に成り立つ貫之の言語観が確立された。
■水平と垂直の交わるところ
山田説のハイライトは、「残余の意識・体験」が「ローカルな言語」をつくりだすプロセスにあります。それこそ、(永井均氏が『西田幾多郎』で使った、西田哲学にかんする表現を借用すれば)、「体験は言葉と独立にそれだけで意味を持ちうる。言葉の意味もまたそういう体験にすぎないのだ」とする貫之現象学の核心をつくものです。また、西田=貫之現象学の二つの根本問題のうちの一つ、クオリア(心)が詞へ生長していくプロセスとはどのようなものか、に直接かかわるものでもあります。
(ちなみに、西田=貫之現象学のもう一つの根本問題、そもそもなぜ詞が他のペルソナに伝わるのかについては、「意識をつくる言語」もしくは「世界を創造する言語」の実質を探究することによって、最終的に解明されるのではないかと私は考えています。たとえば、(永井氏の言い方を真似て)、直接に結合していない私と他人が相理解できるのは、他人が言語を語りうる存在だからであり、同じことを逆の側からいえば、そういう他人が存在していることが、そもそも言語というものを可能ならしめているからだ、といったようなかたちで。しかし、これもまた別の機会にとりあげるべき論点です。)
先に引いた文章で、山田氏は、晩年のモネが庭の柳を映しだす水面に睡蓮を浮かべたことを取りあげて、それこそが、鏡像にすぎない柳を「実像の単なる水面への反映をこえた、独自の自立的宇宙を持つ三次元の存在へと変貌させてしまうからくり」であったと論じていました。これを読んで、私は、(かつて第5章で引き、第12章でその「完全版」を抜き書きした)尼ヶ崎彬氏の議論を想起しました。
いわく、我々は時に応じて様々の思いを抱く。思いにただ浸るのでなく、これを撫でさすり、分かち合い、伝えたいと考えるとき、この思いに一つの客観的な形を与えねばならない。しかし、思いは概念のごとく操作しうるものではない。「思いが我々を捉えているのであって、我々が思いを捉えているわけではない。」それゆえ、捉え所のない思いに言葉の網を不用意にかければ、その「元の肌ざわり」を失ってしまう。悲しい、恋しいという語彙は、ただ感情を大まかに分類する記号、レッテルでしかないからだ。では、どうすればよいか。「いにしえの歌人たちは、我を物思わせる場の中に一片の象徴的な〈物〉を投げこむ時、無形の水蒸気が一片の塵を核として雪に結晶するように、思いが凝固して一つの形を得ることを発見したのである。〈物〉という鏡に映すことによって、〈思い〉は生きたままその姿を定着させる。読者は〈物〉のイメージを喚び起こしつつ、そこに映された〈思い〉をも喚び起こすのである。」
これは、「人のこころをたねとして、よろづのことのはとぞなれりける」の「やまとうた」を、「ことわざしげき」世の中にある人が、「心におもふことを見るものきくものにつけていひいだせるなり」の和歌へとつなぐ技法、すなわち「物への付託法」について述べられたものです。
尼ヶ崎氏がいう「一片の象徴的な〈物〉」もしくは「〈物〉という鏡」と、山田氏が着目する「モネの睡蓮」(山田氏はそれを、水面を水底に変える「密教の呪術器具」にたとえています)との関係。このことをつきつめて考えることで、(狭義の)貫之現象学の核心をなす、歌を「いひいだす」ことの実質、すなわち「心」が「詞」へ生長していくプロセスを解き明かすための糸口をつかむことができるのではないかと私は考えているのですが、そのためには、すべてを垂直の並立関係のうちに繰りいれる山田説と、すべてを水平の交換関係のうちに繰りこむ神田説とが、(いや、もう固有名を離れて、歌論における言語の位置づけをめぐるA説とB説とが)、奇跡的に遭遇する中間領域、すなわち「あわい」(betweenness-encounter)に咲く華の色と香りと気配を、心ゆくまで味わい尽くすことが肝要なのでしょう。
■しるし・あわい・よそ、再び
最後に一言、述べておかねばならないことがあります。
先の山田説(あらためA説)の論述のなかで、「リアル/フィクショナル(イマジナリー、ポッシブル)」の水平軸と「アクチュアル/ヴァーチュアル」の垂直軸とを、あたかもデカルト座標のX軸、Y軸のように直交させ、「アクチュアルかつリアル」から「ヴァーチュアルかつフィクショナル」までの四つの象限(世界)を導きだしました。これは、「哥の伝導体」を取りあげた第7章で採用したのと同じ操作ですが、ここでは、それをさらに方法論的に拡張させて、一つの水平軸に無数の垂直軸が引けること、その逆も可であること、したがって水平・垂直の両軸があい交わる交点=原点は無数に設定できることをつけ加えています。
私の直感が告げるところでは、「リアル/フィクショナル(イマジナリー、ポッシブル)」の水平軸はパブリック(公共的)な事柄にかかわり、「アクチュアル/ヴァーチュアル」の垂直軸はプライベート(私秘的)な事象にかかわります。前者は「他者の体験」(外からみられた体験)にかかわり、後者は「私の体験」(内からみられた体験)にかかわるといってもいいでしょう。さらに、すべての垂直軸を繰りこんだ水平軸は、世界を創造し、その世界のなかに意識をつくりだす「強い」言語ゲーム(定家論理学)に、逆に、すべての水平軸を繰りいれた垂直軸は、意識によって言語がつくられ、その言語が世界そのものである「強い」私的言語(貫之現象学)に、それぞれかかわるといっておきたいと思います。
そして、そのように出自の異なる二つの軸を交差させることで、私は、(以前、第3章の序奏=助走的考察のなかでふれたように)、最終的には、貫之現象学と定家論理学が相互包摂の関係(もう一つの、より高次の垂直的な並立関係)にあることを示唆したいと考えているのです。
(一つ補足しておくと、このあたりの議論は、木村敏氏による、公共的・客観的・三人称的な実在に関する「リアリティ」と、私的・主観的・一人称的な「アクチュアリティ」との区分に近接していきます。ちなみに、木村氏は『関係としての自己』で、「クオリアは、一定の機構を備えてさえいればだれにでも観測可能なリアリティではなく、個人と世界のあいだにそのつど新たに成立するアクチュアリティである」と書いていました。
もう一点、補足します。山田氏は、漢字・漢文の世界と仮名文字・仮名文の世界の違いを、対句を典型とする「コントラスト」と縁語に代表される「アナロジー」の対比によって説明しています。この指摘はとても重要だと思うのですが、本稿では主題的にとりあげることができませんでした。私は、水平軸=コントラスト、垂直軸=アナロジーといった対応づけが可能なのではないかと考えています。)
以上に述べたことは、いずれよくよく吟味して、精密な論証をあたえなければならない(あるいは、最終的に棄却しなければならない)仮説的な論点ですが、ここでは話を先に進めることにして、坂部恵著『かたり──物語の文法』からの話題を引きます。
坂部氏は、同書第二章「〈かたり〉の位相」で、「言語行為に関する、さらにはまた言語行為をもその一環として含む〈ふるまい〉一般に関する二つの図式」を提示しています。詳細は省きますが、その「二つの図式」とは、言語行為に関する「はなし──かたり──うた」と、ふるまい一般に関する「ふるまい──ふり──まい」というもので、そのいずれの場合にあっても、左から右へと進むほど、「(日常)目前の利害・効用に直結するいわば水平の時間・空間から、記憶や想像力や歴史の垂直の時間・空間の奥行のうちへと参入する」と、坂部氏は書いています。
坂部氏の議論は、いまは、これ以上深追いしません。というより、深追いすることができません。引用文につづく各章で展開される坂部氏の議論は、あまりに濃厚芳醇で、通りすがりの一瞥を許さないものなのですから。(坂部氏がいう「水平」「垂直」と、私の直感が告げるそれらとは、おそらく微妙に異なるものなのだと思いますが、そのこともいまは追求しません。)ここでは、文中に「〈かたり〉や〈ふり〉、さらには〈うた〉や〈まい〉の場がひらかれるのは、こうした、日常効用の水平の時空と、記憶や想像力の垂直の時空がたちまじるはざまにおいてにほかならない」とあったことに、とりわけ、そこで使用された「はざま」という語に注目しておきたいと思います。
「はざま」とは、かの「しるし・あわい・よそ」の「あわい」のことです。パース三体(パースの現象学的カテゴリー)のうちの「第三次性=媒介・中間性」に相当し、パース記号論にいう「解釈項」にあたるもののことです。(さらに、貫之=丸山(圭三郎)=ラカン三体でいえば、水面(海面)と水底(海底)によって区画された水中世界(海)、すなわち「人のこころ=深層のパトス=リマジネール」に該当するもののことです。)
私の仮説では、そのような「はざま」=「あわい」を原点として、垂直軸に属する「しるしA」(「著[しる]きあらわれ」としてのしるし)と、水平軸に属する「しるしB」(知る、領[し]るに通じるしるし)とが無数に立ちあがり、そして、貫之=丸山=ラカン三体にかかわるA系列のしるし群からは「よそA」(鏡の裏の世界)が、また、定家=心敬=パース十体にかかわるB系列のしるし群からは「よそB」(絶対的他者)が、それぞれ出現することになります。
★プロフィール★
中原紀生(なかはら・のりお)1950年代生まれ。兵庫県在住。千年も昔に書かれた和歌の意味が理解できるのはすごいことだ。でも、本当に「理解」できているのか。そこに「意味」などあるのか。そもそも言葉を使って何かを伝達することそのものが不思議な現象だと思う。
Web評論誌「コーラ」12号(2010.12.15)
<哥とクオリア>第16章 水平と垂直のはざま──ラカン三体とパース十体(破ノ参)(中原紀生)
Copyright(c) SOUGETUSYOBOU 2010 All Rights Reserved.
|
| 表紙(目次)へ |