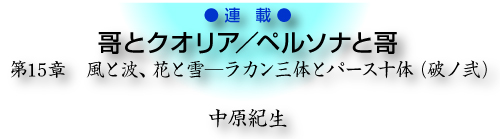|
|
|
Web評論誌「コーラ」 |
|
■創刊の辞 ■本誌の表紙(目次)へ ■本誌のバックナンバー ■読者の頁/ご意見・感想 ■投稿規定 ■関係者のWebサイト ■プライバシーポリシー |
|
<本誌の関連ページ> |
|
■「カルチャー・レヴュー」のバックナンバー ■評論紙「La Vue」の総目次 |
Copyright (c)SOUGETUSYOBOU |
|
|
|
■水面に映る像、貫之屏風歌の虚構論
神田龍身著『紀貫之──あるかなきかの世にこそありけれ』は、貫之文学の本質を、屏風歌歌人としての言葉の営みのうちに見てとります。いわく、貫之は屏風歌歌人としてスタートし、絵に相対することから、絵を詠むという特殊事情から、一つの普遍的な表現方法を確立した。またいわく、屏風歌を詠む経験が、貫之の専門歌人としての名声を高めたのはもとより、屏風歌という固有性をも超えて、ある種の普遍的認識を彼にもたらした。
それでは、屏風歌の経験がもたらした普遍的方法、そして普遍的認識とはどのようなものだったか。以下、神田氏の議論の一端を、若干の編集をほどこしたうえで、紹介します。
まず、貫之における屏風歌の方法論。
絵を絵として詠むのではなく、絵を媒介に世界を出現させること、いいかえると、「まこと」でない絵をもとに、「まこと」以上の世界を出現させるのが屏風歌の方法論で、そのためには、つまり、絵に対して想像力を発動させるには、ある種の媒体が画中にある方が便利である。貫之の場合、そのような絵を賦活する画中装置が、水面(水に映る像)であった。貫之は、絵に時空間を付与すべく、画中の水面を磁場にして様々な言語的実験を試みた。
たとえば、水面を「風」と「波」の共振運動の相としてとらえるのは貫之の得意の手法であり、それらの歌では、「波」と「風」の因果論的な換喩関係をふまえつつ、「波」に着目することで、目には見えない「風」の所在を確認している。有名歌「桜花散りぬる風のなごりには水なき空に波ぞ立ちける」は、このような屏風歌歌人としての練成の賜物である。「ここには風が桜花を吹き散らしてしまった後の空白への凝視がある。散花の残映を「名残」かつ「なごり(余波)」とし、しかもそれを「水なき空」に立つ「波」と喝破した。」
あるいは、「二つ来ぬ春と思へど影見れば水底にさへ花ぞ散りける」では、パラレル・ワールドのごとくに、二つないものがもう一つあることの驚きがうたわれている。鏡像(まことならざるもの=水面に映じた桜)と実像(まこと=岸辺の桜)の間で戯れている。「歌は現実に触発された感動に根拠をおくのでなく、絵というフィクションを媒介に、主として画中世界の虚構の住人に成り代わって詠まれた世界である。しかもそれは言葉だけで織りなされており、「まこと」以上の世界を出現させる当のものが言葉以外にない以上、この虚構論は言葉の問題にまるごと還元される。」
また、絵に対して歌を詠むとなると、絵に欠けているもの(匂いや音や皮膚感覚、また、時間の幅)を特化して対象化しないわけにはいかなくなる。そして、それら諸現象の相互関係を問うたり、共感覚的世界を組織したりすることになる。たとえば、雪と桜、雪と月光、白梅と雪、白梅と白菊、降雪と落花、等々の混合をテーマとする歌は、雪も光も桜も霜も、同じ顔料で描くほかない絵だからこそ発想された。これらは「見立て」とか「喩」と評され、古今集時代の典型的な表現方法といわれるものである。
貫之はやがて、「文字による屏風歌」(特定の絵に貼りつけられた歌ではなく、歌集や家集という紙上に織りあげられた、絵を伴わない「文字の産物」としての歌)の編集作業を経験することで、和歌の意味はコンテクストが決定すること、詠歌主体の変更も可能であること、そして和歌の言葉は無限に引用可能であることを認識する。「フィクションの発見、歌の意味を決定するコンテクストへの認識、それがまさに歌を根拠づける散文なるものへの領域へと貫之を赴かしめたのである。もちろん、このことは遥かに遡れば、歌が書記されるようになったことにその淵源がある。」「和歌が書記されたことで、歌なるものに本来的に孕まれていた反復可能性という問題が顕在化したということである。」
次に、貫之における屏風歌の認識論。
画中の水面を媒体とした歌(鏡像歌)を詠む経験が、フィクションや言語の発見をもたらし、時空間を出現させ、物語空間をもたらした。こうした、屏風歌で培った詠法がそのまま貫之の認識の枠組みになっていく。(屏風歌でなくとも、「二つなきものと思ふを水底に山の端ならで出づる月影」など鏡像を詠んだ歌は数多くあり、屏風歌のそれと弁別することはできない。)
たとえば、視覚・聴覚・嗅覚・触覚等を弁別的に機能させたり交錯させたりするという世界認識の方法。一例をあげると、「今日、海荒らげにて、磯に雪降り、波の花咲けり。ある人のよめる、波とのみ一つに聞けど色見れば雪と花とにまがひけるかな」。ここでは、同じ波なのに、聴覚がとらえた現象(波音)と視覚がとらえた現象(花と雪に見立てられた波)が別物であることの不思議が歌われている。「波は波として客観的にあるのでなく、どう現象するかが存在の問題だとされている。」
あるいは、「いかで人名づけそめけむ降る雪は花とのみこそ散りまがひけれ」という歌にあらわれた認識。「降雪は散花と紛うのに、なぜ「雪」「花」というごとくに弁別的に名付けられているのかと訝しむ。なるほどどのように現象したかで、存在なるものは認定される。花も雪も視覚的に同一ならば、そもそも「花」「雪」という差異もないはずである。現象とは何か、名付けとは何か、という根源的問いかけがここにある。現象なるものが客観的にあるのでなく、どう現象するかが存在の問題だとされており、この認識は鋭い。」
こうした認識は、人の「心」と「言(事)」、人そのものとその外部への(とりわけ言語を媒体とする)あらわれの関係におよぶ。貫之は、画中の「女」の立場で歌を詠み、「男」に成り代わって応ずるという屏風歌の虚構の方法を通じて、自己認識についての普遍的方法を開拓した。「おそらく自己が自己から一歩も抜け出せない状況にあっては、自己について語ることはできないのではあるまいか。自分のことは自分がもっともよく知っているということではない。自身が今何を思い、何を感じているのか、それは外化された自己を介在させることで初めて顕在化するのではなかろうか。ナルシシズムにしても、自身の内側から自然発生したものではなく、水鏡に映じた自身の像を見ることで初めて発現し得たではないか。」
世界は言語的に分節されている。そして、言語世界(鏡像)がいかに多様であろうとも、一皮剥けば、指示対象のない「虚無」である。「鏡の裏には何もないように、言葉や記号そして想像力なりが「虚無」「不在」を根拠に出現するという認識を彼はもっていた。言葉の世界の背後には、常にその不気味な深淵が横たわっていた。」この認識は、海という文学空間のうえに描かれた土左日記の、「不在」「虚無」「死」を根底にすえた世界につながっていく。
貫之晩年のテクストに秀歌集『新撰和歌集』があり、仮名序ならぬ漢文序がついている。「花実相兼ネタルヲノミ抽ク」(言葉の綾に巧みで、かつ中身のしっかりした歌だけを選んだ)云々。貫之の仮名文に、貫之なる主体を生のまま表出し得たものは一つもなかった。「そしてなんと逆説的なことか、最後に到達し得たのが肉声を現前させるものとしての漢文であった。もちろんこの漢文序にみる詠嘆調にしても、これまた「本音」というもう一つのフィクションには違いない。」
その辞世において、(「結ぶ手の雫に濁る山の井の飽かでも人に別れぬるかな」や「袖ひちて結びし水の凍れるを春立つ今日の風や溶くらむ」という自身の名歌を反復引用して)、「手に結ぶ水に宿れる月影のあるかなきかの世にこそありけれ」と詠んだごとく、貫之にあっては、人生そのものがフィクションであった。
■風と波、音声と文字のメタファー
……貫之屏風歌の詠法の起点に画中の水面(スクリーン)があって、その水面(絵に描かれたものと絵に欠けているものとの‘あわい’)から、数々の鏡像(見えない風と見える波とに二重化された‘しるし’)が立ち現われ、それらは、たとえば「雪=花」といった言葉のうえでしかありえぬ像(パンタスマ)を結び、相互に「反復引用」を織り重ね、やがては、「水なき空」(=虚[そら])という虚構の時空間、すなわち言語と散文(物語)の世界(‘よそ’)を出現させることになる。
それらの鏡像群は、しかし、一皮剥けば「虚無」にすぎず、したがって、すべての存在(まこと)は、現象(あらわれ)とその名づけ(言葉)の問題に還元される。「まことならざるもの」の戯れの果てに出現する‘よそ’は、もはや‘しるし’や‘あわい’との位相差(存在論的差異)はもちえず、(あたかも、「波の花」や「波の雪」と「波の音」を弁別することができないように)、ただ、同一平面(海面=界面)に映じた「あるかなきかの」フィクションのうちに折りたたまれていく……。
神田氏の議論を、(前章でとりあげた「しるし」「あわい」「よそ」の語をつかって)そのようにくくることができるとして、ここで決定的に重要なことは、貫之屏風歌をめぐる虚構論のすべてがまるごと言葉の問題に還元されるということ、つまり、そもそもの初めに立ち現われる鏡像が、そして水面そのものが、実は、すでにして言葉の境域にほかならないということです。
「大気と水とのあわい」が織りなす風と波の関係は、土左日記でも、「大気と海水との境域」において継続的に反復されます。二月五日の、「ちはやぶる神の心を荒[あ]るる海に鏡を入れてかつ見つるかな」をめぐって、神田氏は次のように読み解きます。
また、一月二十日のくだり。帰国に際して催された送別の宴で、阿倍仲麻呂が、「我が国にかかる歌をなむ神代より神もよむたび、今は上中下[かみなかしも]の人もかうやうに別れを惜しみ喜びもあり、悲しびもある時にはよむ」といって、「青海原ふりさけ見れば春日なる三笠の山に出でし月かも」の歌を詠んだ。「かの国人、聞き知るまじく思ほえたれども、言の心を、男文字[おとこもじ]に様を書き出だして、ここの言葉伝へたる人にいひ知らせければ、心をや聞き得たりけむ、いと思ひのほかになむめでける。唐土とこの国とは言ことなるものなれど、月の影は同じことなるべければ、人の心も同じことにやあらむ。」以下は、この挿話にみる「本邦初の翻訳論」をうけての神田氏の議論。
そして最後に、土左日記が、「舞台を海というガランとした空間にとったことの意味」が述べられます。
いまひとつ、「紙と筆とのあわい」をめぐる話題を引きます。仲麻呂歌の「翻訳」にあたって、言葉がいったん書記化・視覚化されたこと、すなわち、「音声から音声へと渡りあるくことはできずに、「紙」を媒介する必要があった」ことを踏まえて、神田氏は、次のように述べ、そして、「仮名文字こそが偽装の日本語音という最大のフィクションだった」と結論づけていくのです。
■貫之、そのもう一つの
神田氏が描きだす貫之像、あるいは貫之歌の世界は、(神田氏自身の言葉をもちいるならば)、どこか「書き割り」を思わせるところがあります。
この印象は、いうまでもなく、屏風歌歌人としてその文学的営為のスタートをきった貫之の出自に由来するもの、というより、そのような切り口で貫之を論じきった神田氏の筆の力がもたらしたもので、その極めつきは、たとえば、土左日記における文学空間としての海をめぐって、「鏡のごとき海面に宇宙が映じていようとも、その海面の裏には何もなく、すべては薄い面上での記号の戯れにすぎなかった」と記されているあたりに見てとることができると思います。そこでは、豊穣の海の底知れない深みが、(そして、宇宙すなわち天、いいかえればカミの領域へとつづく果てしのない空の高みが)、「大気と海水との境域」のうちに、つまり、何もない、何も描かれていない屏風としての海面のうちに織りたたまれ、その流動や波模様の連綿たる変容相を通じて、「質料零の非実体的な記号現象」が立ち現われているのでした。
しかし、だからといって、書き割り的な貫之歌の世界が、平板で奥行きのない軽薄なものだといいたいのではありません。それどころか、表層におけるシニフィアンの戯れ、などといったどこか浮薄感の漂う語彙ではすくいあげることのできない、透明な哀しみ、純粋経験としての哀しみのようなものが、書き割り的世界を透かしてほの見えてくるような気さえしています。そして、そのように、徹底して表層における言葉の変容過程に身をゆだねてみることこそが、古今和歌集に編まれた千百の歌を(退屈の蟲をほしいままにさせることなく)読みすすめるための、戦略的といってもいい態度なのではないかとさえ思うのです。
しかし、それは、少なくとも私が追い求めてきた貫之現象学の世界とは、その相貌を決定的に異にしています。たとえば、かの「影見れば波の底なるひさかたの空漕ぎわたるわれぞわびしき」に見られる「地=欲動/海=パトス/空=ロゴス」の空間把握や、「千代経たる松にはあれど古の声の寒さはかはらざりけり」に歌われた「いにしへ」(純粋過去)の世界。もちろん、それらはいずれも、すぎた深読みがもたらすイリュージョンでしかないのかもしれません。あるいは、仮名文字という偽装の日本語音によって覆い隠されていた男文字(漢字)、すなわち、事=言(シニフィアン)の差異を超えて普遍的になりたっている心=観念(シニフィエ)の恣意的な露呈でしかない、と神田氏ならいうかもしれません。
ところが、そのような言葉と心の関係のとらえ方は、これもまた、私がこれまで、いくどにもわたって解読を試みてきた仮名序歌論の世界とは、すなわち、「物(よろづ)/心(人のこころ)/詞(ことのは)」(森羅万象が、心という場所を媒介もしくは媒質として、言語のかたちをもって立ち現われる)の重層的な構造とは、まるでかけはなれているのです。(たとえ、そのような仮名序のとらえ方が、貫之以後の俊成に由来するものであったとしても、その俊成歌論が立ちあがる場それ自体をしつらえたのが実は貫之であった、というのが私の見立てです。)
まわりくどい言い方はほどほどにして、以下、神田氏のそれとは異なる貫之像を具体的に提示することにします。精確には、貫之歌をめぐるもうひとつの解釈の可能性を、山田哲平氏の論考「日本、そのもう一つの──貫之の象徴的オリエンテイション」(岩野卓司・若森栄樹編『語りのポリティクス──言語/越境/同一性をめぐる8つの試論』所収)を引くことで、示してみたいと思います。
■花と雪、木の下というローカルな特殊空間
まず、山田氏が、「対句といっても過言でないこの二首が同時に取り上げられるのはおそらくこの拙論が始めてである」と自負する、その二つの歌(内容と形式の両面にわたって、「非日本的に抽象的」な重層的対称性をもった二首)を掲げます。
桜散る木[こ]の下風は寒からで空に知られぬ雪ぞ降りける
雪降れば冬ごもりせる草も木も春に知られぬ花ぞ咲きける
山田氏によると、後者、「雪が花となる」歌のなかには、春の知っている、まことの花が隠されています。目の前の草や木に降りつもる雪、それを歌人は、春の花と錯覚する、あるいは見立てる(屏風絵の場合であれば、同じ顔料で描かれるしかない雪を花と見まがう)わけですが、このふたつの事象、すなわち雪と花とは、同じ空間において、それも異なる季節に生起するのだから、それらが同時に重なって見えることはありません。「この歌を読んでいるものが表象するのは、あるときは本当の花であり、あるときは雪の花である。作者の心は、雪なのか花なのかどちらなのかと揺れている。」
これに対して、前者、「花が雪となる」歌には、空から降る、まことの雪が隠されています。ところが歌人は、ここでは、「あえて、空に知られていないもう一つの雪が、同時に目の前にあると主張する」と、山田氏はいうのです。
山田氏が、二者並立、二者交換というときの「二者」とは、いうまでもなく花と雪、歌に詠まれた景物のことですが、もうひとつ、より重要だと思うのは、花と雪とが現象する空間にかかわる二相の方です。「桜散る」の歌の場合、雪が降る空と桜の花が散る木の下という、ふたつの異なる空間が同じひとつの歌の世界において重層的に並立しているのに対して、「雪降れば」の歌の世界にあっては、雪が降りつもる場所と花が咲く場所とが同じ空間を共有していて、だから交互に交換して現象しているわけです。
山田氏は、このうち、雪と花の二者をめぐる違い(「雪∧花」もしくは「雪=花」の並立と、「雪∨花」もしくは「雪⇔花」の交換)のよってきたるところを、継続運動を意味する「散る・降る」と、静止状態を内包している「咲く」という、それぞれの歌を特徴づける動詞の性格の違いに求めます。すなわち、前者の歌において、「桜散る」や「雪ぞ降りける」の主語は複数でなければならず、したがって、歌人あるいは鑑賞者は、そこに、一片の雪や花びらの運動の顛末を見るのではなく、「それぞれのものの開始も終了も存在せず、落下物という物に目を凝らすことなく、繰り返される落下運動という揺らぎを主に見ている」。こうして、木の下に散る雪=花と、空に降る雪のふたつの現象が「同時にイメージできる」ことになるわけです。
他方、後者の歌にあっては、「花ぞ咲きける」の主語は単複いずれでもかまわず、「咲く」とは、「すでに咲いている状態を指すか、つぼみから花へと状態を変化させてしまったことに気づいたことを指すのかのいずれか」なのであって、歌人・鑑賞者は、そこに、反復運動をではなく、静止画像のごとき対象物を見ている。意識は雪か花の一方に集中していて、二者を同時に思い浮かべる余裕をもたないというわけです。
花と雪を同時にイメージできるか(並立)、それとも交互に現象するしかないか(交換)。それは、これらふたつの景物を詠みこんだ歌のなかに、それぞれのイメージ(現象)を容れる重層的な空間がしつらえられているかどうかにかかっています。「雪降れば」の歌について見てみると、ここには時間はあるが、季節感それ自体は空間を作らない、と山田氏は指摘します。
ここで山田氏が、「錯覚を超えたある種の非現実の空間が、一瞬ではあるが出現する」といっているのは、「鶯の花ふみしだく木の下はいたく雪降る春べなりけり」の歌のことです。
鶯が花をふみしだく木の下の「透明な箱」、そこには、「春という空間の内部に春の支配を外れた特殊な空間がかりそめに存在する」。この、かりそめの空間が、蒼穹という「大きな傘」に対する、「桜穹」ともいうべき「小さな傘」によって「はっきりと区分けされ」るとき、かの「桜散る」の歌の重層的な空間が成立する。山田氏の精密(もしくは、錯綜)をきわめる叙述を、おおはばに単純化してしまうと、そのようにいうことができるでしょう。ここで注目すべきは、「桜散る」の歌にあらわれた「木の下」という「ローカルな規定」、もしくは「特殊な空間である木の下という場所」です。
以下は、私の勝手な議論ですが、貫之が和歌の世界にきりひらいた「木の下」という空間は、たとえば、時間の先後関係や事象間の因果関係が狂い、あるいは、部分と全体との関係が日常の論理を逸脱し、さらには、「花=雪」といった視覚では表象できない言語的イメージが立ち現われ、言葉と事象がアナグラム状にからまりながら相互に反復引用をくりかえす、夢や無意識の論理、感覚や神話の論理によって統治されたローカルな場所、つまり、「フィギュールとしての哥」が生成する場所にほかなりません。
そして、この「木の下」は、神田氏が、屏風歌歌人としての練成の賜物であると評した、「桜花散りぬる風のなごりには水なき空に波ぞ立ちける」の歌にいう「水なき空」との対比を通じて、水によって充たされた空間へ、すなわち、質料零の皮膜にすぎない水面を映し、同時に、「影見れば波の底なるひさかたの空漕ぎわたるわれぞわびしき」の歌にいう「ひさかたの空」をも映しだす水底とによって区画された、もうひとつの領域へと推移していきます。
(先の引用文中に、「花は咲くことによって、その統治する空間を確保する。しかしむしろ散ることによって自らの支配空間を領有する花もある。桜の花である。」とありました。ここにでてくる「統治」「支配」は、「しるし」の二つの用法のうちの「知る=領る」に通じています。山田氏は、このことを踏まえ、「空に知られぬ」の歌をめぐるひとつの解釈を示します。それは、空=中国、木の下=日本の「それぞれの統治下では、それぞれ別の雪が降る。並行的並存がこの歌の主題であるといえる。ここから貫之の中国に対するオリエンテイションが透けて見えてくる。」というものです。
この議論は、実は、山田氏の論考の全体におよぶ枢要な論点にかかわるものなのですが、ここでは、あえて深追いしません。ちなみに、中国の影は、神田氏の議論のなかでも色濃く見え隠れしていました。このこともまた、いずれ、貫之におけるフィギュールとしての哥をめぐる議論にさしかかった際、必要があれば、あらためて振り返ることにして、ここでは深追いしません。)
■水底に映る像、貫之現象学の並行世界論
いまひとつ、山田氏の議論を引きます。パラレル・ワールドのごとくに、二つないものがもう一つあることの驚きがうたわれている、と神田氏が評した貫之の屏風歌と、屏風歌のそれと弁別することができない作例としてあげられた鏡像歌、そして、このふたつの歌をめぐる山田氏の議論を、以下にまるごと抜き書きします。
二つ来ぬ春と思へど影見れば水底にさへ花ぞ散りける
二つなきものと思ふを水底に山の端ならで出づる月影
山田氏が、「現実とは別の、奥行きを持ったもう一つの自立世界」や、「人間の単なる可視世界を越えたところの、純粋意識によって構成される、もうひとつの空間世界」と規定している世界、すなわち、水面(しるし)と水底(よそ)によって区画された空間(あわい)、それは、桜の花が散る「木の下」というローカルな領域を経て、やがて、土左日記の「海」(生と死の‘あわい’)へとつながっていきます。そして、同時に、雪が降る「空」、月の光が洩れくる「天」、といったぐあいに、水面を界面として、水底へ向かうそれとは別の垂直方向のベクトルをもったもうひとつの空間規定をうみだします。
貫之が最期に詠んだ、「手に結ぶ水に宿れる月影のあるかなきかの世にこそありけれ」の歌にいう「月影」は、「天」という超越的な領域(純粋言語が宿る空間といってもいい)にすまいするものの鏡像なのであって、その「天」は、水底(海底)という、水面(海面)とは異なるもうひとつの鏡の、その背後にある世界(「天」に対して「地」、あるいは黄泉の国)とパラレルな関係をとりむすんでいくことでしょう。
★プロフィール★
中原紀生(なかはら・のりお)1950年代生まれ。兵庫県在住。千年も昔に書かれた和歌の意味が理解できるのはすごいことだ。でも、本当に「理解」できているのか。そこに「意味」などあるのか。そもそも言葉を使って何かを伝達することそのものが不思議な現象だと思う。
Web評論誌「コーラ」11号(2010.08.15)
<哥とクオリア>第15章 風と波、花と雪─ラカン三体とパース十体(破ノ弐)(中原紀生)
Copyright(c) SOUGETUSYOBOU 2010 All Rights Reserved.
|
| 表紙(目次)へ |