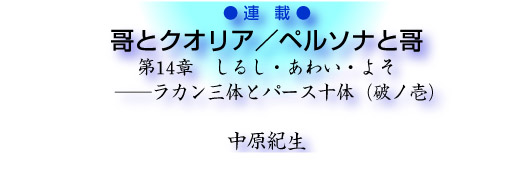|
|
|
Web評論誌「コーラ」 |
|
■創刊の辞 ■本誌の表紙(目次)へ ■本誌のバックナンバー ■読者の頁/ご意見・感想 ■投稿規定 ■関係者のWebサイト ■プライバシーポリシー |
|
<本誌の関連ページ> |
|
■「カルチャー・レヴュー」のバックナンバー ■評論紙「La Vue」の総目次 |
Copyright (c)SOUGETUSYOBOU |
|
|
|
■二つの純粋経験が重ね描かれる場所
第一歌集『海やまのあひだ』に収められた「葛の花 踏みしだかれて、色あたらし。この山道を行きし人あり」について、折口信夫(釈迢空)は『自歌自註』で次のように書いています。
ここで折口信夫がいっているのは、この短歌において、踏みしだかれた葛の花は、ついさっき山道を通って行った人があることを示す痕跡(記号)になっているのではない、ということです。
いや、現実の世界では、そのような因果関係や時間的先後関係(もしくは、意味関係や記号関係)がなりたっているのかもしれないけれども、しかし、少なくともこの作品の世界で、そうした「論理的な感覚」が歌われているわけではない。山道を歩いていると、踏みにじられた葛の花の「其色の紫の、新しい感覚」(知覚体験)と、「ついさつき、此山道を通つて行つた人があるのだ、といふ考へ」(想起体験)とが、二つながら、一方が他方の原因になっている(土の上に落ちた葛の花が、たったいまこの山道を通って行った人によって偶然踏みにじられ、その結果、目に鮮やかな紫の色を土や岩などににじませている)といった因果関係の推理にもとづくのではなくて、なぜだか、これといったわけもなく、同時に「心に来た」。そうして、その二つの純粋経験それ自体を、「紫の葛の花が道に踏まれて、色を土や岩などににじましてゐる処」において重ね描いただけなのだ、と。
この歌のキモは、「色あたらし」の語にあります。葛の花が道に踏まれて土や岩ににじませた、その生まれたての瑞々しい紫の色の「新しい感覚」、色彩語の体系のうちに捕捉される以前の、「其色の紫」(クオリア)をめぐる純粋な知覚体験が、まるごとこの一語に託されていて、その上に、過去の出来事、それも自分が直接体験したわけではない、他者(異なるペルソナ)に生じた出来事の純粋な想起体験が重ね描かれているわけです。それはまた、言葉以前の、いいかえれば、意味するものと意味されるものの二項からなる客観的・日常的な記号関係のうちに整序される以前の、根源的な記号の立ち現われを「しるし」づける詞として、読点と句点の二つの切れ目によって判然と区画された場所のうちにしるされているのです。
その「しるし」が立ち現われるとき、同時に、そこにひとつの「あわい」が出現しています。折口信夫がいう「色あたらしの判然たる切れ目」、私はそれを、短歌作品における上句と下句の切れ目であると同時に、事物と事物のあいだ(たとえば、「海」と「やま」の「あひだ」)であり、さらには、それを通じてはじめて事物と事物が分節される原初の切れ目のことでもある、と拡大解釈しているのですが、いずれにせよ、その「あわい=切れ目」を通じて、因果関係や時間的先後関係その他の「論理の感覚」にからめとられる以前の、いってみれば「よそ」の世界における出来事が、直接的に立ちあがっているわけです。
しるし、あわい、よそ。私は、この三つ組の和語でもって、かのパースの三つの現象学的カテゴリー(パース三体)をいいあらわすことができるのではいかと考えています。しるし=第一次性(質的可能性または潜在性)、よそ=第二次性(個体的事実)、あわい=第三次性(媒介あるいは中間性)といったぐあいに。あるいはまた、丸山圭三郎氏が『言葉と無意識』で図式化した「欲動/深層のパトス/表層のロゴス」もしくは「カオス/ノモス化されないコスモス/ノモス化されたコスモス」の三層構造(ラカン三体)、さらには、古今集仮名序に記された「よろづ/人のこころ/ことのは」もしくは「物/心/詞」の三層構造(貫之三体)をいいあらわす和語。しかし、これらの語彙は、いずれも私のオリジナルではなくて、それぞれしかるべき出自をもっています。
■著きあらわれとしてのしるし
しるし(徴・標)は、しるし(著し)に通う。今日のことばでいえば「いちじるし」く、「ありありと見え、聞え、また感じ取られて、他とまがう余地が無い」(『岩波古語辞典』)もの。また、しるしは、しる(知る、領[し]る)に通う。「物の状態や性質を、すみずみまで自分の思うままにする意。占有・統治・支配・世話の意から転じて、意識の中ですみずみまで認識し自由にする意」(同)。領られ、占められ、標められるものとそれならざるものとの境をしるし、またしめすもの。
坂部恵著『仮面の解釈学』に収録された論考「しるし」は、これら二つの古語の用法を手がかりに、しるしが立ち現われてくる「境位(さかい)」の実相をときあかしています。
まず、第一の用法における「しるし」(著し)は、「あらわれ(現象)としてのしるし」といいかえられ、「しるしとは、一つの現象[あらわれ]が、他のことなった現象[あらわれ]をしるしづけるところに成立する二重化された現象[あらわれ]にほかならない」と定義されます。ここで重要なのは、「しるしをしるしとして成り立たしめるものは、しるしづける現象[あらわれ]をしるしづけられる現象[あらわれ]から分けへだてるその差異[ことなり]である」こと、したがって、しるしが立ち現われてくるのは、「差異[ことなり]の相をもった世界」、すなわち、「くり返し二項対立の差異[ことなり]の重ね合わせからなる差異化[ことなり]のシステムの総体によって分節された世界においてにほかならない」ということです。
差異(ことなり)が事成るとき、つまり、世界が分節化され、同時に世界が創造されるとき、そこに、もうひとつの「言成り」(坂部氏がそんな言葉を使っているわけではありません)の可能性が成就しているはずです。二重化された現象(あらわれ)としての「しるし」にあって、著(しる)き現象(あらわれ)であるしるしによってしるされるもう一つの現象(あらわれ)が、「もはやない」か「いまだない」か「ここにない」かはともかく、それが不在のもの(否定性をおびたもの、たとえば死)としてあるとき、そこに、「分節化された音声」と「ある特定の概念」の差異(ことなり)のシステムとしての言語の世界が立ちあがる契機がはらまれています。しかし、「言成り」が成就するいきさつを究めるためには、「しるし」のもうひとつの相を見極めておかねばなりません。それは、言語を使用する主体(ペルソナ)の「自覚」、もしくは(言語の世界への)「目覚め」にかかわってきます。
■主体の死において立ち現われるしるし
第二の用法における「しるし」については、たとえば、「葛城の高間の草野早しりて標[シメ]刺さましを今そくやしき」の万葉歌にいう「標」の字(不在のひとまたは神による占有のしるしとして、領有をしるしづけ聖別するものという意を帯びている)に着目して、次のように説明されます。
ここでいわれる「原初の渾一の相をもった世界」とは、たとえば、(坂部氏が「しるし」のなかで使っている言葉でいえば)「母なる大地」のことでしょう。母胎との一体化のうちにある、というより、いまだなにものでもないものから、くり返し、「一個の他者」として「わたし」が切り出されてくる。それをするのは「しるし」だが、同時に、そうした「主体の死」を通じてこそ「しるし」は出現する。そして、それはやがて、(同様に、坂部氏の言葉でいえば)「絶対他者としての父」もしくは「不在の(死んだ)父」、すなわち「のり」や「おきて」や「象徴体系」との葛藤と分裂を通じて、「わが身とおなじ織り糸でおりなされた一つの織り物にほかならぬ世界」のなかに、あるいは「わたしをうつす一つの鏡としての世界」のなかに、(すなわち、言語の世界のなかに)、いわば、母なるものとの想像的な一体化から分離されたわたしの「墓標」として、「わたしの鏡像」(対象化されたイメージ、うつし身)をうつしだす。
先走りすぎました。坂部氏は、先に引用した文章につづけて、「わたしがわたしとして、立ちあらわれ自覚されるのは、とりわけ、他者[ひと]、他所者[よそもの]としての欠如の相においてにほかならない」ことを、フロイトが「快感原則の彼岸」でとりあげた「fort−da(いない−いた)の遊び」のうちに確認していきます。
坂部恵の、それ自体ひとつの論理詩ともいうべき、精妙なロジックと華麗なレトリックをもって綴られた、酒精度の高い芳醇な散文に酔いしれて、つい、長々と引用を重ねてしまいました。いそぎ、「あわい」と「よそ」の出自を明かさなければなりません。
(蛇足を加えます。坂部氏によって読み解かれた「しるし」の二つの相のうち、「著きあらわれ」としてのしるしは哥の心(クオリア)に、「主体の不在あるいは死」において出現するしるしは哥を詠出する主体(ペルソナ)に、それぞれかかわっていて、また、西田=貫之現象学の二つの問題、すなわち、クオリア(心)が詞へ生長していくプロセスとはどのようなものか、また、そもそもなぜ詞が他のペルソナに伝わるのか、にたいする回答にもなりえているのではないか。私は、そのように考えています。)
■さかい、あわい、あいだ、界面
まず、「あわい」は、いま引いた文章のなかで、ことなりの相をもった世界、あるいは、生死往来の境位・境界・境域(さかい)として言及されていたもの、すなわち、しるしが立ち現われてくる場所のことにほかなりません。(しるしによってしるされるものである「むらさき野」とは、目に見えるかたちになった「あわい」なのかもしれません。)以下、『モデルニテ・バロック』に収められた講演録「生と死のあわい」から、坂部氏の議論を、適宜、ぬきだしてみます。
あわいという言葉は、語り・語らい、はかり・はからい、というような造語法と同じで「あう」という動詞そのものを名詞化するところでできた言葉。西田哲学の根本概念である「場所」と同様、ダイナミックな動(詞)的な意味、述語的な意味を強く含んだ言葉で、英訳すると“Betweenness-Encounter”になる。この場所「あわい」を基盤にして、死せるものと生けるもの、死者と生者は、極端な場合、その位置を入れ替える。生と死が相互浸透の関係にあること、あるいは生死の可逆性という極限の場合を考えるべきで、すくなくとも過去にはひとびとはそれを考えていた。(ポール・クローデルは、「西洋の劇では何かが起こり、能では何かがやってくる」といったが、この場合やってくるのは何かといえば、死者であり、死霊であり、折口信夫のいう「まれびと」である。)
あわいにはまた、人と人のあわいという用法があり、時間的な意味もある。日本の古い使い方では、あわいは男女のペアの場合に主として使われ、また、「潮時」というような別の日本語で表現できる質的な時間をあらわす。この、人と人のあわいは、(人と物、物と物とのあわい、Umwelt とか milleu といわれるものについても同じだが)、生と死のあわいに包み込まれる関係にある。すなわち、生と死のあわいは、他のすべてのこの世のあわいを包む超越論的場所であり、西田幾多郎のいう「超越的述語面」である。人と人との相互変身、可逆性、あるいは一体化の願望がきわまるとき、死の影もまたひときわその濃さを増す。(世にあるすべてのものが、無の場所の影となり、象徴的表現となるというのは西田の発想の基軸にある考え方であった。)
脈絡のない抜粋ですが、それでも、「しるし」と「あわい」が、(著きあらわれとしてのしるし、もしくは我−汝のことなりを立ち現わしめるしるしと、そうした二重化されたあらわれやことなりが、そこにおいて立ち現われ、相互に交換可能なものとして出会う場所としてのあわいとが)、微妙なニュアンスの違いをもちながら、相互に浸透しあう関係にあることが見てとれるように思います。
ところで、木村敏著『偶然性の精神病理』に「タイミングと自己」という論考があって、そこで木村氏は、「日本人は、時間という現象を「タイム」という客観化可能な(リアルな)「もの」として理解する以外に、タイムがアクチュアルに「タイムする」、その一瞬の微妙な動きを「タイミング」として捉える特別な感覚に古来長けていたのではないか」と書き、その「タイミング」を、「意識と無意識、個人の人称性と個人を超えた匿名性、時間と自己、時間と生命などがたがいに触れ合う界面的な次元」に位置づけています。木村氏の「自他の界面現象としてのタイミング」は、坂部氏がいう「潮時」としての「あわい」とほぼぴったり重なり合う概念ではないかと思います。いや、そもそも木村氏のいう「界面」、あるいは「あいだ」の概念が、「あわい」に通じているというべきでしょう。以下に引くのは、木村氏の論考「〈あいだ〉と言葉」(『関係としての自己』)から、「あいだ」をパースの「解釈項」に関係づけて論じた箇所です。
私は、「あわい=あいだ」は、むしろ、パースの三項関係の記号論そのものを基礎づける現象学的カテゴリーのうちの第三次性に関連づけて考えるべきではないかと思います。そのように考えてこそ、木村氏がいう「位相差」、いいかえれば「しるし」と「あわい」の「存在論的差異」は保持されるからです。
ちなみに、鷲田清一氏は、『偶然性の精神病理』の文庫解説「〈偶然性〉の思考」で、木村敏の思考を「差異の思考、〈あわい〉の思考」と名づけています。「ところで、〈偶然性〉は contingence/contingency という。con-tangere、つまり「ともに‐ふれる」ということである。そうするとこれは、偶然性と触れ(接触であり触覚である)の関係という問題、そして「ふれる」とは触れるであり振れる(気がふれるというときの、そう「こころの病」としての「ふれ」)でもあることになる。木村氏は、〈いのち〉というものを、生命一般が個々の生存へと個体化されてゆく過程で、それとそれでないものとの「界面」として現象すると考えようとしている。ちょっとこみ入った言い方をすれば、そういう界面の生成そのものを、自己表象として自己を隔てる意識の出来事と、自己触発として自己にふれてゆくより根源的な身体の出来事との緊張関係のなかで問いただそうとしている。本書の議論の向こうには、〈偶然性〉をめぐるそんな問題が広がってもいる。」
ここで、鷲田氏がいう「いのち」が(著きあらわれとしての)「しるし」に相当し、そして、「界面」と呼ばれるものこそ、「しるし」が立ち現われる生死往来の「さかい」(境位・境界・境域)、つまり、「それ」と「それでない」ものとが出会いふれあう「あわい」にほかなりません。
■よそ─ふたつの世界の接点
次に、「よそ」。定家の歌、たとえば、「年もへぬいのるちきりはゝつせ山おのへのかねのよそのゆふくれ」に見られる「よそ」(他所、余所、外)という歌語をめぐって、淺沼圭司氏は、「「よそ」についてあるいは定家再読」(『〈よそ〉の美学』第一テクスト)で、次のように読み解きます。
以上をまとめて、「「よそ」は、たしかに「いま、ここ」にはないにしても、「いま、ここ」とまったく無縁の時空にあるのではなく、あるいは「いま、ここ」から絶対的な距離によってへだてられているのではなく、むしろそれとなんらかの──というより、きわめてちかしい──関係をたもちながらあると考えるべき」なのであって、「よそのゆふくれ」の歌では、「「よそ」は「いま、ここ」の瞬間においてあらわれる、過去において持続した時間にほかならなかった」。つまり、定家の「よそ」は、「「現前」と「不在」が戯れ、「有」と「無」が重なり合う場」のことであった。
淺沼氏は、つづけて、「よそ」とイメージの関係、とりわけ、「パンタスマ」としての映画のイメージとの密接な関係に言及します。プラトンは『ソピステス』で、「模倣」によって制作されるもの(イメージ)を「エイコーン eikon 」(実物の大きさ、プロポーションあるいは色彩などを忠実に再現したイメージ)と「パンタスマphantasma」(実物の性質を恣意的に変化させたイメージ)に二分し、そのなかで、「エイコーン」は、実物(具体的存在)との類似関係をとおして、実物の存在的な根拠であるイデア的なものとかかわりをもちうるのにたいして、「ファンタスマ」は、実物との類似関係さえも欠き、当然イデア的なものといかなる関係ももちえないとして、全面的にその意義を否定した。淺沼氏は、そう紹介したうえで、エイコーンを絵画のイメージに、ファンタスマを映画のイメージにおきかえます。
日常的な意識(知覚)にとってはただの白い平面にすぎないスクリーンに、映写がはじまったとたん「不在の対象をそのものとして見る(感じる)」意識、この、知覚や想像や概念作用のいずれともことなる意識のことを「パンタスマ的意識」と名づけ、さらに、ジャン・コクトーの映画『オルフェ』で、オルフェ(オルペウス)が鏡を通りぬけ、その背後のべつの世界(冥界、死の世界)にはいっていったことにふれた後で、淺沼氏は次のように総括します。
生と死、現前と不在、意識と非意識、昼と夜、等々の「ふたつの世界の接点」もしくは「はざま」としての「よそ」は、二重化されたあらわれとしての「しるし」を立ち現わしめる生死往来の境としての「あわい」に通じていきます。また、「よそ」とは、そのようにして立ち現われたパンタスマ、すなわち「しるし」そのものであるといってもいいでしょう。(ただし、淺沼氏が、「よそ」の世界を、「すべてのものが差異を失って共存するカオス的な世界」と規定している点に、「ことなりの相をもった世界」において立ち現われる「しるし」との決定的な違いがあります。これは、「意識のはるか下方に秘匿されている無−意識」のさらに背後にある世界(無世界、非意識の闇)に通じている「よそ」、というより、そのような世界が(パンタスマ的)意識のうちに引き寄せられてあらわれた「よそ」と、著きあらわれとしての「しるし」との違いにほかなりません。)
また、「よそ」には、第二の相におけるしるし、すなわち、わたしを一個の他者(ひと)としてしるしづけるもの、あるいは、人と人の「あわい」に通じていく側面があります。
淺沼氏の議論には、いずれ、定家を主題的に論じる際、立ちかえります。(とりわけ、その「パンタスマ=映画イメージ」論は、「しるし」から「うつし身」へと移行していく坂部氏の議論ともあいまって、定家から世阿弥へ、哥の様(体)から老体・女体・軍体(男体)の世阿弥三体へといたる回路をときあかす鍵になっていくことでしょう。)また、「しるし」「あわい」「よそ」の三者の関係、たとえば、それらを「よそ/あわい(=ふたつの世界の接点としての‘よそ’)/しるし(=パンタスマとしてあらわれた‘よそ’)」と表示し、「よろづ/人のこころ/ことのは」の貫之三体と関連づけて考えることができるかどうか、といった議論もしばらくおいて、ここでは、「よそ」が、鏡や水面やスクリーンと響き合っていることに注目しておきたい思います。というのも、鏡、水面、そして屏風(平安朝のスクリーン)は、貫之にとって、哥が詠出される特権的な場所であったからです。
(11号に続く)
★プロフィール★
中原紀生(なかはら・のりお)1950年代生まれ。兵庫県在住。千年も昔に書かれた和歌の意味が理解できるのはすごいことだ。でも、本当に「理解」できているのか。そこに「意味」などあるのか。そもそも言葉を使って何かを伝達することそのものが不思議な現象だと思う。
Web評論誌「コーラ」10号(2010.04.15)
<哥とクオリア>第14章 しるし・あわい・よそ──ラカン三体とパース十体(破ノ壱)(中原紀生)
Copyright(c) SOUGETUSYOBOU 2010 All Rights Reserved.
|
| 表紙(目次)へ |