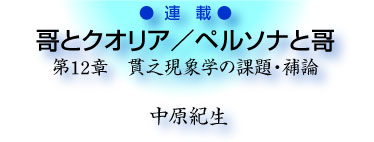|
|
|
Web評論誌「コーラ」 |
|
■創刊の辞 ■本誌の表紙(目次)へ ■本誌のバックナンバー ■読者の頁/ご意見・感想 ■投稿規定 ■関係者のWebサイト ■プライバシーポリシー |
|
<本誌の関連ページ> |
|
■「カルチャー・レヴュー」のバックナンバー ■評論紙「La Vue」の総目次 |
Copyright (c)SOUGETUSYOBOU |
|
|
|
■法界/詩的世界/仮名界
当面の作業、すなわち、歌体論をめぐる議論に一応の決着をつけておくための下準備として、ここで、「広義の」貫之現象学の三層構造をめぐり、いま少し立ち入って考えてみます。そうすることで、「物の伝導体/身の伝導体/詞の伝導体」と「哥の伝導体」との関係をあきらかにし、さらには、たとえば「パース伝導体/ラカン伝導体/ベンヤミン伝導体」とでも表記できる、物と身心と言語の関係をめぐるもっと大きな構図の可能性を素描することができるのではないかと思うからです。
まず、俊成・定家の「新しい花」について考えるために、『花鳥の使』の尼ヶ崎氏の議論を、(比較のために)貫之に関する箇所とあわせ、連続して引くことから始めます。最初の文章は、「心と物──紀貫之」の章の「結び」から。これは以前、第5章で引用した文章の「完全版」です。
次に、「世界を生む言葉」の章の前半、「歌の道の自覚──藤原竣成」の最終節「俊成歌論の位置」から。
最後に、同じく「世界を生む言葉」の章の後半、「物狂への道──藤原定家」の「結び」から。
一言、注記をほどこしておきます。
最後の文章のなかで、尼ヶ崎氏が「仮名界」と命名するときの「仮名」とは、(いうまでもなく、仮名文字の「仮名(かな)」とは違って)、俊成の「古来風躰抄」に「歌の深き道も、空仮中の三体に似たるによりて通はして記し申なり」とある、その「三体」をふまえたもの、すなわち天台教学における「三諦」、空諦(一切は空=無である)、仮諦(一切は仮=現象である)、中諦(真理は空と仮の中間にある)のうちの「仮」をさしています。「すべてのものには本来実体がないのに、この世では仮に存在するものとされていること。また、そのような事物に与えられた名称」(『大辞林』)と定義されているように、「仮名(けみょう)」とは、端的に、「現象」あるいは「現象」に与えられた「名」のことである、(さらには、我々の生活世界にあって、あらゆる現象は、すでにある「名」を割り振られたかたちで立ち現われる)、といってもいいでしょう。
ちなみに、尼ヶ崎氏の法界・仮名界・詩的世界の「三界」の説を、私の語彙に対応させると、それぞれ、法界=物の伝導体、仮名界=記号の伝導体、詩的世界=身の伝導体(「狭義の」貫之現象学の場合)もしくは詞の伝導体(「広義の」貫之現象学、俊成系譜学および定家論理学の場合)とおきかえることができます。
初出の「記号の伝導体」にいう「記号」とは、尼ヶ崎氏が、「例えば「悲しい」とか「恋しい」という記号を並べただけでは、人の胸を掴んで動揺させることはできない。これらの語彙は、ただ感情の種類を大まかに分類するだけのレッテルでしかないからである。」というときの「記号」や「レッテル」を、また、ベンヤミンが「言語一般および人間の言語について」の第十六段落で、「ブルジョア的見解によれば、語は事柄にたいして偶然的な関係にあって、何らかの習慣によって設定された、事物の(ないしはその認識の)記号と見なされてしまう。言語はけっしてたんなる記号など与えはしないのだ。」(細見和之訳)と書いている、その(言語を道具とみなすブルジョア的見解における)「記号」をさしています。そうした意味での「記号の伝導体」や、すでに定義を与えておいた「詞の伝導体」、はては「神語の伝導体」などといった想定上のものまでをも含む、言語現象一般もしくは言語存在一般が成り立つ場所のことを、この際、「言語の伝導体」と総称することにします。
■貫之現象学─始まりの哥の反復
さて、以上、長々と引いてきた尼ヶ崎氏の議論を、私なりにまとめていえば、次のようになるでしょうか。
まず、貫之。「思いが我々を捉えているのであって、我々が思いを捉えているわけではない」という、非人称的な独我論的世界の相貌を帯びた現象世界にあって、「我を物思わせる場」すなわち「身=心」としての「身(み)」のはたらきのうちに内在しつつ、そこに「一片の象徴的な〈物〉を投げ込む」こと、すなわち「心におもふこと」を「見るものきくもの」に付託することでもって、「思い」を「生きたまま」定着(凝固)させる、結晶としての「詞」を創出すること。
いいかえると、(かなり錯綜した物言いになりますが)、ヴァーチュアルな「法界=物の伝導体」から一瞬発出される「閃光」(哥というギフト、もしくは、始まりの哥)を掬いとり、これを、(「世の中にある人」すなわち「仮名界=記号の伝導体」にある人の「思い」をもとりこんで)、リアルかつイマジナリー(フィクショナル)な「詩的世界=身の伝導体」のはたらきを介して、とりわけ、リアルな「物」にイマジナリー(フィクショナル)な「心」(思い、感じ)を付託し、クオリアを象るフィギュールとしての言葉(声、文字)を精錬しつつ、これを「いひいだす」(ヴァーチュアルな次元からアクチュアルな次元へと、ランガージュの力をもって現勢化する)ことで、俗なる「仮名界=記号の伝導体」のうちにアクチュアルな「詞の伝導体」を造形し、(時に、アンソロジーという名のパランプセストのかたちで)、歌を贈りとどけること(始まりの哥、すなわち、一回性をもった出来事を何度でも初めて「今、ここ」で反復すること)。これが、「狭義の」貫之現象学の課題です。
(以下に述べることは、いずれ、貫之における「フィギュールとしての哥」を考察する際の論点になりうるはずなのだが、いましがた再規定したばかりの「狭義の」貫之現象学の課題のなかで、「イマジナリー(フィクショナル)」とわざわざ「フィクショナル」を併記したことにも関連するところがあるので、当面の議論をしばし中断して、少し長くなるがふれておく。
神田龍身著『紀貫之──あるかなきかの世にこそありけれ』は、「貫之テクストにみるフィクションの問題」を多角的に論じた、示唆と刺激に満ちた書物である。そこには、あらためて取りあげ賞味または吟味すべき多くの論点(たとえば貫之歌論の政治性、たとえば男同士の贈答歌に孕まれたホモ・ソーシャル的連帯、たとえば貫之の「伊勢物語」体験、たとえば土佐日記における文学空間としての海、たとえば二度言及される三島由紀夫、等々)がちりばめられているのだが、ここでは、「エクリチュールの問題を徹底して問いつづけてきた貫之文学」と「フィクション」との関係をめぐる議論、同時に、仮名序の「人の心を種として」のロマン主義的ともいえる解釈への批判につながる神田氏の議論を三つ引いておく。
その一は、古今集が屏風歌を認めずにこれを四季歌とし、貫之集が四季の部立を設けなかったのはなぜかをめぐる貫之屏風歌論。神田氏は、「貫之文学がいかに屏風歌なるものから生成されたか」を詳細に解析した上で、「平安朝和歌[とりわけ貫之]にあっては、絵[というフィクション]を媒介するところから四季歌は生成されたし、和歌の自然観も深められた」と指摘する。すなわち、屏風歌歌人として生きたがゆえに貫之が、そして、同時代にあっては貫之だけが、和歌における「フィクション」を発見し、「『古今集』編纂の段階で、和歌の意味はコンテクストが決定すること、和歌の言葉は無限に引用可能であることを認識し」得たのである。
「もちろん、このことは遥かに遡れば、歌が書記されるようになったことにその淵源がある。歌が声として発生した際には、その歌声は発生とともに消失するが、書記化された歌は現場を離れて反復される。だからこそ四季歌にも屏風歌にもなり得るし、詠歌主体の変更[たとえば男から女へ]も可能となり、いかなる詞書を付すかも勝手である。(略)私がいいたいのは、和歌が書記されたことで、歌なるものに本来的に孕まれていた反復可能性という問題が顕在化したということである。」
その二は、土佐日記一月二十日の阿倍仲麻呂の挿話(「唐土とこの国とは言ことなるものなれど、月の影は同じことなるべければ、人の心も同じことにやあらむ」)を「本邦初の翻訳論」と読解したくだり。神田氏は、この翻訳論は「人の心を種として」云々をはるかに超えた批評レベルに到達しているとする。
「仮名序の「言」と「心」とは、詠歌主体の心とそれを基に表出された歌との関係をいうが、ここでは、シニフィアン/シニフィエ、という言語の構造それ自体の分析用語としての使用である。しかも、「心」はすべてを根拠づける起源としてア・プリオリにあるのでなく、「言」から事後的に発見されたとする。これは「種」としての「心」が先行し、そこから「葉」が生ずるとする仮名序の因果論の比ではない。」
その三は、日本語音声を指示する「透明なシニフィアン(記号媒体)」として仮名をとらえるロジックを退け、それは「紙上のパロール(書かれた音声)」すなわち「パロールを装ったエクリチュール」以外ではないとする議論。神田氏は、(たとえば、「桜花散りぬる風のなごりには水なき空に波ぞ立ちける」の有名歌が、「散花の残映を「名残」かつ「なごり(余波)」とし、しかもそれを「水なき空」に立つ「波」と喝破した」ごとく)、「風それ自体でなく、波なる視覚化において初めて風の正体が見極められ、波の背後の「心」が摘出されたように、仮名という音声の視覚化によって、初めて言葉の正体が対象化され得たのである。」とし、「仮名文字こそが偽装の日本語音という最大のフィクションだったことになる。(略)古今集歌の表現は初めから紙上の歌として生成されたものであり、うたわないことを前提にしている以上、フィクションとしての歌である。」と結ぶ。
神田氏の議論が、ここで結ばれているわけではない。以下、「本音」としての漢文、ソシュール晩年のアナグラム研究を思わせる貫之の謎の遺作、そしてフィクションとしての貫之の人生といった魅力的な話題が続く。それ以前にも、「ないものを現前させる」言葉のはたらきや、「水面なるシニフィアンと、仮名文字との喩的関係」等々の大切な論点を取りこぼしている。
が、それはともかく、貫之の歌が、屏風絵というフィクションを鏡(媒介)として、フィクショナルな心と主体を詠む鏡像を始発とするものであったこと、したがって、「人の心を種として」がある政治性・戦略性をもった宣言であったことなどは、神田氏が指摘するとおりだろう。(というのも、三島由紀夫(『日本文学小史』)がいうように、古今集の編纂は、「力による領略ではなくて、詩的秩序による無秩序の領略」を志向するものだったのだから。また、古今集編纂時、すでに貫之が、歌におけるフィクションやコンテクストの重要性を認識していたのなら、仮名序の「言」と「心」とは、「詠歌主体の心とそれを基に表出された歌との関係」ではありえなかっただろうから。)そして、「「心」はすべてを根拠づける起源としてア・プリオリにあるのでなく、「言」から事後的に発見された」こと、それが「偽装の日本語音という最大のフィクション」を担う「紙上の歌」、すなわち貫之歌を典型とする古今集歌の表現を通じて遂行されたこと、これらもまた神田氏の指摘どおりだと思う。
私がこれに付け加えることがあるとすれば、それはただ一つ、それらの議論はすべて、「身の伝導体」から「詞の伝導体」へという、「狭義の」貫之現象学がその果たすべき仕事をなし終えた後でこそ、はじめて成り立つものなのではないかということである。
もちろん、貫之以前にも、在原業平をはじめとする六歌仙、万葉集歌、等々の「やまとうた」の伝統につながる歌の数々が詠まれていた。それは仮名序に書かれているとおりである。だが、貫之の生きた時代はどうだったか。和歌は、公的な世界からは「棄てて採られず」(真名序)、「いろごのみのいへに、むもれ木の人しれぬこととなり」(仮名序)果てていたのである。貫之はそこから、つまり、俗なる「仮名界=記号の伝導体」のただなかにあって、屏風絵というフィクショナルな鏡面に立ち騒ぐ「現象」を凝視し、「我を物思わせる場」そのものへと遡行することによって、歌の本質を独力で再定義しようとした。だからこそ、歌は「人の心を種とし」なければならぬと宣言したのだし、そのようにして生み出された「詞」であったればこそ、事後的に「心」の発見(創出)をもたらす「偽装の日本語音」の力をもちえたのである。私はそう考えている。)
■俊成系譜学─新しい花の発見
貫之がうちたてた「詞の伝導体」のはたらきによって、また、貫之編纂による「偉大な紋切り型辞典あるいは模範的類型集」(大岡信『詩の日本語』)の権威の確立を通じて、「非在のもの、非有非無のもの」もしくは「気配」に対する感覚の洗練や、社交の具としての歌の技術の練磨が進む。「和歌の内容が、実生活という個人的文脈から切離されて自立する〈つくりもの〉となり、その言葉が、現実にありうる世界を記述することをやめて、語の衝突と交錯から独自の言語空間を構築するようになる時、現実という土壌から二重に根を断ち切られた和歌は、まさに「人の心」だけを種として、新しい花を咲かせることになる。この時、時代は中世を迎える。藤原俊成は、貫之以後三百年の間問われることのなかった和歌の本質を再び問い直して新しい歌論を立て、その子定家は「幽玄体」と呼ばれた新しい歌法を産み出した。」(尼ヶ崎彬)
というしだいで、次に俊成。「ある花の色香(価値体験の型)を創出するとは、〈美しい花〉について詠むことではなく、ある花について〈美しい歌〉を詠むことなのである。」ここに生じた反転(『西田幾多郎』での永井均氏の表現を借りるならば、「体験は言葉と独立にそれだけで意味を持ちうる。言葉の意味もまたそういう体験にすぎないのだ」とする西田的確信犯から、「言葉は体験と独立にそれだけで意味を持ちうる。「体験」もまたそういう言葉にすぎないのだ」とするウィトゲンシュタイン的確信犯への転回)を徹底し、「価値体験の型」と「言葉の型」を同時に一つの「モノ」のうちに、すなわち「歌の姿」のうちに「凝固」させること。そして、いにしへよりこのかたの「歌の道の深き心」すなわち「詩的(共同)主観」の系譜に連なっていくこと。
いいかえると、「詩的世界=詞の伝導体」のアクチュアルな自律運動を極限まで追求し、(第8章で引用した大岡氏の言葉を借用すれば)、「無色のもの[=言語]のなかに色を見る一種の透視的な眼」によって見出された「心の色」を、ヴァーチュアルな「歌の姿」のうちにしみいらせること。あるいは「歌の姿」の系譜のうちから「心の色」を抽出(引用)し、「詩的主観」を体得すること。これが、(その実質については、いずれ、貫之現象学をめぐる論考を終えた後の考察に委ねるとして)、俊成系譜学の課題です。
ここでいうヴァーチュアルな「歌の姿」は、貫之現象学における(その端緒となった)「法界=物の伝導体」に対応するもので、それは「詞」のはたらきによって言語的に仮構された、俊成歌論における「新しい法界=モノの伝導体」(「新しい花」、あるいは「新しい《無》」といっていいかもしれないもの)のことです。つまり、俊成歌論にあっては、貫之歌論における「身の伝導体」に相当するものが欠落しているわけです。(俊成は、「有から無へ」の身体技法を駆使してイメージの呪縛からの脱出を試みた仏教の言語観と格闘することで、その歌論を鍛えていった。俊成の歌論に「身の伝導体」が欠落しているのは、(それが「詞の伝導体」の内部に築かれたものであったからということだけではなく)、そのような成り立ちそのものに根ざしているのかもしれない。なお、すぐ後で述べるように、俊成の「新しい花」すなわち「歌の姿」に「新しき心」を吹き込み、そして、字義通りの「新しい身」を、生身の人の振る舞いのうちに実現するのが、定家であり世阿弥である。)
このことに関連して、俊成にとっての「和歌はイメージではない」とする尼ヶ崎氏の文章を引いておきます。
■定家論理学─新しい花の仮構
最後に、定家。しかし、定家論理学については、私は、まだ語るべき言葉を充分にもちあわせていません。それは、俊成系譜学の課題を規定した先の文章で、それをなぜ「系譜学」と呼ぶのかにほとんど言及することができなかったこと以上に、いまだ私の手に負えない論題です。だから、ここではただ、夢見るような気分で、次のように語るしかありません。
父・俊成がひらいた、(詞の伝導体における)アクチュアルな次元からヴァーチュアルな次元への遡行を、極限を超えて徹底し、俊成における「モノ」すなわち「古き詞の姿」を素材に、もう一段の仮構(本歌取り)をほどこして、そうして実現した二重仮構の詞を使って、(二重否定が肯定につながる、といったロジックを介して)、そこにイマジナリーな「新しき心」(あるいは「新しい〈有〉」としてのペルソナ)を産出すること。これを、尼ヶ崎氏の言葉を借りていいかえれば、「詠作時に虚像として生じる作者=詩的主観」の「詠みつつある心」を、すなわち「和歌の産出過程においてのみ生じている、虚構の、しかし動的な生命をもって「深くなや」むことのできる「心」」を、「新しい花」として、俊成の「歌の姿」のうちに吹きこむこと。これが、(言葉が見る夢の世界を統べる)定家論理学の課題であると。
この、定家の「新しい花」は、(おそらく、「物への付託」から「詞への付託」という俊成・定家による歌の革新と、それをふまえた心敬による「心への付託」、さらには「身への付託」といった方法の変遷を介して)、詞のうえに咲くもう一つの〈無〉(もしくは〈有〉)へとつながっていきます。世阿弥の「花」のことです。
先にも少しふれたように、私は、第7章の、世阿弥をめぐる(先走りすぎた)話題のなかで、歌体論にいう「体」は、やがて、客観化された歌の姿としての「身体」(能役者の「振る舞い」)につながっていくのではないか、と書きました。このことについて、新川哲雄著『「生きたるもの」の思想──日本の美論とその基調』に拠りながら、いま少しだけふれておきます。
新川氏は、同書第一章「能楽論における無心」の「花」の節で、能に「花」が咲くとは、「暗黒の闇を切裂いて、一条の光が岩戸から〈出で来る〉ように「花」が咲く」こと、すなわち出現することだといいます。
この後、新川氏は、「岩戸は演者の歌舞に感応して内側から自ら開いたといわざるを得ない」、つまり、演者が「花」を咲かせたのではなく、自然に〈なる〉こととして「花」を語るしかないが、「同時に演者の「花」を咲かそうとする試みなしに、岩戸が自ずと開かないことも確かである」とし、それゆえ、「岩戸が開く=「花」が咲くという一つの〈こと〉が〈なる〉と〈する〉の両義で説かれねばならない」と結んでいるのです。
私は、ひとつの極論として、新川氏がいう「岩戸の向う側」は死者の世界であり、したがって、「岩戸が開く=「花」が咲くという一つの〈こと〉」は、死者の復活のことをさしているのだと考えています。死者の復活、それこそ、俊成系譜学において失われた「身の伝導体」を再び見出すこと(ただし、あくまで「詞の伝導体」のうちにあって、かつそれを食い破るものとして出現させること)だったのではないか。それが、私の仮説です。
(上に引いた尼ヶ崎氏の文章で、「「深くなや」むことのできる「心」」とあったことについて。
西行は晩年、これまで誰も試みなかった「自歌合」(じかあわせ)を二つ作り、これを伊勢神宮の内宮と外宮に奉納することを思いたった。そして、「御裳濯河歌合」の判詞を俊成に、「宮河歌合」の判詞を若き定家に託した。たびたびの催促を経て、ようやく二年余り後に届けられた定家の判詞は、西行をいたく喜ばせる。九番左の「世の中を思へばなべてちる花のわがみをさてもいづちかはせむ」を評して、定家は、「左歌世の中を思へばなべてといへるより終りの句のすゑまで句ごとに思ひ入りて、作者の心深くなやませる所侍れば、いかにもかち侍らむ」とした。この「作者の心深くなやませる所侍れば」を見た西行は、「これ新しく出で来候の御詞にてこそ候らめ」と、定家にその感動を伝えている。
さて、西行は定家の判詞から、どのような「新しさ」を見てとったのか。どのような「新しい批評の精神」(桑子敏雄『西行の風景』)を、また、いかなる意味での「新しい批評基準」や「新しい和歌思想」(尼ヶ崎彬)を見てとったのか。この点については、いずれ、定家論理学をめぐる論考に着手した際に、立ち返って思いをめぐらせなければならない。
ところで、その西行が「反魂の秘術」を行なったとの伝承がある。『撰集抄』巻五第十五「作人形事・於高野山」にこう記されている。世を棄てた聖が、月を語らう友を得んと、広野で拾った人骨に秘術をほどこし、人を作った。しかし、姿は人だが、心がないので、その声はまるで吹き損じた笛のようだった。さて、どうしたものかと案じた聖は、心がなければ草木と同じことと、高野の奥、人も通わぬ所に置き棄てた。
この、死者の魂の復活の物語をグロテスクに逆転させた説話が、なぜ西行の所業に託されたのか。これもまた、(定家における「新しき心」の創出が、折口信夫がその生涯をかけて完成をめざした「死者の書」の物語とどのような関係もしくは無関係を切り結ぶのか、また、一神教の民をとらえた「メシアの誕生」の物語といかなる関係もしくは無関係を切り結ぶのか、といったこともあわせて)、考察に値する論点だと思う。)
■哥の伝導体、再び
「狭義の」貫之現象学、俊成系譜学、そして定家論理学がになうべき課題の規定を終えたところで、以下、それらの合成によって、(というより、貫之から俊成、そして定家へという哥の伝導を通じて)、ひとつの複合的なフィールドが立ちあがり、さらにそこから、次の(いまだ名を与えることのできない)フィールドへの推移が開始されていくさまを、概略的にスケッチしておきます。
貫之がそこから「ギフト」を受けとり、究極的には、(すなわち、「広義の」貫之現象学の課題を果たすために)、そこへと遡行しようとした「物の伝導体」。その「物の伝導体」の上に、「身の伝導体」から「詞の伝導体」へのフィギュールとしての哥の運動がなりたつ。それは、意識と言語の発生(最初の夢・始まりの哥)を、アブダクティブかつレトロダクティブに再現・反復しようとする試みだった。(「一次性=アクチュアルな〈詞〉の世界」の創出。それは、ヴァーチュアルかつリアルな「物」(クオリア)のアクチュアルかつリアルな「物」(歌詞)への付託を通じて、すなわち、「二次性=リアルな〈物〉の世界」を舞台として、実現される。)
その、貫之がしつらえたアクチュアルな「詞の伝導体」のなかで、俊成が、貫之とは別の方向をもって、「歌の姿」というヴァーチュアルな次元をきりひらこうとした。それは詞の世界のなかで、あるいは言葉の見る夢のなかで、新しい《無》を見出そうとする試みだった。(「零次性=ヴァーチュアルな哥の〈姿〉」の創出。それは、「詞の伝導体」のなかに見出された新しい「モノの伝導体」として仮構される。)
そこに定家が、「虚構の、しかし動的な生命をもっ」た「心」を、すなわち、ヴァーチュアルかつイマジナリー(フィクショナル)な「新しい〈有〉」を、(詠まれた歌を「物」として、それへの付託による詠出の技法の確立を通じて)吹き込む。それは法界の外、すなわち「法外」な世界から一瞬発出される「閃光」として、詞の世界に仮構された新しい「物の伝導体」(哥の姿)のうちに吸収される。(「三次性=イマジナリーな哥の〈心〉」の創出。かくして、哥の伝導体が完成する。「物」から「物」へと遡行する、「広義の」貫之現象学の課題が果たされる。)
俊成において見失われた「身の伝導体」、それを世阿弥が、新しい、そして字義通りの「身の伝導体」による(ヴァーチュアルからアクチュアルへの)垂直方向の運動を介して、もう一つの「新しい花」へと結実させる。哥の伝導体における「零次性=ヴァーチュアルな哥の〈姿〉」から、いまだ名づけることのできない新しい伝導体へ向かって。(それは、「広義の」貫之現象学における「物の伝導体⇒身の伝導体⇒詞の伝導体」の運動を、「詞の伝導体」のなかから立ちあがった、新しい、字義通りの「身の伝導体」の運動を通じて反復する。あたかも、ストア派の思考が、「世界が強度として〈存在〉をやり直すこと」(江川隆男)へと向かったように。そして、この運動の成就によって見出される、あるいは仮構される次なる伝導体とは、たとえば利休における「美意識」のごときものをめぐる伝導現象が成り立つ場のことなのではないか。私は、おぼろげにそう予想している。)
これから先、私は、古典和歌の歌体論をめぐる考察の、いわば総仕上げとして、ラカンの「ル・レエル/リマジネール/ル・サンボリック」を、(「狭義の」貫之現象学において中心的な役割を果たし、俊成において見失われ、定家を経て世阿弥によって復活した)「身の伝導体」に関連づけ、そして、(「広義の」貫之現象学における三層構造と密接に関係する、「三つの新ピタゴラス学派的カテゴリー」をもとに構築された)「パースの巨大な記号分類」(前田英樹『言葉と在るものの声』)を、いわゆる定家十体、さらに心敬の連歌十体という「詞の伝導体」の精華に関連づけて、そのそれぞれを「ラカン三体」や「パース十体」の名のもとで、論じたいと目論んでいます。
★プロフィール★
中原紀生(なかはら・のりお)1950年代生まれ。兵庫県在住。千年も昔に書かれた和歌の意味が理解できるのはすごいことだ。でも、本当に「理解」できているのか。そこに「意味」などあるのか。そもそも言葉を使って何かを伝達することそのものが不思議な現象だと思う。
Web評論誌「コーラ」08号(2009.08.15)
<哥とクオリア>第12章 貫之現象学の課題・補論(中原紀生)
Copyright(c) SOUGETUSYOBOU 2009 All Rights Reserved.
|
| 表紙(目次)へ |