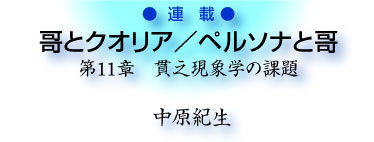|
|
|
Web�]�_���u�R�[���v |
|
���n���̎� ���{���̕\���i�ڎ��j�� ���{���̃o�b�N�i���o�[ ���ǎ҂̕Ł^���ӌ��E���z �����e�K�� ���W�҂�Web�T�C�g ���v���C�o�V�[�|���V�[ |
|
���{���̊֘A�y�[�W�� |
|
���u�J���`���[�E�������[�v�̃o�b�N�i���o�[ ���]�_���u�k�� Vue�v�̑��ڎ� |
Copyright (c)SOUGETUSYOBOU |
|
|
|
���`�����ۂ̓�̃G�������g
�@
�@�O�͂ň������ێR�\�O�Y���̋c�_���Q�Ƃ��Ȃ���A�����ŁA�i���������Ƃ���́j�єV���ۊw�̎O�w�\���ɂ��āA�܂��A�g�̓`���̂��玌�̓`���̂ւƂ����Ƃ��́A���̈Ӗ��������߂����āA���t�ƊT�O�̍Đ����܂��͍Ē�`���قǂ����A���炽�߂ččl���Ă��������Ǝv���܂��B�܂��́A�u�`���́v�̈Ӌ`�̊m�F�������͊m�肩��B
�@��V�͂ŁA���́A�����悻���̂悤�Ȏ�|�̂��Ƃ������܂����B���킭�A�`���mconduction�n�Ƃ́A�A�[�minduction�n�A��㈁mdeduction�n�A���@�mabduction�n�A���Y�mproduction�n�Ɏ����A�����Ă��������鐄�_�̑�܂̌`���ł���B�����ł������_�Ƃ́A�P�Ȃ�F���̍�p�ɂƂǂ܂���̂ł͂Ȃ��A�������E����̐i���A���_���E�ɂ�����ϔO�̘A�����܂߂��A�X�����ۂ̑��ݎ҂̉^���S�ʂ������ǂ闝�@�i���S�X�j�̂��Ƃ����̂������Ă���B�`���Ƃ������_�i�����ɁA�`���Ƃ������ہj�́A���������āA���ۂ̓����ʼnғ����鑶�ݎ҂̉^�����̂��̂ł���A���̂悤�ȉ^�������藧��̂��Ƃ�`���̂Ƃ����B
�@
�i�����ň�A�p�[�X�R���́u�A�u�_�N�V�����v���u���@�v�Ɩ����Ƃɂ��Ă̒��B�u���ρv��u�����v�ł������̂����A�{���́u���A�I���@�v�Ƃ��u���A�I�y���@�z�v�Ƃ��ׂ��Ƃ�����k�����́B�u���A�I�v�́A���Ƃ��Ă̊єV�̂��l�@������S�͂łƂ肠�����b��A���Ƃ��A�����M�j���w�Ñ�l�Ɩ��x�́u���A�M�v���߂���c�_�A���X�ɐG������č̗p�������̂ŁA�ɓ��M�����w�p�[�X�̉F���_�x���A���̋c�_�̋}���Ƃ������ׂ��Ƃ���ŁA���A���̚k�o��G�o�̐��E��ʂ��āu�����ɘA�����鎿�̐��E�ł����ꐫ�̐��E�A���R���̐��E�A���ݐ��̐��E�v�������܌���A�p�[�X�̎v�l�������Ƃ肠���Ă����B
�@�܂��A�u�y���@�z�v�Ƃ́A�u�p�[�X����W�i�S�R���j�v���Ƃ肠�����u����� �V���сv���S���\���ŁA�������������A�p�[�X�͊���ł���A�u�_�N�V�����̍�p�̂Ȃ��ɓ����Ă���ƍl�����A�u�A�u�_�N�V�����Ƃ͑����I�ȁy�����ҏW�z�Ȃ̂��v�Ə����Ă��邱�ƂɐG������ē��ɕ����A�u�y�����z�I���@�v��u�y�����z�I�Ȏ@�v��u�y�����z�I�ώ@�v�𗪂��đ��ꂵ�����́B���̏������́y�ҏW�H�w�z�I�l�@�́A�ÓT�a�́A�Ƃ�킯����W�̐��E���l���邤���ŁA�܂��ƂɎ����ɕx��ł���B���܂��́i�v�����́j��[���A�������_�������ɂ��āA���Y�^�Ƃ��ď����Ƃǂ߂Ă����B
�@�Í��W�́y�A�u�_�N�V�����ҏW�H�w�z�������āA�������̓p�[�X�́u�A����`�i�V�l�L�Y���j�v�ɂ��ƂÂ��O���W�I�u�ގ��v�������ɁA���ۂƌ������A�u�_�N�e�B�u�Ɂy�����ҏW�z���ꂽ�B�������A�V�Í��W�͂����ł͂Ȃ��āA�\�V���[�����̓W�I�u���فv�̌����ɂ��ƂÂ��A���X�̉̂����˂鏃���Ɍ���I�ȍ\�z���Ƃ��ĕҏW���ꂽ�B�܂��A�p�[�X�ɂ���āu�A�u�_�N�V�����v���u���g���_�N�V�����v�i�k�y�I���_�j�Ƃ����������A�����ď��������u�p�[�X�ɂƂ��Ắy�ӎ��Ƃ͐��_���̂��̂Ȃ̂ł���z�v�Ə����Ă��邱�Ƃ��u�����v����Ȃ�A�єV���������ɂ����ĉ̂̕�������u��܂Ƃ����v�ւƑk�y���A�̖̂{�����u�l�̐S�v�ւƑk�y�������Ƃ́A���ꎩ�̂��ЂƂ̃A�u�_�N�V�����������̂ł���A�����炱���A�̂��r�o���邱�Ƃ��ЂƂ́u�S�v��n�o���邱�ƂɂȂ����Ă������̂ł͂Ȃ����B�j
�@
�@�܂����킭�A�`���̂́A�뎟������O�����܂ł̎l�̐��E���A���Ƃ��A�뎟���ƈꎟ�����Ȃ������̋����ƁA���ƎO�������Ȃ������̎������������������Łi�����������m�ɂ����A���̂悤�ȕ��f���Ƃ��Ăł͂Ȃ��A�u���{�����{�����{�����v�̎l�����̍\���������̂Ƃ��āj�d�ˍ��킹���\�}�������B������u�F�̓`���́v�ɂ��Č��Ă݂�ƁA����́A�u�뎟�������@�[�`���A���ȚF�́q�p�r�v�u�ꎟ�����A�N�`���A���ȁq���r�̐��E�v�u�������A���ȁq���r�̐��E�v�u�O�������C�}�W�i���[�ȚF�́q�S�r�v�Ƃ����l�̈قȂ�ʑ��̂��Ƃɂ��鐢�E���A�t���N�^���ȑ��ݕ�ۊW��s�݂Ȃ���d�˕`����Ă����p�����v�Z�X�g�ł���B
�@���̂����u�������A���ȁq���r�̐��E�v�ɂ����āA�i���@�[�`���A���ȁj�N�I���A����i�A�N�`���A���ȁj�̎��ցA����ɂ͌X�̉̂��̂��̂ւƐ����̕����Ɍ������u�q�ω������ꉻ�v�̃v���Z�X���A���ꂱ���ڂɌ����邩�����ŋq�ω����Ă������Ƃ��A���Ȃ��Ƃ��єV�⒉���̘̉̑_���S���Ă����@�\�ł������B�����āA����Ƃ͋t�̃x�N�g����������������̐����^���A���Ȃ킿�u�O�������C�}�W�i���[�ȚF�́q�S�r�v�̐��E�ɂ����āA�u�r�݂���S�v����āA�i�A�N�`���A���ȁj�u�Â����v����i���@�[�`���A���ȁj�u�̂̎p�v�ցA����ɂ͉��ʁ��y���\�i����g�́��U�镑���ւƌ������v���Z�X���A�r�����ƂɂƂ��Ẳ̂̎p�������͗L�S�̂��̑��̉̑̂��߂���̘_�ł���A����ɂ͐�����̔\�y�_�ł������B
�@
�@�ȏ�A���~���Ȃ����r�F�����������炢������܂����A���́A���q�ׂ��`���Ƃ������_�i�`���Ƃ������ہj�ɂ��āA�����\�ۂƘA���Ƃ�����̊�{�v�f�i�G�������g�j�ɕ������邱�Ƃ��ł���̂ł͂Ȃ����ƍl���Ă��܂��B�Ђ炽�������A�\�ۂ́A���_�̑Ώۂ������͑f�ނ���肷�邱�Ƃł���A�����̘A���́A�����̑Ώۂ�f�ނ����݂ɊW����茋��ł����v���Z�X�̂��Ƃł��B
�i�����āA�єV���ۊw�ɂ������̍��{���ɂ��Ă͂߂�Ȃ�A�\�ۂ́A�u����ɉ]���������Ƃ̂ł��Ȃ��Ԃ̑̌��v�̂悤�ȁA��肦�ʃN�I���A�������ɂ��Ď��ɕt�������̂��Ƃ����₢�ɂ������A�A���́A���ڂɌ������Ă��Ȃ����Ƒ��l���A���Ƃ��u�S�Ȃ��g�v��u�������v�̎҂��܂߂āA���╶���Ƃ������������ۂ���i�Ƃ��ĂȂ��������ł���̂��Ƃ����₢�ɂ������B�������A�\�ۂƘA���͋}�ꂵ�̂��̌��t�����ŁA�܂��悭���Ȃ�Ă��Ȃ��B�\�V���[�������R�u�\���ɕ���āA�u�͗�ƘA���v��u�I���ƌ����v�Ɩ������Ă��悩������������Ȃ��B�j
�@�\�ۂƘA���ɂ́A���ꂼ��[��ɂ킽���̑��������āA�܂��A�\�ۂ́A�����\���ƕ\�o�̓�̍�p�ɋ敪���邱�Ƃ��ł��܂��B�ێR���̌��t�����ƁA�\���Ƃ́A�[�w�̉��ӎ��ɂ�����}�����ꂽ�p�g�X�̉���Ƃ��̕\�w�ɂ����郍�S�X���A�܂�u���łɍ݂���́v�̋L�����̂��ƂŁA���̈Ӗ��ł̕\���ɂ̓J�^���V�X�i�j�������܂��B����ɑ��āA�\�o�Ƃ́A�i�\�w�ӎ��͂��Ƃ��A���ӎ�����ӎ��Ƃ������[�w�ӎ������������A���`�ǂ���́j���ӎ��̉���������͘A���̂Ƃ��ẴJ�I�X�̔�A�����i�������j�������炷�����I�ȓ����A���Ȃ킿�u����܂ő��݂��Ȃ��������́v�̑n���i���j�̂��ƂŁA���̈Ӗ��ł̕\�o�͋��y�����炵�܂��B
�@�A���ɂ��Ă��A����ƃp�������ȓ�̋敪���l���邱�Ƃ��ł���ł��傤�B�܂��A�\���ƑɂȂ�̂��A�ێR���������Ƃ���́u�����I�E���ʑ����̕ϊ��v��u�אڂ���ʑ��Ԃ̈ړ��v�ɑ���������̂ŁA�����Ă݂�Ί����A���邢�͐����I�ȓ`�B�̃v���Z�X�̂��Ƃł��B�܂��A�\�o�ƑɂȂ�̂��A���l�Ɂu�ك����F���Ԃ̐����ω��ւƑ��ϑԁv�ɂ�������̂ŁA���`�̓`���A���邢�͐����I�Ȕ����̃v���Z�X�̂��Ƃł��B
�i�����ł����u�����v�́A��S�͂ň������w�����́x�̂Ȃ��ŁA�V�{�ꐬ�����A�u���߂Ă̖��Ƃ������ɒl���閲������Ƃ�����A����́A���Ȃ����Ȃ̌��������t�ɂ���ď��߂ĂƂ炦���Ƃ��̋������܂ޖ��̂��Ƃł���B���̋������Č����悤�Ƃ��邱�Ƃ��A��X��������荇�����Ƃ̍ł��[�����@�ł���ȏ�A���̖������Ƃ���������ꂽ�̂ł����Ă��A����͂�͂菉�߂Ă̖��ƌĂ��̂ɂӂ��킵���̂ł���B�v�Ə����Ă���A���́u���߂Ă̖��v�̍Č��ɁA���Ȃ킿�A����������o���������x�ł����߂āu���A�����v�Ōo�����邱�Ƃɑ�������B�j
�@
�@���āA�`�����ۂ��\�������̃G�������g�Ɋւ��āA�\���Ɠ`�B�̑g�ݍ��킹���\�w�Ɛ[�w�i���ӎ��j�ɂ܂�����~�^���ɁA�\�o�Ɣ����̑g�ݍ��킹���[�w�i���ӎ��j�Ɩ��ӎ��ɂ܂�����~�^���ɂ������̂��Ƃ�����A���̓�̈ٗނ̉^�����Ȃ����̂͂��������Ȃɂ��A�܂��A���̔}��@�\�͂ǂ̂悤�ȋ@���ɂ��̂��A�Ƃ������Ƃ��C�ɂȂ��Ă��܂��B
�@�ێR�����i��́i�V���W�F�j�̂������O�̗͈�i�A���X�^���X�j�������A���J���́u�����E�i���E���G���j�^�z���E�i���}�W�l�[���j�^�ے��E�i���E�T���{���b�N�j�v�ɑΉ�������̂Ƃ��āj�����\�}�A�u�~���i���ӎ��j�^�[�w�̃p�g�X�i���ӎ��E���ӎ��j�^�\�w�̃��S�X�i�\�w�ӎ��j�v�ɑ����Ă����A�u���ӎ��v�A���Ȃ킿�u�}������Ē��b�����l�̗~�]�̏W�Ϗ�ł���A����Ό̔����̃v���Z�X�i�������Č����Ηc������̂��܂��܂ȑ̌��j�ɂ����ăR�[�h����͂ݏo���A�������z������邱�Ƃ̂Ȃ��������I���z�v�ƁA�u���ӎ��v�A���Ȃ킿�u�̒a���ȑO�̌��̌����p������A�̂������Ă�����Ȃ菬�Ȃ�̏W�c�̋L���ƂȂ��đ͐ς��Ă����v�Ƃ�A������͂��炫�Ƃ͂Ȃɂ��Ƃ������Ƃł��B
�i�єV�́u�e����Δg�̒�Ȃ�Ђ������̋��킽���ꂼ��т����v�̉́����̐��E���A��������u��v�Ɓu�C�v�A�����ĊC�̒�Ȃ�u�n�v�Ƃ����O�̊E��𒊏o���A���ꂼ����S�X�A�C���p�g�X�A�n���~���Ƃ��������A��i�\�w�ӎ��j�Ɛ�C�i���ӎ��j����悷��u���ʁv�A�[�C�i���ӎ��j�ƒn�i���ӎ��j����悷��u����v�Ƃ����A�X���b�V���L���ŕ\�L������̊E�ʂ����A������g�ݍ��킹�ĕ\�����Ă݂�ƁA����i�u�n�^�C�^��v�j�͊ێR���̍\�}�ɂ҂�����Əd�ˍ��킹�邱�Ƃ��ł���B
�@�Ƃ��낪�A���̉̂ɂ́u�g�̒�Ȃ��v�Ƃ����A��l�̊E����������߂����t���D�肱�܂�Ă���B�������A����͎��́u���ʂɉf���v�ɂق��Ȃ�Ȃ��̂ł����āA����Ƃ�������}��Ƃ��ċ������A�剪�M���������Ƃ���̊єV�́u�t�|�I�Ȏ���\���v����āi����I�Ɂj�f�������C�����[�W�����ɂ����Ȃ��B���́u�g�̒�Ȃ��v�������A�u�e����v�̉́����̐��E�ɂ����āA���ӎ��Ɛ��ӎ�����悷���O�̊E�ʂ��������߂��Ă���B
�@����́A�`�����ۂ̓�̃G�������g�̑g�ݍ��킹�ɂ��[��A���Ȃ킿�u�\���E�`�B�v�Ɓu�\�o�E�����v�̒��ԗ̈�ɂ����āA���̗��҂����}���͂��炫�������Ă�����̂ŁA���Ƃ��u�����E���B�v�������́u�߈ˁE�ϐ��v�Ƃł����Â��邱�Ƃ��ł���B�ł́A���̑�O�̂��̂̂͂��炫�Ƃ͂ǂ̂悤�Ȃ��̂��B�j
�@�����̂��Ƃ��l����ɂ������āA����V�ꎁ���i������܂���S�͂łƂ肠�����j�w��ƕ҂��Ą����Ώ̐��l�ފw�U�x�œW�J�����u�C���[�W�̍l�Êw�v���A���Ȃ킿���Ί펞��̓��A�lj���\������O�̃C���[�W�Q���߂���c�_���Q�l�ɂȂ�܂��B
�@
���t�B�M���[���Ƃ��Ă̚F�A�Ă�
�@
�@���ɂ��ƁA���A�lj�ɕ`���ꂽ�O�w�̃C���[�W�Q�̂����A���́u���ۓI�ȃC���[�W�Q�v�́u�����疳�ցv�������i�u���������̔́v�Ƃ��Ă̐����A�f���q�̂悤�ɂ͂��Ȃ��j�C���[�W�̗��������ɁA���́u������l����ۓI�ɕ`�����C���[�W�Q�v�́u������L�ցv�������i�������B�ƋL�������ɂȂ����Ă����j�����̉^���ɁA��O�́u��ۓI�C���[�W���������ĕ��ꐫ����������ꂽ�C���[�W�Q�v�́u�L����L�ցv�������i�����ƃ��^�����t�H�[�V�X���Ă����_�C�i�~�b�N�ȉ^�����������O�Ƃ���_�X�����肾���j�����̉^���ɁA���ꂼ��Ή����Ă��܂��B
�@���̓��A�lj�̎O���ނ́A�p�[�X�́u�O�̐V�s�^�S���X�w�h�I�J�e�S���[�v���v�킹��Ƃ��낪����܂��B�C���[�W�̑��Q���p�[�X�́u���̂��� firstness�v�i���A���R�A���ݐ��A���X�j�ɑΉ����A�ȉ��A���Q���u��O�̂��� thirdness�v�i���ՁA�}��A�������A���X�j�ɁA��O�Q���u���̂��� secondness�v�i���A�@���A���ݍ�p�A���X�j�ɂ��ꂼ��Ή�����Ƃ������������ŁB�������A�p�[�X�̌`����w�I�J�e�S���[�_�́A��ؓ�ł͂����Ȃ��[�����Ȃ���������X���Ă��āA�ʂ肷����̌y�X�Ȍ��y�������Ȃ��Ƃ��낪����̂ŁA����ɂ��ẮA��ɁA���J���̎O�̈�_�Ƃ��֘A�Â��Ȃ��炠�炽�߂ĊT�ς��邱�ƂƂ��āA�����ł́A���̋c�_����A�C���[�W�̉^��������킷�u�����疳�ց^������L�ց^�L����L�ցv�Ƃ����\�}���ؗp���āA��ɒ��Ă������₢���l���Ă������߂̎肪��������Ǝv���܂��B
�@
�@�܂��A�u�����疳�ցv�������ۓI�C���[�W�Q�̉^���ɂ��āA���͂�����A�i�ێR���������Ӗ��ł́j���ӎ��ɂ�����^���́q���r�Ɛ��ӎ��ɂ����錻�ۓI�ȁg���h�Ƃ̉~�^��������킷���́A�܂�u�q���r����g���h�ցA�����čĂсq���r�ցv�Ə��������čl�������Ǝv���܂��B
�i�����ł����q���r�́A�i��ϒ��w���c�����Y�����q��Ζ��r�Ƃ͉����x�ł�����Ƃ���́q��Ζ��r�A�������́A�i�䎁���u�{���͐��E���̂��́i���c�I�ɂ����ΐ�Ζ��̏ꏊ�j�Ȃ̂�������ɂ����Ă͎��̉�����Č��I�Ȏw���Ώۂ������Ă��܂��v�Ƃ����Ƃ��́u���v�A���Ȃ킿�u�ό`�����L���v�i�q�@�r�j���g���ĕ\�L�����q���r�̂��ƁB�܂��A�g���h�́A�єV���ۊw�Ɋ֘A�Â���Ȃ�A�J�~����̏����ȑ��^���Ȃ킿�u�F�Ƃ����M�t�g�v���A���邢�̓p�[�X�̗p������b���ؗp����A������́u�M�� flash �v�̖��ł̂��Ƃ����́A����ɂ́A�u����ꂪ���o������F�A�����A���A���邢�͂��܂��܂ɋL�q����銴��A���A�߂��݁A�����́A���ׂđ��Â̐̂ɖłт��������̎��̘A���̂���₳�ꂽ�c�[�ł���ƍl����������Ȃ��B�v�i�w�A�����̓N�w�x�j�Ƃ����Ƃ��́A���́u�c�[�v�ɂ�������̂������Ă���B�j
�@�����āA���l�ɁA�u������L�ցv�̋�ۓI�C���[�W�Q�̉^���́A���ӎ��ɂ�����g���h�Ɖ��ӎ��ɂ�����g�L�h��}���u�g���h����g�L�h�ցv�ɁA�����ŁA�u�L����L�ցv�̕��ꐫ����������ꂽ��ۓI�C���[�W�Q�̉^���́A�\�w�ӎ��ɂ�����s�L�t�Ɖ��ӎ��ɂ�����g�L�h�Ƃ̉~�^��������킷�u�s�L�t����g�L�h�ցA�����čĂсs�L�t�ցv�ɂ��ꂼ�ꏑ�������Ă����܂��B
�i�����ł����g�L�h�́A�ĂъєV���ۊw�Ɋ֘A�Â���ƁA������łӂ��u�t�B�M���[���Ƃ��Ă̚F�v�̓�̃G�������g�A���Ȃ킿�u����v�Ɖ��������������́u�Ăɂ��́v�̂��Ƃ����̂������Ă���B�܂��A�s�L�t�́A�Ăщi�䎁�̋c�_�����p����ƁA�u���ꉻ���ꂽ�ꏊ�v�ɂ�����u�T�O���i�{�����j���ꂽ�����T�O�i�u�����v�Ƃ����{���j�v�������́u��T�O�I�Ȃ��̂Ƃ����T�O�v�������Ă���B���Ȃ݂ɁA��Ζ��̏ꏊ�ɂ�����u�[�I�Ȑ��m�Ȃ܁n�̎����v�������́u��T�O�I�Ȏ����v�̂��Ƃ��q�L�r�ƕ\�L���邱�Ƃ��ł��邪�A�������A�i�䎁�������悤�ɁA�u���ꉻ���ꂽ�ꏊ�v�ɂ����ẮA���̂悤�ȁu�[�I�ɔ�T�O�I�Ȃ��́v���q�L�r�Ɓu��T�O�I�Ȃ��̂Ƃ����T�O�v���s�L�t�́u�Δ䂻�̂��̂��T�O������Ă��܂��Ă���v�B�j
�@���āA��������ƁA��ɂӂꂽ��̓`�����ۂ��Ȃ����̂͂Ȃɂ��Ƃ����₢�ɑ��铚���i���m�ɂ́A���̌����j������ꂽ���ƂɂȂ�܂��B����́A�q���r�����u����������g���h���d���Ƃ�A�����s�f�Ɂg�L�h�ւƂ����炵�A�������ās�L�t�ւƊT�O�����邱�Ƃ̂Ȃ��C���[�W�Q�̂͂��炫�A�܂�u�g���h����i�q���r�ցA�����čĂсj�g���h�ց^�g���h����g�L�h�ց^�g�L�h����i�s�L�t�ցA�����čĂсj�g�L�h�ցv�̎O�w�̍\�}�i�ق�Ƃ��́A�����ɂƂǂ��قNJ��w�ɂ��ςݏd�˂�ꂽ�p�����v�Z�X�g�̂������j�ł��߂����Ƃ��ł���C���[�W�Q�̉^���̂��Ƃł��B
�@
�i����́A�����܂ŎO�̑w�́A�������͖����̑w�̏d�˕`���Ƃ��Ă͂��炭���̂Ȃ̂ł����āA���Ƃ���������u�g�L�h����g�L�h�ցv�������o���ƁA���ׂĂ͐l�דI�ȋL���́u�ϊ��v��u�ړ��v�ɂ����Ȃ��u�ӎ��Ȃ����Ȉӎ��v�i�i��ρj�̃��{�b�g�̐��E���o�����邱�ƂɂȂ邾�낤�B����ɂ�������[�I�ȁs�L�t�������o���Ă���ƁA���̂悤�ȁs�L�t�̏�ɂ́A�����炭�������̎Љ�ɂ�����u�������E�v�����藧���ƂɂȂ�̂��낤�B
�@���邢�͋t�Ɂu�g���h����g���h�ցv�̉^���������o���ƁA�₦����u�����ω��v�Ɓu�ϑԁv�ɂ���čʂ�ꂽ�u���Ȉӎ��Ȃ��ӎ��v�i���j�̋��l�̐��E���Ђ炩���̂�������Ȃ��B����ɓ��l�ɂ�������[�I�ȁq���r�������o���Ă���ƁA�i���m�ɂ́A����́s���t�ƕ\�L���邵���Ȃ����̂ł���͂��Ȃ̂����A���́s���t�̉��ɂ́j�A���������́u�����܁v�̐��E���Ђ炩��邱�ƂɂȂ�̂�������Ȃ��B
�@����ł́A�u�g���h����g�L�h�ցv�̉^���������o���Ă���Ƃǂ��Ȃ�̂��B���͂����ɁA��ŏq�ׂ�A�u�L���疳�ցv�Ƃ����ʂ̃x�N�g�����������^���Ƃْ̋��W��s�u���`�́v�єV���ۊw�̐��E���Ђ炩���̂ł͂Ȃ����ƍl���Ă���B�j
�@
�@���́A���̂悤�ȑw��ɐςݏd�˂�ꂽ���A�lj�̃C���[�W�Q�̂͂��炫���A�i�o�ϓI�ȓ`�B���߂����R�~���j�P�[�V�����s�ׂł���u�f�B�X�N�[���v�ƑΗ�����j��R�~���j�P�[�V�����I�ȕ\���s�ׂł���u�t�B�M���[���v�̓��������Ȃ������̂Ƃ��ĂƂ炦�Ă��܂��B�ȉ��ɁA��S�͂ň��p�������͂��A������x�����Ă����܂��B�i���p���ɏo�Ă���u�����I�m���v�Ƃ́A���Ί펞��A�j���[�����̐ڍ���H�̑g�ݑւ��ɂ���ĔF�m�̈�Ԃ̉��f�I�ȍs�������\�ɂȂ������ʁA���{�I�ȁu�S�̊v���v�ƂƂ��ɐ��܂ꂽ�V�����m���̂�����i�u�F�m�I�������v�Ƃ��Ă��j���������́B���̒m���̔����ɂ���āA���Ƃ��A�A�i���W�[�i�g�A�މ����\�j���傫�ȓ���������u�z���T�s�G���X�̌���v���\�ƂȂ����A�ƒ��͌���Ă���B�j
�@
�@
�@���́A�i���C�Â��̂悤�ɁA�ƒ��̌�����^���Ă݂����Ƃ���ł����j�A���̃t�B�M���[���̂͂��炫�������A�u���`�́v�єV���ۊw�ɂ����āA�u�l�̂���������˂Ƃ��āA���Â̂��Ƃ̂͂Ƃ��Ȃ�肯��v�́u��܂Ƃ����v�̐��E�i�[�w�̓`�����ہj���A�u�S�ɂ����ӂ��Ƃ�������̂������̂ɂ��Ă��Ђ�������Ȃ�v�́u���̒��ɂ���l�v�̉̂̐��E�i�\�w�̓`�����ہj�ւƂȂ��ł����͂��炫�A���Ȃ킿�̂��u���Ђ������v���Ƃ̎������Ȃ��Ă���̂ł͂Ȃ����ƍl���Ă���̂ł��B
�@
����_���E�B���_�E�����A�����ĉ̘_
�@
�@�Ƃ���ŁA���́A���Ί�̓��A�̕ǖʂɕ`���ꂽ�A���Q�ɑ�����̓I�C���[�W���������Â��鐸��̏@���̔ے�̂����ɁA���Q�Ƒ�O�Q�ɑ�����u�L�����⌶�z���Ɛ[���Ȃ���̂���v�C���[�W�̗͂�����Ƃ���V�Ί�^�̏@���ƌ��͂̌`�Ԃ����܂�A�������������I�C���[�W�i�q�G���O���t�ɍ��܂ꂽ�����̐_�X�j�̎�������̏o�G�W�v�g�����s�����̂��A�u��C���[�W�I�Ȃ��Ƃ̏ے��͂����ɂ���āA�����̈З͂��������v�Ƃ���_�A�u�p���`�������Ȃ��A�������O���������Ȃ��O��I�ɒ��z�I�ȕʂ̐_�v���u�������_���ł������ƌ���Ă��܂��B�������A�C���[�W�̉������瓦�����邽�߂ɂ́A���́u���[�Z�̃v���O�����v�Ƃ͋t�̕����������I���^�i�e�B�u�ȓ�������܂����B�B���_�ƕ���������ł��B�ȉ��A�����g�̌��t�������܂��B
�@
�@
�@
�@���̋c�_���g���āA���Ȃ�́u���_�v���\�z����ƁA���̂悤�ɂȂ�܂��B
�@�܂��A�i���A�lj�ɕ`���ꂽ�C���[�W�Q�̖{�����Ȃ����̂Ƃ��ė������ꂽ�j�t�B�M���[���̂͂��炫���u�L�v�̕����ɒ��z���Ă������Ƃ���̂��A�u�L��������ƗL�ցv�i�݂�������ƍ݂邱�Ƃ̕��ցj�������A���̕\�L�ł����A�u�s�L�t����q�L�r�ցv�i���������̂Ȃ��s�t����B��́q�_�r�ցj��������_���ł��B����͑��Q�E��O�Q�̋�ۓI�E�����I�ȃC���[�W�͂��Ƃ��A���Q�̒��ۓI�E���w�I�C���[�W�����ے肵����A�u��C���[�W�I�Ȃ��Ƃ̏ے��͂����ɂ���āA�����̈З͂��������v�Ƃ���_�ւ����铹�ł�����A�����ł�����u���Ƃv�́A���i���j��`�i�����j�Ƃ������������ۂƂ͂��������̂��������������A�܂��A���́u�ے��́v���A�S�I�C���[�W��Ӗ��̌��Ƃ��������ƂƂ͖����Ȃ��̂ƂȂ�ł��傤�B
�i����́A�x�����~�����u�����ʂ���ѐl�Ԃ̌���ɂ��āv�ŏq�ׂ��u�n������_�̌�v���A�܂��u�|��҂̎g���v�ł����u��������v�A���Ȃ킿�u�݂�����͂��͂≽���u�������A�����\�����邱�Ƃ��Ȃ��A�\���������Ȃ��n���I�Ȍ�v�i�w�x�����~���E�R���N�V�����Q�x�j���v�킹��B�������́A�i���܂����o�H���o�āj�A�܌��M�v���u�����_�v�ŏq�ׂ��u�ے�����v���A�܂��u�����w�̔����v�ł����u�_��i�J�~�S�g�j�v���B�j
�@���̈�_���Ƃ͋t�����̃x�N�g���������āA���Q�ɑ�����u�B���_�I�C���[�W�Q�v�ȊO�̂��ׂẴC���[�W�̓�����ے肵�A�u�����疳�ցv�́u���̌������E�v���A�܂�v�҂��܂߂������̎n���i�A���P�[�j�⌳�f�i�X�g�C�P�C�A�j�̐��E�������܌��悤�Ƃ���̂��B���_�ł��B��������Ȃ�ɕ\�L����A�u�s�L�t����s���t�ցv�i�s���t���炻����Y�o����s���Ձt�ցj�̒��ړI�ȁi�g�L�h��g���h��}��Ƃ��Ȃ��j�v�ق��A�Ñ�̗B���_������Â��Ă���Ƃ������Ƃł��B�����ɏo�Ă���s���t�́A�i�P�Ȃ�A����̋q�ϓI����ɂ�����T�O�Ƃ��Ă̂���ł͂Ȃ��āj�A���Ƃ��A���������̓N�w�̌n���u�� oion�v�ɂ��Ƃ����X�g�A�h�̐l�X���A���E�̋��E�̊O���ɂ���Ƃ����̓I�ȁu�v�������Ă��܂��B�ȉ��A�G�~�[���E�u���C�G���w�����X�g�A�N�w�ɂ�����̓I�Ȃ��̗̂��_�x����A��ҁE�]�엲�j���̕��͂������܂��B
�@
�@
�@����́A�u�o�����Ǝ��R�N�w��������j���̃X�g�A��`�ɂ��āv�Ƒ肳�ꂽ���҉��̑�u�̓I�}�e���A���X���������ȕۑ��̃m�C�Y�v�Ɏ��߂�ꂽ�u�i�P�m���j���������̎��́A���邢�́q�튯�Ȃ��g�́r�v�̏͂�����������̂ł����A���̖̏͂����ɁA�]�쎁�́A�u�X�g�A�h�̐l�X�������F���̑�A��R�ĂƂ́A���E�����x�Ƃ��āq���݁r����蒼�����Ƃł���A���������āA���̂Ƃ��A�܂��ɂ��̂Ƃ������́q���݁r�������̂ł���B�v�Ə����Ă��܂��B���́A�����ɂ��u�r�b�O�o���F���v���v�킹��L�q����A�܂��A���̑�ꕔ�u�����w�I�}�e���A���Y�������F���̉������v�̃^�C�g���ɂ�����u�����w�I�v�Ȍ�b�i���Ƃ��u���v�A���Ƃ��u��q�I�����́i���S�X�E�X�y���}�e�B�R�X�j�v�j����̘A�z�ŁA���́A�i�Ñ�̎��R�N�w�Ƌߑ�A����̎��R�Ȋw���܂������f���̈قȂ���̂ł��邱�Ƃ͕S�����m�̏�ŁA�����܂ł���_���Ƃ̑Δ�̊ϓ_����j�A���R�Ȋw���܂��Ñ�B���_�Ɠ�������i��ł������Ƃ���c�݂Ȃ̂ł͂Ȃ����ƍl���Ă��܂��B
�i���R�Ȋw���g���h�Ɓg�L�h�̐��藧����邱�Ƃ�����Ƃ��Ă��A����͂����܂Łs���t�i���_�j�ɂ��s�L�t�i���ہj�̐����̈�Ƃ��Ăł����āA�g���h��g�L�h�����R�Ȋw�̔}��ƂȂ�킯�ł͂Ȃ��B���������A���R�Ȋw���ώ@�E�����E���̑ΏۂƂ���̂́s�L�t�ł����āA�g���h��g�L�h���Ȋw�I�T���̑ΏۂƂȂ�킯�ł͂Ȃ��B�j
�@�������܂��A��_���Ƃ͋t�����́A������̈قȂ铹��i�݂܂��B����́A�t�B�M���[���̐��E�ɓ��݂��A���̒�i���j��j������ւ̒��z���߂������A����������A�C���[�W�̑�O�Q�i���j����Q�i���Ձj�����ݏo�����E�i����I�\�z���j�̐��藧����m��i���j�A�����Ă�������̂��Ă������߂́u�L���疳�ցv�������g�̋Z�@����g���āA�C���[�W���Q�̐��E�ւ̒��ړI�ȃ_�C�r���O�����s���A����ɂ́u����������Ɩ��ցv�i�����������Ɩ������Ƃ̕��ցj�������Đi��ł������Ƃ�����̂ł��B���̕\�L�@�ɂ��������A�u�g�L�h����g���h�ցv�́i�g�̂��������j���H��ʂ��āu�s�L�t����s���t�ցv�́i����́j��̂��A�����ċ��ɓI�ɂ́u�s���t����q���r�ցv�̊o���ɂ����邱�ƁA���ꂪ�����̂߂������ł��B
�@
�@�ȏ�̂��Ƃ���A��_���A�B���_�i���R�Ȋw�j�A�������ғ����鐢�E�̐V�����\�}�������т������Ă��܂����B���Ȃ蕡�G�Ȃ��̂ɂȂ�܂����A����́u�q���r�^�s���t�^�g���h�^�g�L�h�^�s�L�t�^�q�L�r�v�ƕ\�L���邱�Ƃ��ł���ł��傤�B�i�q���r�Ɓq�L�r�A�s���t�Ɓs�L�t�A�g���h�Ɓg�L�h�̎O�̑ƂȂ鍀�������鎟���͂܂�ňقȂ��Ă���B�܂��A���ܓ��������ɑ����邩�̂悤�ɏq�ׂ������A���Ƃ��g���h�Ɓg�L�h�́A�������ē��ꎟ���ɑ�������̂ł͂Ȃ��B�����̂��Ƃ�}������ƕ��G�ɂȂ肷����B����A���������}�����邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�j
�@���̍\�}�������āA���������V�Ί�^�̏@���E���́i�g���h�Ɓg�L�h������̂����ɋz�����Ǘ�����s�L�t�ɂ���ē������ꂽ���E�j����̎O�̒E�o�o�H���Đ�������ƁA���̂悤�ɂȂ�܂��B���A�E���̋Ɂi�q�L�r�j�ցB���m�ɂ́A���̍\�}���̂��̂z��������ցA�܂荶���̊e���i�s���t����s�L�t�܂Łj��ے肵�āB�i���̔ے肪�s�O�ꂾ�ƁA���Ƃ��s�L�t���q�L�r��������邱�Ƃ��߂���_���A���邢�́s���t�Ɓs�L�t�̊W���߂��镁�_���Ȃǂ���������B�j���A�E���i�s�L�t�j���獶���i�s���t�j�ցB�������A���ԁi�g���h�Ɓg�L�h�j��}��Ƃ����ɁB��O�A�����̋Ɂi�q���r�j�ցB���m�ɂ́A���̍\�}���̂��̂���ݓI�ɒ��z��������ցA�܂蒆�ԁi�g�L�h����g���h�ցj��}��Ƃ��A���ɓI�ɂ͂�����ے肵�āB
�@���̂悤�Ɋȗ������Ă݂�ƁA�����ɑ�l�̓��̉\�������サ�Ă��܂��B���Ȃ킿�A���̓��Ɠ����u������L�ցv�̕������������A���̓��Ɠ��l�A���̐��E����̒��z���߂������Ƃ͂Ȃ��A�����āA��O�̓��ƂƂ��Ƀt�B�M���[���̂͂��炫��}��Ƃ��铹�B����́A�i�ꌩ�A�V�Ί�^�̃C���[�W�̉����ւ����铹�Ɠ������̂Ɍ����܂����A�������A�����ł͂Ȃ��j�����܂ł��t�B�M���[���̐��E�̂����ɓ��݂��A�������A��O�̓��̂悤�ɋ��ɓI�ɂ����ے肵���邱�Ƃ͂Ȃ��A�����Ă����Ȃ�A���̓��Ƃ͋t�́u�s���t����s�L�t�ցv�̃x�N�g���������āA�i�V�Ί�^�̏@���E���͂̊�b�ƂȂ邻��Ƃ͎��Ĕ�Ȃ�j�V�����s�L�t�`���悤�Ƃ��铹�̂��Ƃł��B���́A���ꂱ�����ÓT�a�̂̐��E�ɂ����ĉ̘_���T�����Ă������̂Ȃ̂ł͂Ȃ����A�����Ă���́A���Ȃ킿�̘_���߂����V�����s�L�t�Ƃ́A�i��Ƃ́u���Ƃ͂ӂ邫�������ЁA�S�͂����炵�������߁v�i�ߑ�G�́j���������Ă����j�A�u�Â��S�v�i���ɂ��ւ̐��E�j�𗧂�������u�V�������v�̂��Ƃ������̂ł͂Ȃ����A���Ȃ��Ƃ��єV���ۊw�ɂ����Ă͂����������̂ł͂Ȃ����ƍl���Ă���̂ł��B
�@
�i��̍\�}�̍��E���[�Ɉʒu����q���r�Ɓq�L�r�́A���̎n�܂�̎��ɂ����Ă͑��������i����ꌳ�A�������́A����ꌳ�j�B�����āA���̂悤�ȁq�@�r�ň͂܂����́A�܂�u���閼�Â����ʂ��́v�����݂��邱�Ƃ��A�i��ώ��́u�J蓂̊�Ձv�ƌĂB���́A�u�L�`�́v�єV���ۊw�ɂ�����u�������I����v�������͒�Ƙ_���w�ɂ�����u��������Q�[���v�ɂ����ẮA���̂悤�ȁq���r��q�L�r����邱�Ɓi�r�ނ��Ɓj���\�ɂȂ�̂ł͂Ȃ����A���邢�͂��̂悤�ȉr�o���\�ɂ�����̂Ƃ��āA�u�L�`�́v�єV���ۊw���Ƙ_���w��_���邱�Ƃ��ł���̂ł͂Ȃ����Ƃ̌��ʂ������ĂĂ���B
�@�����Ă���́A���Ȃ킿�̘_�ɂ�����q���r��q�L�r�́A���̓����������Ƃ��钴�z�I�ȁq�L�r�ɑ��āA���̓����s���t��Λ��������̂ƃp�������ɁA��O�̓������B���悤�Ƃ��钴�z�I�ȁq���r�ɑ��āA��l�̓����Λ�������V�����s�L�t�̐��E�̂����ɁA���Ȃ킿�V�����u���v�̐��E�̂����ɑ��`�������̂Ȃ̂ł����āA�����́q���r���_���́q�_�r�Ƃ͎��Ĕ�Ȃ�V�����q���r�ł���q�L�r�Ȃ̂ł͂Ȃ����ƍl���Ă���B�������A���̂悤�ȁq���r��q�L�r�Ƃ͂��������ǂ̂悤�Ȃ��̂��A�����Ă������u���i�r�ށj�v�Ƃ͂����Ȃ邱�ƂɂȂ�̂��A���̎����ƈӖ������ɂ͂܂����߂Ă͂��Ȃ��B�j
�@
�����̓`���́^�g�̓`���́^���̓`����
�@
�@���ɂ��ւ̐��E���u���A�����v�ɗ���������V�������̒T���B���́A�єV���ۊw�́i�V�����j�K��̎����ɂ��čl���邱�Ƃ�ʂ��āA�ȉ��A���̖̏͂`���Ɍf���Ă�������̖₢�A���Ȃ킿�A�єV���ۊw�̎O�w�\���Ƃ͂Ȃɂ��A�܂��A�g�̓`���̂��玌�̓`���̂������Ƃ͂����Ȃ�Ӗ������̂��ƂȂ̂��Ƃ����₢�ɁA�i����ɁA�ł���A�u���`�́v�єV���ۊw���u�L���疳�ցv�̉^���Ƃْ̋��W��s��ł���Ƃ͂ǂ��������Ƃ��A�����āA�V�������̐��E�����݂����V�����q���r��q�L�r�����i�r�ށj���Ƃ��\�Ƃ���u�L�`�́v�єV���ۊw�Ƃ͂Ȃɂ��Ƃ����₢�Ɂj�A�ꉞ�̓�����^���Ă��������i�������́A���̂��߂̎肪����Ă��������j�Ǝv���܂��B
�@
�@��̍\�}�A�u�q���r�^�s���t�^�g���h�^�g�L�h�^�s�L�t�^�q�L�r�v�ɂ́A�قȂ錴���ɑ������̂��̂̉^���i�`���j���d�˕`����Ă��܂����B���̂���́A���ɓI�ɂ́q���r�ւƋɂ܂��Ă����u���v�̉^���A���̂���́A���ɓI�ɂ́q�L�r�ւƒ��o����u����v�̉^���Ɩ��Â��邱�Ƃ��ł��܂��B�����ł����u���v�́A���_���E�ɑ��镨���I���E�Ƃ����Ƃ��́u�����v���܂݁A���������āA�L����`�̋����o�̊�̂ƂȂ���̂Ȃ̂ł����A���͂��ꂾ���ł͂Ȃ��A�i���邢�́A��₱�����b�ł����A�F�̓`���̂Łu���A���ȁq���r�̐��E�v�Ƃ����Ƃ��́A�N�I���A�ł���A�̎��i�������Ƃj�ł�����A�͂Ă͉r�܂ꂽ�̂��̂��̂ł�����Ƃ���́q���r�Ƃ��قȂ鑶�ݗl�����������j�A�p��ł����ethe thing�f�A�h�C�c��ł́edas �cing�f�A�J���g�N�w�ɂ����u�����́v�̂��́u���v�̂��Ƃł�����܂��B��������́u����v�́A�i��̋c�_�ɂȂ����߂̕����Ƃ��ďq�ׂĂ����Ɓj�A�x�����~���������u�����ʁv�A���Ȃ킿�u�����̌���^�l�Ԃ̌���^�_�̌���v�������Ă��܂��B
�@��������ƁA���̍\�}�̂Ȃ�����A�i��̓I�ɂ́u���v�Ɓu����v�̓�̈ٗނ̉^���i�`���j���d�˕`�����̈�̂Ȃ�����j�A������}���͂��炫�Ƃ��āA��O�̉^���������������Ă��邱�ƂɂȂ�܂��B���̗̈悱���A�s���t�Ɓs�L�t��[�_�Ƃ����ԁA�܂�u�g���h����g���h�ց^�g���h����g�L�h�ց^�g�L�h����g�L�h�ցv�ƃt�B�M���[�������������ꏊ�̂��ƂŁA���̃t�B�M���[���̂͂��炫���A���́A�u�g�v�̉^���Ɩ��Â������Ǝv���܂��B�����ł����u�g�i�݁j�v�Ƃ́A������u�g�́v�ƁA���̐g�̂��ꏊ�Ƃ��ė���������i�����o�������C���[�W�ƁA�䓛�r�F���������u�Ӗ��̃J���}�v������C���[�W�Ƃ��Ƃ��ɐZ�������j�u�S�v�̓�𐬕��Ƃ��ċ��Ɋ܂ށu�g���S�v�i�������́A���������u�t�B�M���[���Ƃ��Ă̎�́v�j�̂��Ƃł��B
�@���́u�g�v�̉^���i�`���j��ʂ��āA�u���̒��ɂ���l�v�����퐶���Ŏg�p����q�ϓI�Ȍ���i�i�䎁���w���c�����Y�x�ŁA�u�o���̎�̂͏�ɐ��E�̓����ɑ��݂���l�ł���Ƃ����������A����\���̊�b�ɂ��炩���ߐD�荞��ł���v�Ə������p��I�\���j�������炷�̂ł͂Ȃ��A���邢�́A�Ȃɂ��\�ۂ����A�Ȃɂ��`�B���Ȃ��u��C���[�W�I�Ȃ��Ƃ̏ے��́v�i�������ꁁ�_�̌���j���u������̂ł��Ȃ��A����̑�O�̉^���̂�����i�������i�䎁���A�u����m�o���̎�̂͏�ɐ��E�̓����ɑ��݂���l�ł���Ƃ��������n��D�荞��ł��Ȃ���l�̓I�ȓ��{��I�\���̂ق����A�i���҂��A�r�����Ă���Ƃ����Ӗ��ł���A�܂ݍ���ł���Ƃ����Ӗ��ł���j���͈ÂɓƉ�_�I�ł���A�O�����c�N�w�������ł���Ƃ�����B�v�Ə������A�u�����o���v���̂��̂̌���\���j���A���ꂱ���g�������āu�l�̐��v�Ɍ��o���邱�ƁB���ꂪ�A�Ñ�E�����̘̉_�A���Ȃ��Ƃ��єV�̘̉_���߂��������Ƃ������̂ł���A���̂悤�ȑ�O�̌�����A���́u���v�i�N�I���A�߂��̌��t�j�ƌĂ�ł����̂ł����B
�@�����ɁA�u�L�`�́v�єV���ۊw���\������O�̗̈悪����Ђ炩��邱�ƂɂȂ�܂����B���́A�u�����疳�ցv�̉^���i�`���j���ɂ܂�u��Ζ��v�Ƃ������ׂ��E����܂ޏꏊ�̂��ƂŁA������u���̓`���́v�ƌĂԂ��Ƃ��ł��܂��B���́A�u������L�ցv�̉^���i�`���j��s�f�Ɍp������t�B�M���[���̐��E�ŁA����́u�g�̓`���́v�ƌĂ��ꏊ�̂��Ƃł��B��O�́A�u�L����L�ցv�̉^���i�`���j��ʂ��ĐV�����u�L�v�̐��E��n�����A����ŁA�i�u�L����L�ցv�̉^����o�ɁE�������j�q�ϓI�ȓ��팾��Ƃ̂������ɁA�����ŁA�i�u�����疳�ց^������L�ց^�L����L�ցv�Ƃ����C���[�W�̉^�����̂��̂z����j��������Ƃ̂������ɁA���ꂼ��ْ���s�W���Ƃ�ނ��Ԏ��I����Ƃ��Ắu���v���ғ�����̈�A���Ȃ킿�u���̓`���́v�̂��Ƃł��B
�@���́u���̓`���́^�g�̓`���́^���̓`���́v�̎O�w�\���́A���̊єV���ۊw�̃g���A�X�A�u�F�Ƃ����M�t�g�^�t�B�M���[���Ƃ��Ă̚F�^�F�̃p�����v�Z�X�g�v�̉����\���ɑ���������̂ł��B�����āA���̑�O���u�F�̃p�����v�Z�X�g�v�́A�u�M�t�g�^�t�B�M���[���^�p�����v�Z�X�g�v�Ƃ����O�w�\�����̂��̂��i�����ׂȃ��x���ł́A�����ɂƂǂ��قNJ��w�ɂ��ςݏd�˂�ꂽ�t���N�^���ȃt�B�M���[���̉^�����`�����j��������킷�Ɠ����ɁA���̓`���̂��t�B�[���h�Ƃ��ĉr�ݏo������Ă��������̉̂̐��E�̑��ݗl�������A��̓I�ɂ́A�i�u���`�́v�єV���ۊw�̐��E�ƂƂ��Ɂj�r���n���w���Ƙ_���w�̐��E�̂���l�����\�����悤�Ƃ�����̂ł��B
�@
���єV���ۊw�̓�̈Ӌ`
�@
�@��X�͂ŁA���́A�єV�́u��܂Ƃ����́A�l�̂���������˂Ƃ��āA���Â̂��Ƃ̂͂Ƃ��Ȃ�肯��v�́A�i�r���́u���̌Í��W�̏��ɂ��ւ邪���Ƃ��A�l�̐S����Ƃ��āA���Â̌��̗t�ƂȂ�ɂ���A�t�̉Ԃ����ÂˁA�H�̍g�t�����Ă��A�̂Ƃ��ӂ��̂Ȃ���܂����A�F�����������m��l���Ȃ��A�Ȃɂ����͖{�̐S�Ƃ����ׂ��B�v�ɂ��āA�E�c��䎁���������߂����悤�Ɂj�A�u��̎��R�i�����Áj�͐S�̐��ݏo���Ƃ���̂��́i�����Ƃ̂́j���v�Ƃ܂ʼn��߂��邱�Ƃ͂ł��Ȃ�����ǂ��A���̂悤�ȏr���̘̉_�������������Ă����{�I�ȍ\�}�́A�єV�̘̉_�̂����ɂ��炦���Ă���̂ł͂Ȃ����Ə����܂����B�����āA�єV�ɂƂ��Ắu��܂Ƃ����v�̐��������Ƃ́A�u���Ái���j�^�l�̂�����i�g�j�^���Ƃ̂́i���j�v�̎O�w�\���������̂ł���A������A���ɐ旧�u���Áv�̑����炱������邩�A���邢�́A�r�����Ƃ̂悤�Ɂu���Ƃ̂́v�i���̎p�A�������͉r�ݏo�����ꂽ�́j�̑����炱������邩�́A�єV�����炦���\�}�̂Ȃ��ł̉^�������̈Ⴂ�ɋA������̂ł͂Ȃ����Ƃ��B
�@�������A���̂悤�ȋc�_�́u�L�`�́v�єV���ۊw�ɂ����Ă����ʗp������̂Ȃ̂ł����āA�u���`�v�̊єV���ۊw�ł́A���Ȃ킿�A�u��܂Ƃ����v�̐��E���u�S�ɂ����ӂ��Ƃ�������̂������̂ɂ��Ă��Ђ�������Ȃ�v�́u���̒��ɂ���l�v�̉̂̐��E�ւƂȂ��ł������Ɓi�̂��u���Ђ������v���Ɓj���ۑ�Ƃ���ǖʂɂ����ẮA���藧���܂���B
�@��j�����w�Ԓ��̎g�x�ŁA�єV�Ȍ�̉̂̓��̕ϑJ�ɂ��āA�u���t�����𑶍݂̋��菊�Ƃ���a�̂̐��E�v���̐l�����̑O�ɗ���������ɂ��������Ƃ����Ƃ��A���m�ɂ́A�u�a�̂̓��e���A�������Ƃ����l�I��������ؗ�����Ď�������q������́r�ƂȂ�A���̌��t���A�����ɂ��肤�鐢�E���L�q���邱�Ƃ���߂āA��̏Փ˂ƌ�������Ǝ��̌����Ԃ��\�z����悤�ɂȂ鎞�A�����Ƃ����y�납���d�ɍ���f����ꂽ�a�̂́A�܂��Ɂu�l�̐S�v��������Ƃ��āA�V�����Ԃ��炩���邱�ƂɂȂ�B�v�Ə����Ƃ��A�����ł�����u�V�����ԁv�����A�i���̎����ɂ��Ă͂��炭�[���Ƃ��āA���Ȃ��Ƃ����̌`���Ȃ��������ɂ����āj�A�u���̓`���́v���琶�܂�ł�V�����s�L�t���u���v���炩����V�����q�L�r�i�������́q���r�j�������̂ł���A�u�L�`�́v�єV���ۊw�ɂ�����u���v�́A���̂悤�ȁq�L�r�i��q���r�j���r�ނ��Ɓi�����o���̌��ꉻ�j���ꎩ�̂��\�Ƃ���ꏊ��n�����Ă����A�u�������I����v�Ƃ��Ă̗͂������Ă��܂��B�i���m�ɂ́A���������͂����������̂Ƃ��āA�єV�̘_��_���邱�Ƃ��\�Ȃ̂ł͂Ȃ����Ǝ��͍l���Ă���B�j
�@����ɑ��āA�u�g���h����g�L�h�ցv�̃t�B�M���[���̂͂��炫�̂����ɓ��݂���u���`�́v�єV���ۊw�̐��E�ɂ����ẮA��������̒��o���͂��邱�ƁA����������A�u���̓`���́v�i�u���߂��̂Ђ炯�͂��܂肯�鎞�v�ւƘA�����鋤���o���N�I���A�̉F���j�ɍ������A�u�g�̓`���́v����u���̓`���́v�ւ́A�i�x�m�J���́u�Ȃ����߂ނƂ���S�v�̂͂��炫�i�u�\���v�ɂ��J�^���V�X�j�ɑ����Ă����A�u�Ђ��Ԃ�S�̋��܁v�̗��_����u���Ƃ̋��܁v�̗��_�ւ́j�A���������̈ړ��𐬂������邱�Ƃ��ۑ�Ȃ̂ł����āA�����ł́A���łɒB�����ꂽ�u���v�̏�ɂ����A�����v�z�Ƃ̊i���̂����u�s�L�t����s���t�ցv�i�u�̂Ƃ��ӂ��̂Ȃ���܂����A�F�����������m��l���Ȃ��A�Ȃɂ����͖{�̐S�Ƃ����ׂ��v�j�̘̉_���������āA�u���ɂ��ւ�肱�̂����̂����̂������v�̐��ݓI�Ȍn����T�������r���ƁA�����Ă܂��A���̂悤�ȏr���̘_�̏�ɂ����āA�u�q�L�r����q���r�ցv�i�u���߂������͂�m��Ƃ͂��ɂ��ւ̒N�����͂肼�~���̓��v�j�̘̉_���������āA�u�Â����v�Ɂu�V�����S�v�i�y���\�i�j���ӂ�����ƂƂ��A���悻�����т����Ƃ̂ł��Ȃ��ْ���s�W������ނ��Ԃ��ƂɂȂ�݂̂͂₷�������ł��傤�B
�@���́A��ɁA�i��ɁA�Ƃ́A�����g��ł���̘̑_���߂���l�@���I���邱�Ƃ��ł����������ɂ́A�Ƃ������Ƃł����j�A�єV���ۊw�ɂ�����u�t�B�M���[���Ƃ��Ă̚F�v�̖����߂����āA�u����v�Ɖ��������������́u�Ăɂ��́v�ɂ�郉���K�[�W���̂͂��炫�������炷���́A���Ƃ��A�A�i�O�����Ƃ��ẴA���\���W�[�A�q�F�r�̘_���Ƃ��Ẵp���I���W�b�N�╶�@�i�l���A�����A�l�́j�̐����A�u����i���E�̑��e�j�v�Ɓu���v�Ɓu�����v�Ɓu���v�ɂ�����鎄�I����_�A���X�ւƋc�_��W�J���Ă������Ƃ�ژ_��ł���̂ł����A�������A���̑O�ɁA���ʂ̍�ƂɌ��������Ă����˂Ȃ�܂���B
�@
�i�u���o���鏼�ɂ͂���njÂ̐��̊����͂��͂炴�肯��v�̉̂ɗ�������ꂽ�A�������������̎p�Ƃ��Ẳ��������ƁA���̏��𑛂����镗�̉������B������̃t�B�M���[���̂͂��炫����āA�u���ɂ��ցv�̐��E������������B����́A�t�B�N�V���i���ȉ̕���̐��E�ł���A�����ɃC���������A���ȃJ�~�̐��E�ł��������B�������������Ɖ������B���́A�u���`�́v�єV���ۊw�A���Ȃ킿�u�t�B�M���[���Ƃ��Ă̚F�v���\�������̃G�������g���߂����āA��̍�Ƃ̏����̂��߁A�����œ�̑f�ނ��N�W���Ă����B��̑f�ނƂ́A�����ւ́u�����̐���v�Ƌ�S�����́u���R���̉��v�ł���B
�@�����ւ́u�����Ёv�ŁA�u�����ɗ삠��△����v���������邽�߁A�A�V�����E�o�j�E�A�p���剤�ɏ����ꂽ����k���̘V���m�i�u�E�A�w�E�G���o�̑̌�������Ă���B�ނ́A������̕����i�S�y�̔ɍd�M�������Ē������ꂽ�A���G�Ȟ��`�̕����j���Î����Êς��邱�ƂŁA���́u���m�̐���v���߂���^�������o�����Ƃ����B����ƁA�u���̒��ɁA�������Ȏ����N�����B��̕��������l�߂Ă��钆�ɁA���������̕�������̂��āA�Ӗ��̖������̐��̌����Ƃ��������Ȃ��Ȃ��ė���B�P�Ȃ���̏W�肪�A�Ȃ��A�����������Ƃ��������Ӗ��Ƃ�L���Ƃ��o����̂��A�ǂ����Ă�����Ȃ��Ȃ��ė���B�V��i�u�E�A�w�E�G���o�́A����ď��߂Ă��̕s�v�c�Ȏ��������āA�������B���܂Ŏ��\�N�̊ԓ��R�Ǝv���Ċʼn߂��Ă������Ƃ��A�����ē��R�ł��K�R�ł��Ȃ��B�ނ͊Ⴉ��̗������v�������B�P�Ȃ�o���o���̐��ɁA���̉��ƈ��̈Ӗ��Ƃ�L��������̂́A�����H�@�����܂Ŏv�����������A�V���m���S�O�Ȃ��A�����̗�̑��݂�F�߂��B���ɂ���ē��ׂ��Ȃ���E�r�E���E�܁E�������A�l�Ԃł͂Ȃ��悤�ɁA��̗삪����ׂ�̂łȂ��āA�ǂ����ĒP�Ȃ���̏W�����A���ƈӖ��Ƃ�L���Ƃ��o���悤���B�v
�@��S�����́u���Ɠ��������R���̉��Ɖ\���̓��v�ŁA���q�����{�̒�̘@�̉Ԃ̊J�����������A�ʐ�̉͌��Ō������̉Ԃ̊J�����Ɏ����X�����u���̂悤�Ȑ̖̂��̂悤�Ȏv�o�v�����A�u�ق̂��ȉ��ւ̓��ۂ͍��̎����������Ȃ��B���͍��͋��R���̒a���̉������Ƃ��Ă���B�v�u���R���͋��ق�������B�v�Ə����A����ɁA�����̓��̕s�R�I�Ȗ��f�⏗�̍����ւ̂�������́u���ׂĂ��ߋ��ɒ���ł��܂����v���A��̖؍҂̓������ւ̑��ł����ЂƂ�k���Ȃ���A�u��������Ǝ��͉��������Ƃ���։^��Ă��܂��B�������܂ꂽ���������Ɖ����Ƃ���ցB�����ł͂܂��\���\�̂܂܂ł������Ƃ���ցB�v�Ə����Ă���B
�@�܂��A��S�́u���{���̉��C�v�ŁA���@�����[�������u����̃V�����X�i���R�j�̏����ȑ̌n�v�ł���Ƃ��A�܂����C�̗L����u�N�w�I�̔��v����������Ƃ������A�u���͂����R�ɑ��Ĉ��̓N�w�I���ق��������Ȃ��҂́A���C�̔��𖡓����邱�Ƃ͏o���Ȃ��ł��炤�B�v�Ə����A�w���R���̖��x�ł́A���@�����[���u��ƌ�Ƃ̊Ԃ̉��C��̈�v�v���u�o�q�̔��v�ɂ��Ƃ������Ƃɂ��ӂ�A�u���R�������Ɖ��̖ڂ����A���t�ƌ��t�Ƃ̍s������Ƃ��Ď��̌`���̒��֎����邱�Ƃ́A���̌ۓ������ɏے������邱�Ƃ��Ӗ����Ă��B�v�Ə����Ă���B
�@�����āA���̓�̘_�e�ŁA�Ƃ��Ɍ���M�Ɍ��y���Ă���B�w���R���̖��x�ł́A�u�������āu����v�̐M�̒��ɑ؍݂��Ă����R���̈Ӌ`���ʖ������Ղ��|�p�`���Ƃ��Č��������邱�Ƃ͎��̗͂̂䂽��������Ă�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�v�ƁB�u���{���̉��C�v�ł́A�x�m�J�������p���āA�u���C�͉�����̗V�Y�����疳���l���ƒf�肷��̂͗]��ɐ����ł���B��X�͂ނ���j����閽�̎���ɂ�����u����v�̐M��]�������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�x�m�J�����u����̕فv�Ɂw����̖��p�l�̐S�̗͂̋y�тɂ���ʁx���Ƃ�����w���ׂĕ���������ӂ͂��݂Ɏ���Ȃ�o�Â���̂́A���Ȃ炸�����ĕs���̖��p���Ȃ����̂Ȃ�x�Ɖ]�Ă��B�v�ƁB�j
�@
���v���t�B�[����
�����I���i�Ȃ��͂�E�̂肨�j1950�N�㐶�܂�B���Ɍ��ݏZ�B��N���̂ɏ����ꂽ�a�̂̈Ӗ��������ł���̂͂��������Ƃ��B�ł��A�{���Ɂu�����v�ł��Ă���̂��B�����Ɂu�Ӗ��v�Ȃǂ���̂��B�����������t���g���ĉ�����`�B���邱�Ƃ��̂��̂��s�v�c�Ȍ��ۂ��Ǝv���B
Web�]�_���u�R�[���v08���i2009.08.15�j
���F�ƃN�I���A����11�́@�єV���ۊw�̉ۑ�i�����I���j
Copyright(c) SOUGETUSYOBOU�@2009 All Rights Reserved.
|
| �\���i�ڎ��j�� |