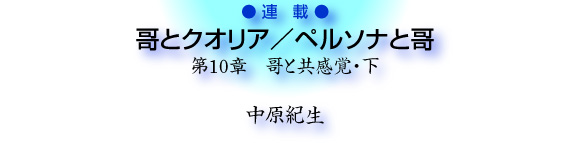|
|
|
Web評論誌「コーラ」 |
|
■創刊の辞 ■本誌の表紙(目次)へ ■本誌のバックナンバー ■読者の頁/ご意見・感想 ■投稿規定 ■関係者のWebサイト ■プライバシーポリシー |
|
<本誌の関連ページ> |
|
■「カルチャー・レヴュー」のバックナンバー ■評論紙「La Vue」の総目次 |
Copyright (c)SOUGETUSYOBOU |
|
|
|
■クオリアの交響、あるいは言語の生成
レヴィ=ストロースは、『みる きく よむ』(竹内信夫訳)に収められた「言葉と音楽」の章で、忘れられた十八世紀の思想家、ミシェル=ポール=ギー・ド・シャバノンの音楽理論を紹介しています。
いわく、音楽はわれわれの感覚器官が感受するさまざまな印象を模倣するのではなく、さらに正確に言えば、われわれの感情を表現するのでもない。旋律だけに還元された音楽は、怒りや激情を表現することはできない。音楽が直接訴えるのはわれわれの感覚に対してであって、それ以外の何ものでもない。音はそれ自身のうちにどんな意味ももっていない。ひとつひとつの音はほとんど無に等しい。それは意味をもたないばかりか、固有の性格ももたない。
そして、「シャノバン──彼は蜘蛛に興味をもっていて、どういう音楽に反応するかをみるために蜘蛛にヴァイオリンの曲を弾いて聞かせたほどだ──は、万物照応の原理を大きく広げるような、ひとつのみごとなイメージを提唱している」、とレヴィ=ストロースは語ります。
レヴィ=ストロースは、シャバノンの音楽に関する反省的思考のうちに、ソシュールの構造論的言語学を予告する思考(「継起性、それが旋律である。同時性、それが和音である」というシャバノンの説は、ソシュールの「継起性の軸」と「同時性の軸」の関係を先駆的に定式化していた)を、また、自身の構造人類学に先行する思考(同様に、「古代人の想像力によって創造され、虚構に富み、幻想のみごとな産物で輝いていたこの詩的世界[神話]は、〈音楽〉の与える魔術的魅力のために用意された領域であった」は、『裸の人』の最終章に提示された命題を支持している)を、それぞれ見てとります。
さらに、「言葉と音楽」の章につづく、(異なる存在次元にある音と色の性質の相同性をめぐる)「音と色」の章では、「シャノバンが鼻音節について次のように書くとき、百年も前に、あたかも彼はランボーの詩の音的構造を記述しているかのように思えてくる」として、「これらの不実な(ingrats)音は、いっそう煌くような音[母音]と融合して、言語の陰影を、質料を、明暗のようなものを作りあげている」というシャノバンの言葉を引用するのです。
レヴィ=ストロースがいう「ボードレール的万物照応」、すなわち「諸感覚のあいだに反響する照応関係」(クオリアの交響)とは、『悪の華』に収められた「万物照応 Correspondances」における比喩表現(「ある香りは、子供の肌のようにさわやかで、/オーボエのようにやさしく、牧場のように緑」阿部良雄訳)が指し示す特異な感覚現象、つまり「共感覚 synesthesia」のことにほかなりません。
この「万物照応の原理」を、シャバノンが、人間の感性にだけ関与する単なる物的現象ではなく、個々の物的現象を比較・結合する精神の知的操作に依存するものとしてとらえ、二十世紀の構造主義の思考にもつながるものへと拡張していったこと。とりわけ、ランボーの詩、たとえば「母音 Les Voyelles」によって表現された、「色聴」と呼ばれる共感覚的現象(「A黒、E白、I赤、U緑、Oブルー、母音よ、/いつか君たちの誕生の秘密を語ろう」鈴村和成訳)のうちに見え隠れする、言語誕生の秘密と密接不可分な「音的構造」の実質を、ランボーより百年も前に記述していたこと。
レヴィ=ストロースが語る、このようなシャバノンの先駆性とは、共感覚こそが言語生成の基盤をなす現象であること、したがってまた社会の構造の基底に潜んでいる体験であることを、音楽という、ただ感覚に直接訴えるだけで、それ自身のうちにいかなる意味をもたない具体的な事象に即して明らかにしたことにある。先の文章を、私はそのように読解しました。(そもそも、『みる きく よむ』という書名自体が、そのことを示唆しているのではないかと思います。)
それでは、共感覚から言語が生成するプロセスとはいったいどのようなものなのか。この問いは、貫之現象学における二つの根本問題のうちの一つ、「人のこころ」を種として「よろづ=クオリアの宇宙」が「詞」へと生長していくプロセスはどのようなものか(西田現象学における表現でいいかえると、「言語に云い現すことのできない赤の体験」のような、言葉で語りえぬものがいかにして言葉で語れるようになるのか)に対する直接の答えになりうるものです。いま一つの問題、そもそもなぜ「詞」が他者に伝わるのか(同様に、直接に結合していない私と他人が、言語や文字といった表現を通じて、また音や形といった物理現象を手段として、なぜ相理解できるのか)という問いに間接的に答えるものでもあります。これらのことに関連して、次に、ある神経科学者の仮説を引きます。
■共感覚的ブートストラッピング説
ラマチャンドランは、『脳のなかの幽霊、ふたたび――見えてきた心のしくみ』(山下篤子訳)の第4章「紫色の数字、鋭いチーズ」に、「共感覚は脳内で神経基盤が発見されうる感覚現象であって、その発見が、もっと把握しにくい心の諸側面、たとえばメタファーを理解する足がかりになる」と書いています。
ラマチャンドランによると、共感覚は、脳内のニューロン結合の混線やその過剰結合によってもたらされる現象です。これが、側頭葉の紡錘状回と呼ばれる(色彩情報を処理する領野(V4)と数字の視覚的外形を表象する領野が隣接している)場所に生じると、アラビア数字の5は赤、6は緑といった、外形にもとづく「低次の共感覚」がもたらされます。また、より高次のTPO(側頭葉・頭頂葉・後頭葉の接合部)に近接した角回と呼ばれる場所(左半球の角回は、抽象的な数の概念を表象すると推測されている)の近辺に生じると、月曜は赤、火曜は藍色といった、外形ではなく数値的概念にもとづく「高次の共感覚」がもたらされます。さらに、これが脳全体にわたって大規模に生じると、芸術家や詩人、小説家に共通する技能、つまりメタファーをつくる技能をもたらします。この「宇宙でもっとも複雑な構造物」とされる脳がもつメタファーをつくる能力とは、「無関係なものごとを結びつける能力」のことです。
(ここでいわれる「メタファー」とは、単なる言語表現の技法、たとえば「声の寒さ」といった比喩表現のことだけではありません。ラマチャンドランがいう「メタファー」は、文章表現のレトリックである狭義のメタファーを超えて、抽象的概念の構築や昆虫の擬態といった事象も含めた、およそ森羅万象にわたる認識と存在をめぐるはたらきにまで拡張することが可能なものなのであって、むしろ「アナロジー」と呼んでいいものではないかと思います。)
ラマチャンドランは、こうした共感覚は一部の人の脳だけに起きることではない、と主張します。その実例として、丸みのあるアメーバのような図形と、とがった角のあるぎざぎざの図形を示し、これらの形は火星人が使うアルファベットの最初の二文字、「キキ(kiki)」と「ブーバ(booba)」なのだが、そのどちらがキキだと思うかとたずねると、(英語圏の人だけでなくタミール語族の人々も)ほぼ全員、ぎざぎざの図形がキキだと答えた実験結果を紹介し、その理由を次のように述べています。キキの図形には鋭い屈曲があり、脳の聴覚皮質に表象される「キキ」という音も鋭い屈曲(抑揚)をもつ。脳は、触覚や聴覚、視覚といった異なる感覚にまたがる「共感覚的抽象化」を実行して、ぎざぎざという共通の属性を認識し、それを抽出し、両者はともにキキであるという結論に到達するのだと。
ところが、これと同じ実験を、左半球の角回に損傷がある患者に試してみると、うまくできない。なぜかというと、角回は、触覚・固有感覚に関与する頭頂葉と、聴覚に関与する側頭葉、視覚に関与する後頭葉が交わる部位(TPOの近傍)に、「さまざまな感覚モダリティを収束し、モダリティに拘束されない抽象的な、周囲の事物の表象をつくるために、戦略的に配置されている」からで、これが抽象化と呼ばれる属性の原始的なはじまりである。この能力は、ヒトが「樹上で生きのび、手でものをつかみ、枝から枝に飛び移るのを助ける」ために進化した。そして、こうしたクロスモーダルな抽象化に従事する能力がいったん発達すると、その構造が、人類の得意とするメタファーやそのほかのタイプの抽象化の「外適応」になった。
以下、ラマチャンドランの話は、言語の起源とその進化にかかわる「共感覚的ブートストラッピング説」へと進んでいきます。その要点は、次のようなものです。
第一。「ブーバ・キキ」の例に見られるように、物体の視覚的外形と聴覚皮質の聴覚表象とのあいだには非恣意的な共感覚的対応が、いいかえれば「共感覚的なクロスモーダルの抽象化」が、あらかじめ存在している。同様のことが、紡錘状回の視覚領野と発声・構音にかかわるブローカ野とのあいだにもなりたっている。さらに、手に関与する領域と口に関与する領域とのあいだにも、運動から運動へのマッピング(共同運動[シンキネジア])がなりたっている。「これで三つのものがあるべきところにおさまりました。第一は手から口、第二はブローカ野の口から紡錘状回の視覚的外形と聴覚皮質の音調、そして第三に聴覚から視覚、すなわちブーバ・キキ効果です。この三つが一緒に働くと、相乗的なブートストラッピング効果が生れ、それがなだれのように作用して、原始的な言語の誕生にいたります。」
第二。言語がもつシンタックス(統語)の階層構造、たとえば、「彼は、私が彼の妻と情事をもったことを彼が知っていることを私が知っていることを知っている」のような階層的な入れ子構造は、道具使用からきたのかもしれない。「一片のフリント石をヘッドにしたて(第一段階)、それに柄をつけ(第二段階)、その全体を道具あるいは武器として使う(第三段階)。この機能と、名詞句のセンテンスへの入れこみは操作的によく似ています。ですから、ひょっとするともともとは手の領域で道具使用のために進化したものが、いまでは外適応してブローカ野にとりいれられ、階層的な入れ子など統語の諸面に使用されているのかもしれません。」
第三。こうした領域間のマッピングは、口腔顔面領域の動きに関するミラー・ニューロン(自分が舌を突き出したり、唇をすぼめたりしているときだけでなく、だれかがそうしているのを見ているときにも発火するニューロン)によって成立しているのかもしれない。「この能力は、ある程度まで生得的なものです(生れてまもない赤ちゃんに舌を突き出して見せると、赤ちゃんはそれをまねて舌を突き出します)が、より複雑な三者の合致、すなわち唇の動きを読みとるのに必要な、[耳から聞こえる]音素の音と、[ほかのだれかの]唇や舌の外観と、[口腔内の筋肉にあるセンサーによって感じられる]唇や舌の位置[固有感覚]との合致は、おそらく子ども時代に獲得されるものと思われます。これらのニューロンが、目で見て発声をまね、それを耳から聞こえる音と合致させることによって、共通の語彙の発達に重要な役割をはたしてきた可能性は大いにあります。」
■二つの備忘録
ラマチャンドランの仮説が、科学者たちの間でどのような評価を受けているのか、また受けるに値するものなのかどうか、残念ながら、そのことを判断するための知識と経験が私には欠けています。ですから、ここでは、「言語起源の共感覚的ブートストラッピング説」の是非をめぐる素人談義は禁欲して、(また、歌の進化における外適応、歌におけるミラー・ニューロン、等々の妄想めいた思いつきを書き連ねることは自粛して)、私が興味をもったことを二つだけ、後の議論につなげるための備忘録として書きつけておきます。
その一は、ラマチャンドランの議論のなかに、しきりに「三」の数字が登場してきたことです。原始的な言語の誕生を述べた箇所で言及される「三つのもの」、統語のツリー構造の起源をめぐる三つの段階、そして共通の語彙の発達に重要な役割をはたす「より複雑な三者の合致」。説明と論証を抜きにして、私の直観が告げることを書きとどめておくならば、第一の「三」は換喩(メトニミー)=指標記号(インデックス)に、第二の「三」は提喩(シネクドキ)=象徴記号(シンボル)に、第三の「三」は隠喩(メタファー)=類似記号(イコン)に、それぞれ関連づけて考えることができます。このことについては、前章で述べた貫之現象学の三層構造、「共感覚/身の伝導体/詞の伝導体」のうち、最後の「詞の伝導体」にもかかわる事柄ですので、次節以下で概観する、ある言語哲学者の議論を通じて、「身の伝導体」から「詞の伝導体」へと向かう若干の手がかりを得た後にとりあげたいと思います。
その二は、視覚と聴覚の間、そして異なる運動の間になりたつ共感覚的対応から、言語の起源とその進化が説明できるとして、では、そのもとになる感覚や運動にともなうクオリアと言語との関係はどう考えればいいのかということです。この点については、『脳のなかの幽霊、ふたたび』の第5章「神経科学──新たな哲学」で次のように論じられています。
ラマチャンドランによると、クオリアは、感覚表象が高次の「メタ表象」(表象の表象)に転換される過程で獲得されます。このメタ表象は、「脳のなかでクオリアに満ちたスクリーン映像を見ている小人」(ホムンクルス)そのものであるか、あるいは、進化的に新しく生じた脳構造(感覚表象に関する計算を実行する「やや自動的なプロセスをより経済的に記述するために人間において進化した「寄生性の」第二の脳」)によってつくりだされたかのどちらかだ。ラマチャンドランは、そう述べています。
ラマチャンドランはまた、メタ表象を生みだす脳の部位として、言語の諸面と結びついた部位、具体的には、(情動的な重要性を判定する)扁桃体、左のTPOの周辺に位置する角回やウェルニッケ野などの構造、「意図」に関与する前部帯状回を候補にあげ、それらの脳部位が、内省的意識や自己感、自己認識(セルフ・アウェアネス)ともかかわっていることを指摘します。
このことは、クオリアと自己が、ともに特定の生物学的機能をはたすために自然淘汰を通して進化してきたものであって、単なる神経活動の副産物(随伴現象)ではないということを示しています。すなわち、「クオリアと自己は同じ硬貨の両面」なのであって、どちらか片方だけをもつことはできない。「特別な神経回路を使って感覚表象や運動表象のメタ表象を生みだす能力──言語を促進し、また言語によって促進される能力──が、本格的なクオリアの進化にも自己意識の進化にも不可欠だったのかもしれません。…クオリアを経験する自己をともなわない自由な立場のクオリアをもつことは不可能ですし、いっさいの感情や感覚を欠く孤立化した自己をもつことも不可能です。」
クオリアと自己意識と言語の関係をめぐるラマチャンドランの議論については、いずれ、貫之現象学における「強い私的言語」をめぐる問題群に取り組む際、立ち帰って考察する必要があるだろう私は考えています。ここでは、クオリアと言語の関係を考えるときに素通りすることのできない決定的なアイデア(強いて言葉にすると、「クオリアの宇宙の縮減によって言語が誕生した」)が織り込まれたパースの文章を、後の議論のための素材として蒐集しておくにとどめます。
■深層のロゴスとしての「思ひ」
丸山圭三郎著『言葉と無意識』に、「〈パトス〉と呼ばれる〈深層のロゴス〉すなわち〈情念という名の言葉〉は、大和ことばの〈思ひ〉に近い。」という文章が出てきます。どういうことかというと、丸山氏は、まず、言葉(=ロゴス)には、「既成の事物や概念にラベルを貼るだけの日常的なルポルタージュ機能」と「存在喚起機能としての根源的差異化の運動」との二つのはたらきがあると指摘します。しかも、この二つは、実は一つです。
丸山氏は続けて、パトスは英語でいうと「ペーソス」(悲哀)だが、これもまたロゴス以前の自然的感性ではあり得ず、これこそ身(み)の深部におけるロゴスの下意識的な働きそのものなのであって、ホモ・ロクエンス(語るヒト)のみが知る「ユーモア」のカウンター・パートなのだ(動物は貰い泣きもせず、思い出し笑いもしない)と書き、こうした深層のロゴス(言葉)としてのパトスをめぐって、小倉百人一首のうち二十余首に現われた「思ふ」という言葉に注目するのです。
(深層のロゴス=言葉としての「思ひ」は、「かげ」でもある。「かげ」は光であり、同時に不可視の闇である。それは、現身の分身としての「詞」である。「影見れば波の底なるひさかたの空漕ぎわたるわれぞわびしき」の歌において、水面に映る「影」とは仮名文字のことで、そこに表出される「思ひ」とは、およそ言葉を操るもののうちに宿る根源的な感情(ペーソス)のことなのであった。)
こうしたロゴスとパトスの(垂直方向の)関係をめぐる丸山氏の議論は、やがて、ソシュールのアナグラムと定家の本歌取りとの妖しい関係、アナグラム的ポリフォニー性の極致としての謡曲の声や能管の音色がもつモノフォニーの幽玄、等々をめぐる魅力的な話題を経て、(丸山氏によって、制度化された表層言語としてとらえられた)ラングと、(同様に、そのような意味でのラングに先立つ象徴性の活動として、「音声言語[パロール]に先立つアルシ・エクリチュール(音声の代理ではない根源的文字、トーテム記号など)やコードなき舞踊としての身振り」とも深く関わる深層の言葉としてとらえられた)ランガージュとの、精確にいえば、「ラング化されたランガージュ」と「ラング化されないランガージュ」との関係をめぐる議論の上に重ね描かれていきます。
このようにして、丸山氏は、「欲動/深層のロゴス=パトス/表層のロゴス」の三層構造(もしくは、「無意識/潜意識/下意識/表層意識」の四層構造)を図式化し、これにラカンの「現実界/想像界/象徴界」を対応させるのです。
■浄化と昇華、二つの円環運動
この三層構造のうちには、二つの円環運動が埋め込まれています。一つは、表層(ラング化されたランガージュ)と深層(ラング化されないランガージュ)との関係にかかわるもので、いま一つは、表層・深層にまたがる広義のランガージュ(ランガージュによって有意味的にゲシュタルト化された「コスモス」)と、丸山氏がいう意味での無意識(ランガージュの産物でありかつランガージュ以前の「カオス」)との関係にかかわるものです。
(丸山氏がいう「身分[みわ]け」とは「動物一般がもつ生の機能による種独自の外界のカテゴリー化」、たとえば「食べられるもの/食べられないもの」の本能的な弁別=差異化のことであり、「身分け構造」は「身の出現とともに外界が地と図の意味分化を呈するユクスキュル的な〈環境世界〉」を意味する。ところが、このような本能に破綻をきたした人間は、シンボル化能力としての言葉によって生み出されるもう一つのゲシュタルトを過剰物としてもってしまった。これが第二の分節の結果生ずる「言分[ことわ]け構造」であり、それは広義の言葉としてのランガージュの世界、すなわちコスモスまたは文化を意味する。「〈コスモス〉とは、人間の存在喚起機能であるランガージュによって有意味的にゲシュタルト化された時・空の世界、つまりは〈言分け構造〉のことであり、生のエネルギーが言葉によって絶えず図と地に二分されながらも、本来的にはとどまることのない〈コードなき差異〉が戯れる流動的文化である」。
斎藤慶典著『知ること、黙すること、遺り過ごすこと──存在と愛の哲学』によると、「身分け=身体的・知覚的分節化」と「言分け=言語的分節化」との間には、フッサールが「一方的基づけ」と呼んだ関係が、すなわち、「一方(言分け)はみずからの存立のために他方(身分け)による支えを必要とするが、ひとたびその支えのもとに一方(言分け)が存立すると、それ(言分け)はみずからを支えている他方(身分け)を自身の内に包摂し・統御する、という関係」が成立している。「言分け」は「身分け」による基づけなしに存立しえないが、「身分け」は「言分け」なしでも存立しうる。しかし、そのことを「言分け」なしに言うことができない。)
第一の、表層のロゴスと深層のパトスとの間の(精確には、「今、ここ」で、表層意識と下意識との間で発生している)円環運動に関連して、丸山氏は次のように書いています。
また、第二の、コスモスとカオスとの間の(精確には、「今、ここ」で、潜意識と無意識との間で発生している)円環運動をめぐって、次のように語ります。
さて、以上、長々と『言葉と無意識』の議論を引いてきました。私がここで、「欲動/深層のパトス/表層のロゴス」もしくは「カオス/ノモス化されないコスモス/ノモス化されたコスモス」の三層を、貫之の「自然/身=心/詞」もしくは「よろづ/人のこころ/ことのは」に重ね合わせて参照していることは、いうまでもありません。
もちろん、「既成の事物や概念にラベルを貼るだけの日常的なルポルタージュ機能」をもつ表層のロゴス=言葉と、「存在喚起機能としての根源的差異化の運動」とともにある深層のパトス=詞とは、たとえ両者が実は一つのものであるにせよ、やはり決定的に異なる場所に住まいしています。とはいえ、しかし、丸山氏の、ある時代の陰影を帯びた語り口でもって提示された概念群をうまく使いこなすことができるならば、貫之現象学、俊成系譜学、そして定家論理学をめぐるこの論考に、際立った広がりと深みをもたせることができるのではないかと思うのです。
たとえば、貫之現象学における「いひいだす心」は、「欲動=無意識=連続体=(ランガージュ以前の)カオス」のうちに根ざしているのであって、実は、富士谷御杖の「なぐさめむとする心」のはたらき(「表現」によるカタルシス)よりもはるかに根源的な運動(「表出」による昇華)につながるものだったのではないか。そして、俊成系譜学にいう「歌といふものなからましかば、色をも香をも知る人もなく」は、「パトス⇒表層のロゴス」(カタルシス)と対になる運動、すなわち「ロゴス⇒深層のパトス」(歌の道の深き心の伝承)をいうものだったのではないか。さらに、「カオスのコスモス化」(昇華=無意識の解放)と対になる運動、すなわち「ランガージュによるカオスの産出」(無意識の創造)こそ、言葉が見る夢としての定家論理学の世界へとつながっていく、もう一つの根源的な運動だったのではないか、等々。
(丸山氏の文章に二度でてきた「今、ここ」が指し示す場所の違いを見極めながら、貫之歌論の三層構造を、ラカンの三体ならぬ三界、「現実界/想像界/象徴界」に接続する。あるいは、身分け構造と身の伝導体、言分け構造と詞の伝導体を架橋しつつ、貫之現象学による俊成系譜学・定家論理学の「基づけ」関係を腑分けする、等々。)
これらの論点については、いずれしかるべき箇所にさしかかった際に考察することとして、ここで、(感覚=感情の論理に支えられた)身の伝導体から詞の伝導体へという、当面の作業に立ち帰ります。
★プロフィール★
中原紀生(なかはら・のりお)1950年代生まれ。兵庫県在住。千年も昔に書かれた和
歌の意味が理解できるのはすごいことだ。でも、本当に「理解」できているのか。そ
こに「意味」などあるのか。そもそも言葉を使って何かを伝達することそのものが不
思議な現象だと思う。
Web評論誌「コーラ」07号(2009.04.15)
<哥とクオリア>第10章 哥と共感覚・下(中原紀生)
Copyright(c) SOUGETUSYOBOU 2009 All Rights Reserved.
|
| 表紙(目次)へ |