|
|
|
Web評論誌「コーラ」 |
|
■創刊の辞 ■本誌の表紙(目次)へ ■本誌のバックナンバー ■読者の頁/ご意見・感想 ■投稿規定 ■関係者のWebサイト ■プライバシーポリシー |
|
<本誌の関連ページ> |
|
■「カルチャー・レヴュー」のバックナンバー ■評論紙「la Vue」の総目次 |
Copyright (c)SOUGETUSYOBOU |
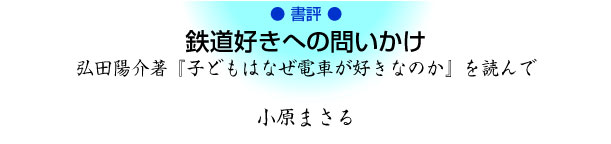
|
|
(本文中の下線はリンクを示しています。また、キーボード:[Crt +]の操作でページを拡大してお読みいただけます。)
1. 鉄道好きへの哲学的なアプローチ
この本は、子どもはなぜ電車が好きなのかを問う本である。著者は、自分の子どもが「でんしゃ」と声を上げるのを見て、「なぜ子どもは電車がこんなに好きなのだろう」と思ったという。教育哲学の研究者である著者は、その哲学的な知見を生かして、著者自身が抱いたこの疑問への答えを探ろうとする。このような試みは、著者が言うように、これまであまりなされてこなかったことであろう。
この本がどのような読者を対象としているかは明確ではないが、鉄道好きの子どもを持った親の視点からこの課題に取り組んだ本であり、そしてそのアプローチの仕方が教育哲学の立場からのものであることが、この本を独特なものにしていると思う。鉄道を愛好している人は、なぜ自分が鉄道好きになったのかという点に関心があるだろうし、自分の子どもは鉄道好きのようだと感じている人も多いだろう。おそらく、この本を手に取るのは、こうした大人たちということになるだろう。この本では、西欧の哲学者の本も引用されているので、それが読者に難解な印象を与えるかも知れない。しかし、自分の子どもの目を通して鉄道を見ようとする著者の姿勢が、やや難解な部分がありながらも、この本を読みやすいものにしていると思う。
私自身も大の鉄道好きであるが、鉄道好きへの哲学的(精神分析学も含まれる)アプローチがどう展開されているのかに興味を持ったので、この本を読んでみることにした。
2. 鉄道が好きになるきっかけ
この本のはじめに著者は、ある玩具メーカーが実施した保護者対象のアンケート調査の結果に触れる。アンケートの対象は、主に十二歳までの子どもを持つ親で、子どもが好きな乗り物を尋ねるものである。その結果を見ると、乗り物の中で電車はトップなのである。子どもに身近な乗り物は自動車ではないかと想像してしまうから、かなりの差をつけて電車好きが多いことに、読者の多くは意外な感じを持つと思う。サンプル数は全体で388人なので、その信頼度には心配な点もあるが、ともかくこのアンケートの結果から著者は、数ある乗り物の中でも鉄道が子どもに愛されていること、またその愛好のピークは五歳頃までで、やはり男の子の方が鉄道好きであることがわかったとして、それらのわけを探ろうとするのだ。
第二章ではおもちゃが、そして第三章ではDVDや絵本が、実物の鉄道と相まって鉄道好きを深めるものとして言及される。そして第四章から第六章で行われるのは、実際の鉄道に出会う時に子どもの心の中で起こることについて、哲学者の理論などを参照して説明する試みである。第七章では、子どもの「ごっこ遊び」と『銀河鉄道の夜』の主人公の話を通して、子どもが電車や機関車に「なる」ことについて触れる。第八章では、電車には「顔」があること、そして『機関車トーマス』を例に、鉄道車両などへの「性格付与」について述べられている。
この中でまず興味深いのは、第四章と第五章である。親と出かけた時に小さな子どもは電車に出会うが、大きな音と共にやってくる電車は、きっと最初は子どもにとって怖いものであるはずだろう。著者の言葉で言えば「驚異の怪物」である。しかし、その凄まじさゆえに子どもは強烈な「生の体験」をすると著者は考えるのだ。そしてその怪物を子どもがなぜ好きになっていくのかを、著者は第五章で、フロイトの衝撃の克服の理論によって説明しようとする。そしてまた著者は。鉄道に出会った時に子どもの心の中に、その場との「緊張感による一体感」が生まれるとするのである。
第六章で著者は、クラーゲスという哲学者の「リズム体験」に関する文章を引用する。それはリズム体験が「緊張を解いて夢見心地にさせ、ついには全く寝入らせてしまう」というものである。先の緊張感の話とは逆の説明のようだが、著者は、このクラーゲスが「(リズムによって人は)自己を取り巻く世界と一時的に融合することができる」と言っているとして、やはり電車がもたらす「一体感」について説明するのである。著者が引用した『リズムの本質』を読んでみると、確かにクラーゲスは、鉄道車両の車輪の「機械的な拍子音」を聞いていて「うとうとしてしまう」と書いている。しかし、緊張を解くのは車輪の拍子そのものではなく、拍子と不可分に結びついている「運ばれていることの体験」だとも言っている。これはとても興味深い指摘だと思う。著者はこのことには触れていないが、この指摘もまた「一体感」を説明できるものだろうから、少しもったいない気がする。
同じ「一体感」の説明でも、第七章はわかりやすい。著者は、鉄道の「ごっこ遊び」の中での子どもの様子について記述する。著者は、子どもが、初めは電車になり、車掌になり、踏切になるというように「自由自在に何にだってなってみせる」と書いている、この記述にはとても共感するものがあるし、「子どもは空想のままに何にだってなれるのである」という指摘にも同感である。ここで展開されるのは、いわば想像力による一体化についてであろう。著者がとりあげる『銀河鉄道の夜』の話は、その意味では、もってこいの題材である。さらに著者は、蝶と一体化した少年時代のベンヤミンの話についても言及するのである。
いずれにせよ第四章から第七章までには、「一体感」をキーワードとする、ひとまとまりの哲学的アプローチがあると思う。それは、「外側と内側、自分と他人の区別がまだはっきりとしない」時期(著者によれば二歳頃まで)の子どもが電車に出会った時、子どもの心がどう動くのかを、哲学者などの理論をかりて想定しようとするものである。そしてそれは、「子どもは、私たち大人と違う世界を生きている」ということを前提とした分析の試みだと言えよう。
実際に著者が言うような形で、小さな子どもたちが「一体感を楽しむ」ことになっているかどうかは想像するしかないが、これらの説明は、この本の表題『子どもはなぜ電車が好きなのか』という問いに答える重要な部分であろう。
3. 「所有原理」と「関係原理」
もう一つの哲学的なアプローチは、「所有原理」と「関係原理」という、二つの原理によって鉄道好きを検討する試みである。これらの原理は、フランスの精神分析学者であるラカンに依拠して精神科医の斎藤環氏が考えたものである。著者はまず第九章で、鉄道好きにおける「コレクションの欲望」について、自分の子どもを例にあげて説明する。
著者の子どもは「二歳頃から電車の名前を覚え始めた」と言い、三歳頃には「鉄道のおもちゃや写真絵本、カードを見て、その名称と形状をコレクションするかのように覚えていった」と言う。また著者は、自身の子どもの頃のガンダムのプラモデルなどの収集について触れ、「すべてを把握し自分の手元に集めたいと言う欲望が男の子にはあるのではないか」と言うのである。そして、このようなコレクションは男の子のものであり、「女の子は、集めることへの執着があまりないように思われる」とする。
著者は「所有原理」が「持ちたいと願うこと」だけではなく「対象を視覚化し、言語化し、さらに概念化してこれを意のままに操作しようとする過程すべて」であるという斉藤氏の文章を引用して、「これはまさに先に見た子どものコレクションの欲望の定義そのままになっている」とする。そしてそれによって、なぜ言語を用いだす「三〜五歳以上」の「男の子や男性に鉄道好きが多いかをうまく説明できるように思われる」とするのである。
つまりこの原理は、例のアンケートの結果が示す「鉄道好きは男の子に多い」ということを説明するものなのである。著者によれば、子どもが「(二歳から三歳にかけて)言葉の世界へ移行していくと」、子どもの鉄道の楽しみ方は、「一体化するというよりも」、「支配・操作の楽しみ方」になっていくという。そして、「この支配・操作の楽しみ方とは、男性の心理のベースとなる所有原理に基づくものであり、一人で黙々と遊ぶことによって深められる」としている。
この本における二つの哲学的なアプローチは、著者が「子どもの鉄道好きと子どもの発達段階」についてまとめたことに対応してることがわかる。「一体感」をキーワードにするものと「所有原理」によるものである、これら二つのアプローチは、それぞれ、おおよそ二歳頃までと、それ以降の年齢における鉄道好きについて説明するものなのである。多くの人にとって、二歳以前の自分が鉄道好きであったかどうかの記憶は明確ではないだろう。だから、「一体感」についての著者の説明に関しては実感が湧かないと思う。しかし、もし鉄道好きの人が「所有原理」による説明を読むならば、自分の中に思い当たることがあると感じるだろう。斎藤氏の理論は説得力のあるものだと思うし、著者がこうした原理を鉄道好きに当てはめて考えてみたことには、大きな意味があると思う。私自身は、大変興味を持って読んだのである。
4. 超えるべきものとしての「鉄ちゃん」
第十章でも、これらの原理は鉄道好きのメンタリティーを示すために使われている。最終章である第十章には、「「鉄ちゃん」を超えて」というタイトルがついている。つまりこの本では、「鉄ちゃん」は超えられるべきものと位置づけられているのである。著者はこの章の冒頭で、「ある程度子どもが大きくなってくると、鉄道の楽しみは「知る」ことや「集める」ことになっていく」とし、「その楽しみは所有、つまりコレクションの欲望に基づいたものである」とする。そして「いわば、「鉄ちゃん」への一本道がそこに拓かれる」と言うのである。つまり著者の中では、「鉄ちゃん」と呼ばれる人たちは、「所有原理」による欲望によって鉄道を楽しむ人たちということになる。
著者は、石井研道という人による1902年発行の『少年工芸文庫』の第一巻「鉄道の巻」から長い文章を引用をする。この「鉄道の巻」では、鉄道に詳しい日野という少年が解説役になっているのだが、著者が注目するのは、この少年が「やはりちょっと「変わった人」としても扱われている」ことである。著者は、その少年との彼の友だちとのやりとりを引用する。そのやりとりは、級友の質問に対して日野少年が答えるものだが、著者は日野少年が「鉄道好きでなければ知らない用語」や「細かい数字」を持ち出していること、日野少年が級友たちが閉口するまで答え続けることに注目する。著者はここから、「鉄道少年は、級友との友だち関係を犠牲にしても、鉄道への愛を貫き通すのである」と指摘する。そして著者は、「子どもは鉄道について学び知ることで、その知性を高めていく。だが残念ながら、社交性といった人間関係についてはなかなか学べないという、今日でも一般に知られていることが、明治の書物からも伺えるのである」とするのである。
「一般に知られている」とすることはやや乱暴かとは思うが、ともかく著者はここから、「鉄道好きにとっては、知識も所有の対象となる。自分だけが知っていることを丹念に追求していくことこそが、鉄道マニアの使命なのである。」と結論づける。そして、「これまで日本の鉄道文化は、『少年工芸文庫』の日野少年のような鉄道マニアによって支えられてきた」と言うのである。「車両や時刻表、音響、駅弁とグッズの収集……」と著者は続ける。鉄道の愛好家がこれを読めば、こんなふうに「これまでの日本の鉄道文化」を定義していいのだろうかという疑問が湧いてしまうだろう。これまでも日本の鉄道文化はそういうものだけではなく、もっと多様なものだと思うからである。
著者はこの本を終わるにあたり、「(鉄道マニアの)一人でこつこつと積み重ねる「所有」の営みを否定するものではない」としつつも、「あえて一つ言いたい」として、「マニヤックな鉄道文化とは別に、もっと持続的でゆるやかな鉄道文化があってもよいのではないかと思う」と書いている。いわゆる「鉄ちゃん」や「鉄子」は「マニアックな鉄道文化」と関係するのだろうが、著者が望むのは、それとは異なる「持続的でゆるやかな鉄道文化」である。だが、著者の望む鉄道文化がどのようなものであるかを具体的に示すわけではない。ただ、著者は「鉄道文化の深い一人遊びの魅力を失わずに、鉄道を通して人間関係を構築する−これは鉄道の良いところばかりを取り上げた親の願望かも知れない」と言うのである。著者にとっての「鉄道の良いところ」とは、やはり「所有原理」にかかわらないもののようである。そして著者は「二一世紀の子どもたちのための新しい鉄道文化が、今後どのように展開されていくのか」を見守りたいと言ってこの本の結びとするのである。
「これまでの日本の鉄道文化」を批判しつつ「新しい鉄道文化」を待ち望む著者のこのような言葉は、現在すでに鉄道を愛好する人になんとも言えない読後感を与えるかも知れない。しかしこの本のこうした結論を、著者による問題提起とみなして受け止めることもできると思う。
5. 好ましい鉄道の楽しみ方を求めて
最終章でも、この本の題名である「子どもはなぜ電車が好きなのか」という問いへの答えは、明確になっていないように思える。それでも、著者の様々な視点からの試みは、意味のあるものだと思う。この本を読んで面白いのは、鉄道好きを分析する試みを通して、鉄道とかかわる著者自身の軌跡が見えてくることである。著者が好むのは「人と人とをつなぐもの」としての鉄道の魅力だろうと思うが、巻末の資料編を見ると、著者自身が相当なコレクション型のメンタリティをもって鉄道にアプローチしていることがわかる。「子ども」を通してという形ではあるが、著者自身が鉄道というものに近づきながら、自分が良いと思う鉄道の楽しみ方を模索しつつあると言えるのではないだろうか。そのように読むことで、この本が提起している事柄がよりよく見えてくると言えるだろう。つまり著者は、まだ十分整理できていないとは言え、異なる性格を持つ二つの鉄道の楽しみ方があることを自身の経験を踏まえながら想定し、彼にとっての望ましい鉄道好きのあり方をイメージしようとしているのではないだろうか。
確かに鉄道には、鉄道に関する知識を得ることや、おもちゃ、鉄道模型、鉄道関係のグッズ、映像や本など、様々な形のコレクションをする楽しみ方がある。そして、これらのものを通して、あるいは別の方法で、鉄道は人と人とを結ぶ形での楽しみをもたらす。後者の具体例は、鉄道の絵本を通して親子が共に楽しむことや、おもちゃや模型を修理したり、子どもにはできない操作をしてみせる父親の喜びなどであり(第三章)、鉄道で働く人々との出会いなど(第十章)である。二つの原理を当てはめれば、前者は「所有原理」の欲望によるものであり、後者は「関係原理」に関わるものとなる。だが、おもちゃや本などは、どちらの楽しみも提供するものであるから、「所有原理」による楽しみがあって、それを生かした「関係原理」による楽しみがあるとも言えるだろう。したがって、この二つの楽しみは鉄道好きにおいては共存するものなのである。著者が好んで引用する小説『鉄道の子ども』のピーターが鉄道好きになるきっかけは、誕生日にもらったライブスチームの機関車の模型であった。残念ながらその模型は壊れてしまうが、ピーターの父親が修理を約束をしてくれたところからこの物語は展開していくのである(第二章と第三章) 。
著者は鉄道の楽しみを「共有」することに価値を感じているようである。そしてそのことによって、著者にとって好ましい鉄道好きのあり方と、少し心配なあり方が対比的に示されていると思う。一人で見られるインターネットなどの鉄道の映像より、絵本が「よいな」と思うのもそのためであろう。また、「級友との友だち関係を犠牲にしても、鉄道への愛を貫き通す」日野少年のような鉄道好きは、「親として考えものかも知れない」と思うのである。つまり著者が「所有原理」と「関係原理」とを関連させて問題にしているのは鉄道好きにおける社会性のことなのである。とは言え、著者は「ひとり遊び」の重要性についてエリクソンを引用して説明しているし、「鉄道文化の深いひとり遊びの魅力」を認めている。著者によれば、「ひとり遊び」は自我の芽生えと共に始まるものだが、それは大人にも必要なものなのである(第九章)。そして、おもちゃの電車は、「ひとり遊び」にとって「もってこい」の素材である。つまり鉄道遊びは、まず一人のための価値ある遊びとして登場し、やがて共有できるものになって行くと考えて良いだろう。
6. 一鉄道愛好者としての呟き
本を読むと言うことは、単に著者の主張することを理解するためにすることではない。それは、読む人が自分で考える機会を作ることだと思う。その本から得た素材によって、自分の考えを組み立てることでもある。この本は、子どもの鉄道好きに関する本である。しかし、同時に「これまでの日本の鉄道文化」に対して問題を投げかける本でもある。私のような者がこの本を読むことは、一人の鉄道愛好者として著者の問題提起に対する答えを探すことなのだと思う。もちろん、それは一個人ができることだとは思わない。しかし、この本を読みながら思いついたことはある。
それは、あらためて例の「所有原理」と「関係原理」を考え直してみることである。「所有原理」にもとづく楽しみは、必ずしも悪いものではないと私は思う。なぜなら、丹念な追求は、鉄道マニアだけのものではないからである。哲学の探究にも、あるいはもっと広く読書全般にもいえることかも知れない。また、例えば美味しいラーメン屋を見つける食の楽しみにも共通することだろう。自分の思い込みに過ぎないとしても、ひょっとして「自分だけが知っている」あるいは「自分が発見した」と思えることの喜びは、人の様々な営みの中で、誰でも味わうものではないだろうか。そしてこの喜びは、競うことはあっても、単に人を打ち負かすことを目的にしているわけではないと思うのである。そしてそれはもちろん「使命」として行うものではなく、良くも悪くもその人の生活にとっての原動力となるものだと私は思う。
この本の説明の中で、「自分だけ」のために楽しむことに何か問題があるかのような記述が生じてしまっているのは、少し残念なことである。なぜなら愛好とは、個人的なものであっていいと思うからである。私の子どもの頃には、鉄道の趣味を共に楽しむ友だちがいて、互いに刺激し合うことができた。しかし同時に、楽しみとは結局自分自身が感じるものであることも承知していた。どう楽しむかは本人次第なのである。愛好というものは本質的に個人の自由にもとづくものであり、そのことなしには共有もあり得ないものだと思う。まずは「ひとり遊び」でいいのだ。そして、人生の中で「どうしても好きだ」というものに出会うことは、本当に大切なことではないだろうか。
しかし、私自身の中に、鉄道に関するマニアックなコレクションの欲望がないと言えば嘘になる。確かにそこには過剰なものがあるのだ。この本を読んで気づかされたのは、その点である。冷静に考えると、そういう楽しみは、精神的な豊かさをもたらすものではないかも知れない。なぜならコレクションの欲望は、手に入れること自体を目的にしているからである。このことは、本は読まなければ意味がないのに、読みきらないうちに次々と関連する本を手に入れようとすることにも似ていると思う。この場合にも、所有するだけで満たされるものがあるように思えるのだ。もちろん、コレクションに走ることには言い訳もある。勉強や仕事に追われている時は、コレクションの楽しみくらいしかできなかったと言えるかも知れないからだ。
7. 量から質へ
斎藤氏は『関係の化学としての文学』の中で、二つの原理を理解し易いように、性愛における男女の欲望のあり方の違いとして説明している。それによれば「所有原理」は「質より量」の原則に支えられている。これに対して「関係原理」の原則は常に「量より質」「程度より強度」なのである。この二つの原理が、そのようなものであれば、これらの原理を鉄道好きの心に当てはめてみることができるかも知れない。男女の違いという観点からではなく、二つの異なる欲望の原理から鉄道好きを検討してみるということである。すでに見たように、この二つの原理による楽しみは切り離して考えることはできないようだ。しかし、「関係原理」による鉄道好きのあり方を期待するならば、「量より質」にウエイトを置いた楽しみ方が、鉄道の愛好においてどのような形であり得るのかをイメージしてみる必要があろう。大変安易な当てはめ方になってしまうが、そうした場合、いったいそれはどういうものになるだろうか。
私自身は、良く味わうこと、じっくりと楽しむことになると思う。確かに量的な追求は虚しいものである。敢えてそうしたコレクション的な欲望を減速してみれば、そこに深みのある楽しみが見えてくるのではないだろうか。最近私が心掛けているのは、例えば過去に撮った写真などの一つ一つを味わい直すことである。こう言うと消極的な姿勢のように感じるかも知れないが、実はそれによって全く新しい視界が開けるという経験をしている。新型コロナウィルスのために以前のようには旅に出られないが、これはいい機会だと思っている。私の鉄道好きは、何十年もずっと同じように続いてきたものではない。その楽しみは人生の過程で途切れることもあったし、大きく変化することもあった。長い間関心を失った後に再び鉄道が自分の心をとらえた時、それは以前とは違う楽しみ方の始まりだったりするのだ。この本で著者が最後に述べる「子どもの成長に沿った形で鉄道好きの質も変化していってもらいたい」という願いは、彼の子ども自身が実現して、叶えられるものだと思う。
筆者はこの本の巻末の資料編で海外の鉄道文化について書いているが、私も海外の鉄道愛好家との交流を少ないながらも経験してきた。インターネットの時代になって、最近それは加速的になっていると思う。アメリカの愛好家の自宅を訪問したこともある。そういう機会に私は、彼らの楽しみ方を目の当たりにして、想像もできないほどマニアックなものがあることを実感した。実物への関心、模型作り、コレクションなど、やっていることは同じだが、私が感じたのは、かの国では、これほどまでに自分が愛好することを堂々と、大らかに楽しんでいいんだということであった。逆に見れば、その時私は、趣味に没頭することに何か罪悪感のようなものを感じてきた自分を発見したわけである。鉄道の趣味はいつか「卒業」すべきものという思いが、どこかにあったのかも知れない。そして自分がそういう感じ方をするのは、私が性質の違う社会で育ったためなのかと自問したのである。さらに私が注目したのは、私が出会った愛好家が、家庭を守り、お金も節約しながら、じっくり時間をかけて楽しんでいたということである。そして、その楽しみを自分ならではのものにしていたのである。また、趣味を家族に理解してもらうことにも、仲間と共有することにも、彼らは本当に長けていると思った。彼らには鉄道への深い愛着があることはもちろんだが、重要なことは、その根底に、自分たち自身の生活を楽しくしようという彼らの底抜けに明朗な姿勢があることなのだ。とにかく、私はそれを感じたのである。アメリカにも色々な愛好家がいると思うし、全てが良い見本とは言えないだろうが、私には自分の趣味を見直すためのきっかけになったのである(しかし、それをまだ十分に生かすことはできていないようだ)。
8. 生きることを楽しくする
日本では何かに没頭する人間は、変わった人と見られがちである。学校でも職場でも協調性が第一に求められていると感じるが、そういう社会が何かに没頭する人間に与えた言葉が「オタク」というものかも知れない。平均的でバランスの取れた人間がとりあえず求められているからであろう。「お別れ列車」や「新型車両」を撮影するためにプラットホームや線路脇に群がることが、世間から見た「鉄ちゃん」の代表的な姿かも知れない。それは、いわゆる「撮り鉄」と呼ばれる人たちの一部ということになるだろう。ひょっとするとそうした「鉄ちゃん」たちは、社会が求める「まずやるべきこと(つまり勉強や仕事)」に追われ、じっくり楽しむ時間がないのではないか、そのために、あのような楽しみ方に夢中になってしまうのではないかと、私などは思ってしまうのだ。もちろん、夢中になることは若い人の特権だとは思うのだが。
著者が言うように、海外の駅のホームでは、鉄道車両を撮影する人をあまり見ないようである。どうして日本では鉄道の撮影が、時には迷惑になるほど盛んなのだろうか。その理由は、個性的な車両が日本の鉄道に多いといったことだけではないだろう。私も鉄道の撮影をしてきたから偉そうなことは言えないが、残念ながら、たぶんこれは鉄道好きのあり方の問題なのであろう。また、鉄道会社などによるイベントの内容も影響しているかも知れない。いずれにせよ、写真撮影やグッズ集めにウエイトを置き過ぎているように思う。この様な現状を見ると、著者が「もっと持続的でゆるやかな鉄道文化」を求めるのもわかる気がするのだ。
著者が望むような鉄道文化を実現するヒントは、生活をどう楽しむかという点にあると私は思う。それは、例の二つの原理にかかわるのかも知れないが、人生観そのものを見直すことに繋がるものだと思う。我を忘れたような集団的なものではなく、自分なりの方法で楽しむことを第一に考えて鉄道に触れていけば、著者が求めることは十分に実現可能だと思う。おそらく、日本においても、すでに多くの愛好家がじっくり楽しむことを実践しているし、過去にも多くの愛好家がそうしてきたに違いないと思うのである。ただ彼らは目立たないだけなのだ。私がこのように見ることできるのも、生活を楽しむことを大切にして、少しゆっくり生きることにしたからかも知れない。この本を読んだことで、期せずして、そうした生き方の意味を自分で確認することになったようである。
ところで、この本は十年近く前に書かれた本である。著者の子どもたちもすっかり成長しているだろう。しかし、彼らが今、鉄道好きかどうかは、どちらでも良いことではないだろうか。鉄道好きの人間だって、いつも鉄道のことを考えているわけではない。人の関心事は多層的なものである。私の場合も、鉄道に触れる時には、いつもその地域の歴史や文化のことが気になってしまう。それがまた鉄道以外の楽しみを豊かにしてくれると思う。自分の周りの世界に好奇心を持って関わっていれば、そうした関心事の層が互いに刺激しあって、次第により深みのある自分の楽しみ方ができて行くと思う。たぶん心配はいらないのだ。それはそれぞれの人が自分で作って行くものだからである。(了)
写真1 PORTER(ポーター)の小型機関車:壊れた模型を安価にオークションで手に入れて、それを修理したもの。実物の資料集めを含め、約1年かけて、かなりの補修をしつつ細密化の加工をした。入手時の破損の度合いが大きかったため、煙突は傾いたままである。修理後快調に走るようになったので、愛着が沸いて、いまだにいろいろ手を入れている。(PORTERは、アメリカの機関車メーカー。有名な弁慶号などもPORTER社製。この模型のような小型機関車も日本に輸入されている。)
もしよろしければ、以下ののブログをご覧ください(twitterの案内もしてますが、更新のスピードは非常に遅いです)。https://shaypapa49.blogspot.com/ ■参考文献
『子どもはなぜ電車が好きなのか 鉄道好きの教育<鉄学>』弘田陽介 冬弓舎 2011年
『若草の祈り』 E .ネズビット著 岡本浜江訳 角川文庫 1971年
原題は”The Railway Children”なので、著者はこの本の書名を『鉄道の子ども』としている。原作の出版は1906年である。著者はこの小説から多くの引用をしている。この物語は、BBCによってTVドラマ化されており、また映画化もされている。
『リズムの本質』 L .クラーゲス著 杉浦実訳 みすず書房 1971年
『関係の化学としての文学』 斎藤環著 新潮社 2009年
★プロフィール★小原まさる(こはら・まさる)1950年代生まれ。愛知県在住。音楽、フランス文学、アメリカ・カナダ西海岸の文化などに興味を持ってきた。趣味は(昔の)鉄道を追うこと。
Web評論誌「コーラ」46号(2022.04.15)
書評:鉄道好きへの問いかけ 弘田陽介著『子どもはなぜ電車が好きなのか』を読んで(小原まさる)
Copyright(c) SOUGETUSYOBOU 2022 All Rights Reserved.
|
| 表紙(目次)へ |


