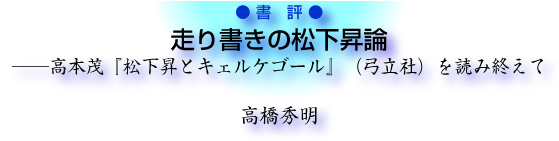|
|
|
Web評論誌「コーラ」 |
|
■創刊の辞 ■本誌の表紙(目次)へ ■本誌のバックナンバー ■読者の頁/ご意見・感想 ■投稿規定 ■関係者のWebサイト ■プライバシーポリシー |
|
<本誌の関連ページ> |
|
■「カルチャー・レヴュー」のバックナンバー ■評論紙「La Vue」の総目次 |
Copyright (c)SOUGETUSYOBOU |
|
|
|
1
高本茂が『松下昇とキェルケゴール』を弓立社から上梓した。昨年の夏過ぎ、二○一○年九月のことである。
高本は必ずしも毎年ではないが、夏に避暑を兼ねて私の住む北海道の地を訪れる。訪れた折には、たいてい会って食事をしたり、私の方で札樽近辺を案内したりする。折々メールのやりとりもするし、電話で話をしたりもする。ただ、松下昇のことについて近年真剣に議論をした記憶はない。私の方で避けていた向きがあったからかもしれないし、高本の方で私相手では話がうまく噛み合わないことを察知していたからかもしれない。
本書と同題の連載評論第一回が、詩と批評の同人誌『BIDS LIGHT』8号に掲載されたのは二〇〇五年三月だった。第二回はその翌年七月発行の同誌9号に掲載されたが、その後『BIDS LIGHT』は休刊状態に陥り、高本から「松下昇とキェルケゴール(3)」と題された第三回連載分が同人への私信として届けられたのは、二○一○年五月の連休明け前後だった。
高本がこれを
そのことを論じる前に、松下昇の表現論の特徴的なところを、ここにとりだしておくことにしよう。松下昇の表現活動について不十分なかたちではあるが考察を試み、一方キルケゴールについては何も言及しないという偏ったものにはなるけれど、もって、高本の手になる本書『松下昇とキェルケゴール』(弓立社)への書評(とも言えないようなコメント)の責を、遅蒔きながら果たしたいと思う。
2
松下昇は、表現過程に独特なこだわりを示した。それは一九六六年十一月の神戸大学新聞に発表された「〈ハンガリー革命〉――〈六甲〉」というエッセイで次のように触れられた方法意識、即ち「対象を変革する(表現する)だけでなく、変革する(表現する)方法そのものを対象の中に加えていく必要」があるとみなす表現行為の捉え方として認められる。あるいは、一九六九年十二月の発言(於都立大開放学校―「私の自主講座運動」)中――「一つの文章、一つの言葉があるとして、それがどこで表現されたかによって、全く意味を変えてしまいます。」と述べられているところの、最初は「表現の階級性」とそのことを呼んでみて、そのすぐ後に、「階級性という言葉ではおおいつくせない、むしろ原罪性というべき問題」と言い直された、そのような問題意識のことである。それは理論的な問題であると同時に実践的な問題でもあった。松下昇のラジカリズムにおいて、表現論をはらまない表現というのは沈黙と同じか、それ以下の生理や自然現象に近いものと考えられたと思う。そのラジカリズムはたとえば次のように表明されもした。
北川透の「わが執着われら難破船」の記述によると、北川は「一九七○年一月、当時、神戸大学の講師であった松下昇から、数枚のビラを受けとった」。そのビラのうち六枚が松下の了解を得て、北川の個人誌『あんかるわ』24号(同年四月発行)に掲載された。上記の引用は、そのビラの一枚からの抜粋ということになる。「この世界で最も幻想性にあふれた領域」というのは、おそらくビラがまかれた大学空間のことを指しているのであろう。ここにみられる学問や研究表現の「根拠の変革」の訴えの根底には、彼の独特の表現過程論が横たわっていると考えられる。
私の理解するところでは、松下のこの表現過程論とも呼び得る考え方の骨組は大きく二ないし三の要素から成っている。ひとつは表現される言語である。もうひとつはある言語表現をそのようなものとしてあらしめる場面である。そして、更にもうひとつ挙げるならその場面に働く支配的権力の力線である。今説明を簡略化させるために、支配的権力の力線は場面に溶け込んで一体化されているものとして考えることにしよう。すると、表現過程論においては、「つぶやきからゲバルトをへて国家、さらには宇宙に至る全て」は、言語と場面に支えられて出来し、また成り立っている、と言うことができる。場面は言語によって表現される。それは表現の与件であると同時にその対象性でもある。つまり、表現において場面は、事実性として、あるいはジャンルや作品形態として、あるいは名づけようのない畏れを湛えた暗黒として、私たちに対象的にはだかるものとされる。
ある発言①がある場面①’においてなされるとする。これは、場面①’が発言①の表現契機をかたちづくったということであり、また同時にそれは、発言①の表現が場面①’を顧慮して、その場面性を繰り込んだ上で表現内容がかたちづくられた、ということでもある。次に、その発言を書面に文字として記録する行為②が生まれるとする。その行為②の場面②’は、最初の場面①’でかたちづくられた表現契機とは異なった別の表現契機を、表現②(=書面作成行為)としてかたちづくる場面性である。そして表現②は場面②’を表現の対象として繰り込むと同時に発言①に繰り込まれた場面①’をも繰り込んだ内容となるものである。また更に進んで、その書面を仮に印刷し(③)、多数に頒布する(④)という行為があるとすれば、その行為ごとの場面③’や場面④’も、それぞれがまた別々の場面性をかたちづくって、それらの行為、印刷③や頒布④としての表現を出来させると同時に、それらの場面性はそこでの表現の前提となる表現①、表現②、……おける各場面性もそこに繰り込んだものとしてかたちづくられる。場面ごとに表現の動機は異なるし、表現の形式も異なるのだが、それらの一連の過程全体が、ひとつの表現過程として綜合されるべきものと、松下の表現過程論では考えられたのだと思う。
3
この場合、松下昇の表現過程論では、第一次的表現である発言行為①には、②、③、④……と、どこまでも波及してゆく表現の流通可能性(松下が好んだ言い方では〈交換〉の可能性)のひろがりに対しての想像力が求められたと考えられる。ひらたく言い直すなら、自らの発言が宇宙の果て歴史の果てにまで届けられる、その空間的時間的変容に耐えられるような発言でなければ、表現として意味はなさないとみなされた。次に、①ではないn次の表現契機に基づく表現行為nには、{n-1}’以下の場面に対する想像力と包括力がやはり求められた。そして、この表現過程論を敷衍させてゆくなら、①の発言行為は必ずしも第一次の表現行為であるとは限らないとも言えるし、逆に、nである表現行為もまたある意味では第一次の表現行為であり得る、と言えることにもなる。オリジナルな表現という概念のかわりに、すべてがなにものかを〈仮装〉した表現でしかあり得ないという考え方が、ここに生み出されることになったと考えられる。
(私に今その用意がないので)ハーバーマスのコミュニケーション理論からの影響ということを除外して考えるなら、あるいは、言語表現の場におけるさまざまな権力介入の問題を閑却した上でなら、このような松下昇の表現過程論には、時枝誠記の言語過程説の影響と、その更に尖鋭化された延伸・拡張の様相を認めるのが妥当のように思う。時枝の言語過程説の特徴は「言語は、行為であり、活動であり、生活である」(岩波文庫『国語学原論 続篇』)と言い切ったところにある。その言語過程はあくまで個人の活動に限局されるものであり、また他者に対してこそなされるという社会的性格を刻印されたものであった。その言語観を時枝は次のように語っている。
時枝がここで述べている要点は二つにまとめることができる。まず、言語は個人ごとの行為だということである。次に、言語は個人的活動だが、その言語形態は必ず他者の応答を予期して成立するという点が他の行為一般とは異なる、ということである。
しかし、本当は時枝も別の箇所で触れているとおり、たとえば「絵画や舞踊等が、ただ表現の満足ということだけで成立する」ということはない。それらの表現もまた批評を予測して、批評意識(時枝の用語に即するなら「表現者」に対する「享受者」の観点)に拮抗しつつなされるものであることは言うまでもない。また、言語表現であっても、文学作品として書かれるときには、ここで時枝の挙げる「絵画や舞踊等」と同様に、「ただ表現の満足ということだけで成立する」かのような外観を呈する側面も有するのである。
時枝は言語活動を徹底的に個人的活動のレベルで考えようとした。つまりソシュールの言語観に対する違いを際立たせようとして、必要以上に言語=行為の側面を強調しすぎたきらいがあるが、言語が行為であることと、その行為が作品や法として規範的な対象性を有して立ち現れることとは、人間の社会生活において、どちらかが正しくてどちらかが誤っているというような、隔てられるべき二つのことがらではないと言うべきである。その意味で、言語は行為であるとともに、行為の成果でもある。人間がなぜ芸術作品を必要とするのかと言えば、往々そう見られてしまうことがあるごとく、現実社会から逃避したいからなのではなく、むしろ現実社会に立ち向かう自らの観念を確認したいからであろう。人間は個人の行為を通して社会生活を営むが、社会が法を必要とするように、社会を生きる個人は芸術作品を必要とするのである。
しかし、松下の表現思想の枢軸は、そのような前提の下には据えられなかったと言ってよい。松下は、社会が法を必要とし、それゆえ社会を生きる個人は芸術作品を必要とする、というふうには考えなかった。法と芸術作品という二つに分裂させられた表現の規範的対象性は、むしろ行為として一元化されるべきだと考えた。「つぶやきからゲバルトをへて国家、さらには宇宙に至る全ての表現の根拠」には言語と場面が想定され、それは一連の行為の表現過程として綜合されるべき根拠へと通じている筈だと考えられた。つまり松下の表現思想では、比喩的な言い方にはなるが、法の言葉そのものが芸術作品の機能を有する行為となる事態こそが目指されたのである。それは松下昇の〈遠い夢〉をかたちづくったと思う。
4
〈遠い夢〉とは何のことか。松下はそのイメージする内容を次のように語っていた。
松下は迷うことなく、「全過程が視えなくなるようにしか存在しない」余剰のみが屈折するその深みへ踏み込んでいったのだと思う。そして、松下が抱いたであろう、その〈遠い夢〉の実体が、錯誤なのであるのか錯誤ではないのであるか、私は性急な判断を下そうとは思わない。高本もそう指摘しているところの、松下昇の前人未踏のと言っても過言ではないような表現営為は、没後十五年を経た今もその全体を検証できるようなかたちでは、私たちの前に開かれていない。開かれるべきなのかどうかさえ私には不明ななかで、どんな判断も宙づりにしたままの短くない年月を私も過ごしてきたのである。
ただ、その〈遠い夢〉を追い求める松下に、法表現の位相と作品表現の位相とを殆ど同位のものとみなして、同じく否定の対象に据えようとした〈錯誤〉の形跡が認められることだけは指摘しておく必要があると思う。時枝の言うように「言語は、行為であり、活動であり、生活である」としても、言うまでもなく行為は、活動は、生活は、必ずしも言語がすべてではない。又、言語が行為であるとしても、言語は行為の成果でもあり、観念として対象的になって、ラングはもとより法や作品として規範性を帯びることになる側面も有する。法廷での表現が、職業や芸術の表現と同じに、強いられた個々の恣意性を発揮する場を指し示すものでしかあり得ないこと、即ち人間の生活の一部でしかないことを、松下は見損なっていたと推察されて仕方ない振る舞いを、北川透ほかの証言を俟つまでもなく、私は彼との一瞬とも言ってよいような短い応接体験を振り返る中で、実感を伴って思い浮かべることができるのである。
5
本書を上梓した高本茂の心境も、私と同じような思いを抱えて行きつ戻りつしていたろうと推察される。そのことへの同情を惜しむつもりも、まして突き放すつもりも私にはないが、しかし、なお腑に落ちないのは、この一書をなした高本に、如上の松下の表現過程論に対する応答の意思が殆ど見られないことである。高本はたしかに、松下の「六甲」や「包囲」の作品表現から法廷での表現活動までをとりあげて論じてはいる。しかし、その論じ方には、松下の表現過程論を媒介した痕、媒介しようとした痕が見受けられない。
松下の表現は、表現行為の次元毎に、その場面を、そして場面に潜勢する前表現あるいは原表現の関係性を包括していくというかたちを必ずとろうとしてきた。私信の処遇から法廷陳述の姿勢にいたるまで例外なくその表現過程論の原則を適用させてきているのである。
本書における高本の表現には、そのことへの応答が殆ど認められない。高本がその問題を本書でとりあげていないのではない。とりあげているにも関わらず、まるでよそごとなのである。よそごとだという印象はどこから来るのか。たとえば、高本が松下と私信を交わしたりする中で自らの異和を松下に表明したり、その後長い「失語」状態に陥ったりしたこと。それらの経緯を振り返りつつ『BIDS LIGHT』という同人誌に本書と同題の連載を開始したこと。その後その表現を著書として上梓したこと。これらの表現の重層性に対して自覚的であろうと意識していた様子が見受けられないということである。いや、もしかしたら、1で紹介したように、本書の中身を初出と殆ど違わないかたちで上梓するという意図、まえがきもあとがきも初出一覧さえもないという、一見ノンシャランスと見紛うその上梓の仕方に、松下表現過程論への高本なりの応答を認めるべきなのかもしれない。とすれば、そのことは何を私たちに伝えてよこすのであるか。
まず私には、高本が激しく後退し、後退したままそこで衰弱しているように思える。その兆候は、大げさな言い方をすれば本書の一行毎に読み取れるとさえ言ってよいくらいだと思う。
たとえば「私は今、この二人について語る資格があるのかどうかを疑わせる職業に就いている。」と高本は言う。高本の職業は大学教授であるが、批評は職業や身分や縁故などと一切関わりない、生活者であり表現者である個人と個人の平場の関係でなされる行為だということくらいは、お互いとっくに踏まえてきたことではなかったろうか。どんな職業についていようと、恐縮することもなければ尊大になることもなく、思うことがあれば好きなように言えばよいだけの話である。なぜ、職業などそんな外形的なことで恐縮してしまうのか。
また、高本はこうも言い募る。
「前者〔松下昇―引用者註〕は闘争当時は支援者・共闘者の耳目をひき、数々の詩人たちから論じられた。後者〔キルケゴール―引用者註〕は50年代・60年代『実存主義』が隆盛を極める中で、その開祖者として注目を浴びた。今、学生たちや知識人にとって、〈大学闘争〉はその痕跡もとどめぬほど忘却されている。また『実存主義』は今では哲学の〈流派〉としては、廃れきっている。」と。
だが、流行り廃りに寄り添う下世話の視線にそれ以上の意味など宿りようがないのは自明のことであろう。現象的な浮沈をとりあげるならそれがどういう要因に基づくのかこそを語るべきであり、下世話な感覚そのままに同情や憐憫や悔しさなどを滲ませてみたところで、自らの甘え以外のなにものも結実させ得ないだろう。
「二人とも孤立無援の闘いを遂行し、たった一人で野垂れ死した」ことが、何か特別のことだとでも高本は言いたいのだろうか。そんなことは、自分自身の身の振りとしても最前あたりまえの覚悟ではなかったか。
いったい高本は何に遠慮し、何に囚われているのだろう。
6
私は、高本が北海道に来れば、経済学と文学の豊かな知識を湛えた、そして記憶に残るすぐれたロシア革命論(「復刻版・ペレストロイカと十月革命物語」として閲覧可能)を変名により展開した古くからの友人として応接してきた。高本が大学教授であろうとガードマンであろうとそのことに寸毫違いなどある筈もない。高本もまた、外目と関わりない浴衣掛けの私に対して同じ応接を見せてきた筈である。
松下昇やセーレン・キルケゴールと私とを同等に見なすことなどできないというのはあたりまえの話だとしても、私への応対がその二人に入れ替わると、何故そこに下世話にして過剰な思い入れを無理に浸入させ、自ら「自分の矮小さと卑小さに赤面する」とか「私のような低俗で薄汚い人格の持ち主」とか「私は松下昇について語る資格のない人間かも知れないが」などと、必要以上に身を低くすることに専心しようとするのか。
松下昇であれセーレン・キルケゴールであれ、敵に対してそんな卑屈な姿勢を示しはしなかった。何のために高本は、松下やキルケゴールを、彼らとは相反する姿勢において語ろうとするのか。彼らのような「孤独な闘い」を自分は引き受けるハメに陥りたくないからなのか。もうそのような孤独や闘いには疲れ切ったからなのか。そんな邪推さえ浮かびあがり、高本の言うのとは違って、「『問題提起そのものの湾曲』とはおそらくこのような事態を言うのではないだろうか。」とさえ言い返したくなる。
指摘すべき点はまだある。この書における高本の一文一文には、まるでコシが感じられず、生煮えの麺のような文章が次々続けられるのには、なにか余人に窺い知れぬ特別な事情があるのだろうとは思う。だが、どんな事情があったにせよ、ここに見られる意識の衰弱は看過しがたいのであり、せめてその一端だけでも指摘しておく必要を感じるのだ。たとえば高本は次のような強調を置いている。
もちろん、沈黙も表現であれば饒舌も表現である。その形態のどちらが豊かな可能性を潜ませておりどちらが単に空疎なのかを、形態の違いだけからあらかじめ決めつけることはできない。その意味で「沈黙を続けてきた」ことが表現(省察、思索、追究)とは無縁できたことを意味すると考えるなら、それこそ「とんでもない誤解」であるのは言うまでもあるまい。しかしこの一文は、その「とんでもない誤解」に少しく荷担するものではないだろうか。と言うのも、「彼の〈表現〉を全部集めればどんな文豪や大哲学者の全集や著作集をも上回ることになるだろう」という言い回しは、おそらく殆ど何も意識せずに、表現の豊かさや可能性の問題を紙の目方量に還元して語ってしまっているところがあると言えるからである。また、次に続く部分にも、意識の弛緩を指摘できるだろう。
この一節は奇妙な捻れを湛えている。前段における「関心の埒外だったに違いない」という推理に対して、後段の「ジャンルそのものの解体をめざしていたに違いない」というもうひとつの推理が並立させられていることが、その奇妙な捻れの印象をもたらす当の原因であると思われる。「解体をめざしていた」なら「関心の埒外だった」ということでは必ずしもないのでは、と思わせられるのだ。また、ごく一般的な見方からすれば、一時北川透や菅谷規矩夫と非常に親しい関係にあったと言える松下にあって、詩のジャンルが「関心の埒外だった」などということはそもそも考えにくいことである。では、松下は「〈詩〉や文学、哲学といったジャンルそのものの解体をめざしていた」という一方の捉え方は、それよいのだろうか。よいとするなら、なぜ松下はそんな「解体」をめざす必要があったのか。しかし高本の筆は、そちらの解明へはなぜか向かおうとしない。
私なりに推察して得る結論はひとつである。高本は、この書において、自らをイタコに擬したのだということ。高本の口寄せに降霊した〈松下昇〉の像は、どうしようもなく衰弱した私たちの現在の意識をそのまま反映しているだろうということ。高本においては、書くことの時間は解体され、語る口の同一性だけが彼の存在を厳しく強迫しているということなのではないか、ということだ。
7
高本も私も「松下昇体験」とでも呼んでよいような、似たかたちの思想的躓きを抱えて二十世紀末を息してきたと思う。
私が勝手にそう呼ぶ「松下昇体験」とは何か。
封鎖解除により大学拠点を失った一九七○年代以降のノンセクトラジカルが、内ゲバや爆弾闘争など死と暴力に血塗られた世界へ親近するか、さもなくばひたすら内向的に自己解体を進めるかしかないと思いを鬱屈させていた時期、松下昇の闘い方は、飛び抜けて鮮やかに映ったに違いない。出会いの発端に触れて、高本はこう書いている。
「友人の一人」というのは垣口朋久のことで、ついでに言えば私が松下昇の存在を知ったのも、その『五月三日の会通信』の「山賊版」を工房朋の主宰者森重春幸から紹介されたからであった。ここで高本が受けた衝撃(高本は「驚愕」と言っている。)こそは、北川透をはじめとする他の多くの者が松下の表現にはじめて触れた際に共通して覚える「驚愕」であり、希望であり、紛れなく「松下昇体験」の一局面をなすものであったと言ってよいだろう。
貧しく義しいプロレタリア階級が、富の独占を貪欲に果たしてきたブルジョワ階級の支配を打ち倒し、自由で公正な社会を実現する、というようなロマンチックな革命幻想がそもそも劣等感情に理屈を張り合わせただけの張り子の虎みたいな空疎しか湛えていないことを、たとえば愚鈍な私は一九八○年代の半ば過ぎまで殆ど感知できないままにきた。
「〈 〉闘争」そして次には「{ }闘争」と名づけられて展開された松下の表現闘争は、そのようなマルクス主義革命幻想の延命としても、またマルクス主義に対する幻滅へ代置される思想運動としても、新鮮な魅力を放っていたと言える。
ただ「松下昇体験」はもうひとつの別の局面へも通じていたのである。高本茂は次のように証言している。
ハーバーマスのコミュニケーション理論では、真理性・正当性・真実性の三点で合意が形成されない場合には、合意に向けての自由な討論がなされることになる。しかし松下は、おそらくそのような相互行為の領域にも支配的権力の働きが作用していて討論の前提やありかたを歪めることがあると考えていたのではないだろうか。その歪曲された問題群の自覚ないし是正のためには、別の強制力を戦略的に施すこともときには必要であると考えていたのだと思う。自らが担任するドイツ語の履修者全員に零点をつけるというような行為に、それはよく象徴的に示されているように思える。
現行の制度に対する根底的な否定が、その制度を無意識に受容している者の生活全般と存在そのものの否定へ直結するかもしれない、というようなことについて松下が思い悩んだ形跡はあまり認められない。闘争のラジカリズムが、闘争に与しない者の存在と生活の項目すべてを批判し否定するに至る展開を必然化させていくことを、松下は少しも恐れていなかったと言い換えてもよい。だがそのような姿勢に独善的な思想が宿らないとは限らないし、なによりも、自由な討論とその過程が、現実的局面から要請されるスケジュールの前に任意に〈宙吊り〉されてしまうことをひとたび肯うなら、その真理性に対する反証の機会自体が成立し得なくなってしまうだろう。私が「松下昇体験」と呼びたい時間の行跡は、そのような局面への立会も含んだ松下昇との応接体験全体のことである。松下昇の闘争を支援する関わりの中で、必ずと言ってよいくらいに遭遇することになる敬意や共感と、別方向から不意にもたらされる息苦しさと不審、その二つの局面が併存する体験のことだと言ってよい。
「松下昇体験」のこの二つの局面に思想が冷静に対処できない限り、松下昇の亡霊はいつまでも私たちを脅かし続けるだろう。私自身のことを言えば、松下昇は決して死んでいないし、私は脅かされ続けたままである。おそらく高本茂においてもまた。
(★編集部註:『松下昇とキェルケゴール』は著者自身のHPにおいて全文公開されています。) ★プロフィール★
高橋秀明(たかはし・ひであき)1951年/小樽生まれ。1976年/詩集『夢国から 敗惨祈呪』(創映出版) 1979年/詩集『禁猟地の未明』(アトリエ出版企画) 1983年/詩集『博物館のある光景』(砂子屋書房) 1997年/エッセイ『かなしき町の歌のしじま』(コミュニティ研究所) 1999年/詩集『言葉の河』(共同文化社)により第二回小野十三郎賞受賞 2008年/詩集『歌ノ影』(響文社) E-mail:hide-mesアットマークqk2.so-net.ne.jp
Web評論誌「コーラ」13号(2011.04.15)
書評:走り書きの松下昇論――高本茂『松下昇とキェルケゴール』(弓立社)を読み終えて(高橋秀明)
Copyright(c) SOUGETUSYOBOU 2011 All Rights Reserved.
|
| 表紙(目次)へ |