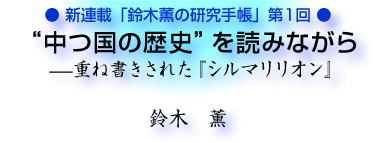|
|
|
Web評論誌「コーラ」 |
|
■創刊の辞 ■本誌の表紙(目次)へ ■本誌のバックナンバー ■読者の頁/ご意見・感想 ■投稿規定 ■関係者のWebサイト ■プライバシーポリシー |
|
<本誌の関連ページ> |
|
■「カルチャー・レヴュー」のバックナンバー ■評論紙「La Vue」の総目次 |
Copyright (c)SOUGETUSYOBOU |
|
|
先に「“父子愛”と囮としてのヘテロセクシュアル・プロット――トールキン作品の基盤をなすもの」(平野智子との共著)と題して本誌10号に書いたけれど、その時はまだ“The History of Middle-Earth”は名を知るのみであった。クリストファー・トールキン編纂の――万一この名前をご存じない方は、ぜひ「“父子愛”」にあたって頂きたい――このシリーズは、なにしろ十二冊もある上、やはりクリストファーが『シルマリリオン』の異稿をまとめた二巻本の『終わらざりし物語』と違い、当節邦訳は出そうもない。まずは刊行された『シルマリリオン』に限って――前回はハンフリー・カーペンターによる伝記と“リンク”させたわけだが――何が言えるか、二人で検討していたのだが(それだけでも書き切れないほどの発見があった)、その後ついに“The History of Middle-Earth”に手を出すことになった。
というのも、“囮”によってはぐらかされた本当の話を探求するうち、これは本来別のものである話が下敷きとしてあって、その上に真の主題が展開されたものであり、本当に地層のようにきれいに剥がれるのに違いないと思えてきたからだ。古い層に重ね書きされ、辻褄をあわせられた結果、一見、統一されて見えるけれど(そして、解説やガイダンスなしでは理解するのが難しく、楽しむのはもっと難しいと、もっともらしく言った専門家さえいるが)、表層を持ち上げるなら――ダリの絵の中で少女が海の皮膚を持ち上げるように――それまで透けて見えていたそれ以前のテクストが鮮やかに見てとれるに違いない。そうした研究は多くの作家についてかねてから行なわれている。トールキンの草稿を調べればいろいろなことがわかるはずなのに、なぜトールキンの専門家は、そうした基本的な仕事を怠っているのか。
そこまで考えてはっと気づいた。トールキンの草稿ならすでに公けにされているではないか。しかも、限られた研究者しか近づけない聖遺物としてではなく、私たちのようなアマチュアでも手の届く刊行本として。未定稿のまま作者が逝った『シルマリリオン』の本文の決定さえ行なったクリストファーは、「中つ国の歴史」=父の背負った業すなわち作品の生成過程を、そのような形で万人に公開しているのだ。
知りたいことはいろいろあった。たとえば、メルコールが蜘蛛の怪物ウンゴリアントを連れてきて楽園ヴァリノールを照らす二本の木を枯らし、世界が真暗になる話だが、本来、むしろ牧歌的で童話的な趣きをそなえていたのではあるまいか。彼らの行為が原罪の目に見える上演となったのは、トールキンが「真の主題」を見出してのちではないか。最終形態では、メルコールによって父が殺され、シルマリルが奪われたことを知ったフェアノールは、メルコールをモルゴス(黒い敵)と呼んで呪い、「それから、フェアノールは審判の輪[リング]から走り出て、夜の中へ逃げ去った」。その後、モルゴスと牝蜘蛛ウンゴリアントの(滑稽な)逃亡劇を挟んで、フェアノールは再び(今度は叛逆者として)現われる――「その時、不意にフェアノールが都に現われ、皆に呼びかけ、トゥーナ山頂の王宮に集まるように要求したが、かれに下された追放令はいまだ解除されてはおらず、かれはヴァラールの判決に背いて現われたのである」。テクストにもあるように「不意に」現われるこのフェアノールは、しかし別人ではないかと、平野智子はかねてから主張していた。「夜の中へ逃げ去った」ところで話は一度終っているのであり、この〈夜〉は十二章先で、フェアノールとフィンウェの話がトゥーリンとニエノールの悲劇として反復される時、妻が実の妹だったと知って「これだけが足りなかったのだ。これで夜が来る」と言って走り出し(「そしてかれは、風の如くかれらの前から逃げ去った」)、自死に至るトゥーリンの〈夜〉に、直接繋がっているというのである。言うまでもなく、〈叛逆者〉フェアノールの方が、〈父を愛する者〉としてのフェアノールより古い層に属するだろう。
幻想文学の手引きのたぐいで、このあたりを、「この宝石を何物にも代えがたく思うフェアノールが返答をためらっている間に、メルコールがシルマリルを奪ったという知らせがはいった。/怒りくるったフェアノールはヴァラールの制止も聞かず、モルゴス(メルコール)に復讐するためノルドール族を率いてヴァリノールを離れる」としているのがあって、「何物にも代えがたく思う」対象を完全に取り違えているが、原書ペーパーバックの裏表紙にも「シルマリルは、エルフの中でもっとも技と工夫にすぐれたフェアノールによって作られた、三つの完璧な宝玉であった。初代の「暗黒の魔王」モルゴスが彼自身の目的のために宝玉を盗んだとき、フェアノールとその一族は武器を取り、宝玉を取り戻すための長い恐るべき旅に出た。これは、彼らの神々に対する叛逆と中つ国の英雄的な第一紀の歴史の物語である」とあるから、別にこれが飛び抜けておかしいわけではない。
実はこういう梗概を最初に作ったのはトールキンその人である。『指輪物語』の「追補篇」で私がはじめて知ったはずの『シルマリリオン』も、そういう話であった――「フェアノールは、エルダール中諸芸と伝承とにもっともすぐれた者であったが、同時にもっとも自尊心が強く頑固だった。かれはシルマリルと呼ばれる三つの宝石を造り出し、それらに二本の木、テルペリオンとラウレリンの輝きをこめた。三つの宝石は敵モルゴスの羨望するところとなり、かれはこれを盗み、二本の木を損った後、中つ国にこの宝石を持ち来って、サンゴロドリムの己が強大な砦の中でこれを守った。ヴァラールの意向にそむき、フェアノールは至福の国を捨てて、一族の大多数を率い、流謫の身となって中つ国に渡った。というのも、かれは自らを恃み、かの宝石を力ずくでもモルゴスの手から奪い返そうと決意したからである」。これを読む限り、シルマリルに触れて手が黒焦げになったサンゴロドリムの主が、長年地下の玉座に引きこもったきり、鉄の王冠に嵌め込んだ三つのシルマリルの重さにひしがれていたとはとても想像できないが、ともあれ、流布しているフィンウェ抜きの要約はこれの劣化コピーなのだ。なんとか『シルマリリオン』を『指輪物語』と一緒に出版してもらおうと、友人で編集者のミルトン・ウォルドマンに宛てて書いた1951年の手紙(『シルマリリオン』序文所収)でも、彼は基本的にはこの筋書きを語っている。しかし、実際に現行の『シルマリリオン』を読めば、モルゴスの襲撃で失われたのが第一にフィンウェであることは明らかだ。「そしてフェアノールは審判の輪[リング]から走り出て夜の中へ逃げ去った」に続く(原文ではセミコロンで繋がれている)文は、「なぜなら、かれにとっては、ヴァリノールの光よりも、あるいは自分の手になる類まれなる珠玉の作品よりも、父親の方が遥かに大事だったからである。エルフであると人間であるとを問わず、かれ以上に父親を大切に思った者がいたであろうか」である。
しかし、大方の読者にはこの文章も、たんに一般的な「父親への思い」として、通常の理解と共感――「居合わせた者の多くが、フェアノールの苦悩を思いやって深い悲しみにくれた」とあるとおり――を寄せられるのみで読み過ごされよう。『シルマリリオン』のテクストはこういうところで掛け値なしの真実を語っているのだが。また、このセンテンスにおいては、「二本の木」、その放つ光を閉じ込めた「シルマリル」、そして「フィンウェ」が並列されており、それを見落してはならない。なぜなら、ここに書かれているのは、「この三つが同じものである」ということ、そしてフェアノールとフィンウェの関係が、「エルフにも人間にも他に例を見ないものだ」ということだからである。
ちなみに、ヴィリエ・ド・リラダンの『未来のイヴ』の幕切れで、人造人間「ハダリー」が沈没する船と運命をともにしたことを知らせる電報をエディソンが受け取った直後、彼女に魂を与えていた「ソワナ」が死んでいるのが発見されること、そして電報が来る前に新聞で見た海難事故の死亡者名簿に「ミス・エンマ・アリシヤ・クラリー」の名があったことが、「シルマリル」「二本の木」「フィンウェ」が相次いで失われることに対応するとして、平野智子は『未来のイヴ』がトールキンの発想源の一つであろうと推定している。どちらの話においても、オリジナルと複製とそれに生命を与えていたものがいちどきに消滅するのである。これは非常に魅力的な仮定であり、あらためて『未来のイヴ』を繙くなら、ハダリーが機械仕掛の鳥たちと棲む「輝きわたる地下の洞窟」、「昔、バグダッドの宮殿の地下で、カリフの幻想が飾り立てた地下室にも似てゐた」人工のエデンの園は、『シルマリリオン』におけるシンゴルの地下の居館メネグロスを思わせることがわかる。
門の先には広い道があって、自然の岩を切り開き地下深く作られた、天井の高い広間や多くの部屋部屋に通じていた。部屋の数は非常に多く、非常に壮麗であったので、この居館は、メネグロス、即ち〈千洞宮〉と名づけられた。(...)メネグロスの柱は、オロメのブナの木そっくりに、幹も大枝も葉も石を刻んで作られ、金のランプで照らされた。そしてそこにはローリエンの庭のように小夜啼鳥が歌い、銀の噴水、大理石の水盤、さまざまな色合いの石を使った床があった。石に彫った獣や小鳥たちが壁を走り、柱を匍い上り、花々の絡んだ枝々の間から覗いていた。 このように描写されるメネグロスは、それ自体が「楽園」ヴァリノールの写しとして作られたものであり、星空の下、無時間のうちにまどろむ中つ国にあって、そこだけが明るく照らし出された人工世界に他ならない。いささか長い引用になるが、『未来のイヴ』第三巻第二章「夢幻境」の描写と較べてみよう――
巨大な圓柱が、間隔を置いて、玄武岩の圓天井の前面の周邊を支へているので、入口から広間の奥の半圓形まで、右手と左手に柱廊が出来上つてゐた。その圓柱の装飾には[...]土台から頂上まで、大きな草の束と、青味がかつた地色の上にすらりと伸びた銀色の晝顏が表現されてゐた。圓天井の中央には、黄金の長い莖の端から、強烈ならんぷが、一つの天體のやうに、吊り下がつてゐた[...]廣間の奥を形づくる半圓形には、庭苑のやうな豪奢な斜面が数知れず造られてゐた。そこには、空想のそよ風に愛撫されてゐるかのやうに、波打ちゆらぐ無數のアメリカの蔓草があり、東邦の薔薇があり、また、香気を放つ露を花瓣に散らし、雌蘂もきららかに、流動する織物に寶石を鏤めたやうな葉をもつ、西インド諸島の花々があつた。この色彩のナイヤガラ瀑布ともいふべき壮観はまばゆいばかりであつた。フロリダ州や南アフリカ沿岸地方に棲む鳥のむれがこの人工の群芳の上を飛び交ひ綾なす色に煌いてゐた。この造花を植ゑてある玉蟲色の半圓形は、廣間のこの部分で、燦爛と輝き二彩の光を放つて満ち溢れ、圓形の壁の目に見える半ばあたりと覺しき高さから、花園の中央に据ゑられた雪花石膏の水盤の土臺のところまで流れ落ちてゐたが、その水盤の中からは、すらりと迸る吹上げの水が雪のやうに白い雨となつてふりそそいでゐた。(齋藤磯雄訳) トールキンの簡潔な文体とはよほど異なる、それ自体が目も綾な美文に象嵌されているが、ここには林立する円柱にほどこされた自然の植物を模した装飾(アール・ヌーヴォーの意匠を思わせる)、「金」の「ランプ」の輝き、「寶石を鏤めたやうな葉をもつ」人工の花々が勢揃いし、雪花石膏/大理石(同じものである)の水盤も白銀の噴水も欠けてはいない。ナイチンゲールの歌さえも――声だけで姿の見えないこの鳥は実は二週間前に死んでおり、遠く離れたエディソン邸の、金属板に刻み込まれた鳥の「魂」を再生する蓄音機から洞窟の蘭の中まで線が延びる「接続された鳥」であって、いつわりの昼に流れる夜の調べは天然にまさる美を持つ人工の花から出ている(ハダリーの得ていた“生命”の仕組みをこれ自体がなぞっていることはいうまでもなく、物語の行く手に皮肉で不吉な影を投げかけてもいる)。ついでに言うなら、ナイチンゲールはミルトンの『失楽園』でもさかんに鳴いている鳥である。トールキンの小夜啼鳥(ローメリンディ)もまた楽園から来たもので、彼はそれをローリエンの庭に、また、メリアンがシンゴルを捕獲したナン・エルモスの森に、要するにエディソンのそれに劣らぬ人工的な世界に放したのだろう。
なお、『シルマリリオン』幕開けの「アイヌリンダレ」[アイヌアの歌]で、創造神イルーヴァタールの前で精霊アイヌア(彼らの一部がヴァラールになって地球へ行く)が楽を奏でる際、メルコールひとりが不協和音を発するのは、ボードレールの「我ト我ガ身を罰スル者」の詩句――「私は神聖な交響楽の中の不協和音ではないか」――に由来するのではないかと平野は言っている。また、楽園に二本の木――何のパロディかは言うまでもない――が用意され、鉱物でありながら「生けるもの」でもある三箇の果実シルマリルが奪われるという見え透いた(?)事件――シルマリルは父子の「愛の結晶」としての「罪の証し」であり、フェアノールが「食べた」〈父〉でもあろう――において、メルコールとともに表には出せない罪を上演してみせる牝蜘蛛(これについてはブログ「アルダの歩き方」で平野が書いている「あらすじ―その1」に詳しい)は、まさしく「我ト我ガ身を罰スル」女ではないかという。実証する手立てはないものの、状況証拠は揃っていると思う。
これにならってさらにボードレールの痕跡を探すなら、「サレド女ハ飽キ足ラズ」を含む、詩人の“黒い”恋人ジャンヌ・デュヴァル詩篇も、“飽くことを知らない女の情欲”を演じるウンゴリアントにはふさわしいのではないか(トールキンにかかると、裸体に飾った宝石がちりちり触れあって音を立てる女が、宝石を貪り食らう蜘蛛に変身してしまうということでもある)。また、先に引いたメネグロスの、玄武岩の岩屋めいた室内や柱廊は、同じ詩人の「前世」のレトリックを、また生きた植物を残らず追放した「ANYWHERE OUT OF THE WORLD」で言及される、鉱物の都市を思い起こさせはしないだろうか。反自然、反生殖の冷ややかな宝石づくしや人工楽園なら、ボードレールの十八番[おはこ]である。「この地では、色褪せるものも萎れるものもなく、花にも葉にも一点の傷もなかった。また、生あることが病むことも堕落することもなかった。なぜなら、石や水に至るまで聖められていたからである」(『シルマリリオン』第一章「世の初まりのこと」)という描写を読むと、そもそもこれらの花や葉は生あるものとは思われず、また、生き物が飲んで無事でいられる水でもなさそうで、不老不死の人形としてのエルフが無時間の箱庭世界で生き生きと動き回り、電気仕掛けの二本の木に美しく照らし出されていたとしか思えない(『シルマリリオン』を映像化しようとする奇特な人は、特に世界の初まりはぜひそのように撮っていただきたい)。星空の下の中つ国に生命の循環はなく、その中でのエルフの目覚めはあたかも電気のスイッチが入ったかのようだ。この時周囲に食べられるものなど、まずなかったはずである(そもそも『シルマリリオン』におけるものを食べる描写の少なさはただごとではない。ウンゴリアントの大食いは例外中の例外で、ホビットなどとても生きられない)。ノルドールが中つ国に戻って月と太陽が生じてのち、はじめて人間的時間が流れ出すのであり、その原因こそエルフの父子の“堕落”であるのだ。
トールキン自身が否定、秘匿したこともあって、古代神話や伝承以外からの影響を云々されることがなく、偏屈でアナクロニックな言語学者が同時代の文学からは隔絶して作り上げた異世界のように、また、トールキンから現代のいわゆるファンタジーがはじまったように言われるのがつねだけれど、さもトールキンが祖であるかのように称される要素の多くは彼のオリジナルではなく、本当にトールキンを特徴づけるものは大部分の読者には見えないのだから継承しているはずもない。だが、少なくともトールキンがボードレールを読んだことがないとは考えられない。『悪の華』に顕著なロマン主義的モチーフは『シルマリリオン』にも流れ込んできているのであり、同性愛も近親相姦も叛逆天使も陰鬱な美青年も(ミルトンのサタンをボードレールは男性美の典型と呼んだ)、意匠として彼以前にすでに存在し、彼はそれを見出し、変形し、利用したのだ(他の作家と同じように。そして彼自身のやり方で)。「“父子愛”と囮としてのヘテロセクシュアル・プロット」でも書いたが、世紀末美術からの影響も実証的に解明されるべきだろう。
話を“The History of Middle Earth”に戻すと、第I巻の“原シルマリリオン”と言うべき「失われた物語の本」の当該箇所をあたってみると、単純にシルマリルを追って中つ国へ渡るフェアノールが本当に存在することが早くも判明した。いや、ここではまだMiddle-EarthでなくGreat landだし、Noldorでなく Noldori、MelkorもMelkoだが、フェアノールはシルマリルを作っており、彼の父は現行の『シルマリリオン』同様、引越した先の家の前でメルコに殺される。しかし彼はフィンウェではない。確かにノルドーリはフィンウェ(フィンウェ・ノルメ)という王を戴いてはいるが、フェアノールは彼の息子ではない。兄弟喧嘩の話は(もちろん父の再婚も)存在せず、メルコはメルコール同様、ノルドーリを虚言で扇動するが、その結果フェアノールが罰せられるわけではない。クリストファーが註釈で次のように述べる通りだ。
『シルマリリオン』では、ノルドールの公子たちの諍いの審理の結果、メルコールの隠された悪が白日の下にさらされるが、ここでは悪の暴露はもっと簡単に、民の不穏な動きをフィンウェ・ノルメが心配したことから起こる。[...]『シルマリリオン』においてフェアノールがフォルメノスへ追放される――フィンウェがそこまでついて来る――話の萌芽がこの物語にはあるけれど、ここではノルドーリ族全員がコール[鈴木註;現行のティリオンに相当する都]を離れて、ヒリの流れが地下に潜る北方の岩の多い谷間へ行くよう命じられるのであり、この命令はマンウェによって与えられた罰というより、警告と自衛のためのように見える。 つまり、同族がそろって都を離れて北方の谷間へ移るのであり、のちのフィンウェのようにひとり突出した(それだけ異常さのきわ立つ)行動に出るわけではない[註]。また、刊行版と同様、メルコは祭の日に襲撃をかけるが、その際「戸口の前」では多くのノルドーリが殺害され、フェアノールの父ブルイスウィルはその一人であるにすぎない。フェアノールはむろん父の死を悲しみはするが、彼がメルコを追って行く目的は、まさしく奪われた宝石を取り返すことである。
もう一つの大きな違いは、メルコがノルドーリを襲った時はまだ蜘蛛を連れておらず(代りに、マンドスの館で手なづけた“gloomy spirits”とやらを従えている。ノルドーリが引っ越す一方、メルコは姿をくらますのではなくマンドスの許に戻されているから、後年のヴァージョンのようにフェアノールに会いに来る暇はなかった)、この時はまだ二本の木は手つかずであることだ。彼は奪った宝石を餌にして「ウンゴリアンテ」を仲間にするが、クリストファーも書いているように、「この物語では、ノルドーリの宝が失われた後にかなりの時間が経過したように見え」、「そのあいだに(...)フェアノールはシルマリルを再び造ろうと空しく試みた。」フェアノールがGreat land行きを主張して演説する時、二本の木はなおも輝いている。
つまり、運命の日の、あの真に感嘆に値する展開――二本の木が損なわれてヴァリノールが闇に沈み、ヴァラールの審判の輪[リング]でフェアノールがヴァラールからシルマリルを開くよう求められ、拒んでいるところにフィンウェ殺害とシルマリル強奪が伝えられる――はまだ無かったわけだ。それどころか、二本の木とフィンウェとシルマリルは、現在星座をかたちづくる星々も時間を遡れば無秩序に散開して見えるはずなのと同様、すでに存在しながら関連づけられていない。ブルイスウィルがメルコに殺されたのはなんと「宝石を守ろうとして」であるが、なるほどこの無理のない理由こそ本来のものであったろう。刊行版のフィンウェについて、「シルマリルを守ろうとして死んだ」という記述をガイドブックのたぐいで見たことがあるけれど、「彼だけが〈暗きもの〉の恐怖に打ち勝ったからである」とのみ説明されている戸口の前でのフィンウェの死が、もはや、そのようなものでありえなかったのは確かである。
「失われた物語の書」では、ヴァラール(古いヴァージョンでは多くの場合“Gods”と呼ばれている)から、二本の木を甦らせるためにシルマリルを開いて銀と金の混じり合った光を取り出せとフェアノールが言われることもない。だいたい、シルマリルの光を容れているのはただのガラス(いくら“such perfect glass he alone could make”にしても)で、光の方は、まだシルピオンと呼ばれていた銀の木の“radiant dew”や、金の木ラウレリンの光の一滴“a tiny single drop of the light”も使われてはいるが、それ以外にもさまざまなものから抽出した光を混ぜ合わせた“magic lights”であり、シルマリルが三つなのはフェアノールが三箇作ったところで材料が尽きたからである。ノルドーリの宝石作りは後年の純然たる工人のしわざではなく、星の光や花びらの露や花の絞り汁で染めたガラス――クリストファーの言う“magic material”――を用いての手作りで、トールキンが自分の子供たちのために創作した物語や、『ホビットの冒険』の雰囲気に近いと言えよう。たぶん後年とは“絵柄”も違うのであろう。
ついでに言うと、初期のベレンとルーシエンの話も、ルーシエンには魔女の面影が濃く、ベレンはエルフである(人間でなく)が現行よりさらに使えない奴で、ルーシエンの婿になるためシルマリルを取りに行ったものの、メルコの手下のサウロンならぬ猫の親玉の奴隷にされて、台所の下働きをしている(水汲み、薪割り、猫たちのための小鳥の串焼き作りに追われ、自分はろくに食べられず寝るひまもない)。そこへルーシエンが助けに来るわけで、狼でなく猫の毛皮にベレンは縫い込まれてモルゴスの玉座の下に這い込む(あの情けない着ぐるみ犬、いや狼の行動にようやく納得が行った)。モルゴスの鉄の王冠からシルマリル一箇を外すのも、キッチンナイフを使ってである。なかなか楽しい話なので、この部分だけを才能ある作家にアニメーションにしてもらってもいいと思う。少なくともトゥーリンの話を実写でやろうなどというのよりはずっといいし、それ以上に見てみたい気がする。
閑話休題。だからこの〈原シルマリル〉は、ヴァラールによって聖別されないし、「アルダの運命、大地、海、空気が」その中に閉じ込められているとも、死すべきものや悪しきものが触れれば手が焦げるとも、「太陽が作られる以前に世を去り、今は世の終わりを待つマンドスの館に坐して、同族の許にはもはや帰らぬフェアノールが戻ってくる日まで、太陽が消滅し、月が落ちるその日まで、シルマリルがいかなる物質で作られたかは知る術もない」とも言われない。要するにそれはまだ、心臓が裂けても言えない〈秘密〉を閉じ込めてはいないのだ。それを破壊することなど絶対に考えられない、父の生ける複製――『シルマリリオン』では、シルマリルを破壊すれば自分も死ぬことになるとフェアノールが主張しているうちに、本物のフィンウェが「戸口の前で」血を流して死ぬことになる――ではなく、もはや宝石の中にしか存在しない、日月以前の(銀と金の光が分かれていない)両性具有の光、「理性から分離していない芸術の光」(例のウォルドマン宛の手紙にある言葉)がそれに生命を与えているのではまだなかった。つまりトールキンはまだ彼の主題を見出していなかったのである 。
このあたり(「メルコの盗みとヴァリノールに暗闇が訪れたこと」)の話について、クリストファーは次のように書いている。
後年の話に見られる、メルコールの第一の動機であるシルマリルへの欲望は、ここでは、ノルドーリの宝石一般に対する欲望としてのみ表現されている。シルマリルは存在するものの、相対的に低い重要性しか与えられていないのが、オリジナルの神話の非常に目立つ特徴である。メルコが攻撃の標的にするのがノルドーリであるところは後年の物語と本質的に一致しているし、メルコが使う論法は、限定されているとはいえ、よく似ている。エルフはヴァラールによってヴァリノールに閉じ込められている、東方の広大な土地はエルフに所有権がある、と彼は言うのだが、メルコの言葉には明らかに、人間が到来することへの言及が欠けている。 要するに最初のうちはシルマリルの物語でさえなかったわけだ。メルコ/メルコールがノルドーリ/ノルドールにもたらした不穏状態は、人間が到来することへの言及(現行版では存在する)を併せるなら、ミルトンの『失楽園』で、神が新たな世界を用意して新たに誕生する人間を住まわせるという噂が天使たちに引き起した動揺に似ているし、実際それが出典であるのだろう。メルコールは堕天使的なヴァラールの叛逆者だが、フェアノールも古いヴァージョンでは〈叛逆者〉としての性格がより強いようだ。フェアノールがロマン主義的英雄の面影づけをされる一方、悪事を重ねるにつれメルコールは道化になってゆく(ティリオンで言葉巧みに不和と叛逆の種を播く彼は、信頼に値する立派な姿をしていると思われるが、蜘蛛と一緒にヴァリノールの平原へ降りてくるところではマンガ的な三頭身でよさそうだ)。彼らはいろいろな意味で、実は互いの分身と考えられる。一つだけ挙げておくなら、現行の『シルマリリオン』でフェアノールは、メルコールの訪問を受けて中つ国へ逃げる手助けをすると誘惑された際、「わが門から去れ、汝、マンドスの囚人よ!」と言って彼を退ける。しかし、「マンドスの囚人」とは、公式にはアマンの地を離れてはならない刑余の身のメルコールであるとともに――いや、メルコールはすでに刑期を終えているのだから、それにもまして――現に都ティリオンの外に追放されてフォルメノスにとどまる、そしてシルマリルを持って楽園ヴァリノールそのものから出て行きたいと思っている、フェアノール自身ではないか。
だから、「かれを助け、かれをこの狭隘なる土地より遠く連れ出すであろう」と戸口で言っていたのは、むしろフェアノールのアルター・エゴであり、フェアノールは中つ国へ――シルマリルを携え、父を置いて――脱出する相談を、自分自身としていたことになる。目撃したフィンウェが「非常な恐れに襲われ」、マンウェに使者を送ったのも当然だ。(原)「クウェンタ・シルマリリオン」にも同様の場面はあるが、そこではフェアノールはモルゴス――と表記されている――の鼻先で「心をではないにしても扉を閉ざし、フィンウェはマンウェに使いを送ったが、モルゴスは怒って去った」とあるだけだ。現行の『シルマリリオン』を読んだ者が思うであろう、メルコールの怒りを買った息子の身を案じてフィンウェが通報したという解釈は、古いヴァージョンにおいてはまさしくその通りなのである。
興味深いのは、兄弟の不和という要素が入ってきてもなお、異母兄弟というアイディアが欠けていることだ。そのためにはフェアノールの母ミーリエルを死なせる必要があったが、至福の国でエルフを死なせるというのはそれだけで大変な事だったのである(人間の読者には見過ごされるにしても)。シルマリルを開くよう求められた時、フェアノールは「私は殺されるでしょう、全エルダールの中で最初に」と言うが、これは最初“I will die”だったのを、ミーリエルが最初の死者になったので、トールキンが“I shall be slain”に変更したのだという(第X巻268-269ぺージ。なお、日本語版では「私は血を流して死ぬでしょう」と説明的に訳されている)。「イルーヴァタールは、御自身のほかには準備し給うたものすべてを明かし給うわけではなく、どの時代にも、過去から継続しているわけではない新たな予測しがたい要素が出てくる」と本文にあるが、それと同じ「新たな予測しがたい要素」がここで出現した――だが、ひとたび現われてみれば、それは必然的な要素だったに違いない。メルコールのフィンウェ殺しは“the first murder”という明白な悪の指標のはずであったが、ミーリエルがアルダにおける最初の死者と定められたのと恐らく時を同じくして、新たな真の罪が隠されることになったのだろう(ミーリエルがなぜ死を願ったか――未来に何を予知したのか――も同様に隠されている)。トールキンの中断された小説『失われた道』については「“父子愛”」で詳しく述べたが、そこで描かれた「早くに妻を亡くし、細君に悩まされない」父子関係が、かくして場所を変えて再現されたのだ(フィンウェの再婚には別の理由がある)。中断された物語を、彼はそこまで自分が営々と書きつづけてきたコーパスを使って――その上に重ね書きすることで――続けることになる。
『失われた道』は「ヌーメノールの滅亡」と並べて第III巻に収められ、クリストファーによる短い前書きを付されているが、そこで彼は、父の発言の或る箇所にこだわっている。トールキンは1964年に書かれた手紙で、1936年頃にC・S・ルイスとの会話から生まれたこの未完の作について語り、(書いているうちに)自分の真の関心はヌーメノールの滅亡にあることがわかったので、「だから、それまでに書いた中でヌーメノール伝説にそもそも関係のなかった材料はすべて、メインの神話に関連づけることにした」(...so I brought all the stuff I had written on the originally unrelated legends of Numenor into relation with the main mythology.)と言っている。
トールキン作品について詳しくない方のために少々説明すると、「ヌーメノール伝説」というのは、「シルマリリオン」で扱われた時代の後に来る、中つ国の西海にあった「ヌーメノール」という島で栄えた人間の王国の話で、時間的にも物語的にも『シルマリリオン』と『指輪物語』をつなぐものだ(正確に言えば『シルマリリオン』という本のうち、シルマリルをめぐる物語が終ったあとの「アカルラベース」の章で語られる)。最後には神の怒りでヌーメノールは海底に沈み、『指輪』でおなじみのサウロンが目だけなのはこのカタストロフの際に肉体を失ったからで、また、この時、中つ国へ逃れた王家の裔がアラゴルンである。アトランティス伝説に重ね書きした、海に呑まれての滅亡の悪夢は、トールキンに長年取り憑いていたものらしい。ここでは手紙の相手に向かって、『失われた道』を書いているうちに自分の真の関心はそっちにあることが判明した、だから中断して云々と言っているわけである。
クリストファーはこの手紙の一節について次のように書いている。確かに『失われた道』は序章(現代から時を遡ってヌーメノールへ戻る父子の話)のみで放棄されているので、前半は理解できるが、「しかし、“だから、それまでに書いた中でヌーメノール伝説にそもそも関係のなかった材料はすべて、メインの神話に関連づけることにした”とはどういう意味だろうか」(強調は原文)。
父はこう言っているようだ――自分はヌーメノールについて書きたいだけなのがわかったので、その時にだけ(『失われた道』を放棄して)ヌーメノールの素材を「メインの神話」に加え、かくして世界の第二紀を開始した、と。しかし、この素材とは何だったのか? 『失われた道』に含まれていたヌーメノールに関する内容のつもりだったはずはない。それはすでに完全に「メインの神話」に関連づけられていたのだから。 だからその素材とは“何か他のもの”であったに違いないとクリストファーは言い、次のように述べる。
『失われた道』はヌーメノール最後の時代のエレンディルと息子ヘレンディルの会話の途中で結局中絶するが、エレンディルはその中で古代の歴史について――モルゴスとの戦いについて、エアレンディルについて、ヌーメノール建設について、サウロンがヌーメノールにやって来たことについて――かなり話している。『失われた道』はそれゆえ、私がすでに述べたように、全面的に「メインの神話」に統合されている。 それゆえ手紙に書かれたようなことは成り立たない、父トールキンの勘違いであったろうと、彼はあっさり断言するのだ。それ以前の草稿についての短い検討の後、クリストファーは最終的に次のように書いている。
1964年の手紙の一節は次のように読むことができよう――「私は中断することになる時間旅行の本を書いたが、その最後で主人公はアトランティスの水没に立ち会うはずだった。それは西の陸地を意味するヌーメノールと呼ばれるはずだった」。さらに、「ヌーメノール」は初めから「シルマリリオン」と完全に結びついて構想されたのであり、ヌーメノールの伝説が「メインの神話と無関係」だったことなど一度もないのだ。(強調は原文) 四ページにわたる前書きは、「引用した手紙は三十年近くあとになって書かれたのである」と、時間の経過に伴うトールキンの思い違いであろうことを強調して終る。
しかし――「“父子愛”と囮としてのヘテロセクシュアル・プロット」をすでにお読み下さった賢明な読者はすでにお気づきであろうが――「メインの神話」にそれまで存在せず、この時はじめて現われた“何か他のもの”、「新たな予測しがたい要素」、すなわち『失われた道』を放棄したトールキンが“本篇”に織り込むことになった素材は確かに存在する。それはエレンディルの語る「古代の歴史」にはまだ含まれなかったもの、彼とその息子ヘレンディルについて書くことで、トールキンが手に入れたものである。トールキンは思い違いなどしていない。実際彼は、ヌーメノール伝説として/に托して途中まで書いたものの、そもそもヌーメノール伝説には関係のなかった材料を、「メインの神話」に投入したのだ。それは“父子愛”の主題であり、彼はイギリスの大学教授とその息子の遥かな過去への時間旅行という回り道をしたのちに、そもそもこれはヌーメノール伝説には関係なく、むしろ作品全体の中心となるべき主題だったと(たぶん、あらためて)気づいたのだ。トールキンは「メインの神話」にそれを回した。その結果、フィンウェとフェアノールは今日私たちの知る彼らになったのであり、その影響はアルダの地殻変動さながら作品全体へ波及して、現に私たちの見る『シルマリリオン』が生成することになったのだろう。
【註】その後の変遷(の一部)を見ると、“The History of Middle-Earth” V巻所収の「後期ヴァリノール年代記」には、メルコールに焚きつけられての兄弟の不和ののち「フィンウェとフェアノールはトゥーンの都を発ってヴァリノールの北に住まった」とあり、(原)「クウェンタ・シルマリリオン」では、「神々の裁定によりフェアノールはしばらくの間、平和を乱した廉でトゥーンを追放された。しかし、彼を他の息子より愛していた父のフィンウェは一緒に行き、他の多くのノーム[ノルドール]も一緒に行った」とあって、後者はやはり集団移住だし、何よりフィンウェはフェアノールと「一緒に」行ったのであり、あとから追って行ったのではない。刊行版では、追放されたフェアノールは都の北方フォルメノスに七人の息子たちとシルマリルを持って移り住み、「フェアノールへの愛に惹かれ、王フィンウェもそこへ来て住まった」。現身の「アリシヤ」をあきらめて「ハダリー」(に相当するシルマリル)と一緒に中つ国へ行くことが望みのすべてになっていたフェアノールは、思いがけなく追ってきた父に、恐らくはつれなく振舞った。フェアノールに門前払いを食わされたメルコールは「復讐の時がまだ熟しておらぬことを看て取った」とあるが、では、「復讐の時」はいったいいつの間に熟したのか。息子がメルコールに中つ国へ誘惑されるのを見て震え上がったフィンウェは、助けを求めてヴァラールに使者を送った。だが、それだけではなかろう。自分を置いてフェアノールが中つ国へ行ってしまうのを恐れたフィンウェが何をしたかは書かれていない。唯一わかっているのは、メルコールが来た時にはまだ起こっていなかった何かが、このあと起こったということだ。かくして復讐の時は熟し、二本の木とフィンウェとシルマリルが一度に失われて、フェアノールに〈夜〉が訪れたのである。
※例によって本文の訳は基本的に『シルマリルの物語』(田中明子訳)に頼ったが、わずかに変更した箇所がある。
★プロフィール★(すずき・かおる)ボードレールのことを平野さんに言われ、自室で『悪の華』を探したが原書しか出てこない。「我ト我ガ身ヲ罰スル者」を見ると、異同のある詩句については全ヴァリアントが欄外に載せられ、巻末の註釈には発想源、引用、模倣、剽窃の可能性のある出典が並んでいる。タイトル(原文ラテン語)はトマス・ド・クィンシーの英語テクストに嵌め込まれた一語であり、結びの「永遠の笑いの刑に処せられてもはやほほえまない」はポーの詩「幽霊宮」から来ているという。『シルマリリオン』についてこういう本がほしかった! もちろん、全ヴァリアントをなんて言っていたら『シルマリリオン』は出なかったろうけれど、電子化されれば……しかし大変な作業には違いない。十代の頃、入澤康夫の自らの詩への“自註”を見て、言葉が「私」の「内面」の表現ではないことを理解したっけ。T・S・エリオットの場合、「廃墟を支えてきた断片」への自註は韜晦として働いており、タロットの溺死した男の背後にはダーダネルス海峡で戦死した友人(「ヒヤシンス娘」の正体)がいると、“T. S.Eliot's Personal Waste Land”でジェイムズ・E・ミラーは言う。(もちろんそれが唯一の“真実”ではなく、事実も文献も同列であり、書かれた人生は紙の上の人生であるということだ。)トールキンの世界で金髪のエルフは神々に愛される優等生であり、面白みのないヴァンヤール族である。別に、背後に黒髪で灰色の目の男を探したいわけではないが(そういう話が出てきたら面白いが)、トールキンについてインターテクスチュアリティが無視されてきたというのは、普通に文学者として扱われてこなかったからだろう。『悪の華』の翻訳、どれも原文を見た後ではこれは違うだろうとしか思えないが(和歌の英訳を読むようなもの)、しかし、ほんの数ページ眺めただけで、個々の詩に限らずこれがトールキンの美意識の一部をかたちづくったに違いないという確信が香気のように立ちのぼる……。外国語を読んでいると紙の上を這い回るしかないが、日本語は有難い。「中つ国の歴史」の翻訳があれば本当に有難いのだが。「映画館の日々」「新・映画館の日々」と題して連載してきたが、映画についてさっぱり書かなくなったので内容に合わないから変更をという編集人の意向もあり、本号から「鈴木薫の研究手帳」にタイトルを変えてみた。何かを専門に研究しているわけではないのでこれはジョークのようなもの。
ブログ「ロワジール館別館」
Web評論誌「コーラ」12号(2010.12.15)
「鈴木薫の研究手帳」第1回:“中つ国の歴史”を読みながら――重ね書きされた『シルマリリオン』(鈴木 薫)
Copyright(c) SOUGETUSYOBOU 2010 All Rights Reserved. |
| 表紙(目次)へ |