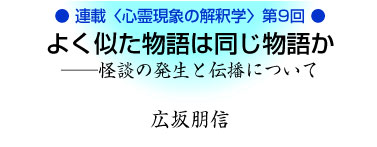|
|
|
Web�]�_���u�R�[���v |
|
���n���̎� ���{���̕\���i�ڎ��j�� ���{���̃o�b�N�i���o�[ ���ǎ҂̕Ł^���ӌ��E���z �����e�K�� ���W�҂�Web�T�C�g ���v���C�o�V�[�|���V�[ |
|
���{���̊֘A�y�[�W�� |
|
���u�J���`���[�E�������[�v�̃o�b�N�i���o�[ ���]�_���u�k�� Vue�v�̑��ڎ� |
Copyright (c)SOUGETUSYOBOU |
|
|
|
�@�O��i�A�ڑ攪��A�{��26���j�A�u���k�̉��ߊw�̖ڎw�����̂́A�̌�����镨��̗ތ^�����ꂽ�̌��ɗ^����e�����A���b�w�Ȃǂ��Q�l�ɂ��Ȃ��璆�a���A�u�悭����b�v�u�悭��������v����̌��̈ٗl�����~�o���邱�Ƃɂ���v�Ƒ匩��������B�匩�����Ƃ���܂ł͂悩�������A�������炪��ł���B�����g�A����ł͂ǂ�������̌��̈ٗl�������o����̂��A���������čl�������˂Ă���B��������͎�T��ōl���邱�ƂɂȂ�̂ŁA�����̘_���̔��͂���܂ňȏ�ɂ��e�͊肢�����B
�@
�悭�����悭�����b�\�\�^�N�V�[�H��
�@�̌��k�Ƃ͑̌��҂̎��_�ōč\�����ꂽ����ł���Ƃ������Ǝ��̂́A����܂ł��悭�m���Ă����B�����ŁA�̌��҂̌�镨���ʂ��ďo�����ɔ��낤�Ƃ��鎎�݂́A�����̏ꍇ�A���ꂩ��̌��ҁi����j�̊֗^�̓x�������ł��邾�����߂邱�Ƃŏo�����̋q�ϓI�ȕ`�ʂɋ߂Â��邾�낤�Ƃ������ʂ��̂��Ƃɍs���Ă����B�܂�A����̂Ȃ��̑̌��ҁi����j�̈ӎu�⊴��ɉe������₷��������r�����A�܂��A��O�҂̎��_�ɗ����Ă�����̑S�̑��ɕω����Ȃ����ǂ������`�F�b�N����Ƃ����������B
�@�������A���ӂ��ׂ��Ȃ̂́A�o�������č\������̌��҂̎�ϐ��ł͂Ȃ��A����̕��Ȃ̂ł͂Ȃ����B
�@��Ƃ��āA�u�������q�v���邢�́u�^�N�V�[�H��v�Ƃ����̂�����蕨�ɏ��H��Ƃ̑����k���l���Ă݂悤�B
�@����Ƃ悭�����b�͓��{�S���ɂ���B�C�O�ɂ����邱�Ƃ��m���Ă���B�������b�̍ו����������q�̍s����Ȃǂ̌ŗL�����͂��ꂼ��Ⴄ���A�悭�����b�̐��͑����B�����w�������k�f�B�e�N�V�����x�i��ъ�1998�A���ݐ�Łj�ł��ӂꂽ���A���J�݂�q�w���㖯�b�l�V�U�D�ԁE�D�E�����Ԃ̏��Ɖ��k�x�i�������[�j�ƃu�������@���w�������q�b�`�n�C�J�[�x�i�V�h���[�j�Ƃ����킹�ǂ߂A���̗ޘb�̑����A���z�̍L���ɁA������ʂ�z���ĕ��ꂩ����l�����邾�낤�B
�@�e�n�Ŏ��b�Ƃ��Č���Ă���u�������q�v����A�̌��҂̎�ϐ��ɉe�����ꂽ�Ǝv���镔�������������Ƃ��Ă��A��q���ˑR�������A�Ƃ����_�ɂ͕ω��͂Ȃ��B����ǂ��납�A��������������������ȏ�A�������̌l�̌��z�ł��邱�Ƃ͂��蓾�Ȃ��Ƃ������Ƃ��l������B����͂���ł悢�Ǝv���邩���m��Ȃ����A�q�ϐ����d�����闧��͉Ȋw��`�ƌ��т��Ă���̂ŁA�H��̑��݂�F�߂邱�Ƃ�O��ɂ͂ł��Ȃ��B�����ŁA���s���̎ԓ������q��������i�Ɖ^�]��Ɋ�������j�Ƃ������ۂ��܂�ɋN����炵���A�Ƃ������Ƃɂ����Ȃ�Ȃ��B����ʼn������������ꂽ�Ƃ����邾�낤���B
�@�u�������q�v�͒n���I�ɍL�����z���Ă��邾���ł͂Ȃ��B���ɋ�����b�͍]�ˎ��㏉���ɂ͂��łɐ������Ă����Ǝv����M���~�`���̃o���G�[�V�����̈�ł���B
�@�^�N�V�[���n�ɂȂ��Ă��邪�A����̊�{�I�ȋؗ��Ă͓����ł���B��������̘b�ɂ͐l�͎Ԃɏ�����P�[�X������B
���@��蕨�ɏ�������Ă���B
���@���͖ړI�n�ɒ����Ǝp�������B
���@���͂��̐��̂��̂ł͂Ȃ������B
�@����Ɠ����p�^�[���̕���́A�ǂ��܂ł����̂ڂ�邩�͂킩��Ȃ����A���j�I�ɂ����Ȃ�Â�������ꑱ���Ă����̂ł͂Ȃ����Ɛ��������B
�@
����Ƃ������A���e�Ƃ�����
�@���āA�����悤�Șb���e�n�Ō��p����Ă���ꍇ�A�I���W�i���̕��ꂪ����A���ꂪ���������ꏊ�ɉ����ĕό`����Ȃ���`�����Ă������ƍl����̂���ʓI�ł���B��ɋ������u�F�{�嗝�������A�������S���̎��v�́A�������q�̋ߐ��o�[�W�����ł���ƂƂ��ɁA�M���~�̕ό`�o�[�W�����ł�����̂����A���̎M���~�̏ꍇ�͍]�ˎ��ォ�炷�łɃ��[�c�T�����n�܂��Ă���A�����Ƃ��悭�m���Ă���Ԓ��i���݂̓����s���c��j�̎M���~�͔d�B�i���݂̕��Ɍ��P�H�s�j�̎M���~�`���̃o���G�[�V�����ł��낤���Ƃ������Ă����B
�@�������A�K�������A�Ԓ����d�B���̂����ꂩ���M���~���k�̃��[�c�ƒ�߂Ȃ��Ƃ��悢�̂ł͂Ȃ����B
�@�����܂ł��Ȃ��M���~�Ƃ́A��ɍ]�ˎ���̕��Ɖ��~��Ƃ��Č����`���ŁA�M���������i���������j���ǂʼn��~�̎�ɎE���ꂽ�i��˂ɓ������܂�ĎE���ꂽ�E�E����Ă����˂Ɏ̂Ă�ꂽ�E�ӂ߂��Ĉ�˂ɐg�𓊂����j�����̖S�삪�A��˂��猻��ĎM�̐��𐔂���Ƃ������́i���@���G�[�V�����͂���������j�B�H�c�E��肩�玭�����܂ł̓��{�e�n�ő哯���ق̕��ꂪ���̒n�Ŏ��ۂɂ��������ƂƂ��ē`�����Ă���B�ɓ��āw���{�̎M���~�`���x�i�C���Ёj�ɂ́A�e�n�̂����n�M���~�`���䂩��̒n�Ƃ��āA�O�\�����ȏオ�������Ă���B
�@���݁A�����Ŋm�F�ł���M���~�`���̌Â����͎̂��������w�i�ɂ������̂ł���B��������A�I���W�i���ȓ`�����������ゲ��ɒa�����č]�ˎ��㏉�߂Ɋe�n�ɓ`�d�����̂ł͂Ȃ����ƍl�����Ă����B�܂�A���݁A���`�����Ă�����̂̂����A�ǂꂩ����I���W�i���ŁA�ق��̓C�~�e�[�V�������Ƃ����z��ł���B
�@���������w�������k�f�B�e�N�V�����x�i1998�A���ݐ�Łj�\�������_�ł͂��̂悤�ɍl���Ă����̂����A���s���̌��ӂɊÂ��āw�]�ˉ��وٕ��^�x�i��Łj���������Ă���������ɁA�I���W�i�����ϗe���J��Ԃ��Ȃ���`�d���Ă����Ƃ������f���ōl���Ȃ��Ă��悢�̂ł͂Ȃ����Ǝv���悤�ɂȂ����B���������͎l�J���k�ł���B
�@�l�J���k�̃q���C���́u����v�i�h�̗��j�Ƃ������͏������Ƃ��Ă͂�������ۂ�^���邩�炾�낤���A���̖��O�ɓ��ʂȈӖ�������Ƃ����������B��\�I�Ȃ��̂��L�I�_�b�ɏo�Ă���C���i�K�q���ɂȂ�������̂��Ƃ������ł���A�܂��̕�����L�̖����@���Ƃ�����������B�����A����Ƃ������́A�]�ˎ���̏������Ƃ��Ă���قǒ��������̂ł͂Ȃ��A�Ӗ����炷������q�Ɉ���Ăق����Ƃ����肢�������ꂽ���̂��낤�B
�@���₪�X�������Ƃ����`���ɂ��āA�u����v�Ƃ������O�ƌ��т���l������B�܂�A����Ƃ͏X�����ɕt���閼�O�ł������A�Ƃ����̂ł���B
�@�v����ɁA�炪�X���A���i���ӌŒn�ŁA������Ǝ�ɕ����Ȃ��L�c�C���̖��O�́u��v�Ƒ��ꂪ���܂��Ă����Ƃ����̂��B�S�i�͂���Ɂu����̖��́A���Ԃ��ł͕v�ɗ����邩�A�v�𗠐�l���̖��ł������v�Ƃ��āA�u��v�Ƃ������O�͕���̒��ňɉE�q��̍Ȃ�������L�����N�^�[����A�z���Ă���ꂽ�𖼂ł��邱�Ƃ��������Ă���B
�@�܂��A�w���{�`��`���厖�T�x�i�p�쏑�X�j�́u����v�̍��i���r�͑��Y���M�@���P�U�T�`�P�U�U�j�ɂ́A�u����Ƃ������͓�k�̎ŋ��Ɏn�܂����Ƃ݂Ă悩�낤�v�Ƃ�����Ŏ��̂悤�ȋL�q������B
�@��k���V��̃q���C���̖��O�𑧎q�̓X�ŕ����Ă��鏩�W����Ƃ����Ƒz������̂��������낢���A���W�M���Ɂu����v�̖��O���������Ƃ����̂́A�̕���̐��E�ł͂����m�炸�A�����Љ�ł̓C���Ƃ������́A�s�H�Ő��i�̈������̖��O�Ƃ͌���Ȃ��������Ƃ������Ă�����B�e���̎ŋ��ɏo�Ă��鉻�����̂悤�ȏ����i���o�[�E�����E�z�X�e�X�ł́A���q�̓X�͂Ԃ�Ă����낤�B
�@�������A�S�i�������r�̘A�z���A���������k�́u�ŋ��v����ɂ��ĂȂ��ꂽ�����ł���A�����N��͕s���ł���ɂ���A��k�̎ŋ��ɐ旧���Ƃ͊m���ȁw�l�b�J�G�k�W�x����ɂ���A����͏��߂��炨��ł���B
�@���������A��Ƃ������O�͏����̖��O�Ƃ��Ă���قǒ��������̂ł͂Ȃ������B���̔N���̒m�l�i60��j�̂����̖����u����v���������B
�@���Ȃ݂ɁA�n�ꕶ�k�́w���쑭�k�x�i���N�j�ɂ́u�G����v�Ƃ����������o�Ă���B���̂���͍��Ð쓇���̗V���ŁA�G�̊G�̂������̂��D���߉G����ƌĂꂽ�Ƃ����B���������Ӂi�u�G�Ɩ���ĕM���ɖ��������̂���v�j�ŁA�e�F�s�ȏ��������������ł���B
�@�Ƃ�����A�u����v�Ƃ������ɓ��ʂ̈Ӗ��͂Ȃ��B����Ƃ���A�]�ˎ���̎l�J�ɁA�����������̏��������ۂɏZ��ł����Ƃ������Ƃ����ł���B����ł́u�M���~�v�̏ꍇ�͂ǂ����낤���B
�@�M���~�̃q���C���̖��́A��Ɍ��܂��Ă���킯�ł͂Ȃ��A�n��ɂ���Ă͕ʂ̌Ăі������邪�A�����Ƃ��|�q�����[�Ȃ̂͂�͂�u���e�v�ł���B���̂��e�Ƃ������ɂ��Ă��A���̐�����̌��ÂĂ��u�����v����]�������̂ŁA�܂�ޏ��̌��^�͛ޏ����Ƃ����������B�������A���e�Ƃ������O���]�ˎ���̏������Ƃ��Ă͂���ӂꂽ���O�ŁA���ꂪ�ޏ��I���i���������̌Ăі��ł���Ƃ���ɂ͂���Ȃ�̗��R���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@���e������ӂꂽ���O�ł���Ȃ�A�e�Ɩ����A���邢�͂��e�ƌĂꂽ�����͉��l���������낤�B�M�͗��Ƃ��Ί������̂ł���B���Ɖ��~�Ɉ�˂͕K���������B���e�A�M�A��˂̎�荇�킹�́A���Ɖ��~�̏W������鉺���łȂ�ǂ��ł�����������A�����Ȃ��Ƃ��������������������Ă����B�������Ƃ���A�]�˔Ԓ��Ȃ�d�B�P�H�Ȃ肪���Ƃ�����ʂȂ킯���Ȃ��B�Ԓ��Ɣd�B���M���~�̖{�Ƒ���������قǗL���ɂȂ����̂́A�����ς�ŋ���u�k�̉e�����낤�B
�@���̂悤�ɍl���Ă���ƁA�S���e�n�̎M���~�̂����A�ǂ������{�ƂŁA�ق��͂ɂ����̂ƌ��߂�K�v�̂Ȃ����ƂɋC�������B
�@
�悭��������͓������ꂩ
�@�����������悤�ȕ��ꂪ����ꍇ�A�����͂��ׂĂ��Ƃ��Ɠ������ꂪ�����̐l�ɓ`������Ă����ߒ��ŕό`�����o���G�[�V�����ł���ƌ��_���Ă悢�̂��낤���B
�@�悢�ꍇ����������łȂ��ꍇ������Ƃ����̂����̎咣�ł���B���̉���ɂ��ƂÂ��Ă��܂��܂Șb���r�������邱�ƂŐ��Y�I�Ȍ������s����̂ł���A����͗L�v�ȍ�Ɖ����Ƃ݂Ȃ����Ƃ��ł���B
�@�������A���܂�������ّ̌��k�ɂ��̍�Ɖ����ᔻ�ɓ��Ă͂߂�Ȃ�A����͉��ّ̌��k�̘b�҂��R���Ă�肷�邱�ƂɂȂ�B����͉\���B���͕s�\���ƍl����B
�@���݂ɁA��Ƃɋ߂�c�ƃ}���̒��x�݂̉߂������ɂ��ĕS�l���x�̉�Ј�����A���P�[�g���̂��Ă݂邪�悢�B���̂��Ȃ�̕������ŗL��������������̎����悤�Șb�ɕ��ނł���ɈႢ�Ȃ��B�����悤�Șb�͓����b�Ȃ̂��낤���B�����悤�Ȓ��x�݂̉߂����������Ă���c�ƃ}�������͓����l���Ȃ̂��낤���B
�@�������A���ׂẮu�^�N�V�[�H��v���k�������ɋN���������Ƃ��ƍl���Ă���킯�ł͂Ȃ��B����ǂ��납�A�^�N�V�[�ƊE�̓����ł��̎�̘b���������������Č���邱�Ƃ̕������Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ƃ���v������������B
�@����^�N�V�[�E�h���C�o�[�̘b�ɂ��A���������b�͂悭��������邪���Ԃ̒N�^�̐g�̏�Ɍ����ɋN�������b�Ƃ��Ă͕��������Ƃ��Ȃ��Ƃ����B�܂��A���^�N�V�[��Ђ̑����یW���ɂ��A�ނ͏�q�Ƃ̃g���u���A�Ƃ��ɗ����̕s����������������d����S�����Ă���A����̉^�]�肩�炳�܂��܂ȏ�����炳��邪�A���Ƃ�������ɂ���H��ɗ����ݓ|���ꂽ�Ƃ����b�͕��������Ƃ��Ȃ��Ƃ����B���W���́u���肪�H��ł��낤�Ɖ^���͐�������v�ƍ��ꂵ�Ă����B
�@������`������Ƃ���̏o���������ׂČ����ɋN�����Ă���Ƃ͍l���ɂ����B�������A����ɂ�������炸�قƂ�Ǔ����Ƃ����Ă悢���炢�ɂ悭�������ꂪ�J��Ԃ������B���̗��R�́A���ꂼ��̕���̌���i�̌��ҁj�������u����Ă���i�^�N�V�[�̐[��Ζ��j���悭���Ă������߁A�X�̑̌��̓����͈���Ă��Ă��A��������s���ȑ̌��������ۂɁA���̕s�������z���ł��鋭���͂�����������̘g�g�݂ӎ��̂����ɗ��p�����̂ł͂Ȃ����낤���B
�@��������ꂸ�ɂ����A�����̕���̘g�g�݂ɂ́A�����̐l�X�̂��ꂼ��قȂ����̌����قړ��������Ƃ��ċz������͂�����̂ł͂Ȃ����B�Ƃ͂������ꂪ������l�Ԃ𗣂�đ��݂���킯�ł͂Ȃ��B������A����ɑ̌����z������͂�����Ƃ����̂͂��̂̚g���ł����Ȃ��B�������A���������g�����ӂ��킵���Ǝv����قǎ����悤�ȕ��ꂪ�̌��k�Ƃ��Č���Ă���B
�@�^�N�V�[�H��Ɍ��炸�A���ّ̌��k�́A���ꂪ�̌��k�ł��邩����A���ꂼ��قȂ�̌��҂����ꂼ��قȂ�o������̌������͂����B����ɂ�������炸�ɂ悭��������Ƃ��Č���Ă��܂����̂Ȃ�A�����Ƃ����s�ׂ̂Ȃ��ɈقȂ�̌���������킹�鉽��������Ɖ��肵�čl����������R�ł���B
�@���́A�����悤�ȕ���̓I���W�i���̕���̃o���G�[�V�����ɉ߂��Ȃ��Ƃ��������́A���͈ꕔ�̖����w�҂̌o�����ɂ���Ɖ����ł͂Ȃ����ƍl���Ă���B�������A������Ӗ����Ȃ��Ƃ����̂ł͂Ȃ��B�����̕�����W�߂Ă݂�ƁA���̒��Ɏ���������b������������͎̂����ł���A���A�l�Ԃ̕����͂�����c�ޏ��Љ�W�c�̈ړ��ƌ��ɂ���ē`�����邱�Ƃ͖����Ȃ��z���ł��邩��A�I���W�i�����`�����邤���ɕό`���đ����̒n��Ńo���G�[�V�����Ƃ��Ďc��Ƃ��������ɂ�����͎̂��R�Ƃ��炢����B
�@�������A�o�����Ƃ��Ă͌ʂ̎������A�����\��������������̘g�g�݂Ō���邱�Ƃɂ���āA�����悤�ȑ̌��k�ɂȂ�B�o�������������̘g�g�݂�̗ތ^�ƌĂԂƂ���A�����̌𗬁E�`�d�ƂƂ��ɓ`����ꂽ�̂́A����̓��e�ł͂Ȃ��A����̗ތ^�̕��������A�Ƃ������Ƃ���Ɖ����Ƃ��ėL���ł͂Ȃ����낤���B
�@�قȂ�l�ɂ��قȂ�̌��ł����Ă���������̗ތ^�������Č��ꂽ�̌��k�͎����悤�Șb�ɂȂ�B�����l�ɂ�铯���̌��ł����Ă��قȂ镨��̗ތ^�������Č����ΈႤ�b�ɂȂ�B����͉����ł͂Ȃ��Ď����ł���B
�@
���v���t�B�[����
�L����M�i�Ђ낳���E�Ƃ��̂ԁj1963�N�A��������B�ҏW�ҁE���C�^�[�B�����Ɂw���^�l�J���k�@������w�l�b�J�G�k�W�x�x�A�w�������k�f�B�e�N�V�����x�A�w���k�̉��ߊw�x�ȂǁB�u���O�u���ȉƂ̌����\�v �@
Web�]�_���u�R�[���v31���i2017.04.15�j
���S�쌻�ۂ̉��ߊw����X��F�悭��������͓������ꂩ�\�����k�̔����Ɠ`�d�ɂ��āi�L����M�j
Copyright(c) SOUGETUSYOBOU�@2017 All Rights Reserved.
|
| �\���i�ڎ��j�� |