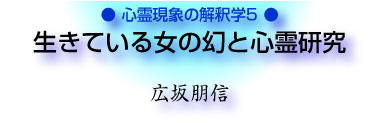|
|
|
Web評論誌「コーラ」 |
|
■創刊の辞 ■本誌の表紙(目次)へ ■本誌のバックナンバー ■読者の頁/ご意見・感想 ■投稿規定 ■関係者のWebサイト ■プライバシーポリシー |
|
<本誌の関連ページ> |
|
■「カルチャー・レヴュー」のバックナンバー ■評論紙「La Vue」の総目次 |
Copyright (c)SOUGETUSYOBOU |
|
|
|
当代一流の科学者たちが認めたのだから心霊現象は証明されたと誇らしげに語る人もいる。その一方で、一流の科学者ですら心霊術師のトリックに引っ掛かったのが嘆かわしいという人もいる。いずれの場合も、科学の役割を過大評価している。
カントは理論の暴走を経験によってたしなめた。エンゲルスは経験の過信は理論によって正すべきだと提言した。
この連載コラムの前々回で、私はヘーゲルのメスメリズム評価を検討しながら次のように書いた。
実はこの見解は私の創見ではなく、アンリ・ベルクソンの見解を真似たものである。英国心霊協会会長に就任したベルクソンは、「生きている人の幻と心霊研究」という講演を行い、後に自著『精神のエネルギー』に収録した。なお以下での引用は原章二氏の新訳(平凡社ライブラリー)によるが、講演タイトルは長年なじんだ旧・白水社版全集の邦訳タイトルを用いる。
当時のイギリスを代表する倫理学者シジウィックらによって設立された心霊研究協会は、どこぞの政府の審議会とは比較にならないほどのメンバーを集めていた。なぜ当時の知識人たちが心霊研究に関心を示したのかということ自体、思想史研究の一つのテーマとなりうると思うが、今回はそうした話題は扱わない。
この講演でベルクソンは、なぜ科学者たちは心霊研究は否定するのかという問いを立てている。科学者たちは、ある特定の心霊現象を否定するのではなく、心霊現象一般を研究対象にすることを否定する。その理由としては、そもそもデカルトに代表されるように、近代の自然科学は心的な領域を研究対象から排除することによって自らを成立させたからだという、わりと簡単な答えもあるのだが、ベルクソンはとんでもないことを言い出す。心霊現象は、自然科学の研究対象と原則的に同じ性格を持つものなのだ、というのである。
心霊現象は自然現象と同じだというのは、デカルトやカントとは違うベルクソン自身の「精神」観を考える上で興味深いものだが、本稿では先を急ぐ。心霊現象は自然現象と同じ種類の現象なのだから自然科学的研究の対象となるべきなのに、科学者たちがそれを忌避するのはなぜか。ベルクソンによれば、それは、現実の心霊研究の方法がいわゆる科学的方法ではなく「歴史家の方法と予審判事の方法との中間にあるもの」によってなされているからである。
このようにして得られた事実の確実性は、スペインの無敵艦隊が敗北した史実と同じような確実性であり、数学的な確実性でも物理学的な確実性でもなく、「歴史や裁判の場合に得られるような確実性と同じもの」だ。このことは「自然科学で使われる観察や実験の方法に拠るべきであると思われる諸事実が、歴史や裁判におけるように扱われるのはおかしい」という反応を引き起こす。それが心霊研究に対する不快感、嫌悪の背景にあるとベルクソンは言う。
つづいてベルクソンは、科学者の心霊嫌悪の特徴として数値化になじまないことを挙げる。数値化批判は彼の十八番であるうえ、この「生きている人の幻と心霊研究」では面白い例を挙げているので、以下、少し長く引用する。ある会議で同席した科学者(医学者)が次のように言ったのだという。
医師はこの例を挙げながらもそれは偶然の一致だと結論した。「自分の夫がまったく元気なのに死んだとか死にそうだとかいう夢を多くの妻が見る」のであって、正しかった場合もその一つにすぎない。「一覧表を作ってみれば、その一致が偶然のなせる業であることがわかるだろう」。
この意見に対してベルクソンは次のように指摘する。
この主張に、私もおおむね賛同する。超常現象の体験談を否定する人たちの決まり文句は、それは幻覚・錯覚・思い違いに過ぎない、というものだが、幻覚と錯覚は厳密には違うタイプの体験である。錯覚は枯れススキを幽霊の手招きと見誤るたぐいのもので、思い違いを指摘されれば当人も「なんだ、見間違いか」と納得する。これに対して、幻覚の場合は、それが幻であることを当人も自覚している場合もある。そこには何もないはずなのに、何かが見える、何かが聞こえる、そういう体験である。生霊か死霊かを問わず、一般に幽霊というのは、そこにいないはずの人の幻像のことである。そこにいる人の実像であれば、それは幽霊ではない。単にそこにその人がいただけのことだ。つまり、幽霊とは幻であるからこそ特異な体験として記憶されるのであって、それを幻覚にすぎないといっても意味がないのだ。
しかも、その幻が空想や妄想ではなく、対応する事実に一致する場合、すなわち「本当の幻視」であった場合は、体験者にとってさらに強い意味を持つ。ベルクソンが取り上げている例は、何となくそういう感じがしたとか、あとから考えてみればその予兆であったとかいうたぐいの虫の知らせではない。そこにいないはずの人、そこではないどこかの出来事が鮮明に見えた場合を「本当の幻視」と呼んでいる。このケースを否定するために持ち出されるのが、「偶然の一致」という便利な言葉だが、ベルクソンはこの紋切り型の態度を明快に批判した。
しかしながら、ベルクソンの論理にもどこかしっくりこないものがある。生きている人の幻が事実に一致するならば、という条件がついているが、それをいかにして確認するのかという問題である。取り上げられた事例で、その婦人がどのような状態で幻を見たのかはよくわからないが、ある人の個人的な体験を第三者が検証するとしたら、それこそテレパシーによって伝えられるのでもない限り、結局「歴史家の方法と予審判事の方法との中間にあるもの」、「歴史的批評的な方法」によるほかないのではないかと思う。
I氏のケース
ベルクソンに倣って私も「生きている人の幻」の事例を挙げてみよう。
体験者は、仮にI氏としておこう。体験時の年齢は四〇代半ば。職業は、今で言えば公務員で仕事は公共施設の警備。公務員といっても世襲の上級官僚とは違い、基本的に昇進・昇給はなく、年俸は初任給のままだが時間的にはかなり余裕があり、内職も黙認されている。再婚した妻とのあいだに四人の子どもがおり、木造一戸建ての官舎で暮らしている。安定を画に描いたような生活だが、一つだけ気がかりなことがある。経済的困窮を理由にして協議離婚した前妻に、離婚の本当の理由が今の妻と結婚するためであったことを知られてしまい、かつその前妻が失踪したままであることだ。
I氏の体験について述べる前に、もう少し彼の個人史を振り返っておこう。失踪した前妻のことが気になるのは、彼のささやかながら安定した今の身分が、もともとは急死した前妻の父親の地位を継いだことによって与えられたものだったからだ。地方から職を求めて首都に出た彼は、前妻の家に婿入りすることによって今の地位を得た。前妻の側にとっても家長の急死により、至急、婿を取って職を継がせないと地位を失うことになるという事情があり、両者とも納得ずくの打算的結婚であった。そのため、前妻の容貌について、難病の後遺症から非常に醜かったのにI氏は就職のために結婚したと言い立てる人たちもいたが、差別意識丸出しのヘイトスピーチをここに再現する気にはなれないので省略する。
さて、打算的結婚の二年目、I氏は上司の家の使用人女性に恋愛感情を抱いた。彼女と結ばれたいがために、生活が窮乏したと偽って前妻を上級官僚の家に働きに出した。当時の慣習では上級官僚などの富裕層の屋敷で就労するには住み込みが原則であったため、離婚する必要があった。前妻も苦しい生活を続けるよりは働きに出たいと考えていたので納得し、離婚して働きに出た。その際、I氏は前妻に嘘をついただけではなく激しいDVもしたとされるが、検証しようがないので棚上げしておく。
ともあれ、こうして前妻と離婚したI氏は、上司の元使用人女性と再婚した。それが現在の妻である。その際に上司は、元使用人女性を自分の妹分という待遇にして、上司の家からI氏に嫁がせる体裁を取った。身分制度のやかましい社会であったため、こうした抜け道を用意することが必要だったのである。もっとも上司のこの配慮が、上司の使用人女性が実は上司の愛人であったとか、すでに上司の子を身ごもっていたとか、すべては子飼いの部下を丸め込みたい上司の策謀であったとか、いろいろな陰謀論の温床となった。
このニュースは、意外に早く風説とともに前妻の耳に入り、だまされた、自分をないがしろにされたと知った彼女は烈火のごとく怒った。大げさなことを言う人は鬼女となって暴れまわったと表現する。前妻は勤務先から失踪した。その際、I氏、上司、それに再婚にあたって仲人をした同僚を皆殺しにすると宣言したと言う噂もあって、これは繰り返し流布されたこともあって、かなり多くの人が信じている。
以上が平凡な公務員I氏が、生きている女の幻を見るに至る前史である。
冷静な男
もうお気づきの方もあろうが、ここで匿名にしたI氏とは伊右衛門、失踪した前妻の名はお岩と言い伝えられている。ご紹介したのは、鶴屋南北が『東海道四谷怪談』を執筆するにあたり参考にした「実説」または「実録」(と呼ばれる伝説)の前半部分の粗筋である。なぜ匿名にして紹介したのかといえば、はなから「四谷怪談」の名を持ちだすと、どうしても南北の『東海道四谷怪談』やそれを原作とした映画・テレビドラマなどのイメージが投影されてしまうだろうからであり、ここで名を明かすのは、以下、引用するにあたり匿名を維持するのが面倒くさいからである。
平凡な幕府御家人、伊右衛門が失踪した前妻お岩の幻を見た体験を示す前に、もう一つ、彼の性格を示すエピソードを挙げておく。伊右衛門はお岩を離縁してすぐに再婚した。入り婿が跡取り娘を離縁しての再婚だから世間体が悪く、婚礼はごく親しい者たちだけでとりおこなわれたが、それでも宴は深夜まで続いた。祝い酒もまわり、歌や踊りで盛り上がっている最中のことであった。
……行燈の脇から一尺ほどの赤い小蛇が一匹這い出した。新婦をはじめ、酌をしていた女たちも驚き騒ぐので、伊右衛門は蛇を火箸ではさんで庭へ放り捨てた。ところが、しばらくするとまた先ほどの蛇が行燈の上へ這い上がっていた。伊右衛門はそれを見て、「今庭へ捨てたと思ったが…。蛇は酒を好むというから、匂いを嗅ぎつけて酒盛の仲間入りをしたいのだろうが、火箸から逃れられるものではないぞ」とまた火箸ではさみ、裏の薮へ投げ捨てた。……
原文は江戸時代の文章だが、ほぼ忠実に現代語訳した。原文をご覧になりたい方は『近世実録全書第四巻』(早稲田大學出版部)に収録された『四谷怪談』に、おおよそ一致する場面がある。
赤蛇は三たび現れた。今度は祝言の客の一人が素手でつかんで裏庭に持っていき、「おまえ卑怯だぞ、どうして執着するのか、もしまたやってきたら頭をぶっつぶすからな。生きながら畜生となったのは、自分が愚かなためだ。もう二度と来るな」と言い聞かせて放してやった。
つまり、この客は蛇を、だまされたお岩の化身と見なしているのである。彼がそのように感じたのは、前妻の怨念は蛇となって祟るという、仏教系の説話に多くある知識を背景にしている。ところが伊右衛門はそうは感じていない。彼の感じ方の背景にあるのは蛇が酒を好むという通説でしかない。蛇の出現に過剰な意味を読み込まず、実際的に対処している。冷静な男、それが「四谷怪談」の、現在見つかっているもっとも古い記録、享保十二年版『四ッ谷雑談集』に記された伊右衛門の人物像である。
帰ってきたお岩
さて、伊右衛門の再婚から十五年。その間に、お岩は自分がだまされたことを知って、今の九段南の勤務先を飛び出しJR四谷駅まで、つまり三番町の旗本屋敷から四ッ谷御門まで、ものすごいスピードで駆け抜けたらしい。その際、制止しようとした男たち二人を投げ飛ばし、一人を蹴り倒したそうだが、真偽のほどはわからない。ともかく、どこまで走っていったのか、四谷左門町の近くまで来たという伝承もあるが、なぜかかつての自宅には立ち寄らず、そのまま西へ走り抜けた。以来、消息はフッツリと途絶えた。お岩は疾走し失踪した。
それから、意外にも伊右衛門は平穏無事な十五年間をおくっていた。その間に、再婚した後妻とのあいだに四人の子をもうけていた。長女については再婚を世話した上司が実の父親だという噂もあったが、これも真偽のほどはわからない。ともかく彼は幸せだった。ある夏の夕暮れ、妻子たちと夕涼みをしながら、平凡な人生だが子宝に恵まれた自分は果報者だと妻と話しながら、ささやかな幸せをかみしめていた時に、それは現れた。
以下、正確を期すために原文を引く(ただし句読点や括弧を補った)。
状況を説明しておく。伊右衛門は庭に面した座敷の戸を開け放ち、夕涼みをしていたのだが、この庭はやたらと奥行きがある。伊右衛門が所属していたのは御先手鉄砲組という幕府軍の鉄砲隊なので、泰平の世でも鉄砲の練習が出来るようにと、間口は狭いが奥行きのある細長い敷地が与えられていた。だから、「向の木蔭」というのはかなり距離のあるものと想像してほしい。そこから座敷までのあいだには自家菜園があったり、植木が植えられていたりしている。「何やらん白き物ちらゝと見へける」というのも、薄ぼんやりとかすんで見えたのではなく、木立を隔てて遠くに人影が見えたのである。
その人影が近づいてきて、見れば先妻のお岩であった。お岩は伊右衛門を恨めしげな目で見て通りすぎた。お岩の視線に射すくめられた伊右衛門は、一瞬、虚を突かれたようになって彼女が縁先を通りすぎていくのを見送ってしまった。あっと気づいてあわてて縁側に出たけれども、もう姿は見えなかった。
あの女は奉公先を飛び出して行方知れずになったと聞いていたが、何を血迷ってここへ来たのか、という冷血な感想の是非はさておいて、お岩の姿を見た伊右衛門は、彼女が生きていることを前提に考えていることに注目してほしい。歌舞伎の『東海道四谷怪談』をはじめ、映画などの多くの「四谷怪談」では夫に裏切られたお岩は死んだことになっている。しかし『四ッ谷雑談集』ではお岩は死んでいない。少なくとも死亡が確認されていないものとして描かれている。だから彼女の姿を見た伊右衛門は、迷わず本人だと思って、なんで今ごろやって来たんだと思ったのだった。ところが、隣にいた妻に「今の女を見たかい」と尋ねると、妻は「自分は見ていない」と答えた(「童」は「わらわ」の当て字)。そこで伊右衛門は、そうするとあの女の姿は自分だけに見えて他の人には見えないのか、と気づいて、適当な話でその場を誤魔化した。
こうして、伊右衛門の見たお岩の姿は「生きている女の幻」に認定されたのである。
このあと、伊右衛門の子どもたちのうち三人と妻が病死し、それがお岩の祟りとして語られていくことになるのだが、伊右衛門がお岩の幻を見たのはこの時だけなので、ここでは扱わない。興味のある方は、拙訳に、畏れ多くも横山泰子氏(怪談研究界のクイーン!)の序文を冠して今夏刊行された『実録四谷怪談 現代語訳『四ッ谷雑談集』』(白澤社発行/現代書館発売)をご覧いただければ幸いである(トちゃっかり宣伝)。
ご紹介した『四ッ谷雑談集』は、引用文が三人称で書かれていることからもおわかりのように小説である。江戸時代初期にあった事件に貞享・元禄の頃のゴシップを混ぜ合わせて、それを怪談の枠組みに流し込んでまとめあげたものだろうと思う。だから、物語の全体はフィクションである。南北の歌舞伎によって日本を代表する幽霊となったお岩様の物語も、文章化された記録としてはこの『四ッ谷雑談集』が享保十二年と最古だが、この他にも複数のヴァリエーションがあって、どれがオリジナルな伝説かは決めがたい。
それではなぜこの『四ッ谷雑談集』から「本当の幻視」の例を取り出そうとするのか。自著の宣伝であることは見え透いているとはいえ、あまりに無謀ではないかと心配される方もおられよう。確かに自己宣伝ではあるが、それなりにこじつけることはできるつもりである。
第一に、『四ッ谷雑談集』の全体はフィクションとはいえ、各場面の要素となる細部の具体的描写は、あらかた事実を反映しているものと思われるからだ。つまり、先妻の生き霊を見た男の名は伊右衛門ではなかったかも知れないし、失踪した先妻の名もお岩とはいわなかったかも知れない。けれども、失踪した先妻の幻を見た体験自体は、実際にあったことをどこかから借りてきてはめこんだものと言えそうなのだ。
どうしてそう推論するかというと、『四ッ谷雑談集』は実録、すなわち事実談であることを標榜しており、小さなことでも調べていくと、たいていモデルとなる人物や事件が見つかるからである。これについては『実録四谷怪談 現代語訳『四ッ谷雑談集』』にわかった範囲で注を付けているのでご覧いただきたい(トしつこく宣伝)。
第二の理由は、この『四ッ谷雑談集』が採用している特徴的な構成である。作中で事実として描かれる出来事を語る際に、メインストーリーを演じる人物以外の人物たちが語り手として登場して、その出来事を語る上で参照した伝説や説話について百物語よろしく述べているのである。例えば、婚礼の夜に現れた赤蛇をつまみだした客は、そのあとで、前妻の生霊が蛇となって祟る物語をして、伊右衛門と後妻も同様な破滅に至るだろうと、物語の展開を暗示するような話をしている。
こうした構成をとっているため『四ッ谷雑談集』の全体はフィクションであるが、題材となった出来事と、それを物語るために参照された説話とが比較的見分けやすいという利点がある。一部始終が事実談として一見整合的に描かれている近代的な「体験談」、例えば私小説などより、よほど虚実の間がはっきりしているのだ。そういうわけで、伊右衛門の見たお岩の姿を、生きている女の幻を見た体験の一事例として取り上げてもよさそうに思うのだ。
つまり、ベルクソンは「歴史家の方法と予審判事の方法との中間にあるもの」、「歴史的批評的な方法」を心霊研究が科学たりうるには不十分なものとしたが、心霊現象の体験談のほとんどは体験者の感じたことをありのままに記録したものではなく、たいていは暗黙のうちに先行する怪談・奇談の影響を受けて物語られているものなので、むしろ「歴史的批評的な方法」こそ、体験談を取り扱う際に先んじて、まさに予審として適用されるべき方法ではないかと私は考えている。そして「歴史的批評的な方法」を採るならば、『四ッ谷雑談集』もまた、心霊研究の一つの題材になりえるだろう、というのが本稿のこじつけである。
伊右衛門の沈黙
さて、伊右衛門の体験で特筆すべきは彼の冷静さである。お岩の幻を見ても「きゃー、幽霊」と悲鳴をあげたりしない。「狐狸の化そこなひて我を驚すか」という感想ももらしているが、江戸時代の武士の狐狸理解をあまり馬鹿にしてはいけない。多くの場合、それは錯覚や急な放心、白昼夢などに実際的に対処しようとする場合に持ち出される言葉で、迷信や狂信とはかけ離れたものである。だから「狐狸の化そこなひて我を驚すか」という感想は、あの女は何を血迷ってここに来たのかという感想と並列して語られているのだ。
そして、お岩の姿が幻であることの認定は、隣にいた妻がそれを認知していたかどうかによっている。その結果「扨は我に計見へて外の人には不見」という結論を得て、それ以上は妻には語らない。
この伊右衛門の沈黙をどう理解するか。共有不可能な、個人の内面的経験だと考えて妻に話すのをやめたのだろうか。どうもそうではない。続きを読んでみよう。
門といっても御家人の官舎だから大名屋敷のような門ではなく、玄関口から出てすぐのところにある引き戸である。誰かがその戸を叩いて伊右衛門の名を三度呼んだ。どなたかと聞いても返事はなく、急いで外に出てみたが誰もいなかった。近所の若者の悪ふざけだろうと思って引き返すと、また名を呼ぶ声がする。今度はすぐさま戸を開けてみたが、やはり誰もいない。さては狐か何かの仕業だろう、やかましいことだとつぶやいて座敷に戻ろうとしたところ、虚空からしわがれ声で「伊右衛門永くは有まじ、観念して命を待べし」と言ってからからと笑う声がした。
しわがれ声というのには伏線があって、お岩は疱瘡の後遺症で声がしわがれていたという設定になっている。
さて、ここでも伊右衛門はうろたえてはいない。まず、近所の若者のいたずらを疑い、ついで狐の仕業と片付けている。狐の仕業というのが実に軽く扱われていることに注意してほしい。「かしましき事哉」と言い捨ててすむようなレベルであって、現代なら、なんだ空耳か、という程度のニュアンスである。伊右衛門はここまでのところ、きわめて現実的な対処をしようとしている。ところが、虚空からしわがれ声が聞こえてきた。行方不明の前妻お岩の声である。
それでも伊右衛門は不敵な心構えの者だったので少しも騒がず……、と『四ッ谷雑談集』の語り手は言うが、さすがの伊右衛門もお岩の声を聞いてうろたえたのである。狐狸妖怪の仕業と思うなら、煙草を一服して寝てしまえばよかったのである。実際にそうやって妖怪に取り憑かれるのをやり過ごした事例がある。ところが伊右衛門は「おのれ臆病者め、この伊右衛門に言いたいことがあるなら面と向かって言えばよいものを、声ばかりで姿を見せぬとはけしからん」と怒ってしまった。こうした時はまず相手を誰何して名乗らせるのが先決なのに、しわがれ声を聞いて相手をお岩と決めつけ、喧嘩を売ってしまったのである。
さて、この伊右衛門の態度は、お岩の姿や声を自分個人の内的な経験、平たく言えば幻視や幻聴と思っている人のとる行動ではない。相手がいることを前提にして反発しているのである。ただ、その相手の姿や声が自分以外の人には見えないし聞こえないことを承知しているだけである。お岩の姿や声は伊右衛門の内心から生まれたのではなく、外からやって来たのだ。そのように彼は自分の体験をとらえている。そして、仕事で使う鉄砲を取りだして、空砲の音をもって相手を驚かし、追い払おうとしたのだ。
その結果、銃声に驚いた幼い娘が引きつけを起こして死に至る。また、伊右衛門は鉄砲を撃った理由を妻に説明しなかったため、夫婦の間に不信が生じた。これがその後続く伊右衛門の一家の不幸のきっかけとなったというのが、『四ッ谷雑談集』の物語るところだが、その後のことはここではふれない。その後の顛末が気になる方は『実録四谷怪談 現代語訳『四ッ谷雑談集』』をご覧いただきたい(トしつこく宣伝)。
幻は私の心の外からやってくる
以上、長々と述べてきた伊右衛門の体験をどうとらえるべきか。これを彼個人の内的経験とするなら、十五年間封印してきた前妻の記憶が、ひょんなきっかけで甦り幻視・幻聴となってあらわれたと結論してよさそうだ。けれども、伊右衛門自身はお岩の姿や声を自分の意識の内部で生じた表象だとは考えていない。それは妻に見えない以上、幻ではあるけれども、自分の意識の外から、言ってみればお岩の側から現れた。このように私が推定するのは、実は私自身に、そこにいるはずのない人の姿を眼前にありありと見た経験があるからだ。
伊右衛門の場合と同様、自宅で妻とくつろいでいるときにそれは現れた。二、三メートル先にある椅子に、見ず知らずの男がこちらに背中を向けてもたれかかっていた。突然のことに驚いて声も出なかった。しばらく凝視していたら、妻が「どうしたの?」と声をかけたので、「あの男は、どこから入って来たのだろう」と言おうとした途端、男の姿は消えた。そこで私はその男の姿は自分一人の幻覚であったかと気づいて、妻には何も言わず、何か別の話題に紛らわせたのも伊右衛門と同じである。今回、『四ッ谷雑談集』を精読する機会を与えられて、この場面は自分の実体験とまったく同じだと感じた。もっとも、私には離縁した前妻はいないので、そこは伊右衛門とは事情が違うのだが。
おそらく、そこにいないはずの人の姿がありありと見えるという体験は、伊右衛門と私だけではなく、調べればかなり多くの人が似たような体験をしているのではないかと思う。このような体験に真実味があるからこそ『四ッ谷雑談集』の作者もそうした場面を採用したのだろう。私の場合は、見ず知らずの男の後ろ姿だったので、あるいはこれが自己像幻視というものなのかともその時は思って、それ以上は深く考えなかったが、あらためてここで書き出してみると、自己像幻視なら見ず知らずの男とは感じないはずだろう。やはりその幻は私の意識の外からやってきたと考えた方がしっくりくる。
こうした幻のよそよそしさ、自分の想像力で思い描いたイメージに感じるものとは違う異質な感じは、あるいはベルクソンの同時代人であるフロイトによる「不気味なもの」についての考察を参照すれば、ある程度の解釈が可能かもしれないが、与太話もずいぶん長くなったので、それについてはまた別の機会にしたい。
★プロフィール★
広坂朋信(ひろさか・とものぶ)1963年、東京生れ。編集者・ライター。著書に『実録四谷怪談 現代語訳『四ッ谷雑談集』』、『東京怪談ディテクション』、『怪談の解釈学』など。ブログ「恐妻家の献立表」 Web評論誌「コーラ」20号(2013.08.15)
<心霊現象の解釈学>第5回:生きている女の幻と心霊研究(広坂朋信)
Copyright(c) SOUGETUSYOBOU 2013 All Rights Reserved.
|
| 表紙(目次)へ |