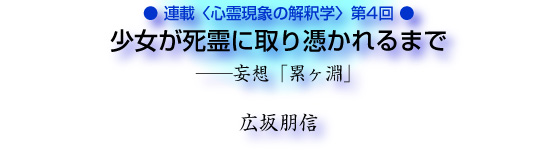|
|
|
Web評論誌「コーラ」 |
|
■創刊の辞 ■本誌の表紙(目次)へ ■本誌のバックナンバー ■読者の頁/ご意見・感想 ■投稿規定 ■関係者のWebサイト ■プライバシーポリシー |
|
<本誌の関連ページ> |
|
■「カルチャー・レヴュー」のバックナンバー ■評論紙「La Vue」の総目次 |
Copyright (c)SOUGETUSYOBOU |
|
|
|
夏場なのでどうあっても幽霊を出したいところである。この連載コラムは、カント、ヘーゲル、エンゲルスと来たのだから次は順当にいったらベルクソンあたりなんだろうが、赤毛ものばかり続くのも少し飽きてきたところだ。それに、夏の幽霊と言えば日本の風物詩であるから、今回はがらりと趣向を変えて日本の幽霊を出したい、いや、お出でいただきたい。ということで、ハイ出ました、出ていただきました。どなたかというと、「累ヶ淵」の累さんである。ルイじゃありませんよ、かさね、と呼んでください。実在した人物ですからね、失礼のないようにしたいものです。
なぜ累さんかというと、宣伝めいて恐縮だが(実はまったくの宣伝なのだが)、「累ヶ淵」の原話の一つで、江戸時代の怪談実録『死霊解脱物語聞書』を翻刻・出版する企画があり、この連載のお陰かどうか、不肖広坂にも久しぶりに怪談のお座敷がかかって、監修者の小二田誠二先生(静岡大学)のお手伝いを勤めさせていただいた。そんなわけで、この一年というもの私がいちばんよく読んでいた怪談は、実はカントでもヘーゲルでもエンゲルスでもなく『死霊解脱物語聞書』だったのである。この怪談のヒロインが累さん。たいへん面白いこの本格実話怪談は、今夏『江戸怪談を読む 死霊解脱物語聞書』(小二田誠二解題・解説、白澤社発行・現代書館発売)として刊行されたので、是非ともご購読くださいますようお願いいたします。
ご存じ圓朝『真景累ヶ淵』から
さて、『死霊解脱物語聞書』と聞いてもご存じない方でも、「累ヶ淵」と言えば、三遊亭圓朝の名作人情噺を思い出されるだろう。
ご存じ圓朝の『真景累ヶ淵』は、旗本・深見新左衛門が高利貸の皆川宗悦を斬殺したことを発端に、深見の息子・新五郎と新吉、宗悦の娘・豊志賀とお園が、互いに仇同士だとは知らずにかかわりを持ち新五郎は過ってお園を殺し、豊志賀は愛人にした新吉に見捨てられて死に、その怨みから新吉に取り憑いて新吉の行く先々で怪事件が起こるというストーリーで、落語というより長編小説のような趣である。この長い物語の中でも、豊志賀と新吉のエピソードは歌舞伎に翻案されてしばしば上演されるほか、小説はもちろん、この噺を原作としたコミック『累』(エンターブレイン)や、中田秀夫監督の映画『怪談』(2007年公開、尾上菊之助・黒木瞳ほか出演)もある。
ところでこの圓朝『真景累ヶ淵』は、冒頭に「名題を真景累ヶ淵と申し、下総国羽生村と申す処の、累の後日のお話でございまするが」とことわりが入っている。もともとこの噺は「累ヶ淵後日の怪談」という題名であったそうで、つまり「累ヶ淵」として知られている物語の後日談である、という位置づけになる。
江戸時代、寛文十二年(1672)、下総国岡田郡羽生村(現在の茨城県常総市羽生町)で、菊という少女に父親・与右衛門の先妻である累(かさね)の死霊が取り憑き、村中を巻き込んだ騒動が足かけ四か月にわたって続いた。この騒動は、羽生村に隣接する飯沼弘経寺の修行僧だった祐天が念仏の功徳によって死霊を往生させて決着した。この事件について語ったものが、円朝の前提としている「累ヶ淵」である。
羽生村の事件が江戸に伝わるや多くの人々の関心を呼び、歌舞伎、浄瑠璃、文芸、落語、講談など、さまざまなジャンルでこの事件を題材にした作品が生み出された。文芸では曲亭馬琴による『新累解脱物語』(文化四年、1807)があり、歌舞伎では鶴屋南北による『法懸松成田利剣』(文政六年、1823)の後半が羽生村の事件の話になっており、今では『色彩間苅豆』として独立して上演されている。また、文人たちの随筆や日記にも登場する。こうした二次作品群のなかで、現在もっとも有名なのが、幕末・明治になってから創作された『真景累ヶ淵』である。
それではそもそもの「累ヶ淵」とはどういう話だったのか。圓朝は『真景累ヶ淵』の中で、その発端になった羽生村の事件について短くふれている。
年上の愛人・豊志賀の嫉妬に嫌気がさした新吉は、病気の豊志賀を見捨てて家を飛び出すが、その間に豊志賀は死んでしまう。「此の後女房を持てば七人まではきっと取殺すから然う思え」という遺書を見た新吉は、豊志賀と暮らした江戸にいるのが怖くなって、恋仲のお久と、お久の故郷である羽生村をめざして駆け落ちする。二人が鬼怒川(引用文中では絹川)のほとりにたどり着いたところで、圓朝による「累ヶ淵」の説明が入る。
圓朝が「鎌で殺したのだと申しますが、それはうそだと云う事」と言っているのは、この噺に先行する累ヶ淵怪談の代表的な作品、例えば、馬琴の『新累解脱物語』、南北の『法懸松成田利剣』などでは、累は夫・与右衛門に鎌で切り殺されたことになっているからだ。
また、圓朝は登場人物の作蔵とお賤に次のようにも言わせている。
この会話からは、累の事件が有名であったこと、累は二六年にわたって祟りをなしたこと、累の物語には「助」という子がかかわっているが、どういう事情かはっきりしないこと、累の墓は浮気封じの願掛けに効くとして女性に信仰されたこと、などがわかる。
さて、現在もっとも知られている累ヶ淵怪談、三遊亭圓朝『真景累ヶ淵』から、元の羽生村の事件についてわかることはこの程度である。まさしく作蔵のセリフのように「何だか判然(はっきり)しねえ」のである。それは圓朝の怪談噺が後日談であることと、それに先立つ累ヶ淵怪談については広く知られていることを前提としているからでもあるが、先に述べたように、元をたどれば羽生村の騒動から派生したとはいえ、実に多くのジャンルで、さまざまな脚色をほどこされて語られてきた結果、もともとはどういう話だったのか、事件の概要がはっきりしなくなっていたからでもある。
『奥の細道』のかさね
松尾芭蕉『奥の細道』に次のようなくだりがある。岩波文庫から引く。
みちのくをめざして那須野を北上する芭蕉と曾良は、途中で馬を借りる。そうすると、幼い子どもが二人、馬のあとを追ってついてくる。一人は少女で名前を尋ねると「かさね」という。聞き慣れない名前がかわいらしく感じられたので曾良が一句詠んだ。そういう場面である。なんだかほのぼのとした味わいのある場面で、ご記憶の方も多かろう。
しかし問題は「かさね」という名前である。岩波文庫の『おくのほそ道』に併載されている江戸時代の注釈書『奥細道菅菰抄』には、「名をかさねと云」の注釈として、次のようにある。
安永七年(1778)の時点で、このように思った人もいたわけだ。
『奥細道菅菰抄』は、芭蕉が那須野で出会った、かさねという小姫が成長して、後に怨霊となり、祐天上人に教化されて往生を遂げる(だと面白いのにな)というように想像し、「大概時代相応にて、きぬ川も亦此あたり近し」と想像に蓋然性を与えようとしているが、かなり無理がある。
芭蕉が奥の細道の旅に出たのは元禄二年(1689)。翌元禄三年に累騒動を描いたドキュメント『死霊解脱物語聞書』が刊行されているが、実はそれ以前に、天和二年(1682)頃成立したと思われる『古今犬著聞集』(刊記は天和四年(貞享元年)1684)に、累の怨霊を祐天上人が成仏させたとの記事がある。
そもそも、累騒動が起きたのは寛文十二年(1672)のことで、この年に与右衛門の一人娘・菊に、父の先妻にあたる累の霊が憑依して大騒ぎになるのだが、その累が与右衛門に殺されたのは、さらにさかのぼって正保四年(1647)のことであって、元禄二年(1689)に芭蕉が出会った小姫が、その四十年ほど前に殺されていたとはとうてい考えられず、「大概時代相応」とはとても言えない。また、場所についても、同じ鬼怒川流域とはいえ、羽生村のある水海道界隈と芭蕉がかさねという小姫に出会った那須のあたりとではかなり距離がある。
案ずるに、『菅菰抄』の著者は累の事件にはあまり詳しくなかったのだろう。『死霊解脱物語聞書』の刊行が元禄年間だったことから、元禄のころ関東で起きた事件として認識して、そのイメージをかぶせてしまったというところではないか。ただ、芭蕉が書いているように「かさね」という名前が珍しいものだったとすれば、やはり、『奥の細道』と累伝説とのあいだに何らかの連絡があったのではないかと連想してしまうことは避けられないように思う。
つまり、累ヶ淵の元の話がはっきりしなくなったのは、円朝が『真景累ヶ淵』を創作した幕末・明治になってからのことではなかった。すでに江戸時代中頃に、有名だけれども真相のよくわからない事件になっていた。
累が淵怪談の舞台
元禄の初めの頃、おそらく元禄二年だろうと思われる。残寿という僧が、江戸から羽生村を訪れたはずである(確証はない。以下、筆者の妄想まじりの記述になるのでご注意)。目的は、累憑依事件の関係者への聞き取り調査であった。
残寿とは、自己申告によれば、累を往生させた祐天の弟子にあたる浄土宗僧である。当時の祐天は、浄土宗教団の役職を離れ、増上寺を出て江戸で独自に布教活動をしており、江戸の庶民からたいそうな人気を得ていた。祐天の人気は優れた弁舌にもよるのだろうが、それ以上に、累の怨霊を成仏させたという祈祷僧としての実績が世間に流布していたからでもあった。祐天の活動については、高田衛『江戸の悪霊祓い師』(筑摩書房)に詳しいのでここでは省略する。
残寿はその祐天を師と仰いだ。そして、羽生村での師の活躍に夢中になった。顕誉上人(祐天)にお会いした折にたびたび懇願して直接お話をうかがったと言っているから相当な入れ込みようである。その残寿が羽生村に向かったのは、祐天の談話だけでは不明な点があったからである。残寿の書き記した『死霊解脱物語聞書』は上下巻にわかれており、上巻には祐天は登場しない。累の怨霊が菊にとり憑いたのは一月二三日だが、祐天が累の怨霊と対決した三月十日まで、一月半以上も日にちがある。この間に羽生村で何があったのか。
残寿も読んでいただろう『古今犬著聞集』では、この間の事情を「とやせまし、かくやせまして、日をふりし」(そうこうしているうちに日がたって)と簡単にすましている。残寿はそこが気になった。師匠にも根掘り葉掘り尋ねたことだろう。だが、おそらく祐天は、自分も詳しいことは知らぬ、と答えた。そこで残寿が羽生村の人々に聞いてみようと思い立ったのか、あるいは祐天が、その間の事情は羽生の人に聞け、と言ったか。ともあれ、残寿は羽生村をめざして江戸を発った。懐には祐天による羽生村名主宛の紹介状を携えてのことだったろうことは想像に難くない。その旅の途中、奥の細道の旅に出た芭蕉師弟と知りあって、累の話をしていたと仮定したらさぞや面白かろうと思うのだが、妄想をふくらませるのもほどほどにしておこう。
事件の舞台となった羽生村は、水海道の町に近い鬼怒川沿いに開けた農村だが、背後に飯沼弘経寺という大寺院があった。事件当時、祐天が修行僧として所属していた寺である。羽生村に着いた残寿は、まずこの飯沼弘経寺に身を寄せたのだろうと思われる。江戸時代の飯沼弘経寺は単なる寺ではない。北関東における浄土宗の拠点である。私が現地を訪ねときに、現在の弘経寺本堂から1キロくらい離れたところに弘経寺大門跡を見つけて驚いた。そこが元の大門だとすると、かつての飯沼弘経寺の境内はとんでもなく広大なものだったことになる。広い敷地に多数の堂宇が立ち並び、大勢の僧侶が生活して、北関東一円の浄土宗寺院のセンターとしての業務を行なっていたわけだ。そこでの日用品を納める業者も周囲にいただろうし、同じ宗門の本山である芝の増上寺との連絡のために江戸との間を往復する人もいただろう。この弘経寺に隣接した羽生村は、単なる農村ではなく大寺院の門前町でもあったわけだ。
残寿は菊に会ったか
弘経寺で旅装を解いた残寿は、さっそく羽生村名主の三郎左衛門と年寄(名主の補佐役)の庄右衛門を訪ねたに違いない。祐天の紹介状の効力は絶大で、残寿は大歓迎されたはずである。『古今犬著聞集』には、累事件の後、すっかり祐天に感化された三郎左衛門と庄右衛門が念仏信仰の宣布に一役買っている姿が描かれているほどだ。さっそく十七年前の事件を目の当たりにした男たちが呼び集められたことだろう。
男たちが呼び集められた、と私が推測するのには理由がある。『死霊解脱物語聞書』には大勢の人々の発言が記録されているが、女性の発言者が極端に少ない。当事者である菊、累、累の霊、の三者を除けば、名前のない老婆による発言が一か所あるだけだ。事件は長引くにつれて村中どころか隣村にも知れわたる騒動になっていくのに、その記録に村の女たちの発言がほとんど残されていないのは不自然である。これは取材対象が男性に限られていたからではないか。もし、菊をはじめとして村の女たちが集められていたら、『聞書』は現在残されているものとは違った形になっていたかもしれない。
そして『聞書』に登場する羽生村の人々は、累の家のメンバーを除けば、村役人である三郎左衛門と庄右衛門のほか、念仏杢右衛門、八右衛門という人物以外には名前がない(このうち杢右衛門は事件当時すでに故人である)。『聞書』下巻で八右衛門は累殺害以前の古い因縁を語り伝える証人として重要な役回りを演じるが、この他にも累の墓所の菩提寺である法蔵寺の住職や、累の怨霊との会話に加わった村人たちも大勢いるのに、彼らの名前がない。もし残寿が一軒ごとに訪ね歩き、一人ずつから取材したのであれば、もう少し名前が記録されていてもいいはずだ。
以上のことから、残寿の取材は、名主が自分の屋敷に村の男たちを呼び集め、江戸からの客人にあの時のことを話してやってくれ、とうながして行われたと想像する。そして、集められた村人たちの中に、当事者である菊の姿はなかった。
残寿はおそらく菊と会っていない。遠目に姿を見て、ほら、あれがお菊さんだよ、と名主か年寄から教えられることはあったかも知れないが、じかに会って言葉を交わすことはしなかったはずだ。残寿が羽生村を訪れた元禄の初め頃、菊は存命だったが、『聞書』では事件後の菊について「今に安全とぞ聞へける」(今も安らかに暮らしていると伝え聞いた)と巻末に記すだけである。もし残寿が菊本人にあって当時の話を聞き、今の暮らしの様子を見ていたのであれば、「とぞ聞へける」とは書かなかっただろう。
なぜ残寿は菊に直接取材しなかったのか(あるいは、できなかったのか)。理由はいくつか考えられるがここでは詮索しないでおこう。ともあれ、『死霊解脱物語聞書』上巻は、残寿が憑依事件の当事者に取材して書き上げたものではあるが、それは憑依の当事者にではなく、事件の目撃者、それも男性にのみ取材したものであろうことを仮説として提出しておきたい。
羽生村という語り手
名主の屋敷に呼び集められた村の男たちは、三十代が中心だったはずである。十七年前、今は亡き菊の父と夫を除けば、憑依に最初に気づいたのは月待の行事で集まっていた「隣家の若き男共」であり、累の怨霊と初めて言葉を交わしたのも「村中の若者共」だった。事件当時、十代から二十歳そこそこくらいの青少年だった男たちが、この村の累世代なのである。江戸からの珍客を迎えて、同窓会よろしく思い出話に花が咲いたことだろう。
この集まりは、一日ではすまず、二日、三日と続けて行われたかもしれない。このときの聞き取りが『死霊解脱物語聞書』上巻の主なニュースソースであろう。祐天も詳しくは語らず、『古今犬著聞集』では「とやせまし、かくやせまして、日をふりし」としか書かれていない空白の期間にどんなことが起きていたか、残寿は興味津々で聞き入ったに違いない。
こうした集まりでは、大勢の人が、自分の見たのはこうだった、自分が聞いたのはこうだったと口々に語る「藪の中」現象も起きるはずだが、『聞書』にはその痕跡がほとんど見られない。特に『聞書』冒頭の二つの章、累殺害の様子を描く「累か最後之事」と、累の怨霊が最初に菊にとりついた場面を描く「累が怨霊来て菊に入替る事」は、まるで週刊誌の事件記事のようにきれいにまとまっている。
これには二つ理由が考えられる。第一に、聞き手である残寿による編集である。『聞書』執筆の目的は、世間に流布して人々は噂しているが、前後の事情も表現も語る人によってまちまちで、確かなことがわからなくなってしまった累の怨霊得脱の物語を、祐天をはじめとする当事者たちへの取材によって再構成しようということであった。だが、その動機はあくまでも祐天の活躍を描くこと、ひいては念仏信仰の優位を説くことにあった。残寿はこの方針に沿って、村人たちの証言を取捨選択し、再構成し、書き換えすらした。そのことを残寿は『聞書』本文でことわっている。
第二の理由として、体験談を語る村人たちの側で、この事件についての共通認識がすでに出来上がっていたことが考えられる。とにかく大事件だったのだ。事件発生から残寿が羽生村を訪れるまでの十七年、その間にも羽生村にはいろいろな人たちが訪れ、何が起きたのかと何度も尋ねられたことだろう。あるいは、代官所から名主へ問い合わせがあり、村方書上のような報告書を提出するよう求められていたかもしれない(発見されれば私的には第一級史料だ)。羽生村は、こうした問答を繰り返すうちに、事件を一人ひとりの体験としてではなく、村の歴史の一コマとして要領よく伝えるパターンを作りだしていったと想像される。障害のある妻を夫が殺す「累か最後の事」、若い娘に死霊が憑依して人格が変化する「累が怨霊来て菊に入替る事」、『聞書』巻頭のショッキングなこの二つの場面は、羽生村の共通認識としてある程度まで物語化されていた部分だったのではないか。その語り手は、一人ひとりの名前と顔をもった具体的個人ではなく、羽生村という集合意識だったと想像される。
このように考えてくると、『死霊解脱物語聞書』上巻は、ある意図をもって取材する聞き手・残寿と、集団的語り手である羽生村との協働作業によって成立したと言える。
累の醜さとはなにか
『死霊解脱物語聞書』は次のようにはじまる(以下、原文は小二田誠二氏の翻刻を拝借するが、句読点は適宜変えた。原文には読点「、」はなくすべて句点「。」である)。
テンポのよい文体で、事件の起きた時期、場所、主たる人物(与右衛門、菊、累)の職業と続柄を簡潔に示しながら、この事件が世間の噂(天下の人口)となり多くの人を驚かせたとニュースの反響まで述べている。声に出して読み上げるとリズムがあって、昔のお坊さんはこういう調子で庶民に説法していたのかな、と思わされる。
なぜ、こんな事件が起きたのか、その大元の原因を過去にさかのぼって詳しく調べると、と言っているのはもちろん残寿である。以下、残寿が羽生村での現地調査の結果を踏まえて過去の殺人事件の概要を明らかにしていくのである。
まず、被害者である累が描写される。顔は悪いし性格も悪い女だとひどい言われようだが、残寿は累に会ったことがない。これは羽生村の伝承なのである。残寿はこの後、累殺害の様子を描写してから、その年を正保四年(1647)としている。羽生村での残寿の聞き取り調査が私の想定通り元禄二年(1689)だとすれば、せいぜい四五歳以上の年齢の人でなければ累の顔を覚えていることはあるまい。ましてや性格については幼い子どもでは判断できないから、さらに一世代上の人たちの証言による他はない。そして、先に想定したように残寿の取材対象は世代的には三十代が中心だった。だから「顔かたち、類ひなき悪女にして剰へ心はえまでも、かたましきゑせもの也」という人物描写はこの時点で既に、生前の累を知る人たちから後続の世代に語り伝えられたもの、すなわち羽生村の伝承であった可能性が高いと思うのだ。
累の醜さとは何か。これを考える上で参考になるのが、『死霊解脱物語聞書』下巻の、それも全編のクライマックス「顕誉上人助か霊魂を弔給ふ事」にのみ登場する八右衛門老人の証言である。三十代の村人を中心とした集団的語り手と、村役人として事態の収拾に奔走した三郎左衛門と庄右衛門、この他にもう一系統、別のニュースソースに残寿は羽生村で接触した。それが存命であれば七七歳であったろう八右衛門である。累と同世代の八右衛門に残寿が直接会ったかはわからない。あるいはすでに故人で、八右衛門の言葉として名主か年寄かが記憶していたものを残寿は聞き取ったのかもしれない。いずれにせよこの老人の証言には、三十代男性たちを中心とする羽生村の伝承とは微妙に異なるニュアンスがある。
さて、八右衛門は累の容姿についてなんと言ったか。差別的表現だが原文にあるのでご容赦願いたい。「めつかいてつかいちんば」、「かたわもの」、「かたわ娘」。八右衛門はそう言った。片目と片手と片足に障害があったというのである。生前の累を苦しめただろう病がなんだったのか正確にはわからない。ただ、何らかの身体障害のある女性だったということははっきりとしている。そして「めつかいてつかいちんば」、「かたわもの」、「かたわ娘」という表現が、累が少女時代に村の悪童どもから投げつけられた罵声そのものであったろうことも。
八右衛門は、累の不幸の原因を累の父の代からの因縁として、累の家の中に封じ込めるようにして語っているのだが、私はそうは考えない。累は醜さのゆえに嫌われていたが、親の遺産として「田畑少々貯持故に、与右衛門と云貧き男」を婿にとって暮らしていた。ここでは「田畑少々」とだけあるが、あとで累の怨霊は菊の口を借りて「此かさね親のゆづりを得て、持来る田畑七石目あり此たはたは村中一番の上田なり」と言っている。つまり累は、この村では裕福な部類に入る家の一人娘だったのである。裕福といっても、七石という石高が現在の貨幣価値にしてどの程度の年収に当たるのか単純比較はできないが、少なくとも障害を持つ娘を成人するまで大切に育てあげるだけの財力があった。これは江戸時代の話なのである。子どもが生まれても育てられないと思えば間引きすることも珍しくない時代だったのだ。当時、障害のある子どもを育て上げ、家を継がせるのは並大抵の苦労ではなかっただろうに、それをなしとげるだけの力が累の親にはあった。
さて、「かたましきゑせもの」、すなわち頑なでとげとげしい女という性格評価は、この財産に由来するのではないか。江戸時代初期のことだから女家長もそれほど珍しくはなかっただろうが、身体に障害があり、若くして親に死に別れて兄弟姉妹もなく、差別され孤立していた累としては、親の遺してくれた田畑宅地を守り抜くことだけが自らの生きる術であったはずである。頑なにもとげとげしくもなろうというものだ。だから、羽生村の伝承における累の性格は、村と累との関係の中でつくりだされたものだろうと私は考えている。
財産目当ての婿か
孤立無援の累のもとへ婿入りしてきた男がいた。羽生村の伝承では、累が親の遺産として田畑を持っていたので与右衛門という貧しい男が入婿して住みついた、となっていて、いかにも財産目当ての婿だろうという印象だが、古老・八右衛門の記憶では微妙な違いがある。両親の没後、累が独身でいるのを心配した先代の名主が、代々続いた家をつぶすわけにはいかないとして、与右衛門を婿として世話したのだという。
与右衛門とは累の父の名前を継いだもので、この男の元の名前はわからない。しかし名主の世話なら、それなりに身元の確かな男だったろうし、単に金目当てで近づいてきたとは思えない。そんな男であれば、累は警戒して受け入れなかっただろう。名主の選んだのは、累の差別に加担したことのない他村の男、障害のある累をいたわる気の優しい青年だったのではないか。だから与右衛門は、婿入りしてきた当初は、累を助けて実直に働いたのだろうと思う。『聞書』には、累が殺される直前の夫婦の会話が記録されている。
「わたしの荷物がとても重い、ちょっと分けて持ってくれない?」、これが生前の累の言葉として残寿が書き留めた唯一のものである。これに対して男(与右衛門)は、「もう少し鬼怒川べりまで背負って行って、そこから俺が替わりに持つから」と答えている。この会話から累が与右衛門に心を許しているように感じるのは私だけだろうか。なかよく仕事に精を出す農民夫婦の姿が目に浮かぶのである。だが、この時すでに彼は妻殺しを決意した後だった。与右衛門はどうして心変わりしたのか。
引用した文章は謎めいている。哀れなるかな、賤しい者の生活ほど恥の多いことはない、というのが、残寿の個人的感想なのか羽生村の伝承にあった言葉なのか。いずれにしても、ずいぶんと上から目線の発言で、もし羽生村の伝承であれば自虐的とすら言える。続く文章は与右衛門の心変わりの理由を述べているのだが、いったい誰が彼の胸中を語りえたのか。残寿の聞き取り調査の時点で与右衛門はすでに死んでいる。仮に、事件後、悔悛した与右衛門の懺悔の言葉を誰かが記憶していたのだとして、それは何者だったのか。
この女を守って一生を送ることが俺の人生だとしたらやりきれない、という与右衛門の思いに、隣人の視線、友人の意図が影響していることを語っている。これは与右衛門に累殺害を教唆した村人がいたことをほのめかす言葉であり、羽生村としては外聞が悪い。どうにかしてこの妻を殺して別の女を嫁に貰おう、というのは、極論すれば周囲の意志を代弁しているにすぎないことになるのだから、仮にそれが事実だとしても羽生村がそれを語るだろうか。
そこで、もしや祐天らを含む弘経寺サイドによる状況分析だったのではないか、そうであれば上から目線も、与右衛門は因果応報の理をわきまえない者だったので、といういかにも仏教的な理由付けも自然に聞こえる、とも思ったが、よく考えるとやはり違う。羽生村の人間以外にこれを語りようがない。
集団的語り手としての羽生村は、元禄二年の時点ですでに世代交代していた。羽生村が自分たちの不名誉を語るはずがないと想定したが、残寿が聞き取りの対象とした三十代の現役世代からみれば、与右衛門の累殺しは四十年も前の昔話なのである。彼らの祖父世代にあたる事件関係者の多くもすでにこの世を去っていただろう。その上、彼らの多くは、累に憑依された菊から、累が誰にどのようにして殺されたのか、殺人事件の様子を被害者の口からじかに聞くという得難い体験をしていた。その鮮烈な経験は、老人たちの自己弁護の言葉より、はるかにリアリティがあっただろう。
累殺し
さて、いよいよ悲劇の発端が描かれる。正保四年(1647)旧暦八月十二日のことであった。この日、累と与右衛門は夫婦連れだって畑に出て飼料用の大豆を刈り取った。南北の歌舞伎『色彩間苅豆』はこの場面に取材している。
夕刻、与右衛門は収穫物を累に多めに背負わせて家路についた。累が自分の荷物の重さに不満をもらし、与右衛門がなだめたのはこの時の会話である。累は仕方なく息を切らしながら鬼怒川のほとりまでたどりついた。その時、累の背後から与右衛門が非情にも襲いかかった。
累に重い荷物を背負わせて鬼怒川のほとりまで行かせたのもすべて与右衛門の計画のうちだった。計画では背後から突き飛ばして川で溺死させるつもりだったのだろうが、おそらく背負った荷が重すぎて累はあおむけに倒れた。川の水かさは思ったより浅く、累は助けを求めてもがいていた。そこで与右衛門も川に飛び込んで累の胸を踏みつけ、助けを呼ぶ口に川底の泥を押し込み、裏切った夫を睨みつける眼をつぶし、首を絞めて息の根を止めた。それから遺体を川の水で洗って、事故死と偽って菩提寺の法蔵寺に葬った。
殺害の手口の描写が詳しすぎると奇妙に思う人もいるかもしれないが、この殺人事件には複数の目撃者がいた。
累殺害の現場を二人の村人が見ていたのである。アリバイもトリックもない。これが推理小説なら話はここで終わりだが、『聞書』では、この目撃者の沈黙こそが長いドラマの始まりとなる。殺害現場の目撃者は累が嫌われ者だったため、こうなるのも運命さとのみ言って、与右衛門を告発しようとはしなかったのだ。それから二五年、与右衛門の犯罪は羽生村の半ば公然の秘密として、沈黙の底にしまいこまれた。
我は菊にあらず、汝が妻の累なり
累殺害から四半世紀の間に、与右衛門は、おそらく累を殺して手に入れた財産に物を言わせたのだろう、次々と六人もの後妻を迎えたとされている。五人目までは子どもももうけずに早死にし、六人目の妻との間にやっと娘が生まれた。この「女房を持つ事、段々六人也」というのは羽生村の伝承なのだろうが、どうも与右衛門の強欲ぶりを強調するための誇張のような気がしないでもない。
生まれた子は菊と名づけられた。遅くできた子どもだから与右衛門は可愛がったことだろう。菊の母親は、娘が数えで十三になった年の八月中旬に亡くなったと『聞書』には記されているが、これは八月に殺された累との因縁をほのめかすためではないか。法蔵寺過去帳を調査した浅野祥子氏の論文「『死霊解脱物語聞書』の考察」(「国文学試論13号」大正大学、1997)によれば、キヨという名前だったらしい菊の母親は五月没とのことである。
母に死なれたばかりの菊に、あわただしく縁談がすすめられた。おそらく菊が十四歳になるのを待って、その年の暮れ十二月に同村の金五郎という少年を菊の婿に取った。現在よりは結婚適齢期が早かったとは言え、十四歳では一家の主婦と言うには若い、いや幼い印象がある。もっとも、この結婚の目的は婿を取って与右衛門の老後の生活を支えるためであったそうだから、許婚を早めに同居させて家業を手伝わせることに主眼があったのかも知れない。
年が明けて寛文十二年一月四日より、幼妻菊が急な病になった。どうも様子が尋常ではない。一月二三日、菊の病状は急変した。
菊は突然、床に倒れ、口から泡をふき、両目に涙を流し、「ああ苦しい、我慢できない、誰か助けて」と泣き叫び、苦痛のあまりついに気絶してしまった。与右衛門も金五郎も肝を冷やしたのは当然である。意識を取り戻させようと「菊よ、菊よ」と呼びかけた。かつては気絶とは、魂が体外に抜け出たため起こるものと考えられていたので、名前を呼んで、どこかに行ってしまった魂を呼び返そうとしたのである。
しばらくして菊は息を吹き返したが、菊の身体には菊ではない者が帰ってきていた。
目を覚ました菊は父親をハッタと睨みつけ、声を荒げて言った。「お前、こっちに来い、噛み殺してやる」。与右衛門は娘の豹変にうろたえた。「菊よ、気でも違ったのか」。
少女は宣言した。「我は菊にあらず、汝が妻の累なり」。
ここから怨霊と羽生村との足かけ三ヶ月にわたる長いドラマが始まるのである。
以上、『死霊解脱物語聞書』上下巻全十二章のうち、巻頭の「累か最後之事」のあらましと、第二章「累が怨霊来て菊に入替る事」の冒頭部分をご紹介した。本稿では、「累か最後之事」についてやや詳しく私見を述べたが、『聞書』はこの後からが本編で、上巻では村役人と累の怨霊との緊迫した交渉、臨死体験をした菊の語るあの世の物語、再び帰ってきた累に振り回される村人たちが活写され、下巻ではついに祐天が登場、己の信仰を賭けて菊に取り憑いた死霊と二度の対決を繰り広げる。いずれの場面も様々な解釈が可能であり、読んで面白く詮索して楽しい読み物なので、続きをお知りになりたい方はぜひご覧いただきますようお願いいたします(ト最後まで宣伝なのでした)。
★プロフィール★
広坂朋信(ひろさか・とものぶ)1963年、東京生れ。編集者・ライター。著書に『東京怪談ディテクション』、『怪談の解釈学』など。ブログ「恐妻家の献立表」 Web評論誌「コーラ」17号(2012.08.15)
<心霊現象の解釈学>第4回:少女が死霊に取り憑かれるまで――妄想「累ヶ淵」(広坂朋信)
Copyright(c) SOUGETUSYOBOU 2012 All Rights Reserved.
|
| 表紙(目次)へ |