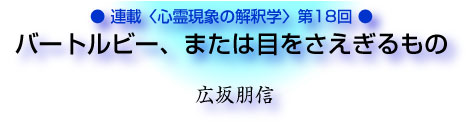|
|
|
Web評論誌「コーラ」 |
|
■創刊の辞 ■本誌の表紙(目次)へ ■本誌のバックナンバー ■読者の頁/ご意見・感想 ■投稿規定 ■関係者のWebサイト ■プライバシーポリシー |
|
<本誌の関連ページ> |
|
■「カルチャー・レヴュー」のバックナンバー ■評論紙「La Vue」の総目次 |
Copyright (c)SOUGETUSYOBOU |
|
|
|
前回(第17回)、「ドゥルーズは幽霊を見たか」と題してドゥルーズによるベルクソン仮構作用説の解釈を見た。
ドゥルーズの『哲学とは何か』(河出文庫)におけるベルクソン解釈のベースとなっているのは、仮構作用は「知性による、死の不可避性の表象に対する、自然の防御的反作用」(ベルクソン『道徳と宗教の二源泉』)だというアイデアである。知性は生の道具であるのに、その知性のもたらす「死は必然である」という表象は、生を意気阻喪させ、ややもすると人をニヒリズムに陥らせる。これに対して、生命は知性を欺くニセの知覚を生みだし、人をしてニヒリズムの穴にはまらぬよう回避させる。これがベルクソンの言う仮構作用のプロトタイプである。
ドゥルーズは、仮構作用によるヴィジョン(幻視)の例として、ユートピアのような場所(異世界)ではなく、精霊、神々、巨人のような人物像を強調している。ベルクソンが『二源泉』で記録した、故障したエレベータの中から忽然と現れ、故障を知らずにエレベータに乗りこもうとした婦人を外に突き飛ばして彼女を救い、また忽然と消えたあの幻の人がドゥルーズの言う巨人にあたる。
このヴィジョンを『哲学とは何か』や「管理と生成変化」(『記号と事件』河出文庫所収)でのドゥルーズの発言に引きつけてみれば、次のようなことが言えるはずだろう。いまグローバルな市場における知性である〈市場の-ための-思考〉が、われわれの生を脅かしており、この危険に対する防御反応として仮構作用がはたらく。〈市場の-ための-思考〉が、われわれの生を脅かしていることへの警告として、われわれが市場主義のニヒリズムに陥らぬように、グローバルな市場における知性を欺くべく仮構された幻視(被知覚態)が現われる。ベルクソンの仮構作用は第一義的には生命の自己防衛反応だが、文学はこの仮構機能の適用だとされている。ドゥルーズが着目するのはむしろ文学・芸術の創造である。ドゥルーズは評論「文学と生」で次のように言っている。
「たしかに、文学の登場人物たちは完全に個別化=固体化されたものであり、漠然としていることも一般的であることもない。けれども、彼らの個別的特徴は、一つのヴィジョン〔視覚=幻影〕にまで彼らを高め、そのヴィジョンが、彼らにとってはあまりに強力な一つの生成変化としての限定されざるものの中へと、彼らを押し流していく。エイハブ船長とモービィ・ディックの幻影がそれだ。(中略)作りごとぬきの文学は存在しない。だが、ベルクソンが見て取ることのできたように、作りごと、仮構作用というのは、自己を想像することや投影することに存するのではない。それはむしろ、こうしたヴィジョンにまで到達するものなのであり、こうした生成変化あるいは力にまでみずからを高めるものなのである。」(ドゥルーズ『批評と臨床』河出文庫p16)
「一つの民衆=人民(ピープル)を創り出すことこそが、仮構作用の役目なのだ」(ドゥルーズ、前掲書p17)。芸術家は、そのような幻視(被知覚態)を積極的に創造すべきだ、とドゥルーズは当為の言葉で言っているように読めた。
■「ぼく、そうしない方がいいのですが」(バートルビー)
しかし、いきなり白旗をあげるようで面目ないが、私は自分のドゥルーズ解釈に自信がない。というのも、もし、私の印象が的外れでなければ、以下の推測も当たっているはずだからだ。私の推測とは、ドゥルーズの言う被知覚態としての人物像(幽霊)の最適の例として、メルヴィルが短編『バートルビー』で創造した、あの何もしない青年バートルビーが挙げられるはずではないか、というものである。
メルヴィルがドゥルーズの偏愛する作家であることは周知の通り。そして、『バートルビー』についてドゥルーズは「バートルビー、または決まり文句」と題した文章を書いている(『批評と臨床』所収)。しかし肝心の『哲学とは何か』にはバートルビーのバの字も出てこない。『白鯨』のエイハブ船長とモービィ・ディックは出てくるのに。この事実の前に、バートルビーこそまさしく仮構作用によるヴィジョン(幻視)の好例だ、との私の鼻息はあっさりと息もたえだえになってしまった。とはいえ、毎度のことながら〆切は目前に迫っており、他にたいしたアイデアもひねり出せないので、当たらずとも遠からずとまでは言えないにしても、せめて無理やりこじつければそう見えなくもないというところまでは何とか持っていこう。
メルヴィルの創造したバートルビーは、広い意味での幽霊を思わせる性格を持っている。以下、筋書きを追いながら、バートルビーが幽霊的な人物であることを示す。引用する訳文は、もっぱら牧野有通訳『書記バートルビー/漂流船』(光文社古典新訳文庫)に拠るが、バートルビーのかの有名なセリフ「ぼく、そうしない方がいいのですが」だけは坂下昇訳『幽霊船他一篇』(岩波文庫)を拝借する。
語り手の「私」は、ウォール街に事務所をかまえて富裕層相手の顧問弁護士のような仕事をしている。「お金持ちの方々の債権証書や抵当証券、または不動産権利証書なんかに囲まれて、気分よく仕事をするのを好む人間なのであります」。つまり〈市場の-ための-思考〉に長けた人物として設定されている。この「私」の事務所に書記(書類の清書係)として雇われた青年バートルビーは、初めのうちは目覚ましい働きぶりをしてみせるが、ある日を境にパタリと仕事をしなくなる。出社しないのではない。むしろ事務所に泊りこみ、居ついてしまいながら、「私」が何を命じても「ぼく、そうしない方がいいのですが」と言って何もしようとはしない。
このコントの主人公バートルビーは生きた人間なのだが、作品中で語り手の「私」は彼について幽霊を連想させる形容を幾度もしている。自分のブースに引っ込んで出てこないバートルビーを、三回呼んでようやく彼が姿を現わしたときに「私」はこんな感想をいだく。
「まさに、魔法のおまじないの決まり文句にしたがって現れる亡霊のように、三度目の呼びかけで、彼は隠れ家の入口に現われました。」(p44)
そして、日曜日にふと事務所を訪れたときに、そこにバートルビーが住みついていることに気づく場面。
「するとその時、さらに驚いたことに、鍵が内側から回されたのです。そして、ドアを半開きにしたまま、私に向かってやせ細った顔を突き出したのは、誰あろう亡霊のようなバートルビーだったのです。」(p48)
この時のバートルビーが「死人のような不気味さを漂わせていること」に「私」は「異様に強い影響力」を感じて、ついには次のような「異様な幻想」を思い浮かべる。
「そうです、あの書記の青白い顔が私の眼前に浮かび出たかと思うと、次には、彼のことを気にも留めない見知らぬ人々の間で、冷え冷えとした死に装束に包まれ、横たわっているのです。」(p53)
得体の知れないバートルビーの奇行に手を焼いた「私」は彼を解雇しようと決心するが、「それでもやはり、奇妙なことですが、迷信めいた何かが私の心の扉をノックし、そんな目的を実行してはならないと命令し、もし私があえて、こんな、人間で最も孤独で惨めな男に向かって辛辣な言葉を一言でも発したら、私を悪党として糾弾するぞ、と言うのを感じたのです。」そこで、バートルビーに「少しは物わかりのいい行動をするようになると言ってくれ」と懇願するのだが、その返事はこうだった。
「「今のところ少しは物わかりのいい行動をしない方がいいと思います」というのが、彼の穏やかで死人のような返事でした。」(p59)
業を煮やした「私」は、ついにバートルビーに解雇を宣告するが、しかし、バートルビーは「出て行かない方がいいと思います」と言って事務所に居座り続ける。
「「出て行かんのか――」私はやっとのことでつぶやきました。けれどもまたもや不可解な書記が持つあの不思議な力に支配され、どんなにじれったく思っても、その支配力から完全に抜け出すことはできませんでした。(中略)けれども、死人のような彼が私を制圧するのを許すなんて――そんなことだけはとうてい我慢できない。それじゃどうしたらいいというのだ?」(p71-p72)
思い悩んだ「私」は哲学書を読んだりした挙句「私のこの世での使命は、バートルビー、君がとどまりたいと思う期間だけ、君に事務所の部屋を提供してやることだ、と悟ったのです。」(p78)
しかしこの達観も長くは続かなかった。
「とうとう、仕事仲間の間で、私が事務所で飼っている奇妙な生き物について怪訝そうにささやく声が広まっていくようになりました。これは私を大いに悩ませました。(中略)友人たちは私の事務所の幽霊のような存在について、絶えず容赦のない意見を広めてゆくものですから、とうとう私の中で大きな変化が起こりました。私は全力を傾けて、この耐えがたい悪夢のような怪物を永久に取り除こうと決意したのです。」(p80)
「私」は、「どうしたら? いや、どうすべきなのだろう? 良心は、あの男、というよりあの幽霊に対してどうしたらいいと言うだろう?」と悩んだ挙句、バートルビー一人を残して事務所を引っ越した。つまり、逃げ出したのである。バートルビーは追いかけて来なかった。しかし、そのかわりに「私」が借りていた部屋の次の入居者(「私」と同業の弁護士)や家主がやってきて、あの男をどうにかしてくれと苦情を申し立てた。無理やり部屋から追い出されたバートルビーはビルのなかをうろつきまわり「昼は階段の手すりに坐って、夜は玄関ホールで眠る」のだという。いきがかり上、いやいやながら「私」はバートルビーに会いに行き、何か仕事を世話しようとするが、すべて拒否される(「いいえ、今のところ何も変わらない方がいいと思います」)。「私」は交渉が不首尾に終わったことを家主らに責められるのを恐れて、数日間、馬車で逃げ回る生活を送る。
結局、バートルビーの最後はあっけなかった。家主が警官を呼んで、浮浪者として取り締まらせたのだ。「バートルビーは浮浪者として「墓場」と呼ばれている刑務所へ連れて行かれ」(p91)そこで死んだ。メルヴィルは物語の最後に弁護士「私」にバートルビーの前歴についての「話していいかどうかわからない噂」「あいまいな風説」を語らせている。
「バートルビーは首都ワシントンにある配達不能郵便物局の下級職員だったのですが、管理者が代わったことにより、突然罷免されてしまったということです。この噂について考える時、私は自分に襲ってきた感情をうまく表現することはできません。「配達不能郵便物(デッド・レターズ)」、それは「死者(デッド・マン)」のような響きを与えないでしょうか?」(p100)
亡霊、死人、幽霊、悪夢のような怪物、死者、これらバートルビーを形容する言葉から、この青年が幽霊的な人物として語られていることは明白である。そして、この点についてドゥルーズが触れていないということも同じくらい明白な事実なのだ。
■手紙を燃やす話―『耳袋』巻之三より
ここでウォール街の事務員の幽霊性について脱線的注釈を入れておこう。
バートルビーは事務所に居ついたからといって、何か特別のことをするわけではない。彼を穏便に解雇(厄介払い)しようと悪戦苦闘している弁護士(「私」)にとり憑いているわけでもない。その証拠に、「私」が事務所を移転しても、その引っ越し先まで追いかけてくるわけでもなく、「私」の去ったもとのビルディングに居座っている。つまり、バートルビーが幽霊だとして、それは人にとり憑くタイプではなく、場所にとり憑く幽霊なのである。場所にとり憑く幽霊の中には、その場所を自分のテリトリーとして、そこに侵入する者を恐怖させるタイプもいるが、バートルビーはただボーっとたたずんでいるだけだ。こうしたタイプの幽霊は、根岸鎮衛の随筆集『耳袋』の「明徳の祈祷其依所ある事」にも記録されている。
「祐天大僧正は其徳いちじるき名僧なりし由。或日富家の娘身まかりしに。彼娘折節一間なる坐舗の角に彷彿とたゝずみゐたる事度々也。両親或は家内のものゝ眼にもさえぎりけるにぞ、父母も大に驚き、「狐狸の為す業や、又は成仏得脱の身とならざるや」と歎き悲しみ、誦経なし或は祈念祈祷をなしぬれど、其印無りければ、祐天いまだ飯沼の弘教寺にありし頃、彼験僧を聞て請じけるに、祐天申けるは、「何方へ出候哉。日々所を替候哉」と尋しに、「日々同じ所に出る」よし語りければ、「我等早速退散さすべし」とて、右一と間へ階子(はしご)を取寄、火鉢に火を起して彼一室に入りて誦経などなせし上、右亡霊の日々佇みけるといへる所へ階子を掛け、祐天自身と天井を放しみしに、艶書夥しくありしを、一つか程に取りて直に火鉢の内へ入れ、扇ぎて煙となし、「此後必ず来る事有まじ」と云ひしに、果して其後はかゝる怪しみなかりけるとなり。娘のかたらふ男ありて、艶書共右天井に隠し置しにこゝろ残りけると、早くも心付し明智の程、かゝる治者にらば祈祷も験奇あるべき道理也。」(『耳袋 上』岩波文庫p330-p331、仮名遣いは適当に変えたところもある)
祐天大僧正は其徳いちじるき名僧なりし由、とは『耳袋』の筆者、根岸鎮衛が回顧して言っている言葉で、この事件のあった当時、祐天いまだ飯沼の弘教寺に籍を置く修行僧であった。したがって愛娘が亡霊化した富家の主人が「彼験僧を聞て請じけるに」というのは、祐天の名声を聞いて招いたということである。祐天は、飯沼弘教寺付近の村で起きた憑霊騒動を解決して一躍有名になった。その顛末は『死霊解脱物語聞書』に詳しいが、同書刊行以前から、口コミなどで広く知れわたっていた。
富家の主がこの若き傑僧を呼んだのは、亡き娘の亡霊が座敷に現れたからである。さて、親たちは、これは狐狸妖怪の仕業か、それとも何かこの世に執着があって往生できないのか、と嘆き悲しみ、いずれにしてもこのままにはしておけないと、いろいろと祈祷をしたけれども、娘の幻は消えない。そこで祐天が呼ばれ、シャーロック・ホームズばりの推理で、娘が天井裏に隠しておいたラブレターを発見(死者のラブレター、デッド・レターズ?)。これが執着の対象であったかと手紙を焼き捨てたところ、怪異はおさまった、という話である。
この話は、明和五年(1768)刊の『新選百物語』にもう少し詳しい類話「紫雲たな引く密夫の玉章」があり、これはラフカディオ・ハーン「葬られた秘密」の原話となったことでも知られている。この話では、幽霊となったのは丹波の国の両替商の若妻お園で、動機は生前の不倫の証拠である手紙一束、それを見抜いて手紙を焼き捨てるのは禅僧太元和尚とされている。この話を、舞台を関東に移し替えたものが、天明の頃から文化十一年(1781-1814)にかけて書き継がれたとみられる『耳袋』に記録されたのだとも考えられよう。
『耳袋』の祐天も、『新選百物語』の太元和尚も、隠されていた手紙を焼き捨てることで、娘の亡霊を往生させたと語られた。ちなみに手紙を焼くという点では、バートルビーも手紙を焼いていたとされる。物語の最後に「私」が披露するバートルビーの経歴についての「噂」「風説」は、彼が配達不能郵便物局で配達不能郵便物(デッド・レターズ)の係をしていたというものだった。
「彼はいつまでもそんな配達不能郵便物を扱い、燃やすためにのみ仕分けするのです。このような仕事よりも、絶望感を深めるのに適した仕事があるでしょうか。荷車一杯の分量でそれらの手紙は毎年焼かれるのです。」(メルヴィル、p100-p101)
バートルビーが焼いていたのは死者の残した手紙ではなく、もはや受取人のいない、死者への手紙であった。
■目にさへぎるもの
『死霊解脱物語聞書』を基準にすると『耳袋』の祐天はリアリティに欠ける。そもそも祐天の事情聞きとりがあまりにも簡単にすぎる。『死霊解脱物語聞書』に記録された祐天は、事前に情報を集め、現場におもむいてからも、羽生村の娘お菊に繰り返しとり憑く累の怨霊と根気よく対話して成仏させている。ところが、『耳袋』の祐天は、幽霊はどこに出るのか、いつも同じ場所なのかどうか、これだけ聞いて、よっしゃあとは任せておけと請け合っており、幽霊と直接対決をしていない。
このことから、私は『耳袋』の「明徳の祈祷其依所ある事」のストーリーは高僧による亡霊供養を語る際のテンプレを用いているのであろうと判断するが、それはこの話の枠組みについてであって、ここで語られる心霊現象(体験)についてではない。この話における心霊現象(体験)の核心とは何か。それを探る上で、この話を記録した『耳袋』という随筆集の特徴を確認しておきたい。
この連載の前々回、第16回「幽霊の理論―江戸編」で指摘したように、『耳袋』の著者・根岸鎮衛には、何らかの関連のある話を並べて書き留める傾向がある。このことを念頭に置くと、「明徳の祈祷其依所ある事」の直前に置かれている「三峰山にて犬をかりる事」が注目される。
武州秩父(埼玉県)の三峰山にある三峰権現(現在は三峰神社)は、火難・盗難除けに霊験あらたかな神として諸人の信仰を集めていた。人気のある霊山なのでその別当(社僧)のところには金がザクザクあるのだが、その金を盗むと、盗人は乱心したり、足腰が立たなくなったりして下山できなくなるという。それくらい有難い三峰権現の発行する火難・盗難除けのお札をもらうことを「犬をかりる」と言うこともあったそうだ(『耳袋』の記述)。ちなみに、この習わしは現在でも「御眷属拝借」として続いている。犬とは狼のことで、大口真神として神格化され、三峰山の神の眷属とされている。三峰権現のお札をもらうとは、この狼様をお借りして帰るということだ。
さて、ある人が三峰権現のお札をもらいに来て、別当にこんなことを願った。「犬をかりるといいますが、実際にはお札をもらうだけです。これで犬を貸してくださったことになるのでしょうか。霊験をこの目で見せていただきたい(神明の冥感目にさへぎる事を)」。そこで別当はその願いがかなうようにと祈祷してからお札を授けた。その帰り道、山を下りていくと一頭の狼が後になり先になりついてくる。霊験の偽りでないことを知ると同時に、狼を連れて帰ることの恐ろしさに、権現社に戻ってわけを語り、霊験を疑ったことを後悔して「お札だけいただきたい」と願うと、別当はあらためて祈祷してお札を授けたところ、「其後は狼も目にさへぎらずありしとや」。
この「三峰山にて犬をかりる事」を先の「明徳の祈祷其依所ある事」と読み比べてみると、高徳の僧の法力つながりのように見えもするが、よく読むとそれだけではない。そもそも三峰権現の別当は「福有」(裕福)だとは書かれているが、法力があるとは書かれていない。祐天については、『死霊解脱物語聞書』の塁を成仏させたのも法力によるものではないし、幽霊の残したラブレターを見つけたのも観察力・洞察力が優れていたということだろう。
それでは、この二つの話の共通点は何かというと、霊異の見え方についての表現が同じなのである。
「三峰山にて犬をかりる事」→目にさへぎる・目にさへぎらず
「明徳の祈祷其依所ある事」→眼にもさえぎりける
「目にさへぎる」は、『耳袋』の記事の文脈から察するに、目先にちらつく、視界に不意に現れる、ということのようだ。見ようとせずとも見えてしまう、そんな視覚体験のようである。根岸鎮衛が「三峰山にて犬をかりる事」の次に「明徳の祈祷其依所ある事」を書き留めたのは、この視覚体験のありようの共通性からだったろうと私は考えている。
さて、「明徳の祈祷其依所ある事」で語られた娘の亡霊は、座敷の片隅でぼーっとたたずんでいるだけで何かをするわけでも、何かを訴えるわけでもない。ただ、家族らの目をさえぎる、つまり視線の先に現れる、視界の中に浮かび上がるだけである。その姿は、見る者が見ようとして見ているというよりは、見えてしまうのである。
とはいえ、ただいるだけ、ただ見えるだけといっても、富家の娘はいつも同じ座敷にただずんでいた。いつも同じ場所に現れるということから、その場所になにか特別な思いがあるのではないかという憶測を人々にいだかせ、幽霊の遺念についてさまざまな解釈が語られる。『耳袋』の祐天の洞察もそんな解釈の一つである。隠されていた恋文を燃やしたあと、娘の姿が現れなくなったことからそれは正解とみなされたようだが、幽霊自身が何も語っておらず、祐天も幽霊との直接対話をしていない以上、ほんとうのことはわからない。
バートルビーの雇い主も、彼がなぜ何もしようとしないのか、解雇を言い渡されてもなぜ出て行かないのかについて、あれこれと(好意的な)推測をしていたが、これも本当のところは結局わからずじまいだった(「あなたはその理由をご自分でおわかりにならないのですか」)。ただ、配達不能郵便物(デッド・レターズ=死者からの手紙、死者への手紙)を燃やすためにのみ仕分けしていたバートルビーの身の上に言及し、「ああ、バートルビー! ああ、人間の生よ!」と絶句して物語を締めくくった「私」は、何かに触れていたような気もする。
■ゴジラ対バートルビー
バートルビーの幽霊的特徴についてドゥルーズが触れていないと言ったが、彼のメルヴィル論「バートルビー、または決まり文句」(『批評と臨床』所収)には、バートルビーの特徴として「突如として現れ、姿を消す人間」(前掲書、p157)であることが指摘されている。「突如として現れ、姿を消す」ことは、幽霊の特徴としていくつか考えられるものの一つでもある。「突如として現れ、姿を消す人間」がいるのなら、それは忍者か幻術師か幽霊である。普通の人間なら突如として姿を現し、突如として姿を消したりはしない。したがって、バートルビーが幽霊的特徴を具えていることをドゥルーズも暗に認めていることになる…、はずだ…、たぶん。この細い糸を頼りにして、もう少し屁理屈をこねてみようと思う。
とりあえず、ドゥルーズ自身が明言していないので積極的にそうだとまでは言えないが、消極的には、つまりそれを強く否定することはできないという程度の意味で、バートルビーには幽霊的性格があるということにしよう。それでは、仮構機能の作り出した被知覚態としての人物像であるかどうかについてはどうだろうか。この点について、ドゥルーズがはっきり明言しているのは「エイハブ船長とモービィ・ディックの幻影」である。この例は、幽霊というより妖怪、いや怪獣に近い。白鯨ことモービィ・ディックは、ゴジラみたいなものだ。ゴジラとバートルビーではずいぶんとスケールが違う。だが、もしかして、あのバートルビーならゴジラが襲ってきても一向に動じず「出て行かない方がいいと思います」と平然としているかもしれない。よし、このイメージに賭けよう、がんばれ!バートルビー。
そんなことを思いながらドゥルーズのメルヴィル論を読み進めていくと、まるで、私の邪まな関心を見抜いたかのような文章に行き当たった。
「われわれは、エイハブ船長とバートルビーという、これほどまでに異なる人物を混ぜ合せようとしている。あらゆる点で、二人は正反対なのではないか?(中略)偏執狂者と憂鬱症者、悪魔と天使、死刑執行人と犠牲者、〈速きもの〉と〈緩慢なるもの〉、〈雷で打つもの〉と〈石化したもの〉、〈罰しえぬもの〉(あらゆる罰の彼方にある)と〈責任を負わぬもの〉(あらゆる責任の手前にある)だ。」(ドゥルーズ、前掲書、p166)
しかし、これはドゥルーズ自身の文章なのだ。なんと、案ずるより産むがやすし、ドゥルーズ自身がゴジラもといエイハブ船長とバートルビーを対になるものとして語っているではないか。ドゥルーズは「メルヴィルの作品に出てくる偉大な人物を分類」して、「一方の極には偏執狂ないし悪魔」つまりエイハブ船長タイプ、「もう一方の極には、天使ないし聖なる憂鬱症患者」であるバートルビータイプがいるとし、両者は「あらゆる点で正反対」でありながら「両者とも同じ世界にとりついており、互いに交替する」としている。
「それというのも、両者、つまり人物の二つのタイプ、エイハブとバートルビーはあの根本的な〈本性〉に属し、そこに住みつき、構成員となっているからだ。二人はなにもかもが正反対だが、それでいて、本源的で、独特で、頑固で、二方向からとらえられている。つまり、「プラス」の記号か、「マイナス」の記号の影響だけを受けているという点で、おそらくは同じ被造物なのだ。」(ドゥルーズ、前掲書、p168)
なおドゥルーズは、エイハブ船長ともバートルビーとも違う第三のタイプとして、バートルビーの雇い主であった弁護士「私」を挙げているが、これは前二者に比べれば副次的人物とされているので、今は置いておく。私の心霊学にとっては、ドゥルーズの視点から見たとき、バートルビー(幽霊的人物像)がエイハブ船長と正反対のようでありながら、ある意味で同類であり、交替可能だということが確認できればそれで十分なのだ。念のためダメ押しをしておくなら、ドゥルーズはバートルビーを〈独創人〉の一人としており、「独創人は、一人ひとりが孤独で力強い〈図形(人物)〉(フィギュール)であり」、エイハブ船長もそうである(「エイハブまたはバートルビー……」)。
■死者への手紙
以上のことから、ドゥルーズの言うようにエイハブ船長が仮構機能の作り出した被知覚態としての人物像であるなら、バートルビーも仮構作用によるヴィジョン(幻視)の一例とみなしても当たらずとも遠からずだと言ってもよいように思う。ちなみにドゥルーズはこのメルヴィル論を次のようにしめくくっている。
「バートルビーは病人ではなく、病めるアメリカの医者、呪医(メディシン・マン)であり、新たなるキリスト、あるいはわれわれすべてにとっての兄弟なのである。」(ドゥルーズ『批評と臨床』河出文庫p186)
バートルビーが病めるアメリカの呪医であるなら、さぞや巨大だろう。巨人とは、ベルクソンのいう仮構作用によって生み出された人物像の特徴としてドゥルーズが挙げたものだった(ベルクソン自身は巨人とは言っていないにもかかわらず)。
ところで、私の当て推量どおりにバートルビーが仮構機能による人物像(被知覚態)だとして、しかし、この物静かな青年のヴィジョンがいったいどのようにして「一つの民衆=人民(ピープル)を創り出す」のだろうか?この問いは、私の心霊学の範囲外にあるのだが、気にならないでもないので、中途半端に言及しておく。
バートルビーがアメリカの呪医だとして、メルヴィルが仮構機能によって作り出した被知覚態が巨人として実体化して、SFアニメ(例えば『エヴァンゲリヲン』とか)のように、現実の巨大資本主義国家アメリカを癒したりするわけがない。そうすると、やはり、存在しないドイツ国民に呼びかけたフィヒテの行為遂行的言説(ドイツ国民に告ぐ!)よろしく、呼びかけることによって「一つの民衆=人民(ピープル)を創り出す」のだろうか。仮にそうだとして、それが成功する確率は、はなはだ稀なことではないだろうか。
1990年のインタビュー「管理と生成変化」(ドゥルーズ『記号と事件』所収)で、ドゥルーズとガタリの『千のプラトー』に「悲痛な声」を聞き取ったというネグリは、2000年にマイケル・ハートとの共著『〈帝国〉』を発表し、そこでバートルビーについて、ドゥルーズやアガンベンの「存在論的解釈」を念頭に置きながら次のように言っている。
「バートルビーの拒否はそれほどまでに絶対的なものであるので、彼は完全な空白、特性のない男〔人間〕、あるいはルネサンスの哲学者たちならホモ・タントゥムと呼ぶであろう者、すなわち、ただの人間にすぎないもののように見えてくる。」(ネグリ、ハート前掲書、水嶋一憲・酒井隆史・浜邦彦・吉田俊実訳、以文社、p265)
「これらのたんなる人間と彼らの絶対的な拒否は、権威に対する私たちの憎しみをそそらずにはおかない。労働と権威の拒否、つまりじつをいえば自発的隷従の拒否は、解放の政治の始まりにほかならないのだ。」(ネグリ、ハート前掲書、p266)
しかし、その拒否(「ぼく、そうしない方がいいのですが」)は、解放の政治の始まりだとしても「それはたんなる始まりにすぎない。拒否することそのものは空虚な振る舞いでしかない」。バートルビーは「美しい魂の持主であるかもしれないが」、「完全に独りぼっち」で「いまにも自殺しそうな状態」にある。「政治的な観点からしても、(労働や権威や自発的隷従を)拒否することそのものは、一種の社会的な自殺にしか通じていないのである。」(ネグリ、ハート前掲書p266-p267)と手厳しい。ネグリは「たんなる拒否を超えて」、「新しい生の様式」、「新しい共同体を構築すること」が必要だとぶちあげるのだが、その当否こそ、私の「心霊学」的関心の範囲外であるのでもうこれ以上は触れない(ネグリは幽霊には興味がないようだ)。
説話のなかの祐天は、江戸時代の呪医として、死者の遺した手紙を焼き捨てることによって、亡霊(あるいは亡き娘の姿が目をさえぎることに悩む家族)を癒した。配達不能郵便物(デッド・レターズ)の係をしていたバートルビーも、手紙を焼いているが、それはもはや受取人のいない、死者への手紙であった。死者の遺した手紙と死者への手紙とでは、正反対の性格を持つ。語り手「私」はかつてのバートルビーの仕事をかなり感傷的に想像している。
「あの青白い職員は、時には折りたたまれた手紙から指輪を取り出したことでしょう―その指輪がはめられるはずだった指は、もしかするともう墓の下で朽ちているかもしれません。窮状を救うとして大急ぎで送られた紙幣―その紙幣が救うはずだった男はもはや食べることも飢えることもありません。自暴自棄になって死んだ者への許しの手紙、絶望のうちに死んだ者への希望の手紙、救われない不運によって煩悶死した者への吉報、人に伝える使命を抱きながら、これらの手紙はすべて死へと急ぐのです。」(メルヴィル、p101)
「私」の想像通りなら、バートルビーは、仮に彼自身が「一つの民衆=人民(ピープル)を創り出す」巨人だったとして、「一つの民衆=人民(ピープル)」を創り出したかもしれない呼びかけ(すなわちバートルビー自身)が焼却処分されるのをその目で直視していたということになる。この文章を読むと、おそらくはドゥルーズの意に反して、投瓶通信というアドルノに由来するヴィジョンが私の目をさえぎる。その手紙を受け取る人はいるのだろうか。私もまた「私」とともに絶句する。
「ああ、バートルビー! ああ、人間の生よ!」
短編『バートルビー』は、柴田元幸・訳で下記のサイトに無料公開されております。 『書写人バートルビー ──ウォール街の物語』https://info.ouj.ac.jp/~gaikokugo/meisaku07/eBook/bartleby_h.pdf ★プロフィール★
広坂朋信(ひろさか・とものぶ)1963年、東京生れ。編集者・ライター。著書に『実録四谷怪談 現代語訳『四ッ谷雑談集』』、『怪談の解釈学』、共著に最新作『猫の怪 (江戸怪談を読む)』など。ブログ「恐妻家の献立表」 Web評論誌「コーラ」40号(2020.04.15)
<心霊現象の解釈学>第18回:バートルビー、または目をさえぎるもの(広坂朋信)
Copyright(c) SOUGETUSYOBOU 2020 All Rights Reserved.
|
| 表紙(目次)へ |