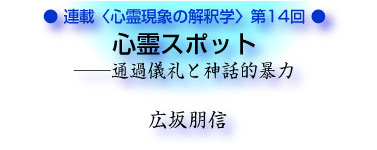|
|
|
Web評論誌「コーラ」 |
|
■創刊の辞 ■本誌の表紙(目次)へ ■本誌のバックナンバー ■読者の頁/ご意見・感想 ■投稿規定 ■関係者のWebサイト ■プライバシーポリシー |
|
<本誌の関連ページ> |
|
■「カルチャー・レヴュー」のバックナンバー ■評論紙「La Vue」の総目次 |
Copyright (c)SOUGETUSYOBOU |
|
|
|
「古代ギリシアては、冥府へ下る入口だといわれる場所がいくつもあった。私たちが目覚めているときの生活もまた、いくつもの隠された場所に冥府へ下る入口のある土地であり、夢が流れ込んでくる目立たない箇所に満ちている。」(ベンヤミン「パリのパサージュ2」、『ベンヤミン・コレクション6 断片の力』ちくま学芸文庫より)
心霊スポットについては、以前この「コーラ」にも書かせていただいたような気がしていたが、今バックナンバーを確かめると私の思い違いであった。近年、小野不由美『残穢』(新潮社)の映画化(竹内義洋監督、2016)、川奈まり子『実話怪談 出没地帯』(河出書房新社、2016)、吉田悠軌『怪談現場東京23区』(イカロス出版、2016)、澤村伊智『ししりばの家』(角川書店、2018)、松原タニシ『事故物件怪談 恐い間取り』(二見書房、2018)などのヒットもあってか、すでに引退した心霊スポット・ライターの私にも久しぶりにお座敷がかかって、人前で何か話さなければならないことになった。その心覚えのために、あらめて心霊スポットについて考えていることをここに書き出しておく。
幽霊、あるいは妖怪が住みついていると噂される場所があり、近年では「心霊スポット」と呼ばれる。そこで肝試しのことを心霊スポット・ツアーと呼ぶことも多い。
本稿では「心霊スポット」という語を文字通り「心霊が依り憑く場所」としてではなく、怪異が起こる(起こった)として伝えられる場所、という程度の意味で用いる。なお、心霊スポットの「心霊」とは、幽霊(人間の霊魂の顕現とされる幻)であったり、妖怪(怪異の主体としての精霊・神霊)であったりするが、あまり厳密に考えず、怪異の主体の総称として理解しておくことにする。
心霊スポットは、日本全国にある。ひとしきり話題になって忘れ去られてしまう場所もあれば、幽霊や妖怪を神として祀る寺社ができて伝説を偲ぶ名所となっているところもある。
従来、心霊スポットの条件は、通俗読み物を通して流布された「心霊学」的知識によって、地縛霊という観念で説明されてきた。すなわち非業の死を遂げた者の霊魂が命を落としたその場所に思いを留めている状態を地縛霊と呼び、地縛霊の憑いている場所が心霊スポットである、という説明である。
ところが広島市と長崎市には原爆によって非業の死を遂げた者が無数にいるわけだから、街中に心霊スポットが遍在していてもおかしくはないのに、そうした話はあまり聞かない。一方で、沖縄の戦跡にはたくさんあるのだそうだ(仲村清司『ほんとうは怖い沖縄』新潮社、2010)。地縛霊についての説明は、あたかも自然現象の起きる条件についての説明のようになされるが、地域差があるということは非業の死イコール死亡現場への憑依という図式では語れないことは明白である。
とりあえず、地縛霊という考え方には積極性はない。もちろん、一定の場所に居続ける幽霊や妖怪もいるだろう。だが、それは幽霊や妖怪にとってその場所に居続ける理由があったからと理解するべきであって、「地縛」という形容はふさわしくない。ましてやそれで心霊スポットの条件を説明したことにはならない。
しかし、地縛霊という考え方が登場した事情の方はよく理解できる。本稿では現代風に心霊スポットと呼んでいるが、聖地、霊地、または魔所、魔境と呼ばれてきたような、なにやら俗世とは異なる雰囲気を漂わせ、奇跡や怪異が起きたと伝えられる場所は確かにある。(ここまで、一柳廣孝監修、今井秀和・大道晴香編著『怪異を歩く』青弓社に寄稿したエッセイ「よみがえれ、心霊スポット」と一部重複することをお許し願いたい)。
狐屋敷の怪―─『新選百物語』より
心霊スポットという呼び名こそ、そう古いものではないが、幽霊や妖怪の住みついている場所があるという伝承は洋の東西を問わず古くからある。日本の場合、化物屋敷などと呼ばれることが多い。どこまでさかのぼれるかは知らないが、すでに平安時代にはそれらしい場所があった。今回はそのようなケースを、江戸時代の怪談集『新選百物語』(篠原進監修/岡島由佳翻刻・訳、白澤社)からいくつかご紹介する。
この『新選百物語』はラフカディオ・ハーンのネタ本だったことで知られているが、破損した部分があるため著者や刊行年が確定できず、これまであまり研究されてこなかったどころか、翻刻の公刊すらされていなかった珍本である。収録されているのは全十五話(内一話は結末を欠き、最終話は挿絵のみ残存)で、本自体は珍本だが、各話のストーリーは他に類話があって、昔話や伝説などにヒントを得て創作されたフィクションだろうと想像される。同書に描かれる怪異は体験談ではないし、その内容も近世の怪談としては特に珍しいものとはいえないが、だからこそ、江戸時代の人々の怪異と場所との結びつきについての感覚を垣間見ることができるように思われる。
まず化物屋敷の怪異については巻五の一「思ひもよらぬ塵塚の義士」で描かれる。信州のある村に、狐屋敷と呼ばれる塵塚があった。そこが狐屋敷と呼ばれたのは、狐が人を化かすという噂が流れたからであろうが、村で手習いの師匠をしている武士はそんな噂は気にせず、村人からすすめられるままに、そこに屋敷を新築した。
怪異は新築祝いの宴が散会したその晩から始まった。夜も更けたころ、庭先から下駄の音がかすかに聞こえる。なんだあの音は? と不審に思っているうちに、ガタリ、ガタリと下駄の音は近づき、武士が刀を引き寄せ警戒していると、屏風の向こうから苦しげな声で敵討ちを頼む声がし、それが夜明けまで続いた。こうしたことが毎晩続いて、五日目の夜、また怪異が訪れたところを武士が「何奴!」と誰何して屏風を引き払うと、古びた髑髏が一つ。「おのれ、正体を現せ」と詰め寄れば、髑髏は実は自分は父の仇を追ってここまで来たが、ついに仇を討ち果たせぬままこの地で息をひきとった者で、往生できずにここに住みついた人に敵討ちを頼んだが皆恐れて逃げ出してしまったと告白。武士は亡霊に同情し、かわりに仇を討ってやりました、という話である。
化物屋敷と知って住みつく勇士の話は化物屋敷譚の定型と言っていいし、亡霊に仇討を頼まれる話もいくつもあるが、この話の基本は、不吉な噂のある土地に建てられた住宅に亡霊が現われる話である。この「塵塚」とは辞書によればゴミ捨て場のことだそうだが、ここでは廃屋としておいてもよいように思う。不吉な噂のある廃屋を更地にして立てた住居に現われる怪異といえば、江戸怪談では皿屋敷がそうだし、また、現代の小説で言えば『残穢』がこの系譜に入る。
ポイントは、不吉な噂のある土地の廃屋にそのまま住みつくのではなく、いったん廃屋を取り壊して住居を新築していることである。真新しい建物の建っている土地は、かつては狐屋敷と呼ばれる廃屋だった。つまりそこでは過去と現在が線引きされながらも、重ね合わされている。
霰松原の妖怪―─『新選百物語』より
住居ではなく町はずれの荒れ地に怪異が現われるのは『新選百物語』巻四の一「鉄砲の響にまぬかる猟師が命」。姑獲鳥(らしきもの)や大入道(の首)がドーンと登場する妖怪退治譚である。
舞台は、現在の大阪市住之江区安立町の付近。このあたりはかつて霰松原と呼ばれる風光明媚な土地だったが、今では針などを商う人家の立ち並ぶ町になった、と語りだされる。霰松原は歌枕の一つで、現在、同地にある霰松原公園にその名残をとどめており、江戸時代に針を扱う商人が多かったのも事実だったようだ。
怪異は安立町の南側を流れる大和川流域で起きた。人家の立ち並ぶ紀州街道沿いの町を離れると、夜はひと気のないさびしい松林となる。そこで堺の町から帰ってきた二人連れの尼僧が、赤子を抱いた女から、この子を抱いてくれてと頼まれる。ウブメの怪である。これは只者ではないと直観した尼僧らは念仏を称えながら通り過ぎて難を逃れた。だが、その後も夜にこのあたりを通る旅人が殺されたり行方不明となることがあいつぎ、妖怪退治のために雇われた猟師も、大和川にかかる大和橋のあたりで巨大な坊主の首ににらまれ、足をつかまれて投げ飛ばされた。幸い、持っていた鉄砲の引き金が引かれ、銃声が鳴り響いたおかげで猟師は助かり、高僧を招いて祈祷をしたところ、その後、怪異はやんだという。
この話の舞台も、いにしえの名所・霰松原と現在の安立町と、過去と現在が重ねあわされた土地として設定されている。
井戸の底からの招き―『新選百物語』より
『新選百物語』にはもう一話、場所が問題となる怪異が描かれている。巻五の二「井筒によりし三人兄弟」がそれである。タイトルから知れる通り井戸が問題の場所だ。
現在の徳島県の佐古の町に三人兄弟で経営する加嶋屋という大店があった(業種不明)。あるとき、加嶋屋兄弟の長兄が井戸に落ちて死んだ。次男が跡を継いだが、この次男も長兄の一周忌の夜に井戸に落ちた。このときは幸いにも井戸から引き上げられて回復したが、その後また井戸に落ちて死んだ。こうたて続くと、何か隠された理由があるのではないかと、親類一同が調べたが、長兄は人格者、次男にも浮いた噂もなく、借金もなかった。結局、三男が跡を継いで、次男の一周忌が過ぎて十日ばかりたった夜、三男も井戸に落ちた。これもすぐに引き上げて薬を飲ませたりしたところ、精神状態が安定しなかったが、三十日ばかりたつと正気に返った。そこで親類らが集まって「どうして井戸に飛び込んだのだ?」と問いただすと、三男の言うには、夜眠っていると誰かの呼ぶ声がする。夢かと思ったが井戸の方からたしかに声が聞こえるので起きていくと、死んだ兄たちが井戸から半分身を乗りだして手招きしている。それを見た途端に、戦慄と恍惚の気分に襲われて井戸に入った、そこから先は覚えていない。三男はそう語った。加嶋屋の人々は、これは只事に非ずと、ただちにこの家を立ち退き、方角を考え地祭りして(方違えをしたのだろう)、大工町(現在の徳島市)に宅地を求めて家業を再開すると、怪異は起らず商売繁盛し子孫も繁栄した。
この三人兄弟連続自殺(一名は未遂)事件の話では、井戸にどのようないわく因縁があったのか(あると思われたか)については何も語られない。この話は「狐たぬきの所為なるか、其のゆえんをしらずとある老人のかたられし」と終わっている。つまり、怪異の理由がわからないのである。この点は、霰松原の妖怪も同じで「何の所為といふ事をしらずと語られける」と締めくくられている。これも理由がわからないのである。
もちろん、そもそも理由がわからないからこその怪異なのだと開き直ってしまうこともできる。「塵塚の義士」の場合も、怪異の原因が、仇討ができずに死んだ男の亡霊の訴えだったとわからないうちは、「狐屋敷」と名づけられたように、妖怪が住みついたと思われていたのだろう。理由がわかってしまえば、幽霊の出現自体が怪異かどうかを棚上げにさえすれば、仇討の助太刀を頼まれたこと自体は怪異ではない。
怪異の理由をつきとめたことによって怪異を怪異ではなくした「塵塚の義士」に対して、理由のわからない三人兄弟連続自殺・自殺未遂事件の関係者らは、ともかくその場を離れることによって災厄を遠ざけた。井戸から兄弟を誘ったのが本当に兄たちの亡霊だったのか、狐狸妖怪の仕業だったのかはわからないが、その井戸にさえ近づかなければ災厄をまぬかれえると考えたのである。
村はずれの廃屋、町はずれの松林、河原、橋、そして井戸は、民俗学系妖怪学では、「境界」と呼ばれる。とりわけ、宮田登が『妖怪の民俗学』(岩波現代文庫)等で展開した境界説は、地縛霊説を越える心霊スポットの説明理論として注目される。宮田氏の遺著『都市空間の怪異』(角川書店)にその要約ともいえる文章があるので引いておこう。
「妖怪の出現にあたっては、その場所性というものが、強く影響していることはこれまでも指摘されてきた。具体的には、三辻とか四辻といった道が交差する地点あるいは橋のたもとであるとか、橋の中間部、坂の頂上とか、坂の中途などに独特な境界がある。それは私たちが無意識のうちに伝えている民間伝承の累積として定着している民俗空間の中に位置づけられている。」(宮田、前掲書)
ここでは交差点、橋、坂が例に挙げられているが、境界とはそれらだけに限定されるものではない。宮田氏の意図を忖度するならば、ある空間の内側から見たときの外部と内部を隔てると同時に連絡するような場所が、現在と過去、この世とあの世(異界)の接点と重ね写しされて意識されるときに、その場所が「境界」となる、と理解すべきだろう。『新選百物語』で妖怪の現われた霰松原は、大和川で隔てられた堺との境界の地でもあった(堺という地名自体が境界という意味でもある)。村はずれの廃屋が狐屋敷と名づけられたのは、そこが狐(に代表される自然)の住まう山界との境界に位置していたからだろう。井戸もまた、地下という異界との通路を連想させる施設である。
ベンヤミンの「敷居学」と心霊スポット
小松和彦は『妖怪文化入門』(角川ソフィア文庫)で、欧米の「境界」に関する理論的研究書として、ジュネップ『通過儀礼』、ダグラス『汚穢と禁忌』、ターナー『儀礼の過程』とならべて、ベンヤミン『パサージュ論』をあげている(小松、前掲、223頁)。しかし、ベンヤミンの『パサージュ論』(邦訳は岩波現代文庫で全5巻)は、パリのパサージュ(アーケード商店街)をめぐる膨大な未完成の草稿で、都市論、ボードレール論、資本主義論、歴史哲学など多岐にわたるテーマが散りばめられており簡単には扱えない。ただ幸いなことに境界論については、メニングハウス『敷居学』(現代思潮新社)がある。
メニングハウスはベンヤミン『パサージュ論』に頻出する「敷居」というタームに着目して、ベンヤミンの著作の全体を「敷居学」として特徴づけようとしている。もちろん敷居とは、まず家屋の戸口のことだが、「たとえば上の世界と下の世界を分かつ移行の境界線としての湖面や、冒涜すれば婚姻関係の侵犯の場合と同じく償いを覚悟しなければならない墓地のような空間的敷居であったり、あるいは年代の変わり目や特別な記念日(誕生日、定礎式、棟上式)に見られる移行の儀式のような時間的敷居」(メニングハウス、前掲書、42〜43頁)も例に挙げられていることから、広く境界のことと受け取ってさしつかえないように思う。
境界が人間に与える影響をベンヤミンは「敷居の魔力」と呼ぶ。
「通過儀礼(rites de passage移行儀礼)とは民俗学で、二つの状態、空間、時間の間の敷居が乗り越えられることを意味する。たとえば「帰国してきた軍司令官がローマの凱旋門をくぐれば、凱旋将軍ができあがる」とベンヤミンはいう。これは「通過儀礼と関連している」が、同様にパリの街路にも、いやベンヤミンの神話的な「地誌学」の全体にもあてはまる。こうした行為としてのパサージュ(移行)―─すなわち場所としてのパリのパサージュ(街路)だけではなく―─は常に「敷居の魔力」や「敷居を越える経験」に、空間と時間の連続体における中間休止に結びついている。」(メニングハウス、前掲書、9頁)
肝試し、心霊スポット探訪もある種の「敷居を越える経験」である。通過儀礼の経験だともいえるが、儀礼行為はそれに現実的な意味を与える共同体の規範がなければ無意味である。
「通過儀礼―─死や、誕生や、結婚や成人などに結びついた儀式を民俗学ではこう呼ぶ。近代の生活ではこうした節目は次第に目立たなくなり、体験できないものになってしまった。われわれは、別の世界への敷居を超える経験にきわめて乏しくなってしまっている。」(ベンヤミン『パサージュ論』第3巻、岩波現代文庫)
心霊スポットに行くことが社会の成員として認められるために必要な課題であるならともかく、首尾よく怪異に遭遇したとしても、せいぜいが仲間内で誇れる程度のことである。通過儀礼の要件を満たすとはいえない。あくまでも娯楽としての肝試しの域を越えるものではない。しかし、肝試しがかつては通過儀礼だったころの名残を留めているように、心霊スポット探訪も単に興味本位の娯楽にとどまらず、なにか、大勢の人々を惹きつける要因があったのに違いない。
他界から異界へ
心霊スポットは、どこかに現実にあるとされながらも、この世のものならぬ死霊や神霊の支配する異界と地続きになっている場所だと思われている。それは本来、あの世であり、死後の世界=他界でなければならないはずである。
他界がこの世と地続きの異界に転化することについては吉本隆明の指摘がある。
「村落共同体の共同幻想は、ハイデガーのいう「その死に向って存在している」現存在の時間性を、空間の方に疎外した。それだから〈他界〉は、個体にとって生理的な〈死〉をこえて延びてゆく時間性にもかかわらず、村境いの向う側の地域に〈作為〉的に設けられたのである。
ほんらい村落のひとびとにたいしては時間性であるべき〈他界〉が、村外れの土地に場所的に設定されたのは、きっと農耕民の特質によっている。土地に執着しそこに対幻想の基盤である〈家〉を定着させ、穀物を栽培したという生活が、かれらの時間意識を空間へとさしむけたのである。」(吉本、『共同幻想論』角川文庫)
引用した文章の前段を、そこで吉本には使われていない異界という言葉を使って言い直せば、次のようになる。すなわち、生きているものの世界はどこまでもこの世であり、あの世(他界)ではない。あの世にいくには死ぬほかはない。他界はあくまでも死んだ後の世界である。この世とあの世の境界は、死ぬ前と死んだ後という時間的な区分である。この時間的な区分を村境のこちら側と向こう側に転化したのが異界である、ということになる。
つとに知られているように、吉本の『共同幻想論』は、柳田国男の『遠野物語』を主な材料に、「人間にとって共同の幻想とはなにか」という問いに応えようとしたものであり、引用した文章も『遠野物語』の山中異界譚、幽霊譚、棄老譚を考察した「他界論」からである。
一読すれば誰しも、近代化の浸透したとは言い難い明治時代の村落社会の成員の意識を、不可逆性、単線性を特徴とする近代的な時間概念をツールにして批評することに妥当性があるのかどうか気になるところだろう。
しかし、ここで吉本を引いたのは彼の議論を批判するためではない。むしろ、引用した吉本の指摘が半ば近世的な村落社会の成員についてよりも、近代化の浸透した私たち現代人の意識の方によく当てはまるのであれば、そのように読み替えて事態を明らかにするための道具として使うことができる。
日帰りの地獄めぐり
私たちの大多数は時間について、過去から現在を経て未来にいたる時間の流れは不可逆的であるとイメージしている。各個々人においては個性的な時間イメージを内に秘めているとしても、私たちの社会生活は時間の不可逆性、単線性を基準にして営まれている。乗り遅れた電車を呼び戻すことはできないし、期日までに支払ができなければ督促状が舞い込むことになる。
ハイデガーが「その死に向って存在している」(『存在と時間』)と人間の在り方を規定するときの時間概念も、不可逆性と単線性を基本にしている。それは哲学者だけの特殊な時間ではなく、私たちの誰もがそれに追い立てられて生活している近代社会の標準時間である。だから「ほんらい」「〈他界〉が」「時間性であるべき」なのは「村落のひとびとにたいして」ではなく現代社会に生活する私たちに対してなのだ。そうすると引用した吉本の文章の後段はもとの文脈から切り離して次のように読み替えられる。
―――ほんらい近代社会のひとびとにたいしては時間性であるべき〈他界〉が、町外れの土地に場所的に設定されたのは、きっと都市民の特質によっている。土地をもたずそこに対幻想の基盤である〈家〉を定着させず、労働時間を賃金に換える生活が、かれらの時間意識を空間へとさしむけたのである。――
多くの都市民の生活は、タイムカードに刻印された労働時間を換金することで成り立っている。単調であるにもかかわらず、やり直しのきかない近代的時間に支配された生活から離脱しようにも、土地(生産手段としての農地)をもたず、共同体的社会に加入していない都市の青年層には選択肢はあまりにも少ない。かつては定年まで勤め上げて退職金でローンを完済し郊外のマイホームで悠々自適の老後を送る人生設計にもそれなりのリアリティがあったのだろうが、バブル崩壊以後、それはむなしい夢物語となった。
右肩上がりの未来がないにもかかわらず、じわじわと追いつめられながらも単調な時間を繰り返していかねばならない。それは近代的時間によって我が身をすり減らしていく経験である。祝祭的時間の到来が期待できないとしたら、残るのは時々自らをリフレッシュして毎日の単調さに耐えうる自分を維持するほかないではないか。
リフレッシュが決して通過儀礼であるはずがないのは、死と再生のイニシエーションは祝祭的時間において行われるものだからだ。しかし、「移行とそこに捧げられる儀礼は、すべてを平坦化する近代の生活においてますます「目立たなくなり、体験できないものになってしまった」(メニングハウス、前掲書、p90)。「すべてを平坦化する近代の生活において」は、時間軸上に変身や成長のドラマを期待することは既に放棄されている。
現代の都市民には、死してのち蘇る儀式よりも、現世の空間上の場所に置き換えられた死(心霊スポット)に至近まで近づいてダッシュで逃げ帰る、いわば日帰りの地獄めぐりの方が、自分の生存を再確認し再び元気づけられるという意味でのリフレッシュとしてリアリティをもっているのかもしれない。
神話的暴力
小松和彦の示唆に従ってベンヤミン『パサージュ論』を参照すると、心霊スポットとは効力を失くした通過儀礼の場所ということになるが、ある境界的な場所が肝試しという通過儀礼を行うのにふさわしいとされる理由はそこからは出てこない。『パサージュ論』では、境界、敷居や門はすでにあるものとして語られているからだ。そこで、同じベンヤミンを媒介として別の推論をしてみたい。ただし、私が着目するのは『パサージュ論』ではなく、『暴力批判論』である。
ベンヤミンは『暴力批判論』において、法的暴力の自家中毒ともいうべきジレンマ(これは現代的な言い方をすれば構造的暴力と言ってもよい)を破壊するような「別種の暴力」を要請する。それは「ある決まった目的に手段として関係しているわけではない暴力」であり、顕現としての暴力(宣言としての暴力)である。「ここで問われているような、媒介的ではない暴力の機能」として、ベンヤミンは「憤激」を挙げる。
ベンヤミンによれば憤激のような暴力は「手段ではなくて、宣言」であり、「この種の宣言のもっとも含蓄のあるものは、何よりも神話のなかに見られる」として次のようにいう。
「神話的な暴力は、その原型的な形態においては、神々のたんなる宣言である。その目的の手段でもなく、その意志の表明でもほとんどなくて、まず第一に、その存在の宣言である。ニオベ伝説は、これの顕著な一例をふくんでいる。」(ベンヤミン『暴力批判論』岩波文庫、p55)
いま引いたところを別の訳でも読んでみる。
「原像的な形態における神話的な暴力は、神々のたんなる顕現にほかならない。神々が抱く目的の手段ではなく、神々の意志の顕現でもほとんどなく、まずもって神々の存在の顕現なのである。」(ベンヤミン『ドイツ悲劇の根源(下)』ちくま学芸文庫、p264)
神話的暴力は、それが怒りのように、目的に対する手段ではないにもかかわらず、結果としては(「客観的な顕現様態」においては)法措定的暴力になってしまう、というのがベンヤミンの趣旨である。
ベンヤミンは神話的暴力の顕著な例として、ギリシア神話からニオベーの伝説をあげる。
ニオベ伝説
ベンヤミンが神話的暴力の例として挙げたニオベ伝説は、タンタロスの娘ニオベ(下記ではニオベー)が神の怒りにふれて子供を殺される話。オイディプス伝説、アンティゴネーの悲劇と続くテーバイの王族の一連の悲劇の中の一つである。
「ニオベーは子供に恵まれたので、自分はレートーよりも子供に恵まれていると言った。レートーはこれに憤って、アルテミスとアポローンを子供らにむけてけしかけた。そして娘の方は家の内でアルテミスが射倒し、息子のほうはキタイローン山中で猟をしているところを、すべてアポローンが殺した。しかし男の子の中アムピーオーンが、女の子ではネーレウスと結婚した年上のクローリスが助かった。(中略)ニオベー自身はテーバイを棄てて父タンタロスの所へシビュロスへ行き、そこでゼウスに祈って姿を石に変えられ、涙が昼夜その石より流れている。」(アポロドーロス『ギリシア神話』岩波文庫、p129-p128。文中「射倒し」の「倒」の字は旧字。なお訳注一〇九には「クローリスの本名はメリボイアであったが、兄弟姉妹の殺されるのを見て蒼くなり、そのためにクローリス「蒼白の女」の名を得たという」とある。)
ニオベが石になった、という話とよく似た話を柳田國男が書いていた。
柳田は「老女化石譚」(「巫女考」『柳田國男全集11』ちくま文庫版所収)で「諸州霊山の麓などに、これも諸国行脚の比丘尼が、石と化して跡を留めたという話」、いわゆる姥ヶ石伝説が数多くあることを挙げ(柳田、p194)、これは伝えられているように、女性が女人禁制の結界を破ったため神罰を受けて石と化したのではなく「むしろその山を信仰した姥・比丘尼の行法と関係のあったもので、往返の道者たちがこれに基づいて石に名づけたのを、その慣行が断絶して後、悪い方にこれを解説するに至ったのだろう」と推理している(柳田、p203-p204)。
ニオベ伝説は、神々に呪われたテーバイの一族という文脈の中の話であり、それでなくてもギリシア神話と日本の伝説を無媒介に比較することは、トンデモなく危険きわまりないことなのだが、ニオベ伝説のオチは奇岩の起原説話として後世に作られたものであろうこと、ニオベという女性はおそらくは巫女かそれに類する役割を担っていた人だったのではないかという連想が、どうしてもぬぐい去れない。そうすると、ニオベの子どもたちが神々に殺されたというのも、神事としての犠牲と何か関係があるようにも思えてくる。
ニオベ伝説についてのベンヤミンの解釈は次の通り。
「たしかにアポロとアルテミスの行為は、ただの処罰行為と見えるかもしれないが、しかしかれらの暴力は、ある既成の法への違反を罰するというよりは、むしろひとつの法を設定するものなのだ。ニオベの不遜が禍いを招くのは、それが法を侵すからではなくて、運命を挑発するからにほかならない。挑発されたこの闘争において、運命はぜがひでも勝ち、勝って初めてひとつの法を出現させる。」(ベンヤミン、前掲書、p55)
境界の設定
ニオベの伝説から姥ヶ石伝説を連想したところまでは、まんざらトンデモな脱線でもないらしい。というのは、ベンヤミンが次のようにも言っているからである。
「ところで、暴力は不確定で曖昧な運命の領域から、ニオベにふりかかる。この暴力はほんらい破壊的ではない。それはニオベの子らに血みどろの死をもたらすにもかかわらず、母の生命には手を触れないでいる。ただしこの生命を、子らの最期によって以前よりも罪あるものとし、だまって永遠に罪をになう者として、また人間と神々との間の境界標として、あとに残してゆくのだ。」(ベンヤミン、前掲書、p56))
「境界が確定されれば、敵は滅ぼしつくされることはない。ばかりか、勝者の暴力がきわめて優越しているときでも、敵にも権利が認められる。しかも魔神的・二義的なしかたで「平等」の権利が認められる。すなわち、条約を結ぶ両当事者にとって、踏みこえてはならない線は同じ線なのだ。」(同上、p57)
「ところで、法を認識する上で、境界設定の行為は、もうひとつの点でも示唆にとんでいる。法律とか境界変更とかは、少なくとも太古では不文律だった。ひとは知らずにそれを踏みこえて、贖罪を余儀なくされることがある。というのは、書かれも知られもしていない法律が破られると発動する法の干渉は、すべて、刑罰とは呼ばれずに贖罪と呼ばれるのだから。しかし、知らずに贖罪の手におちる者が不運だとしても、贖罪の登場は、法の精神からすれば偶然ではなくて、運命である。」(同上、p58)
これは宗教・民俗的な「境界」、姥ヶ石伝説の場合は霊山の女人禁制の結界と重なる話である。ニオベが石になったという伝説は、やはりギリシア版姥ヶ石なのだ
ベンヤミンはギリシア神話を引き合いに、顕現としての暴力が境界を措定することによって法措定暴力となることを示し、このような神話的暴力こそ法的暴力の根源的な形態であることを示した。
やはり柳田国男の『一目小僧その他』(『妖怪談義』講談社学術文庫)によれば、その橋を渡るときに、ある謡曲を謡ってはならぬ、というタブーのある橋がある。謡いながら渡れば凶事がある、というのである。
かつてこの系統の説話で有名だったのは、山梨県・笛吹川にかかる国玉大橋で、「葵の上」を謡うと祟りがある、と伝えられている(後年「野宮」に変わったらしい)。謡曲を謡うと怪事があると戒められている場所は各地にあり、禁じられている曲も「葵の上」だけでなく、「杜若」(静岡)、「楊貴妃」(熱田)、「道成寺」(磐城)、「山姥」(上路越)などさまざまである。また、起こる怪異も、道に迷う(国玉大橋)、天狗倒し(鹿児島)、幽霊(越後五泉町)などであり、「杜若」は化物屋敷だった(『譚海』)。
こうした伝承は、してはいけないとされる禁忌(法)に触れたから罰が加えられた、つまり法維持的暴力が発動された話のように語られやすいが、考えてみるとおかしなことがある。この種の話はたいてい、最初に祟りにあった人の物語として語られ、その事件以前にすでに謡曲を謡うことが禁じられていたかどうかはわからない。また、なぜそれ(ここでは謡曲)がタブーとされるのかについても、はっきりとはわからない(柳田はいくつかの推測をしているが当たっているとは限らない)。こうした点で禁忌が侵犯に先立つ「視るなのタブー」を語る説話とは異なる(というよりは、「視るな」という声が発せられたその時を描いた説話と考えてもよいかもしれない)。
こうした伝承の原型は、ある人がある場所で何かをしたら凶事が起きた、故に以後そうした行為(ここでは謡曲)を禁ずる、という形だったのではないかと思う。何が神々の意志に背くことなのか、あらかじめわかっているわけではない。たまたま誰かがそれをしたらよくないことが起きたので、それが語り継がれたのだろう。禁忌を犯したから云々という説明は、あとから付け加えられたと考えてよいのではないか。
禁忌を犯したから祟りがあった、のではなく、(人間の側からすれば)それをしたら祟りがあったのでそれが禁忌になった、そういう話だと考えると、タブーの起源説話は、神話的暴力の発現を語るものだと言えるだろう。
霊出現の地
禁忌を犯したから祟りがあったのではなく、それをしたら祟りがあったのでそれが禁忌になったのだとすると、禁忌の土地とは、祟りのあった場所ということになる。それでは、そもそも祟りとはなんであったのか。
柳田国男は「霊出現の地」と題した小文で、「祟り」の語源は神の顕現だろうという仮説を記している(柳田国男「霊出現の地」『定本柳田国男全集第十五巻』筑摩書房)。
まず柳田は信州諏訪で、祭り墓(埋葬地とは異なる拝礼所)を「タッショウ」と呼ぶことを取り上げ、この呼び名は中部地方を中心に広く分布していると指摘する。タッショウ、オタッショ、タッチュウなどと少しの変化はあるが、墓のことをそう呼ぶらしい。「しかしすべての墓地を一様にさう謂ふのではなくて、其中の或特殊のものに限つたのかと思はれるふしがある」として、さらに地域を広げ、タチヲ(淡路)、オタッチョウ(壱岐)、タッチョウモト(対馬)、ヲタッチュウ(豊後日田)、タキショ(大隅)、タッバ(三重県志摩)などの例を挙げている。そうして、このタッショの語源を推測する。以下、あまり言及されない文章なので、少し長くなるが柳田の文を引く(漢字は現行の書体に替えた)。
「無論是ぐらゐの資料だけでは断定は出来ぬが、敢て意見を述べるとタッショのショはやはり処であり、タチは現はれることでは無からうか。今日の「立つ」といふ動詞には、もうさういふ意味までは含んでは居ないが、面影に立つといひ、夢枕に立つといひ、雷をカンダチ、朔日を月立ち、その他龍をタツと訓じ、水中の怪物をタツクチナハ(佐賀地方)といふ類の、例を挙げるならばまだいくらも有る。死者の月忌をタチ日といふなども、今では供養をする日と解せられて居るだらうが、本来は魂髣髴として来り享ることを謂つたのかと思はれる。神霊が立てば必ず祭をする故に、祭りをする処と変化したとても不思議は無い。タタリといふ言葉は我々は罰を与へる場合にしか使つて居らぬけれども、沖縄などのタアリは神が顕はれることであり、諏訪の神社でも巡幸の日に行く先々の大樹の下で、祭をすることを、曾てはタタヘ(湛へ)と謂つて居た。現在は祭り墓の所在地をさう呼ぶやうになつたが、以前は或は山や林の奥に「立ち所」といふ墓地があつて、それへ行つて祖先の霊を迎へ又は祭る風習があつたのではないかどうか。」(柳田、前掲書、571頁)
つまり、柳田によれば、「祟り」という語の原義は、「立つ(顕れる)」である。後年、その結果が望ましいものであれば、霊験あらたか、と呼ばれ、望ましくない場合にのみ「祟り」の語が使われるようになったが、もとは神意、または霊威がその存在を自ら現す、つまり顕現することを指す言葉であった。
柳田の推測は、ベンヤミン『暴力批判論』の岩波文庫版では「宣言の暴力」となっている文章が、ちくま学芸文庫版では「顕現の暴力」と訳されているのにも、ピッタリ当てはまる。神話的暴力は、祟りの暴力である、としてよいと思う。神話的暴力を「祟り」だとすると、祟り(顕現・宣言)によって発生した特定の場所の禁忌、境界・結界は神話的暴力の痕跡であり、現代のわれわれがいう心霊スポットとは、その退化した残滓だとも言える。
なんだか景気の悪い結論になってしまった。結局、心霊スポット探訪には、史跡めぐり程度の意味しかないのだろうか。だが、メニングハウスが、敷居に対するベンヤミンの関心について、次のように指摘しているのは私を勇気づける。
「この挽歌は、単に過去のものを呼び覚ますことに終始しているわけではない。むしろ逆に、そこから、いやむしろそのなかで、現在が認識できるようになる。そして「すたれたもの」のなかにベンヤミンは同時に「革命的なエネルギー」が働いているのを看取する。それは果たされなかった約束であり、未来になってようやくその本来の意味が明らかになるかもしれないものである。ベンヤミンは十九世紀のパサージュ建築とその敷居の魔力を、崩壊しつつある、いやすでに過去のものとなった、だがまさにそれゆえに現働的な「知覚世界」とみなした。」(メニングハウス、前掲書90〜91頁)
心霊スポットもまた「すでに過去のものとなった、だがまさにそれゆえに現働的な「知覚世界」」としてよみがえってほしいものである。
★プロフィール★
広坂朋信(ひろさか・とものぶ)1963年、東京生れ。編集者・ライター。著書に『実録四谷怪談 現代語訳『四ッ谷雑談集』』、『怪談の解釈学』、共著に最新作『猫の怪 (江戸怪談を読む)』など。ブログ「恐妻家の献立表」 Web評論誌「コーラ」36号(2018.12.15)
<心霊現象の解釈学>第14回:心霊スポット――通過儀礼と神話的暴力(広坂朋信)
Copyright(c) SOUGETUSYOBOU 2018 All Rights Reserved.
|
| 表紙(目次)へ |