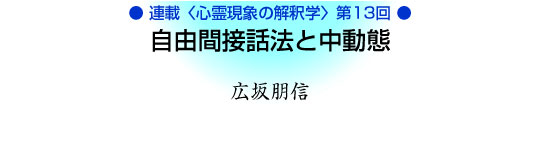|
|
|
Web評論誌「コーラ」 |
|
■創刊の辞 ■本誌の表紙(目次)へ ■本誌のバックナンバー ■読者の頁/ご意見・感想 ■投稿規定 ■関係者のWebサイト ■プライバシーポリシー |
|
<本誌の関連ページ> |
|
■「カルチャー・レヴュー」のバックナンバー ■評論紙「La Vue」の総目次 |
Copyright (c)SOUGETUSYOBOU |
|
|
|
前回まで、中村雄二郎や真木悠介の用語法に引きずれて「アニミズム」という言葉を使ってきたが、中村のあげるバリ島の魔女ランダにしても、真木の描く石牟礼道子氏の姿にしても、アニミズムというよりはシャーマニズムという言葉を使った方が実態に近いかもしれない。もちろん、「アニミズム」にせよ「シャーマニズム」にせよ、その言葉自体は人類学者・民俗学者・宗教学者ら観察者によってつくられた、理解のためのモデルであって、当事者の実態とはズレが生じるだろうことは当然である。そのうえでなお、アニミズムよりはシャーマニズムだろうと私がいうのは、憑依ということを問題にしたいからである。いささか独断的に言ってしまえば、心霊現象と呼ばれるもののうち、憑依こそは最優先で考察されるべきものである。
■三遊亭円朝『怪談牡丹灯籠』栗橋宿の場
今年(2018年)月2日、現代の江戸落語の名人・桂歌丸師匠が亡くなった。歌丸師匠は後半生において、円朝落語、特に『真景累ヶ淵』『怪談牡丹灯籠』のような、演ずる噺家の少なくなった長編怪談物の復興に力を入れた。なかでも十八番となったのは、『怪談牡丹灯籠』の、萩原新三郎がお露にとり殺される「お札はがし」の場ではなく、その後日談、栗橋宿の場であった。
円朝『怪談牡丹灯籠』栗橋宿の場は、この有名な物語のなかでも微妙な要素、少し気取った言い方をすれば両義的な要素を含む。直前までの話の流れは、前回ご紹介したので省略して、その続きを申し上げますならば、家主の萩原のもとに毎夜美女の幽霊が通ってくることを盗み見した伴蔵とおみねの夫婦。そこへ霊の、もとい、例の幽霊がやってきて、悪霊除けのお札をはがしてくださいと頼みこみます。ただ同然で住まわせてくれている家主に死なれては暮らしに困るからと、百両くれればはがして差し上げましょうとふっかけますが、幽霊は承知したうえに、ついでに新三郎の拝んでいる金無垢の仏像もどこかにやってくれと頼み込みます。
そこで、金に目のくらんだ伴蔵とおみねの夫婦は、萩原の仏像をすりかえ、お札をはがして幽霊の願いをかなえてやります。すると、翌朝萩原は骸骨を抱いた変死体となって発見され、後暗いところのある伴蔵は、今でも幽霊が出るという噂を言いふらし、幽霊が怖いというのを言い訳にして、おみねを連れて故郷の中山道栗橋宿に逃げていきます。
これでお札はがしの場は終わるのですが、最後の伴蔵のつくった噂話の内容は、お露・お米の幽霊に加えて萩原まで幽霊となって現れるというもので、これは有名な翻案、『おとぎぼうこ』の「牡丹灯籠」にはなく、その原作である『せんとうしんわ』にあるエピソードですから、円朝は『せんとうしんわ』の原文か、その読み下しを読んでいただろうことの傍証になるというのは、本稿にとってはまったくの蛇足でございます。
さて、百両の大金をもって栗橋宿に身を隠した伴蔵とおみねは同地で荒物屋を始めて成功をおさめ、すっかり旦那様気分になった伴蔵はお国という女にいれこみ、邪魔になった女房おみねを殺してしまう。強盗の仕業に見せかけて、何食わぬ顔でおみねの葬儀を終えた七日目のこと、怪異が起こった。ここからは下手な要約ではなく、円朝の名調子を引用する。
呼ばれてやってきたのは、萩原新三郎にお露を紹介した山本志丈。伴蔵おみねの夫婦とも顔見知りであった。
山本志丈は藪医者だが、憑物の対処には心得があったとみえて、「これは早速宿へ下げたまえ、と云うと、宿で又こんな譫語を云うと思し召そうが、下げれば屹度云わない、此の家に居るから云うのだ」と教える。
このあと、志丈と二人きりになった伴蔵は、萩原の変死は実はすべて自分の仕組んだことだったと打ち明ける。この栗橋宿の場が両義的だというのはこの点である。
この告白は、一見すると怪異はすべて人為(伴蔵の企み)であったというふうに読めてしまう。けれども、萩原は確かに死んだはずのお露とお米の姿を見て、言葉もかわしていた。だからこそ、お札を張って自室に立てこもっていたのである。また、関口屋の奉公人に次々とおみねがとり憑いた口走りをどう考えるか。結局、円朝は、死霊にとり憑かれるという現象を否定せずに物語の設定にとりこんでいる。これも本稿にとっては蛇足なのだが、『真景累ヶ淵』冒頭の「幽霊というものは無い、全く神経病だということになりましたから」という言葉が独り歩きして、円朝落語は合理的と思い込む人もいるようなので、ここに余計な注記を加えておいた。
■誰が語っているのか
もちろん円朝『怪談牡丹灯籠』はフィクションだが、栗橋宿の場で語られたような憑依現象は現実に起こる。おそらく円朝は『真景累ヶ淵』の原話である『死霊解脱物語聞書』も参考にしたのだろう。
憑依現象は、現代では精神疾患の一種として扱われることが多い。例えば、医学生だった頃のC・G・ユングによる憑依現象の観察記録『心霊現象の心理と病理』(みすず書房)では、最初から「夢遊症の発作」として被験者の観察を始めている。そればかりか、「夢遊症の会話においては、亡くなった親族や知人を、その特徴をすっかりそなえた調子できわめて巧みに真似したので、ものに動じない人にまで、強烈な印象を与えたのである。例えば彼女が聞いて知っているだけの人の真似をあまりにも的確にするので、それを聞いた人は皆、彼女にはすくなくともすばらしい俳優の才能のあることを認めないわけにはいかなかった」(ユング、前掲書、24頁)と、憑依は演技であるといわんばかりである。
ユングの観察した霊媒S・W嬢は、実はユングの母方の従妹であり、職業的霊媒ではなく、家族や友人によるプライベートな交霊会(テーブル・ターニング)の最中に憑依された(ユングによれば夢遊症の発作を起こした)のであった。彼女に憑依したのは、彼女の誕生前に物故した彼女とユングの共通の祖父であった。彼女が会ったことのない祖父の「特徴をすっかりそなえた調子できわめて巧みに真似した」ことに「強烈な印象」を受けた「ものに動じない人」とは、ユング自身のことだろう。ユングは、おじいさんとそっくりだ!と驚き、以後、一年以上にわたり、彼女を中心とする交霊会に参加して詳細な記録をとった。彼女の憑依が演技だというのは、医学生として論文にまとめるにあたってのあとづけの表現だろうが、そればかりではないようにも思う。
第四回目の交霊会の記録である。
祖父としての話は、自発的で、暗示は無かったというのは、その場にいた誰も、彼女に祖父として話すように誘導しなかったということである。つまり、彼女は自発的に祖父として話し始めた。そうすると、自発的に話しているのは誰かが問題になる。ユングの目の前で起きている出来事ははっきりしている。十五歳の少女のかたちをした生きた身体が、死んだ祖父の言葉を語っている。この単純な出来事をどう描写したらよいのか。
これは長々と引いた『怪談牡丹灯籠』栗橋宿の場での憑霊騒動でも同じである。関口屋の女中おますは、死んだ関口屋の女房おみねとして語っている。これに対して、ユングのような近代医学の学徒ではない伴蔵は「腹の中では、女房のおみねがおれに取り付く事の出来ないところから、この女に取付いておれの悪事を喋らせて、お上の耳に聞えさせ、おれを召捕り、お仕置きにさせて怨みをはらす了簡に違いなし」と、実に端的に事態を捉えている。
一方、ユングの場合は、霊媒があくまでユングの従妹のS・W嬢である限り、語っているのは死んだ祖父であるはずがない。そこで、これは彼女が無自覚に演技しているのだろうと書くことになる。祖父の霊が孫娘に憑依したのだと言ってしまえば簡単であるが、近代医学を学ぶユングにはそうは書けない。S・W嬢の催眠状態での言動はあくまで「夢遊症の発作」でなければならない。彼女は夢を見ているのである。実際、前回の交霊会では、祖父の夢を見たと彼女は言っている。だから、祖父の霊とは、彼女の夢のなかの祖父であるはずだ。そうであれば、彼女は自分のことを第一人称で語り、私は祖父がかくかくしかじかと語っているのを聞いたというように語らなければならない。しかし、彼女は自分のことを第三人称で「彼女はここにはいない。彼女は去った」と語り、祖父として、亡き祖父の言葉らしいものを語っている。いったい、語っているのは誰なのか?
■自由間接話法
憑依という、現代では特殊とみなされる現象をどう描写するか。そのヒントを思わぬところで見つけた。次に引くのはドゥルーズ+ガタリ『千のプラトー』(河出文庫)の一節である。
直接話法とは、私は煙草が吸いたい、というようなもの。これに対して間接話法とは、第三者が「広坂は煙草が吸いたいと言っていた」というようなもの。自由間接話法とは、それこそ落語でよく聞かれるもので、語り手が登場人物の言動について語りながら自分の意見をさしはさんだり、登場人物の心情を述べるくだりで客観的な情景描写や事情の説明をしたりする、あの話法である。國分功一郎は『ドゥルーズの哲学原理』(岩波書店)で、この自由間接話法をドゥルーズの文章(思考)の特徴として指摘している。
國分はさらに「自由間接話法では、語られる側の判断が語っている者の判断であるかのように現れる。語る側と語られる側が判明に区別されない。語る者が語られている者へと生成変化している、と言ってもよい」としている(國分前掲書、124頁)。
語る側と語られる側、関口屋の女中おますと伴蔵女房おみね、ユングの従妹のS・W嬢とユングの祖父、『死霊解脱物語聞書』のお菊と累、憑依される者が語る者で、憑依する者が語られる者である。だが、憑依という現象のさなかにあっては両者の区別は判明ではない。だから霊媒に対して聞き手はしばしば「今話しているのは誰か?」と尋ねることになる。さらに、語られる者=憑依する者が複数である場合もある。交霊会が繰り返されると、一人の霊媒によって語られる者=憑依する者は増えていくことがあるようだ。ユングの観察したS・W嬢の場合がそうだったし、『死霊解脱物語聞書』のお菊にとり憑いた累が往生すると、かわりに助という児童の霊があらわれた。「私」のなかにはさまざま声があることはドゥルーズとガタリも述べている。
念のため断わっておくが、ドゥルーズとガタリは心霊主義者ではないし、著作のなかで心霊現象を論じているわけでもない。ただ、自由間接話法こそが会話や談話のベースにある話法であって、直接話法や間接話法はそこから抽出されたものだというアイデアが、憑依現象における言葉を考える上で有益なヒントになることを示したかっただけだ。
■國分功一郎『中動態の世界』
前述のように國分功一郎は自由間接話法をドゥルーズの思考の方法として取り出している。國分はドゥルーズのヒューム論を引きながら、ドゥルーズが「論述の対象となっている哲学者によって意図的に概念として使われていたわけではない言葉を概念化して提示している」ことを指摘している(國分、前掲書、26頁)。これはドゥルーズのベルクソン論にも当てはまることなので納得できる(ドゥルーズは『ベルクソンの哲学』の冒頭で、ベルクソンの「直観」はニセの問題を否定する働きだと強調しているが、ベルクソン自身はあまり強調してはおらず『哲学的直観』でちらりと言っているだけだ)。とはいえ、ドゥルーズ自身が「私の方法は自由間接話法です」と直接話法で述べているわけではない。自由間接話法がドゥルーズの方法だというのは、國分がドゥルーズを徹底的に読みぬくことで、それこそ自由間接話法で「意図的に概念として使われていたわけではない言葉を概念化して提示」したのであろう。
そこで私も悪乗りして自由間接話法的に考えるなら、この自由間接話法への関心の延長線上に國分の新著『中動態の世界』(医学書院)があるに違いない。
中動態とは、能動態でも受動態でもない言葉(動詞)のことである。それは能動態と受動態の中間物でもないし、ましてや両者の対立を止揚した高次の言葉とか、そういった特別なものではない。日常生活のなかでごく当たり前に感ずることなのに、それを現わす言葉を、能動態か受動態か、どちらかを選ばなければならないとすると、うまく話せない。そこで、古代の文法書に出てくる「中動態」を復活させて、私たちの経験を語り直してみようという試みである。この発想からして、直接話法でも間接話法でもない自由間接話法を強調してみようというアイデアに通ずるものがある。
國分は中動態の例として古語の「見ゆ」を挙げている(『中動態の世界』183〜184頁)。手元にある旺文社古語辞典第九版には、「自分の見ようとする意志によるのでなく、眼前の情景が視界に入ってくるという意。」と解説されている。たいていの場合、「見える」と訳す。見える、といえば、本稿のあつかうジャンルでよく口にされるのが「視える人」である。もちろんこれは視力のある人という意味ではなく、「(霊が)視える人」のことであって、この「視える人」のなかには視覚障碍者も含まれる。
(霊が)視えるとはどういうことか。職業的霊媒ではない人たちにとっての視霊体験は、見よう、見たいと思って見たのではなく、たいていの場合、ふと気がついたら見えちゃった、というものである。見えちゃってから見え続けるものだから職業的霊媒予備軍になる人も若干はいるが、多くの人はごくまれに見える程度なので、たまにはこういうこともあるものなのだと納得して平穏無事に暮らしている。視ようと思って視る人とは違うのである。こうした体験を理解するうえで、國分の提唱する「中動態」という考え方はたいへん有益である。
中動態が「使える」のは、視霊現象についてだけではない。憑依現象の記述においても使える。円朝『怪談牡丹灯籠』栗橋宿の場での関口屋女中おますの口走りは、もしおますが能動的にしていることなら、実は伴蔵の女房殺しの現場を秘かに見ていて、女将さんの仇討をするつもりで、亡きおみねの口真似をして伴蔵の犯罪を暴いたということになろう。反対に、おますが受動的に誰かの意志で語らされているのであれば、殺されたおみねがおますの口を借りて告発しているのだということになる。
ユングの交霊会観察記の場合も同様に、S・W嬢の催眠中の言動が、彼女の能動的な意志によるのであれば、彼女は会ったことのない祖父の言葉を、たぐいまれな演技力によってそっくりに真似していたことになる(ユングはそう記述した)。しかし、ユングは言外にそれ以外の可能性もにおわせている。彼はこう書いたのだ。
「彼女にはすくなくともすばらしい俳優の才能のあることを認めないわけにはいかなかった」。すなわち、彼女の言動が優れた演技であるというのは、その場にいた全員が最低限の譲歩をした場合の評価であって、それ以外の「強烈な印象」を排除するものではない。端的に、祖父の霊が孫娘に憑依したと受けとった人もいたはずである。
中動態は、こうした憑依現象を記述するにも役に立つはずである。便宜上、能動と受動という言葉を使ったが、通常の能動と受動とはニセの対立であって、実は能動的な意志がどちらにあるのか、強制力を発揮しているのは誰なのかだけが問題となっている。ユングの観察記録のケースで言えば、「発作中の話はまったく自発的におこなわれたもので、これに関する暗示は前もっては一切与えられていなかった」ことにユングが注意を喚起しているのは、憑依現象の主体をS・W嬢に絞り込むためである。これによって、他の参加者は免責され、あとは、S・W嬢の「演技」が意図的であるかないかだけが問題となる。しかし、そもそも憑依とは、誰かの意志によって成立するものなのだろうか。
中動態の考え方によれば、「恋に落ちる」、「疲れる」なども中動態的現象である。恋に落ちるという動詞の主語は確かに「私」だが、恋をしようと意志して恋するのは、それこそ未だ恋を知らない少年少女の「恋に恋する」のたぐいであろう。疲れるの主語も「私」だが、疲れようと意志して疲れる人がいたとしたら、おそらく「疲れる」という語の意味を少し誤解していることになるだろう。恋愛も疲労も、そうあろうとしてなれる状態ではなく、もろもろの事情の結果、そうなってしまうのである。
憑依の動詞形「憑かれる」も、恋愛や疲労と似たところがある。「憑かれる」は形式的には「憑く」の受動態だが、意図的に、能動的に「憑く」人は現実にはいない。例えば、有名な『源氏物語』の六条御息所の生霊は恋敵に憑くが、六条御息所自身は自らの生霊が葵上に憑りついていることを知らない(事後、間接的に察知するだけである)。死霊や狐狸妖怪が人に憑く場合はあるが、それは憑かれている人の口からそう語られるだけで、生きた人間の経験としては、意図して憑くことは成り立たない。霊媒が行なっているのは、意図して憑かれるという能動的に受動的な行為、まったく形容矛盾だが、能動態と受動態だけで語るならそうとしか言いようのない行為である。「憑かれる」が「憑く」の受動態ではなく、もともと中動態だとすれば、このような矛盾した説明をしなくてもすむ。そのとき、私たちは憑依という現象について、別の理解の仕方を試みることが出来るようになるだろう。
★プロフィール★
広坂朋信(ひろさか・とものぶ)1963年、東京生れ。編集者・ライター。著書に『実録四谷怪談 現代語訳『四ッ谷雑談集』』、『怪談の解釈学』、共著に最新作『猫の怪 (江戸怪談を読む)』など。ブログ「恐妻家の献立表」 Web評論誌「コーラ」35号(2018.08.15)
<心霊現象の解釈学>第13回:自由間接話法と中動態(広坂朋信)
Copyright(c) SOUGETUSYOBOU 2018 All Rights Reserved.
|
| 表紙(目次)へ |