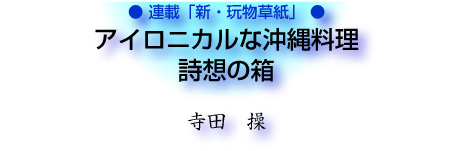|
|
|
Web評論誌「コーラ」 |
|
■創刊の辞 ■本誌の表紙(目次)へ ■本誌のバックナンバー ■読者の頁/ご意見・感想 ■投稿規定 ■関係者のWebサイト ■プライバシーポリシー |
|
<本誌の関連ページ> |
|
■「カルチャー・レヴュー」のバックナンバー ■評論紙「La Vue」の総目次 |
Copyright (c)SOUGETUSYOBOU |
|
|
アイロニカルな沖縄料理 八重洋一郎詩集『沖縄料理考』出版舎Mugen/2012・7・7)を開く。料理考とあるが、詩集はけしてグルメではない、生きのびるための食なのだと優しく笑いかけながら宣戦布告された。
《あのドストエフスキー描く/悪魔さえまっさおな/ニヒリスト/スタヴローギン/豪華なパーティーの席上/だれかにチョット/声をかける/お耳を拝借…… そして何かを/ささやく(ふり)/ガフッ!/耳をちぎれんばかりに//(昔 恋人を争って相手の耳を食べたものもいる)//コリリ コリリ クラゲのような/その噛みごこち》(「耳ガー」)
人を鞭打ち傷口にできたカサブタを食べる王(「カサブタ」)。アワモリ飲んで豚足食べて、痛風になる(「アシティビチ」)。大都会からひからびて帰ってきた者を慰謝する(「ソーキ汁」)などと、食は風土と歴史の連鎖なのだと思い知らされた料理考だが、料理人には、研ぎ澄まされた感性はあるが、声高に政治思想を攻撃する単純な技は使わない。むしろ包みこんで骨まで食べてあげようか、ハブ酒に漬けられても死なないんだよ、といったような内に秘めた戦闘性があり、「生き継いで」「生き継いで」「生き継いで」という科白を呪言とする、逞しい人々のエネルギーを掬いあげる。シャベルという粋な労働をひきうけている政治家の何枚もある舌の味何枚もある味(「舌」)には笑える。《生きものは/みな/骨と皮/これにありつけたら最上のしあわせであった敗戦直後の/あの頃/幼年も少女も少年も/大人さえ/青年たちは一日稼いだわずかな日銭をポケットに探り/たらたらと 額いっぱい/汗たらし/大盛りすばを二杯食べた》(「すば」)の美しさと怖さとアイロニー。詩人の最高の料理とは、《わが生涯 最高のあこがれ/かすみを食って生きること そして/神秘をうたうこと》(「霞」)だと言われた。
詩想の箱『現代詩文庫198倉田比羽子詩集』(思潮社/2012・8・30)を開きながら、詩語を紡ぐ「詩想の箱」は、ひとつとして同じ形状を持つものはないのだと改めて思った。箱のなかで培養された詩のかけらは、同時代を生き、同じ空気を吸っていても、同一ではありえない。世界の見方、組み方は、その人の文体として顕現する。
《目が覚めると、雪が降っていた。窓の外の人々は生きるためにここに集まってきた。窓辺でわたしは名前を呼ばれて、無意識に、はい、と答えて出ていった。わたしの名前が明かされた。高揚の瞬間、自足した。誰かがわたしの中へ溶け込んだ。〔ユニオ・ミスティカ〕。解体‐邂逅。恐怖などなかった。内なる悦びがわいた。わたしはほんとうはずっと〔倉田比羽子〕になりたかったのだ。》
この〔ユニオ・ミスティカ〕を自分のことのように読んだ読者はいなかっただろうか。私は誰か、何者なのか、名前を呼ばれないことは不在と同じ…と分裂するわたしに苦しむ「鏡の園」は、忘れたころに鎌首をもたげて…ゆさぶりをかけてくる…。
「追悼特集 新井豊美」(『現代詩手帖』2012・3月号)では、遺稿となった詩「箱」から、新井豊美さんがたどりついた「詩想の箱」を視た。心身に起きた異変や死の予兆を幻視する自身の鋭いまなざしがそこにあった気がした。
《水源を囲んだ空間 空間をとりまくように配置されている壁 それ/が正しい順序だ その逆ではなく水場 中庭 壁 そこへゆくため/には 全体をもう一度初めから通過してゆかねばならない 由緒あ/る曲がり角 多くの抽斗をそのなかに隠し持つ壁 それ自体があな/た自身のように一つの迷路を構成するその箱の中で暗所は暗所をの/みこんでさらに膨らみ 曲がり角は角ごとにピシピシと悲鳴をあげ/て直角に折られてゆく おもわぬ場所で出会う抽斗 時のひやりと/した澱みをおそるおそる引き出す中で 発見された旧い金銭貸借簿/蛇皮のベルト 体温計 拓の櫛 爪きり鋏 アメジストの標本 か/らくりをさらに覆して発見されたもうひとつの曲がり角 もうひと/つの暗所 さらに多くの抽斗をめぐりめぐって あなたは中庭まで/容易に到達できない 不能という中庭の中心に蹲って》(「箱」前半)
浮海啓詩集『ふあいあ ふらい ああるの独白』(白地社/2012・9・10)の冒頭には、哀悼詩「さようなら 吉本隆明さん」が置かれた。イメージの造型で詩を紡いでこられた浮海氏には珍しく、2012年3月18日、午後3時の出棺の様子がリアルに描写された。
《棺が/霊柩車にかかるころ/冷えた手をかけ/つのる思い/熱いまま 押し込む/さようなら。/ふたたび さようなら。/さらに/―さようなら。》
見送った後、浮海氏に異変が起きた。《その夜から/奥の歯が空洞になる/腫れあがって/鈍痛//おさえて/慰め/いつか忘れて/舌を噛む》(「辛くなる」)と、失ったものの大きさと対峙する。はかりしれない想いと喪失感に襲われる浮海氏の「詩想の箱」には、吉本隆明氏が棲んでいる。10月9日、俳人・吉本和子さんが夫・隆明氏の後をおうようにひっそりと老衰で亡くなられた。
『現代詩文庫195 松尾真由美詩集』(思潮社/2012・8・31)を読みすすめば、言葉の生成の現場へと拉致され同化を迫られるような奇妙な感覚になる。
《水位がどこか ふちをあふれつづけている/頬に鈍いろの筋はえがかれ/みぞおちに白い輪がひろがり/自分が〝よこたわる〟ひとかげになってゆくのがわかる/雨やはげしさにもえのこされるようにして/性別や年齢や感情を消して/燭光を低めてともる/そのような存在の一人/〝よこたわる人〟というしずくのような種族だと気づくと/天井も壁も消える/雨つぶの数だけ/ひとかげはあたりをうまれはじめる》(「秘めやかな共振/もしくは招かれたあとの光度が水底をより深める」)
横たわる不在のひとかげに書き手のひとかげが寄りそい、溶けあい、世界の不在へと言語の海を漂っていく。
(個人誌「Poetry Edging」№23―2013年11月1日発行―より転載)
★プロフィール★
寺田 操(てらだ・そう)詩人。編集として『幻想・怪奇・ミステリーの館』(「エピュイ23」白地社)。詩集として『みずごよみ』(白地社)、『モアイ』 (風琳堂)、評論として『恋愛の解剖学』(風琳堂)、『金子みすゞと尾崎翠──一九二○・三○年代の詩人だち』(白地社)、『都市文学と少女たち―尾崎翠・ 金子みすゞ・林芙美子を歩く』(白地社)、童話として『介助犬シンシアの物語』(大和書房 /ハングル版はソウル・パラダイス福祉財団より )、共著として『酒食つれづれ』(白地社)、『小野十三郎を読む』 (思潮社)。2011年5月に『尾崎翠と野溝七生子』(白地社)を出版。
Web評論誌「コーラ」19号(2013.04.15)
「新・玩物草紙」アイロニカルな沖縄料理/詩想の箱(寺田 操)
Copyright(c) SOUGETUSYOBOU 2013 All Rights Reserved.
|
| 表紙(目次)へ |