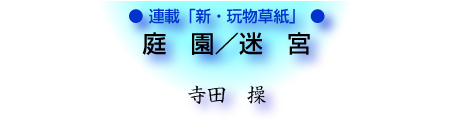|
|
|
Web評論誌「コーラ」 |
|
■創刊の辞 ■本誌の表紙(目次)へ ■本誌のバックナンバー ■読者の頁/ご意見・感想 ■投稿規定 ■関係者のWebサイト ■プライバシーポリシー |
|
<本誌の関連ページ> |
|
■「カルチャー・レヴュー」のバックナンバー ■評論紙「La Vue」の総目次 |
Copyright (c)SOUGETUSYOBOU |
|
|
庭 園 ベランダの鉢植えに蜂がやってくる。土に触るのは苦手、おまけに虫が怖いときている。野道で摘んだヨモギに青い小さな虫がついていたのを見つけて、草餅にする気にならず捨ててしまったとき、「虫がつくのは新鮮な証拠だよ」と笑われたが、虫愛ずる姫になどなれない。けれど、草木のないベランダは殺風景だからと、パセリ、クレソン、ローズマリー、ミント、バジル、ラベンダーなど、食べられる草の鉢植えや季節の花を少しだけベランダで育てている。コンテナで野菜を育てたことがあったが、ミニトマトもキュウリも茄子も苺も唐辛子も木の芽も、どれもこれも小さくしか育たなかった。書斎の窓際には、コーヒー豆などのいくつかの観用植物。小さな我が庭園だ。冬場は豆苗、人参、蕪、大根などの野菜の残りもので水耕栽培。数年前にスーパーの景品でもらった名も知らぬ植物は、妖しく伸び出していまや70センチの丈。次々と大きな葉をつけて緑の涼を運んでくれる。
大正から昭和初期に珠玉のファンタジーが多く生まれた。詩人・吉田一穂『埋もれた花園』は、本草学者と二人の孫娘が暮らす古都の花園。月の光に咲く世にも稀な花を新たに作ろうと変種実験に没頭する学者と、薬草の毒気に身体を蝕まれていく孫娘。ひとりの孫娘はいつしか花園に姿を消してゆくという怖くて美しい物語だった。梨木香歩『裏庭』(新潮文庫/2001)は、かつて英国人バーンズ一家の別荘だった、荒れ放題の洋館の庭が舞台。そこには、普段は絶対に入ることができない秘密の「裏庭」があった。その庭は鏡の表面がゆれて霧が晴れるように不思議な風景が現れる庭。自在に往来できるようになると人の影が希薄になり、死の世界に近づくという不思議な庭。庭をめぐる物語は、妖しくて怖い。
種村季弘『ビンゲンのヒルデガルトの世界』(青土社/1994・8・15)は、ドイツ生まれの聖女で植物学者、医学や作曲までてがけた天才女性ヒルデガルト(1098~1179)の評伝的エッセイ。聖女・エコロジー時代の預言者などと祀り上げられ、二十世紀末のドイツでは、ヒルデガルト・ルネッサンスブーム(緑の思想)が巻き起こった。一方では魔女的なイメージもある彼女に対して種村の関心は自然学・宇宙学にあり、ヒルデガルトという名そのものに、庭園=薬草園の本質的な意味が隠されていると推測している。つまりHildegardのgardは「庭園(Garten)」を意味し、Hildはドイツ語「戦い」の意。そこに君臨するのは、《庭園の女主人もしくは女庭師たる、フリーデガルト(平和の庭)、リープガルト(愛の国)のような名の女性である》と。戦士と庭園の名前を持つ彼女は、薬草園を、あらゆる病と闘う「戦いの庭」として、また病人を保護し安らぎ与えるアジールとして庭園を営んだ。これは、中世の医療機関の中心が修道院にあり、民間医療家や「宝石彫刻師」と呼ばれていた外科医はいたが、社会的に公認された医者という職業がなかったという時代背景がある。庭園で野菜や植物を栽培しながら実用化したヒルデガルトは、植物の形態、性質、薬用処方などを記した「植物の書」『自然学』を著した。修道院と薬草園との縁は中世初期から見られ、食用・薬用の植物カタログ・登録などは、検地台帳的な意図を持って作成されていたようだ。
薬草園の庭師ヒルデガルトの背を追うと江口 節詩集『草蔭』(土曜美術社・2008・10)の一篇と出会う。
《わたしは/野に落とされたスコップだった/掬う、という形のまま/掘る、という目的のまま/ごろん、と転がっている/まだ言葉を持たず//柄を握る持ち主を知らず/世界の始めに ひとりで/いた》(「野」)
淺山泰美・編集発行『庭園 Poetry Garden』終刊号/2012・4・22)の短篇「白亜荘のふたり」は、恋のため家を出た母と、母の住むアパートに会いにいく12歳の娘だったころの切なく甘美な回想譚。この世のどこにもない言語で設計された「庭園」に、母が弾くハープの音色が響きわたる「ストーリー・ガーデン」。
迷 宮 詩人が俳句や短歌を、俳人が詩をと、ジャンルの横断は珍しいことではなくなった。第一句集『群赤の街』(冨岡出版/2000・3・15)から12年の大橋愛由等の第一詩集『明るい迷宮』書肆 風羅堂/2012・1・17)を開く。どのジャンルを表現の根にするかは、《変転してしまった/その後も/うたは生まれ/対生の奏では/あるがままに/先んじた開花は/風のまにまに/吹かれていよう》(「木化」)と、作者自身の胸の内にある。と思いつゝ、句集から詩集への変遷は、阪神淡路大震災から東北大震災への時空移動であり、災厄に遭遇した街と人の暮らしをめぐる迷宮譚だ。
《左手を洗い/背中を見つめ/豆腐を陰干し/月の飲み水を補填する/木曜日がやってくる》 (「その一日」)
一番鶏が鳴く啼く夜明け前から詩人の一日が始まる。若水を汲み手を洗うといった、新年の神聖な儀式を彷彿とさせる飲み水の補填。左手を洗う仕草は、わたしの、そして、無数のあなたの左手であり、背中をみつめる無数の眼であり、迷うことなくポリタンクに飲み水を補填する習慣ができた明るい日常だ。明るいというのは、何事も起こらずに過ごせて、次の木曜日がやってくれればいいのにという、希望につなぎたいからである。
夜明け前、二番鶏が啼くころ亡き母へ手紙を書き、午前十時十五分、《木曜日の/闇を造る漢(おとこ)に/見せるつもりの/天竺牡丹の花弁の数をかぞえ/やがて飽きてしまう午睡前》、昼下がり、夕暮れ、夜の闇……。生者と死者が呼び呼ばれ、一日を紡いでいく光景。これは、近未来ではなく、私たちが日々であう痛みを伴う「その一日」、だから読み手は思わず自分の傍に引き寄せ、迷宮めぐりへと押し出されていくのだ。
瀬尾育生「純粋言語論」(『詩論へ 4』首都大学東京 現代詩センター/2012・2・29)から、磁場を動かす大きな災厄を「存在災害」と呼ぶべきという言葉に目を止めた。そして《存在が語りだしている言葉、事物や植物や動物が語りだしている言葉を「純粋言語」と呼ぶならば、いまわれわれが直面しているのはまさに「純粋言語の語りだし」である。そういう場面にいまわれわれは立ち会っているのだ》からは、この世の「迷宮」をさまう人の口を通じて発せられる、純粋言語を思った。
例えば、『滅ぼされたユダヤの民の歌』の作者・イツハク・カツェネルソンの『ワルシャワ・ゲットー詩集』(細見和之訳・解説/未知谷/2012・4・25)。読み手である当方の感受性不足で、詩人の発語のリズムがうまく受容できなかったのだが、はっとさせられたのは、最後篇に置かれた詩「一九四二年八月十四日 私の大いなる不幸の日」だ。妻ハナと、下のふたりの息子が、ワルシャワ・ゲットーから近郊のトレブリンカ絶滅収容所へと移送されてしまった日のこと。その日、不在であったカツェネルソンと長男は移送をまぬがれたが、後にアウシュビッツで虐殺される運命が待ちうけていた。
《どうして私はたいした理由もなしに家を離れたのだろう?/息子たちの顔も見ずに、妻の顔も見ずに ?//お前の顔を見ていれば、私のハナ、もしお前の顔を見ていれば――/そうすれば、すべては、すべては違っていただろう !》
死者の声が、やがて自らも死へと追い込まれていく生者のことばに宿り、詩を書かせている。カツェネルソンのその詩の現場に降り立った細見和之は、カツェネルソンの語りだしに立ち会い、彼の詩を「翻訳」するように連作「トレブリンカ/日置」を次のように綴る。
《それにしてもあの日どうして私はひとり家を離れたのか?》《災厄についてのひどい噂がガスのように漏れている。》(「災厄の二十キロ圏内」『庭園』2012・4・22)。いとしい家族を死においやったトレブリンカで起きたこと、自身を待ちうけている死。それは、同時に、「フクシマ」で起きたことに通底し、あらゆる災厄とつながって語りだされていく言語の行方なのだ。
(個人誌「Poetry Edging」№22-2012年07月01日発行-より転載)
★プロフィール★
寺田 操(てらだ・そう)詩人。編集として『幻想・怪奇・ミステリーの館』(「エピュイ23」白地社)。詩集として『みずごよみ』(白地社)、『モアイ』 (風琳堂)、評論として『恋愛の解剖学』(風琳堂)、『金子みすゞと尾崎翠──一九二○・三○年代の詩人だち』(白地社)、『都市文学と少女たち―尾崎翠・ 金子みすゞ・林芙美子を歩く』(白地社)、童話として『介助犬シンシアの物語』(大和書房 /ハングル版はソウル・パラダイス福祉財団より )、共著として『酒食つれづれ』(白地社)、『小野十三郎を読む』 (思潮社)。2011年5月に『尾崎翠と野溝七生子』(白地社)を出版。
Web評論誌「コーラ」18号(2012.12.15)
「新・玩物草紙」庭園/迷宮(寺田 操)
Copyright(c) SOUGETUSYOBOU 2012 All Rights Reserved.
|
| 表紙(目次)へ |