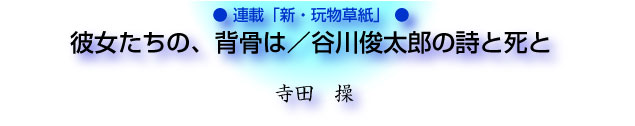|
|
|
Web評論誌「コーラ」 |
|
■創刊の辞 ■本誌の表紙(目次)へ ■本誌のバックナンバー ■読者の頁/ご意見・感想 ■投稿規定 ■関係者のWebサイト ■プライバシーポリシー |
|
<本誌の関連ページ> |
|
■「カルチャー・レヴュー」のバックナンバー ■評論紙「La Vue」の総目次 |
Copyright (c)SOUGETUSYOBOU |
|
|
(キーボード:[Crt +]の操作でページを拡大してお読みいただけます。)
彼女たちの、背骨は 浦歌無子詩集『光る背骨』(七月堂/2021・11)のタイトル詩はメキシコ生まれの画家フリーダ・カーロ(1907年〜1954年)に捧げられていた。
《背骨の透き間から生えてくるものがある/それは緑いろの植物です/わたしの人生は背骨のなかに幾重にも折りたたまれ/閉じ込められてしまったのに/わたしの背骨は/空を持っていた光を持っていた透きとおる水を持っていた》《わたしの背骨はメキシコの大地となった》
彼女の背骨は彼女の生きざまに直結している。肋骨が折れ鎖骨が脊髄が骨盤が折れても、この世の嵐に抗い立ち向かって大地に素足で立つ凛として。次はドイツ生まれの画家で生物学者のマリア・シビラ・メ―リアン。上州生まれで「毒婦」の伝説化された高橋お伝。イギリス生まれの化石発掘者で生物学者のメアリー・アニン。福岡県糸島郡生まれのアナキスト・作家の伊藤野枝(1895年〜1923年)。五人の彼女たちへのオマージュで構成された詩集からは激しい風が吹いてきた。
時計を巻き戻せば、発端はルイス・キャロルの『不思議の国のアリス』を想起させた第一詩集『耳のなかの湖』(ふらんす堂/2009)だ。少女アリス(であろう)が十匹のネズミの長い尻尾を両手でつかんでいる表紙画には仰天した。《あなたがわたしの名前を一度も呼ばないことでわたしの背骨は三日月のように曲がり光るつるぎを手に入れた》(「月の光」)と、その後のアリスの変身世界を追跡した。ホップ・ステップ・ジャンプしたのか、内なる炎が燃え上がる契機を待っていたのか。
伊藤野枝は《わたしは女のかたちをした真っ赤な戦車》(「雨よ貫けわたしの骨を」)。血色の化粧函入りの『伊藤野枝全集』上下/学藝書林/1970)が、老女アリスに再読することを促した。瀬戸内晴美(寂聴)の『美は乱調にあり』『余白の春』など貪ったあの時代へと。

誰だろう?
撮影:寺田 操(C) 谷川俊太郎の詩と死と 毎月一回、朝日新聞文化欄に連載の谷川俊太郎の詩「どこからか言葉が」は読んでいた。一語一語は平易なのに凝縮された深さをもっていたが、どうしてだろう、実感として胸に響いてこなかったのは…。
2024年11月13日掲載の詩より。
《目が覚める/庭の紅葉が見える/昨日を思い出す/まだ生きてるんだ//今日は昨日のつづき/だけでいいと思う/何かをする気はない//どこも痛くない/痒くもないのに感謝/いったい誰に?//神に?/世界に? 宇宙に?/分からないが/感謝の念だけは残る》(「感謝」)。
掲載の翌日、TVニュースで谷川俊太郎の訃報が流れた。1931年東京生まれ、2024年11月13日、老衰のため92歳で死去。人気のある詩人だったから、アフォリズムな詩「感謝」が生前最後の詩とはかぎらないだろうが、生きて書いてきたことのすべてに「感謝」という二文字を残して「雲隠れ」したように思えた。死後に別の世で自分の詩をどのように眺めているのだろう。
詩、ラジオドラマ、絵本、テレビアニメの主題歌(鉄腕アトム)、翻訳、校歌、他ジャンルとの共演。詩歌を中心にして放射線状に延びる谷川俊太郎の活動は数えきれないほど多彩だ。愛読者ではなかったが、何冊かの気になる詩集は手元にあり、論じた詩集もある。取り出してページを開いてみるのはしかし数冊だ。最初に入手したのは『世間知ラズ』(思潮社/1993)。詩集を買ったのははじめてだった。付箋が貼ってあるページの詩から読んでみたい。
《言葉はエキゾチックなものだ/自分が一日に食ったものを書き出してみたことがある/まるでどこかのレストランのメニュのように見えた/それを食った自分が誰かのお客さんみたいだった》《言葉の鍵では開けることの出来ない扉がある/母語ですらエキゾチックに思える国にぼくらは住んでいる/そこが本当の故郷だ》(「言葉の鍵」)。
そのころの私は? 何をしていたのか。言葉と事物との繋がりにくい関係に悩んでいたのだろうか? 再読していて目に留まったのは、《私の父は九十四歳四ヶ月で死んだ。/死ぬ前日に床屋へ行った》から書き出された「父の死」だった。父の死をめぐる状態から救急車を呼び病院へ遺体を自宅に連れ帰り、死体検案書から葬儀。そして喪主挨拶、一九八九年十月十六日北鎌倉東慶寺、夢に現れた着物に羽織を来た六十代ころの父……ドキュメンタリータッチな描写の詩が巻頭を飾る。父の死の年齢にわずか二年早く旅立った息子である谷川俊太郎の心境を推し量る。実にリアルなこの詩を思い出させたのは、長い夏日の続いた初秋に旅立たれた友人のお別れの会に参列したときのこと。ご子息の喪主挨拶が、生前の父の姿を彷彿とさせる小説のワンシーンのようであり、散文詩のような柔らかい語り口で参列者の胸に深く届いたことにあった。
一篇の詩は、読者のそのときどきの心模様をキャッチして、読者の側に返してくれる。はじめて読んだときに心に響いた「言葉の鍵」が、いまもその当時の気持ちのまま現在の私に届いてくるわけではない。若い日に目を止めなかった《ベッドの横には電話があってそれは世間とつながっているが/話したい相手はいない》(「世間知ラズ」)が「老い」の現実を体験中のいまでは実にリアルに思えてくる。タイトルに惹かれたのは『夜中に台所でぼくはきみに話しかけたかった』(青土社/初版1975/26版 1995)だ。
《そして私はいつか/どこかから来て/不意にこの芝生の上に立っていた/なすべきことはすべて/私の細胞が記憶していた/だから私は人間の形をし/幸せについて語りさえしたのだ》(「芝生」)
扉詩の静謐さに惹かれた。
金泥のデカダンス
撮影:寺田 操(C) (個人誌「Poetry Edging」No.60ー2025年03月01日発行―より転載)
★プロフィール★
寺田 操(てらだ・そう)詩人。編集として『幻想・怪奇・ミステリーの館』(「エピュイ23」白地社)。詩集として『みずごよみ』(白地社)、『モアイ』(風琳堂)、評論として『恋愛の解剖学』(風琳堂)、『金子みすゞと尾崎翠──一九二○・三○年代の詩人だち』(白地社)、『都市文学と少女たち―尾崎翠・金子みすゞ・林芙美子を歩く』(白地社)、童話として『介助犬シンシアの物語』(大和書房/ハングル版はソウル・パラダイス福祉財団より)、『尾崎翠と野溝七生子』(白地社)、共著として『酒食つれづれ』(白地社)、『小野十三郎を読む』(思潮社)、『尾崎翠を読む 講演編 2』(今井出版)、2018年8月に共著『宮崎駿が描いた少女たち』(新典社)を刊行。
Web評論誌「コーラ」56号(2025.08.15)
「新・玩物草紙」彼女たちの、背骨は/谷川俊太郎の詩と死と(寺田 操)
Copyright(c) SOUGETUSYOBOU 2025 All Rights Reserved.
|
| 表紙(目次)へ |