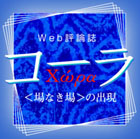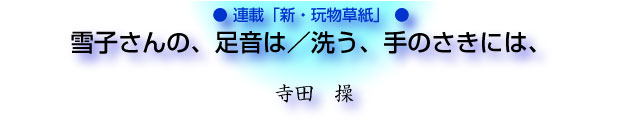|
|
|
Web評論誌「コーラ」 |
|
■創刊の辞 ■本誌の表紙(目次)へ ■本誌のバックナンバー ■読者の頁/ご意見・感想 ■投稿規定 ■関係者のWebサイト ■プライバシーポリシー |
|
<本誌の関連ページ> |
|
■「カルチャー・レヴュー」のバックナンバー ■評論紙「La Vue」の総目次 |
Copyright (c)SOUGETUSYOBOU |
|
|
(キーボード:[Crt +]の操作でページを拡大してお読みいただけます。)
雪子さんの、足音は 木村紅美『雪子さんの足音』(講談社/2018)、書き出しの「眠るように死んでまだきれいなうちに下宿人に見つかるというのが、雪子さんの理想の最期だった」にハッとさせられた。「君たちは」「どのように生きるか」と言った問いかけより、「どのような死に方」をしたいのか、するのかという問いのほうが若いころから切実だったからだ。女友達三人で「最後は死だね」と語りあかした若い日の一夜のことが思いだされた。その後の彼女たちの消息は……ミステリーゾーンとしておきたい。野垂れ死(家族に看取られて死ぬなどいやだ)を願っていた一番若かった私は、子どものころから病問屋なのに一番長生きしそうだ。
老い方にモデルなどなく、百人の老女がいれば百通りの老女像がある。映画『雪子さんの足音』(監督・浜野佐知、脚本・山崎邦紀/2019)を見た一度目は神戸元町映画館。語り手・湯佐薫が部屋に飾った絵は好きな画家・松本竣介だったので自然と薫の世界目線となり、後日原作本を購入した。二度目の豊中すてっぷホールでは、老女を演じる吉行和子さんいわく「とんでもないバーサン」ぶりが痛かった。身近にいる友人たちの顔と重なりすり替わり、老女の集合無意識のように思えたのだ。若い芸術家志望者への雪子さんの過剰なお節介行為とギフト精神。言い換えれば欲望とエネルギーのかたちや死への企みは、私(わたしたち)が密かに宿している炎のかたちだ。出前と称して料理を持って階段を上がる雪子さんの後ろ姿、エロティックな脚の美しい怪しさ。ドアをノックする手の不気味さにゾクリとした。だからこそよけいに惹きつけられるのだと思えた。大なり小なり雪子さん的な言動を日々の暮らしのなかで無意識に行っていることが鏡像のように映しだされ、不意を突かれた観客もあっただろう。そうです、これは「雪子さん」のそして、私(わたしたち)のモノガタリなのだと思えた。雪子さんの足音が今日もかすかに耳朶がとらえて…。

街道の石像
撮影:寺田 操(C) 洗う、手のさきには、 土石流と冠水が町を襲う。水がひいても泥は乾くと砂塵になって巻きあがる。家族写真の泥を丁寧に拭っている手の動きに目が釘づけにされる。長すぎる残暑のある日、一篇の詩がせりあがってきた。
「砂がたまっているんです/たらいの底にたまっているんですよ/洗いながら年寄りだなとか若いんだなとか/娘や息子とおなじくらいかなとか/なんども洗うんですよ遺体の服を洗うんです/なるべくきれいにしてあげたいから/いちまいいちまい洗うんですふり洗いするんです」
(「洗う」)
橋場仁奈詩集『半球形』(荊冠舎/2019・4)から。開く前からドキン、ドッキンと心臓の音が高くなる。怖いけれど開きたい、開くともっと怖くなる。雨の日に水溜りから手が伸びて、その手に足を掴まれるような怖さといってよいだろうか。『あーる/、は駆ける』(荊冠舎/2022・8)では、「tatatatata…」「hahahahaha…」などいくつものオノマトペが連打され、その圧倒的な音(怨でもあろうか)、凄まじいリズムに肝を冷やした覚えがある。
「洗う」からは、身体が脱け出て衣服が残されるが、服にまとわりつく人の体臭や記憶は容易に洗い流せるものではない。ちいさな手足、爪、お腹、髪の毛、ここにいてここにいない人が残したくぐもった声は衣服にまとわりついている。タマシイは衣服の周辺にいつまでも漂っている。「いちまいいちまい洗うんですふり洗いするんです」と呪文をとなえながらひたすら洗う、あらう、洗う。成仏してねと念じながら洗う生者の手がズームアップする。洗えばあらうほど洗う人の胸のうちに砂が沈殿していく。「あたしはあたしを傾ける傾けても傾けても砂がたまってき/てあたしはあたしを傾けひっくりかえし木の木っ端でがんが/んたたく火事だ火事だ」…死者は生者に憑依し、チェンジする。気がつけば砂だらけのあたしは砂だらけの衣服をはぎとられ柩のなかにいる。詩の情景のなかにひきずりこまれた。
関根由美子詩集『川を洗う日』(詩的現代叢書47/2021・8・12)、表紙画の清涼感あふれる水泡、裏返せば手のひらにのせたくなるようなカラフルな水球。冒頭の「かわ」は、《今日は 川を洗う日です。/川の家から回覧板がまわってきた》からはじまり、《今日は川を洗う日です。》で終わる。川を洗う手の作業がズームで映像化され、絵のない絵本のように感じた。洗いすぎないようにね、洗いすぎて浄化されると、水はきれいに澄んでも小魚たちが (餌がなくなる!)住めなくなると、読み手に声が届く。声の主は「波」だろうか? 人の吐く息、亀の子タワシの川を浚う音が静かに水の中へ落ちる。詩集では、いくつもの「水の記憶」が語られた。山津波が起こり、河川が氾濫し、家が流され、土石流が川底に沈殿し、人の命を浚っていく。川底から《ぷわり ぷわり/不気味な 泡》が浮上し、水底を人の眼から隠す。生きるということは、厄災と道連れなのだと思い知らされた。紡がれた体験は、なかなか思うように言語化できないものだ。身の内から立ち上がり外化するまでにはいくつものハードルが言語の作用としてあり、一生、言語化できない記憶のほうが多い。
『川を洗う日』は、ドキュメンタリータッチの方法と、メタファーとしての「水」「記憶」「厄災」が、確かな時間として召喚される。旅先でバッグを開けると、溢れんばかりの鳥の糞や薄鼠色の豆のような粒々がびっしりと詰まっていた。バッグを逆さにして叩いて掻きだし「洗った」はずなのに、濡れていない。しかも、わたしを証明する物が無くなっていた。名前を告げても友人たちは怪訝な顔をする詩「バッグの中身は」に身震いした。私たちに自身を証明する確かなものが果たしてあるのだろうか
 木の遊具
撮影:寺田 操(C) (個人誌「Poetry Edging」No.59ー2024年11月01日発行―より転載)
★プロフィール★
寺田 操(てらだ・そう)詩人。編集として『幻想・怪奇・ミステリーの館』(「エピュイ23」白地社)。詩集として『みずごよみ』(白地社)、『モアイ』(風琳堂)、評論として『恋愛の解剖学』(風琳堂)、『金子みすゞと尾崎翠──一九二○・三○年代の詩人だち』(白地社)、『都市文学と少女たち―尾崎翠・金子みすゞ・林芙美子を歩く』(白地社)、童話として『介助犬シンシアの物語』(大和書房/ハングル版はソウル・パラダイス福祉財団より)、『尾崎翠と野溝七生子』(白地社)、共著として『酒食つれづれ』(白地社)、『小野十三郎を読む』(思潮社)、『尾崎翠を読む 講演編 2』(今井出版)、2018年8月に共著『宮崎駿が描いた少女たち』(新典社)を刊行。
Web評論誌「コーラ」55号(2025.04.15)
「新・玩物草紙」雪子さんの、足音は/洗う、手のさきには、(寺田 操)
Copyright(c) SOUGETUSYOBOU 2025 All Rights Reserved.
|
| 表紙(目次)へ |