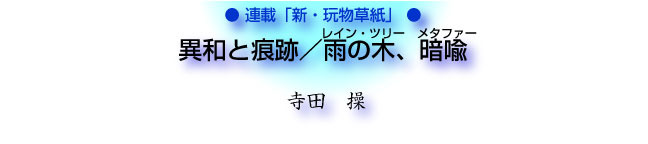|
|
|
Web評論誌「コーラ」 |
|
■創刊の辞 ■本誌の表紙(目次)へ ■本誌のバックナンバー ■読者の頁/ご意見・感想 ■投稿規定 ■関係者のWebサイト ■プライバシーポリシー |
|
<本誌の関連ページ> |
|
■「カルチャー・レヴュー」のバックナンバー ■評論紙「La Vue」の総目次 |
Copyright (c)SOUGETUSYOBOU |
|
|
(キーボード:[Crt +]の操作でページを拡大してお読みいただけます。)
異和と痕跡 笠井嗣夫『異和と痕跡 2004―2022』(七月堂2022・12・1)から、書くことにおける異和と、行為としての痕跡について考えさせられた。なかなか文の枠から逸脱できないでいる私個人の悩みがあるためだ。書かれた文には18年もの長い時間と体験や思考の堆積とふり幅があり、全面的に加筆訂正されたようだ。いくつもの時間のずれや文体の違いなど、錯綜とする思考は、重なりあい反響しあっていただろう。少し前に海東セラ個人誌「ピエ」24/2022・7・30)に4回にわたり連載されていたディラン・トマス「磔刑」の最終回の訳を拝読していた。ケルト文学は、尾崎翠やフィオナ・マクラウドなどの世界を解読するための当方の扉であったので、幻想文学のいくつかが本書に入っているかと勝手に期待をしてしまったのだが……。
読み進めて驚かされたのは、映画、小説、戯曲、音楽、現代詩、時事など射程距離が広くて、知っているのは、聴いたのは、見たのは、ほんのわずかだった。読んだ本や見た映画とて、見る角度、読む切り口、書く語り口が〈未知〉で辛辣だ。とりわけ詩や詩批評に関するものには、強烈なパンチと同時に深い愛を感じた。冒頭「アレクサンドリアの断崖」には、体感した時代の「結節点」が、「62年」と記されていたから、笠井氏は少し上の世代になる。62年当時の思想評論、詩集や詩誌はリアルタイムでは知らない。「断崖」とは「非連続の別名」、あるときは「こちらから世界に切れ目を入れる」のだと、その文の流れに引き込まれ溜息ついた。
表紙の笠井美希さんの写真もまた「世界に切れ目を入れる」行為だろうか。草の上?に寝転び、丸首セーターにジャケット姿の女性がカメラを構えている。ファインダーの先には何が写っているのか。表紙に見入る読者を写真の側からみている「まなざし」を意識した。
 紫陽花寺の半夏生
撮影:寺田 操(C) 雨の木(レイン・ツリー)、暗喩(メタファー) 小雨の降る夜、バルコニーに出て深夜バスを見送った。急こう配の坂道をあがっていく車窓の光と街灯が信号のない横断歩道を照らすとき、歩道に立つ大きな楠は雨を幹にためて屈伸している。わたしの影はきっとあのバスに乗車したに違いない。
大江健三郎『「雨の木(レイン・ツリー)」を聴く女たち』(新潮文庫1986・2・25)を読みながら駆け足で逝く春を見送った。「人が死に向けて年をとる」というフレーズに胸を突かれた。生きものとしての人の宿命だが、ざわざわしてしまった。「詩」に向けて「年をとる」と誤変換?すると、生と死と詩の関係が雨の木として浮かびあがってきた。登場人物たちの死へと向かっていく情動、心の裡の火種を垣間見たからだ。発語へとおもうように向かっていけない「生」と「性」と「死」の複雑な絡まりが描かれた5つの短篇連作。「頭のいい」「を聴く女たち」「首吊り男の」「逆さまに立つ」「泳ぐ男――水のなかの」のタイトルの前後に「雨の木」という暗喩がつき、読み手を見知らぬ土地へと連れ出そうとしていた。最初の――頭のいい「雨の木」――の冒頭では、いきなり「――あなたは人間より樹木が見たいのでしょう?」と、ドイツ系のアメリカ人女性にいわれた。パーティー会場の客間から連れ出されポーチから暗い闇の大半を埋める巨大な樹齢百年もの前に立った主人公。彼女は「――あなたが知りたいといった、この土地なりの呼び方で、この樹木の名は「雨の木(レイン・ツリー)、それも私たちのこの木は、とくにあたまのいい「雨の木」。」主人公の僕はハワイ大学の「東西文化センター」が主宰した《文化接触と伝統の再認識》なるセミナーにでている。会議の後の交流パーティーでの唐突な樹木との出会いが短篇連作の冒頭の作品の主題とされた。彼女(アガーテ)は、さらに「――「雨の木」というのは、夜中に驟雨があると、翌日は昼すぎまでその茂りの全体から滴をしたたらせて、雨を降らせるようだから。他の木はすぐに乾いてしまうのに、指の腹くらいの小さな葉をびっしりとつけているので、その葉に水滴をためこんでいられるのよ。頭がいい木でしょう。」と説明してくれた。作家自身がモデルとおぼしき作品だが、むろん私小説ではなく精巧に構成されたフィクションだ。僕は外国に出るたびに、「その風土での、いかにもその土地らしい樹木を見る」ことを楽しみとしていて、樹木の「土地での独自の呼び名を知ることで、はじめてその樹木をよく知ったと、その樹木に真にめぐりあったと感じるのだ」と言う。雨の木はインドボダイジュと我が国で呼ばれている木だと推察される。土地とそこで生き死にする人間と、樹木とは「似かよっている」ところがあるように思えるというのはうなずける。「雨の木」を主題とした連作の意図が2作目の―─「雨の木」を聴く女たち─ーの冒頭に明かされる。巧みな繋ぎかただと感心させられた。「雨の木」を主題にした作曲家の演奏会では、「人間と人間の位置、人間と世界の位置関係」を、「宇宙論的な視座で並びかえる」と演奏家の位置を探り当てる。これが世界文学というものなのだろうか。しかし、読み進めていくうちに、読者を物語のなかに踏み込ませない、といったような見えない壁にぶつかる。「雨の木」のメタファー(暗喩)の喚起力と、彼・彼女たちの躰にしみこんでいく「悲嘆(グリーフ)の気分」についてだ。また、短篇連作全体を包み込み、しかも通奏低音でもあるメタファーを明かしてしまうと、読み手にも「読むこと」のエネルギーと人間と世界の位置や関係について、アレゴリー的な解読を要求してくるようにも思えた。
若い日に読んで途中放棄した本でも、中高年になって読むと、読める、味わえるという本も少なくはないのだが。読み進めるほどに複雑に枝が絡まり、巨大な樹木にこの身が喰われてしまうような怖さを感じた。
 阪急宝塚駅構内の帽子
撮影:寺田 操(C) (個人誌「Poetry Edging」№55―2023年07月01日発行―より転載)
★プロフィール★
寺田 操(てらだ・そう)詩人。編集として『幻想・怪奇・ミステリーの館』(「エピュイ23」白地社)。詩集として『みずごよみ』(白地社)、『モアイ』(風琳堂)、評論として『恋愛の解剖学』(風琳堂)、『金子みすゞと尾崎翠──一九二○・三○年代の詩人だち』(白地社)、『都市文学と少女たち―尾崎翠・金子みすゞ・林芙美子を歩く』(白地社)、童話として『介助犬シンシアの物語』(大和書房/ハングル版はソウル・パラダイス福祉財団より)、『尾崎翠と野溝七生子』(白地社)、共著として『酒食つれづれ』(白地社)、『小野十三郎を読む』(思潮社)、『尾崎翠を読む 講演編 2』(今井出版)、2018年8月に共著『宮崎駿が描いた少女たち』(新典社)を刊行。
Web評論誌「コーラ」51号(2023.12.15)
「新・玩物草紙」異和と痕跡/雨の木(レイン・ツリー)、暗喩(メタファー)(寺田 操)
Copyright(c) SOUGETUSYOBOU 2023 All Rights Reserved.
|
| 表紙(目次)へ |