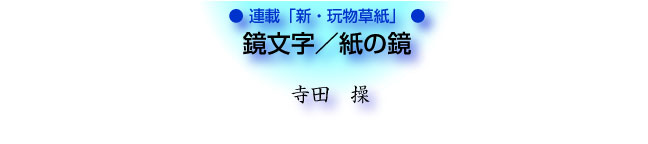|
|
|
Web評論誌「コーラ」 |
|
■創刊の辞 ■本誌の表紙(目次)へ ■本誌のバックナンバー ■読者の頁/ご意見・感想 ■投稿規定 ■関係者のWebサイト ■プライバシーポリシー |
|
<本誌の関連ページ> |
|
■「カルチャー・レヴュー」のバックナンバー ■評論紙「La Vue」の総目次 |
Copyright (c)SOUGETUSYOBOU |
|
|
(キーボード:[Crt +]の操作でページを拡大してお読みいただけます。)
鏡文字 レオナルド・ダ・ビンチが折に触れて紙片につづった「手記」を思い出した。左ききの彼は、裏返しの「鏡文字」と言われる字で、右から左へと書いていたそうだ。古い図録をさがしてみると、『天才 レオナルド・ダ・ビンチ展』(1974・9・1~12・1/宝塚ファミリーランド)のチケットも挟み込んであった。
ルーイス・キャロル『鏡の国』(岡田忠軒訳/角川文庫/昭和34・10・10 初版/昭和62・12・30 52刷)では、マントルピース(炉だな)の上にあがって鏡を通して見える部屋をみたアリス。鏡を通してみる部屋は、アリスがいる客間と同じだが、あべこべになっている。こっちの火が煙を出せば、向うの部屋も煙があるはず。テーブルの上にのった一冊の本を鏡にかざすと、向うの部屋でも一冊かざす。「ただし字があべこべになっている」のだった。「鏡の国」の御本(詩)だからだ。原題は「鏡を通り抜けて」(1871)だが、評判をとった第一作『不思議の国のアリス』(1865)に合わせたようだ。
鏡の向うに何がある。そこは凍りついている? 死者の国? うっかり裏側に入りこめば、戻ってはこられないという噂がありますよ。けれど、アリスは往還通路としての「鏡」の向うに「ひらりと飛び降り」たのだ。そして全身を感応体として、あらゆる不思議な現象と自由に対峙していく。ノンセンスの世界として。そのするっとした通過の仕方が、なんともいえない魅力なのだ。
さて、鏡がどのような状態になったとき、通りぬけることが可能なのかといえば、鏡が「キラキラ輝く銀色のもやのように溶けだして」きたときだった。梨木香歩『裏庭』(新潮文庫/2001・1)では、玄関廊下の突き当りの大鏡の表面に陽が射して鏡に反射すると、「ゆらゆらと湯気が立っているように揺れ」、この世にはない秘密の裏庭が出現した。
 空の果てには
撮影:寺田 操(C) 紙の鏡 降る雪の向うに深夜バスを見送った翌朝、天沢退二郎の訃報(1月25日/86歳)に接した。本棚から天沢退二郎 批評論集『紙の鏡』(洛神書房/1968・11)を取り出し、箱の表紙のタイトルが「鏡文字」になっていることを確かめる。表・裏の表紙を開けば、見返し部分は朱色の上が丸い凸の変形模様が中心から外側へと広がっていた。一歩また一歩と中心へ向かって歩いて行きたくなるような妖しい求心力があり、胸がドキドキしたことが思いだされた。1968年12月12日に購入している、20歳だ。若いころに入手した書物には購入日と名前を記入している。1960年代終わりから70年代にかけて、詩と批評の書物を多く入手している。いっときにこれほど多くの詩と批評を読んでいたのか? 活字を追いかけただけ? 記憶が脱落しているが、本棚の一角を占める書物たちはいまも不思議なオーラを発している。
エピグラムには《自分を映してみつめなければならないのは、鏡の中ではない。人々よ、紙の中におのれを見よ。》と、アンリ・ショーのアフォリズムが置かれていた。背後から声をかけられた。アンリ・ミショー『みじめな奇蹟』(小海永二訳/国文社/1969・5)だ。黒生地に白文字で著者・訳者名が、朱色でタイトルが刻印された箱入りだ。購入日は1969年6月25日だから天沢本からのキャッチだろう。小海訳の序文には〈この書物は一つの探検だ。ことばによる、記号による、デッサンによる。メスカリンが探検の対象だ〉とミショーの言葉。天沢の「紙の鏡」には、パリ国立近代美術館のミショー回顧展へでかけたときの印象記がある。「静かな展覧会だったと思う。なぜだろうか」との呟きが気になった。250点もの作品がかもしだしている「沈黙それ自体のまぎれない実在」を前にした天沢の背中を、視線を、その先のイメージをみようとしていたのは、まぎれもない一人の読者=わたしだ。そして天沢はこうも言う。「未知を志向し未知の世界への旅立ちを続けて、しかも実際につねに新しい体験を記録しながら、やはりぼくらからさほど隔たらぬところに位置しつづけているという事実に、ある種のさびしさを感じたのである」と。さびしさとは弱々しさと同義なのであろうか。静けさとは、さびしさの本質なのだろうか。新しい体験(メスカリン作用)によっても、さらなる彼方へ、遠くへとは行けなかったことを意味しているのだろうか。若い日に感じた謎は、いまもなお、謎のままである。
『紙の鏡』には、ゴダール映画「レ・カラビニエ」よりの画像5枚、アンリ・ミショー「デッサン・メスカリニアン」と水彩が挿入されている。本文構成は、1、詩と言葉をめぐる時評など――2、宮沢賢治、村野四郎、吉岡実から加納光於、アンリ・ミショーの絵画、ゴダールやブニュエル、ヒッチコックなどの映画論――3、海外滞在中に得た詩語をめぐるポリフォニックな体験。若い日に鉛筆でラインを引いた個所や書き込みは3分の1にも満たない。
「深い稠密な泥のなかで目をひらく者がいるとしよう。ひらかれた水晶体の表面はたちまち細かな泥粒でびっしりと覆われ、やわらかな圧力がそこへ集中してくるだろう。そのとき目は何を見るかといえば全てを見るのである」(「状況への序言」)と、はじめられた批評の言葉そのものが散文詩のようであった。
書くことをめぐる、読むことをめぐる不思議が「紙の鏡」を通して展開されていく。文字は単なる記号ではないから、生きもののごとく蠢動し、溶け、侵犯し、詩語の深い淵に書き手と読み手を誘い込む。実に不定形な世界だ。写りこんだ世界と書き手をモンタージュのように配置して、批評は評者自身に匕首をつきつける。「紙の鏡」は書くこと読むことの比喩と思えば怖くなる。イメージ通りの貌が鏡に写っているだろうか。
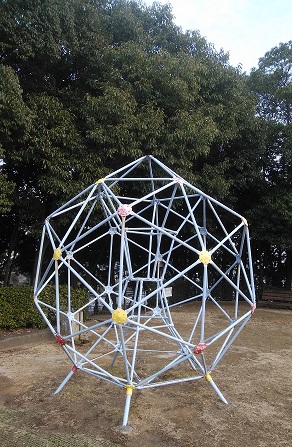 公園の遊具
撮影:寺田 操(C) (個人誌「Poetry Edging」№54―2023年03月01日発行―より転載)
★プロフィール★
寺田 操(てらだ・そう)詩人。編集として『幻想・怪奇・ミステリーの館』(「エピュイ23」白地社)。詩集として『みずごよみ』(白地社)、『モアイ』(風琳堂)、評論として『恋愛の解剖学』(風琳堂)、『金子みすゞと尾崎翠──一九二○・三○年代の詩人だち』(白地社)、『都市文学と少女たち―尾崎翠・金子みすゞ・林芙美子を歩く』(白地社)、童話として『介助犬シンシアの物語』(大和書房/ハングル版はソウル・パラダイス福祉財団より)、『尾崎翠と野溝七生子』(白地社)、共著として『酒食つれづれ』(白地社)、『小野十三郎を読む』(思潮社)、『尾崎翠を読む 講演編 2』(今井出版)、2018年8月に共著『宮崎駿が描いた少女たち』(新典社)を刊行。
Web評論誌「コーラ」50号(2023.08.15)
「新・玩物草紙」絵文字/紙の鏡(寺田 操)
Copyright(c) SOUGETUSYOBOU 2023 All Rights Reserved.
|
| 表紙(目次)へ |