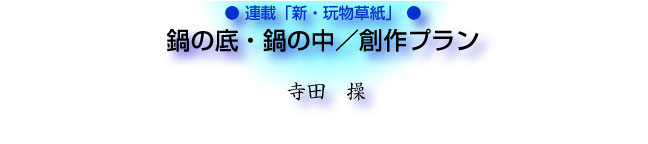|
|
|
Web評論誌「コーラ」 |
|
■創刊の辞 ■本誌の表紙(目次)へ ■本誌のバックナンバー ■読者の頁/ご意見・感想 ■投稿規定 ■関係者のWebサイト ■プライバシーポリシー |
|
<本誌の関連ページ> |
|
■「カルチャー・レヴュー」のバックナンバー ■評論紙「La Vue」の総目次 |
Copyright (c)SOUGETUSYOBOU |
|
|
(キーボード:[Crt +]の操作でページを拡大してお読みいただけます。)
鍋の底・鍋の中 吉井 淑詩集『鍋の底の青い空』 (澪 標/2022・4・30)には、いきものたちが集まる「森の寝所」があり、時を超えて生と死が煮つめられ交歓される。
《台所にいると/ふと/遠い人がすぐそばにいたり/近い人がずっと遠くにいたりする//鍋の底が抜けた/みると/空がひろがっていた//空の底に/揺れる桐の葉影/曲がった腰骨のぐりぐり/うつむいて寂しい笑顔//あんまりのぞき込むと/底の底まで抜けてしまうと/修繕屋は言う/放っておけ 放っておけ//わたしの骨のぐりぐりも/やがて尖るだろう/老いた母たちがしたように/毎日肉じゃがをつくって///果てのない鍋で/野蒜や虫も煮るだろう/森や雨も混ぜるだろう/風の香りをさくさく振って》
おじいさんやおばあさん、嘘つき「むっちゃん」、峠を越えてくる「ふうかやん」ことばを煮つめる鍋の底。
村田喜代子『鍋の中』(文藝春秋・1986)の田舎では、八十歳のおばあさんの家に四人の孫が預けられた。おばあさんは、小鍋をしまい大鍋で野菜や魚が溶けてどろどろになる手料理を作る。だが、孫たちは食べられない。語り手である孫の一人が台所仕事を交代した。おばあさんは、小さな畑でとれた苺、ほおずきトマト、黒とうもろこし、獅子唐辛子…孫に渡し、サヤ豆に筋をとり、下ごしらえの手伝いにまわる。怖いのは、おばあさんから家族をめぐる怪談めいた話をきかされたことだ。おばあさんをふくめた十三人きょうだいの、ドラマのような人生には、孫たちの係累にまつわる秘密の部分もあるが、おばさんの記憶は錯綜としている。半信半疑だが、孫たちは気持ちが揺さぶられる。おばあさんの鍋のなかに投げ込まれたのだ。食材をどろどろに溶けさせる大鍋は、規範言語から解き放たれた詩語の喩のように感じた。鍋底が抜けて森や雨や風にまじり、やがて文字以前の世界に還るのだろうか。
 ピーターラビット展にて
撮影:寺田 操(C) 創作プラン 尾崎翠『「第七官界彷徨」の構図その他』(「新興芸術研究」1931・6月号/『尾崎翠集成』(上)ちくま文庫/2002・10)は、およそ90年も前に発表された小説の創作プランのテキスト化だ。小説の意図、計画の設計図(プラン)が詳細に書き込まれていた。場面の配列地図、登場人物の心理と行動。時代心理(非正常心理、特殊な詩境)。一人称以外の人物心理描写には独語、新造語など。作品全体は、円形を描いてぐるりと一廻りするプランだったが、最初の二行を削除したため配列地図は直線に延びてしまった。作品は生きもの、作者の思惑を超えて、いや作者さえ裏切って蠢くものだ。大正から昭和初期に『第七官界彷徨』、『こほろぎ嬢』、『地下室アントンの一夜』などのシュールでモダンな作品を紡ぎ出した尾崎翠。「私はひとつ、人間の第七官にひびくような詩を書いてやりましょう」と詩の境地に誘い込んだ『第七官界彷徨』(「文学党員」1931・2~3月号)は、イメージコラージュしたくなる不思議な世界。
恩田陸『三月は深き紅の淵を』(講談社/1997)は、本文の中で創作プランを挿入させている。この長篇小説は一冊の稀覯本(「三月は深き紅の淵を」)をめぐる四部作の物語。第一章「待っている人々」では、幻の本探しに招待された青年が隠し場所を推理するのだが、小説は実際には存在しない。第二章「出雲夜想曲」では、幻の本の作者を探して出雲に旅する二人の女性編集者。小説は実際に存在するが、どうも合作ではないかと疑惑が沸き上がる。第三章「虹と雲と鳥と」では、これから書かれようとしているところの話は、離ればなれになっていた異母姉妹に秘められたある惨劇。第四章「回転木馬」では、この小説を作者が今まさに書こうとしているところ、というプランが綴られる。四つの章がそれぞれ独立した物語となっていて、それらがそのまま幻の一冊の本の物語に収斂されていく。三つまでの話は企画通りに進むが、四つ目のタイトルだけが決まっていた「回転木馬」をどう終えるのかが思い付かない。
《この書き出しはどうかな、と考えた。タイトルが「回転木馬」なのだから》、《この書き出しはどうだろう。/小説のタイトルには使えそうで使えないものがある》、何度もリフレインされる「書き出しは」のフレーズ。
作者(私)は、長篇を書く前に映画のポスターの予告篇のようなものを書く。レタリングしたタイトル文字を書き、惹句を書き、粗筋を書く。予告編を書いていると、吉原幸子の詩の一節「書いてしまへば書けないことが、書かないうちなら書かれやうとしているのだ」を思い出す。子供のころ児童文学のカタログを見るのが好きだった。タイトルと表紙の写真から内容を想像する楽しみ。タイトルが怖いアンデルセン『絵のない絵本』。夜行列車の雰囲気が忘れられず二度目の出雲への旅立ち。美術館で見た、たくさんの子供たちが血みどろの戦争をしている絵小説。実作者の日常が紛れ込んでいるような書物遍歴や旅のこと。個人的なテーマは「ノスタルジア」にあるが、《心地好く切ないものであるのと同時に、同じくらいの忌まわしさにも満ちている》懐かしさである。物語の奥に誘われると、「外側」の四つの話と「内側」の四つの話が入れ子構造になっている。
《世界というものがぐるぐると大きな円を描いて、時間的にも空間的にも循環しているという感蝕》というのは、この長篇小説が円環構造になっているということでもある。自分の尾を噛むウロボロス。反復・再生・輪廻・聖なるもの……無限反復が、新しい物語を呼びこむ。
小説はコロナ禍に再読したのだが、記憶から欠落している部分も少なくなかった。第四章では、進行中の作品が断片的に挿入され、物語のプランが同時進行される。物語と現実が溶けあって回転木馬のように廻り続けるが、語り手=実作者ではないだろう。人称の使い分けが見事だ。実在の作家の創作プランを丸ごと挿入していると思わせるマジックが、実に効果的に働いていた
 大阪・中之島美術館
撮影:寺田 操(C) (個人誌「Poetry Edging」№53―2022年11月01日発行―より転載)
★プロフィール★
寺田 操(てらだ・そう)詩人。編集として『幻想・怪奇・ミステリーの館』(「エピュイ23」白地社)。詩集として『みずごよみ』(白地社)、『モアイ』(風琳堂)、評論として『恋愛の解剖学』(風琳堂)、『金子みすゞと尾崎翠──一九二○・三○年代の詩人だち』(白地社)、『都市文学と少女たち―尾崎翠・金子みすゞ・林芙美子を歩く』(白地社)、童話として『介助犬シンシアの物語』(大和書房/ハングル版はソウル・パラダイス福祉財団より)、『尾崎翠と野溝七生子』(白地社)、共著として『酒食つれづれ』(白地社)、『小野十三郎を読む』(思潮社)、『尾崎翠を読む 講演編 2』(今井出版)、2018年8月に共著『宮崎駿が描いた少女たち』(新典社)を刊行。
Web評論誌「コーラ」49号(2023.04.15)
「新・玩物草紙」鍋の底・鍋の中/創作プラン(寺田 操)
Copyright(c) SOUGETUSYOBOU 2023 All Rights Reserved.
|
| 表紙(目次)へ |