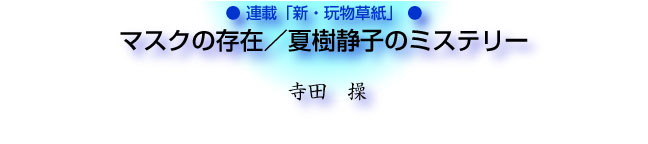|
|
|
Web評論誌「コーラ」 |
|
■創刊の辞 ■本誌の表紙(目次)へ ■本誌のバックナンバー ■読者の頁/ご意見・感想 ■投稿規定 ■関係者のWebサイト ■プライバシーポリシー |
|
<本誌の関連ページ> |
|
■「カルチャー・レヴュー」のバックナンバー ■評論紙「La Vue」の総目次 |
Copyright (c)SOUGETUSYOBOU |
|
|
(キーボード:[Crt +]の操作でページを拡大してお読みいただけます。)
マスクの存在 春には花粉症がでるのでサングラスとマスクと帽子は必需品。外出時には予備のマスクを持ち歩く。マスクにはほぼ抵抗は少なかったのだが……。どこを見てもマスク・マスク・マスクが街を闊歩しているとなれば、鼻が顔から抜け出して街を歩きはじめるというゴーゴリ―的な世界ではないか。マスクの女とか、マスクの男とかではなく、「マスク」という「存在」が街を歩くのだ。なにしろ世界中を「マスク」が席巻してしまったのだから。なかでも民族色豊かなマスクの登場には驚かされたし、その地には新たな雇用も生み出された。
コロナ禍がはじまった春から顔に馴染んでしまったマスクについて、長谷川龍生「マスクの存在」(現代詩文庫『長谷川龍生詩集』所収/思潮社/1969年)が気になった。
《ひとが、むなしく/かすかに呼吸(いき)をひきとるとき/そのひとの顔から/マスクが、はずれる//よろこびに焼きただれた色。/孤独な時間にさらされた皺の起伏。/殺人者の鼻。/ありふれた二つの空洞(うつろ)な眼。//音も、たてずに/ふうわりと/はずれていくマスクの下から/そのひとのデスマスクが/もうれつな速度で沈んでいく。――》
ここまで読んでハッとした。この「マスク」は、人が意識的あるいは無意識につける不可視の仮面の「喩」なのであろうと。コロナ禍では、顔を覆うカラフルでお洒落なファッションマスクの流行があり、世界に遅れまじと、老いも若きもマスクファッションに目覚めた。レースのマスクカバーまで登場した。
マスクは感染症から身を守る役割だけではない。その下にはデスマスクを潜ませている。マスクの本質は生と死をチェンジさせる「境界」だ。不織であれ布であれ、繊維は皮膚にはりつき一体化することもある。季節が二巡しても変異種が次々と顕われ、距離をとればマスク不要と言われても外せない心理。見知らぬ顔になってはいないかと心配だ。詩は《ひとが、退屈もしらずに/この世界の空気を吸おうとするとき/そのひとの顔の上に/マスクがはりつく。》とある。素顔を隠すためのマスクが、皮膚の細胞と同化した場面を想像して怖くなった。《ある日、あるとき/ぼくは、そっとマスクをはずした。/まだ、ぼくの顔は/デスマスクになっていない。》と詩は終わりホッとした。詩は過去(向こう側)から召喚され、目の前の現実にリンクしてくることがある。
 阪急宝塚駅階段
撮影:寺田 操(C) 夏樹静子のミステリー 「ミステリーの女王は、福岡の街に美しい罠〈トリック〉を仕掛けていた」帯文のキャッチコピーに目を留めた。『ミステリーの女王 夏樹静子と福岡』福岡市文学館/2022・3・19)を開いた翌日の午後、某局TV「夏樹静子サスペンス」を見つけた。このチャンネルは古いTVドラマが多いが、時代の出来事や風俗、世相のクロニクル的面も強く創作の参考になる。夏樹静子のミステリーのTVドラマ化も背景には、実際に起きた事件がヒントになった作品もあり、時代の推移、街の変貌、人の心の奥に棲みついた得体のしれない悪意や殺意などの緻密な描写には注目していた。夏樹静子のミステリーはTVドラマ化されることが多く、「女検事 霞夕子」「弁護士 朝吹里矢子」などのシリーズものはよく見ていた。その日の作品は「日向夢子調停委員事件簿④」、原作「最後に愛を見たのは」(講談社/1984・10・20)。父子二人の少年と、母子二人の少女の周辺で時間を隔てた起きた二つの殺人事件の謎とトリック。映像では白い粉が入った小瓶をランドセルにぶら下げた少年少女の姿が印象に残る。もちろん彼らはそれが毒物だとは知らない。殺人に関わる大人たちの怪しい行動より、孤児的な感覚の少年少女が気にかかった。グリムや宮沢賢治の童話の系譜に繋がるミステリーだ。原作が映像化されるとき、時代設定、展開、結末などは変更されることが少なくない。映像は別のテキストだからだ。
夏樹静子ミステリーを謎解きやストーリー展開だけを愉しんでいた私に、読みの新しさを気づかせたのは、『敍説Ⅲ15/特集?夏樹静子』花書院/2018・10・10)だった。二沓ようこ「夏樹静子作品における団地の風景」(『幻の探偵作家、大貫進の時代4』))のアプローチは団地の発見だ。東京生まれの夏樹静子が結婚して福岡へ、断筆のあとに子育てしながらの作家デビュー。子を抱いたときに「母と子のありさま」を書きたい内発的衝動から生まれた作品は1970年の『天使が消えていく』。鉄筋コンクリート5階建てのマンモス団地に暮らし、「主婦作家」と呼ばれながら「団地ミステリ」という新趣向を展開した。憧れの場所はときに「柩」にも「檻」にも見える異世界だと思うのは実体験だろう。団地・失踪といえば安部公房『燃えつきた地図』(1967)の遠近法を使った描写が印象的だが、夏樹はさらに等身大の女性たちの不安や怖れをミステリアスに描いた。二沓さんが指摘したように「作品が時代を反映していく」「時代とともに作家が変貌していく」リアルさに迫ったのだ。
夏樹静子ガイドブックは万華鏡だ。表紙にはブルーインクで執筆された原稿用紙の特徴のある文字、その上に置かれた写真には、障子と椅子が映る部屋で我が子を抱く母。本文では、家族アルバムや写真で振り返る「夏樹静子クロニカル」、作品の聖地巡礼に誘う「夏樹静子が歩いた街」と舞台となった福岡の街のMAP。夏樹静子というペンネームで福岡を舞台とした初めての短編「見知らぬ敵」が収録されている。殺害方法は交換殺人だが、玄界灘の崖がおもいがけない結末を用意していた。
興味を惹かれたのは「夏樹ミステリー×現代女性史」で、登場する女性たちの時代背景と姿をリンクさせた試みだ。70年代では「母性と自我のせめぎあい」、「ジェンダーフリーの芽生え」、「子は誰のものか」。80年代では「『女の時代』の幕開け」、「専業主婦のアイデンティティの揺らぎ」。90年代では「家庭も仕事も恋も、みんな欲しい」、「生殖医療の進歩と法整備の溝」……作品と時代背景、職業や服装、女性をめぐる価値観などの解読。母性幻想、蒸発、ウーマンリブ、ジェンダーレス、子殺し、産後うつ、主婦症候群、翔んでいる女、子の虐待、生殖補助医療……夏樹の取材と分析を踏まえて浮き彫りにされていく女性像。渇きと不安のなかの70、80年代は高橋たか子やデュラスを引き寄せていた私だが、5歳下の妹は夏樹静子を読んでいた。ミステリーのなかの主人公たちは、わたしのなかの、あなただ。
 尼崎市七松町のギャラリー
撮影:寺田 操(C) (個人誌「Poetry Edging」№52―2022年07月01日発行―より転載)
★プロフィール★
寺田 操(てらだ・そう)詩人。編集として『幻想・怪奇・ミステリーの館』(「エピュイ23」白地社)。詩集として『みずごよみ』(白地社)、『モアイ』(風琳堂)、評論として『恋愛の解剖学』(風琳堂)、『金子みすゞと尾崎翠──一九二○・三○年代の詩人だち』(白地社)、『都市文学と少女たち―尾崎翠・金子みすゞ・林芙美子を歩く』(白地社)、童話として『介助犬シンシアの物語』(大和書房/ハングル版はソウル・パラダイス福祉財団より)、『尾崎翠と野溝七生子』(白地社)、共著として『酒食つれづれ』(白地社)、『小野十三郎を読む』(思潮社)、『尾崎翠を読む 講演編 2』(今井出版)、2018年8月に共著『宮崎駿が描いた少女たち』(新典社)を刊行。
Web評論誌「コーラ」48号(2022.12.15)
「新・玩物草紙」マスクの存在/夏樹静子のミステリー(寺田 操)
Copyright(c) SOUGETUSYOBOU 2022 All Rights Reserved.
|
| 表紙(目次)へ |