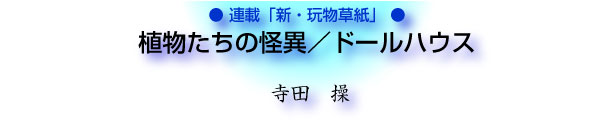|
|
|
Web評論誌「コーラ」 |
|
■創刊の辞 ■本誌の表紙(目次)へ ■本誌のバックナンバー ■読者の頁/ご意見・感想 ■投稿規定 ■関係者のWebサイト ■プライバシーポリシー |
|
<本誌の関連ページ> |
|
■「カルチャー・レヴュー」のバックナンバー ■評論紙「La Vue」の総目次 |
Copyright (c)SOUGETUSYOBOU |
|
|
(キーボード:[Crt +]の操作でページを拡大してお読みいただけます。)
植物たちの怪異 星野智幸『植物忌』(朝日新聞社・2020・5)は、人間と植物の交歓、チェンジ、一体化、食物連鎖などがモチーフとされた近未来の魔訶不思議で不気味な世界だ。植物の殿堂「からしや」を舞台に、小説世界がリアルに迫ってくる。地球温暖化、人口爆発、食糧問題、自然災害やウィルスの襲来といった、人間を取り巻く環境の激変が現実に起きているからだ。とりわけゲノムテクノロジーの急激なる進化で、遺伝子操作にスポットが当てられたことについて。植物と人間の親和性が揺らいでいくことに背中が凍りついた。「桜源郷」では、花見をしたひとがそっくり消える事件が勃発。桜の森へ入り消えることを選ぶ人々。既視感さえ覚えてしまった。「喋らん」では、合成ではない人間の声でしゃべるラン、シクラメン、トポスたち。喋る草の開発は、ルイス・キャロル『鏡の国のアリス』に登場した喋る花たちをファンタジーから追い出した。人造植物の商品化だからだ。頭皮に植えられたヘチマ、ゴーヤは食用に用いられ、ファッションにもなる「スキン・プランツ」。花を咲かせると生殖機能が失われ、新世代が誕生しなくなる。種が地中に埋まり発芽すると胎児の実がなり、人間の声で泣きはじめる。植物転換手術を受けた青年の心臓には植物処理がされ、交換可能な花歯車が活けられる「ぜんまいどおし」。人間の文明を破壊する「ひとがたそう」。「プレードランナー」もどきのハイパー植物たちの陰謀を暴く特殊工作隊のガーディナーたち。人間との接ぎ木が可能になった植物たちの野望。植物の変身譚や擬人化のモノカタリは本棚でひそかにネットワークを形成している。古今東西の世にも不思議な世界は坂口安吾に梶井基次郎に変奏され、星野版ではさらに更新されて新しいモノカタリが生まれた。
朝倉かすみ『植物たち』(徳間文庫/2019・3)は、現代社会で起きている世相や現象をキャッチして、植物の生態に仮託した世界だ。構成はイメージの基になった植物名と生態を本文の前置きとしている。例えば二篇で対になった「どうしたの?」はホテイアオイ(大繁殖することもある)の葉柄が布袋の腹のようにふくらんでいる。「どうもしない」はリトルサムライ(乾燥地帯に堅く直立した葉)。「どうしたの?」の語り手は69歳の独り物男性。盛り場近くにあるギャラリー兼アトリエの二階建て空き家を購入。日課とした公園の散歩で十七歳の家出少女アズと出会った。アズは「どうもしない」の語り手で「ドールハウス」みたいだと男の家に住みつく。やがて少女たちが増え、胎児を抱えて眠る妊婦(ホテイアオイ)たちの巣づくりの場に変容した家。彼は彼女たちを芸術品のように扱い、見守るリトルサムライになった。
 花の道沿いの宝塚ホテル
撮影:寺田 操(C) ドールハウス コロナ禍で増えた「お家・時間」でドールハウス造りがひそかなブームになっているらしい。ミニアチュアの家で遊んだ記憶はないが、子供用の洗濯機(ハンカチ1枚洗える)、扇風機、キッチン用具など、5歳下の妹が買ってもらっていたことなどと懐かしい。
恩田陸『私の家では何も起こらない』(MF文庫/2013・2)には、丘の真上に立つ幽霊屋敷と呼ばれる「家」をめぐる怪談が集められた。会話体だけで構成された作品が多いのだが、「あたしたちは互いの影を踏む」の姉妹の話には背筋が凍りつくような恐怖を覚えた。アップルパイを焼きながら姉妹が抱えて来た秘密があらわになり……。聖地であると同時に魔所でもある丘の上の屋敷で起きた事件と、肉体が消えても屋敷のなかに棲み続ける死者たち。文庫版あとがきで、恩田は子供の頃に読んだルーマー・ゴッデン『人形の家』から、ドールハウスに住む人形たちが疑似家族を作り暮らしていたが、邪悪な人形がやってきて共同体が壊れたことについて語り、ドールハウスを怖いと感じるのは「人形の家と自分の世界とが入れ子状態になっていることを意識するからからかもしれない」とも述べていた。本棚をながめると、大好きな怪奇幻想の世界は「家」をめぐる物語が多いことに気づかされる。なかでも「建物」をめぐる物語にはワクワクするし、写真や設計図があればなおうれしい。近代建築の残る神戸の旧居留地近くや、大阪の淀屋橋界隈で仕事をしていたことがあった。海野弘『モダン・シテイふたたび 1920年代の大阪へ』(創元社/1987)には、勤務先に隣接するビルが掲載されていた。なんという幸運だったろう。モダン建築関係の書籍は(「二笑亭」など奇想天外な建築から現代建築まで)本棚に収まることになった。建築は時代を写す鏡でもあると思う。
海東セラ詩集『ドールハウス』(思潮社/2020・11)は待っていた一冊だ。《ふり向いてごらんなさい、背後はどこまでも開かれている、ここはあらかじめ不完全にオープンな部屋です。》と、ドールハウスの空っぽな空間に思い通りの室内装飾をしていくのは実にクリエイティブな作業だ。小説を読むとき、主人公たちがどんな部屋でどんな家具に囲まれて暮らしているのか想像するのは楽しいのだから。と思えば「たてまし」のように、増殖をしはじめるとブレーキがかからないのは怖い。家としてのバランスを崩しても、家は「いきもの」であることを主張しはじめる。
詩集はアフォリズム・モンタージュといってよい掌篇ではないだろうか。ヴァルター・ベンヤミン「一方通行路」「一九〇〇年頃のベルリンの幼年時代」(『ベンヤミン・コレクション3』浅井健二郎編訳・久保哲司訳/ちくま学芸文庫/1997)が本棚から合図してきた。かつて私はベンヤミンの引用とモンタージュの方法にも触発されていたことがあった。海東さんのアプローチは「床」「天井」「屋根裏」「下廻りの階段」「砂壁」「デッドスペース」「窓辺だけの部屋」、今一番の関心事「換気」と多岐にわたる。建物の形象、素材、構造の表出に加えて、隠喩としての建築(柄谷行人)的な文脈をも引き寄せたくなる。
《迷いこんだものがいるなら/ば抱いてやります。さびしい声を拾いあげてやる、雅量は/いつだってあるのです。》のは「縁の下」だ。人の声やざわめきや息などが建物の内から漏れ聴こえ、生活する人のしぐさや食卓風景も見える。建物の堆積した記憶が詩人の脳内に分け入り、物象の奥深くで目にしたものを言語として変換する。ベンヤミンなら「文を奪い取る」と述べるだろうか。「仮寓」の坂道、いしだたみ。庭に干された白いシーツにはどんな影が映るのか。
詩篇はときに散文を欲望する、小説への変容を企てている。けれど容易に物語へと移行してはならない。詩人は、ぎりぎりの詩の縁に作品を置いていた。
 花の道の時計
撮影:寺田 操(C) (個人誌「Poetry Edging」№49―2021年07月01日発行―より転載)
★プロフィール★
寺田 操(てらだ・そう)詩人。編集として『幻想・怪奇・ミステリーの館』(「エピュイ23」白地社)。詩集として『みずごよみ』(白地社)、『モアイ』(風琳堂)、評論として『恋愛の解剖学』(風琳堂)、『金子みすゞと尾崎翠──一九二○・三○年代の詩人だち』(白地社)、『都市文学と少女たち―尾崎翠・金子みすゞ・林芙美子を歩く』(白地社)、童話として『介助犬シンシアの物語』(大和書房/ハングル版はソウル・パラダイス福祉財団より)、『尾崎翠と野溝七生子』(白地社)、共著として『酒食つれづれ』(白地社)、『小野十三郎を読む』(思潮社)、『尾崎翠を読む 講演編 2』(今井出版)、2018年8月に共著『宮崎駿が描いた少女たち』(新典社)を刊行。
Web評論誌「コーラ」45号(2021.12.15)
「新・玩物草紙」植物たちの怪異/ドールハウス(寺田 操)
Copyright(c) SOUGETUSYOBOU 2021 All Rights Reserved.
|
| 表紙(目次)へ |