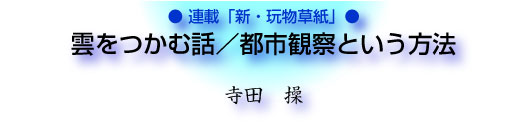|
|
|
Web評論誌「コーラ」 |
|
■創刊の辞 ■本誌の表紙(目次)へ ■本誌のバックナンバー ■読者の頁/ご意見・感想 ■投稿規定 ■関係者のWebサイト ■プライバシーポリシー |
|
<本誌の関連ページ> |
|
■「カルチャー・レヴュー」のバックナンバー ■評論紙「La Vue」の総目次 |
Copyright (c)SOUGETUSYOBOU |
|
|
雲をつかむ話 多和田葉子「雲をつかむ話」(『雲をつかむ話-ボルドーの義兄』講談社文芸文庫/2019・4・10)は、「人は一生のうち何度くらい犯人と出遭うのだろう」という衝撃的な書き出しではじまる。多和田葉子の小説は、ある種の言語実験も兼ねているので、物語を多層的な視点から読むことを強いられ、想像力が試されているようで読む前から緊張する。この文庫を枕辺で少しずつ読んでいるのだが、ストーリーを追っていくことで日常のストレスを発散するミステリーやサスペンスなどの愉しみからは遠い場所に連れだされるため、なかなか前に進めない。かといって別の本を読むとせっかく連れ出された場所から、最初のページに引き戻されるという気がして枕辺から遠ざけることはできない。書き出しの続きは「犯罪人と言えば、罪という字が入ってしまうが、わたしの言うのは、ある事件の犯人だと決まった人間のことで、本当に罪があるのかそれともないのかは最終的にはわたしにはわからないわけだからそれは保留ということにしておく。」と、「犯人」と「犯罪者」とを区別することで、「犯」という漢字にまつわるさまざまな意味や姿態を、小説世界に組み込んでいく。意味は固定化されない、姿態は多層である、ということだろうか。
ごくごく普通の暮らしをしている人の人生にも、犯人の人生と交差することがあるという12話の連作。語り手が出遭った「犯人」たちと紡ぎあげる虚と実のあいだで揺れる「体験談」とは、まさに「雲をつかむ話」だ。――それにしても体験談というものが何度も繰り返し話しているうちに嘘になって熟していくのはなぜだろう。嘘をつくつもりなど全くなくても、語りの滑走路を躓かないように走るには、まばたきするくらい短い時間内で「記憶の穴」を埋めていかねばならない。――と語るその「記憶の穴」には真実が埋められているのだろうか
 中之島公会堂の内部のステンドグラス(昨年冬のクリスマスイベント)
撮影:寺田 操(C) 都市観察という方法 織田作之助『夫婦善哉』講談社文芸文庫/1999・5・10)には、わずか7年の作家生活の代表作6篇が収録されている。織田作之助(1913~1947)の代表作といえば、船場のぼんでダメ男柳吉と、しっかり者の芸者蝶子の夫婦漫才的な「夫婦善哉」が挙げられる。確かに大阪らしい男女の機微や人情が濃厚で、法善寺横丁の風情や道頓堀界隈などはいまでも人気のスポットだ。「頼りにしてまっせ、おばはん」の名セリフが有名となったが、原作にはない。映画は原作とは違う映像テクストだ。文学の舞台となった(聖地巡り?)には原作を読んでもらいたいもの。
「夫婦善哉」ほどの人気はないが、小説の面白さを堪能できるのは、料理屋を転々とする順平(「放浪」)、伝染病院に勤務のかたわら将棋の定跡にのめりこむ楢雄(「六白金星」)、バタ屋(拾い屋)の手伝い・青物行商・紙芝居・貯蓄会社の外交官、病院雑役夫と人生双六のごとく転がっていく長藤十吉(「アドバルーン」)。いずれもダメ男列伝である。職業や住まい、女性関係を転々とする男たちは、昭和のモダン都市大大阪の裏町をうろつく遊歩者。当時の世相や人々の暮らしぶりが、新聞の三面記事のように浮き彫りにされるのが魅力だ。作品には具体的な食べ物や店の名がちりばめられ、地名や事物や名称、物の値段などの記述が目立つ。モノにコトを語らせていくのだ。
文体も語り口も美意識も織田作之助とは対照的だが、埴谷雄高『死霊』1~8章 講談社/1981~1986)にも昭和初期の東京、はりめぐらされた大小の運河と橋の形状や隅田川周辺のアンダーワールドな光景が緻密に描写された。形而上学的と評される長篇小説だが、男たちの難解な哲学問答より、女たちの圧倒的な存在感や、事物を印画紙に転写するような都市観察の方法に惹きつけられた。その視線をくるりと大阪へ向けると、織田作之助が描いた都市を放浪する男たちの光と影とが映像となって浮かびあがる。
なかでも満州事変が勃発した昭和6(1931)年頃の「アドバルーン」は、時代を置き換えて読めば、格差社会でネットカフェを転々としている現在の若者たちと似たような世界だ。食いつめて大阪の灯を見てから死のうと、東京から戻ってきた十吉が向かったのは水都大阪の夜の街。
《大阪駅へ着いたのは夜でした。(略)大阪駅から中之島公園まで歩きました。公園の中へはいり、川の岸に腰を下して煙草を吸いました。川の向う正面はちょうど北浜三丁目と二丁目中程のあたりの、支那料理屋の裏側に当たっていて、明けはなした地下室の料理場が殆ど川の水とすれすれでした。その料理場では鈍い電燈の光を浴びた裸かの料理人が影絵のようにうごめいていました。》
中之島公園は明治24年開園。35年には公会堂、36年には日本銀行、37年には図書館完成。明治期の中之島は経済と文化の中心地。御堂筋の地下鉄工事は昭和5年着工し、都市はダイナミックに整備され都市景観を変貌させていった。織田作之助は、中之島公園を囲む表通りの華やかな顔から視線をそらせ、裏側にファインダーをあてる都市観察の方法をとっている。中之島公園の水面にうつるネオンは、十吉には、心休まる灯だ。川面に落ちる街の灯が消えるまで川底を眺めていた十吉は、バタ屋(拾い屋)の秋山さんに声をかけられ命を救われた。その後の十吉は職業転々としながら数奇な運命をたどるのだが、昭和初期の世相のめまぐるしい変貌ぶりが、中原中也の詩「生い立ちの記」のような語り口で描かれていた。幼いころに見た道頓堀の夜景の回想シーンは幻想的だ。眼と耳と足と皮膚感覚を駆使して、人々の多彩な生きざまに視線(灯)をあて、都市を観察した織田作之助は、まさしく全身感応体の都市遊歩者であった。
 兵庫県立美術館ギャラリーでの「アリス展」部屋展示の「お茶会」テーブル
撮影:寺田 操(C) (個人誌「Poetry Edging」№44―2019年11月01日発行―より転載)
★プロフィール★
寺田 操(てらだ・そう)詩人。編集として『幻想・怪奇・ミステリーの館』(「エピュイ23」白地社)。詩集として『みずごよみ』(白地社)、『モアイ』(風琳堂)、評論として『恋愛の解剖学』(風琳堂)、『金子みすゞと尾崎翠──一九二○・三○年代の詩人だち』(白地社)、『都市文学と少女たち―尾崎翠・金子みすゞ・林芙美子を歩く』(白地社)、童話として『介助犬シンシアの物語』(大和書房/ハングル版はソウル・パラダイス福祉財団より)、『尾崎翠と野溝七生子』(白地社)、共著として『酒食つれづれ』(白地社)、『小野十三郎を読む』(思潮社)、『尾崎翠を読む 講演編 2』(今井出版)、2018年8月に共著『宮崎駿が描いた少女たち』(新典社)を刊行。
Web評論誌「コーラ」40号(2020.04.15)
「新・玩物草紙」雲をつかむ話/都市観察という方法(寺田 操)
Copyright(c) SOUGETUSYOBOU 2020 All Rights Reserved.
|
| 表紙(目次)へ |