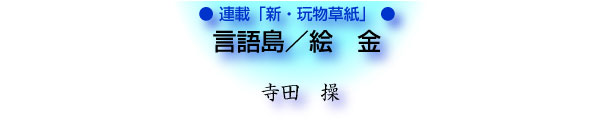|
|
|
Web評論誌「コーラ」 |
|
■創刊の辞 ■本誌の表紙(目次)へ ■本誌のバックナンバー ■読者の頁/ご意見・感想 ■投稿規定 ■関係者のWebサイト ■プライバシーポリシー |
|
<本誌の関連ページ> |
|
■「カルチャー・レヴュー」のバックナンバー ■評論紙「La Vue」の総目次 |
Copyright (c)SOUGETUSYOBOU |
|
|
言語島 言語の島(言語島)とは「ごく狭い範囲に限って他の言語を用いる地域が、海中の島のような状態で存在するもの」『大辞林』(三省堂)。山岳地方や隠里、無人島に近い群島、地域ごとの移住でそこだけでしか通用しない言語のことなど。人が住まなくなれば消滅してしまう。言語島をゆっくりと反転させてみる。どこにも存在しない、存在しているが見えない「言語島」が立ち上がってくる。
森見登美彦の長篇小説『熱帯』(文藝春秋/2018・11・15)は、最後まで読むことができない幻の本を追って本の内側に滑りこんだ男の不思議な冒険譚だ。孤島の浜辺に流れついた記憶喪失の男は、島々は魔王の「創造の魔術」の裡にあり、消えたり現われたりするのだと聞かされた。密林のなかの観測所、砲台のある島、地下牢の囚人、謎の組織学団、不可視の群島」の海図。世界と一体化したような海域で起こる謎めいた現象……。
時里二郎『名井島』(思潮社/2018・9・25)は、「この島には/ことばをめぐる争いしかない」「島は記憶の捨て場である」(「島のことば」)と、過去と未来の中継点として描かれた。アンドロイドのサナトリウム、流し雛の流れ寄る島のモノカタリ。なかでも「雲梯」には心が震えた。後鳥羽院が流罪になり隠岐に向かうとき、口頭で託されたコトノハを森のなかに落としてしまったオキナは、「忘れてしまった」とは言わなかった。さまよううちに身体から遊離していくコトノハの術の不可思議に気づいた。院の歌を身体に抱えること身が持ちこたえられなくなること。月夜茸(毒茸だ)に変容したコトノハの光の塊が猿ほどに身体が縮んだオキナを吸いとり心が残った。はだかの心を容れる新しい身体(初期型アンドロイド)が生まれた。「ことばは人のものではない/借りたものだから/返すにしくはない」(「通訳」)。言語をめぐるアルカイックでSF的な詩歌の世界へと誘われた。
 「神戸異人街の旧ハンター邸の扉」撮影:寺田 操(C)
絵 金 新聞の新刊本広告を眺めていたら、「絵金」の文字がズームアップしてきた2018年の夏。広告はモノクロームなのに、血染めの赤色が文字の奥から立ち上がって噴きだしてくる気配に、思わずドキリとして、サッと顔をそむけた。一呼吸して広告に目を落とすと、木下昌耀『絵金 闇を塗る』集英社/2018・7・10)だ。近頃の新刊本には作者の写真が掲載されていることが多く、時代小説の作家としては若い。刊行記念に大阪と高知でのサイン会の日時・会場が記載されている。高知には第42回「土佐赤岡絵金祭り」会場内、問い合わせは「絵金祭り」実行委員会事務局。「絵金祭り」は、1970年代後半に赤岡町で始まり、毎年7月に開催されている。まだ続いていたことに驚かされた。祭りは絵金を主人公にした映画『闇の中の魑魅魍魎』(1971/中平康監督・麿赤児主演)の流れから再評価の機運が高まってのことだろう。
小説を手にしてみると、表紙絵には蝋燭の奥で怪しく揺れるおどろおどろしい絵金の芝居絵があった。この絵はみたことがある。我が家の本棚の片隅には、もう何十年も開いていない『異端画家 絵金の芸術』(解説・近森敏夫/光潮社/一九七一・一〇・二五)があるので確かめてみると、二曲一隻の「花上野誉石碑の四段目志度寺」だ。あいにく画集の方はモノクロームなので血塗られた赤色はみられないが、絵金の色彩の特徴である赤と黒と緑のうち、緑がどこに使われているのか分からないのが残念だ。
泉鏡花原作の映画・清順流フィルム歌舞伎『陽炎座』(一九八一)をみたとき、老人形師が開く秘儀の集まりで裏返しの世界がでてきた。人形を裏返して空洞をのぞけば人妻と男が背中合わせに座っている死後の世界だったが、その背景に使われていた、おどろおどろしい絵は、絵金ではなかったろうか。パンフレットを買って映画についてのエッセイを某誌に書いたのだが、室内で行方不明になり、確かめようがない。しかし、あれは、やはり「絵金」だったような気がする。映画の舞台は大正末期にして昭和元年の一九二六年、東京。エッセイを書いたご縁で拝受したのが、『絵金の芸術』だと記憶しているのだが……。
「――えきんさんを、おいかけたらいかんぞね。」「――絵金さんを追いかけよったら、噛みつかれるがで。」と、芝居絵屏風の横に老婆がたたずみ、枯れた口が蠢いて語りかける木下昌輝『絵金 闇を塗る』だが、幕末から明治にかけ生きた天才とも異端とも、贋作師とも呼ばれた絵師・絵金こと弘瀬金蔵(1812~1867/文化9~明治9)が主人公ではない。老婆の口がつむぐのは、絵金に噛みつかれた男たちの物語だ。絵金の支援者・豪商仁尾順蔵、師・狩野派の前村洞和、土佐家老・桐間蔵人、歌舞伎役者・市川團十郎、土佐勤王党の武市半平太(彼は絵金の弟子)、岡田以蔵、同時代の絵師河田小龍など。いずれも毒を孕んだ絵金の「絵」と出会ったことで狂っていく男たちだ。彼らの血みどろの人生が闇に塗られた。
高知の髪結いの子として生まれた金蔵。土佐藩のお抱え絵師で狩野派の流れを汲む池添美雅に師事して画才を認められ、18歳で江戸へ。狩野洞白に師事、前村洞和に私淑して狩野派の技法を習得。帰国して藩のお抱え絵師に取り立てられ、林洞意(絶家となっていた藩医林家の株を買い士分格に)と名乗った。ところが、狩野探幽の偽絵を描いたというスキャンダルで城下追放、絵も焼却された。城下を放浪しながら紺屋、染物屋などで絵を描き、祭りのために歌舞伎などの芝居絵を描く町絵師になる。赤・黒・緑を基調にした彩色で、提灯絵、大屏風など、まるで床の間絵を裏返したよう奇怪な世界をつくりあげた。庶民にとり夏祭りの芝居絵に絵金は欠かせない。だが、解説の近森敏夫によれば稚拙な偽絵群もあるという。
 「クローズした宝塚ガーデンフィールズ隣接のレストランの扉」撮影:寺田 操(C)
(個人誌「Poetry Edging」№43―2019年07月01日発行―より転載)
★プロフィール★
寺田 操(てらだ・そう)詩人。編集として『幻想・怪奇・ミステリーの館』(「エピュイ23」白地社)。詩集として『みずごよみ』(白地社)、『モアイ』(風琳堂)、評論として『恋愛の解剖学』(風琳堂)、『金子みすゞと尾崎翠──一九二○・三○年代の詩人だち』(白地社)、『都市文学と少女たち―尾崎翠・金子みすゞ・林芙美子を歩く』(白地社)、童話として『介助犬シンシアの物語』(大和書房/ハングル版はソウル・パラダイス福祉財団より)、『尾崎翠と野溝七生子』(白地社)、共著として『酒食つれづれ』(白地社)、『小野十三郎を読む』(思潮社)、『尾崎翠を読む 講演編 2』(今井出版)、2018年8月に共著『宮崎駿が描いた少女たち』(新典社)を刊行。
Web評論誌「コーラ」39号(2019.12.15)
「新・玩物草紙」言語島/絵金(寺田 操)
Copyright(c) SOUGETUSYOBOU 2019 All Rights Reserved.
|
| 表紙(目次)へ |