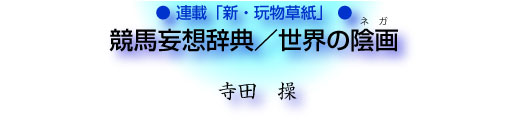|
|
|
Web評論誌「コーラ」 |
|
■創刊の辞 ■本誌の表紙(目次)へ ■本誌のバックナンバー ■読者の頁/ご意見・感想 ■投稿規定 ■関係者のWebサイト ■プライバシーポリシー |
|
<本誌の関連ページ> |
|
■「カルチャー・レヴュー」のバックナンバー ■評論紙「La Vue」の総目次 |
Copyright (c)SOUGETUSYOBOU |
|
|
競馬妄想辞典「自分の書くものについては競馬の話からはじめないと決めていた」と、乗峯栄一『競馬妄想辞典』あおぞら書房/2018・6・26)――には、やはりね、と納得させられた。「競馬以外から話をはじめる」を「あなたのコラムはこれでいいんです」と懐の広いところをみせてくれた編集長との出会いは、「乗峯栄一スタイル」を実行・貫徹できるチャンスとなったことを考えれば、書き手としてのポリシーは大切にしないといけないことの教訓だ。作風(芸風)は時代、自分の年齢、書く場所、読者層に応じて変更していかざるを得ないことがあるのだが(感性が変容してきたとか)、ポリシーは変更しないぞと同感したところで、目次に「JRAにポリシー変更を勧告する」とあり、なんだ、どうしたのかと読みだして……ああ書き手のポリシーそのもののことではないのだと胸をなでおろしたものの、「ポリシー変更」の心当たりありますよねと自分の胸に……。純文学(詩)から他ジャンルにも手を出して、世界の片隅で生き延びてきたのではないですか? ともう一人の私に暴露されるが、「書く」場所がどこであれ、芯の部分に「詩」があればいのだと嘯いてみて。
競馬を縦軸として、競馬への愛を語りながら、社会学、生物学、物理学、歴史学、文学、心理学などを横軸として縦横無尽に走るライター乗峯栄一の面白いこと。読者から「日本一当たらない予想屋」と言われ、調教師から「あんたに本命にされたら勝てへん」とからかわれ……そんなことなどもろともせずに、「人生に必要なことは競馬で学んだ」ですって。薀蓄ばかりを語りたがる団塊の世代とは違うさりげなさのセンスに耳を傾けてみようかなと思わせる好感度。「競馬」だから「競馬以外の」ことは書いてはいけないというのは古い体質だ。織田作之助の短篇「競馬」(「書を持って競馬場へ」)から「小説は本当のことを書け」にはギクッとさせられたのだが。
 撮影:寺田 操(C)
世界の陰画 森 雄治詩集『蒼い陰画』(ふらんす堂/2018・11・15)は、どなたの御縁で届けられただろう。未知の詩人だったので、はじめに略歴を読んだ。
1963年、大阪府生まれ。少年期を吹田市で過ごす。その頃から詩、小説を書き始める。1983年より、愛媛県今治市に移住。1995年1月、病歿(享年31歳)とある。1995年1月といえば阪神淡大震災、未曽有の揺れ、どこへ連れていかれるのかと不安に震えた劇しい冬だ。兄・森 信夫の「付記」によれば、森 雄治が十七歳~二十歳のときに書いた詩をまとめたもので、十八歳の時のノートには「青の陰画」と記されていたと。詩集について弟は生前口にすることがなかったという。
手書きノートは初稿が書かれた後に多数の書き込みがなされ、判読困難な状態になっている詩もある。初稿を採り、処理して編まれたとの詩集上梓時の事情。 帯に刻まれていた《ガラス玉の風景/そこに指紋をつけてはならない/なぜならつけるまでもなく/繊細にどよめき崩れてゆくだけだからだ》は、冒頭に置かれた「意識」のなかほどの詩句だ。森 信夫による青と銀のドローイングと詩句が一枚の画布に《繊細にどよめき》溶け合っていたように思えたのだが、詩句のなかほどでは《薄命の夢の凝縮が/遠い叢林の狂乱をあおって青く染まる》となり、《窓辺/わたしの脳髄で/ガラス玉は鈍く痛む》で終わる。壊れる寸前のガラス玉に細かい罅が入り、ズームアップしてきた。詩は、読み手の感情を写し取る鏡だ。
行わけ詩と散文詩の二部構成だが、ノートの「青の陰画」から詩集タイトル「蒼い陰画」へ、「青」から「蒼」に、「の」から「い」への変更がある。死者から生者へと手渡されたバトンなのか? などと勝手な妄想も引き寄せながら、十田撓子の栞「蒼の眼を持つ男のこと」のタイトルに招きよせられるように、神話的な時間(詩的時間)に入っていく。すると、十田撓子の栞はそのまま散文詩と読めるし、森 雄治の世界に紛れ込ませて編んでもいいくらい、ふたつは溶け合っていた気がした。あなたを見て、あなたを追尾するわたしとして、あるいは、タマシイの同伴者と言い換えてもいいだろう。栞を書く者と詩を書いた者とが鏡像として向き合い、反転し、ひとつとなって深い森に分け入る。追従しようとするあらゆる批評が拒まれているように思えたし、詩集という宇宙に迷いこむことさえ躊躇させる何かがあった。
詩集の最後に置かれた「神話」から、――一切の陰画(ネガ)を収めた《記憶》のように――との詩句をみつけた。陽画(ポジ)と陰画(ネガ)は水際で、境界線上で鬩ぎあいながら、森 雄治の世界を創出するエネルギーとなっていったのであろうか?
最後に置かれた「神話」では、青空の切り口から鉄格子を伝って降りて来た飛行士が、陽光の裡が銀色に病んでいるのを目撃した、という箇所にはっとした。詩全体のシンボルカラーともいえる「青」はその裡に、銀色を孕んでいたのだ。さらに全身を病み発光しているのに、遠目からは《今、まさに羽化しかけている異種なる生物の蛹》という風にも見えるのだったと。
《彼の見てきた世界もまたあの空の薄膜の向こう側に依然として存在しつづけるはずであった 彼の見たものがそれだったとして も 彼の生命の終りによって彼自身が崩れその見てきたという廃墟(ソドム)に他なる他ない》(「神話」)
『蒼い陰画』読了後に再読したくなったのは、地理学、天文学、神話や神秘を取り込んだH・P・ラヴクラフト『ラヴクラフト全集3』(大瀧啓裕訳/創元推理文庫/1984・3・20)だ。《久遠の太古にこの都を築き、居住していた者が、よし人間であるにせよ、その住民のことを語ってくれるような彫刻や碑文は何一つ見つけられなかった。》 (「無名都市」)
 撮影:寺田 操(C)
(個人誌「Poetry Edging」№42―2019年03月01日発行―より転載)
★プロフィール★
寺田 操(てらだ・そう)詩人。編集として『幻想・怪奇・ミステリーの館』(「エピュイ23」白地社)。詩集として『みずごよみ』(白地社)、『モアイ』(風琳堂)、評論として『恋愛の解剖学』(風琳堂)、『金子みすゞと尾崎翠──一九二○・三○年代の詩人だち』(白地社)、『都市文学と少女たち―尾崎翠・金子みすゞ・林芙美子を歩く』(白地社)、童話として『介助犬シンシアの物語』(大和書房/ハングル版はソウル・パラダイス福祉財団より)、『尾崎翠と野溝七生子』(白地社)、共著として『酒食つれづれ』(白地社)、『小野十三郎を読む』(思潮社)、『尾崎翠を読む 講演編 2』(今井出版)、2018年8月に共著『宮崎駿が描いた少女たち』(新典社)を刊行。
Web評論誌「コーラ」38号(2019.08.15)
「新・玩物草紙」競馬妄想辞典/世界の陰画(寺田 操)
Copyright(c) SOUGETUSYOBOU 2019 All Rights Reserved.
|
| 表紙(目次)へ |