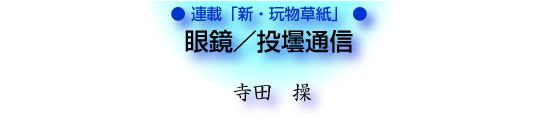|
|
|
Web評論誌「コーラ」 |
|
■創刊の辞 ■本誌の表紙(目次)へ ■本誌のバックナンバー ■読者の頁/ご意見・感想 ■投稿規定 ■関係者のWebサイト ■プライバシーポリシー |
|
<本誌の関連ページ> |
|
■「カルチャー・レヴュー」のバックナンバー ■評論紙「La Vue」の総目次 |
Copyright (c)SOUGETUSYOBOU |
|
|
眼 鏡
《女の眼鏡はごくかすかな音をたてて割れました。》と書きだされた武田泰淳「めがね」『ニセ札つかいの手記』(中公文庫/2012・8・25)では、近眼同士の男女の恋の行方に「眼鏡」が影を落とした。女は眼が悪いのに、男の前でも仕事場でも眼鏡はかけていなかった。男のほうは、《眼鏡は命から二番目に大事なもの》というほど強度の近眼だ。二人が一泊旅行した先の岩苔の公園で、珍しくサックから眼鏡をとりだした女は、風景を見まわしてから男との間のコンクリートのベンチに眼鏡を置いた。小さな事件が起きた。男が不注意に動かしたトランクの下で薄いレンズは砕けてしまったのだ。眼鏡を買ってあげると男は約束したのだが、女は病に倒れ……。
ふいに視界に飛びこんできて、心を奪うというのは、恋愛の文学誌ではおなじみだが、磯﨑憲一郎『終の住処』(新潮文庫/2012・9・1)では、「サングラスの女」が登場した。電車のなかでもサングラスを外さない女は、理想の女に見えるほどの美しさだった。女から目が離せなくなり、同じ駅で降りて、アパートへ招きいれられた。サングラスを外した女は文句をつけようのない美人だったが、冷酷なまなざしを思い描いていた彼には期待外れとなった。《目を見るまでは、その人を知ったとはいえないということか》と思いながらも、素顔を受け入れて関係を持ったとき、彼は女に完全に敗北したのだ。
花粉症で、目にアレルギーがではじめた数年前から、外出時には度入りのサングラスを外せなくなくなった。マスクをかけるときは度の入らない大きめのサングラス(目じりの皺が隠れる)やPC用の縁がカラフルなメガネ。高校生のときから近眼だが、めったに眼鏡をかけてこなかったし、遠近両用の眼鏡は映画館や美術館くらいでしか使用しない。裸眼で新聞も本も読める、パソコンだって打てる、なのに、花粉症からこちら、眼鏡を忘れると不安になる。
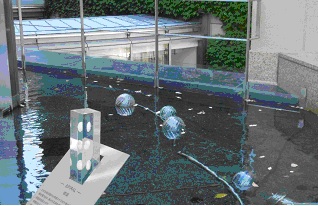 撮影:寺田 操(C)
投壜通信 ある日、突然届いた一通の手紙。湊かなえ『未来』(双葉社/2018・5・23)は、二〇年後のあなた(私=三〇歳)から一〇歳の私に届いた「未来からの手紙」に返事を書くという書下ろし長編ミステリーだ。書簡形式のミステリーは小説の形式としては珍しくない。箱や瓶に詰めた「未来の自分に宛てた手紙」を地中に埋めるタイムカプセルもある。
未来からの手紙といえば、エドガー・アラン・ポオ「ユリイカ」『詩と詩論』(創元推理文庫/1979・11・23)だ。この論文は、一八四八年の千年後の二八四八年に書かれ、栓をした壜に封じられて海に漂っていたところを発見されたという設定だ。奇想天外なアイデア、モチーフは、一八三三年発表の小説「壜のなかの手記」『ポオ小説全集1』(創元推理文庫/1974・6・28)が良く知られている。
夢野久作「瓶詰の地獄」『日本探偵小説全集4 夢野久作集』(創元推理文庫/1984・11・30)は、昭和三年発表の四〇〇字一五枚ほどの掌編。海洋研究所に島村役場から送られてきた一通の手紙と流れついた三本の麦酒瓶。潮流研究用の瓶が流れついたら海洋研究所に届けるようにと申し渡されていたからだ。瓶のなかには三通の手紙が入っていた。江口雄輔「夢野久作主要作品案内」(「ユリイカ」1989・1)は、作品背景として久作と息子が博多湾の竜頭岬に海水浴にでかけた事実(息子杉山龍丸の文から)をあげている。渚に漂う一本の硝子瓶を見つけた久作は、息子の前で栓をとり「博多湾の潮流検査の瓶」かもしれないとのぞいたが違っていた。ポオ「壜の中の手記」のモチーフを取り込んだと推測されるが、久作の実体験がヒントになっていたようだ。海難事故で離島に流れついた十一歳の兄と七歳の妹が、三本の麦酒瓶に詰めて次々と流していった手紙だが、救助を待つことが地獄に変わり、成長した兄と妹を悲劇へと向かわせた。
我が国におけるポオの受容は、大正期に芥川龍之介、谷崎潤一郎、佐藤春夫などに、怪奇・幻想・ミステリーを多作させ、昭和初期には江戸川乱歩、夢野久作の人気を沸騰させた。欧米でのポオの受容はどうだろう。
細見和之『「投壜通信」の詩人たち』(岩波書店/2018・3・14)は、難破船から瓶に詰められて海に流されたポオ「瓶のなかの手記」から、「投壜通信」の構造、形式を系譜とした詩人たちの足跡を追った。マラルメ、ヴァレリー、エリオット、ツェランなどの作品を「イメージを縦軸」と「現実との関わりを横軸」として考察。導かれたのは、「詩はいったい誰が書いているのか」との問いだ。「投壜通信」のリアルは、ワルシャワ・ゲットーのなかで書かれた手書き原稿を壜に詰め、収容所の地中に埋めたイツハク・カツェネルソン。一九四二年二月一〇日の日付を持つ《家のなかは寒い、私は恐れる/自分の家のなかなのに、恐怖が私に襲いかかる、》(「寒さの歌」)は、反復され、朗読され、翻訳されることで、未来へと繋いだ。
倉橋健一「はてない旅」(「はだしの街」57号/2018・5・1)では、延縄船の船倉に詰め込まれた人たちを髭面の船長が声を荒げて怖がらせている。
《タンポポ、スミレ、オシロイバナ、レンゲソウ/幼い頃のなつかしい花々の香り漂う思い出から/どこへ連れ去られるのか/あてのないはてしない船旅に/今はただできうるかぎり単調でありたいと変調する//そういえば幼ごにまつわる遠い時代/酷薄な戦さがあって街という街は廃墟に帰したが/直前になってこんなお触れが出たのはご愛嬌だった/子どもだけは逃げさせろ親子の絆をぶち切っても逃げさせろ/さてさておかげであの子もこの子も平等に孤独になるばかりだった》ここには「厄災」に遭遇したときに紡がれた記憶がある。誰かに何かを伝えようする多声を聞き取り危機を察知するのは「詩」だろうか。
 撮影:寺田 操(C)
(個人誌「Poetry Edging」№40―2018年07月01日発行―より転載)
★プロフィール★
寺田 操(てらだ・そう)詩人。編集として『幻想・怪奇・ミステリーの館』(「エピュイ23」白地社)。詩集として『みずごよみ』(白地社)、『モアイ』(風琳堂)、評論として『恋愛の解剖学』(風琳堂)、『金子みすゞと尾崎翠──一九二○・三○年代の詩人だち』(白地社)、『都市文学と少女たち―尾崎翠・金子みすゞ・林芙美子を歩く』(白地社)、童話として『介助犬シンシアの物語』(大和書房/ハングル版はソウル・パラダイス福祉財団より)、『尾崎翠と野溝七生子』(白地社)、共著として『酒食つれづれ』(白地社)、『小野十三郎を読む』(思潮社)、『尾崎翠を読む 講演編 2』(今井出版)、2018年8月に共著『宮崎駿が描いた少女たち』(新典社)を刊行。
Web評論誌「コーラ」37号(2019.04.15)
「新・玩物草紙」眼鏡/鳥瞰図/少女が増えた(寺田 操)
Copyright(c) SOUGETUSYOBOU 2019 All Rights Reserved.
|
| 表紙(目次)へ |