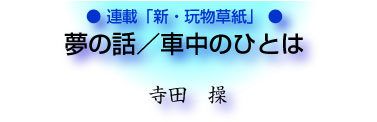|
|
|
Web評論誌「コーラ」 |
|
■創刊の辞 ■本誌の表紙(目次)へ ■本誌のバックナンバー ■読者の頁/ご意見・感想 ■投稿規定 ■関係者のWebサイト ■プライバシーポリシー |
|
<本誌の関連ページ> |
|
■「カルチャー・レヴュー」のバックナンバー ■評論紙「La Vue」の総目次 |
Copyright (c)SOUGETUSYOBOU |
|
|
夢の話 明け方よく夢をみる。たいていは断片しか覚えていないが、ときに「物語」を紡ぐように鮮明に覚えている。脳内に映像化されている箇所を書きだそうとするが、うまく表出できなくてもどかしい。ひとつひとつの場面は鮮明に思い出せるが、言語化には距離ができる。
森内俊雄『夢のはじまり』(福武文庫/1987・1・10)は、15篇の幻想小説集。トイレで洗った手先から「緑色の液体石鹸のきついにおい」が漂ってきて、早退届を書いた男。課長には「きみの姿がね、時々透き通って見えるんだよ。幽霊みたいに」と言われた。出社・退社の時間がどの日も定刻より二分と狂っていなかった彼の異変。早退して妻と息子の待つ家に戻るだけの話だが、家は迷路のような路地裏にある。三ヶ月まえから家族は眠らなくてもよくなり、奥の部屋にはリスや九官鳥やセキセイインコに変身させられた弟、妹、伯母などが騒ぐ「夢のはじまり」。十年前に勘定を踏み倒して逃げたバーの白い扉の前に立っていた「路地を左に曲がって」。瓶のなかの虫をみながら酒をのみ、どこかへ脱け出していくことを夢想する「瓶の顔」。いずれも、日常から脱け出したい無意識が引き寄せた、怖くて奇妙な夢の話。
夢見で、確かにわかっているのは、どこかで見たこと、体験したことが、断片化され、バラバラに宇宙に散り、その断片(ピース)が、別の組み合わせを求めて、離合集散。アナザーテキストとして顕れてくるようなのだ。大抵は「ああ、あれだ」と思い当たることが少なくない。
 車中のひとは 電車のなかは詩や小説の種が無造作に撒かれた不思議な場所だ。この場所でから生まれた作品を読むことも少なくない。
真壁 仁編『詩の中にめざめる日本』岩波新書610/1966・10・20第1刷)を読みなおす機会があり、ページを繰っていくと、電車の中の一コマを切り取った磯村英樹「途中」に呼び止められた。若い日に読んだときは、声がかからなかったのだが。
《いま〝途中〟だとおもっている顔が/電車に並んで腰かけている/立って吊り革にぶら下がっている/電車が終着駅へ着けば次の途中へ乗り換え/電車を下りても途中/家に辿りついても途中/飯を食うときも途中/なにかが行くさきにあるような気がして/死ぬまで途中の顔をしているにちがいない/そんな中途半端な顔ばかりが並んでいる/いまを生きている顔はないのか/見廻していると/いきなり清冽な水しぶきを浴びせられた/頭のてっぺんから足のさきまで/しゃきっとピアノ線がとおっているその女/なにかをいまに賭けようとするその姿勢》(「途 中」)
「途中の顔」には驚いた。乗り物のなかの出来事といったモチーフは特別なものではない。詩人は、車中を見廻しながら、いまを生きている顔をさがしている。彼もまた「途中の顔」をしているのだ。そこへいきなり《清冽な水しぶきを浴びせ》かけたひとりの女。心奪われた。ファムファタールだ。息をのんで見つめる目に気づいた女は、電車が止まったとき、さりげなく男の方に寄ってきた。人に押されてきたように自然なふるまいで、やわらかいからだを押しつけてきた。《あやしい燃える眼でぼくの心を串刺し》にした瞬間、すばやく財布を抜き取って去っていった。彼女はスリだったが、男は女から《燃えたついのちの火》をもらった。
吉野弘「夕焼け」『吉野 弘詩集』(ハルキ文庫/1999・4・18)の車中光景は、磯村英樹「途中」とは対照的だ。詩集『幻・方法』(1959)に収められている。満員電車のなかで若者と娘が坐っていた。その前に老人が立った。うつむいていた娘が立って席をゆずった。そそくさと座った老人は礼もいわずに次の駅で下りた。娘は座ったが、また老人が娘の前に押し出されてきた。2度目も譲ったが、3度目は席を立たなかった。《次の駅も/次の駅も/下唇をキュッと噛んで/体をこわばらせてー―。》とリアルな描写だ。先に下車した詩人はうつむいたまま坐っている娘のことが気になっている。《やさしい心に責められながら/娘はどこまでゆけるだろう。/下唇を噛んで/つらい気持ちで/美しい夕焼けも見ないで。》と。吉野弘の作品にはバスや電車のなかでの体験がいくつもある。まもなく母になりそうな若い女性が膝のうえで白く小さな靴下を編んでいる「早春のバスの中で」。出産育児の手引書を読みながら、電車の中でまどろむ若い女性「白い表紙」。電車の動きに合わせて若い母親の膝のうえで声を発する一歳ほどの男の子「或る声・或る音」。日頃わたしたちがなにげなく目にする光景である。
いま電車の中では「顔」をもたないひとが増殖している。座席でも、吊り革ぶら下がりでも、スマホをいじるためうつむいていて、どの顔にもグレーの沙がかかっている。本を読むのは少数派だ。車中で化粧する女性もちかごろではめったにみかけなくなった。もはや「顔」は「顔」であるとは言えなくなっているようにおもえる。いやさまざまな風景に溶けこんで、輪郭を消しつつあるのかもしれない。口角をあげてお喋りに夢中の中高年女性なども、顔をあげているにもかかわらず、沙のベールをかぶっているようで「会話」だけが車中に響き渡る。隣あわせた子どもづれの夫婦は、それぞれが片手で子どもの世話をやきながら、片手でスマホをいじっている。どこの国でもない、この国の電車の中の一コマ。だから、「途中の顔」でも「中途半端な顔」でも、ずらりと並んでいる「顔」をみられた時代は、まだ生きていることを実感できたのではないだろうか。
 (個人誌「Poetry Edging」№35―2016年11月01日発行―より転載)
★プロフィール★
寺田 操(てらだ・そう)詩人。編集として『幻想・怪奇・ミステリーの館』(「エピュイ23」白地社)。詩集として『みずごよみ』(白地社)、『モアイ』(風琳堂)、評論として『恋愛の解剖学』(風琳堂)、『金子みすゞと尾崎翠──一九二○・三○年代の詩人だち』(白地社)、『都市文学と少女たち―尾崎翠・金子みすゞ・林芙美子を歩く』(白地社)、童話として『介助犬シンシアの物語』(大和書房/ハングル版はソウル・パラダイス福祉財団より)、『尾崎翠と野溝七生子』(白地社)、共著として『酒食つれづれ』(白地社)、『小野十三郎を読む』(思潮社)、2016年3月に『尾崎翠を読む 講演編 2』(今井出版)。
Web評論誌「コーラ」31号(2017.04.15)
「新・玩物草紙」夢の話/車中のひとは(寺田 操)
Copyright(c) SOUGETUSYOBOU 2017 All Rights Reserved.
|
| 表紙(目次)へ |