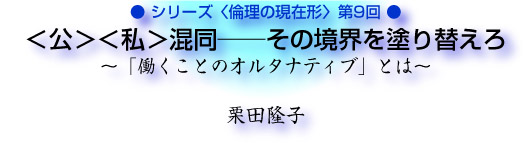|
|
|
Web評論誌「コーラ」 |
|
■創刊の辞 ■本誌の表紙(目次)へ ■本誌のバックナンバー ■読者の頁/ご意見・感想 ■投稿規定 ■関係者のWebサイト ■プライバシーポリシー |
|
<本誌の関連ページ> |
|
■「カルチャー・レヴュー」のバックナンバー ■評論紙「La Vue」の総目次 |
Copyright (c)SOUGETUSYOBOU |
|
|
|
1.まず「あの頃」の「不登校」を(しつこく)振り返る
──不登校、ひきこもり、フリーター、ホームレス、メンヘル、非モテ、自傷行為、イジメ、自殺──雨宮処凛の出世作『生きさせろ!難民化する若者たち』では、フリーターという現象を軸に、様々な人へのインタビューを行い、これらの事象をぶっ通しで考えろと促した。これが2007年。労働問題をベア闘争でも待遇の問題でもない、生存問題として捉えたところが、もっとも画期的だった。それも、「かわいそうな人」とすらみなされない立場──「自己責任」を負うべきとみなされた立場、やや古めの言葉で言えば「自業自得」とみなされた立場―から考えたことが特筆すべきことだった。
この点を、どうか、この(拙い)文章を読んでくださる方々には心に留めてほしいと思う。フリーターが「非正規雇用」という言葉に置き換わり、この事態に対し社会的な責任を担わせ、不十分でありながらも法律をも変えようとしている、2010年の、この時期において。
というのも、どうも私には「あの頃」のあの反復が起きかねない、と危惧するからだ。「あの頃」とは、私が10代の頃、不登校をしていた時期のことである。もう20年も前の出来事だ。不登校が「子どもの甘え」などという問題ではなく「社会的な問題」であり、「どの子どもにも起こりうる」という観点を確立したものの、その後「子どもの権利条約」の批准という政策的な運動へと力点が移っていった、あの一連の流れだ(※1)。結果「子どもの権利条約」(日本での正式名称は「児童の権利に関する条約」)は批准されたものの、子どもの権利が確立されたという実感は薄いまま、「虐待」だの「貧困」だのという、一見、不登校とは異なる問題が目に映る現状。そして不登校/登校という枠組みそのものを揺るがす方向、すなわち「学校」というハコ・制度・仕組み・教育内容を根本的に変革するという方向には結局、向かわなかった。確かに学校に行ってさえいればどうにかなる、という「学校神話」は解体されたかもしれない。その代わり、「スキル」「専門性」「即戦力」という剥き出しの競争原理が学校空間を跋扈し、「学校に行ってさえいれば安心」ではなく「学校に行っても不安」という、不安を感じる層の拡大を生み出した(※2)。とどのつまり、学校に行く/行かないで区別することなく子どもの権利はその選択と共に尊重され、なおかつ教育を受ける権利があるという肝心な論点がすっぽり抜け落ちてしまった。
確かに「学校に行かなくても社会には通用する」という考え方が不登校の「学校神話」を解体する一つの戦略だったのかもしれない(※3)。しかし「学校神話」は解体されたが、学校は解体されなかった、ないしは、学校が社会の競争原理に追随し、促進するものとなった(※4)ということは何を意味しているか。いかなる子どもも、人間として尊重されるという権利の徹底が出来ず、子どもの(ひいては大人の)能力を、企業社会という環境に馴致できるかどうかでみなす構造、企業の要請人員を育成する学校という構造を崩せなかったということだ。別の言い方をすれば、いかなる子どもも尊重される、という人権の可能性を信じ、具現化することができなかったのだ。当然それは大人社会の反映ということで、憲法25条の理念に沿った生活保護を受ければ「税金泥棒」といわれ、住まいを失くせば「人」としての扱いを受けられず、時に襲撃され、殺される。住民票を失えばそもそも選挙権すら事実上剥奪される。正規職員という立場でなければ社会保障を受けることが困難となる。大人の社会に生得としての「人権」を具現化させていく努力がなければ、当然子どもの権利条約だってハリボテとなる。そして大人の権利同様、「子どもの権利」と言う言葉は、精神面、心理面、経済面、健康面等々を含みこんだ上での「権利」のはずだが、法律(正確に言えば条約)はまさに有形無実となっている。不登校の活動界隈ではこの「子どもの権利条約」が大いに取り上げられたものの、日本の貧困問題においては、この条約は実効性に乏しいのか、極めて影の薄いものとなっている。
ちなみにこの「子どもの権利条約」の第6条は「1.締約国は、すべての児童が生命に対する固有の権利を有することを認める。」そして「2.締約国は、児童の生存及び発達を可能な最大限の範囲において確保する」とある。しかし、この条約がどれだけ実感を持って今の日本で受け止められているかというと、極めて心もとない。
「子どもの権利条約」の時期は不登校や管理教育の問題が世の中で取り上げられた。その前後に子どもの権利条約が国連に提出され、日本が批准するかどうかを決断する時期と重なった。政策決定の問題には当事者以外の人間の関わりうる幅が広くなる。不登校の問題という個人の精神と社会の制度が複雑に入れ込む問題はそうそうに手は出せないが(それゆえか、不登校―登校拒否は「病」という概念と関連が深く「医療」問題と密接であった。この問題の複雑さは「ひきこもり」の問題へとそのまま引き継がれ、しかも「不問」のままにされつつあるのではないか)、「法律」「政策」の分野なら分かりやすく、手が出しやすい、いやむしろ、当事者以外であっても積極的に介入できるのはこの分野だ。そうして、「子どもの権利条約」は批准された。しかし、それだけだったのではないか。
法律や、政策が無意味ということではない。しかし日本では「政策」「法律」の類の成立がその時々に浮上したトピックに積極的に取り組んでいた人々が作り出すものであり、結果その「トピック」が時代遅れとみなされれば、「法律」そのものも、忘れ去られる。言い換えればブームに便乗する人々によって法律や政策が出来上がり、そのブームが過ぎ去れば法律も忘れ去られる。または法律を変えたことで、何か一仕事済んだ気になってしまう。そうして、活動を担ってきた人間が疲弊してくるとか、マスコミが取り上げなくなるといった状況の中でブームが去れば、問題そのものが忘れ去られ、根本的な解決には絶対に至らないという恐ろしい陥穽が、今もまた口を広げて待っているのではないだろうか?
2.「恐怖」から考える
実際のところフリーターの運動で問題の核となった派遣法の根本的な改正は今のところかなり危うい。今、ロビー活動や、要望書を送っているところだが(※5)、この時点でどれだけ派遣社員(とりわけ女性)の立場が変化されるかはわからない。しかし、もしかしたらもっとも問題なのはこの時期に法律が変わらないことよりも「法律」を担う主体が、「ブーム」によって左右されてしまい、「権利」とは何か、「労働」そして、「賃労働」とは何かという根本を問う視点が、法律や政策や、そのほかの活動のなかでは軸にならず、その時期の流行や政治力学により決まる法律と決まらない法律が生まれてしまうという事態なのではないか。
この原稿は労働におけるオルタナティブとは? という観点を論じてほしいという依頼だったのだが、なぜこのような不登校の話からはじめ、さらには、活動論的なことを論じ始めたかといえば、オルタナティブを考えるという視点はそれこそ10年、20年に渡って現状に影響を及ぼし、社会を変化させることがいかにして可能かということから論じなければ、はじまらないと思ったからだ。一見「オルタナティブ」と見えたものであっても恐ろしいほどに回収され、この社会を不問のままにするということがあちらこちらで見受けられる。そうであるならば、それこそまず20年前をこの私が語りうるとすれば、「不登校」という観点は語りやすくそれと同時にこの不登校で置き去りにされた問題がフリーター、ニート……といったものへ変奏されたと感じているゆえに、この話題からはじめさせていただいた。
特に私は、この「労働」を問うはじめの「とっかかり」としては「労働が持つ暴力性」、「労働への恐怖」ということを語らずにはおれないのだが、この「恐怖」という感覚は、実は私にとってはひどく懐かしく、遣る瀬無い感覚だ。そう、それはまさに私が学校という場所に感じた感覚。これと似た感覚を30代で、再び、何度となく味わうこととなった。私自身が大学院を辞め、仕事を探し、とはいえ正社員の仕事などというものに雇われることはなかった。そもそも30も過ぎていわゆる「社会経験がない」人をいわゆる正規雇用として雇う会社は(少なくとも2002年においては)ほとんどない。いや、正規雇用どころか最初は「派遣社員」の仕事ですら回ってこなかった。エクセルもワードもろくに扱えない人間が事務職などできるわけがなく──そして職場で「教育」するという観点はなく「即戦力」として派遣労働者は扱うことが前提だからだ。とはいえ、資格がいらないとされる工場労働は不器用で、却って足手まといとなる日々。それでもなおかつ社会(=会社)というものに、生活を維持させるために入らなければいけないと感じたとき、改めて「社会」というものへの恐怖を感じた。
そう、「社会」というものは、そこに入れなければ人から責められる以上に、自分の無能力さを責めずにはいられないものだから。もっといえば自分で自分を責められるだけ、まだマシと思えるような、自分が社会に馴染みうる他者になりすましたい欲望が渦巻く状態。それはあの学校に行か(け)ない時代となんと似通っていることか。そこにうすうす気がついたので、自分で自分を責めても仕方がないと思えたが、しかし、だからこそあらためて何が問題となるのかを、今度こそ全力で問わなければならないと決意した。それはやはり自分がある程度「大人」となり、子どもの頃の不登校の時代と違い、自分の言質にある程度の「責任」が持てると考えたからでもある。自己責任とは違う責任を、逆に取ってやろうじゃないかというところから、私なりの表現がはじまった。
“「家」はやはり社会ではない、子どもとして家に居続ける限り、私はやはり社会とはどこか隔絶している、なぜなら誰かの「社会的活動」のもとに自分の生活を維持させているから、だから自立しなければならない”と私は思っていた。しかしなんという矛盾だろう。フリーターであった私は、家から出るにあたり、そもそもお金がないから金銭面で親の援助を受けたし、さらには不動産屋からの信頼もないので、結局「父の娘」として、つまり父が連帯保証人とならなければ、私は「自立」することすらできなかったのである。家を出るから「自立」なんて、まったくの嘘っぱちだと実にショックな出来事だった。その後、私は基本的には、「自活」していたといえるのかもしれないが、その間においても、私は自立したすがすがしい思いなど、味わうことはついぞなかった。というのも、そのような経緯で「自立」した手前、「社会人」「自立」という言葉の嘘くささが、私の心の中から離れ去ることはなかったからだ。
しかし実際マイホームを買った人間が、例えば「頭金」は親が出すとか、親から何らかのサポートを受けている人は、鳩山家のみならず、相当多いだろう。しかし、日本では社会的なセーフティーネットが充実していないといった社会的なメカニズムが機能しているなかで単純に「親から援助を受けるのが悪い」とは言いがたい。しかし何が許せないかといえば、そのような親からの援助を受けている人間が、かなりの多数であるにもかかわらず、「税金」で生きている人間や、ニートやフリーターといった親からの援助が際立って目立つ人間へのバッシングがこの国では根強いからだ。バッシングをする人間の相当数に対し、「冷酷だ」とか「共感能力がないのか」という言い方を私はしない。むしろ一言こういいたい。
「嘘つき」と。
きっと私自身が「自立」を目指した人間であるからこそ、この「嘘くささ」から、労働を社会を、そして己を捉え返すしかなかった。その捉え返しの方法として、もっともみっともない、情けない私自身の感情―「恐怖」(※6)という言葉を発することからしか、はじめられなかったのだ。
さてこの恐怖をもう少し言語化すると、「私は存在しないほうがいい人間だ」―この感覚。そしてこの感覚を表現するさまざまな事象は、この10年、いや20年、形を変え、姿を変えて立ち表れていくゾンビのようだ。このゾンビたちは、マイケル・ジャクソンの「スリラー」じゃないが、まさに増加し、踊り出すくらいの勢いだ。「私は存在しないほうがいい」などという言葉は太宰の小説じゃないが、どこかナルシスティックでセンチメンタルな響きさえあり、こういう感覚を面と向かって訴え出ればどこかに嘘が出てくる。だからこそ、「私は存在していないほうがいい人間だ」という叫びは、音なき悲鳴となってしまう。
そして悲鳴の変わりに聞こえてくるのは、たとえば人身事故のアナウンス。そしてそれに人々は慣れきってしまい、もはや人身事故は人々を遅刻させる要因としてしか認識されない。時折「チッ」などと舌打ちさえして。今となっては、頻度が高まった結果、自分たちの行動を足止めする以上のものとしては受け止められない、人身事故のアナウンス。人間は何にでも慣れてしまう。戦時中の空襲警報も意外とこんな調子で人々は受け止めてたんじゃないだろうか、と思う(※7)。そして自殺がもっとも多いのは「月曜日」(※8)というあたりに、労働への恐怖と労働の暴力性が匂ってくる。そしてこの例えば恐怖、困惑、沈黙から、社会構造を見据えること──もしかしたらこれこそが、社会的なネットワークや、知り合いの議員がいなくても、まずはじめられる政治的な営みではないか。
そしてこの「労働の恐怖」は主観的なものだからこそ、説明が困難であり、語っても賛否両論がつきまとうものだが、この労働への恐怖の観点は、例えば「教育」の現場関係者から語られていることが多い(※9)。教育から労働を見つめることによって、まさに構造として社会を見つめる視点を、作り上げることができるのではないだろうか。
3.<失業の権利>から労働を考える(※10)
労働の恐怖について語ったとき、その労働への恐怖をかたちづくる一つの要因として「日本では失業の権利が存在していないから」という意見が寄せられたことがある(※11)。
確かに今の日本では、まず失業給付において会社側の「解雇」と「自己都合」で分離され、自己都合退職では3ヶ月間の待機期間が設けられる。我慢して働くことが美徳であることは制度からも垣間見える。またそもそも雇用保険に入れない職種もある(※12)。
ハローワークでは、失業給付を受けられない人として「高望みばかりする人」「引きこもりの人」「主婦の人」「病気の人」などが説明に挙げられる(※13)。「病気の人」は傷病手当金の対象であるからだとしても、それ以外はいったいなにを意味しているのか。つまりは失業という「状態」に対して失業給付が与えられるのではなく、「企業」に帰属したいか否かという意志に対して金が払われるということだ。それはつまり、雇用保険というものが、人権的な見地から支払われているという意識ではなく、「会社が払ってやっている金」であり、それだからこそ、会社への恩義的な(?)意志を要請されると考えられる。
「会社勤め」だけが「労働」としてみなされるのであれば、フリーランス・個人事業主・主婦的な働き方は「労働」とはみなされにくい。会社という組織に馴染めなければ、権利はないよ、というメッセージ。やはりこれは「恐い」。事実、「個人事業主」という雇用形態は、労働基準法の遵守をすり抜ける使用者側の口実としてしばしば使われているように、「オルタナティブ」な労働を行うことが、すっぽり労働者の権利を抜け落ちさせていく現状。労働基準法等の労働三法が、基本的にこの雇用関係を前提としているのだから、非常に根が深い問題といえる。それにしても、この経験は社会というものは「承認されなければ入れない」というメッセージをどう変えていくか、ということだったとおもう。だからこそ誰かの承認、というかたちではなく、自らが社会を作っていくという試みである「フリーターズフリー」へと参加したのだ(※14)。
そう、ここで先ほど少し取り上げた「子どもの貧困」と子どもの権利問題に通じる関係が露呈される。そのような事態に対して「個人事業主ではなく、実質上は雇用関係にある労働者だ」と主張することは、一定必要なことであろう。しかし、そもそも「雇用関係」以外にある労働形態が権利の外とされることをも問題にする必要がある。そこでまず明確にしなければならないことは、「労働」をどのように定義するか、だ。そしてその定義に従い、いかなる社会を構築していくかを明確にしなければならない。
たとえばヨーロッパでは労働は苦役とみなされるからこそ「時短」こそが公共の福祉と考えられる。他方アメリカでは労働が「チャンス」であるからこそ、チャンス増大の契機として規制緩和・労働の流動性という発想にいたる。日本ではどうだろう。おそらく「労働」は「職場に滞在すること」「職場を居場所とすること」なのではないか。とくにホワイトカラーでは、会社という場所に滞在することが労働なのではないか。あたかも「家」のように(それゆえか女性は主婦的な位置を要求され、賃金も低くなる……)。しかも経済的な発展を生むと考えられた職場が「家」となることこそが、いまだに日本の職場の「理想図」なのではないか。リストラという名の解雇はあるものの(あたかも勘当?)、雇用の流動化ということが起こりにくいのは、まさに会社の理想が「家」だからではないだろうか。勘当はしても、いろいろな人を家族にはしないという発想。だから「家」を転々とする日雇い的な労働は「労働者」として認識されにくく、短時間パートは職場という家に長い時間滞在していないから、やはりダメなのである……。
4.<公><私>混同──その境界を塗り替えろ
「労働」こそ「居場所」であり「家」であると、敢えて定義するというのであれば、それもよい。おそらく、日本では労働することは自明のものであり、労働とは何かということを明確に定義してこなかった。そうであればこそ、ここで意図的に、「労働」こそ「居場所」であり「家」であると定義することに意味はある。労働が家のような居場所であるならば、逆に「家」とは何かを問うことが出来る。「労働とは何か」を考えていって「家」をむしろ考えていかざるを得ないという展開のほうが、私にはどこか痛快に感じる。むしろこの「家」から考えていくというやりかたでまさに、<公><私>混同、その境界を塗り替えてゆきたいのである。それは「自立」という言葉に強迫的になっていた私自身の、振り返りの作業でもある。不登校にしても「家ではなく「学校」に行く」ことが要求され、仕事にしても「家にいては生活が成り立たない」ということで職場へと心を向けた。もちろん、そのような状態で「家」にいたところで、悶々とするだけなのだが、私としては「家」という場所に向かい合うことで、「労働」の概念を変えたいのだ。「家」に入る「女」という意味の「嫁」ではなく、「家」と向かい合い、対峙する「女」としての「嫁」に私はなりたい。
たとえば、日本は職場という「家」にしても、「家庭」という「家」にしても、どちらにしても賃金としては高く見積もられない「しごと」(家事労働・介護労働・感情労働・性労働)を、どう位置づけていくかという方向に向かいあうことだ。ここでおそらくもう一つのテーマとつながる。つまり「能力」を承認してもらうことで「仕事」を得るのではなく、「生存」を軸に、「生存」に必要な仕事を担うゆえに、まさに生きていけることができる社会へと変えていくこと。人権という概念が、条件づけられるものではなく、まさに憲法に書かれた生得的な人権を具現化させていく方向で考えていくこと……。
上野千鶴子氏がかつて『家父長制と資本制──マルクス主義フェミニズムの地平』(岩波書店)のなかで「労働概念の解放」を訴えていたが、この労働概念の解放とは(ここからは上野氏の議論ではなく、私の論となるが)「専門性が高い」からこの仕事に価値があるのだと訴えるのではない。生存に必要な仕事への評価がなぜ低いのかという問いへと転換することなのではないか。つまり、専門知ではない暗黙知(tacit knowing)がなぜ軽んじられるのかと問題提起しなければいけない。単純労働・肉体労働・感情労働は専門的だから価値がある、のではなく、生命を生み出し、生きていくのに必要な労働に対し、なぜ安値をつけるのかと問い、新しい価値観を生み出さねばなるまい。オルタナティブな労働が真に機能するとは、まさに現状の「労働概念」からの解放、同時にその変容を、個人のレベルから法のレベルに至るまで透徹させていくことではないか。この労働概念の変容という「しごと」の見取り図を作り、もくもくとこなしていくことが、私のこれからの「しごと」となるだろう。そしてこの「しごと」に(いわゆる反貧困や労働問題の「ブーム」が過ぎ去っても!)関心を持ってくださる方がいらっしゃれば、幸いだ。おそらくこの「しごと」こそ「一人では無理、力を貸してほしい」(※15)ことだから。
★プロフィール★栗田隆子(くりた・りゅうこ)1973年東京生れ。大阪大学大学院文学研究科博士課程中退。有限責任組合フリーターズフリー組合員(「フリーターズフリー」2号の編集責任を担当)、女性と貧困ネットワーク呼びかけ人。『子どもたちが語る登校拒否』(世織書房)に10代時に寄稿。その他『フリーター論争 2.0 フリーターズフリー対談集』(フリーターズフリー編・人文書院発行)。共著として『1995年 未了の問題圏』(中西新太郎編・雨宮処凛ほか・大月書店)。2010年4月に『フェミニズムはだれのもの? フリーターズフリー対談集』(フリーターズフリー編・人文書院)を刊行。その他雑誌・学術誌・新聞等で論考を発表。
HP:VITA PUELLAE Web評論誌「コーラ」10号(2010.04.15) 〈倫理の現在形〉第9回:<公><私>混同──その境界を塗り替えろ〜「働くことのオルタナティブ」とは〜(栗田隆子) Copyright(c) SOUGETUSYOBOU 2010 All Rights Reserved. |
| 表紙(目次)へ |