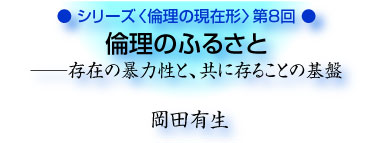|
|
|
Web評論誌「コーラ」 |
|
■創刊の辞 ■本誌の表紙(目次)へ ■本誌のバックナンバー ■読者の頁/ご意見・感想 ■投稿規定 ■関係者のWebサイト ■プライバシーポリシー |
|
<本誌の関連ページ> |
|
■「カルチャー・レヴュー」のバックナンバー ■評論紙「La Vue」の総目次 |
Copyright (c)SOUGETUSYOBOU |
|
|
|
はじめに
以下では主に、社会のなかでの暴力性や権力性といったもののなかで、非常に限定されたもの、個人的なものだけについて考えるだろう。
それは、基本的に個人によらない暴力(権力)は検討されないということと同時に、個人が他の個人(または生き物)に対して行使するのでない暴力についても検討されない、ということである。端的に言えば、国家による暴力や、革命やストライキなどの暴力・権力は、その是非を含めて論の直接の対象にはなっていない。
そこで、この個人的なものとは、私的なものといってもよく、それだけが「倫理」の名において問題にされるということには、それ自体権力の濃い影を見てとることが(おそらく)できるであろう。
だがともかく、ここではそのこと(個人的な暴力性・権力性)について考えることにする。
① もどかしさの意味
土井敏邦監督によるドキュメンタリー映画『沈黙を破る』の冒頭に次のような場面があった。
イスラエル国内で占領地における軍事支配の実態を告発する活動をしている元兵士のユダヤ人青年が、あれはオリーブの木なのか、枝に足をかけて実を採ろうとしながら、カメラに向かって活動を通じて人々に何を伝えたいのかを静かに語っている。彼は、「もちろん、(暴力の)被害者は誰よりもパレスチナ人たちだ。それは言うまでもない」と前置きしながら、「しかし、自分たち(元兵士)も別の意味で、やはり被害者なのだ、ということを伝えたい」というふうに言うのである。
この場面を見たとき、私は、彼が言葉を前置きしたところに、とても息苦しいもの、もどかしさを感じた。それは、自らが加害者として行使した暴力を振り返って、その社会的な構造を自覚し、それを変えていくために当事者として発言しようとする際に突き当たる、息苦しさだろうか。
加害者である側が、「自分も被害者なのだ」と言うことには、何か後ろめたさがつきまとう。
それはひとつには、そう言うことで自分が免責されたがっていると思われることへの不安があるだろう。
だがそれは、この後ろめたさの主たる内容ではないと思う。
むしろ、こういうことではないか。
自らが行った暴力行為について告発することで、暴力が生産されつづける現実を変えようと決意するような人は、「自分も被害者なのだ」という言明が、「真の被害者」とも言うべき、自分が傷つけ圧迫を今も加えているだろう人たちの「被害」を相対化してしまうこと、また、その人たちの軽視というよりも無視されている生きた存在を、いっそう社会のなかで見えにくいものにしてしまうことへの危惧に、敏感である他ないだろう。
「自分も被害者なのだ」という言葉が、自分の意図に反して、(イスラエルのユダヤ系市民という)マジョリティーの立場にある自分個人の行為の免責につながり、他人が被った暴力の事実が、また暴力を振るわれ今も同様の状況を生きている他人の生の現実そのものが、その自分の無防備な発言によって社会のなかで隠され、いっそうその人たちが傷つけられてしまうのではないか。
そうした危惧を持つだろうということである。
この危惧のゆえに、そうした現実を隠蔽する仕組み、暴力を受けつづけている他人の存在を見えにくくする仕組みに抗うように、「もちろん、(暴力の)被害者は誰よりもパレスチナ人たちだ。それは言うまでもない」と彼は決まって前置きせざるをえないのである。
「私も被害者だ」と言って構造を告発することによって、かえって自分が暴力を加えた当の人々の存在が希薄にされてしまうなら、それは構造の維持に手を貸すことになる。そのことに苛立ちながらも、それを恐れて口を閉ざすなら、いっそう「沈黙」を強いるものに加担することになるから、それでもなお構造に関して述べざるをえない。それは、「私も……」という形をとることになる。ここに息苦しさがある。
だがこうした葛藤が生じる根底には、他人との関係によって構成されるはずの、自分の「あるべき生」が誰かに奪われている、という怒りがあるのではないか?
構造を告発する自分の言葉、それは同時に、構造のなかに組み込まれて他人に暴力を振るうことを言わば強いられていた自分の生と身体の不快や苦しみを表明し、それを支配してきた不当な力を告発する言葉(叫び)でもあるはずだ。
私(書き手である自分)は、ここで賭けられているものが、不当に他人から隔てられ、かすめとられたその人(加害者)自身の「あるべき生」であるような気がし、それに共感をおぼえているのである。
ここで思い浮かぶのは、加害者である元兵士の生や身体の現実性は、いわば被害者である他人の存在の側から照射される(与えられる)のではないか、という考えである。
自分が暴力を振るったときには、兵士の生には現実性はなかった。彼(彼女)の生がそれを獲得するのは、自分が他人に不当な暴力を振るったことを自覚して、告発(告白)の行為をはじめるときだ。その困難との葛藤のなかで、はじめて自分が失っていたもの、あるいはそもそも一度も獲得されてこなかったのかも知れない貴重なものが、彼(彼女)の前に開かれる。
要約すれば、他人との倫理的な関係の意識(自己の暴力性の自覚)より前には、私には生も身体も所持されていなかったのではないか(だが、その後私は、それを「所持」するのか?)。
暴力に他ならなかった他人との関わりを、構造に反して意識化し告発する営みのなかで、私ははじめて何かを見出し、接続する。そう言えはしないか?
だがさらに、こういう問いが浮かぶ。
構造に由来するこうした事態のすべては、それらが私が(私の)被害者であるこの他人との間にもった関係の喪失(したがって私の身体性の喪失)である以前に、まず他人自身の存在の否定につながりかねないものであるからこそ、許しがたいことなのではないか。
それは、真に重要なものは、この他人(私ならざる者、他者)の側にこそあると、私には感じられているということだろう。そのこと自体が、私が生きている現実性だと、私には思われているのではないか。
だとすると、私はここで、果たして何かを「取り戻そうと」あるいは、「獲得しようと」しているのだと、言ってしまってよいのだろうか?
こうしたことについては、ずっと後でもう一度触れる。
ところで、この自分(書いている私自身)の場合にはどうだろうか。
私は子供の頃から、弱者に対するいじめや虐待のようなことをしてきたし、逆にされてもきた。今もそのような構造から無縁になったわけではまったくない。
私が「倫理」に関心を持つのは、上に書いたような「私の生の現実性」を取り戻したい、ないしは創り出すことで自分の生らしきものを生きていきたい、という願望があるからだろう。
そう願いながらも、私の暴力の被害者である、人や生き物の存在は、どのようなものとしてあるだろう。その存在は、少なくとも、私にとって以前よりも大切で身近なものとなっているだろうか。
そうなっていないのなら、私はなすべきことを行えていないのだ。
② 部品化される身体と生
映画『沈黙を破る』をめぐって、もう少し続けよう。
映画のスタッフは、海辺の町ハイファの近郊に住む、やはり告発をつづけるある元兵士の両親を訪ねる。兵役経験のある父は息子の考えと行動を兵士にあるまじきものとして厳しく批判するが、教師でもある母親は、占領地という特殊な環境で暴力の体験を経ざるを得なかった息子の境遇を気遣う発言をする。
だが、この両親のインタビューのビデオを見た息子は、父と母とは、違うようだが実は同じ事を言っているのだと、強く非難する。この映画のなかでも、ひときわ印象的な場面のひとつである。
息子は、おおむねこのように言うのだ。
母のような人は、つまり一般にイスラエル市民(概してユダヤ系の)はということだが、「国内」に自分たち市民の平和な日常があり、占領地には若者(兵士)たちが暴力の行使を強いられるような特殊で過酷な現実がある、というふうに考えている。つまり、自分たちは平和のなかに居て、占領地の現実や暴力とは無縁であり、息子(娘)たちだけが非日常の状況下で暴力の行使に追い込まれて、その罪を背負っているのだということを痛ましく感じているのだ。
だが、それは違う。市民社会の平和な日常は、占領という現実のひずみを暴力で抑え込むことによって維持されているのだ。「自分の姿を鏡に映して見るべきだ」と青年は叫ぶ。親の世代の者たちをはじめ一般市民は、自分たちが「平和な日常」と思うものを守るために、兵士たちを占領地に差し向け、暴力的な支配の実行を強いている。つまり、真に占領地でパレスチナ人たちに暴力を振るっている主体は、「平和な日常」のなかに居て、息子(娘)たち(現場の兵士)の苦悩に心を痛めている市民たちなのだ。なのに、彼らの多くは、そのことを自覚しようとしない。
そのことへの怒りを込めて、この元兵士の青年は言う。
「私たちは、あなたたちの拳だったのだ」。
この場面には、現実に暴力を振るわざるをえない立場(現場)に置かれた人間と、それを意識せずに誰かに強いることによって安定を享受している立場の人間との対立、前者による後者への告発、抗いが示されている。
この青年は、両親の自分に対する眼差しのなかに、国家や社会が人に他人への暴力を強制する構造のあらわれを見出して憤っている。
そこでは、一方である人々は意識せずに(自分の子どもを含めた)若者たちを暴力の現場へと差し向けることで自分の日常と国家のあり方との同一性を確保し、また一方でその若者たちは生きた隣人としての具体性を消去されて攻撃か支配の対象としてしか眼前に現れなくなった弱い他人たちに暴力を振るうことで、マジョリティとしての自分の力を自覚し、やはり国家や社会との同一化に安心感を得る。
他人の存在にせよ、自分の姿にせよ、国家や社会によって「見えぬことにせよ」と指示されたものを、その通り見えないものとして扱うことによって、「自分の生から遠ざけられている」という個人の虚しさや不安は、暴力・排除・否認というメカニズムのなかで処理されて、構造のなかに回収される。
もう少し詳しく言うなら、国家や資本などが権益を確保するのに都合のよいような暴力・排除の行使のために、この「虚しさや不安」を埋めようとする暴力性が動員されるのである。つまり、私の身体、情動のようなものが、国家や資本によって盗み取られて(寄生されて)使用される。
この映画の青年は、自分が国家や支配的な社会のあり方(その重要な要素は近代的家族という装置だろう)という「大きな物」の部品(「拳」)とされ、その「大きな物」の維持のために不可視とされた人たちへの暴力を再生産していく、その構造から出ることを、両親に、市民に、また観客である私たちに呼びかけているのだ。
自分が他人に振るっていた暴力は、それがただ暴力であるからというだけでなく、自分の心や身体が知らぬ間に何かの部品のようにされることで行使されていた暴力であったがゆえになおさら忌まわしいと感じられるのであり、暴力といえばより根本的な暴力はその「部品化」する構造であるというべきではないか。この構造によって、人間同士のすべての関わり、接触は、生の実質を奪われてしまうかのようだからだ。
いや、それは暴力というよりも、権力による暴力の簒奪(転回)ということであり、権力が私の身体や情動を乗っ取ることによって、私に自他の身体や生活の破壊を強いているのである。
この青年のように、自分の姿に真に気づいた人は、この構造から脱そうとしてもがき始める。それは時に、自覚なく自分に他人を殴る「拳」となることを強いた(ときには身近な)人々への、怒りを込めた呼びかけとならざるをえない。
だが怒りの呼びかけによって、彼はその呼びかけている当の家族や友人、同僚たちとの、生きた関係を回復しようともしているのである。
自分が帰属してきた集団や社会(それは自分のマジョリティとしての特権を保障してきた実体でもあるわけだが)に対する、この青年のような告発は、その仕組みにしたがって他人を排除したり圧迫してきた自分の存在を捉えなおすと同時に、家族や隣人たちとの関係を、身体と拳というような、相互に手段としてだけ捉えるような関わりでなく、そこから脱する生きたものとして見出そう、奪い返そうとする行為であろう。
ときには怒りを含んだ呼びかけから始まる、そのような関係性の構築こそが、私と他人(他者)との仕組まれた収奪的な関係の解体を可能にするはずだ。
ところで、こう書いている私自身は、そうすることで、自分がそのなかに意識せずに身を置いてきた暴力の構造に本気で向かい合い、他者に暴力を加える立場から脱する努力を、果たしてしてきただろうか。
自分に関して(ここでは、私が自分自身や他者に加えてきた多大な直接的暴力への問いは脇に置いて)、さしあたってひとつ言えることは、眼前の他人との関係に制限を加えた方が、つまりはその関係が自分の特権や利益を構成している枠組みを壊さないようなものに制限しておいた方が、私にとって有利だと感じられるような意識のなかで生きてきた、ということだ。
ここでは、私の利益に合致しないようなあり方を他人が示すこと、そのようなものとしての他人(他者)が私との現実の関係の場に登場することは、出来る限り忌避されることになる。
他者は私の利益を保持する枠組みに合うように切り取られているわけだが、ところでこの「私の利益」なるものは、実はもともと私には属していないことを知るべきではないか。
私がその枠組みのなかにとどまること、それも他人への暴力の行使、迫害的な無視という手段によってとどまることは、私ではなく、枠組みにとってこそ利益となる。この私でないものの権益のために、私は眼前の他人の生きた存在を「見えないもの」のように扱い、あくまで手段としてだけ利用するという、根本的な暴力の行使に差し向けられている。
これが、私と周囲の全ての人たちとの基本的な関わりのあり方だ、ということではないか。
それなら、私が生きている日常は、眼前の、あるいは近隣の他人たちを生きた存在としては「見えないもの」として扱うことによって、国家や大きな力の権益に、私が奉仕してしまっているような日常である。
③ ヴェーユの「不幸」と「自己放棄」
社会や国家とも名指せる大きな力が人間を支配することによって生み出される人間の悲惨、その支配の構造のなかで「見えないもの」のようにされた人たちに容赦なく差し向けられる暴力について、シモーヌ・ヴェーユほど考えぬいた思想家は稀だろう。
彼女は、社会の権力の構造のなかで「見えないもの」とされ、自他による否定(侮蔑)と暴力を集中的に被る対象とされていく人々の状況を「不幸」という言葉で捉え、それについてたとえば次のように書いている。
不幸のもう一つの結果は魂の中に無気力という毒を注入して、少しずつ魂を不幸の共謀者にすることだ。だれでも十分に長く不幸だった人には、自分の不幸との一種の共謀関係がある。この共謀関係はその人が自分の運命を改善しようとするすべての努力につきまとう。それはその人が不幸から解放される手段を探すのを妨げ、ときには解放を願うことまで妨げる。するとその人は不幸の中に住みついて、人々はその人が満足しているのだと思うこともある。さらにこの共謀関係は、その人が心ならずも解放の手段を避けて逃げるように、その人を押し進めることがある。その場合この共謀関係はときどき滑稽な口実におおわれている。不幸からぬけ出した人でも、魂の底まで永遠に傷つけられていれば、まるで不幸がその人のなかに寄生虫のように住んでいて、思いのままにその人をみちびいているかのように、もう一度不幸の方へ押し進めるものが残っている。ときどきこの衝動は魂が幸福に向かうすべての動きに勝ってしまう。もし不幸がある恩恵の結果によって止んだときには、それが恩恵をあたえてくれた人への憎悪をともなうこともある。これは一見説明のできない粗野な忘恩の行為の原因になる。(「神への愛と不幸」より 『神を待ちのぞむ』春秋社、p.112、2009年) ここでは、ひとつのことに気づく。
それは、(②で書いたこととは違って)ここでは何かにとりつかれ寄生されているのは、他者に暴力を振るう加害者ではなく、その暴力の被害者である「見えない」存在というべき他人たちである、ということだ。このとりつかれ寄生されている状態のことを、ヴェーユは「不幸」と呼んでいるのである。
つまり「不幸な人々」は、何かにとりつかれる(寄生される)ことで国家や社会といった器官のなかに組み込まれているのではなく、逆にそのことによって社会や権力から排除されているわけである。
すると「不幸」は、必ずしも権力という地上のものに属しているわけではないことになる。これは、非常に重要な点だが、後で立ち戻ろう。
ところで、上のような「不幸」についての描写は、蔑視や暴力の被害者に対する捉え方として、ネガティブにすぎるのではないかとも思われるだろう。だが、ヴェーユにとって、「不幸」という概念の核心は、社会的な排除にある。彼女が問題にしているのは、われわれによる社会からの排除が他者に何をもたらすかということであり、したがって他者を排除しないですむような社会性を創出することがいかにして可能か、ということであるはずだ。
だがそうして創出される社会は、すでに「われわれの社会」ではありえないだろう。(排除する側である)「われわれ」とは、実は(たとえば)国家という寄生者が永らえるための器官でしかないからだ。
ヴェーユは、人間を捕らえて苦しめるものである「不幸」を、しかし人間が神の秩序に近づくための貴重な契機として肯定的にも捉えるのだが、ここでは当面、上に引用した文から次のような意味を読みとっておきたいと思う。
私(たち)は「不幸」にとりつかれ支配されているかのような人々を、「非人格的」(アンペルソナル)な状況にある存在と見なして、そこから「解放(救済)」しようと考えるが、それは当の相手の憎悪や反発を招くことがある。それは、私に「一見説明のできない粗野な忘恩」と感じられさえする。
だがそのように感じられるのは、他人を「不幸」から解放しようとする私(たち)の人格的な考えの「正しさ」が疑われていないから、その行為や意図の権力性が批判の対象になっていないからだ。
言い換えるなら、私が「不幸」の外に居て「人格」を保持しえているということ、「人格」という(社会的な)鎧を身にまといえているということの権力性と暴力性が自覚されていない(注1)。
権力の場の外で不幸な人に関わろうとするなら、それは私の(鎧の)「自己放棄」においてしか可能ではない、とヴェーユは述べる。
「名もなく、誰も知らない」、存在を気づかれることもなく、気づかれたとしても数分で忘れられてしまう、そのような他人と関わるには、私は人格的な私を「自己放棄」し、「自分が縮小することを受けいれ」る以外にない。この出会いは、純粋なものであるならば、必ずそのことを私に要請せずにはいないはずだという意味のことを、ヴェーユは言うのである。
そのときにだけ、私は「人格」という権力の仕組みの外部で、この仕組みによって見えないものにされてきた他人を見出し、その人に関わって共に生きる可能性を見出す。言わば、「見殺し」のシステムの外で、他人に接続できるのだ。彼女はそう言っているように思える。
ところで、この「自己放棄」という言葉は、もちろん人格という鎧からの解放を意味しているのだろうが、それにしても生に対して否定的なニュアンスを持っていることは否めないだろう。
④ 「不幸な人々」とは
ここで、ヴェーユの言う「不幸な人々」とは、いったい誰のことであるのかを、よく考えておこう。
こうした思想を、ヴェーユは工場での労働の体験のなかで培ったことが知られているので、具体的には「不幸な人々」とは大工場で働く底辺の労働者などを指すものと考えられよう。
だが大事なことは、それがどのような属性の人を指すかということよりも、むしろ私が現実に、自分よりも弱い立場にあるさまざまな他人を「不幸な人々」にしているのだ、という事実の方である。
ヴェーユが常に見すえていたのは、私が身にまとっている社会的な鎧が、いわば社会のなかで見えない存在、叫びを聞かれることのない存在としての「不幸な人々」を、必然的・不可避的に産み出しているという現実である。
窓ガラスが目に入らない人は、自分が窓ガラスを見ていないということを知らない。(「われわれは正義のためにたたかっているのか」より 『ロンドン論集とさいごの手紙』勁草書房、p.49) 私にとって、目の前の人間が、尊重されるべき生きた存在と見なされず、また扱われていないとき、その人は「不幸な人」である。それが誰であっても。
言い換えれば、目の前の人を「不幸な人」、「見えない存在」にしている、そしてその他人に(意識していなくても)暴力や圧迫を加えて恥じないでいる、私のこの精神の状態、生き方、それこそが問われるべきことであり、脱ぎ捨てられ、打ち壊されるべき何かである。
ヴェーユはその「何か」を「人格」という語で、また「注意力の欠如」という語によって示すのである。
⑤ 弱者攻撃のメカニズム
ところで、こうした(「人格」とも呼ばれる)特権の鎧をまとった人々の暴力性について、「諸国民」あるいは「国民政党」という鎧を有する人々という重要な事例をめぐって、ヴェーユは次のように喝破している。
その党員がもし突然血と肉をもった人間、あるいはたましいをもった人間、要するに集団の一部分以外のものにまいもどるとしたら、その時こそ、あの保護、あの甲冑を失ってしまう。しかし、善悪を超越するという特権はきわめて貴重なものであるから、永遠にその特権を選んでしまった多くの男女は、愛、友情、肉体的苦痛や死を前にしても、頑固にその態度を変えようとしないのである。 ここには、恐ろしいことが語られている。
私の暴力が、弱者へ、不幸な人々へ向けられるのは、私が特権を享受しているからこそ、(ここでは党員や国民という)特権の鎧を「高い犠牲をはらって獲得した」からこそである、という。一般に人は、自分の力や特権を確かめるために他人を攻撃しようとすると言えるかもしれないが、そこにはもう少し込み入った心理的メカニズムがあるということだ。
主観的には、私が犠牲者であるということのひとつの意味は、私が「愛、友情、肉体的苦痛や死」といった生の具体性を断ち切ることによって、この特権的な鎧を身にまとっているということ自体である。その断絶や断念を、私はどこかで不当なものであると感じていて、それに対する代償を求めている。その代償として、私は弱者を攻撃することで自分の特権を確認し、自分のはらった犠牲が価値あるものであること、言い換えれば自分が特権のなかに留まりつづけることは自分にとって不当な(理不尽な)選択ではないことを納得しようとしている(また国家は、攻撃によって各人にそのことを納得させようとする)。ヴェーユは、そう言っているわけである。
そこには、弱者がおうおうにして(鎧をもつという)「高い犠牲」をはらっていないように見えるという、特権者の嫉妬や反感が関与しているかも知れない。
いずれにせよ、「鎧」を手離すことをしないままに、不当さを納得しようとするなら、その方法は、このような弱い(特権の外の)他人への攻撃ということ以外にない。そして国家にとっては、国家自体の権力を損なわない形で国民(市民)たちのフラストレーションを解消させるには、弱者(他者)攻撃を行うよう仕向けることは理に適った手法である。
そのように読める。
ここまで来て、思い出されることがある。
それは、冒頭に書いた、『沈黙を破る』に出てくるあの元兵士が言った、「私も被害者だ」という言葉である。
同様の訴え、叫びを、あの映画に出てきた何人かの元兵士たちの言葉のなかに感じ、私はそれを、「自分は国家や社会による犠牲者だ」という意味で言われたものと解釈した。そしてそこに、あるべき己の生を奪われているという思い(怒り)を感じとって、共感したのである。
だが、自分自身を何か大きな構造の犠牲者(被害者)であると考え、自分が本来なら所有していたはずであるのに不当に奪われてしまったもの(生、世界)を想定するということ、その気持ちのなかには、自分の意図を越えた情念のようなものが潜んでいるのではないか。
自分が弱者である他人に対してふるった暴力のなかに、その情念があったかもしれない。それは自分のなかに、常にあるのかもしれない。
自分は犠牲者(被害者)であるという考え、不当に奪われた私本来の生がどこかにあるはずだという思いが、それに対する代償を当然のこととして求める気持ちを生み出し、それを埋めようとするかのように、自分の身体が弱者への攻撃に駆り立てられていく。
その記憶が頭をよぎるからこそ、暴力の加害者であった者は、「(暴力をふるった)私も被害者だ」と言う時に、不安を感じて口ごもるのではないか。
だとすれば、ここにはもうひとつの、さらに根深い罠が直感されていることになろう。いわば、権力構造の解体に向けられるべき暴力が、生にまつわる「不当さへの代償」という(人格的な?)要素を挿まれることによって、権力に乗っ取られ変質してしまう、というような。
⑥ 倫理の発見
ヴェーユの考えでは、特権の鎧が他者の存在を私から消し去ってしまう(見えなくしてしまう)仕組みは、私がこの世界における生について抱く「債権」の観念と関係がある。
自分から何かが出て行くたびごとに、わたくしたちは少なくともそれと同等のものが自分にかえって来ることを、絶対に欲している。そして自分がそれを欲するから、それには権利があると信ずるのだ。わたくしたちの債務者はすべての人、すべてのもの、宇宙全体である。わたくしたちはすべてのものに対して債権を持っていると信じている。わたくしたちが持っていると信ずるすべての債権は、いつも未来に関する過去からの想像上の債権である。これこそ放棄すべきものなのだ。(「主の祈り」について」より 『神を待ちのぞむ』p.213) つまり、私はこの世界(宇宙)の全てについて債権を持っていると、はじめから信じている。この根本的な思いが、人が(たとえば国民というような)特権を自明のものと捉えてしまうこと、その特権(鎧)に同一化することで、それを有しない人々を自分の視界から消し去ってしまうことを、可能にしているのである。
彼女が目指すのは、己が消し去ってしまった人々を再び見出し、つながるために、この鎧を自明のものと考える枠組みから(「放棄」によって)ぬけ出すということであり、そのような枠組みを解体する、打ち壊すということであろう。
それは社会的・政治的な構造をめぐる戦いであらざるをえないが、そこに終わるものではありえないのは、また言い換えれば永続的にそこにとどまり続けるしかないものであるのは、この戦いが本質的には「自分には生についての権利(債権)がある」という気持ち、「私は不当に生や世界を奪われている」という気持ち自体が孕んでいる権力性からの解放を目指すものだからである。
不当に奪われている何かがあるのだが、それは私に帰属するものではありえない。むしろ私に帰属するものであるとしか考えられないことが、不当さの核心である。私は、この不当さに対してどこまでも戦う。だがそれは、私個人が感じている不当さを、他人や世界に向って突き破るがために、戦うのである(しかし、そのとき賭けられているものは、いったい誰の生だろう?)。
やや異なる視点から、言い換えよう。
私は、「債権」にもとづいて自分の生を捉えている限り、つまり自分の生を最終的に自分に当然(あるべき本来の姿で)返還されるべきものとして考えている限りは、他人との関係に向って自分を開いていくことが出来ない。
それは、この考え方においては、私は現在の自分自身を肯定していないからだ。「あるべき生」を想定するということは、現在の自分自身の生を、何らかの意味で「あるべきでない」ものを含んだものと規定することを意味する。
生の「債権」を手放せずにいる者は、結局、自分自身を肯定していない、許せていないのだ。このことから、他人への理不尽な暴力が、さらに生み出されていく。
「債権」の思考からの解放とは、現在の自分の生(身体)に対する根本的な肯定を目指すものであるといえる。
ここに、ヴェーユの思想の、もっともポジティブな意味を見ることが出来るのかもしれない。
脇道にそれるようだが、実際、私自身が子供の頃から現在までに振るってきた、他人や動物への虐待的な暴力や支配を考えてみると、その根には、自分自身の生についての「不当さ」の感情から脱却できていないということ、それゆえに自分自身の生と身体を許せずにいるが故の残忍さというものに、気づかざるを得ないのである。
この「不当さ」(債権)の情念こそ、他人を「見えない」ものにし、社会的に弱者(鎧を持たないもの)と指定された対象への暴力の行使を私に容易にさせている、主たるものではないだろうか。
さて、こうした考えを踏まえると、私と(他人である)「不幸な人々」との関係も、別の角度で捉える必要が出てくるだろう。
人はときとして、自分がひそかに、もしくははっきりと実感している、生にまつわる「不当さ」を、他人である「不幸な人々」の姿に投影し、その不幸を我が事のように憤ったり悲しんだりする。
それは、他人の生に関心をもつ糸口としては意義のあることだが、同時に投影することによって、その人の実在を奪っているという側面もあるであろう。つまりそれもまた、「不幸な人々」を産み出すひとつの仕方だということになる。
ヴェーユはもちろん、こういう権力性も退けようとするだろう。
そして、そうした態度こそが、倫理的と呼ばれるべきものではないだろうか。
だとすれば、私は「倫理」という言葉を、これまでよく理解できていなかったのだ。権力の構造からの徹底的な脱却の戦略としての、倫理というものを。
ここで、先に③のはじめに引用した、「神への愛と不幸」の一節を思い出してみよう。
ヴェーユは、人が何かにとりつかれることによって「人格」を奪われ、社会から排除されている状態を、「不幸」という言葉で呼んだのだった。
この人間にとりついていたもの、寄生していたものとは、実は絶対的なものである神である。人(私)は、この絶対的なものにとりつかれて「人格」を失うことにより、他人を侵し支配する権力の磁場から離脱する。
私は、生と世界に対する債権の放棄を通してはじめて、(神という絶対者の力を通じてだろうが)自らが「不幸な人々」を産み出してしまう仕組みの外に出ることが出来るのである。
ヴェーユが「絶対」を追い求めつづけたのは、目の前の他人の存在を、権力の作用からあくまで遠ざけておきたいと真摯に願ったからなのであろう。
倫理とは、そうした素朴な願いの別名なのだと思う。
⑦ 倫理のふるさと
しかし、ここで付言しておきたいことがある。
ある人が、目の前の人の不幸な存在に気づき、共感すると同時に、そこに自らの思い(怒り)を投影するとき、それはなるほど権力の罠に落ちることではあるが、つまり他人を別様の仕方で「不幸」のなかに呪縛する危険と暴力性を孕んだ行為ではあるが、しかしここには、無視できないひとつの力があるはずだ、ということである。
自らの権力性と暴力性に気づいて、少しずつ倫理と孤独に目覚めながらも、人は他人との埋められることのない距離の克服を、断念するわけにはいかない。
ヴェーユの願い、「倫理」なるものが要請されたのも、元来はこの距離の真の克服(同一化ではない)が求められたが故ではなかったか。
『沈黙を破る』の冒頭に登場したあの青年は、「私も被害者だ」と口にすることの権力性と暴力性、それが自分が暴力を振るい今も圧迫しつづけている当の人の存在をいっそう「不幸」なものにする危険を自覚しながらも、(自己を含む)構造への告発の言葉を発することを選んだ。
それは、その行為だけが、私が他人と真に関わって生きる場所を開く力を持っていること、暴力と沈黙を強いるような構造から身を解き放つことで私の生存の可能性を特権の外側へと広げ、同時に他人の私への信頼を可能にすることで他人の生存をわずかでも支えうるものであることを、信じるが故だろう。
他人と私とが共に生存する場を切り開くことに対するこの信頼、あるいは権力を踏み越えて他者と共に生きることへの欲望こそが、権力を撃つための唯ひとつの決め手ではないだろうか。
私が倫理を必要とするのは、それが権力の媒介なしに他者とつながり生きていくことを可能にする手引きだからであり、つまりは私が他者を深く欲望するからこそである。
この欲望の故に私は、ときには倫理に違反する危険をおかしてでも、他者に関わろうとするのであり、それ故そのことへの責任を負ってもいる。正当化されることのない、生そのものの暴力性への責任、自分が生きているという事実にもとづいた無限の責任を負っているのである。
私は、暴力的に生きるしかない存在だからこそ、倫理を必要とするのだ。
締めくくりに、ここから、この「責任」について考えてみよう。
私がこの世界に生きている限り、それ(生)は何がしかの暴力性、権力性をはらまざるを得ない。ここでは、暴力を一切ふるわなきことも、また暴力である。
また私は、必ず自分にとって「見えない」存在を作り出し、その「見えない」存在と共に生きている、ともいえる。だからこそ、私によって「見えない」存在とされた人々からの告発は、あるいは何かの理由によるその存在への「気づき」は、私の生が(部分的にであれ)構造の外側においてもありうるという事実を保障するものとして、働きうるのである。
だが同時に、忘れてはならないことは、私は生きている限り、「見えない」存在と共に生きるという、この不透明性を、決して免れない、ということである。
私が生きるということは、自らの暴力性、権力性を携えて生きる、という以外のことではありえない。
だから重要なのは、人間(私)の暴力や権力性の、どの側面、そこに働いているどんな力の要素を批判するか、ということである。
問題は、
A 私が他人に暴力や権力を行使しているということ、また私にとって「見えない」存在を私が作り出しながら生きているということ(生きざるを得ないということ)
と、
B 私が、構造への黙認・服従をとおして、その存在(人々)を現に見殺しにしていく(権力に積極的に加担する)、ということ
との隔たりにある。
ここでA、Bは、二種類の暴力ということではなく、単一な暴力の二種の側面、相といってよいだろう(注2)。
Aは、最終的には免れない生の事実性であり、Bは社会的な権力の作用(支配)である。Aは、もちろん個々の場面において問われねばならないが、そのことをとおしてBを撃たない限り生の毀損の拡大再生産が止むことはない。そして、Bを問うことこそが、私の他者に対する真の「責任」である(社会的な権力の作用が、巨大な暴力の遂行に関わるものであることを考えれば、このことの妥当さは、なおのこと明瞭だろう)。
免れない生の事実性としての暴力と、「見殺し」という社会的な権力行使への加担との両者を分かつもの、それが「倫理」をわれわれにもたらすところの、いわば始原的な感情であると思う。この感情が、いわば倫理の「ふるさと」(坂口安吾)であり、「仁の端」(孟子)であろう。
私の生が、権力的であること、また暴力的であることを決して免れない(その意味で有限である)としても、そのことに由来する他人の苦しみや思いを感受する能力、あるいは想像する能力を、私が手放すいわれはない。手放さねば、私の(私による)社会的な生の遂行は、より困難になるとしても。
社会的な権力は、その感情を手放すことを要求する、言い換えれば、自分の有限性ゆえに他人たちを「見殺し」にすること、理不尽な暴力の行使による犠牲を否認あるいは正当化することを、私に強いてくるのである。
この強制は、無論私自身の身体に対する暴力についても差し向けられるだろう。
それはしばしば、「仕方ない」という言葉によってなされる。
私が、他人や私たち自身を見殺しにすることは、私が有限な人間である以上は、避けられないこと、「仕方がない」ことである。(また、他人が私に行使する暴力も、社会のためには「仕方がない」ものである)。 これが、社会的な権力が私を服従させようとする命題、人間と人間を分断して支配するための命題なのだ。
私が、自らの有限性を認識しながらも、「無限の責任」という言い方を選ぼうとするのは、この命令と支配に抗って、私を他人の実在につなぎとめる感情の力を手放すまいとするからこそである。
そしてまた、私が「倫理」という語を掲げる最も深い動機も、そこにあると言ってよいだろう。
他人との分断こそが、私の生を損なう最大のものだということを、私の身体は知っているのだ。
原爆の投下を「仕方なかった」と言い放った政治家が居たではないか、経済成長や改革による犠牲を仕方がないのだという風に言い放つ大臣や学者や官僚が居るではないか、利潤のための首切りを仕方ないと言ってはばからない経営者だの知事だの学長だのが横行しているではないか。
そうした人間たちが権力を握り続けることを(したがって私と他人たちへの甚大な暴力の継続を)、仕方ないと言って容認したり支持したりしている、そしてそんな考えを持たざるを得ないところに私たちを追い詰めているこの現実の社会のあり方を変えようとしない、私たち自身の自暴自棄の態度、その非情さ、冷淡さ、倫理と愛情の放棄こそが、問われるべき核心なのだ。
この意味でこそ、私は自分の生と同時に、「見えない」他人たちの生を、現に見殺しにしているのである。
私が倫理にこだわるのは、私が他人との(あえて言うが)人間らしい共存、関わり合う生というものを求めるのは、虐待や攻撃や搾取によらない関わりを欲するのは、一言で言えば、生きている隣人や生き物たちの存在を手放したくないのは、それは、私が感情によってつながることを欲するその世界こそが、私が生きて存在していることのほんとうの基盤(「ふるさと」)であると知っている(願っている)からなのだ。
その基盤を手放さないため、自分の生を放棄してしまわぬために、私は「仕方ない」という命題に抗って、日常を覆っている現実の権力のさなかに「感情」の力を注いでいく。自ら注ぐことによって、感情と感情との交流を、私のこの生のなかに実現するために。
それは危険に満ちた、ひとつの願いである。
私の最大の倫理的責任、そして欲望、それは巨大な暴力の支配に逆らって、感情が流通する、この生の基盤としての世界を、あくまでも守りぬくことに他ならないのだ。
★プロフィール★
岡田有生(おかだ・ありお)
1962年生まれ。男性、独身、親と同居。プロフィールに書くようなこともなく現在に至る。ブログ:Arisanのノート
Web評論誌「コーラ」08号(2009.08.15) 〈倫理の現在形〉第8回:倫理のふるさと──存在の暴力性と、共に存ることの基盤(岡田有生) Copyright(c) SOUGETUSYOBOU 2009 All Rights Reserved. |
| 表紙(目次)へ |