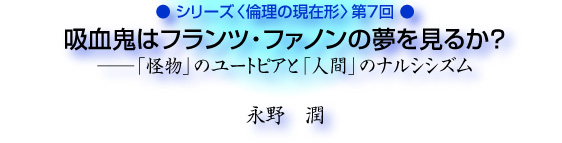|
|
|
Web評論誌「コーラ」 |
|
■創刊の辞 ■本誌の表紙(目次)へ ■本誌のバックナンバー ■読者の頁/ご意見・感想 ■投稿規定 ■関係者のWebサイト ■プライバシーポリシー |
|
<本誌の関連ページ> |
|
■「カルチャー・レヴュー」のバックナンバー ■評論紙「La Vue」の総目次 |
Copyright (c)SOUGETUSYOBOU |
|
|
|
■宇宙怪物と人間
藤子F不二雄(ふじこ・えふ・ふじお)のSF短編マンガは、繰り返し同じ世界を描いています。それは「人間」がマイノリティーとなる世界です。それは、いわゆる「ディストピアもの」と言ってもいいでしょう。たとえば、「絶滅の島」という作品(1985年)(注1)では、人類が絶滅の危機に瀕した地球が舞台です。地球は毛むくじゃらの巨大な「宇宙怪物」たちに突如攻撃され、圧倒的な軍事力の差に、地球人はほとんど殺戮されてしまったのです。生き残った主人公の少年は言います。「戦争なんてものじゃなかった 一方的に焼き尽くし、破壊しつくし、殺しつくし……。 人間をまるで雑草か何かのように……。」彼を含む27人は、「秘島ツアー」で孤島にやってきていたため殺戮をまぬがれ、生き残ったわずかな人間です。しかし、その人々も宇宙怪物に見つかってしまい、襲撃を受けます。人々は武器をもって抵抗しますが、次々に捕らえられ、残虐な仕方で殺されていきます。今このマンガを読む人の中には、この宇宙怪物の姿に、テロとの戦い、などと称して、人々をまさに雑草かなにかのように殺戮している現実の大国の軍隊を想起する人もいるでしょう。
結局最後に生き残るのは、少年、少女と、中年男性の三人です。男性は少年に、次のような話をします。「フ、フ……。皮肉なもんだねえ。ミツユビムカシヤモリって知ってるかい。原始的なは虫類で、生きた化石とさえいわれた……。そう、この島にだけ生き残っていた珍しいヤモリなんだ。学者が気づいたときには、もう、手おくれだった。人間の手で捕りつくされて絶滅したんだよ。昔から、そのヤモリの黒焼きが肺病の特効薬だという俗信があったおかげでね。ヤモリを絶滅させた島で、今度は、人間が絶滅させられようとしてるわけだ。ワッハッハ……。」少年は「あいつら、悪魔ですよ。血を流してたのしんでるんだ。逃げまどう人間を、突き刺して、引き裂いて……。まるで、虫けらみたいに……。」と怒りを新たにするのですが、それに対して男性はこのように答えます。「その意見には、虫けらのほうから苦情がでそうだね。それに、宇宙怪物の目からみれば、人間も虫けらもおんなじことなんだろうね。長い間、人間は、地球の主人公としてかって気ままにふるまってきた。ほかの動物を生かすも殺すも、人間さまの心しだい。だから、こんど、人間が狩られる立場にたったとしてもえらそうに文句をいう資格は、ないんじゃないかと……。ま、精いっぱい生きのびようと努力すること。わしらに残された道はそれだけさ。」(『藤子・F・不二雄少年SF短編集 (2)』小学館コロコロ文庫、1997年、p.226-8)
その後、宇宙怪物に見つかって絶体絶命となったとき、男性は少年と少女に「逃げろ!!」と叫び、たった一人で貧弱な武器をもって巨大な宇宙怪物に向かっていきますが、まさに虫けらのように一瞬にしてたたき殺されます(この後の物語の結末については書きません)。
さて、この作品には、「宇宙怪物」、「人間」、「虫けら(ミツユビムカシヤモリ)」という三者の間の、二つの関係が描かれています。つまりこの作品は、「宇宙怪物」と「人間」の関係が、「人間」と「虫けら」の関係を暗示する、という構図になっているわけです。「宇宙怪物」との関係において、私たち「人間」は被害者となります。そのことを描くことによって、「虫けら」との関係においては、私たち「人間」こそが加害者である、ということを読者に想起させる、というのが、この「寓話的」マンガのテーマであるように見えます。
■テレパシーと音声言語
『手話でいこう──ろう者の言い分 聴者のホンネ』は、秋山なみ(あきやま・なみ)さんと亀井伸孝(かめい・のぶたか)さん夫婦によるエッセイ集です。秋山さんはろう者、亀井さんは聴者です。この本は、二人の日常を描いたとても楽しいエッセイ集ですが、また同時に、この社会のさまざまなところに存在する、ろう者にとっての「壁」についても描かれています。この本の中に、文化人類学者である亀井さんが、ある聴者の集まりでした講演会の内容について書かれた興味深いエッセイがあります。亀井さんに、講演前にこんな質問紙が寄せられたそうです。「『ろう者はろう者どうし結婚することが多い』『ろう者はろうの子どもが欲しいと思うこともよくある』と聞きましたが、ろう者の気持ちが想像できません。やっぱり聞こえた方がいいんじゃないでしょうか。」これを読んだ亀井さんは、ろう者がおかれている言語環境、すなわち「自分ががんばっても身に付けがたい異質な言語に囲まれ、ふだん自然に話している言語が無理解のために圧迫を受ける」という環境を講演参加者に疑似体験してもらうために、あるストーリーを作りました。それは「テレパシー言語に囲まれた音声言語の話者たち」というストーリーです。
この話では、「テレパシー宇宙人」と「聴者」の関係が、「聴者」と「ろう者」の関係を暗示する、という構図になっています。「テレパシー宇宙人」との関係において、私たち「聴者」は被害者となります。そのことを描くことによって、「ろう者」との関係においては、私たち「聴者」こそが加害者である、ということを読者に想起させる、というのが、このストーリーのテーマであるように見えます。
この話では、マジョリティの言語である「音声言語」と、ろう者の言語である「手話」との関係が、「テレパシー言語」と「音声言語」の関係に置き換えられています。たとえば、テレパシー訓練とは、ろう児に唇の動きの読み取りと発音の訓練を行う口話法の訓練に対応しています。日本のろう学校では、長い間口話主義の教育が行われてきました。口話主義とは、手話を「言語」としては認めず、すべてのろう者に対して音声言語の習得を強制するものです。
ちょうど、「絶滅の島」で、架空の宇宙怪物を作り出すことで、人間に虫けらの立場を疑似体験させようとしていたのと同じように、ここでは、架空のテレパシー宇宙人を作り出すことで、聴者にろう者の言語環境を疑似体験させようという試みがなされています。そして、亀井さんも言うように、この架空の世界でのテレパシー宇宙人の姿とは、現実の世界における聴者の姿にほかなりません。亀井さんは、この話があまりによくできすぎていたために、講演が終わったあともしばらく、身近なできごとをすべてテレパシー宇宙人に置きかえてみる癖が付いてしまったそうです。ろう者にとってこの社会での暮らしとは、次のようなできごとが日々押し寄せる暮らしなのです。
亀井さんは、「人口の99パーセント以上をテレパシー宇宙人が占め、どんなに主張しても音声を言語として認めようとしない世界」に引越したときどのように感じるか、という気持ちをもとに「現実のろう者と聴者の関係を考え直してみませんか」と聴者に訴えかけます。このように、このとてもすぐれたストーリーは、あくまで聴者に向けられた聴者のためのものです。このストーリーは、あくまで、聴者に「ひとまず関心を持ってもらうため」のものでしかない、ということも、忘れてはならないでしょう。
■吸血鬼と人間
ここで、藤子F不二雄のもうひとつのSF作品を紹介したいと思います。それは「流血鬼」(1978年)です(注2)。(最後までストーリーを紹介するのでネタバレがいやな方は注意してください)。最初のコマは、殺人の場面です。民家の中で寝ていた男が、胸にくいを突き刺されています。恐ろしい断末魔の叫び声が上がり、血しぶきが噴き出しています。くいを刺したのは中学生ぐらいの少年です。その場から逃走し、洞窟の中にある隠れ家に帰った少年は、そこで待っていたやはり中学生の仲間に、自分が行った行為を報告しますが、その凄惨な場面を思い出して嘔吐します。それに対して、仲間の少年はこう言います。「ショックを受けたのはわかるけど、やつらの息の根を止めるには、それしか方法がないんだから……。気にするな。相手は人間の形こそしているが、怪物なんだ。」(前掲『藤子・F・不二雄少年SF短編集 (2)』p.76)
実は、「人間の形をした怪物」とは吸血鬼のことで、物語のこの時点で、世界は吸血鬼に征服され、支配されてしまっていたのでした。ルーマニアの村で原因不明の「奇病」が発生し、同時に吸血鬼のうわさがながれます。その後、この「奇病」は世界中に広まり、病原体のマチスン・ウィルス(注3)が発見されます。このウイルスに感染した患者は死後に生き返り、人間を襲って血を吸うゾンビになるのです。ある日の夜、吸血鬼たちは、マチスン・ウィルスをガス状にして散布してクーデターを起こし、世界を征服します。からくも生き残った主人公と友人は、洞窟に身を潜め、人間たちの反攻がはじまり、反乱軍が自分たちを救助してくれることを待っているのです。ただし、吸血鬼は夜行性なので、昼間街に出て、寝ている吸血鬼を襲ったりしている、というわけです。
しかし、友人もその後吸血鬼に捕らえられてしまい、主人公がたった一人になった隠れ家に、突然、主人公のおさななじみ、いや、おさななじみだった吸血鬼、が一人でやってきます。以前は、吸血鬼になることを極端に恐れていた彼女ですが、いまはすっかり吸血鬼としてのアイデンティティをもっています。彼女は、たった一人の生き残りの人間となった彼に対して、自分と同じような吸血鬼にならないか、と説得にやってきたのです(彼女はそのために自分に少年の血を吸わせてほしい、と言います)。「だれが信用するもんか!やさしそうにみせかけても、吸血鬼なんだ!!」と警戒する少年に、彼女はこう言います。「わたしたちを吸血鬼とよぶなら、あなたたちは流血鬼よ。安らかにねむってる人の胸に杭を突き刺すなんて! なんのうらみもない善良な人に!」そして彼女は、吸血鬼は人を殺しているように見えるが、それはウイルスを伝える手段のひとつであって、感染者は一時的に死んだように見えても、すぐに回復する、そして、回復した人は、それまでよりもはるかにすぐれた能力を獲得する、と説明します。いわば新人類として生まれ変わるのだ、と言うのです。しかし少年は納得しません。「はるかにすぐれた……か。赤い目、青白い肌〔感染者にはこのような身体的変化が現われるようです〕……。もとのままのきみでいてほしかったよ。」少女はこう答えます。「それは旧人の感じ方よ。体質が変われば感覚も変わっていくわ。」(同書p.102-3)話し合ったうえで自発的に吸血鬼(新人)になってほしい、と考えていた彼女は、根気強く説得の努力を続けますが、ついにはあきらめ、最終的には、強制的に、暴力的に、少年を吸血鬼にします。獲得した強い力を使って、彼女は少年に襲いかかり、血を吸います。こうして、最後の人間(流血鬼)がいなくなり、世界は吸血鬼(新人)の世界となります。
■反転するまなざし
この作品は、最初に紹介した「絶滅の島」と大きく違う点があります。この作品の中には、たった一つの関係しかありません。すなわち「人間」と「吸血鬼」(同じことですが「流血鬼」と「新人」)の関係です。そして、「絶滅の島」では、別の関係を暗示する、ある固定した関係が描かれていただけなのですが、この作品のストーリーのポイントは、関係が、逆転し、入れ替わるというところにあります。ある晩から世界が逆転するのです。これまで奴隷であり怪物であったものは、その晩から世界の主人になったのです。
そして、私たちは、「絶滅の島」においては、「流血鬼」に存在する「何か」が排除されていたことに気が付くのです。たしかに、「絶滅の島」では、人間と、人間以外のもの(虫けら)の関係の「非対称性」が描かれていました。それをきっかけに、人間の虫けらに対する「見方」や「関わり方」を改めようと反省した人もいるかもしれません。しかし、これらの作品は、「虫けらの視点」と直接相対してはいません。つまり、宇宙怪物の「まなざし」は描かれていても、虫けらの「まなざし」は不在なのです。
サルトルは、『存在と無』(1943年)において、「まなざし」というキーワードを中心とした他者論を展開しました。それによると、独我論的な「私の世界」が崩壊して、「主観としての他者」が現われるのは、他者にまなざしを向けられる、という体験においてなのです。
例えば、誰もいない公園で、私が「木」を見ている。このとき、私の世界に他者はいません。次に、公園で、私が「『木』を見ている人」を見ている。このとき、私の世界に他者が現われます。他者は、木の、私には見えない側面を見ている、ということを私は知っています。それは、私の世界の一部が他者に奪い取られることです。他者は私の世界に出現した「排水孔」だとサルトルは言います。彼/女に向かって、私の世界は流出します。これをサルトルは「内出血」と呼びます。しかし、この他者はあくまで「対象としての他者」です。私はいまだに、いわば第三者として木とその人の両者を見ている主観です。ところが、その人が木から視線を移して、私に「まなざし」を向ける。そのとき、私はもはや他者との関係において第三者ではなくなります。それは、独我論的な「私の世界」が全面的に崩壊することでもあります。私は、「彼/女の世界」の中の単なる一対象となります。「主観としての他者」が現われる、ということは、すなわち、逆に「私が対象となる」ことなのです。そして、他者の対象となった私が「主観としての私」をとりもどすためには、「まなざし」を反転し、再び相手を見返すほかはない。この、私と他者との関係の対称性のことを、サルトルは「相克conflit」と呼びます(サルトル、松浪信三郎(まつなみ・しんざぶろう)訳『存在と無』ちくま学芸文庫、2007年、p.95-130、p.367)。
そして、「絶滅の島」では、この、関係性の「相克」としての側面、言いかえれば「敵対性」を描くことが結局は回避されていたのではないでしょうか。しかし、私たち人間は、第三者ではなく「紛争conflit」の一方の当事者なのです(注4)。一方、「流血鬼」の場合は、「まなざしの反転」のドラマが描かれていました。「吸血鬼」は、これまでずっと、私たちのまなざしにつらぬかれ、怪物としてさげすまれ、杭を打たれ、殺されてきました。しかし、吸血鬼は人間たちに「まなざし」を反転させます。洞窟にやってきた吸血鬼の少女は、少年にむかって、すなわち「人間」に向かって宣告しました。「あなたたちは流血鬼だ」と。
サルトルは、黒人詩人の詩集への序文として書かれた「黒いオルフェ」(1948年)において、こう書いています。
まなざしの反転ということについて、私にとって印象深い映画の一シーンがあります。「過激」な闘争スタイルで時代を駆け抜けたCP(脳性マヒ)者の団体「青い芝の会」を描いたドキュメンタリー映画『さようならCP』の一シーンです。そこで、青い芝の会の横塚晃一(よこづか・こういち)さんは、カメラを手にしてこのように語っていました。
■ろう者のユートピア
さて、先に紹介した「テレパシー言語」の「寓話」はどうでしょうか。いうまでもなくそれは、関係の「反転」を描いたものではありませんでした。音声言語の話者(聴者)を支配することになるのは、架空のテレパシー宇宙人であって、聴者が抑圧している当の人々、つまり手話の話者(ろう者)ではありません。もしこれが「流血鬼」タイプの物語であれば、音声言語の社会を征服し、支配するのは、ろう者である、ということになるでしょう。そのような物語を、聴者の人々は果たして受け入れるでしょうか?
しかし、事実、ろう者の間では、そのような「ろう者が支配する世界」の物語は、めずらしいものではないようです。長瀬修(ながせ・おさむ)さんは、ろう者が支配者となる「ろう者の国」という発想が、ろう者の間では流通しているのではないか、と言っています。(長瀬修「障害学に向けて」石川准(いしかわ・じゅん)・長瀬修編著『障害学への招待』明石書店、1999年、p.32)
「デフトピア」とは、「デフ(ろう者)」にとっての「ユートピア」という意味でしょう。長瀬さんも紹介していますが、「ろう文化宣言」(木村晴美(きむら・はるみ)・市田泰弘(いちだ・やすひろ)「ろう文化宣言──言語的少数者としてのろう者──」『現代思想』青土社、1995年)の起草者でもある木村晴美さんも、ろう者が支配する「ろう者の国」の想像をふくらませています。
長瀬さんは、「ろう者の国」と似た、肢体不自由者のユートピアの発想についても紹介しています。
テレパシー宇宙人に支配された世界、それは、聴者にとってのディストピアでした。しかし、「ろう者の国」とは、「デフトピア」、すなわち、ろう者にとってのユートピアなのです。
さて、「私たち」は、「彼/女らのユートピア」が「私たちのディストピア」であること(私たちと彼/女らの相克=敵対性の関係)にいまさら気づいて慄然とするかもしれません。しかし、本当に慄然とすべきなのは、「彼/女らのユートピア」が、いまだに「ユートピア」でしかないことに対してではないでしょうか。実際、彼/女らにとっては、この現実こそが、すでにディストピアだからです。
吸血鬼は夢を見ます。人間=流血鬼が世界から一人もいなくなり、世界が吸血鬼のものとなる夢を。しかし、彼/女が目覚めたとき、彼/女は自分の胸に突き刺さった杭を発見するのです。
■人種主義に反対する人種主義
「ろう者の国」は、ひとつのユートピアでしかないのですが、ろう者たちは、聴者の社会の中に、手話という言語を中心とした、「ろう文化」があることを強く主張しはじめています。そうした主張に対して、攻撃的、敵対的なものだと不快感を持つ聴者も多いです。「それは逆差別だ」「仲良くすればいいのに、自分から壁を作って閉じこもろうとしているではないか」などと言うのです。まさにそれが、宇宙人=聴者の姿です。テレパシー宇宙人のたとえを思い出して下さい。手話だけで集会をしたら、聴者は「排他的だ」と批判します。「隔離教育はやめて、聴者の学校で共に学ぼう」と聴者たちはろう者たちに言います。「手話に閉じこもってはだめ。広い視野を持ちなさい」と聴者はろう者を説教します。「無色透明」「普通」な人間を僭称する聴者たちが、日々、ろう者ではなくなることをろう者に求めているのが、この社会なのです。その中で、ろう者は、自分たちが聴者とは「違う」文化をもった「ろう者である」、と主張し、あなたたちの騙る「普通」とは、「聴者の文化」でしかない、と主張しなければならないのです。現在の社会そのものが、差別によって成り立っているのですから、差別の否定とは、現在の社会そのものの否定です。その否定を逆差別と言うのであれば、逆差別を通過しなければ差別はなくならない、ということです。「青い芝の会」は綱領の中で「われらは健全者文明を否定する」いいましたが、問題はここでの「否定」です。サルトルは、さきほど紹介した「黒いオルフェ」において、黒人による黒人性の肯定である「ネグリチュード」という概念が、「否定」としての側面をもつことを強調し、それを「人種主義に反対する人種主義」と呼びました。
ただし、サルトルは、この「否定」を、弁証法的進行の一契機としてとらえます。「人種主義に反対する人種主義」という否定性の契機はそれ自体で充足するものではなく、最終的には「総合」の契機を準備している。そして、「総合」の契機とは「人種のない社会での人間的なものの実現」です(同書p.189)。その意味で、この「人種主義に反対する人種主義」(としてのネグリチュード)は、「己れを破壊する性質のもの」(同書p.189)なのです。それは「経過であって到達点ではなく、手段であって最終目的ではない」(同)のです。とはいえ、「人種のない社会での人間的なもの」とは、ヨーロッパの欺瞞的なヒューマニズムが唱える「無色で抽象的な人類」(同書p.147)とはまったく違うものです。ヒューマニストたちは、自分たちを「普通の人間」だ、と僭称し、「普遍性」を語りますが、その「普通」や「普遍性」とは、ニセの普通であり、ニセの普遍性なのです。ネグリチュードの肯定は、そうした「ニセの普遍性」を破壊し、〈普遍性〉そのものを求める運動です。だからそれは、特殊に閉じこもることではなく、その逆です。サルトルは、黒人たちを「普遍的なものの曙光を見出すべく、特殊精神をどこまでも生き抜こうとする人間(同書p.192)」と呼びます。また、マジョリティが僭称するニセの「普遍性」とは、あらかじめある、静止した、モノとしての普遍性であるのに対し、ネグリチュードがめざす〈普遍性〉は、固定した「状態」や「性質」ではありません。そして、ネグリチュードそのものもまた、固定した「状態」や「性質」ではなく、〈普遍性〉をめざす「運動」としての否定性です。「自由な意識による、一定の状況の超越」(同書p.192)であり「自由な人間によって選択され、とことんまで絶対的に生き抜かれる実存的態度」(同書p.193)なのです。サルトルがネグリチュードを「不安定な休息」「爆発的な固定性」「自己を放棄する自尊心」「一時的であることを自覚している絶対」(同)と呼ぶのも、そうした意味です。
■流血鬼のナルシシズム
ところで、「流血鬼」では、主人公が吸血鬼の少女に血を吸われるシーンの後さらに、きわめて印象的なラストシーンが描かれています。ページをめくると、ベッドの上で目を覚ました少年が描かれています。少年の目は赤く、肌は青白くなっています。少年の目の前に、白衣を着た医師がいるのですが、医師は少年に、実は自分は少年に杭を突き刺された吸血鬼(新人)なのだ、と言います。驚く少年に、医師はさらに、旧人と比較にならぬ強い体力をもつ新人は、細胞再生ですぐもとの体になるのだ、と言います。こうして、「すっかり健康体」となり退院した彼を、おさななじみの少女が迎えに来ます。ラストシーンに描かれているのは、一見これまでと変わらない当たり前の街角の風景です。しかし、それは、これまでとはまったく違う世界なのです。すなわち、もはや「流血鬼」が一人もいなくなった世界、「敵」が一人もいなくなり、新人が完全に勝利した世界、言いかえれば、吸血鬼にとってのユートピアです。最後のコマには、この、新しい町の「さわやかな夜空」の下で明るく笑いあう少年たちの姿とともに、吸血鬼の少年のこのような言葉が書かれています。「気がつかなかった。赤い目や青白い肌の美しさに!気がつかなかった!夜がこんなに明るく優しい光に満ちていたなんて!」(『藤子・F・不二雄少年SF短編集 (2)』p.107)
このシーンを読んだ私たちは、吸血鬼たちのまなざしに貫かれた「戦き」とは、別のものを感じるのではないでしょうか。この徹底して明るいラストシーンの光景を見て、なんともいえない居心地の悪さ、不気味さ(ウンハイムリッヒ)を感じる読者も多いでしょう。なぜなら、そこは「吸血鬼の世界」なのであり、このラストシーンには、「私たち」がどこにもいないからです。サルトルは、フランツ・ファノンの著書『地に呪われたるもの』(1961年)への序文で、これと同じ「居心地の悪さ」について書いています。それは、ファノンの本を読むヨーロッパ人が感じる居心地の悪さです。
1925年、カリブ海の西インド諸島の南端近くの、フランス領のマルチニック島で、黒い皮膚をもつマルチニック人として生まれたフランツ・ファノンは、フランスで精神科医となり、北アフリカのアルジェリアの病院に赴任しました。そこで出会ったアルジェリア独立闘争に身を投じ、その指導者の一人となります。『地に呪われたるもの』は、36歳で白血病で死ぬファノンが、死の直前に一気に書き下ろした激烈な書物です。ファノンはこの本で、植民地の状況がどのようなものか、そしてそこからの解放がどのようになされるべきか、について熱く語っています。しかし、では、ヨーロッパについては? ヨーロッパについてファノンは、その救いようのないナルシシズム、「ますます卑猥化していくナルシシズム」(フランツ・ファノン、鈴木道彦・浦野依子(うらの・きぬこ)訳『地に呪われたるもの』みすず書房、1996年、p.310)を指摘します。ファノンは言います。
「人間について語ることをやめようとしない」ヨーロッパが語る「人間」とは何か? それは、植民地と奴隷と怪物を外部に作り出すことで成り立っている「人間」、すなわちヨーロッパの人間です。ヨーロッパのナルシシズムとは、欺瞞的ヒューマニズムのことでもあります。ファノンの書物の序文で、サルトルはこう言いいます。
ヨーロッパのヒューマニズムにおける「人間」とは、つまり「ヨーロッパ人」のことでしかありません。ヨーロッパのヒューマニズムとは、「普遍的人間」について語っているように見えて、結局は「私たち」について語る「ナルシシズム」に他ならないのです。ヒューマニズムの賛美とは、自己賛美でしかありません。「青い芝の会」の綱領も、健全者たちのナルシシズムを「愛と正義のもつエゴイズム」と呼んで告発しています。
もちろん、ヨーロッパを批判するヨーロッパ人もいます。サルトルは、フランス人がほかのフランス人に対して「私たちはだめになった!」と毎日のように語っている、と皮肉を言っています。そんなフランス人が必ず付け加えるのが「ただ唯一の救いは……」という言葉です。自分のアドバイスに耳を貸せば、フランスは危機を乗り越えられる、と言うのです。結局、これも自己批判、というナルシストたちのおしゃべりにすぎないのです。「私たち」は、独我論的な「私たちの世界」から一歩も外に出ません。
そしてファノンは、そんなナルシストたちに「訣別しよう」(ファノン『地に呪われたるもの』p.308)と言います。サルトルはこう書いています。
サルトルは、「黒いオルフェ」で、黒人たちのまなざしに貫かれた白人たちの
これに続くサルトルの文章は、「流血鬼」のラストシーンを読む「私たち」のことを書いている、としか思えない文章です。
では、こんな風に、ファノンの書物を紹介するサルトルは、一体なんだと言うのでしょう。彼もまた、フランス人のナルシシズムについてフランス人に向かって語っているに過ぎないのであって、やはりナルシシズムの中にいるとしかいえないのではないでしょうか。サルトルはあっさりそれを認めます。
一方サルトルは、このようなことも言っています。植民地の人々は、ヨーロッパの人間、そしてヨーロッパが暴力によって作り上げた植民地体制そのものを暴力的に否定する運動を通じて「新たな人間になる」(同書p.80)と。そうした歴史の運動の中で、ヨーロッパの人間は「客体」でしかありえない。
しかし、サルトルはそれを嘆いているわけではありません。この〈他者〉が作る歴史の中で、ヨーロッパ人もまた「非植民地化」されて新しい人間になるのであり、サルトルは、私たちが、〈他者〉が作る歴史の流れに「合流」することを祝福するのです。ファノンの書物への序文を、サルトルは次のように結びます。
巷にあふれる、サルトルの哲学は「主体性の哲学」で「ヨーロッパ中心主義」だ、などという単純な批判が的外れなことは、これを見てもわかると思います。
■注
注1 この作品は、1980年の『スターログ』に掲載された初出バージョンではセリフがいっさいなかったということですが、1985年に『別冊コロコロコミック』に掲載されたバージョンでセリフが追加されたそうです。本論で紹介するのは、小学館文庫に収録されたセリフのあるバージョンの方です。
注2 この作品は、1954年に発表されたリチャード・マシスン(マチスン)による小説『I Am Legend 』を実質上の原作とし、ストーリーやテーマをかなり引き継いでいます。しかし、私見では、藤子の「流血鬼」のストーリーは、『I Am Legend 』よりもずっと優れていると思います。
注3 この物語の「原作者」リチャード・マチスンにちなんでいます。
注4 サルトルの他者論は、結局は独我論の袋小路に陥る、などとしばしば批判されました。しかし、浅田彰(あさだ・あきら)は『構造と力』の中で、当時のサルトルバッシングの風潮の中ではめずらしく、このように述べています。
★プロフィール★
■永野潤(ながの・じゅん)
1965年生まれ。専攻は哲学。現在、東京都立大学、関東学院大学等にて、哲学・倫理学などの非常勤講師。
著書:『図解雑学サルトル』(ナツメ社)
論文:「断崖に立つサルトル―自由と狂気についての素描」(日本現象学会『現象学年報』第11号)、「違和としての身体─岡崎京子とサルトル」(ナカニシヤ出版『身体のエシックス/ポリティックス−フェミニズムと倫理学の交叉』所収)、「サルトルと女とアンドロイド―両義性の倫理へ/意識・身体・自己欺瞞」(岩波書店『岩波応用倫理学講義5性/愛』所収)、「合法性が正当性を虐殺するとき」(情況出版『情況』2006年1・2月号)等。
★本稿を収録した新刊が刊行されました。Web評論誌「コーラ」07号(2009.04.15) 〈倫理の現在形〉第7回:吸血鬼はフランツ・ファノンの夢を見るか?(永野 潤) Copyright(c) SOUGETUSYOBOU 2009 All Rights Reserved. |
| 表紙(目次)へ |