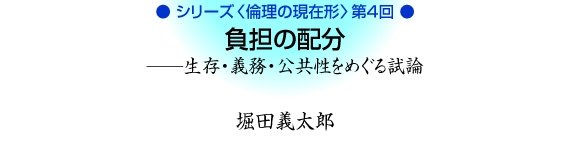|
|
|
Web評論誌「コーラ」 |
|
■創刊の辞 ■本誌の表紙(目次)へ ■本誌のバックナンバー ■読者の頁/ご意見・感想 ■投稿規定 ■関係者のWebサイト ■プライバシーポリシー |
|
<本誌の関連ページ> |
|
■「カルチャー・レヴュー」のバックナンバー ■評論紙「La Vue」の総目次 |
Copyright (c)SOUGETUSYOBOU |
|
|
|
0. 倫理――望ましい社会的協働のあり方とその基盤となる共同性への問いとしての
倫理は、いかなる問題にかかわっているのだろうか。一般的には、人が他人との関係で「すべきこと」や「してはならないこと」を定める規範にかかわっている、と言えるだろう。もちろんこの回答に対しては即座に、そもそも「べき」とはどういう意味か、その「規範」の正当化根拠はなにか、といった問いが提起されうるし、実際に問われている。しかしこの試論では、より素朴に、そして基本的なところから考えていこう。根本的な問いはしばしば素朴なかたちで提起されるし、また素朴かつ基本的な問題に回帰するからである。 最初に、以下で用いるキーワードとその連関について確認しておきたい。キーワードは、「必要」「負担」「自由」「平等」「権利/義務」である。これらの概念については多くの議論があるが、それらはおおむね次のような理路で連関していると言える。 まず、私たちは生きるためには食べたり住んだりする「必要」がある。さまざまな必要をみたすためには活動・労働をしなければならない。それらの活動は「負担」である。この、必要をみたすための負担はすべての人間に等しく課されている。私たちはこれらの負担から「自由」になりたいと思っている。そして私たちは、社会をまずは、この必要と負担における「平等」を前提にして、相互に協力して負担を分担し、各人の必要を効率的にみたす協働のシステムだと考えている。この考え方では、社会的協働は、各人にとって独力で生きるよりも負担を軽減し、より多くの「自由」を得るための手段として位置づけられている。つまり協働は、まずは何より、各人の負担を軽減するものでなければならない[註1]。協働関係を取り結ぶ理由は、各人が相互に他者にもたらしうる利益である。逆に言えば、人は協働のなかで、独力で生きる場合に負うより以上の負担を他者のために負うことはない、とされている。各人は、自らの必要のための負担を超えて他者に何かを「させる/させられる」ことはない。人は、他者に不利益を与える行為以外の何をしても「自由」だとされる。「不利益を与えない限り何をしてもしなくてもよい自由」が「消極的自由」と呼ばれる。この「消極的自由」の各人への保障が、協働の前提としての共同性の基礎とされる。それによれば、社会的協働の基盤にはまずは、各人に消極的自由を「権利」として保証するための「義務」、つまり「害・不利益を与えるな」という義務がある。 しかし、他方で、誰もが独力で生きる能力をもっているとは限らない。独力で生きる能力の平等性を前提にした協働と共同のシステムでは生きられない人がいる(それは新生児に限らない)。そうした人々は、他人に利益を与える能力をもたないため、「他害以外の何をしてもしなくてもよい」という「消極的自由への権利」だけを基礎とした社会では生存は保障されない。消極的自由への権利だけからは、相互便益にならないような贈与は完全に各人の自由・恣意に委ねられるからである。だが、私たちは人に与えるものを持たない(あるいはそれを少なくしか持たない)人は貧窮しても仕方がないとは思ってはいない。必要な人が必要に応じて得られる権利が保証されるべきだと思っている(たとえば、日本の憲法第25条はこの規範にもとづいている)。これは、必要に応じて他者に財や行為の支出を公的に要求できるということであり、自由という語を用いれば「積極的自由」と呼ばれるものである。この積極的自由が公的に保障される、つまり「権利」として位置づけられるとすれば、消極的自由への権利を制約する場合がある。 そして、これまで私たちは、独力で生きられない他者を「家族」の自然な感情等を前提にして、家族に委ねてきた。さらに義務を課してきた(親の養育放棄等は処罰される)。しかし、家族に委ねることに限界があり、また委ねるべき理由がない(「自然な愛」等があるとしてもそれは義務を課す理由にならない)とすれば、誰が誰の必要のためにどこまで負担を負うべきか、そしてそれはなぜか、こうした点があらためて問題になる。 おおむねこうした点について、以下では、まずこの二つの自由概念によって特徴づけられうる「必要」と「負担」の分配様式の関係性を再検討し、その後、それに対応する二つの共同のルールの関係性を「すべきこと」「すべからざること」つまり「義務」の性質と程度に着目して検討してみようと思う。 相互便益のための手段としての協働システムでは、他者に利益を与える活動(労働)をしない限り、何も得られない。このシステムでは、財や行為は各人の協働への貢献にもとづいて分配される。第一節では、この分配様式を「労働ベース」の分配様式と呼び、この分配様式で権利として保証されるのは、まず何よりも消極的自由だということを確認する。そして、この「労働ベース+消極的自由への権利」と形容されうるような社会的協働の前提とその問題点を見る。 第二節ではこれを受けて、「必要」に応じて得られる権利としての「積極的自由への権利」の位置を確認する。これは、先の様式に対置させるとすれば、「必要ベース+積極的自由への権利」に基づく共同性としてまとめることができるだろう。私たちの社会はこれまで必要に応じて財や行為を支出するユニットとして「家族」を位置づけ、他者に利益をもたらす能力を持たない人の世話をとくに女性に委ねてきた。第二節では、その問題点を確認する。 そして、第三節では、これらの二つの共同性の関係性を、二つの自由への権利に対応する義務の性質と、その区別の基準という観点から再検討する。そして最後に、問題は、この二つの分配様式がそれぞれ妥当する範囲はどこまでであり、両者の妥当範囲を区別する線の根拠はなにか、という問いが要請する態度を明らかにする。
1. 労働ベースの分配様式と消極的自由への権利 まずは私たちの社会を駆動しているルールの大きな部分を占めている「労働ベースの分配様式」と、そこで想定されている人間像および自由概念について確認しよう。 1-1. 労働ベース、契約モデル、自然状態と非協力状態、消極的自由への権利 「労働ベース」の分配様式にもとづく領域においては、私たちは、《単に「事実」として生を維持するための活動をせざるを得ないことが多いだけであり、仮にそのような活動をせずに生きていけるならば、その方が望ましい》という態度をとっている。この立場からは、他者との関係性から完全に隠遁することも、さらにはたとえば断食をして死ぬことさえも――推奨はされないにしても――当人の自由であるということになる。 自らが生きるために必要な活動を、単に事実として「せざるを得ない」からしているだけだ、という態度で行動しているとき、そこに「すべきだ」という義務が入りこむ余地はない。そこではもちろん、他人の生のための活動・負担を負うべきだ、とも言えない。各人は各々、必要に応じて「せざるを得ない」活動をしているのであり、互いに自らの利益と負担を計算して取引しているだけだ、ということになるからである。自分に利益を与えてくれる物資や技能を持たない人間は、そこでは取引の相手にならない。じっさい、私たちは、他人の生活を支えるために自分に利益にならないモノを買ったりはしない。 これに対して、こうした態度と行動方針――たとえばJ・ハーバーマスならば「戦略的態度」と呼ぶ態度――で行動する場面は、私たちの生活の一部に過ぎない、と言う人もいるだろう。たしかに、私たちは自らの利益を差し置いて(特定の)他者のために活動することもある。また、市場での売買契約の場面でも、単に貨幣に換算できるような利益だけではなく、個別的な人間関係等を斟酌することもありうる。たとえば、R・ノージックが述べたように、保有物を「チャリティ精神」にもとづいて寄付したり贈与したりすることもあるかもしれない。しかしその場合、その相手も中身もその量もタイミングも、完全に贈与する主体の恣意に委ねられることになる。 問われるべき点は、たとえばハーバーマスが「戦略的態度」と呼ぶような態度は、私たち自身が日々採っている態度であり、それを完全に否定できる者は誰もいないということ、しかし私たちは、それには問題があることも同時に知っており、そしてさらにその問題点はノージックが称揚するような「チャリティ」だけでは解消できないということも知っている、ということ、これらの点を踏まえたその先にある。 その問題を見る前に、このような行動様式にもとづいて取引し合う人間――たまに余裕があるときにチャリティで寄付する人間――とはどんな人間か、を確認しておこう。それはまずは、他者にとって有用なモノを生産する能力を有しており、それを交換することで生を維持できる人間である。そこでは、個人に課される制約は、相互に自己の利得を得るために取引交渉し、合意された約束(契約)だけだとされる。たしかに、私たちの社会は、人々がその存在理由に同意しないようなルールや制約は認められない、という原則を採っている。この原則自体を完全に否定することは誰にもできないだろう。もちろん後述するように、私たちは、《人びとが同意・契約すればいかなる制約も許容される》とも《同意しなければいかなる制約も許容されない》とも考えてはいないのだが、まずは、社会制度やルールを合理的個人の合意事項(契約)として構想する理論の前提にある人間像を確認しておこう。その人間像を端的に示しているのは、たとえば次のような議論である。
この契約モデルの前提となる合理的人間は、「合意」の前提として設定されている状況すなわち「契約が結ばれる原点たる自然状態」[註3]から明らかになる。 契約の「原点」として位置づけられている「自然状態」は、「無制約な自由を各個人が享受する状況」[註4]だとされている。すなわち、「各個人は財の利用に関して、いかなるルールにも拘束されず、他者の身体や他者が保有する財を含めたすべてのものを自由に利用しながら、自らの選好を充足していく」[註5])ような状態である。そのような状態から合意と契約を経て導出される状態は、「自然状態における各個人の効用を向上させるようなものでなければならない」[註6])とされる。この種の契約論によれば、「契約当事者が合理的人間であるかぎり、自然状態における非協力的な相互作用が当該個人にもたらす効用を更に低下させるような原理に同意することはない」[註7]からである。 この議論――自己利益を最大化する合理的人間同士の契約に基づいて社会の規範的原理を構想する議論――の前提には、現在の「効用」が「低下」しないか否かの計算に基づいて他者と協力するかどうかを選択できるような人間像がある。それはすなわち、協力しないこともできるという選択肢をもつ人間――「非協力的」な状態でも生存可能な人間――である。つまり協力を得るための交渉材料を、非協力状態ですでに保有している人間である。逆に、協力しなければ生きていけない人間にとっては、協力によってそれ以上「低下」するような「効用」などない。だから、協力を得なければ生きていけない状態にある人は、上記のような社会理論では居場所はない。 とはいえ、このような契約論がたしかに、私たちの社会の一側面を的確にモデル化していることを明確に自覚しておく必要がある。私たちの生活の大部分は、自己利益と選好を前提にした合理的な収支計算に基づく交渉を通して、相互の合意にもとづいて必要な財やサービスを交換する領域によって構成されているからである。そのとき、私たちはおおむね、相互に他者を自己利益のための手段として位置づけている。 ここでは、そこでモデルになる人間とは、生存に必要な消費財を自力で獲得でき、生活を成立・維持できるだけの能力を有する人間だ、という点をあらためて確認しておこう。こうした一種の契約論的な社会理論の前提にある人間像は、保障されるべき「自由」の性質についての政治哲学の議論蓄積のなかでは「消極的自由論」と呼ばれる立場にも共有されている。「消極的自由論」とは、諸個人に対する干渉・介入の許容条件を、「他者からの干渉されない状態を守る」という目的の実現に限定する議論である。
つまり、禁止されるのはもっぱら作為による加害であり、そこで保障されるべき自由は、「作為的加害以外の、何をしても・しなくてもよい」という自由になる。ここからは人が生きるために必要な活動を「すべきだ」といった規範は出てこない。
1-2. 問題点 では、こうした「労働ベース+消極的自由の保障」を基礎とした社会理論の何が問題なのか。 単純に、そこでは、誰も何もしないことによって生存が脅かされる人(幼児・病人・高齢者等)を、何もせずに放置すること(不作為)は何ら問題にならなくなる、ということである。「消極的自由論」では、他者の協力が必要な人を支援することを諸個人に要請することはできない。それどころか、むしろ個人はそうした要請を干渉として拒否することさえ正当化されてしまう。だが、私たちは「交渉・取引材料をもたない人(幼児・病人・障害者・高齢者等)は死んでも致し方なし」とは言わないし、そのように思ってもいない。 たしかに、他者の協力を得なければ生を維持できない人への分配と支援も、個人の自己利益の合理的計算――たとえば「保険」――を通して可能だ、という議論も展開できないことはないかもしれない。だが、上記のモデルで仮に保険が成立したとしても、それがカバーする範囲は非常に限られる。なぜなら、自己利益最大化の論理だけに従うとすれば、保険には自己の将来のための貯蓄以上の意味はなく、他者の必要を保障するためのものではあり得ないからである。上記のモデルでは、保険の主体は非協力的な状態で交渉能力をもつ人である。そこではそもそも、障害や疾病で他者の協力を得るための交渉材料をもたない人びとは、保険の対象にさえならないだろう。せいぜい自らが被りうる事故やリスク、あるいは身近な人などが対象になるだけだろう。 この点で「労働ベース+消極的権利」にもとづく議論は、リベラリスト――たとえばR・ドゥオーキン――の「保険」論とはまったく異なる。もちろん、ドゥオーキンの議論についても「保険」では必要が保障されないという点を指摘できる。だが、上記の契約論を文字通りに体現する人からすれば、せいぜい《そんなことは当然だ》という答えしか得られないだろう。それに対して、ドゥオーキンにとって「保険」は、障害や怪我などの当人の決定に起因しない不平等を是正するためのものであり、その前提には、人びとは相互に「等しい尊重と配慮」をもって処遇し合うべきだという価値がある。この価値を共有している議論に対しては、必要保障の手段としての保険の限界と同時に、たとえば、個人間分配の問題を異時点間の個人内分配問題へと置き換えること自体がその導入理由(相互に「他者を尊重・配慮すべき」だという理由)に反するのではないか、という指摘も成立する余地がある[註9]。それに対して、社会関係を完全に個人の自己利益の向上機能という点から説明する理論には、そもそもドゥオーキンらのリベラリストとが異なり、議論の共通前提が存在しない。ここで、このような「労働ベース+消極的権利」論は一つの価値観を戯画化しているのだと言うとすれば、それはナイーブである。むしろ必要なことは、私たちがこの価値観と拮抗する価値を有しているとして、それらがどこでどのように使い分けられているかを自覚し、それが妥当かどうかを問うことである。 では、この価値観と拮抗する、もう一つの価値観とはなにか。それは、私たちが、協力を得るのに交渉材料をもたない人びとは、与える側の恣意的な贈与に依存しているのだから逼迫しても仕方がない、とは考えないということが示している。じっさい、たとえばとくに、親が子を養育しない場合には「ネグレクト」あるいは保護責任者遺棄致傷/致死罪等として処罰さえされる。家族に課される義務の程度の問題は後述するが、ここで少なくとも次のことは言える。つまり、もし《交渉材料をもたない人は死んでも致し方なし》という立場をとらないならば、何か別の価値観・行動方針があるということを、私たちは認めていることになる、ということである。それは単純に、自力で必要をみたせない場合、他者から支援を得られたほうがよい、という価値観である。 では、積極的な支援活動をすべき場合があるとして、では、誰が・誰に・いかなる理由で・どの程度それを課すことができるのか。またその「べき」という義務が覆う具体的な範囲はどこまでか。たとえば親は子を、どこまで・いつまで世話する責任をもつのか。こうした問いに答えを与える必要がある。
2. 必要ベースの分配様式と積極的自由への権利 2-1. 家族への期待とその問題点 消極的自由の保障という最小限のルールに基づき、自力で生活資源を獲得し合理的に決定・判断する個人同士の合意に基づく契約によって織り成される領域では、自らの生を維持できない人が存在する。多くの人の自発的な「贈与」によって、そうした人々の生の必要が十分にみたされるならばよい。だが、「労働ベース+消極的自由への権利」というルールからは、贈与の相手・内容・量は基本的に諸個人の恣意に委ねられる。それでは、贈与を必要とする人の生は保障されない。そして、贈与する人の生も保障されない。 この点は、すでにフェミニズムの議論が指摘してきたことでもある。現在の社会では、子や高齢者等の世話・贈与は「家族」とくに女性に期待されている。「労働ベース+消極的自由への権利」に基づく領域は、他者を世話せずに済む「男性」をモデルにしている。この男性の立場は、育児や養育そして介護などを必要とする人びとの支援負担を女性に負わせることによって維持されている。 上で見たように、「自然状態」とそれを前提にした「契約主体」のモデルは、生活に他者の協力が必要な人々ではない。社会状態や制度の正当性が、自己利益を追求する諸個人の合意だけに求められるとすれば、他者の利益になる財や技能を持たない人々は契約に基づく社会から排除される。誰も消極的自由を制約(消極的権利を侵害)する者が存在しなくても、生来の能力の差異によって生活を維持できなくなる人びとが存在する。 これまで、こうした「労働ベース+消極的自由への権利」というルールの欠陥を埋める役割は、「家族」とくに女性に期待されてきた。そこには、《女性は自然に子を産み育て、親を介護する(家庭内でケアする)のは当然》という観念がある。この性別役割分業によって、市場における契約主体の生活パターンは、世話する活動をせずに済む男性の生活パターンになる。そして他者の世話を課される人(女性)は、職場で要求される「ケア-レス」(Himmelweit)な男性の生活パターンに従うことができないため、育児休業取得率や離職率等などの基準を用いて合理的に排除されることになる。「雇用継続をしている女性の育児休業取得率72.3%に対して、男性は0.5%(2004年)である。他方、第一子出産後離職した女性が67%になるなど、女性にとって仕事と育児の両立が困難な状況」が、企業にとって雇用の際の判断材料にされているからである[註10]。 家族に委ねることの問題点を整理しておこう。それは大きく分けて二つある。第一に、もっとも大きな問題は、家族をあてにすることは、世話される側が十分に必要をみたすことができる制度ではない、という点である。まず、家族がいない人の必要はみたされない。また、家族がいても、家族が適切な支援者であるとは限らない。仮に家族が引き受けたとしても、家族に過度な負担がかかる場合がある。さらに、世話を受ける側には、家族以外から支援を受ける選択肢が与えられず、恣意的な干渉があっても回避できなくなる。そして、負担をかけているという感覚は、世話に対する要請の差し控えの動機になりうる。第二に、世話する側とくに女性が不利益をこうむる。女性は就職時に差別され、また家族内で劣位に置かれる可能性が高まる。 第一点から確認しよう。まず、世話を受ける側に、家族以外から支援を受ける選択肢が与えられない状況は、恣意的な干渉の可能性を生む。なぜそう言えるのか。一般に、任意の関係性において、その関係性の性質・様態に関して主導権を握ることができるのは、当の関係から撤退することによる損害が少ない側である。必要度が高い側のほうが、それを充足する関係性に対する維持要求が高まる。関係性に対する維持要求が高い側の方が、関係維持のために負う負担の大きさに対する許容度が高くなる(求める側と求められる側の非対称性)。 家族という個別的な関係性に支援関係が限定されている場合、被支援者は、自らのニーズをみたすためには、家族成員との関係性を維持しなければならない。関係性からの撤退がもたらす損害の程度すなわち関係性維持の必要性の高さは、関係維持のためのコストを多く支払わせる動機になる。必要を満たすための援助・被援助関係において、援助される側がその関係性を選択できない場合、関係様式に対するコントロール可能性すなわち自由度は、一般に低下する(ジェンダー役割等でこれが逆転している場合もありうるが、それは稼得者男性が上位に君臨できる一般的なジェンダー・ヒエラルキーが持続しているだけであり、このヒエラルキー自体が、すぐに見るように、この非対称性を説明するのと同一の要因で説明できる)。 また、支援要請を差し控えて我慢している状態に適応し、支援が過少であること自体を、当人が自覚しなくなる場合もある。最初は苦痛を感じていても、程度によるが人は「慣れてしまえば大丈夫」に思えるようになってしまうからである。これはとりわけ家族以外には長期療養所や施設でしか生きられなくなっている人たちが、療養生活のなかで適応していくケースに該当する。満腹時には、贅沢な食べ物からふだんは得られるはずの満足度も逓減する。それとは逆に、渇望しているときには粗末な食べ物でも欲するようになる。痛みが増せば人は、まずはそこから逃れることを最優先せざるを得なくなる。人は、殴られ続けると《これ以上殴られないならば何をしてもよい》と思えてくるものである。同じく、劣悪な状態に置かれ続けると、人は、まずはたとえば「何でもよいから食べること」だけを欲求せざるを得なくなる。そして、要求実現活動を負担する側にとっては、相手が要求を差し控えることは負担軽減になる。 さらに、支援を必要とする側が要求を差し控える理由のなかに「負担をかけている」という感覚が含まれる場合もある。その極にあるのは、「家族の負担になりたくない、迷惑をかけたくないから」という理由で、積極的な治療を拒否して死ぬことを選択するようなケースである。世話を差し控えられることで、自らが他人に迷惑をかけているという感覚が強められ、「これ以上迷惑をかける前に死にたい」という望みがさらに強まる、という救いなきケースが実際に存在する。そしてそれは、上記の諸条件から容易に理解できる(言うまでもなく、理解可能だということと許容可能だということは異なる)[註11]。 また、家族が「ケアユニット」として位置づけられているかぎり、家族に過度な負担がかかる場合がある[註12]。現在の日本社会では、たとえば子の「監護・教育」の義務が親に課されており[註13]、扶養義務も課されている[註14]。だが、それらの義務がどの程度の範囲の負担を正当化するのかは曖昧であり、子や親や同居人の養育や介助や介護は、その大部分が実質的に家族に委ねられている。だが、たとえば、「子が障害を持つことは可能性として予期しておくべき範囲内にあるのか。出生前に障害の有無を診断できるのにそれを行わずに生まれた障害児の介護は、診断をあえて行わなかった親の責任とされるのか。これらの問いへの答えによって設定される義務、義務の範囲は変わってくる」[註15]。具体的な事例は省略するが、親が子の養育負担を回避する回路が保障されておらず、義務の範囲と宛先が曖昧にされていることが、世話する家族(とくに女性)に過度な負担を課している。 次に第二の問題点を確認しておこう。女性にケア役割が課されることで、男性の生活パターンが労働市場で基準とされ、家族をもつか否かにかかわらず、先に示したような統計に基づいて、女性はとくに就職時に不利な処遇を受けることになる。また、家族のケア役割を担う女性は、その生を維持するためには、市場で男性が獲得することに依存せざるを得なくなる(「二次的依存状態」に陥る)。それは、性的行為をはじめとした男女間の相互行為における主導権を、男性が独占しやすい構造の条件になる。現在の社会は、男が「生活のための財の供給を独占することによって女を従属させることができる」[註16]社会である。
生産者に所有権が与えられることで、家族内で男性が女性を支配しやすい構造が作られる。さらに、家族は「私的領域」として位置づけられるため、そのなかでの具体的な相互行為の適切性は客観的なルールによってではなく、個々人の固有かつ特異な人格の関与と自由で自発的な合意(それが「愛」と呼ばれたりする)によって規定されることになる。生活資源の所有権の非対称性と、私的領域に付与される性質が、男性の女性に対する支配関係(干渉の可能性[註18])を構造的に支えている――この観点から、セックスの際の行為の能動性/受動性の役割分担を即物的に反省してみる必要があるだろう[註19]。 家族をもたないとしても、女性の就業機会は削減され、日常生活においても男性優位のコミュニケーション・モードのなかで生活せざるを得なくなる。
2-2 積極的自由への権利 これらの諸問題を解決すべきだとすれば、生を維持するために他者から支援・贈与を得ることが必要な人に、必要なときに必要なものを保障するべきだ、ということになる。 家族に世話負担を期待し、さらに家族内で女性に負担を課すようなシステムを解消するための方策には、様々な提案がある。細かく見れば議論の余地があるとしても、大きな方向性としては、N・フレイザーが提唱する「普遍的ケア提供者モデル(Universal Caregiver Model)」によって提出されていると言ってよい[註20]。それは、「男性を女性=主要なケアワークを行う人びとに近づける」ために「女性の現在のライフ・パターンを万人にとっての規範とする」モデルである[註21]。このモデルは、「家族」の境界を越えた世話・支援負担の分担を要請する。世話・支援が必要な家族をすべての人間がもつわけではないし、必要なケアの程度にも家族間で差異があるからである。家族を構成しない人も、ケアが必要な人のケア負担を――その具体的な形態は様々でありうるが――部分的に担う必要がある。 生を維持するために他者から支援を得ることは、他の人びとに対して積極的な支援活動を要請する。ここで「積極的自由」を、「公的権力」が「他者ではなく自ら自身のものであることを求める」[註22]自由だとすれば、他者の能力を借りて生を営むことへの自由が公的に保障されるべき場面がある、ということである。自由が保障されるべきだという表現を、「権利がある」と言い換えるならば、必要に応じて《他の人びとに対して何らかの行動を取るように要求する権利》としての積極的権利がある、ということになるだろう。もちろんこの権利は、作為的他害の禁止・防止以外の理由で《他の人びとに対して自分に干渉しないことを要求する権利》としての消極的権利[註23]に対立する。 積極的自由(への権利)の要請が「行為させる」ための干渉を含む限り、それは、消極的自由(への権利)を制約するだろう。では、それが許容あるいは要請されるのはいかなる場面だろうか。所有権を制約する財や行為の供出に対する義務は、積極的支援・贈与がなければ生命を維持できない人が目の前にいるような「緊急事態」だけに限定されるのか。 たとえば、現在とくに家族成員に課されていて、しかし分担されるべき負担/分担すべき負担の内容と程度は、いかなる基準で決まるのだろうか。そもそも二つの自由への権利は同位対立するものなのか[註24]。以下では、この二つの自由への権利に対応するとされている義務の性質とそれを区別する基準という観点から、あらためてこの点を考えてみよう。
3. 義務の性質とその根拠 3-1. 義務の性質を区別する基準に基づく検討――コントロール可能性 消極的自由への権利に対応するのは作為的加害の禁止という義務である。他方、積極的自由への権利に対応するのは、支援活動要請を引き受ける義務である。前者の禁止義務は、それを履行しない場合には非難・処罰の対象となるタイプの義務と概ね対応しており、後者は履行しなくても非難されないが履行すれば賞賛される「慈善」に対応する、と一般に考えられている。 義務の性質についての「完全/不完全」という古典的区別を用いれば、他者の所有権の侵害の禁止は「完全義務」であり、他者を積極的に支援する義務は「不完全義務」だとひとまずは言える。この点、完全義務と不完全義務についての諸説の検討を通してM・シューメーカーは、「他者を害すべからず」という否定的な義務が「完全義務」になるのは、それがいつでもどこでも誰に対しても効力をもつからである、と指摘している[註25]。たしかに、とくに物理的な暴力による危害は、脱文脈的(というよりもむしろ文脈破壊的)である[註26]。この義務を履行することは容易である(「何もしない」だけですべての他者に対してこの義務を履行したことになる)。履行しないとつねに非難・処罰の対象になる。それに対して、「他者を裨益すべし」という義務は、それに対応する具体的な行為を指定することが一般的に困難である。他人に利益を与えるべきだ、という肯定的な義務は、そもそもその宛先が特定され、状況が限定されなければ、その履行手段を特定できない。何をすれば履行したか(何をしなければ不履行か)が不明な行為を、たとえば法的に処罰することはできない。何が「利益」になるかについては、人によっても時と場合によっても幅が大きいからである。 こうした区別が一般的に妥当であることは認めざるを得ないだろう。しかしこの議論から読みとるべきは、完全/不完全という義務の性質を区別する基準は「作為/不作為」ではなく、むしろ履行手段の特定性にある、という点である。履行手段の特定性という基準は、一般に帰責可能性の根拠とされるコントロール可能性と重ねてよい[註27]。「作為的加害の禁止」か「不作為の禁止(積極的行為の要請)」かという区別の前に、履行手段の特定可能性・コントロール可能性が、義務の性質と程度を決定していると考えるべきだろう[註28]。前節の議論を踏まえれば、義務としての要請度は、①保障されるべき必要・権利内容の重大さと、②履行手段の特定・コントロール可能性の高さを基準として、これらに比例して高まり、どこかで「不完全」から「完全」に移行するのだろう(一般的には①のほうが②より優先される)。そしてこの基準は、作為/不作為の区別とは必ずしも重ならない。たとえば、生命は保障されるべき諸権利の範囲を設定している(生命は権利の対象ではなく、諸権利を持つための条件である[註29])。積極的行為に対する義務も、誰のいかなる自由を誰がどのような方法で保障できるか、についての特定の程度に応じて強くなる。 じじつ私たちは場合に応じて、損害を与えないように配慮して行動すべきだという「積極的な義務」を認めている。たとえば「善管注意義務」「注意義務」「結果回避義務」である。損害を与える可能性の高い行為、医者の手術が典型的だが、より日常的な活動としては通常の車の運転についても「専門家」として注意義務が要請されている。車に乗る前には、やりたくなくても整備する義務(車検に出すことも含めて)がある。整備不良は、たとえ事故を起こさなくてもそれだけで罰金の対象になる。その理由は、ブレーキやハンドルが故障した自動車を運転することは、他者に損害を与える可能性が高いからである[註30]。 この事実は、損害の程度とその原因に対する制御可能性などに応じて、作為か不作為かは副次的なものになる、ということを示している。その場合、何かをすべきだということになる[註31]。したがって、 (a)特定の行為が害になる場合 → することが禁止される。 (b)何もしないことが害になり、これを回避・軽減できる行為が特定されている場合 → しないことが禁止される/することが要請される。 というかたちで、消極的自由への権利に対応する「作為的加害の禁止」の義務と、積極的自由への権利に対応する「積極的支援行為」に対する義務が成立する。 まとめれば、他者を裨益すべし(他者を害しないよう配慮し行動すべし)といった積極的行為に対する義務はすべて不完全義務であるわけではない。その義務の程度は、それに対応する他者の権利内容の重要さおよび履行手段に対する自己のコントロール可能性に比例して高まる。他方、完全義務のなかにも要請度において高低がある(でなければ量刑判断は不要である)。作為的加害は基本的にすべて禁止され、処罰されるが、たとえば「動機を形成するに至った事情に酌量の余地があるか否か」等々によって個々の刑の重さは変わり得る。
3-2. 自由の内容、義務の要請度、そしてその決定基準 必要および自由への権利に対応する義務の性質および要請度は、保障されるべき自由と必要の内容に応じて変わる。では、保障されるべき自由・必要とは具体的には何を指すのか。またそれは、いかなる基準で決めればよいのか。 まず、保障されるべき自由は、「損害からの自由(安全)」という語が想起させる物理的・身体的な被害よりも、広くとられるべきだろう。私たちはたとえば、信教の自由や政治的活動の自由は保障されるべき対象になるだろうし、一定の自由時間をもつことやレジャーのための経済的な自由も含めてよいと考えている。では、軽減・解消されるべきものの範囲を、いかなる基準で決めればよいのか。まず、それを、諸個人の主観に完全に委ねることはできない。当人がたとえ切実に望んでいたとしても保障対象にならないものがあるし(高価な嗜好)、逆に、たとえ当人が享受(制約の解消)を望んでいないとしても、保障されるべきだと言えるものもある。 また、たとえば「栄養失調と脱水で意識が朦朧としており、もはや独力で回復不能」等、すでに当人がその身体と生命の保全活動能力を失っているような場合、たとえその原因が当人の怠惰等にあったとしても、社会はその人を救助できるならば救助体制を保障すべき義務がある。たしかに、「自業自得なのだから痛みを甘受せよ」と言えるような場面もあり得る。だが、緊急状態ではそうは言えないとすれば、他者に要請される義務の程度は、当人のその時点でのコントロール可能性の喪失度(緊急度)に応じて高まり得るということになる。仮にその結果を生じさせた原因に対する当人のコントロール可能性や関与の度合いが高かったとしても、当人が選択し決定した結果は「自己責任」だから全面的に当人に引き受けさせてよい、とは言えないケースもある[註32]。だから、たとえば、結果をもたらしたのが「選択の運(option luck)」だったか「自然の運(brute luck)」だったかに応じて保障の範囲を決定しようとする議論は、その時点での事態に対するコントロール可能性という軸を看過している点で包括的ではない。 さらに、たとえば、仮に当人が熟慮して死を望み、頑として説得に応じようとしない(そしてその態度と選好に何ら変更可能性がない)としても、私たちは「そういう人は自殺しても仕方がない」とは言わない。また、そういう人は救急救命の対象にすべきではない、とも思わないだろう。自殺未遂の常連者でも救急救命の対象になる。もちろん、実現した状態に対する当人の態度の肯定度や[註33]、その原因に対する当人の選択可能性の程度が、結果が当人に課す負担の軽減や損害の解消のために、他者に課されうる義務の要請度を低下させる場合もある。しかし、「これでいいんだ、放っといてくれ!」と言われても介入や説得の試みが推奨されたり、さらに介入が要請されたりする場面がある。目の前で飛び降り自殺しようとする人を羽交い絞めにして止めた人に対して、仮にその際、助かった人が不可抗力で怪我をしたとしても、私たちは怪我をさせつつも止めた人を賞賛することはあっても、「君はその人に暴行を働いたのだ」として非難したりはしない。また、そのような場合に止める責務を負う役割を担う人を、制度的に保障することも肯定されるだろう。 上記の議論のどこまでに同意するかによってその内容と程度は変わるが、少なくとも私たちは、たとえ当人が拒否していても保護されるべきものがある、と考えているはずである。では、医療現場で医師が「死にたい」と言う患者の自己決定を覆そうとして説得することや、患者の意思に反して救命措置を行った場合はどうか。諸条件をめぐる議論を省略して言えば、生命を維持した医者を非難も処罰もすべきではないと言えるだろう。 もちろん、当人の意に反しても当人のために保護されるべき利益があるとして、それを保護するだけでよいというわけではない。現に自傷や自死しようとしているのを防ぐためにその時点で拘束することが許容されるからといって、その後も拘束し続けておけばよいとは言えない。逆に、当人がどれだけ要求しても保障されなくてもよいものもある。もちろんこれは、それが「保障できるか否か」という軸とは別である。たとえば「恋愛」は保障できない。恋愛は、当事者相互の自発性以外にものに媒介され得ない関係性だと観念されているため、「保障」された瞬間、恋愛としての性質を喪失するからである。 そして、他者に保障されるべきものの内容とその要請度は、誰にどの程度の負担が課されることが許容されるか、にもかかわる。では、具体的に、同居している人には他の人びとに比して高い保護・養育等の義務があるということになるのか。それには、あると言わざるを得ないだろう。同居人は、養育や介護が他の人よりも容易にできるため、それに応じて義務の程度が高まることを否定することはできない。しかしその義務は、同居するか否かについての自由が確保されていることが前提である。またそれは、養育・介護者自身の経済的・時間的・活動の自由を保障するための、他の人びとによる支援義務と両立するだろう(具体的にいかなる制度が望ましいか、についてはここでは措く)。 だから、生命の維持そのものにかかわるような重大な「必要」や「自由」にかんしては、たとえば日本に住む人びとにもアフリカで飢えている人や難民の人びとに対して支援する義務があるように、自らの行為可能性の程度に応じて積極的に活動する義務がある。その義務が課す負担の内容と程度を決める客観的な基準はないだろう。だが、だからといって諸個人の主観的な判断にすべてが委ねられているわけでもない。[註34]
4. 公共性への問い 4-1. 負担の計算、受容条件、公共性 見てきたように、必要・負担・自由・権利・義務にかかわる諸論点は、コントロール可能性の配分という観点から再整理できるだろう。言うまでもなく、生命にとっての「必要」は当人にもコントロールできない必然性である。制約と負担の内容と程度に応じて、その解消と軽減のために他者に課される負担に対する要請の強さは変わる。生命維持を極として、保障されるべき必要・権利・自由には重みが異なる。この重みに応じて、実現のために他者に課される義務は強くなる(負担・制約が許容される範囲は広がる)。こうした優先順序と重み付け問題を回避することはできない。 保障対象になる必要および自由の具体的な内容を決める方法について、齋藤は「保障を要求しうると自ら判断する個々の当事者の主張(およびそれを支える理由)が受容可能なものであるか否かを公共の議論において検討すること」が「適切なアプローチ」であると述べている[註35]。この指摘は妥当だろう。とくに、たとえ「公共の議論」に委ねられる余地なく認められるべき基本的な必要があると言えるとしても、その手段が他者に課す制約の範囲には限界があり、そのトレードオフは別途議論の対象になるからである。ある人の生存にとってたとえば腎臓移植が必要だとしても、その提供を他者に「義務」として課すことはできないだろう[註36]。 要求内容に応じて、またその実現のために個々人に課される負担の質量の大きさに比して、要求に対する義務の性質も強度も変わる。要求を受容するとは、そのための負担を負う側がその分担を引き受けることである。だが、どの程度の負担を受容すべきかについて、諸個人の主観的決定やその集計を無条件に基準にすることはできない。保障されるべきものの範囲の決定基準について指摘したことが妥当だとすれば、そのために負うべき義務や負担の範囲の決定基準についても同じことが言えるからである。つまり、誰の何を保障するために何をどこまで負うべきか、に関して、諸個人の「主観的な判断」は最終的な根拠にならない場合があるということだ。たとえば「私」は、自らが担うべき負担の程度を、誰が何をどれだけ要請しているか、についての手持ちの判断材料を用いて重み付けし、判断している。だが、その私の決定は「贅沢な嗜好」にもとづいているかもしれない(それは逆に、他者に分担を要求してよい、と私が判断している程度についても言える。つまりそれは実は――その可能性は低いが――「倹しい」のかもしれない)。 この点に関しても、任意の要求を「公共的」に受容するための条件を、「それを退けうる理に適った理由を挙げることができない」[註37]という点に求める齋藤の議論は妥当だと言えるだろう。これは、受容可能性の条件を「理性的拒絶不可能性」に置くということである。この規定には、受容可能性を広く開いておくことができるという点で意義がある。この規定は第一に、要求の受容条件を制限するのではなく、拒絶条件に限定をかけており、第二に、「理に適った理由」という限定によって拒絶条件が厳格になっているからである[註38]。 この議論についてさらに見ておくべきは、この規定もまた、重み付け問題にかかわっているということである。任意の「要求(A)の受容」が問題になるのは、それが他者(複数)に何らかの負担を課すことになるからである。さらに、ある「要求(A)の受容」が「要求(B)の拒絶」になる(その逆も真)というケース、つまり両者が排他的な二者択一になるようなケースも少ないとは言えない[註39]。その場合、「要求(A)」の実現のためにここまでの負担ならば受容すべきである(「要求(B)」は却下すべきだ)という主張が、それを退けるに足る理由があるかどうかについての吟味にかけられる。 もちろん、こうした要求間の直接的なトレードオフは、何らかの望ましくない状況制約を前提にした「強いられた二者択一」である、という指摘もある。そして多くの場合それは妥当である。その場合、負担を分散させることで、排他的な二者択一や権利間の衝突を回避することが目指されるだろう。またじっさい義務の許容度と負担の程度の比例関係からも、分担者が増えれば負担は軽減し、履行容易度が高まるため、個々人に対する要求も容易になる(「この程度のことならすべきだ」と言えるようになる)。しかし、ここでも確認しておくべき点は、強いられた制約を問題化する議論も、負担の計算を前提にしてしか成立し得ないということである。多くの人が軽い負担で解消される「べき」問題だ、と述べていることになるからである。 また、この計算を、たとえば《人さえ増やせば個々人の負担が軽減されて目的の実現可能性が高まる》といった、ありがちな「人材調達論」と区別しておく必要がある。最後に、この区別を通して、負担の配分問題が、社会的協働の基礎としての倫理的な「べき」「べからず」にかかわる公共的問題である、ということを明らかにしておこう。
4-2. 理由共有可能性と実現可能性 「人材調達論」では、個々の分担者に、分担理由が共有されている必要は必ずしもない。人材調達論にとって第一義的に重要なのは、目的の「実現可能性」だからである。しかし見てきたように、負担の配分問題がその「理由の公共性」の問題であるとすれば、分担に対する「理由」の共有可能性という条件が課されることになるだろう。この観点からすれば、目指されるべき点は、分担理由の承認と共有が「協働関係」の媒体になることである。 たしかに現実には、理由が共有されていなくても、他の媒体によって協働関係そのものを実現することは可能ではある。「人材調達論」の余地はここに生ずる。しかしもし、負担分担問題に答えるのに「理由の共有」など無視してよい、と言うとすれば、他者の承認や了解は、単にその答えに沿った政策実行を容易にするための手段としての意味しかもたなくなる。それはある種の(たとえば植民地総督府功利主義的な)密教道徳と区別されないだろう。だが、このような立場は、自らの「論」としての存立の基盤を遡及的に否定することになるだろう。密教はその内容が一般的な他者に向けて語られたときには、密教としての性格を失うからである。逆に言えば、他者の了解が不要ならば、他者に向けて語ること自体に意味が見出されなくなる。 それに対して、私たちはむしろ、次のように考えるべきだろう。つまり、たとえ最終的に「議論の余地なき結論」を導き出すために論証しているとしても、論証の遂行過程そのものが、その結論を掘り崩しうる可能性を原理的に排除できないのだ、と。言い換えれば、仮に「議論の余地なき結論」が結論として前提された議論でも、その導出過程そのものが、すでにその結論の妥当性の説得の過程になっており、そこでは理由の共有可能性に向けた語りを免れない。とすれば、私たちは遂行的に、理由共有可能性に向けて「説得」するという立場をすでに引き受けてしまっているのであり、また、その立場を引き受けないことはできない、ということになるだろう。 行為理由と行為とに何らかの(内在的)関係があるとすれば、理由共有可能性は実現可能性の十分条件になる。さらに、「理由共有可能性」を自らに課す立場と課さない立場との違いは、《諸個人の主観的な判断が必ずしも正しいとは限らず、人々の意見の一般的な集計による決定が必ずしも正当性を持たない場合がある》という認識をどのように位置づけるか、にもかかわるだろう。 私たちは、《諸個人の主観的判断が必ずしも正しいとは限らず、その集計と同意の結果がすべて正しいとは限らない》ということを知っている。この「諸個人」のなかに自分だけが含まれない、とは誰も言えない。つまり私たちは、自らの主観的判断・計算が必ずしも正しいとは限らないということを知っている。これは、私たちは自他の判断・計算の正否を判定するような「客観的な基準」をもっていない、ということである。これを認めることは、たしかに主張の力を弱めるかもしれない。だが、それは悲観すべき事態ではないだろう。むしろそれこそが、具体的な要求とその理由を、その共有可能性に向けて提示し説得するための条件だからである。 5. おわりに 私たちは、現時点で手持ちの判断材料を用いて、主観的な基準で下す自らの計算と判断が必ずしも「正しい」とは限らない、ということをすでに知っている。言い換えれば、私たちは、自らの主観的な判断と重み付けのどこがなぜ間違っているか、をあらかじめ知ることはできない。そしてこの(いわば)非知の知は、それ自体が公共的な妥当性への問いの条件である。 必要なことは、具体的な負担の配分問題に即して、判断基準を明示しつつ、自分自身を可能的な負担分担者に含めて[註40]、あるべき方策を提示することである。それは、「この具体的要求(A)の実現のためならば、私たちはこれくらいの負担ならば分担して負うべきではないか。なぜなら……」といった形になるだろう。そしてこの理由共有可能性への問いの宛先はもちろん限定されない。
★プロフィール★ 堀田義太郎(ほった・よしたろう)日本学術振興会特別研究員。専攻は医療倫理学、障害学。共著に『はじめて学ぶ西洋思想』(ミネルヴァ書房)、「優生学とジェンダー――リベラリズム・家族・ケア」(大越愛子・井桁碧編『脱暴力へのマトリックス』青弓社)、論文に「決定不可能なものへの倫理」(「現代思想」第34巻第41号)、「ケアと市場」(現代思想」第36巻第3号)、「性売買と性暴力――身体性の交換と自己決定の限界」(『女性・戦争・人権』第8号)、「生体間臓器提供の倫理問題――自発性への問い」(『医学哲学・医学倫理』第24号)など。 http://www.arsvi.com/w/hy03.htm Web評論誌「コーラ」04号(2008.04.15) 〈倫理の現在形〉第4回「負担の配分――生存・義務・公共性をめぐる試論」堀田義太郎 Copyright(c) SOUGETUSYOBOU 2008 All Rights Reserved. |
| 表紙(目次)へ |