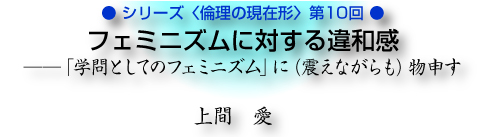|
|
|
Web評論誌「コーラ」 |
|
■創刊の辞 ■本誌の表紙(目次)へ ■本誌のバックナンバー ■読者の頁/ご意見・感想 ■投稿規定 ■関係者のWebサイト ■プライバシーポリシー |
|
<本誌の関連ページ> |
|
■「カルチャー・レヴュー」のバックナンバー ■評論紙「La Vue」の総目次 |
Copyright (c)SOUGETUSYOBOU |
|
|
|
1.フェミニズムに対する反応:バックラッシュとフェミ嫌いと「やり過ごせない」違和感
私はアカデミズムの場でフェミニズムに携わる若年フェミニストとして、フェミニズムに対して違和感を抱き続けている。フェミニズムによって私自身が救われた経験を持ちつつも、何か、やり過ごせないひっかかりが残る。この違和感はいったい、何なのか。
「フェミニズムに対する違和感」が、異議申し立てや反動などの形で現れたのは、最近のことではない。海外に視点を移せばフェミニズムに対する批判は、もっと以前から展開されてきた。1980年代のアメリカにおいて、「フェミニズムは白人高学歴女性の諸権利を拡大していくもの」という異論を唱え、「ブラックフェミニズム」としてその意義を唱えていこうとした1人に、ベル・フックスがいる。彼女の著書『ブラック・フェミニストの主張──周縁から中心へ』から、当時彼女がどれほどの勇気を持って、黒人女性として声を上げていったのかがうかがえる。白人のフェミニストたちについて、フックスは次のように手厳しく分析する。
白人フェミニストたちがあまりにも自文化中心主義的であったこと。そして白人エリート富裕層としての特権性や権威性に無自覚であったこと。これらに対する第三世界の女性たちからの批判は、現在の多様なフェミニズムの声を形作っているといえる。
日本においても、「従軍慰安婦」関係者、アイヌの人々、在日韓国・朝鮮の女性たち、被差別部落の女性たち、障がいを持つ女性たち、セクシュアルマイノリティらからの異議申し立てがなされ、性差別だけにとどまらない重層的・複合的な差別の問題が、フェミニズムに対しても突きつけられた。
最近の日本における、フェミニズムに対する違和感・嫌悪感の事例としては、ジェンダーフリー・バッシングが挙げられるだろう。ジェンダーフリー・バッシングとは、主に教育現場における性教育が「行き過ぎたもの」として攻撃されたことに端を発し、その後、「ジェンダー」や「フェミニズム」といった言葉が入った書籍が公立の図書館の開架から取り除かれ、排除されるという「フェミフォビア」とでもいえそうな現象が全国に瞬く間に飛び火していった一連の出来事である。そこで反応していたのは、「女性らしさ/男性らしさ」という規範、貞操や道徳を守りたい保守派の政治家や教育者であった。
ジェンダー論の研究者伊田広行は、バックラッシュの主体である「保守派」の動きを支えたのは「フツーの人」だったという(伊田 2005)。また社会学者の鈴木謙介も、フェミニスト嫌いを表明していたのは「保守派」の人々だけではないとし、バックラッシュに一定の理解を示す「普通の人々」がいたからこそ、バックラッシュは政治的実効性を持つに至ったと分析している(鈴木 2006)。
場所を現代の日本に限定してみると、フェミニズムに対しての違和感・拒否感・嫌悪感は、家父長制を生きる「保守層」と「普通の人々」と「フェミニストを自称する者」から出されているとみていいだろう。前二者、つまり、保守層からのフェミニズムへのバックラッシュと、それを支える「普通の人々」の嫌フェミニズム的な態度に関する分析は数多くなされている(註1)。たとえば、バックラッシュについて多くの論考を出している荒木菜穂は、「将来の生活への不安、自己イメージの不安定化は、自己の防御のための、癒しとしての差別、憎悪の必要性を生み出」し、その結果、「平等なはずなのにエリート層の恩恵を受け、特権を得ようとするマイノリティへの「逆差別」意識がもたれる」ようになり、「「逆差別」として捉えられたフェミニズムは、「勝ち組」「負け組」双方の男女から嫌われることになる」と、そのメカニズムを明らかにしている(荒木2007)。
以上のように、フェミニズムに関する違和感・拒否感・嫌悪感は多々あろうが、ここで私は、私のフェミニズムに対する違和感と、いわゆる「バックラッシュ」や「嫌フェミニズム的態度」とを区別しておきたい。後発のアカデミック・フェミとして、先達のフェミニストたちに対して違和感を表明することは、フェミニズムを攻撃してそれを無きものにしようと目論む「保守層」の利益となる「利敵行為」になりかねないからである。私にはバックラッシュのような、フェミニズムが勝ち取ってきた「女の言語」を女の手から再び取り上げ、性差別を野放しにしていく意図は全くない。私が「第一に対抗相手にすえるべき他者」は言うまでもなく、バックラッシュを起こしている保守層である。そして場合によっては、保守層のバックラッシュを支えている嫌フェミニズム的な「普通の人々」も、フェミニズムが告発し糾弾することによって築き上げてきたものを無に帰さないために(また、女性としての自分自身を生きやすくするために)、対峙しなければならない相手となりうる。
上記のことをご理解いただいたうえで、いよいよ今回の論考の主題である「フェミニズムに対する違和感」に詳細に論じていきたい。
「フェミニズムに対する違和感」を検討する方向性としては三つある。一つ目は、フェミニズムが主として展開されている場所が、運動とは対局の場にあるという感覚に根ざしたものである。特に、女性学やフェミニズムが大学という高等教育の場に入り込み制度化していったことの効果について考えてみたい。またその際、「学問としてのフェミニズム」の比較の対象として「運動としてのリブ」を参照し、論じてみたい。
二つ目は、一つ目と関連が深いのであるが、フェミニズムが学問の営みとして他者を分析・表象することに潜む暴力性に注目する視点である。フェミニズムが学問である以上、その研究対象が必要となる。そして多くの場合、フェミニズムの研究対象は、性差別構造・性抑圧構造にある女性たちとなる。他者を「分析」し「考察」する立場としてのフェミニズムの特権性・権力性について論じてみたい。
三つ目は、「フェミニズムは若者の声や新たな経験を掬うことができるか」という視点である。フェミニズムが展開されているアカデミズムの場は、新規参入者である「若年」研究者にとって、理論と研究実践の訓練と習得の場である。このような場において、若年者の経験は言語化できるのであろうか。とりわけ若年者の経験が先達のフェミニストにとって「新たな経験」であった場合、これが考察されるべき重要な経験として取り上げられる余地はあるのであろうか。この問題について考えてみたい。
これまで、「フェミニズムとは何か」「フェミニストとは誰か」を明確に定義せずに論じてきた。定義そのものについては、フェミニズムの内部においても異論渦巻くところであろうが、ここでは、フェミニズムをさしあたり、「性別という属性による抑圧や暴力について、異議申し立てをおこなう思想や運動」(荒木 2007)、もしくは「性差別をなくし、性差別的な搾取や抑圧をなくす運動」(フックス 2003=2000)としておきたい。
フェミニズムが辿ってきた道のり、取ってきた立場性は本当に多様性に富み、男並の平等をめざしていく方向性を取る者や、オルタナティブな生活実践を行う者などがおり、一括りにはできず、誰がフェミニストなのか明示しようとすればするほど、それは影のようにどこかへと消えていってしまい、それが造られた像であることを思い知らされる。
けれども、私が「フェミニズムに対して違和感を抱いていること」という現実からは逃れることができないし、私が違和感を抱く対象としての「フェミニズム/スト」が一つの実像を結ばない幻影に過ぎないからといって、私の違和感までも雲散霧消していくわけではない。人種、民族、セクシュアリティの点においてマイノリティに属する人々が、彼ら自身が生活していく過程で感じた「違和感」を言語化し、世の中に対して異議申し立てした途端に、「それは思い込みにすぎない」「単なるルサンチマン」「被害くらべにすぎない」などという反応で、彼らの声は無視されてきた歴史を考えるとき、今回の私の論考もそのような無視で迎えられる可能性を孕むものだと危惧しつつ、論じ始めることとしたい。
2.「フェミニズム=理論・学問、リブ=運動」という構図
運動の場では、「フェミニズムと言えば主に大学において担われている」という感覚が共有されているように思える。そこでまず、フェミニズムに対する違和感を明らかにする際に、この視点に立ったうえで、「フェミニズム=理論・学問」の比較対象としてのリブについて考えてみたい。
「リブ」と言えば田中美津が真っ先に思い浮かぶ。彼女が書き溜め、フェミニズムと対置されて語られる「リブ」から伝わってくるものとは、「〈ここにいる自分〉から出発する」ということである。そして、女性排外主義、家父長制を基本とした社会システムの中で、「女としてのわたしの解放」を叫びつつも、男を目の前にして思わず正座してしまう、そのような矛盾した自分を〈取り乱し〉という言葉によって、自己否定から自己肯定の高みにまで持っていく、その卓越した矛盾の表現力である。
自己肯定。田中の言語はそこに尽きる。矛盾する自分のその一部を切り捨てたり踏みつけたりせずに、しっかりと受け止め、自分の感覚をその身体性ごと言語化する思想が、そこにはある。田中は言う。「私が敬愛する上野千鶴子さん。彼女は「ウーマン・リブはしっかりと私たちのフェミニズムに継承されている」と言う。そうかなあ。継承されたのは上っつらの理屈の部分じゃないかしら。」(田中 2010)
フェミニズムも当然、当事者である女性から出発した当事者の思想、学問体系であることは間違いない。そして家父長的、性差別的なシステムを自ら支えさえもする女性の姿を、フェミニズムも明らかにしてきた。
しかし、フェミニズムが展開されている大学、大学院という場では、先行研究を押さえるという形で先人のフェミニズムの思想とその意味をしっかりと「誤解なく」把握し、その上で自論を展開すべし、というフォーマットが用意されている。用意されているというよりも、それ抜きには、一人前の「研究者」として認められない。このような環境では、自らの違和感、経験を言語化したとしても、「それは以前に○○という研究者が言っていることで目新しいものではない」という指摘を受け、新規性のある創造的な語りを期待される。
リブを経験し、かつ大学院という場で研究した経験もある菊地夏野が指摘するように、そのような古典的なディシプリンにフェミニズムの問題意識をあてはめるよりも、ディシプリン自体を変えていくような力が必要かつ魅力的である(菊地 2005)。にもかかわらず、積み重ねという体系化を重んじるあまり、私たちアカデミシャンとしてのフェミニストは、〈どこにもいない女〉を立ち上げ、〈ここにいる自分〉を抑圧し、切り捨ててしまうことを余儀なくされる。
また、フェミニズムが大学という場で展開されていることには、次のような問題が指摘されている。前述の菊地によれば、「新自由主義的システムへと向かう社会環境の変動は、大学にも無縁ではないどころか、大学を重要な一拠点として進められている」という(菊地 2005:42)。そのため、大学を基盤とするフェミニズムは、家父長制や性差別的な社会システムを解明しながら、「選択するのはそれぞれの女性」とでも言わんばかりの、自己責任論的な空気を醸し出している、と受け取られてしまうのも不思議ではない。
フェミニズムは、性差別や性抑圧構造を告発していく段階において、女性を「抑圧されたもの」として一旦は同一化・一元化したといえる。このことは、「女性」というカテゴリーを被差別者・被抑圧者として固定しまう効果を持ったことが、意図せざる効果として指摘されている。その一方で、大学教育の場でのフェミニズムは、女性、とりわけまだ差別体験の少ない大学在学中の女性に、「わたしのことはわたしが決める」という主体性・自己肯定の言説に触れる機会を提供した。しかし、一歩大学の外に出れば、そこには性差別的なシステムに覆われた社会が広がり、主体性を持って選択できることは限られている(註2)ことが露呈する。
さらに、大学という場の現在の状況を考慮してみると、事態はいっそう深刻である。まず学位取得後のポストが圧倒的に不足していること、それにも関わらず、大学院重点化計画の影響で大学院進学者の数は増加する一方であり、大学院生は競争の渦の中に否が応でも飛び込まざるを得ないこと、そしてその結果、一部においては、大学院での研究自体が、消費財と化してきつつある(上野 2001)。フェミニズムもまた「消費財」「お勉強するもの」として捉えられるとしたら、〈どこにもいない女〉をフェミニズムを学ぶ上で学習し、江原由美子(1991:98)が驚いたような「フェミニズムを行動指示命令と読んでしまう」(つまり、教科書的に「こうすべきもの」として読む)学生が出てくるのも当然であり、フェミニズムの思想を個人の行動規範としようとして振り回され、フェミニズムに対して「いったいどうしろっていうんだ」と不満を抱く者が出るというのも、当然といえよう。そしてそれは、「学生の読みの幼さ」として片づけられる性質のものではないはずである。
運動としてのリブは自分たちの経験を自らの言葉によってその身体性ごと発信していった。それに対して、学問としてのフェミニズムは、客観性・根拠を持ちあわせるために他者である「女性」の経験を対象とし、〈どこにもいない女〉を(意図せざる結果だとしても)立ち上げてしまい、その理論を業績として蓄積していったといえるならば、リブと同じ「当事者主義」ではありつつも内実としては、リブとフェミニズムにはかなりの開きがあることにならないだろうか。
3.学問としてのフェミニズムの権威性
フェミニズムが制度化し、高等教育の場で展開されるようになったために、「自分ではなく他者を記述の対象とする」ということが学問的要請となった。「対象」を選び、データを取り、分析する。そのこと自体は「社会制度」の方向付けのためには必要なこともあろう。しかし、そこには二つのこと──「業績のために対象者の女性を利用する」ことと「分析し、解釈し、結論付ける」こと―が不可避の要素として立ち上がってくる。他者を表象することは、それ自体、暴力であり搾取であると言える(註3)。「当事者学」を謳いつつ、他者としての多数の女性の経験、生きざまを調査し分析し解釈づけることの特権性と、フェミニストの人たちはどのように折り合いをつけているのだろうか。
日本女性学会が発行する学会誌『女性学』の第8巻(2000年)において、「女性学と「権威」化―他者を表象することをめぐって」という小特集が組まれ、幾人かの女性学研究者、フェミニスト・リサーチャーがその葛藤を、自らの体験として生々しく記している。「フェミニストであることと研究者であること──個人史を題材に」というタイトルで、辻智子は1950年代に紡績工場で働いていた女工たちで構成される「生活を記録する会」のメンバーを対象とし、当時の生活記録に書くことができなかった思いやその後のことを聞き取ることによって修士論文を書こうとした時に抱いた罪悪感を四つ記している。それらは、「修士号を取得するという利己的な目的のために、相手を利用しているのではないか」「何の権利があって人の経験を俎上に乗せ料理しようとするのか」「戦後日本の経済「発展」のツケを農村に負わせてきたことに対する負い目」「話してくださった方々の信頼を裏切っているのではないか」というものであった(内藤・辻 2000:106)。辻は次のように記している。「こうした罪を意識するにつれて、私は、もうこんりんざい論文なんてものは書くまいという思いを強くした」(ibid:107)
また、セクハラやDV被害者の調査に関わってきた内藤和美も同じような悩みを抱え、自身がしてきたことを「集められた記述に加えられていく私の言葉は、他者の経験を説明〜定義してしまうという暴力であった」(ibid:113)と振り返り、現在は二次資料を扱う方向へシフトしていると吐露している。
フェミニズム研究を行う際に、直接に他者に接触することなしに「女性」を対象とし分析する方法として、二次資料分析や理論研究が行われることも可能でありかつ必要であるが、もしそれが「他者としての女性」と接しない手段として選ばれた研究手法であったとしたら、それは忌々しき事態であろう。しかし当然、私はその「忌々しさ」は内藤などの、辛さゆえに二次資料に携わるようになった個々のフェミニスト・リサーチャーに帰責できるものではないと考えている。むしろ、このこと自体がこれまで何度も問題提起されてきたにもかかわらず、さほど掘り下げられることもなく現在に至っている状態そのものが問題とされるべきであろう。
しかし、たとえ辻や内藤が「自己内省的」に自らの研究上の葛藤を書き記し、「研究」や「研究者」にもれなくついてくる加害性・権威性を問題の俎上に乗せようとしたとしても、論文を対象者自身のことばとしてではなく、研究者個人の業績として書きあげてしまえるような現在の研究システムをそのままにしている限り、単に自分の罪悪感を吐露したに過ぎないのではないだろうか。彼らは他者を表象し搾取するという「研究者としての加害者性に向き合った」といえるのであろうか。自戒を込めて、私はこのような疑問を持たざるを得ない。
しかしこの「研究にまつわる権威」については、学問としてのフェミニズムに限ったことではない。アカデミズム全般が抱える、常に自問していくべき性質の問題であり、フェミニズムだけが「研究対象の方々に対して権威的に振舞っている」という誹りを受けるのはアンフェアなのかもしれない。
しかし、フェミニズムが性
この「フェミニズムの研究としての権威性」は、比較的若いフェミニストたちの間から提起されてきた問題である。研究職に就くフェミニストたちが、運動の場にいるフェミニストたちや研究対象となってきた女性たちから受ける批判の目は、フェミニズムが大学という場で再生産されるに至った今日においての、先達フェミニストの代から続く「積み残し」の課題といえるだろう。
4.世代間の対立:若年者の経験はフェミニズムで言語化できうるか
次に、フェミニズムに対する違和感について、三つ目の視点「フェミニズムは若者の声や新たな経験を掬うことができるか」から考えてみたい。
これは一番難しい論点、むしろ論点にもならない愚痴と捉えることもできる類のものかもしれない。というのも、フェミニズムが展開されている場である大学は、研究機関であると同時に「教育機関」でもあり、そこではそこに所属する若年者、すなわち「学生」の「成長」と「育成」が前提となっている。大学では、「無知」で「無能」な学生は、「学習」し「知識を身につけ」研究方法を「習得」していくことが期待されている。「若者の声を掬うことができるか」という問いは、その「自明の前提」を疑問に付すことと同義であり、それはひいては「学生の本分」を放棄すること、すなわち、アカデミズムの場でフェミニズムを展開することを放棄することにも通じかねない。異議申し立てをすると同時に、自分の立っている地盤を掘り崩していくようなものである。しかしこれは院生フェミニストである私にとって切実な問題である。
新参者のフェミニストあるいは研究者である私が、自分の経験を出発点として研究を行おうとするとき、私はまず先行するフェミニズム理論や研究成果を読みなおし、私の経験がどこに位置付けられるのかを見極める。しかし私の経験・感情・違和感などは、そもそも最初から言語化できない代物であって、その段階においてそれらを既存の論じられた枠組の中で論じられるかどうかなど、解りえない。また先に述べたように、私の論じようとしていることが既に論じられていると
ここで「見做されれば」と強調したのには理由がある。つまり、私の「女性」としての経験=研究を、「価値がある」もしくは「既に論じられている」と「見做す」のは私ではなく、その道の先を行くフェミニストでありアカデミシャンである。そこにおいて私の経験を語る私の言語・文法は、既存のフェミニズムの体系に沿ったものであると同時に、専攻するコースのディシプリン(例えば社会学や歴史学)に則ったものでなければ認められない。仮に認められたとしても、その時点において私は、「語る言語(理論)」と質と量に不釣り合いなほど、「語る内容(経験)」を失っているかもしれない。
これは、「若者の経験はフェミニズムで掬い取ることができるか」という観点からすると、思いのほか深刻な事態であると思われる。くどいようだが、フェミニズムは主に大学という学問の場において展開されている。大学の外において、女性同士がリブの時のように連帯できるような場所があればまだしも、比較的若い年齢層の男女がフェミニズムにじかに触れる場がほぼ高等教育機関のみであるという現状では、もしフェミニズムにアクセス可能な時期、すなわち大学および大学院在学中を過ぎてしまえば、彼ら/彼女らがフェミニズムに「偶発的」に出会う確率は大幅に低下してしまい、意識的にアクセスしようとする努力がなければ出会いはないだろう。フェミニズムは「経験の理論化」(上野 2001)であるが、先達フェミニストが理論化した彼女/彼らの「日常的な経験」を実感する年頃(例えば、就職時、結婚時、出産時など)には、フェミニズムに触れる機会はかなり少なくなっており、目に入るのは巷にあふれる「嫌フェミニズム」的言説ばかりなのである。もちろん、すべての若者がフェミニズムと出会う必要性はない。しかし、ことが現状のままであれば、フェミニズムにおいて「若者の経験の言語化」はいつになっても達成されないことになる。それどころか、「若者の経験」を感知する感性さえも、刷新される機会を失ったまま、既存のフェミニズムにとって価値ある「日常の経験」のみが、理論化され続けることにつながりかねないのである。
さらに、大学内部におけるフェミニズムとの出会いそのものもまた、不幸なものに終わる危険性を孕んでいる。まず、若い年齢層の男女の経験のうち、既存の枠組に則った形からはみ出す、もしくは感知できないものはそもそも表現されず、生産されるのは既存の理論体系に合致したものばかりという事態が引き起こされかねない。また、「フェミニズムとアカデミズムの不幸な結婚」を著した菊地は、「フェミニズム理論のテキストは(中略)知識と訓練のある読者には参考になるが、そうでない読者を排除する結果になっている」(菊地2005)と述べる。フェミニズムが理論よりも「経験」に重きを置く思想だからこそ、かえって「経験していない者」、すなわち若い年齢層の男女やそれとは別の経験をした者がその思想にアクセスしがたい疎外状況をつくり出しているともいえる。
「フェミニズムは若者の経験・声を掬えるか」という問いに対して、フェミニズムは、現在の状態においては、否定的な回答を出さざるを得ないのではないだろうか。それは、フェミニズムが展開されている大学という場が、社会の他の構成体と同じく、若年者差別を前提とした場所であることに起因しているからだと考えられる。とはいえ、「教育」という発想そのものが若年者に対する差別、抑圧を生みだしていると言ってしまえば、人間が発達・成長していくことを前提として設計されている近代社会においては、身も蓋もない話になってしまう(註5)のであるが。
1980年代中頃、アメリカにおいて当時71歳になるバーバラ・マクドナルドが、若い世代のフェミニストたちの「高齢者差別」に対して異議申し立てを行う論考を発表した。以来、高齢者差別には「エイジズム」という概念が付与され、この概念は、高齢者介護の現場における虐待や医療現場における医療者の高齢者差別を分析するために広く用いられるようになった。しかし、本来「エイジズム」という言葉を1960年代にR. バトラーが創りだした時には、それは高齢者差別に留まらない年齢差別を指すものとして機能していた。「エイジズム」が主に高齢者差別を指すようになってからというもの、若年者に対する差別という点に関しては今日にいたるまで、等閑視されてきた感がある。そろそろ、「若年者差別」としての「エイジズム」をフェミニズムが再検討することが必要といえるのではないだろうか。
5.全てが自分に帰ってくる再帰的な「違和感」
これまで、私のフェミニズムに対する違和感は、フェミニズムが大学において展開されていることに起因するものとして論じてきた。しかし同時に、これらの問いは、私が大学院に居続ける限り、再帰的に私自身に対して突き付けられる、罪悪感に限りになく近い違和感でもある。実際、大学から一歩外に出ると、嫌フェミニズム的な言説が流布している。誇張されたもの、事実無根の言説があるのは確かであるけれども、しかしその中には、根源的な批判を突き付けるものもあるように思える。すなわち、学問としてのフェミニズムが持つ権力性・抑圧性に対する批判である。
これまでくどくどしく、学問としてのフェミニズムへの違和感を述べてきたが、それを感覚的に表せば、より端的に説明することができるかもしれない。ヤマンバギャルの例で表してみよう。渋谷などの都市の繁華街に出没していたガングロ、ヤマンバギャルたちには、男の視点をものともせず、媚を売る自分と決別し、自分の欲望のままに変身を遂げる、一種の居直り、またはふてぶてしさがあった。そこに田中美津は、<ここにいる自分>から出発したリブの精神を少しだけ垣間見、「ちょっとだけ懐かしくなった」という(田中 2010)。しかし、どんなに彼女たちが「男」の視線を排しかわしていったとしても、そんな彼女たちに「萌え」、憧憬の対象としての自分たちの世界に取り込む男は必ず出てくるのである(註6)。「男」はどこまでも、女性に絡みつき依存し、自分たちの論理や世界観に「
今日、多くのフェミニズムの対象となる女性たちにとって、上記の構図における「男」の位置にくるものこそ、フェミニズムなのではないだろうか。フェミニズムの研究対象となる女性たちや運動の場にいるフェミニストたちは、「学者のフェミは」と非難することによって自分たちの経験の他者による理論化を拒み続けるが、彼女たちのその「抵抗」の仕方もまた、フェミニズムの研究対象となり、フェミニズムの既存の理論に組み込まれていく。逃げてもあらがっても振り払ってもからみつかれ、取り込まれる。そのような感覚を、学問としてのフェミニズムと相対するとき、違和感や拒否感として、「普通の人々」である女性たちも抱いてしまうのではないだろうか。運動の現場で、そして大学の外で、私も彼女たちと同じような感覚を抱く。と同時に、「学問としてのフェミニズム」に属する立場の自分自身に、再帰的に違和感と嫌悪感を持つのである。
しかし、「女性」自身にこのような、他者に取り込まれまいとするふてぶてしさと居直りのパワーが存在するからこそ、「フェミニズムに未だ理論化しつくせない領域が存在する」と、肯定的に捉えることができるのではないだろうか。「完全な理論など存在しない(だからフェミニズムに過大な要求をすべきでないし、フェミニズムがすべての説明責任を負うわけではない)」という言い方で、フェミニズムに対する違和感をなきものにすることなしに、「フェミニズムの理論化しつくせない領域が存在すること」を再評価したいと、私は思う。それが、「女性」自身による「女性」相互の肯定につながり、<ここにいる自分>からの出発点となり得る気がするからである。
しかしそうは言いつつ、「学問としてのフェミニズムに対する(私の)違和感」から提起された問題はまだ議論もされずに残っている。今回はまず、この問題提起を、「女性内部の分派行為」とされることなく、そして保守層の「女性に対する巧妙な抑圧・搾取」に根拠を与えることなく、本論考で伝えられたならば幸いである。そして次の段階として、抑圧的な性差別構造に反動的に戻ることなく、既存の「学問としてのフェミニズム」に迎合することなく、新しい世代の「身体感覚」から始まる「フェミニズム」を模索していきたい、とささやかながら願っている。
■文献
荒木菜穂,2007,「「フェミニズム嫌い」に関する一考察」『国際文化学(神戸大学国際文化学会)16:75-86.
江原由美子,1991,『ラディカル・フェミニズム再興』勁草書房.
Hooks, Bell.1984,"Feminist Theory: from Magin to Center" South End Press. (=1997,清水久美訳『ブラック・フェミニストの主張――周縁から中心へ』勁草書房.)
伊田広行,2005,「フェミ嫌いの論理あるいは気分・無意識に対する私の語り方」『季刊唯物論研究』93:43-54.
伊藤公雄,2003,「バックラッシュの構図」『女性学』11:8-19.
――――,2004,「ヘイト(憎悪)/フォビア(嫌悪)の構図」『インパクション』143:28-37.
過剰姉妹,「SCOOP!!!!! 過剰姉妹」『インパクション』 171:40-5.
菊地夏野,2005「フェミニズムとアカデミズムの不幸な結婚」『女性学』12:34-46.
内藤和美・辻智子,2000,「フェミニストであることと研究者であること──個人史を題材に」『女性学』8:103-15.
鈴木謙介,2006,「ジェンダーフリー・バッシングは擬似問題である」上野千鶴子ほか,『バックラッシュ!――なぜジェンダーフリーは叩かれたのか?』双風舎.
田中美津,2005,「自縛のフェミニズムを抜け出して――立派になるより幸せになりたい」『女性学』12:8-15.
――――,2010,『新装改訂版 いのちの女たちへ――とり乱しウーマン・リブ論』パンドラ.
上野千鶴子,2001,「女性学の制度化をめぐって」『女性学』9:106-117.
上野千鶴子・宮台真司・斎藤環・小谷真理ほか,2006,『バックラッシュ!――なぜジェンダーフリーは叩かれたのか?』双風舎.
内海崎貴子,1999,「女性学教育の問題点――女子大の存在、女子学生・男子学生を中心に」内海崎編『日本の女性学教育 The education of women's studies in Japan』東信堂.(所収:天野正子編『新編日本のフェミニズム8 ジェンダーと教育』岩波書店.)
若桑みどり・加藤秀一・皆川満寿美・赤石千衣子,2006,『「ジェンダー」の危機を超える!――徹底討論! バックラッシュ』青弓社.
★プロフィール★上間愛(うえま・あい)1982年生まれ。現在東京大学大学院人文社会系研究科修士課程。大学在学時に非婚で出産、息子が一人いる。オルタナティブな家族の形を模索する研究を続ける一方、最近は「沖縄戦というトラウマと語り」「有機農業」「公共空間と安全」「女性と貧困」など多様な分野に関わっている。
Web評論誌「コーラ」11号(2010.08.15) 〈倫理の現在形〉第10回:フェミニズムに対する違和感──「学問としてのフェミニズム」に(震えながらも)物申す(上間 愛) Copyright(c) SOUGETUSYOBOU 2010 All Rights Reserved. |
| 表紙(目次)へ |