|
|
|
Web�]�_���u�R�[���v |
|
���n���̎� ���{���̕\���i�ڎ��j�� ���{���̃o�b�N�i���o�[ ���ǎ҂̕Ł^���ӌ��E���z �����e�K�� ���W�҂�Web�T�C�g ���v���C�o�V�[�|���V�[ |
|
���{���̊֘A�y�[�W�� |
|
���u�J���`���[�E�������[�v�̃o�b�N�i���o�[ ���]�_���ula Vue�v�̑��ڎ� |
Copyright (c)SOUGETUSYOBOU |
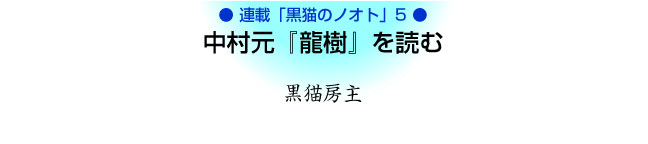
|
|
�i�{�����̉����̓����N�������Ă��܂��B�܂��A�L�[�{�[�h�F[Crt +]�̑���Ńy�[�W���g�債�Ă��ǂ݂��������܂��B�j
�Q�l����
���R�Y��E��R�t���w��̘_�������ρ��i�����̎v�z�R�j�x�i�p��\�t�B�A���Ɂj
���R�Y��u���ϓN�w�ƈ����_�v�i�w���R�Y�꒘��W�T�x�t�H��
�N�����E��R�t���w���݂̕���<�q�A�r�_���}�r�x�i�p��\�t�B�A���Ɂj
�������w���n���T�x�i�����܊w�|���Ɂj
���앐���w��̎v�z�j ���n����������{�ߑ�ցx�i�u�k�Њw�p���Ɂj
�{���[��w�u�b�_���l�������Ƅ��������̂͂��܂��ǂށx�i�p��\�t�B�A���Ɂj
�{���[��w�C���h�N�w���̓��x�i�u�k�БI�����`�G�j
�@
���lj��̖ڈ�
�@�������w�����x�����A�����̎咘�ƌ�����u���_�v�̓lj��A���ɉ��N�Ƌ�ς𒆐S�ɍs�����A�����̗����͓���ł���̂ŁA�������̉�������C���ɕ⑫�I�Ɋ��R�Y�̉���ɉ����ēlj����s���B
�@�����ɂ��u��ςƂ́A�����鎖���i��؏��@�j����ł���A���ꂼ��̂��̂��Œ�I�Ȏ��̂�L���Ȃ��A�Ɗς���v�z�ł���B�v�A�[�I�ɂ����A��ςƂ͂��̒�`�ő����ł��낤�B�Ȃ��Ȃ�A�u���̓N�w�͒�܂������`�Ȃ���̂������Ă��Ȃ��v�i�����Ap.129�j����ł���B�i���u�v�Ƃ��������̎��̉�������邽�߂ɋ��`�����Ȃ��̂����H�j
�@�����A�悭�悭�l����ƁA���́u�����v�Ƃ́u���@�v�̂��Ƃł���A���́u�@�����́v�̈Ӌ`���悭�������Ă����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�܂��A�����Ō����u��v�Ƃ͎��R�E�S�̂��܂܂��A�l�ԓI���ۂɊւ��o���I�����Ɍ��肵�đ�����̂�����̂悤�ł��邪�A���̕ӂ�̑��������A��敧���Ɛ���ؗL���i�L���j�Ƃł͈قȂ���������������̂ŗv���ӂł���i�@��^�@�L�j�B
�@�܂��A�����̎�v�_�푊��ł���A�L���́��@���⁃�@�L���̊T�O�Ƃ̑Δ�ŁA<��>�⁃���N���𑨂���K�v������B
�@�Ȃ��A�u���́v�Ƃ����T�O���́A�u�́i���́j�A���i�{���j�A�@�A��(���̖̂{���j�A���i���́j�A�L�v(����,p.92)�Ȃǂ̌��t���g�����A�����Ӌ`�ł���B
�@
�P.�u���_�v�̍[�T
�@�����́A�L���Ȃǂ����@�ɌŗL�̐����i�����j��F�߂������ʼn��N����ʂ�������邱�Ƃ�ᔻ�����B�����́A���@�͋Ȃ킿�������ł��邩�牏�N���A�܂����N���邩�玩������������ł���Ƃ����B������Ƃ͉��N�̂��Ƃł�����B
�@�Ȃ��u��v�Ƃ́u���v�̂��Ƃł͂Ȃ��B�u�L�����v�Ƃ����Η��z�����T�O���u��L�v�ł���A�u��v�̔��Η��O���u�s���L�������͕s��Ȃ�v�ƂȂ�B
�@�����́A�w�ʎ�o�x�ɉe�����A�w���_�x���ŁA����ؗL���Ȃǂ̖@�L�i�܈ʎ��\�ܖ@�j���ɔᔻ��������`�ŁA�L�ׁi���ہA�푢���j�����ׁi��푢���A��Z���́j���Ђ�����߂��A�O�ꂵ�����ː��i���������傤�A���݈ˑ����j�Ƃ��Ẳ��N�A�����鑊�ː����N������A���ϔh�A�y�ё�敧���S�ʂɑ���ȉe����^�����B
�@�������ɂ��A���_�̎咣���鉏�N�́A�L���̉��N�_�Ƃ͒��������Ⴗ�邪�A�㐢�����̉،��@�̖@�E���N�̎v�z�ɂ͔��ɗގ����Ă���Ƃ����B�@�E���N�̐��ɂ����ẮA�L�ז@�E���ז@��ʂ��Ĉ�ؖ@�����N���Ă���Ɛ�����邪�A���̎v�z�̐��͒��_�Ɍ����������Ƃ����B�i�����w�����x �̗v��j
�@�u�ꌾ�ł����A�w�ʎ�o�x�̐_��Ƃ������������ō��̐^���̏�ɗ����āA��ʂ̓N�w��ᔻ���鏑���ł���B�v�i���R�Ap67) �@cf;��ʂ̓N�w���A�r�_���}�n
�u���Ȃ̗��_���咣��������A���w�h�̗��_��ᔻ���邱�Ƃɐ�S��������A�茾�_�؎��𑽗p���Ȃ��B���̂����ɉ����I�����E�f�B�����}�E�l��ے肪�ނ̕���ƂȂ�B�v�i���R�Ap133�j
�@�u���_�v�́u��18�́i�A�[�g�}���̍l�@�j�́u����̖��̍l�@����n�܂��Ă��邪�A��̖��E���̖̂{���̖��E�^���̒�`�E���N�̖��E�^���̉i�����Ȃǂɋc�_�͓W�J���Ă��āA���ϓN�w�̊�{�I������悭���f���Ă���B�v�i���R�Ap68)�@cf;�������̋��n���u��E�����E����v�w�ʎ�o�x�j
�@
���ϓN�w�̐��i
�u�ᔻ�����w�h�̋��`�𒉎��ɍČ��������̂Ƃ������Ȃ��B�X�̋��`�A�����v�f�Ƃ��č\�������̌n�̌����ƂȂ��Ă���v�ҕ��@�ɔᔻ�͌������Ă���B���@���N�w�̌n�̌����ᔻ�B�i�[�K�[���W���i�̒���ɂ����ďd�v�Ȃ̂͂Ƃ肠����ꂽ���ł�������A�����ᔻ����_���ɂ���B
���̔ᔻ�̘_���́A�����̃^�C�v�ɊҌ��ł���v�i���R�Ap.91�`92�j���}�Q��
�@
���L�[���[�h
���N�A�@�A�@��^�@�L�A�L�A���L�^���L�A���̐����������{�����{���A�T�O�^���݁A����^�A�[�g�@�}���A�����^������
�@
�������̃v���t�B�[��
�����i��: N?g?rjuna�j�́A2���I�ɐ��܂ꂽ�C���h�����̑m�ł���B�����Ƃ́A�T���X�N���b�g�̃i�[�K�[���W���i�̊��ŁA���{�ł͊���p���邱�Ƃ������B���ϔh�̑c�ł���A���{�ł́A���@�̑c�t�Ə̂���邱�Ƃ�����B
�^���@�ł́A�u�t�@�̔��c�v�̑�O�c�Ƃ���A���ҁi��イ�݂傤�j�Ƃ��Ă��B�������A��������������������ǂ�����A��ܑc�����q�Ƃ̎���̊u���肩��A�����Ɨ��҂̓��ꐫ���^�⎋����ӌ�������B��y�^�@�ł́A�����m�̑��c�Ƃ��ꗴ����F�A������m�Ƒ��̂����B���̕�F�Ƃ��ē`�L�ł͕`�����B�iWiki���j
�@
�Q.�\���m���Ƃ���
2-1�j���������́u��v�����敧���́��̎v�z�ւƎ��铹��
�w�ʎ�o�x�ɏo�Ă���A���ȋ]���̐��_�ƕ�e�͂ɂ݂����p�Y�Ƃ��Ă̕�F�̕���́A�o�Ƌ��c�̗��ȓI�Ȃ������ᔻ�A����͖������Ƃ������Ƃ��݉ƕ����҂̗ϗ��I�E�@���I�ȑԓx�Ƃ��āA��敧���̊���Ƃ��Čf���Ă���B���@�������̊�b���Ƃ��ċ�̎v�z��W�J�@���@���Ƃ��w�ʎ�o�x�̋�̎v�z�͖������Ƃ����ϗ��E�@���Ƃ͂����蕪�����Ă͂��Ȃ��B�@���@�������A���̂��ƂɂƂ���Ȃ��A�Ƃ�����F�̐S�\�����A���@���͖̂{�̂������Ȃ��A��ł���A�Ƃ����F���܂ŏ������Ƃ���ɓN�w������B�i���R�Ap.39�`40�j�������P�F��F�Ƃ́A������2�F��敧���̐���
2-2�j�����̔ʎ�o�T�ɂ������ґz�i���Ƃւ̕s�M�j
�@����ґz(��)�E���邵�̂Ȃ��ґz�i�����j�E�]�ނƂ���̂Ȃ��ґz�i����j
���̎O����ґz�́A���ׂĂ̂��̂�ΏۂƂ��āA����炪�{�̂̂Ȃ���ł��邱�ƁA�����Ȃ���̂ɂ���Ă����邵�Â��邱�Ƃ̂ł��Ȃ����ƁA����ׂ����̂ł͂Ȃ����Ƃ��ґz����B
�@�܂��A�ґz�͐_��Ƃ����ɂƂ��Ă�����̐^���̕��@�@���@�����ґz�ɂ���āA���̖��O�A���̂������͏����A�v�҂��ׂ����́A�\�����ׂ����́A�m�o���ׂ����̂͂��ׂď����A�Ō�Ɏc�����ō��^���A����͐����������A�ł��������A�����炸���炸�A���ꂽ���̂ł��Ȃ��ω������Ȃ��A�����Ȃ�`�ł����ۂ����A���ԓI�ɂ���ԓI�ɂ������E���ӂł���B����͂��ׂĂ̌���𗣂�A�Î�ł���A�ǓƂł���A����ł���B(���R�Ap.40�`41�j
���@�ō��̐^���Ƃ��ẮA���̂���ł���A�����Ȃ���̂ɂ���Ă����邵�Â����Ȃ��A�Ƃ������Ƃ́A�w�ʎ�o�x�̐_��Ƃ������l�Ԃ̂��Ƃ�M�p���Ă��Ȃ������Bcf�G�w���_�x�A�h���Ƃ̗ގ�
�@
�R.�w���_�x�ɂ�����A�F���E�v�ҁE���t�̊W(���ʂɊւ��āj
�u�v�҂͂��Ƃ̋��\�ɂ��ƂÂ��ċN����v�i�Y�_�����t�̋��\�A����I�������j
�u�l�Ԃ̎v�҂́A���݂Ƃ͖��W�ȋ��\�ɂ����Ȃ����Ƃɂ��ƂÂ��Ă���B�v
�u���f�Ƃ������̂͏��Ȃ��Ƃ���̖�����K�v�Ƃ���B���f�́A���������āA�����̊T�T�O�̑��݂�\�z����B���f�͌���̑������ɂ��ƂÂ��A�v�҂́A���Ƃ̋��\��肨����A�ƃi�[�K�[���W���i���l�����̂͂���߂ē��R�̂��Ƃł���B�v
�u�l�Ԃ̔F���͒��ς���m�o�E���f�E�����Ƃ����ߒ��œW�J����B�����Ȓ��ςɂ����Ď�ςƑΏۂ̕�����Ȃ���A�厫�ƕo���Ƃ̕�����Ȃ��B���ς̐��E�͑S��Ȏh���ł���B�v�i���R�Ap74)
���u�ґz�v�u���ρv���u�Î�v���u�{�̂̂Ȃ����Ɓ����t�����̉������ɂ����Ȗ{�̂������Ȃ��v�F�v�ҁE���t�̑ΏۂɂȂ�Ȃ�����u�Î�v�u����v���ō��̐^���B�@
�@�u�i�[�K�[���W���i�͂��Ƃ�{���Ƃ��������̔F���ߒ���|�����Ƃ����Ă���̂ł���B����ꂪ�Ȃ��ׂ����Ƃ́A�v�ҁE���f���璼�ς̐��E�t�s���邱�Ƃ��A�Ƌ����Ă���̂ł���B�v�i���R�Ap76)�@
�@cf�G�J���g�̔F���_�u�������̂Ƃ��Ă̑Ώہ��ɂ��Ă̔F���������Ƃ͂ł����A�������I���ς̑ΏۂƂȂ���́��A�܂�A�����ہ��ɂ��Ă̂݁A�������͔F�����邱�Ƃ��ł���B�v�i�w���������ᔻ�x�j
�@
�S.�����ɂ����̂̒�`
�@����(suabhãava�Ƃ��{��(prakrti)�Ƃ́A�����I�E�P��s�ρE�P��Ȃ��́B
�@�����A�����̐��E�ɂ�����̂͂��ׂđ��Ɉ˂��Đ��N���A�˂ɕψՂ��閳��Ȃ��́A�����ĕ����I�ȑ��݁B���̂悤�ȑ��Ɉ˂鑶�݁A���N�������͎̂��̐��E�{������������Ȃ���̂ł���B(���R�Ap109)�@���ȉ��u���_�v�����p�B
�@15��1�u�����ꎩ�́��i�����j�����ƈ��Ƃɂ���Đ����邱�Ƃ͉\�ł͂Ȃ����낤�B������萶���������ꎩ�́��́�����o���ꂽ���́��i����̂��́j�Ȃ̂ł��낤�v
�@15��2�u�܂��ǂ����ā����ꎩ�́����������������o���ꂽ���́��ƂȂ�ł��낤���B���ƂȂ�A�����ꎩ�́��́����o���ꂽ���̂ł͂Ȃ����́��i������̂��́j�ł����āA�܂����̂��̂Ɉˑ����Ȃ����̂�����ł���v
�@15��8�u�������{����A������̂��L�ł���Ȃ�A���̂��͖̂��ł͂��肦�Ȃł��낤�B���ƂȂ�A�{���̕ω����邱�Ƃ͂������Đ��������Ȃ�����ł���v
�@7��30�u�܂��A�L�ł�����̂̏��ł��邱�Ƃ͋N���肦�Ȃ��B���ƂȂ�A�i������̂��j�L�ł����Ă��������ł��邱�Ƃ́A��̂��̂ɂ����Ă͋N���肦�Ȃ�����ł���v
�@cf�G�L���́u�L�ז@�v�F�u�����E�����ɂ���Đ��ł��鎖���A�u���ז@�v�F�����ω����z������Z��ΓI�Ȃ��́v�i�����Ap.96�`97���܈ʎ��\�ܖ@�j
�@
�T.�L���ɂ�����u�@�v�̊T�O�i�����Ap83�`94�j
5-1�j�u�@�v�Ƃ�
�@�u�����N�w�Ƃ͖@�̓N�w�ł���B�v(�����Ap83)
�@�@�Ƃ͌ꌹ�I�ɂ́Adharma�Ƃ��������A���u�����v�Ƃ����Ӗ��A���u���܂�v�u�O�́v�u���@�v�@���`�i�C���h��ʂɒʂ���p��j������3�F�_���}
�@�Ȃ��A���́u���@�v���u���́^�����v�ɕω��������H�@���@��@�L�v�咣�̓��H
5-2�j�@�̑̌n�̊�b�Â�
�@���n�����͎��R�F���̖����l���O�ɂ����Ă���B
�@c�G�{���ɂ��A�u�b�_�́A�{���_�I�i�`����w�I�j�ɂł͂Ȃ��A�����I�Ȓn���ł̈��ʊW��Nj��B���@�o���_�ҁF�B���_�^���ݘ_�̘_���ɔ�ׂ�A���Ƃ�T�O�͎��݂̑Ώۂ����Ƃ���펯�̈���o�Ȃ��f�p�Ȏ��ݘ_�ҁB���@���̌����͋����[���j
�@�@�Ƃ͈�̑��݂̋O�͂ƂȂ��āA���݂̂��̓��ꐫ�ɂ����āA���������߂�Ƃ���́u�����v�ł���A�@���̂��̂͒����ԓI�ɑÓ�����B���@���̉��߂́u���@�v�u�O�́v�Ƃ����ꌹ�I�ȉ��߂Ƃ���v����B���@�@�͎��R�I���݂́u�����v�ł��邩�玩�R�I�����Ɠ��ꎋ���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�i����,��85�j
�@���̖@�̑̌n�Ƃ��āA���]�i��ނ̖@�̗̈�ł���̂��\������W�܂�j�A�Z���i�F������эs���̐�������̈�Ƃ��Ă̘Z�̏�j�ȂǁA�܂����N���i�Ƃ��ɏ\��x�������D���j���l�����Ă����B(cf�G���]�\�\���E�̐}�j
5-3�j���N���y�������L��
�@���n�����̖������牏�N���͒ʑ��I���߂��������܂��B���@��������́i�L��j�̐������]�����Ԃɂ��Ă͂߂ĉ��߂����悤�ɂȂ����B
�@���Ȃ킿���N���ɂ���Ė@�̓���W�����Ƃ���o���Ă���܂��Ȃ��B���N���͖@�̓���𗣂�ĕ��̒ʑ��I���߂Ɏx�z�����悤�ɂȂ����B���@�L���̎���ɂȂ�ƁA���N���͑S�����w�̒��S����t���I�Ȃ��̂ɂȂ����B
5-4�j�Ȃ��L���͖@�L���咣������
�@�L���͉��N�ɂ���Ė@�̑̌n�̊�b�t�����闧����̂Ă�B���@�@���u�L��v�Ƃ݂Ȃ����ƂɊ�b�Â����B������������u�L�E���v�̋ɒ[���͔r������Ă����B���@�Ȃ̂ɁA���́u�L�v���咣�����̂��B
�@�u�b�_�́u���ׂĂ���ꂽ���͖̂���ł���v�i���s�����j��������B���@��̑��݂͙��ߙ��߂ɐ����ϑJ������̂ł���A���琶�ŕω����Ȃ��A��Z�Ȏ��̂͑��݂��Ȃ��B
�@�Ƃ���ŁA���s������咣���邽�߂ɉ��炩�̖���Ȃ炴����̂�K�v�Ƃ���B���@�łȂ���u����v�ł���Ƃ����咣���������Ȃ��B�@���@����Ȃ鑶�݂�Ȃ炵�߂�A��荂���̌���������͂��ł͂Ȃ����B�������A���̂ɂƂ��ɖ@�́u�L�邱�Ɓv���咣�����̂��B
5-5�j�u�L��v�̘_���I�\��
�u����v�Ƃ����T�O�F�@�u�ł���v�u�Ȃ�v��esentia�`���_���w�A�@�A�u������v��existentia���ݘ_�^�L�_(Ontologie) �� ���R�I�F���ł͂Ȃ��N�w�I�F���i���@�L�̗���j
5-6�j�@�L�̐������闝�_�I����
�@�X�̑��݂͕ω����ł��邪�A����́u���肩���v�u���邱�ƈ�ʁv�͕ω����Ȃ����̂ł͂Ȃ����B���@�Ƃ��Ắu���肩���v�͂�荂���̗̈�ɂ����ėL��͂��ł���B�i���̓_�ɂ����āA�L���͊ϔO�I�j���@�@�́u���ꎩ�g�̖{���i�����j�����v���̂Ƃ��Ă�荂���̗̈�ɂ����ėL�邩��A�����ԓI�ɑÓ�����B���@�������āA�@�͗L�遁�@�͎��݂���A�Ƃ��ꂽ�B
�@�u�c�c�ł��邠�肩���v�Ƃ��Ă̖@���A�L���ɂ���āA�u�c�c�ł��邠�肩���A���L��v�ƗL���ɂ���ď���������ꂽ�B(����,p90�j �i�@�{���Ƃ��āu����v�A�A���݂Ƃ��āu����v�Ƃ����W�j
�@������4�F���ݘ_�̎O���}��
5-7�j�@�Ɩ{��
�@��敧���͂ł́u���ꎩ�g�̖{���v���������Ƃ������Ă��邩��@�ł͂Ȃ��Ǝ咣�B
�@���́u���ꎩ�g�̖{���v��L���́u�����v�Ƃ݂Ȃ����B�@���@�L���́u���́v�̎��݂��咣�����Ƃ����邪�A���́u���́v�Ƃ́u���ꎩ�g�̖{���v�̈Ӗ��ł��邩��A�o���I�����ƍ������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�u���́v�����R�I���݂Ƃ��Ď��݂���Ӗ��ł͂Ȃ����낤�B
�@�u���ꎩ�g�̖{���v���������{���F�@��esentia��existentia�Ƃ��Č����ꍇ�A�u�{���v�Ƃ́u�c�c�ł���v���Ƃ����݂Ƃ��ꂽ�B
5-8�j�u�{���v�u�{���v���u���́v�Ƃ���邱�Ƃ���A�u�@�v���u���́v�Ƃ��ꂽ�B
�@�@���u���́v�Ƃ͌o���I�Ȏ����ł͂Ȃ��A���R�I���݂��\�Ȃ炵�߂Ă���u���肩���v�Ƃ��Ắu���́v�ł��邱�Ƃɒ��ӁB(����,p94�j
�@���݁i���́j�����炵�߂�u���肩���v���u���́v�Ƃ݂āA���Ȃ킿�u���́v�̖{�������̂Ƃ݂Ȃ����B�@���@�T�O�̎��݂�F�߂�B
�@�u�@�L�v�́u�L�v�Ƃ́u�o���E�ɂ����ėL��v�Ƃ����Ӗ��ł͂Ȃ��B
5-9�j���������
�@�L���͊T�O�݂̂Ȃ炸���f���e���Ȃ킿���肪���ꎩ�g���݂��邱�Ƃ��咣�B���@����A������L�Ƃ���A�܈ʎ��\�ܖ@�̐S�s�����s�@�̒��ɓ����ꂽ�B���@�ŋߑ�̋L���_���w�ł́A����̋L���\�����T�O���邢�͖���ɉ�����邱�Ƃ��\�B�[�I�ɂ��肩���Ƃ��Ắu�@�v�Ƃ��đ�����l�������͏[���ɈӖ������B
�@
�U.���L�̈Ӌ`�ip.95�`�j
�@�u���L�v�Ƃ́u�L�v�isat�j�Ƃ����ށigenus�j�̒��̂����̎�ispecies�j�ł���A�u�L�v���O���͋��������e�͖L���B���́u�L�v�Ƃ����^�O�́A���e�̔��e�Ƃ����ׂ����̂ŁA��`���邱�Ƃ��ł��Ȃ������̂��́B�̂ɢ���L�v�̈Ӗ��́u���v�idravya�j�̕��͂��瓾����B�u�L�v�̑��̎�̂����e�̔ے�A���́u�L�v�Ƃ̎퍷�����L�̓��e�ł���B
�@
�@���L�F�u���肩���v�Ƃ��Ắu��v�u�z�v�̂��Ƃ��L�ז@�̂�
�@�@���L�Ƃ́A���ԓI��ԓI�K����Ă��鎩�R���I���݂��\�Ȃ炵�߂�u�����v�Ƃ��Ă̖@�Ɂ@�ւ��Ă݂̂���ꂤ��B
�@�A�@�͎��R�I���݂́u���肩���v�ł���̂ɁA���ɁA�ˑ������A�Ɨ����Ă���B
�@���L���ے肷��L�@
�@���L�^�{�ݗL�F�j�A���A�r�A�ԏ�A�R�A�сA�ɁA���R�I���ݕ�
�@���җL�F���A�Z�A����A����A���֊W�ɂ����đ�����u�L�v���@���ϔh�ɉe��
�@�@�@�@�@���җL�������L���a���L�A�����L
�@���L�F�T�̖сA�e�̊p�̂悤�Ȗ��������A���R�I���݂̗̈�ɑ��݂��Ȃ����́B
�@�a���L�F���]�̂悤�ȘA�������l���݂̂悤�Șa���B
�@
�V.�L���ɂ�����u��v�̈Ӌ`
7-1�j���]�\�\���E�ł���B�L�ז@�Ɩ��ז@���܂ނ��A���]�͗L�ז@�̂݊܂ށB
7-2�j�ߋ��E���݁E�����̎O���B�����͎��ԂƂ����Ɨ��̎��̂�F�߂Ȃ�����u�O���ɑ�������́v�ł��낤�B�@�̕ω��́A���N�i���j�A�����i�Z�j�A�فi�ω��j�A���Łi�Łj�̎l�L�ז@�ɂ�āA�N����B
�@
�W.�L���̎�_
�u���邩���v���L��A�Ƃ�������Ȃ�ΓO��I�Ɏ��L�Ȃ�@�͈̔͂��g�傹�˂Ȃ�Ȃ��͂������A�����ł���ȏセ�ꂪ������Ȃ��B���@�g�傷��A�܂��܂��o���_�I�Ȏ��ݘ_�̗���ɗ����@�B�V�F�[�V�J���ɐڋ߂��邩��B�����ɗL���̎�_������A�o���͋ɗ͂��̖������w�E����B�u���_�v�̔j�ז@���܂������@�L�̂��̗���̎�_��˂��Ă���B
�@�O�����L�@�̍P�L���O���ɂ����Ď��L�Ȃ�@�́i�@���̂��́j���P�ɂ���B
�@�O���̋�ʂ́u�ʂ̕s���v�ɂ��Ƃ�������������i���`�j�A���Ȃ킿��p�̈قȂ�ɏ]���ĎO���̋�ʂ����Ă���A�Ƃ������B
�@
�X.���m�N�w�Ƃ̑���
�@�v���g���N�w�Ƃ̗ގ����w�E����Ă��邩��Arealism�Ƃ�Ԃɂ��Ă����ݘ_�Ɩ������O�_�i�B���_nominalism�ɑ���j�Ɩ��ق����悢��������Ȃ��B
�@�������A�T�O�݂̂Ȃ炸����̎��̗L�iAnsich-sein�j���F�߂Ă��邩��u�T�O�̎��O�_�v�Ƃ����ꂪ�҂�����ƓK�����Ȃ��B������5�F���݂Ƃ�
�@
10.��̘_��
10-1�j�^���_�̔ے�̘_��
�@�w���_�x�Q�͂̃e�[�}�F�q�����́r�́u���v�Ɓq����͂��炫�r�́u���v��L���̂悤�ɊT�O�����̉�����ƁA��̋��̑Η��������邱�Ƃ��w�E�B�v���T���K�_�@�i�A�T�@�j
10-2�j�u�O����j�v�̘_�@
�@���҂Ƌ��@�Ƃ�Η������߂āA�����_�j�i�ꎞ�j�A���̔��i�͂��炫�j�n�߂邱�Ƃ�_�j(��)�A�Z�i�Ƃǂ܂邱�Ɓj��_�j�i�O���j�B
10-3�j�u���́v�̓N�w�I�Ӌ`
�@����������̂�����v�Ƃ�������́A�`���_���w�I�ɂ݂�Ή����T���܂�ł��Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�A����͉𖾔��f�^���͔��f�ł���A���u���������́v�Ƃ����T�O�̒��ɏq��̢����v���Ƃ����T�O���܂܂�Ă���B���͂���Ώq����o����B�Ƃ��낪�A�����͕��͓I���f�ł͂Ȃ��A�g���I���f�^�������f�������B������6�F�������f
�@���̗��R�́A�@�L�̗���͂��ꂼ��̋��Ƃ���<�����>�����̂܂��݂Ƃ݂Ȃ�����A
�u���������́v�Ƃ����u������v�Ɓu����v�Ƃ����u������v�͑S���ʂ̂��̂Ƃ���A�u���������̂�����v�Ƃ�������͊g�����f�ł���A��̋���͂��炫���܂ނ��ƂƂȂ�B
�@�������Ƃ���ƁA���̓�̋���͂��炫�����鍪���͂�����ɋ��ނׂ����B�u��������̂��́v�i�@�̂݁j�ł���A���̂����Ȃ���e�����ۂ��Ă����̎��̂������ɂ��Č���������̂ł��낤���B���ꂪ�����̘_�_�B
10-4�j�w���_�x�̘_�������v���T���K
�@����������{�I�ȑԓx�Ƃ��āA���̓N�w�͒�܂������`�Ȃ���̂������Ă��Ȃ��B���ϔh�͌����Ď���̎咣�����Ȃ��B�咣�����݂��Ȃ��A�܂��ɂ��̌̂ɁA���_�I���ׂ����݂��Ȃ��B(p.129�j�@���@�w���_�x�̘_���͐��_�ł͂Ȃ��v���T���K�i�A�T�@�j�B�@���@���������̗��ꂪ�_������邱�Ƃ͂��肦�Ȃ��A�Ƃ����m�M�@���@��敧�����i�T���܂߂āj�_��I�ґz�����H�������̂́A���̂悤�Ȏv�z�I�������������B
10-5�j�w���_�x�ɂ�����_�@�̊�{�`��
�@�O����j�F�i10-2���Q�Ɓj
�@��ٖ�j�F���֊W�ɂ����̊T�O�͈�ɔقɔƎ咣�B
�@�܋���j�F��ٖ�j����_���I�ɓ����o����B�@����̂��̂ł��邱�ƇA�ʈق̂��̂ł��邱�ƇB�b������L���邱�ƇC�b�����̂��ǂ���ł��邱�ƇD�����b�̏�Ɉ˂��Ă�����̂ł��邱�Ƃ�ے�(�܂̌����ɂ��_�j�j
10-6�j�s�f�s��
�@�����k�ɂƂ��āu�s�f�s��v�͐�̐^�������A�u�O�����L�̍P�L�v������L���̕ى��B
�@�����ɂ��A���L�Ȃ�@��F�߂悤�Ƃ���A���ꂪ��������u��Z�v�Ƃ������_�I���ׂɑ��A�������f�ţ�Ƃ������_�I���ׂɊׂ邩��A�@�L�̗���ɂ����Ă͕s��s�f�Ƃ������Ƃ͕s�\�B���Ƀ_���}�����̖̂������́i�������j�ł��邩�炱���A�s��s�f�Ƃ�������B(p.142�j
10-7�j���O�_�I�v�҂̔r��
�@�@�����L�Ƃ݂Ȃ��v�z���U���B�T�O��ے肵���̂ł͂Ȃ��A�T�O�z�I�Ɏ��݂Ɖ�����X����r�ˁB�T�O�Ɍ`����w�I���݂�t�^���邱�Ɓi���@�L�j��ے�B
10-8�j���ϔh�ƌo��
�@���m�̊w�҂͋��ɗB���h�ƌĂ�ł��邪�A�T�O�z�I�Ɏ��݂Ƃ݂Ȃ��X���ɔ��B
10-9�j�w���_�x�̖ړI
�@�������̎��ۂ����݂��ɑ��݈ˑ��܂��͑�����ɂ����Đ����i�����ҁj���Ă��邱�Ƃ𖾂炩�ɂ��邱�ƁB�������ł�<����>�́A�C���h���N�w�̌`����w�I��������́A�L����<�܈ʎ��\�ܖ@>�̑̌n�̂����̂������̃_���}���܂߂āA���ł��悢�B
�@
11.���N
11-1�j�w���_�x�̒��S�v�z�Ƃ��Ẳ��N
�@�@�������������������
�@��������F�������A��ł��錻�ۂ�l�Ԃ��ǂ��F�����������čl���邩�ɂ��ẮA���ړI�ɒm�o�@����Ƃ������Ƃ����ł͂Ȃ��A�T�O�⌾����g�p���邱�Ƃ��l������B�����́A�l�Ԃ���ł���@�O�E��F������ۂɎg���u���t�v�Ɋւ��Ă��A���݂������̂ł���Ƃ���B
�@���̐����A�����T�O�𗣂ꂽ�^���̐��E�ƁA�����T�O�ɂ���ĔF�����ꂽ����̐��E���A���ꂼ�����`�� ���������Ƃ�����̐^���ɕ�����B���t�ł͕\���ł��Ȃ��A���̐��̂���̂܂܂̎p�͑��`���ł���A�T�O�łƂ炦��ꂽ���E��A���t�ŕ\�����ꂽ�߉ނ̋����Ȃǂ͐������ł���Ƃ���A�u������v�ƌĂ��B(Wiki���)
11-2�j���N������A�h��
11-3�j�Ջp����Ă����w���_�x�̉��N��
�@�@�w���_�x�͉��N�𒆐S���Ƃ��Ă���B
�@�A�w���_�x�͏]������̏���Ő������N�i�\������j�ɑ��Ǝ��̉��N������A�������R�ӎ��������Ď咣���Ă���B
11-4�j�A�r���_�}�̉��N��
�@��������́i�O���j���O�E��։�ߒ������ԓI�ɏ\������̊e�x�ɂЂƂ��Ă͂߂ĉ��߂���B�O�����d�̈��ʂɂ���Đ�������ِ��w�I���߁B�i�}�F�\������Ap169�Q�Ɓj���ԓI�p�N�I�������̐��B
�@���߉��N�F�ꙋ�߂ɏ\��x���ׂĂ����Ƃ��������B�_���I�^���ݘ_�I���ꂩ��̉��߂ŁA�w���_�x�̉��N�ƈꖬ�ʂ���Ƃ��낪���蒍�ڂɒl����B�ْ[�A�u��O�i��u�j�ɂ������N�̋`�L��v
�@���ʉ��N�F�L���̒��S�I�������A���ʂƂ́u�ω����W�̒i�K�v�̂��Ƃ������B���N�͂����ς�L��i��������́j�Ɋւ��Đ������B
�@�v��F�����N�����A���L�Ȃ�Ɨ��̖@�����̏�����������N����Ɖ����ꂽ�B
11-5�j�w���_�x�ɂ����鉏�N�̈Ӌ`
�@�@1�́E20�͂ł́A�u���ɂ���āv�̈��ʊW�̉��N��ے�B
�@�A�w���_�x�̉��N�́u���ː��v�i���݈ˑ����j�̈Ӗ��Bex�G8��-12�́u�s�ׂƍs��̂̊W�v�u�b�ɂ���ĉ�������A���ɂ���čb������v���@�@�Ɩ@�̘_���I���֊W�@���@���@�͑��݂Ɉˑ����邱�Ƃɂ���Đ����@���@�������A����͖@�L�̗���ɂ����Ă͐�ɋ�����Ȃ������B
11-6�j�w���_�x�̘_���̓��ِ�
�@�u�`���������Ȃ�����A�a�����������Ȃ��v�Ƃ����_�@���������A�_���`���Ƃ��Ă͑O���ے�̌�T��Ƃ��Ă���B
�@�Ȃ��Ȃ�A��L�̖���́u�`����������Ȃ�A�a����������v�o�`���a,�`���a�p�̔ے薽��Ƃ��čl�����邪�A����Ȃ�ΐ������́u�a���������Ȃ���A�`���������Ȃ��v(��)�@�o�ʂa���ʂ`�A�ʁi�a���`�j�p�ł���B
�@���A���A���ː��ɗ��ĂA�u�`���������Ȃ�����A�a�����������Ȃ��v�͈ÁX���Ɂm�a���������邩��A�`����������v�����O��ɂ����Ă���ƍl����ƊԈႢ�ł͂Ȃ��B(p.192�j
�@���l��ے��F���̖�������Ƃ���A�i�L�i���j�A���i�j�A�L�i���j�����i�j�A��L�i�j���i��j�ƂȂ�A���̂S�ځu��L�v�A������e�g�������}�Ƃ������A�u�L�����v���W�����}�B�Ƃ���ŁA���R�Y��ɂ��A���̎l����`���_���̒��ŗ������邱�Ƃ͍���ł��邪�A����_�c�̈�ɂ����Đ������Ă��閽����A����Ƃ͈قȂ����A��荂���ȋc�_�̈悩��ے肵�Ă䂭�ߒ��Ƃ��āA�l��ے�ُ͕ؖ@�I�Ȑ��i��ۂ��Ă���ƍl���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�i���R�Ap135�j
�@���݂ɁA�T���W�����̕s�m�_�F�u�Ȃ܂��_�@�v�Ƃ����̂������āA���̍\�������l��_�@�Ɏ��Ă���B�u�b�_�́u���L�\�_�v�i�`����w�ɂ��ċc�_���Ȃ��j�ɉe����^�����炵���B
11-7�j�L�ז@�Ɩ��ז@�ɂ킽���đ���
�@���҂͖������ł���A���ˑ��ւ̊W�ɂ����Đ����B
11-8�j�،��@�̖@�E���N�Ƃ̗ގ�
�@�@�E���N�F�L�ז@�E���ז@��ʂ��Ĉ�ؖ@�����N���Ă���A�Ɛ����B
11-9�j�W���C�i���Ƃ̊W
�@��ؖ@�̕\�������n�������T�̂����ɂ͌�������Ȃ��̂ɁA�W���C�i���̂����ɂ͌�������B�u��̂��̂�m��l�͈��m��B��̂��̂�m��l�͈�̂��̂�m��v�ȂǁB
11-10�j�]���̉��N�Ƃ̊W�ip.197�j
�@26�͂̏\������̎�肠�����̖��
�@26�͂́u�����@�i���敧���j������đ��`�̓��ɓ��邱�Ɓv�i�ځj������̂ł��邪�A�i�[�K�[���W���i�͑S�������r�˂����̂ł͂Ȃ��A�O���̐������]�̏�Ԃ����������Ƃ��ėe�F�B���@�������N�@
�@����`���v�i�ō��̐^���j�F1�͂���25�͂܂ł̉��N
11-11�j�w���_�x�̏\������̊g�����߁ip.203�j
�@�w���_�x�ɂ����Ă͏\������̂����̑O�̍������̍�����b�Â���W����A��̂��̂̊W�͌����Ċe���Ƒ��Ɨ��ł͂Ȃ��ő��ˑ����ł���A�Ɗg�����߂��ꂽ�B��̎����͑��݂Ɍ��肵�����ɖ����̑��֊W���Ȃ��Đ����A���瑼�̂��̂Ƃ͖��W�ȓƗ��Œ�̎��̂����߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ƃ����咣�̉��ɁA���ː��̈Ӗ��̉��N��������B
11-12�j���N�̈Ӗ����܂܂Ȃ����N
�u�����v�u�����v�u�����v�u�������v�Ƃ������N�̂�����^��ے肷�邱�Ƃɂ���ĉ��N�𐬗������߂悤�Ƃ����B�i�P�͂̃e�[�}�j���@�u�s���s�Łv
11-13�j�ے�̘_���̑�\�Ƃ��Ă�<���s�r
�@���s�́w���_�x�̏@�|�@���s���s�ŁE�s���E�s�f�E�s��E�s��`�E�s�ً`�E�s���E�s�o
11-14�j�w���_�x�̋A�h���Ɓw�ʎ�o�x
�@�w��ʎ�o�x�ɂ����ẮA�l���̈��̋�A�s���Ȃ邱�Ƃ��q�ׂ���ŁA��F�͉��N��@���ɒm��ׂ��ł���Ƃ����āA���s������Ă���B�� ���̕����Ɓw���_�x�Ƃ̖��ڂȊW��F�߂�������Ȃ��B
11-15�j����Ə��@����
�@18�͂ɂ����閳��̐����́A���@�����i�����̐^���j�𖾂炩�ɂ��邽�߂ɂȂ���Ă���B
�@18-��3�u<�킪����>�Ƃ����ϔO�𗣂�A����ӎ��𗣂ꂽ���̂͑��݂��Ȃ��B<�킪����>�Ƃ����ϔO�𗣂�A����ӎ��𗣂ꂽ���̂Ȃ���̂�����҂́A�i���́j���Ȃ��̂ł���v
����~�𗣂ꂽ���n�Ƃ������̂��ʂɂ���Ǝv���l�́A���͐^�������Ă��Ȃ��B
�@<�킪����>�Ƃ����ϔO�𗣂ꂽ���ƂƂ����Ɨ��Ȍ����܂��͎��̂��l����Ȃ�A���͎����̐^�������Ȃ����ƂɂȂ�A�Ƃ����Ӗ��B�i�`�����h���L�[���e�B�j
�@�����ł́u��v�Ƃ́u���́v(�{�́E�{���j�̈Ӗ��ł��邩��A�u���䁁�������v�����v
11-16�j����Ƃ͉��N
�@22��3�u���̂��̂ł��邱�ƂɈˑ����Đ�������̂́A����ł���Ƃ������Ƃ����藧�v
11-17�j���N�ɂ��l�@��̊�b�Â�
�@�u���s����v����@����v�u���ώ�Áv�u��؊F��v
�@���ϔh�͖������̈Ӗ��ɉ����Ă���B�`�����h���L�[���e�B�ɂ��A������L������͉̂��N���Ȃ��B���N�����̂łȂ����͖̂���ł͂Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�A���݂��Ȃ�������̉��͖���ł͂Ȃ�����B���@����Ȃ���͕̂K�����N���Ă���B�@���؊F��v�����N�ɂ���Ċ�b�Â����Ă���B
�@
12.��̍l�@
12-1�j�����_�҂ƍU�����ꂽ���ϔh(24�͂̃e�[�}�j
�@24��7�Ŕ��_�u����͋�ɂ�������p(���@)�E��i���̂��́j����ы�̈Ӌ`��m��Ȃ��B�̂ɓ��͂��̂悤�ɘ_������̂ł���v
12-2�j���N���Ӗ������
�@24��18�u�ǂ�ȉ��N�ł��A����������͋�Ɛ����v
12-3�j���N���Ӗ����閳����
�@�L��ے肵�Ė����咣�����̂ł͂Ȃ��A���L��ے肵�Ė���������������������_��
�@�u���N�v�u��v������ƂƂ��Ɂu�������v�����������B
�@15��1�u<���ꎩ��>(����)�����ƈ��Ƃɂ���Đ����邱�Ƃ͉\�ł͂Ȃ����낤�B������萶����<�@���ꎩ��>��<����o���ꂽ����>�i����̂��́j�Ȃ̂ł��낤�v
�@�������̎����i���@�j�͖������ł��邪�̂ɁA���ۊE�̕ω�������������v�i�p���W�K�[�j
12-4�j�����鎖�ۂ����݂�������������
�@24��14�u�K��������̂ɑ��ẮA��������̂��K������B�K�����Ȃ����̂ɑ��ẮA��������̂��K�����Ȃ��v���u��؊F��v�A����s��.�A���L�ł���Ȃ�Έ�͐������Ȃ��B
12-5�j���N�E�������E��̎O�T�O
�@�_���I��b�Â��̏����F���N �� ������ �� ��
�@���j�I���W�̏����F��i����т��̓��`��j�� ������ �� ���N(p.246�`247)
�@�������A��ς͕����̍��{�v�z�A����ɑ��ɂ����Ă݂̂��������̂ł͂Ȃ��B
12-6�j�w���_�x�̗��j�I�E�v�z�I�ʒu
�@���������ȗ��A��͐�����Ă������A��ɑ��āu�^�����v��l������u��X�̉߂�����v�Ɏ������̂ŁA�����ŗ������u���̈����̌̂ɋ�ł��邩�v��������邽�߂ɁA�w���_�x�ɂ����葖������B
�@���������āA���j�I�ɂ́w�ʎ�o�x�̊e�w��ʂ��Ă݂���悤�ȋ�ς���b�Â���^���̏I���ł���ƂƂ��ɁA�v�z�I�ɂ́w�ʎ�o�x�����̂��߂̎n�߂ł���B���w���_�x�͋�ς̓��发�B
12-7�j�̔r��
�@�u�����₭�Ԃ����v�́w���_�x�̒��S�v�z�̈�B���̎v�z�́w�ʎ�o�x�̏\����^��\��̒��̈�A�u���v�͂�����Ӗ����Ă���B
�@13��7�u��������������s��Ȃ���̂����݂���Ȃ�A��Ƃ���������̂����݂��邾�낤�B������ɕs��Ȃ���͉̂������݂��Ȃ��A�ǂ����ċ�Ȃ���̂����݂���̂ł��낤���v
�@13��8�u��̎�����E�����߂ɏ��ҁi���j�ɂ������ꂽ�B������ɐl���������������Ȃ�A���̐l�X���w���Ƃ����悤�̂Ȃ��l�x�Ƃ�̂ł���v
12-7���̋�
�@�@��͈�̌���ł��邱�Ƃł���ɂ�������炸�A���̋��L�Ɖ����邱��
�@�A�̈Ӗ��ɉ�����B�u���Ɏ������邱�Ɓv�Ɛ������B
�@��܂��͒f�ł̈Ӗ��ɉ��߁B�Ƃ́A�{���A��L�̈Ӗ��ł���ׂ����������āA�����L�̈Ӗ��Ɖ����邩�A�܂����̈Ӗ��ɉ����邩�A�����ꂩ�ł���A���ʁu�v�܂��́u��Ɏ������邱�Ɓv�ƌ����Ă���B
12-8�j�������₷���u��v
�@������Ȃ��́A���邢�͌����Ƃ݂Ȃ��₷���̂��}�v�̗���B
�@
13.�j�����@�[�i
13-1�j�L���̃j�����@�[�i�_
�@�j�����@�[�i�̎��̂�F�߂Ă����i���ז@�ɂ���u��Ŗ��v�_���}�ɂ���ĉ\�ƂȂ�jp.96�Q��
13-2�j�����̍U��
�@�L�͕K���V���Ƃ���������L���A���L�ׂł���A����ɔ����ĘV���Ƃ���������L�����A�����ׂł���L�͍l�����Ȃ��i25��4�j�B�ip.287�j
�@�������A�L�����L�ƍl�����Ƃ��Ă��A���́u�L�v�͈�́u���肩���v�ŗL��A�u�L����́v�idas Seiende�j�̈Ӗ��ŗL��A�g�D�E�I���̍l�����ɋ߂��ł��낤�B
�@����ɔ����ė����́i�����ł́j�u�L�v���u�����I���݁v�iExistenz�j�̈Ӗ��ɉ����ėL�����U���B
13-3�j�o���̃j�����@�[�i�_�Ƃ��̔���
�@�o���́u���Ȃ邱�Ƃ̂݁v�Ƃ������A���ː��̗��ꂩ��L���ے肳���̂ł���Ζ����ے肳��邩��A���͂��肦�Ȃ��B
13-4�j����l�ɂ͔��ɂ݂���c�_
�@25��10�u�t�i�u�b�_�j�͐����Ɣ݂Ƃ��̂Ă邱�Ƃ�������B����̂ɁA�w�j�����@�[�i�͗L�ɔA���ɔx�Ƃ����̂��������B�v
�@�L�ibhava�j�������������ibhava�j
�@���iabhava�j���������݁i�f�Łj�ivibhava�j
�@�����ꌹ�ɗR�����A�Ή��W�ɂ��邩��w�j�����@�[�i�͗L�ɔA���ɔx�́A�����̃C���h�l�ɂ͊�قɋ����Ȃ�������������Ȃ��B
13-5�j�j�����@�[�i�Ƃ�
�w���_�x�ł́A�j�����@�[�i���u���L�����₭���₭�ށv�ƂȂ����Ɓu��L�v�ƂȂ����Ƃ��_�j���Ă��邪�A����̓j�����@�[�i���l�啪�ʁi�@�L�ƇA���ƇB�L�����C�L�ł��Ȃ����ł��Ȃ����Ɓj��₵�Ă邱�Ƃ𖾂炩�ɂ��邽�߂Ɍ`�𐮂��ďq�ׂ��̂�������Ȃ��B
�@�j�����@�[�i�͈�̋Y�_�i�`����w�I�_�c�j�𗣂�A��̕��ʂ𗣂�A����ɂ�����Η��z���Ă���B���@�j�����@�[�i��������邽�߂ɂ͔ے�I�����������Ă�����ق��ɂ��������Ȃ��B
�@25��3�u�̂Ă��邱�ƂȂ��A�i���炽�Ɂj���邱�Ƃ��Ȃ��A�s�f�A�s��A�s�ŁA�s���ł���B�����@���ꂪ�j�����@�[�i�ł���Ɛ������v
�@�A�h���A���N�ƃj�����@�[�i�ƂɊւ��ĂقƂ�Ǔ��l�̂��Ƃ��q�ׂ��Ă���B
13-6�j�։�ƃj�����@�[�i�͓�������(p.294)
�@25��9�u������[���]��]����āA���邢��[������]�����Đ������������Ԃ��A���炸��炴��Ƃ��́A���ꂪ�j�����@�[�i�ł���Ɛ������v
�Ɛ�������A���݂ɑ��˂��ċN�����Ă��鏔������ŕϑJ����̂�}�v�̗��ꂩ��݂��ꍇ�ɁA������������܂��͗։�Ɩ��Â���̂ł���A���̖{���̂������̕����݂�j�����@�[�i�ł���B�l�������Ă����Ԃ������։�ł���A����z��������ɗ��Ƃ����j�����@�[�i�ł���B
�@25��20�u�j�����@�[�i�̋��ɂȂ���̂͂��Ȃ킿�։�̋��ɂł���B���҂̂������ɍł����ׂȂ邢���Ȃ��ʂ����݂��Ȃ��v�@���@��敧����ʂ̎��H�v�z�̍���
�@�l�Ԃƌ����̊W�͂��̂悤�Ȃ��̂ł��邩��A�j�����@�[�i�Ƃ����Ɨ��ȋ��n�����̂Ƃ��Ă���ƍl���Ă͂Ȃ�Ȃ��B�^�Ɏ��݂���ƍl����͖̂}�v�̖��ρB�̂Ɂw�ʎ�o�x�ɂ����Ă̓j�����@�[�i�́u���̂��Ƃ��v�u���̂��Ƃ��v��栂��Ă���B����Ɠ����ɗ։�Ƃ������̂��܂����݂��Ȃ��B
13-7�j���@�������j�����@�[�i
�@���ϔh�͉��N���Ă��鏔�����̋��ɂɃj�����@�[�i�����o�����̂ł��邩��A�������̐������\�Ȃ炵�߂Ă��鑊�ː����Ӗ����鏔�@���������Ȃ킿�j�����@�[�i�ł�����Ɛ�����Ă���B
13-6�u���ׁv�Ƃ�����̌��ӂɕ��A
�L���ɂ��ΗL�ז@�Ɩ��ז@�Ƃ͑S���ʂȖ@�ƍl�����Ă������A���ϔh�͗L�ז@�̐������Ă��鍪��ɖ��ׂ����o�����B���@���o�T����N�ׂƌ���
�@���������ɂ����ẮA�l���݂��\�������̎��ۂ����N�̂��Ƃ��ɏ]���@���̑����u�^�@�v�Ƃ�сA����ɂ��̐^�@��<����>�Ƃ��̂������A�������Ė��ׂƂ������̂�z�肵���̂ł͂Ȃ��ƍl�����Ă���B���ϔh�͂��̖��ׂƂ�����̌��ӂɕ��A���Ę_���Ă���̂ł��邩��A���̓_����݂Ă���ς͏��������̂����̎v�z���p�������̂ł���A����Ӗ��ɂ����Ă͐����h�ł���B
�@����ɁA���ϔh�̓j�����@�[�i�͋�ł���Ƃ������Ă���B��j�����@�[�i�
13-7�j��_�ȗ���
�@�����̌��������𗣂ꂽ�ފ݂ɁA�j�����@�[�i�Ƃ������n���邢�͎��̂����݂���̂ł͂Ȃ��B���˂��ċN�����Ă��鏔���ۂ��A�����ɑ������ꂽ�����������}�v�̗��ꂠ���璭�߂��ꍇ�ɗ։�ƌĂ��B����ɔ����Ă��̓��������ۂ̉��N���Ă���@������O������A���ꂪ���̂܂܃j�����@�[�i�Ƃ�����B�։�ƃj�����@�[�i�Ƃ͑S�������̗���̔@���ɋA������̂ł����āA���ꎩ�͉̂��獷�ʂ̂�����̂ł͂Ȃ��B�i�c�c�j�j�����@�[�i�̋��n�ɓ����Ƃ������Ƃ������Ȃ̂ł���B�ip.297�`298�j
13-8�j��͖�������
�@16��-5�u�������`�����ꂽ���̂͐��ł̐���L������̂ł����āA������ꂸ�A��E���Ȃ��B��������́i�O���j������Ɠ��l�ɔ�����ꂸ�A��E���Ȃ��v
�@16��-9�u�w�킽���͎����̖������̂ƂȂ��āA�j�����@�[�i�ɓ���ł��낤�B�킽���ɂ̓j�����@�[�i��������ł��낤�x�ƁA���������Ό���L����l�ɂ́B�����Ƃ����傫�ȕΌ����N����v
�@�u�����Ɖ�E�Ƃ�����v�Ǝv���Ƃ��͑����ł���A�u�������Ȃ��A��E���Ȃ��v�Ǝv���Ƃ��ɉ�E������v�i�w���_�`�x�j
�@�u�j�����@�[�i���Ȃ��v�Ƃ����̂́A����Ȃ�`���_���w�������ĉ��߂��邱�Ƃ̂ł��Ȃ����n�ł���B�ip.299�j
�@
�����w�҂䂦�̓r��̊��z(���L�[��)
�@�߉ނɂ���E�Ƃ͒������������ɂ���ė։��f���邱�Ƃ��������A���̕��@�͐��E�ɋ��Ȃ���ɂ��Đ��E�𗣒E�^�z���邱�Ƃ������B����𐢊E�ɑ���u���z�_�I�ԓx�v�Ƃ��Ă�<�ԓx�ύX>�ƌĂ�ł݂悤���B�i�����ܑ��O�Y�͉�E�ɂ��āu���ۊw�̒��z�_�I�G�|�P�[�Ə����߂��v�Ə����Ă���B�w���E���킩��@���Љ�w����x�A�����܊w�|���Ɂj
�@�����ۂ����E�����N���D��Ȃ��s���s�ł�<��>�ƓO������i���́j��F�̑ԓx�́A���ς��u���܁A�����Ɂv�ƌ������āA���E�𐴏i�~�ρj���邱�ƂȂ̂�������Ȃ��B<��>�͖{�����Ȃ��䂦�Ɂu�J���ꂽ�Ђ낪��v�ł���A���ʂ��Ȃ����݂̍m��Ƃ��Ă̟��ςł��邾�낤�B
�@
1�j�����̔ے聁���ȓ��ꐫ�̔ے�^���Ȓ��S���̔ے�@���@�u�{�����݁v����u�W���݁v�ւ̊J���^����A���ݓI���݂̍m��i���ː��j�B
2�j�u��19�́@���̍l�@�v�ւ̊��z
�@�u���ԁi���݁j�v���u���܁E�����̎��v�Ɠ��`�Ƃ���Ȃ�A�u���Ԃ̕s���݁v�Ƃ������Ƃ́u����v�Ƃ������Ƃɂ��Ȃ�B�܂��A�u���N�Ƃ��Ă̌��݁v���u��Ƃ��Ă̎��v�Ƃ������ƂɂȂ邾�낤���H
�@�ؑ��q�ɂ��A���l�ǂɂȂ�Ǝ��ԁE��Ԋ��o���Ȃ��Ȃ�A�������ł��銴�o��������B�i�w���ԂƎ��ȁx�A�������Ɂj
3�j�J���g�ɂ��A���ԂƋ�Ԃ́A�l�Ԃ̊����ɂ��Ȃ������ϓI�Ȍ`�����u���ρv�ł���B���������̌`���́u���ԁv�A�O�������̌`���́u��ԁv�ł���B�i�w���������ᔻ�x�j
�@
�i���e��2019�N01��08���ɍs��ꂽ�Ǐ���p�ɍ쐬�������W�����ł��B�j
�@
���v���t�B�[�������L�[��i����˂��E�ڂ�����j�B1950�N�㐶�܂�B�uWeb�]�_�u�R�[���v�̕ҏW�E���s�l�A�u�N�w�n���u��i���j�v���b�l�B����܂łɂ�����̓Ǐ���̐��b�l�����Ă����B10��̍��͎��l����Ƃ��u���Ă����炵�����A���͐̂̂��ƂȂ�B�u���O�F�V�� �m���[�� �J�t�F�ʊ��ATwitter�F���L�[��
Web�]�_���u�R�[���v50���i2023.08.15�j
���L�̃m�I�g�T�F�������w�����x��ǂށi���L�[��j
Copyright(c) SOUGETUSYOBOU�@2023 All Rights Reserved.
|
| �\���i�ڎ��j�� |
