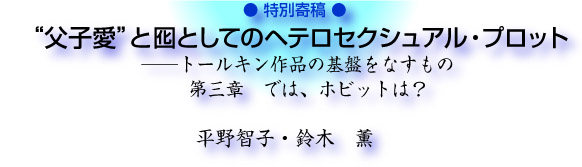|
|
|
Web評論誌「コーラ」 |
|
■創刊の辞 ■本誌の表紙(目次)へ ■本誌のバックナンバー ■読者の頁/ご意見・感想 ■投稿規定 ■関係者のWebサイト ■プライバシーポリシー |
|
<本誌の関連ページ> |
|
■「カルチャー・レヴュー」のバックナンバー ■評論紙「La Vue」の総目次 |
Copyright (c)SOUGETUSYOBOU |
|
|
『指輪物語』再訪
ホビットとは何だろう(そう訊けば、多くの本がこぞって教えてくれるだろう)。『ホビットの冒険』(1937年)と『指輪物語』(1954年)に登場する、足の裏に長い毛の生えた、茶色のもじゃもじゃ頭の「小さい人」たち。トールキンはなぜこのような存在を必要としたのだろう。『ホビットの冒険』では、「ドワーフ」、「エルフ小人」、「オーク鬼」らは、明らかに伝統的な物語世界からやって来ており、ガンダルフさえ、ただの魔法使として私たちの前に現われる。ガンダルフは『指輪物語』では天地創造の前からいたマイアールの一人であったことになっているようだが、『シルマリリオン』の世界にもとから属するわけでないことは後者を読めばすぐわかる。起源を曖昧にされているが、ホビットが「イルーヴァタールの子ら」(エルフと人間を指す)の一員ではなく、『シルマリリオン』の創造主イルーヴァタールの計画に最初から入っていたわけではないことも同様だ[☆24]。また、陽気で愉快なトム・ボンバディルは、「いいかね、皆の衆、トムは川や木よりも先にここにいた。トムは最初に降った雨の粒、最初に実ったどんぐりの実を憶えている。[…]エルフたちが西方へ渡り始めた時、トムはここにいた」と語っている以上、マイアでしかありえないが(エルロンドが「最古にして父なきもの」と呼んでいるのを見ると違うのかもしれない)、カーペンターの伝記によれば、トムの出自はトールキンの二男マイケルのものだったオランダ人形で、(長男の)「ジョンはこれが嫌いである日便所の中に押し込んでしまった」(191)。トム・ボンバディルはトールキンが書きはじめて放棄した子供用の物語の主人公になったこともあり、救出されたのち詩の主人公となったが、最後には『指輪物語』の中に永久にその姿をとどめることになった。
「トールキンの想像力」の「一方には、ほんの楽しみのために、(多くの場合)自分の子どもたちを楽しませるために、作られた物語」が、「他方には[…]彼自身の伝説に関わるより大きなテーマ」があって、トールキンがホビットのビルボを発明した『ホビットの冒険』までは両者は出会うことがなかったとカーペンターは言っている(203)。正確には、本当にそれらがつながったのは『指輪物語』においてだろう。カーペンター自身、「当初トールキンがビルボ・バギンズの気楽なブルジョア的世界を『シルマリルリオン』の広大な神話的風景につなげようなどとは露ほども考えていなかったことは確実である」と述べている。「しかし徐々に彼の神話からさまざまのものが浸透しはじめた」(211)。『ホビットの冒険』が、そして『指輪物語』がなかったら、『シルマリリオン』はけっして私たちのもとにまで届かなかったことだろう。人々(と出版社)がトールキンの次回作を待ち望むようになるためには、「一般の人々の想像力に適合するような平易なもの」(カーペンター、203)が必要だったのだ。「もちろんトールキンはこの欠落に気がつかなかったし、特段に自分にとって重要だとも思わなかった」。彼にとって重要だったのは、「ただ自分の興味を満足させるために」『シルマリリオン』を完成させることで、「他の人がこの仕事に関心を抱いてくれることはほとんど期待していなかった」(『指輪物語』の「著者ことわりがき」より)。
『ホビットの冒険』の続篇を書くよう期待されていたトールキンは、実際は「古い世界の始まりと盛時を語る」『シルマリリオン』の完成と出版をこそ望んでいた。しかし、それが望み薄の状況にあってそこだけは開かれていた『指輪物語』の場に、今や唯一の出口を見出したエルフの世界が「浸透」してきたのだ。その結果、一九五〇年にはアレン・アンド・アンウィン社宛の手紙で、トールキンは次のように書くことになる。「怪物をつくってしまったのです。(万が一だれかに向くということがあるとしても)子供には不向きな、途方もなく長く、複雑で、非常に心の痛む、ぞっとするようなロマンスを。しかもそれは実際には『ホビットの冒険』の続編というより『シルマリリオン』の続編なのです」(強調引用者。カーペンター、247-248)
スタンリー・アンウィンは理解しなかった。しかし、現代の読者は彼以上に理解しているだろうか? なぜ『指輪物語』は、(古い世界の)「終わりと衰退」を語るものになったのか。なぜ、エルフたちは衰退してゆくのだろう(そもそも〈エルフの世界〉とは何か?)「一つの指輪」が破壊されたのち、なぜ、エルフたちは中つ国にとどまることができずに、灰色港から西方の不死の国へ船出することになったのか(それ以前から続いていたとはいえ)。しかも、あれだけの労苦の果てに指輪を消滅させるという功績を立てた、エルフでもないフロドまでがなぜ?
これは『シルマリリオン』を読むことなしにはわからない事柄である(だから、トールキンが「著者ことわりがき」を公にしたとき、こうした問いに答えられる者は一人もいなかったと言える)。そして実は、「神話の
端的に言って『指輪物語』とは、エルフの「浸透」によってフロドがエルフになる話である。アラゴルンとアルウェンの物語など、畢竟、原型として先立つベレンとルーシエンの物語同様、囮としてのヘテロセクシュアル・プロットにすぎない。「地に足のつきすぎた」どころか、世代交替によって続いてゆく人間的時間、すなわち「生活」からはみ出したフロドは、エルフとして灰色港から旅立つしかないのだ。
トールキンの不死のエルフとは――そもそも不死を夢見る動機とは――「失われた道」で少年アルボインが実にわかりやすく説明している、次のようなものであった。
トールキンは「失われた道」ではヌーメノールの父子のものであった〈愛〉を、『シルマリリオン』のエルフの父子へ移した。彼らの愛、すなわち罪が、人間の死を生むことになった(これは『失楽園』でサタンの娘〈罪〉が〈死〉を生むのと符号している)。長子エルフが先に目覚め、あとから次子の人間が生まれるというイルーヴァタールの〈ストーリー〉が、エルフの原罪が人間に死をもたらすという〈プロット〉へ変わったのである。
〈愛〉を抜き取られたヌーメノールの話には、不死への執着や人間の傲慢さという要素が目立つようになった。また、『指輪物語』では、完全に人間(ないしホビット)視点なので、エルフが吸血鬼と異ならず、西へ旅立つことがもはや不吉なこととしか思えなくなっている。しかし、「それでもまだお父さんと一緒にいられれば好いと思う」という少年の単純でプリミティヴな願望は、「裂け谷のビルボのかたわらに心安らかにとどまり、憩いたいという抗いがたい願い」を持つフロドにまで続くことになるだろう。
オリエントとしてのアルダ
今日、『シルマリリオン』を知った目で『指輪物語』を読み返すなら、まず気づくのは、ビルボとフロドが〈父子〉であることにすでに重大な意味があったこと――トールキンの主要テーマの変奏であったこと――である。ビルボ・バギンズは「大金持ちで大変人」であり、「徐々に過ぎゆく時の歩みも、バギンズ氏にはなんの影響も及ぼさないように見えました。九十歳のかれは五十歳の時と同じでした。九十九歳になると、世間は、持ちのよい人といいはじめましたが、不変の人と呼んだ方があたっていたでしょう」。九十九歳の時、彼は年下のいとこ(これはcousinで、日本語のいとこより範囲が広い)の中で「一番年上でもあり、ビルボの一番お気に入りでもあった」フロド・バギンズを養子にする。「この時、フロドは、まだホビットのいう気楽な二十歳代で、つまり子供時代と、三十三歳で達する成人との間でした」(正確には養子になったとき、フロドは二十一であったことがこの先の記述でわかる)。
彼は幼くして両親をなくしており、サムの父親である〈とっつぁん〉に言わせると、ビルボが彼を引き取ったのは、「あの方のご親切ななさり方のなかでも、あれ以上のことはござるまいよ」ということになる。ホビットの視点は基本的に人間の視点に近いと言えるので、とっつぁんの感想はこのエピソードを読んだ、人間の読者の抱くものでもあろう。言い替えれば、トールキンは、最初から妻を持たないビルボとその後継者の関係が、(読者である)人間の目に不自然に見えないよう工夫したのだ――『失われた道』の父たち息子たちの場合よりずっと自然に[☆25]。
ビルボの長寿には、『ホビットの冒険』で彼が手に入れた指輪のせいであるという理由づけがされている。そして、111歳の誕生日にビルボが姿を消したあと、彼の財産を受け継いで、「ビルボがそうだったように、フロドも一人で暮らしました」と語られる。大家族が枝分かれした横穴に同居するのが通例のホビットの中で、彼らは例外的な独身者なのであるが、それだけではない。「時がたつにつれ、人々は、フロドにもまた「持ちのよいひと」のきざしが現われているのに気づき始めました。外から見たところ、かれは、大人と子供の境を脱け出て成人になったばかりの頑健で元気いっぱいのホビットの様子をいつまでも失わないでいました。[…]しかしどうもおかしいとみんなが思い始めたのは、ふつうならもっと重々しく落ち着くはずの五十という年齢にフロドが近づきはじめた頃からでした」(「旅の仲間」上)。
指輪を廃棄する旅に出る前からすでに、彼には通常の「生」からはみ出る兆候が見られている。それは「メリーとピピンは、フロドもまた、ビルボのように、時々エルフたちを訪れるのではなかろうかとあやしみました」とか、〈「このあたりだって、あのきれいな衆と知り合いで、噂の聞けるお人もいるんだぞ。」と、サムはいいました。「たとえば、おらが仕事をしに行くバギンズの旦那がそうだ。旦那はいってなすった。エルフたちは船出するんだと。旦那はエルフたちのことをいくらか知ってなさるんだ。ビルボ大旦那はもっと知ってなすった。[…]」〉といった、エルフとの親交の噂として言及される。
ところで、「あのきれいな衆」と呼ばれるエルフとは、何よりもまず美しい男のエルフである。これは、人間の読者に対しては特に強調しておかねばならない。旅の初めにフロドとサムにピピンを加えた一行が黒の乗手に脅やかされつつ道を急いでいたとき、「歌に笑いのいりまじった声」、「星明かりの空気をふるわせ」る「澄んだ声」として、エルフたちはまず感知される。ついで、「かれらの髪に、かれらの目に、星の光がきらめくのをホビットたちは見ることができました」。エルフたちはフロドの名を知っており、訝しむフロドにこう答える。〈「わたしたちが知っていることは多い。」とかれらはいいました。「あなたがビルボといる所をよく見かけたことがあるから。」〉明らかに彼らは、「エルフの友」ビルボと、その伴侶フロドの関係について、〈とっつぁん〉に代表されるホビットより多くを知っているのである。
二度目に一行(ピピンと馳夫(アラゴルン)が加わっている)が出会う、裂け谷から彼らを迎えにきたグロールフィンデルの場合も、その接近を知らせるのはまず音である。
そして、薄れゆくたそがれの光の中に輝き出す星々のようにそれがあらわれる。
これがトールキンのエルフ――花の中に住む愛らしい少女や「妖精の女王」ではない、彼の創り出したエルフである[☆26]。やがて、裂け谷のエルロンドの館の大広間で、館主の傍に坐しているのを見出すとき、彼はフロドの目に次のように映る。
宴が果て、一同が暖炉の火が燃える別の広間に移って、音楽が奏でられはじめると、「フロドは、一堂に会した人たちの美しい顔を心楽しく次から次へと眺めやりました。燃える火の
こうして、繰り返し記述されるエルフの美しさがすっかり読者の心に沁み入ったところで、フロドはビルボに再会する。ホビット村を去って旅をしたあと、裂け谷に戻ってきたのだとビルボは話す。「そしてずっとここにいた。あれこれやってみたよ。本の続きも書いた。もちろん歌も作ったさ。エルフたちが時々それを歌ってくれるがね。[…]それから歌や話に耳を傾けたり、瞑想にふけったり。ここじゃ時間はただ存在するだけで、過ぎ去ることがないみたいだ。何から何まで驚くべき所だよ。」
やはり、エルロンドのその名も「最後の憩」館は、エルフだらけの理想の養老院であったのだ! 教授職を退いてまだ日の浅い頃、鬱屈をつのらせたトールキンの日記は較べるのも哀れである――「何も成しとげることができない。行き詰まりと退屈のはざまに、そして不安と錯乱のはざまにあって、私はどうなるのだろう。本も無く、ひとりっきりで語りかける相手もいない。ホテルや老人クラブの一室に吸い込まれることになるのか。神よ……」(カーペンター、285)
むろん、「わたしは世界中の塔や宮殿を全部見せてもらうより、ビルボに会いたいんです」と言ったフロドは、彼のそばにそのままとどまることはできない。指輪を捨てる旅に出なくてはならないからだが、目的を果たしてフロドが戻り、執筆を引き継いで自らの冒険の話を書き終えると、やがて、ビルボとフロド、それにエルロンド、ガラドリエル、ガンダルフという三人の指輪保持者は、海を渡って中つ国を永遠に去ることになる。その理由については、この、「最後の憩」館滞在時に、すでにこう語られていた。
ここで言っておかなければならないのは、『指輪物語』における、指輪に関するもっともらしい御託は基本的にヨタだということだ。
何やらよくわからないが(エルロンド自身「たしかなことはわからぬ」と言っている)、予想される悲劇的な未来。大義のためならそれに喜んで耐えようという高貴なエルフの義侠心。「わたしが指輪を持って行きます。」というフロドの申し出。「運命はかく定まった」というマンドスの声(『シルマリリオン』で、中つ国で目覚めたエルフを聖なる西方の国ヴァリノールに連れてくることが決まったとき、こう言ったのだ)がまたも聞こえてきそうではないか。
そう、『シルマリリオン』を読んだ目で見ると、「指輪」もまた、それを捨てに行くという表面の筋は、モルゴスに奪われたシルマリルを奪い返しに、ノルドールがヴァリノールを捨てて中つ国に渡ったというのと同じ、いい加減な口実、人目をくらます囮、見せかけの物語、表の設定であることが見えてくる。
周知の通り、裂け谷に至るまでに、すでにフロドは黒の乗手に襲われ、肩に傷を負わされている。一見治ったように見える傷はフロドを苦しめつづけ、グロールフィンデルに出会ったとき、夕闇が深まるにつれ、彼は痛みと悪寒で倒れそうになる。「グロールフィンデルは地面にくずおれようとするフロドを抱き止め、やさしく両腕に支え、深い懸念を浮かべてその顏を覗き込みました。/かれはその指でフロドの肩の傷を探りましたが、その傷のただならぬことを知って懸念するかのように、かれの顏はますます憂色を深めました。しかしフロドの方は、脇から腕にかけて感じていた冷たさが薄れ、肩から手へと少しずつぬくみが伝わって来て、痛みもやわらぐように思えました。かえらを包む夕闇も、まるで雲が退くように薄れてゆくように思われました。友人たちの顏もふたたびはっきり見えてきて、新たな希望と力が少しは戻ってきました。」
グロールフィンデルの“愛撫”を誘い出したこの傷は、のちにエルロンドの館でガンダルフがフロドに説明したところでは、次のようなものだ。
ちょっとしたホラーであり、フロドならずとも「身震い」したくなろうが、ガンダルフの説明はまだ続く。
これが吸血鬼譚に他ならないことは容易に見て取れよう。だが、繰り返して言うが指輪がどうこうという部分(ガンダルフの科白にもあるが)はヨタであり、冥王だの、指輪の幽鬼だのというのも表設定であって、口実に過ぎない。
本当に恐ろしいのは(あるいは魅惑的なのは)、幽鬼に負わされた傷を口実に、フロドがエルフたちに「手当て」され、エルフ化して行くことだ(もともとエルフとの親交が囁かれてはいたが、それが推し進められる)。むろん彼らは血など吸わないし、生ける死人でもないので“吸血鬼化”とは言うまい。だが、彼らは致命的な外傷を負わないかぎり死なず、年も取らない「不死者」、つまり死すべきものから見れば怪物であり、その点、吸血鬼と何ら変わりはしないのだ。襲ったのは黒の乗手ということになってはいるが、吸血鬼の一噛みがそうであるようにフロドの受けたのはエロティックな傷であり、彼はついにそこから癒えることなく中つ国をあとにすることになる。
なぜなら、中つ国からエルフが去るということは、同性愛が公然と認められていたキリスト教に汚染されないヨーロッパも失われてしまうということだからだ。トールキンはそれを、過去の異教世界としては書かなかった。また、世紀末の耽美主義者や画家同様彼より少し前の時代に属する、男性作家たちのように、アジアやアフリカの(異世界)としても書かなかった。エレイン・ショウォールターによれば、そうした「男性冒険小説」には、「ヴィクトリア時代のモラルから自由になることのできる、どこか神話的な場所に行ってしまいたいという男たちの憧れが実にさまざまなかたちで表現されている」のであり、「世紀末の作家にとってこの自由な空間とは、自分たちとは違う浅黒い肌の人々が棲む「闇の大陸」アフリカ、あるいは神秘的な東洋のどこかであった」(『性のアナーキー』149)。しかしトールキンは、白皙のエルフが住まうアルダを創造したのだった。ショウォールターがエドワード・サイードを引いて言うには、《「オリエントはヨーロッパでは経験できない性的な冒険にはうってつけの場所であった」。そのような性的経験においては、男と女の境界線がぼやけてくるということもありえただろう》(149-150)。リチャード・バートンの有名な“男色帯”(「両性具有や男色や倒錯が支配する」「逸脱の地」)に触れて彼女は続ける。(男色帯は)「イベリア半島からイタリア、ギリシア、北アフリカ、小アジア、アフガニスタンへとのび、さらにパンジャブやカシミール地方を経由して、中国、日本、トゥルキスタン、そして南アジアの島々に達している。バートンによれば、こういった地域では、「男性的な性質と女性的な性質の混合が起こる」。[…]「この悪徳が人々のすみずみにまではびこり、最悪の場合でも些細な罪ぐらいにしか思われていない[…]」(150)
「男性的な性質と女性的な性質の混合」――トールキンにとってそれは両性具有的な美しいエルフであったので、間違っても人々にそのような「悪徳」の表現であると悟らせることはなかった。彼はヘンリー・ライダー・ハガードのように登場人物を遠くまで行かせはしなかった(子宮の洞窟の中心で待っている恐ろしくも美しい不死の女王は彼の感受性に訴えるものではなかった)。せいぜい、オックスフォードから一歩も離れずに、小心な教授を頭の中に聞こえてくる声にしたがって前世にタイム・ジャンプさせる程度だった。だが、試行錯誤の末、大胆にも彼はヨーロッパをオリエント化するに至った。そしてそのことを誰にも気づかれなかったのだ。
けれども、これまで述べたような設定(裏設定)ゆえにフロドは暗い。日に六度ごはんを食べる陽気で快活なホビットのイメージは主にメリーとピピンから来ようが、彼らはいわばグランド・ツァー(※)に出た(実際、いいところの坊ちゃんの)若者ホビットであり、文字通り一回り大きくなって帰ってくる。
しかし彼らもまたカップルなのであり、『指輪物語』にエオルが紛れ込んだかと目を疑う、意識不明の息子ファラミアに火をかけて焼身心中しようとしたデネソールを、ピピンは、フロドが敵に捕えられた証拠を見せられ、すべての望みが崩れ去ったかと思われたとき、メリーと離れ離れになったわが身に引きくらべて理解する。
『指輪物語』は必ず「追補篇」まで読まなくてはならない。少なくともサムが日常へ帰ってくるところで物語は終わるなどと記す愚はそうしていれば避けられるが、それ以外にも、たとえばメリーとピピンがその後どのように生き、最後はどうなったかについても、きわめて示唆的な記述を見出すことができるのだから。[☆28]
玻璃瓶とエラノール
『指輪物語』の幕切れで、中つ国に残るサム(とメリーとピピン)が見守る中、遠ざかる船上の「フロドの持っているガラドリエルの
これは、ガラドリエルの別れの仕種がフロドによって反復されているのであり、フロドもまたエルフになったことの証と見ることができよう。ガラドリエルの指輪「ネンヤ」の光は、ロリエンにおいて「さながら宵の明星が地上に降りてきて奥方の手にやすらっているかのように、ちかちかと瞬きました」(「旅の仲間」下)と描写されていたが、ガラドリエルの「玻璃瓶」もまた、「エアレンディルの星の光がわが泉の水に映じたのを集めてあります」と説明されるのだから、要するにそれはトールキンの物語のすべての核心であり、フィンウェとフェアノールの〈愛〉そのものに他ならぬ、シルマリルの光なのだ。
フロドを見送ったサムがメリーとピピンとも別れ、ひとり家に戻ってくると――
これは物語が終っての日常への帰還などではない。幼い娘エラノールがここで出てくるのは、けっして「現実効果」などではない。エラノールとはロスロリエンに咲いていた小さな金色の花の名で、「太陽星」(エルが星、アノールが太陽)を意味する。彼女は「この年に生まれた、あるいは儲けられた子どもたちは――その数は大勢でしたが――皆見るからに美しくまた丈夫でした。そしてこの子どもたちの大部分が従来ホビットの間では滅多に見られなかった豊かな金髪の持ち主でした」(「王の帰還」下)とある「大いなる豊饒の年」の翌年の生まれだが、実際に彼女も金髪で、「ホビットというよりエルフの乙女のように見えた」と「追補篇」の年表の註にもある[☆29]。「サムワイズのあとの二人の娘も金髪であった。その頃生まれた子どもたちの多くが金髪の持ち主であった」。
どうしてこんなに金髪の子供たちが生まれたのか、ロリエンの思い出なのか、それとも小麦の豊作とでも連動しているのか論理的には説明不能だが、これをトールキンの白人至上主義と見るのは間違っている。なぜなら、ここでは金髪とはけっして良きものでは――少なくとも、良きものの記号ではないからだ。
サムの膝に乗せられたエラノールの金髪は、その名前が金色の太陽の花であることからもわかるように、人間-異性愛の象徴である。サムが最前別れてきたフロドが船上でかざした玻璃瓶は、それに対立する、エルフ-同性愛-芸術なのだ。「物語と歌の終り」とは――「第三紀が終わり、指輪の時代は過ぎ去って、この時代の物語と歌にも終わりが来た」とは、正しくこのことを意味する。王となるアラゴルンに向かって、「三つの指輪の力もまた終わった。そしてあんたの目にはいる土地のすべて、またその周辺に横たわる土地のすべてが、人間の住む場所となろう、なぜなら人間の支配する時代が来たからじゃ」と言う、ガンダルフの科白も同様だ(ただし、三つの指輪の力云々というのは物語のための口実である)。人間と異性愛の時代が来たのであり、そしてトールキンは人間の話など書く気はなかった。
「大いなる豊饒の年」にはホビット庄では、先に引いたように美しく丈夫な子供が大勢生まれ、果物も穀物もあり余るほど獲れ、「パイプ草」もビールの出来も素晴しかったとされる。いかにもいいことばかりが起こったように書かれているが、実はこの豊饒と多産から、帰還したフロドはひとり疎外されている。人間の時代に「エルフ」は、人交わりのならない悲しい生き物として消えてゆくしかない。彼は繰り返し病み、そしてビルボとエルフたちとともに西方へ船出する時が近づく[☆30]。
一方、ローズと結婚してエラノールを得たサムは中つ国にとどまって、異性愛と生殖のサイクルを巡り終えねばならない。「おらは行かれません」と言うサムに、「そうとも、サム。ともかく今はまだ行けない、港より先にはね。もっともお前も、ごく僅かの間とはいえ、指輪所持者であったわけだね。お前の時も来るだろう[…]」とフロドは言う(指輪所持者云々は口実である)。サムは待たなければならない――妻が死ぬまで[☆31]。トールキンが待ったように――エディスの死を待って、オックスフォードに帰ったように。しかし、トールキンには人間の寿命しかなかったので戻っても二年しか生き延びることができなかったが、サムにはフロドのもとで暮らす時間を超えた時間がある。
「その後ずっとみんな一緒にしあわせに暮らしました」という物語の終りの決まり文句について、「それで、どこで暮らすんでしょう。おらがちょいちょい考えるのはそのことですだ」とかつてサムは言ったものだ。それは妻子のいるホビット庄ではなかった。ロリエンでも、「最後の憩」館でもなかった。ガラドリエルもエルロンドも西の国に去ってしまうからだ。「お前はこれから長い年月、欠けるところのない一つのものでなければならない。お前はこれからたくさんのことを楽しみ、立派なものになり、よいことをするんだから」というフロドの言葉通り、彼はホビット庄の長を七回つとめ、ビルボの「赤表紙本」に自分の物語を記し終えたのち、百二歳でエラノールに見送られて灰色港から海を渡って去る。最終的にどこで暮らすのか、ついにサムにもわかっていたのだ。
★プロフィール★
平野智子(ひらの・ともこ)
平野さんはどう書けばいいかを(電話で)囁いてくれる私のミューズです。【鈴木】 鈴木薫(すずき・かおる)
本稿は先に第二章となった部分が書かれ、読者の理解のために比較的短いまえがきとあとがきをつけるつもりが、結果的に元の三倍の長さになりました。『指輪物語』がこういう話だったとはわれながら驚きです。 あらためてコンセプトを記せば――
1. トールキンは腐男子である。
2. トールキンのエルフはフェアリーである。
というところでしょうか。
ブログ「ロワジール館別館」
Web評論誌「コーラ」10号(2010.04.15)
特別寄稿「“父子愛”と囮としてのヘテロセクシュアル・プロット――トールキン作品の基盤をなすもの:第三章 では、ホビットは?」平野智子・鈴木 薫
Copyright(c) SOUGETUSYOBOU 2010 All Rights Reserved.
|
| 表紙(目次)へ |