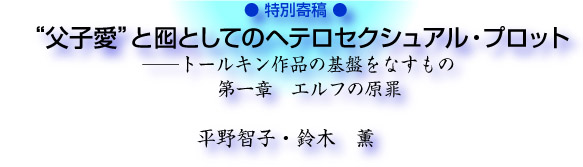|
|
|
Web評論誌「コーラ」 |
|
■創刊の辞 ■本誌の表紙(目次)へ ■本誌のバックナンバー ■読者の頁/ご意見・感想 ■投稿規定 ■関係者のWebサイト ■プライバシーポリシー |
|
<本誌の関連ページ> |
|
■「カルチャー・レヴュー」のバックナンバー ■評論紙「La Vue」の総目次 |
Copyright (c)SOUGETUSYOBOU |
|
|
あるトールキン論
ハンフリー・カーペンターの『J・R・R・トールキン 或る伝記』(1982年)は、端倪すべからざる書物である。原著が出たのがトールキン逝去後わずか三年の1977年、「遺族、友人、トールキンの著作の版元などの全面的な協力を得、利用しうる伝記資料を残らず使ってなった、いわば“公認”の伝記」(訳者「あとがき」)とうたわれているのを見れば、“公認”であればこそ、かえって生涯の外形的な出来事をかいなでるにとどまるのではないか、すでに役割を果たし終えた本で、今ではこれにまさる伝記が出ているのではと思われもしよう。実際、著者は、「私は、彼の虚構作品に対する批評的判断に一切立ち入らずに、トールキンの一生を物語ってみようとした」(「序」)と称し、これを(真に)受けて邦訳者は、「こうして描き出されたのは、非凡な人間ではない。巨人でなければ天才でもない、どちらかといえば、人間的な弱点を知的な抑制によってどうにか支えている、“あたりまえの人間”の姿である」[…](ただひとつ、この現実世界よりもはるかに豊饒で、はるかに“現実的”な世界を所有し、言語化したことを除いては)」と述べ、次のように続ける。「“あたりまえの人間”の生涯が語られることはない。[…]それでよいようなものであるが、ここでは、不思議な物語世界を生み出したために、ごくあたりまえの人間の一生が、克明に語られることになった。われわれは一風変わった、しかし等身大の人間の一生を、一つ余分に生きなおすことができるのである。望外のことといわねばならない」)――さても翻訳者とは自分の訳しているものが何であるかを知らない種族であることか!
実際にはカーペンターは、『ホビットの冒険』と『指輪物語』の作者が、そこそこの学問的業績はあったにしても「何の変哲もないオックスフォードの教授、中期英語の西中部方言を専門にし、子供を育て、庭の手入れをするありふれた郊外生活を送った教授であった」という、「不思議な逆説」について、次のように書いている。「そうだろうか? 正しくは正反対のことが真実ではないのか? むしろわれわれが不思議とすべきは、あのように才気煥発で想像力豊かな精神が、学問と家庭生活のいじましいくりかえしの中にとじこもって幸せでいられたということ、コーンウォールの岸壁に砕ける波の響きを慕う魂の持主が、中産階級のたむろする海水浴場のホテルのラウンジでお年を召したおばさまがたと語り合うことに満足したということ[…]こうしたことこそ、不思議に思うべきではないだろうか。どう考えたらいいのだろう?」(137)。
どうもこうもない。彼自身の文章中にすでに答えは出ているではないか。トールキンは幸せでいられなかったとカーペンターは言っているのだ。
最終章で彼はトールキン夫妻の有名な墓碑――エディス・トールキンの名にルーシエンの名を添え、J・R・Rの名にベレンの名を添えた(「いささか奇妙な碑文」と伝記作者は言い添えている)――を紹介している。墓の所在地が「トールキンが愛したイギリスの田園とは懸け離れた郊外」であることに読者の注意をうながしながら、カーペンターは、「その終末においてさえ、共同墓地の質素な墓によって、彼の送ったごくあたりまえの生活と、あのような神話を生み出す非凡な想像力の背反を、われわれは想起させられる」と言い、彼の想像力はどこから来たのか、その文学的ヴィジョンの源は何か、なぜそのヴィジョンが世界中の読者の心を打ったのか、と問う――
カーペンターは何を言おうとしているのか。トールキンの「真の伝記」が「『ホビットの冒険』であり、『指輪物語』であり、『シルマリルリオン』である」こと――これは完全に正しい。「彼についての真実」は、他のどこでもない、その作品の中に読み取られるという主張、これは文字通り受け取られなければならない(もしもここまでこの伝記を注意深く読んできた人なら、まさかこれをありがちな紋切型と見なすことはあるまいと思うけれど)。そしてそれは要するにもしそれを見る目がありさえすれば(ホフマンの『胡桃割り人形と鼠の王様』の最終部にあるフレーズだ)見られるものなのだが――カーペンターはそれを見ることができたのだろうか?
できたのだ、そして黙っているのだ。「この種の本の中では答えようのないもの」だと書いているその当の本の中で、彼が唯一、「あたりまえの生活」と「非凡な想像力」を仲介するものとして選んだもの――墓碑銘。そこには、トールキンの「非凡な想像力」の産物であるベレンとルーシエンの名と、「あたりまえの生活」(とは、しかし何か)を送ったジョン・ロナルドとエディスという、つかのま生を享け、今は失われた存在の名が、混同されて――正確に言えば、混同されることを願って――並べられている。そこでなら、「ごくあたりまえの生活」と「非凡な想像力」の隔たりは解消するとでもいうように。だが、そうやって相反するものが一つになるなどという考えは、トールキンはもちろん、この伝記作者の頭にも、一瞬ですらよぎることはなかったに違いない。むしろ、その「背反」が、何にもまして、否定しようもなく、あらわになり、鋭く、むき出しに、突きつけられ、逃れようもなく迫ってくる場所――しかし、「それを見る目」を持たぬ者にとっては、フィクションと現実の混同にたやすく誘われ、何とも甘ったるいヘテロセクシュアル・プロットに心地よく浸ることになるであろうその場所で、彼が見たのは、この墓誌に言及する多くの人々が語るものとは全く別のものだったと思われる。
だが、彼はそれを語りえなかった。「この種の本の中では答えようのない」ものであるからだが、しかし(実は)、それでも彼は語っている――語られた対象、つまりトールキンと同じやり方で。なぜなら、トールキンもまた、直接的には語りえないものを語ろうと努めた人であるからだ。カーペンターが明らかに対象と同じ――トールキンを模倣したとしか思えない――語り方を採用していることからも、トールキンの遺稿を調査する中で、彼がそれを見出したのであろうことは察せられる。この本が、たんに「トールキンの一生を物語ってみようとした」にすぎないという著者の控えめな表明に反して、ユニークなトールキン論たりえているのはそのためだ。
カーペンターのエディス・トールキンについての記述は、彼女とその夫の“ヘテロセクシュアル・プロット”をことさら美化しようとするものではけっしてない。十九と十六で下宿人同士として知り合い、ともに親のない身で、少年は十八の時に後見人である神父から年上の娘との交際――手紙を含む一切の接触――を二十一になるまで禁じられてそれに従い、二十一歳の誕生日に彼女に手紙を書いて、相手がすでに他の青年と婚約していたことを知る。誕生日の五日後、トールキンはエディスに会いに行き、その日のうちに彼女は婚約破棄を決める。
孤独な子供たちの出会いと別れと再会は、確かに、ほどよく感動的な物語ではある。結婚はさらにその三年後であったが、このいきさつについてカーペンターは、「フランシス司祭は利口な人間ではなかった。ロナルドとエディスを強制的に別れさせることによって、少年少女の間の淡い恋を、障害によってなおかきたてられる恋愛へと変質させていることに気がつかなかった」と書き、トールキン自身の三十年後の次のような文章を引く。「たぶん、あのような恋(真実の関係によって結ばれた純粋な関係であったにしても)を永続的なものにしようとする意志は、他のことによっては固まらなかったろう」(60)
エディスは夫より二年早く、八十二歳で亡くなっているが、もし彼女がトールキンより長生きしていたら、初の伝記はどんなものになっていただろう。結婚生活における(双方の)不満についての少なからざる言及に、彼女の直接的な言い分が加わったかもしれないのはもちろんだが、彼らの結婚の理由についても、彼女の側からはトールキンとは別の見方があったのではないか。それを公にするかどうかは別にして[☆1]。三島瑶子が、ジョン・ネイスンによる同様に“公認”の亡夫の伝記が出たあとに、回収を図ったことが思い合わされる。三島の性的傾向一般に関する話よりも、むしろ、彼女との結婚を決めたのが、癌の診断を受けた三島の母親(後に誤診とわかった)に息子の結婚を見せてやるためだったという記述に憤り、(当然のことながら)深く傷つけられてのことらしい。本を出す以前、ネイスンが瑶子さんの話も聞きたいと言ったとき、彼女は「瑶子の話はないわ」と答えた。また、三島を“怪しい”と言う人々の存在に言及して一笑に付し、同意まで求めたという。完全な否認。それが彼女の選んだ道であり、その後も彼女は、緒方拳が三島を演じるフィルムの日本公開阻止その他に成功しているが、それは三島が恐らくは舐め切っていたであろう世間に対して取った態度を忠実になぞることでもあった。堂本正樹が『回転扉の三島由紀夫』を出したことで、それも過去の話となってしまったが。
トールキンに関して『回転扉の三島由紀夫』のたぐいの書物が出ることは(残念ながら)ないであろう。では、「彼の送ったごくあたりまえの生活」の前で、私たちはいつまでも「あのような神話を生み出す非凡な想像力」との「背反」を感じていることしかできないのだろうか。そんなことはあるまい。三島に、その暗黙の教えに鈍重に従った――あるいはそれが彼女のなしうる唯一の抵抗あるいは復讐でさえあったのかもしれないが――遺産相続人がいたように、トールキンにも、まるで未亡人のように作品を守り、遺稿を整理して出版することに生涯を捧げた(ている)忠実な相続人があった。結婚相手の条件として自分の小説を読まない女であることを挙げた三島の場合と違い、彼はトールキンの作品に精通し、二人は、もし『シルマリリオン』を完成できずにトールキンが死ぬようなことがあれば、彼が代わって「完成して、刊行するようにと、決めて」(300)さえいて、実際そうなったのであるが、クリストファー・トールキンと三島瑶子が決定的に違うのは、前者がまぎれもなく作家に愛されていたことである。
愛――ノルドールの王フィンウェが、追放になった息子のあとを、王としての責任を放棄して追って行った理由が「フェアノールへの愛に惹かれ」であり、ドリアスを出奔したトゥーリンのあとを追ったベレグが、「かれへの愛情に負け、分別に背いてトゥーリンの許に留まり、帰ってゆこうとしなかった」のであってみれば、トールキン作品における〈愛〉が――とりわけ男同士のそれが――取り扱いに注意を要する言葉であるのは言うまでもない。むろん、私たちは、「伝記が文学鑑賞の助けになるとは」思わないのと同様、文学鑑賞が伝記の助けになるとも思っておらず、作品内に見出される〈愛〉をそのまま、現実のトールキンの、三番目の息子へ向けられた〈愛〉に適用しようなどとは思っていない。ただ、そこには明らかに並行関係が――トールキンとエディスがベレンとルーシエンであるという話とは比較にならないものが――見出されるのであり、恐らくカーペンターはそれを承知の上でこの本を書いている。
「ややくどくて、退屈するが」
未刊だった『シルマリリオン』(邦訳題は『シルマリルの物語』)の草稿にカーペンターがどれだけ目を通すことができたのか、また、クリストファーによる整理と編集を経ないそこからどれだけのものを汲み取り得たかは不明だが、少なくとも(残念ながら)『或る伝記』にフィンウェへの言及は見当たらない。しかし、トールキンの未完の小説「失われた道」については、注目すべき記述がある。C・S・ルイスの提案で、彼が宇宙旅行もの、トールキンが時間旅行ものを書くということで仲間うちで試みられたこの企画に関しては、ルイスのものがSF三部作へ発展したことや、トールキンのテクストが『シルマリリオン』と『指輪物語』をつなぐヌーメノールすなわち中つ国の西方に位置する巨大な島の物語の祖形の一つであることがしばしば言及されるが、カーペンターは「『失われた道』自体がニュ[ママ]ーメノールの物語を語ろうとする企てとは逆に一種の理想化された自伝であることは明白である」とはっきり書いているのだ。“理想化された自伝”――「失われた道」をまだ読む機会のない人(カーペンターの伝記が出た当時は、一般読者は全員がそうであったわけだが)は、その時までぜひこの言葉を心に留めておくといい。
「失われた道」は、トールキンと同時代のオックスフォードの歴史学教授とその息子が、ヌーメノールへ“時間旅行”する話である。といっても、タイム・マシンなどではなくて、前世の自分に同一化してその場所へ戻ってゆくとでも言ったらいいだろうか[☆2]。父であるアルボインは(当然のことながら)以前には息子でもあった。そして、息子としては父を熱愛したように、父としてはもっぱら息子オードインを愛している。人工言語(実はヌーメノールの言葉)への関心を、彼は子であったときは父と、今は息子と、二人だけで共有している。この言語とは彼らが作り出すというよりも思い出すもので、アルボインとオードイン(これらの風変わりな名前にもそれぞれ言語学的由来がある)は、アトランティスのように海に沈んだヌーメノールにおいても父子であり(そこではエレンディルとヘレンディルという名であった)、その言語を使っていたらしい。次第に取り戻される物語=記憶も彼らは共有することになる。では、彼らの妻/母は? カーペンターは次のように書いている。
トールキンの“理想化された自伝”とは、「早くに妻を亡くし、細君に悩まされない」というものであった(とカーペンターは言っている)! むろん、「失われた道」が一般読者の目に触れていなかった時点では、こうした細部と、トールキンの夫婦生活についてのカーペンターの忌憚のない記述を関連づけて読むのは、よほど注意深い読者に限られていたかもしれない。「トールキンがかくありたいと望んだような父子関係」についても同様だ。「父子関係の描写が」「ややくどくて、退屈する」――そうか、くどくて退屈なのか、とあれを知らない読者は思って、読み過ごすことだろう。だが、知っている者は――あれを「くどくて、退屈する」とは、この伝記作者はホモフォビアから内容に触れることを避けて通る気かと、一瞬、誤解しかねない。しかし、すぐに気づいて苦笑するだろう――確かに、あの思い込みの強い単調さは「くどくて、退屈」と評されるべきものなのかもしれない……。
過去へ戻ってからの、父親視点の叙述を引こう。
あるいは、
これ以前、アルボイン/エレンディルは、過去へ戻るという自分の選択に息子を巻き込んでよいものかぐずぐず悩んでいる。自分の申し出を息子が受け入れるであろうことを確信しているだけに、なおさら――。
やはり、「ややくどくて、退屈する」としか言いようがあるまい。
しかし、『シルマリリオン』をすでに読み、この時には中断を余儀なくされたこの父子関係が、のちに中つ国へ、人間からエルフへ、フィンウェとフェアノールとして――要するに必要な変更を加えられて――移されたのだとすでに見て取れる読者の目には、次のようなアルボインの逡巡は、別のことのあからさまな暗示ではないかと思えてくる。
アルボインの内的独白は、眠りに落ちる瞬間に近づくにつれ、混迷(ないし意味不明)の度を深めてゆく。
父親であることは事実ではなく「一つの選択」? とはいえ、「それは完全に意図した選択ではありえない」のだという(“恋に落ちるという選択”のように?)。たぶん、父親――あるいは父子関係――という言葉の意味に、通常とは違うものがあるのだろう(ということは誰にでも察しがつこう)。とはいえ、父親でないものがそう偽装しているというわけでもない。
アルボインは“選択”し、二人はヌーメノールへ「戻って」エレンディルとへレンディルになる(そこへ戻るとは、すなわちその「父子関係」に「戻る」ことを意味するのだ)。だがトールキンはその先を書か(け)なかった。そして、『シルマリリオン』では、フィンウェはけっしてこのように
アタリンヤ(アタリニャ)とは、クリストファー・トールキンが父の遺稿をまとめて出版したうちの一冊である『終わらざりし物語』に収められた断章「あやめ野の凶事」で、イシルドゥア(サウロンの手から「一つの指輪」ごと指を切り取り、「あやめ野の凶事」においては、指にはめたまま川に飛び込んだ「指輪」が水中で抜け落ちて、『指輪物語』のそもそもの発端を作った人物だ)との別れに際し、息子が彼を指して呼ぶ名でもある。一人逃げることをためらう父に口づけして行かせる、卒然と読めば恋人同士かと見まごう纏綿たる口説きは、しかし、実際には見紛っているわけではないのだろう。たぶん、「アタリンヤ」という呼称自体、「父上」とも“Father”とも異なるコノテーションを持つのだろう(何が書かれているかはエルフとエルフに強い影響を受けた人間には自明であり、のちの世の人間の読者のみが誤読するのだ)[☆3]。そのためにこそトールキンの人工言語は作られたのであり、「アタリニャ、テェ=メラーネ」を口にのぼせる場を可能にするためにこそ、トールキンのエルフをめぐるすべての物語は書かれたのであろう。(『シルマリリオン』の)「人名と地名は、トールキンの発明言語から組み立てられたものだ。これらの言語の存在こそ、全神話体系の
言語学的関心と物語への情熱が手をたずさえていること――これについてはアルボインに託した次のくだりが、たぶん最も直截に語っていよう。
ホモソーシャリティ?
注目すべきは、この、トールキンの愛しあう父と子の関係は、通常のホモソーシャリティ――男の友情の外見を取り、女を排除するが、同性愛とは一致したりしなかったりする――と同一ではないことだ。ホモソーシャリティについては、C・S・ルイスの登場を語る章での(むろん、この言葉を使ってはいないが)カーペンターのコメントが大いに参考になろう。『四つの愛』に収められたルイスの「友情についてのエッセイ」について、彼は次のように言っている。
ただし、七ページ先でチャールズ・ウィリアムズが現われ、ルイスが彼に熱を上げるようになると、先ほどのは建前であって、トールキンが彼を忌避したことは「完全に知的なものとはいえないかもしれ」ず、「真の友情というものは、別の人間が加わっても嫉妬心を抱かないものだとルイスは『四つの愛』の中で明言しているが、しかし、そこでルイスは自分について語っているのであって、トールキンについて語っているのではなかった」とカーペンターは率直に指摘している。カーペンターによれば、彼らの世代の場合、第一次大戦で多くの友人を失ったことに一部由来してもいる「この種の友情は人目につくものであったが、同時に、完全に自然で不可避のものであった。同性愛ではないが(ルイスは、このような仄めかしを、当然の嘲りをもって一蹴した)、しかし、女性は排除された。このことはトールキンの一生における大きな謎だが、その解析を企てても、何もわかりはしないだろう。逆に、この種の友情を経験したことがある人なら、それがどんなものか、はっきりとわかるものである。たとえよくわからなくても、それが『指輪物語』の中に表現されていることを見つけることができる」(171-172)
確かに見つけることができよう。しかし、『指輪物語』のエルフたちが、「同性愛ではないかという仄めかしを、当然の嘲りをもって一蹴」する、などという場面が考えられようか。仄めかしなどありえないまでにイノセントだからではもちろんない。取り立てて言う必要がないほど、それが性関係を含みうることは「完全に自然で不可避」であるからだ。とはいえ、『指輪物語』における男同士の関係の多くは、基本的には単なるホモソーシャリティに見える[☆4]。
同性愛ではないかという「仄めかしを、当然の嘲りをもって一蹴」しうる友人たちの前で、「失われた道」のようなテクストを朗読するのがどんな経験であり、彼らからどのような反応を得られたかはそれ自体興味深いが、男たちとの(それも最上の友と互いに認める者たちとの)ホモソーシャルな関係のうちに身を置きながら、トールキンがある意味完全な孤独のうちにあったことを推察するのは難しくない。カーペンターによれば、彼の生きたのは「ワイルドの時代に、オックスフォードに初登場し、一九二〇年代から三〇年代の初めになってもまだぐずぐず残っていたその後継者たち」である耽美主義者の、「過度のダンディズムと、それに暗示されるホモセクシュアリティに対する反抗」が、「簡素で男っぽい衣服への嗜好」の一部をかたちづくっているような時代だったのであり、今日、私たちの目にいかにも英国の大学教授らしいと映る、彼らの写真に見る「普通の」地味な服装や髪形が抑圧したものがあったのである。トールキンの美意識について私たちはほとんど何も知らない(彼の作品を通して以外には)。現実には彼は「おぞましい家」に住んでいた。「おぞましい絵のかかった、どんなにおぞましい家か、とても口にすることはできない」。W・H・オーデンがこう言ったのも、彼の美意識がそこに表現されていないのに驚いてのことだろう(実際にはオーデンがお茶を飲んだのはエディスの部屋だったが)(カーペンター、293)。
だが、この無知をいつまでも放置しておくことは、トールキンの作品に外から解釈を押しつける“おぞましい”たわ言の増殖にしか寄与しないだろう。著名な作家であることを考えれば驚くべきことだが、ありし日の彼が何を好み、何を見、何を読んだのか――具体的に彼を通過したどんなものからあの作品が構成されるに至ったのか――私たちは今なおほとんど知らないのである。たとえ彼自身が影響について語らず、自分の好みを明かすことがなかったにしても[☆5]。
トールキンの服装からは、彼が(何を非としたのかではなく)「何を是としたか」も、読み取ることができるとカーペンターは書いている。「つまり穏当で気がきいていて華美でなく、イギリス的なものに対する愛情を」。「しかしそれ以上ということになると、彼の衣服からは、それを着た人間の微妙で複雑な内面の本性はなにもわからない」と、彼はいかにもこの伝記作者らしく周到につけ加えている(148-149)。
トールキンの“萌え”は父子関係に収斂してゆくのだが、これには複数の利点があったと思われる。まず、人間の読者には、父子というだけで、性的な関係であることが全く見えなくなってしまうことだ。そして――利点という言葉がふさわしいかどうかはともかく――彼が敬虔な信者であったといわれるカトリシズムにおいて、父子関係(父子の〈愛〉)とはまさしく核心をなすものであり、これを冒涜と思えるまでに最大限に流用しえたことだ。今回は十分な検証をする余裕がないが、トールキンが『シルマリリオン』の下敷にした重要なテクストの一つは、明らかにミルトンの『失楽園』であり、具体的な細部の照応が可能である。ヴァリノールという楽園、二本の木、造られた果実である三つのシルマリルという道具立てが揃っているのは十分に見て取れながら、いかなる罪が犯されたのかが理解できないために、指摘する者がいないのだろう。
もう一つの重要な枠組は「オイディプス王」で、これは『シルマリリオン』の序文に収録されているウォルドマン宛書簡でトールキンも(気乗り薄ながら)挙げているインターテクストであるが、誰の目にも明らかな(トールキン自身むろんそれについて言っている)、兄妹であると知らずに近親姦に陥るトゥーリンとニエノールの物語のみに関して言うのではない。フィンウェとフェアノールの場合がすでにオイディプスなのだ(ただしこちらはもちろんすべてを知っている)。フィンウェは、ライオスとイオカステーを一身に兼ねた存在で、結婚前のライオスの行状に相当するもの――メリアンにナン・エルモスの森で足止めされる以前、彼のもとに通ってきていたエルウェとの関係――も欠けてはいない。フェアノールの誕生を語るくだり(122)に、邦訳では「フィンウェの長男で最もかれに愛された男子が生まれた」とあるが、ここは原文に忠実に「最もかれに愛されたもの」とすべきであったろう。
最も愛されたもの
トールキンの場合、「最もかれに愛されたもの」が誰であったかは見間違いようがない。それは妻であるエディスなどとは比較にならない関係である。トールキンのエディスとのぎくしゃくした仲をも、すでに触れたようにカーペンターはあからさまに描写している。しかしそのあとに、たいていは直前に書いたことを半ば打ち消すようなことをつけ加えて衝撃を緩和し、二人がそれでもなお愛情深い夫婦であったことを印象づけようとしている。このやり方は(トールキンも『シルマリリオン』で愛用しているのだが)、読者をはぐらかしきれずに、しばしば矛盾した、二枚舌の印象を残すことになるが、次の記述など、それがほとんど滑稽の域に達した例だ。
これはたんに、他人の前では自分たちの愛情を疑わせないように完璧に取りつくろうことができる夫婦だったということではないか。トールキンはエディスにはカトリシズム(彼にとってそれは早逝した母の思い出に通じるものだった)への改宗にはじまって少なからぬ犠牲を強い、独身時代の彼女の交友関係(改宗がすでに、それに深刻な打撃を与えるものだった)を根こぎにし、のちには彼女には馴染めないオックスフォードで(そこで彼は男たちとの付き合いに熱中した)長年暮らすことを余儀なくさせた。引退後、その罪滅ぼしに避暑地ボーンマスで過ごすようになると、「彼女は自分本来の環境に戻り、完全にくつろいだ。オックスフォードでは絶えてなかったことだし、彼女の結婚生活の他のどんな時期にもなかったことだった」(292)。要するにエディスは、ボーンマスのミラマー・ホテルで出会う引退した俗物たち(とはカーペンターは書いてないが、「保守的で子供達や孫達のこと、共通の知り合いのことについてお喋りするのが好きで、時たま海岸で散歩する他は、一日の大半を宿泊者用のラウンジで過ごすのを幸せと感じ、正餐の後にもずっとコーヒーを飲み、寝る前にテレビ室で九時のニュースを見れば満足する、そういう人たち」(292)と言っている)と話が合ったのだ。「ロナルドの作家としての名声をエディスがどんなに誇らしく思ったか」とは、「いまや彼女は彼らの誰にも負けないくらい経済的に豊かだったし、肩書についても、国際的に著名な著者の妻という地位は、彼女の気後れを払拭した」(202)という記述を見れば(見なくても)、彼女の喜びが、彼女の生活の快適さに彼の作家としての成功が直接関係していることから由来するのは明らかだ。
トールキンはそのような会話を楽しめなかったし、「たまたま客たちの中に、きちんとした考えを口にできる男友達を見つけることはできても、囚われの身になったような気が頻繁にして、黙りこくったまま無力な怒りに落ち込むのだった」。こう記した直後にカーペンターは、「しかし、それを除けば、ボーンマスの休日は、トールキンには、願ったりかなったりのものであった」(293)と言っているけれど、もはやそれを読んでも、読者はあまり喜ばしい気持ちにはならないであろう。
すでに引用した、二人がはた目にも(は?)いかに愛情深い夫婦だったかという記述の直後には、「二人のしあわせの最大の源泉は家族に対する共通の愛情であった。生涯の終わりに至るまで二人を結び合わせたもの、結婚生活に於けるもっとも強い力は、この愛情であった」とある。要するに子供の存在だけが彼らをつなぎとめていたのかと読まれかねないこの文章ではじまる節が次のように結ばれるのを見るとき、私たち――発表時の読者と違い、イノセントではない私たち――はそこに、ほとんどカーペンターの悪意すら見て取りはしないだろうか。
エディスが三度目に身ごもった子は、彼女自身は「女の子であってほしいと願った」が、男の子だった。「赤ん坊はすくすくと育ち、ことの他、父親の寵愛を受けた。父親の日記。『今や、私は神がさずけたもうたものなしには生きていけない』」(132)
これが、一九二四年に生まれたクリストファーへの最も幼い時の言及であるが――ちなみに、上の二人の息子および末娘についてのこうした記述はない(少なくとも『或る伝記』には)――二十年後、五十二歳になったトールキンは、空軍に召集され南アフリカでパイロットの訓練を受けていたクリストファーに宛てて『指輪物語』の進捗状況を書き綴ることになる。作品についてもむろん非常に興味深い記述が続くが、ここでは目的を限って引用することにする。
これらは、カーペンターが私たちのために集めておいてくれた、「最もかれに愛されたもの」についてのささやかな記録である。さらに歳月が流れ、教壇を去り、ボーンマスに家を買ってオックスフォードから移転した一年後、トールキンはクリストファーにこう書くことになる。「[…]私と同種の人間はここにはいない。[…]そして何よりも、お前がいないのが淋しい」(294)。例によってカーペンターは、この手紙を引用した直後に、「しかし、この犠牲には目的があり、その目的は達成された」と述べ、エディスがいかにそこで幸せになったかを物語り(「結婚以来もっとも幸福で、その幸せは、一貫していやましになっていくのだった。この新居の住み心地のよさ、苦労の種の階段がないという利点の他に、ミラマー・ホテルを訪れ、そこでできた友人関係を楽しむという永続的な喜びがあった」)、「そして、トールキン自身にとっても、全体としてみれば生活はずっとよくなった。エディスの幸福は、彼にとって深く満足すべきことだったし、それは彼自身の心理状態にも反映した」(295)と説くのだが、トールキンの結婚生活について述べるカーペンターの手口はすでに十分伝わったと思うので省略したい。
ところで、トールキンのかくのごとき引退生活と対蹠的なめぐまれた“作家”のそれを、『指輪物語』の読者なら知っているはずだ。彼はこう語っている。「ここは暖炉がとても気持ちがいいし、食べものも非常に上等だ。それにエルフに会いたきゃエルフはいるし。これ以上何が望めるだろう?」
裂け谷のエルロンドの館に滞在するビルボが、「紙やペンや鉛筆が散らかって」いる部屋で、指輪を破壊する旅から戻ったホビットたちを迎えてこのように言う。話しながらもつい眠り込んでしまう老いたビルボは、最後にフロドにこう持ちかける。
現実世界では「行く前」ではなく行ったあとに、「持っていく」のではなく残していったものを、息子が(フロドもビルボの息子(養子)である)「選んだり整理したり」して「恰好」をつけることになるのだが――。トールキンはこの残酷な類似に気づいたであろうか? 彼の人生が芸術を模倣し、しかしそこにはエルフはおらず、(裂け谷ではなく)「なんとも名状しがたい海岸の保養地」の、(エルロンドの館ではなくミラマー・ホテルの)「中産階級のたむろする海水浴場のラウンジでお年を召したおばさまがたと語り合う」しかなかったことに。トールキンは最後にはオックスフォードへ帰ることになる(エディスの死によって解放されて)。エディスがボーンマスで「結婚以来もっとも幸福」であったとすれば、トールキンはマートン学寮で「いまだかつて憶えがないほど自由で、好きなように人生を生きてよかった」(299)。エルフではなく、ホビットですらないので、残された時間はわずかであったが。「ボーンマスが、ある意味では、結婚生活の初期にエディスが直面したことを残らず償うものであったように、マートン通りでのトールキンのほとんど独身者流のあり方は、ボーンマスでの彼の忍耐に対する報酬であるかのようであった」と、いつもながら適切にカーペンターは書いている。
「この堕落した世界の悲しい定め」
エルフについて、「彼らはあらゆる意味で人間なのである。いやむしろ、堕罪によってもの事を成し遂げる力を失う以前の人間なのである」(115)とカーペンターは言うが、これは半分しか正しくない。一方に「堕罪」した人間がおり、一方にそうでないエルフがいるような書き方を彼はしている。真実は、エルフの堕落の結果、人間が生まれたということだ。ヴァリノールでフィンウェとフェアノールによって犯された罪(表面的には、それはモルゴスが来てシルマリルを奪って行ったという事件としてしか人目に触れない)によって、太陽が生まれ、中つ国で人間が目覚める[☆6]。太陽はエルフの衰微のしるしとされるが、人間もまたそうなのだ。いや、正確に言えば、「もの事を成し遂げる力を失」ったエルフとして人間はそこにいて、彼らを前にエルフたちは失われたものとして西方に去って行くしかない。
『指輪物語』の読者は、サウロンと「一つの指輪」が滅ぼされたとしても、エルフたちはヴァリノールへ船出しなければないという設定に、疑問を抱かないのだろうか。中つ国からエルフたちが去らなければならないという理由は、少なくとも『指輪物語』の中には見当たらない。『シルマリリオン』を知らずしてなんで『指輪物語』がわかるのかと、トールキンは心から思っていたに違いないのだ。
人間はエルフとして堕落し、堕落した結果、人間となった。エルフは去り、人間はそれを
「エディスのいじましい悩み」に対して大袈裟なと思うなかれ。これは実は本質をついているのだ。
これは、トーマス・マンがリスト・アップしてみせた「人間の中の二つの方向」である(海野弘『ホモセクシャルの世界史』による)。『シルマリリオン』も『指輪物語』も明らかに芸術家小説であり、前者では創造神「イルーヴァタール」と名告って、作者は
その一斑は、本稿の最終章で示すが、その前に、トールキンの“理想の父子関係”のネガと言うべき、エオルとマイグリンの場合について考察することにしたい。『シルマリリオン』においてモルゴスは表面上の――物語の上での――形式的な(悪)であり、トゥーリンとニエノールが近親姦に陥ったのも「モルゴスの呪い」のせいであって、さればこそ彼らは読者の同情を獲得しうるわけだが、そうしたエクスキューズが剥ぎ取られたとき何が起こるか。それが「エオルの場合」である。
(第二章に続く)
Web評論誌「コーラ」10号(2010.04.15)
特別寄稿「“父子愛”と囮としてのヘテロセクシュアル・プロット――トールキン作品の基盤をなすもの:第一章 エルフの原罪」平野智子・鈴木 薫
Copyright(c) SOUGETUSYOBOU 2010 All Rights Reserved.
|
| 表紙(目次)へ |