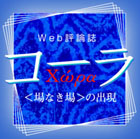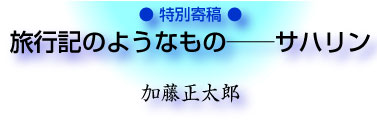|
|
|
Web�]�_���u�R�[���v |
|
���n���̎� ���{���̕\���i�ڎ��j�� ���{���̃o�b�N�i���o�[ ���ǎ҂̕Ł^���ӌ��E���z �����e�K�� ���W�҂�Web�T�C�g ���v���C�o�V�[�|���V�[ |
|
���{���̊֘A�y�[�W�� |
|
���u�J���`���[�E�������[�v�̃o�b�N�i���o�[ ���]�_���u�k�� Vue�v�̑��ڎ� |
Copyright (c)SOUGETUSYOBOU |
|
|
|
�@�ɉE���͂̋c�ȓƐ�
�@
�@��N�i2011�N�j12���ɍs��ꂽ�O�c�@���I���̒��O�Ɏ��́A�����V�����{�łɌf�ڂ���Ă����A�����ȃA���P�[�g���ʂ������̂ł���B����́A���{�I����̑S���҂ɑ��čs��ꂽ���̂ŁA������Ɂu�����p�~�v��u����ő��Łv��u�s�o�o�Q���v�ɑ���^�ۂ�₤���ڂ��������̂ł͂��邪�A���̖ڂɔ�э���ł����̂́A���V�A�A�����A�؍��A�k���N�ɑ���u�e���݁v��₤���ڂȂ̂ł������B�����Ă����ɂ́A�u����v�u�ǂ���Ƃ������Ȃ��v�u�Ȃ��v�Ƃ������p�ӂ���Ă���A���҂��Ƃɂ��̌��ʂ������~�Ƃ����L���Ŏ�����Ă����̂ł���B���������Ύ��́A�u�e���݁v�Ƃ������t�ɋ��┽���������Ă��܂��A�n�ǂ��邱�Ƃ������A�܂��蔲�������Ȃ������̂ŁA���̏ڍׂɂ��Ă̋L���͋ɂ߂ĞB���Ȃ܂܂Ȃ̂ł���B�܂�A������������Ώۂɖk���N�͂Ȃ������������ꂸ�i�u�e���݂��Ȃ��v�͓̂��R�̂��ƂƂ���Ă��邩��j�A����Ɂu�č��v����������������Ȃ��Ƃ��������肳�܂Ȃ̂ł��邪�A���������̂��Ƃ́A�����v�킸�ڂ�w���Ă��܂������R�ɂ͉���e�����Ȃ��Ǝv���̂ł���B���͎��̂悤�Ɏv�����̂ł������B
�i�P�j����c�����Ɂu�����ւ̐e���݁v�̓x�����ȂǕ����ĉ��̈Ӗ�������̂��낤���B���������m�肽���͂��̂��̂́A���E���a�ɂ��Ă̗��O��v�z�ł���A�u�e���݁v�́u����E�Ȃ��v�Ȃǂɂ���ĊO����j�����E����邱�Ƃ��������Ƃ�����A����͂ނ���댯�Ȃ��Ƃł͂Ȃ����낤���B
�i�Q�j�܂�����́A���������ȒP�ɓ����邱�Ƃ��ł���ނ��̎���Ȃ̂��낤���B���Ƃ��u���V�A�ɐe���݂������Ă��܂����v�Ɩ��ꂽ�Ƃ��A�ǂ��������炢���̂��A���ɂ͌��������Ȃ��̂ł���B�K���Ɏ����g�́A�T�n�����i�����j��10���قǗ��s�������Ƃ�����B�����琸��t�̉Ƃ��āA���̎��̃G�s�\�[�h���ۂȂǂɂ��ĉ������璝�邱�Ƃ͂ł��邾�낤�B����ǂ�����������~�ȂǂɏW��ł���Ƃ͓���v���Ȃ��̂ł���B�ł́A�s�������Ƃ��Ȃ��ꍇ�͂ǂ�����̂ł��낤���B�h�X�g�G�t�X�L�[��g���X�g�C���v�������ׂ�̂ł��낤���B���邢�͓��I�푈�̂��Ƃ�z�N���ׂ��Ȃ̂ł��낤���B���邢�́u�k���̓y�v�̂��Ƃ��܂��͑��ɔO���ɂ����ׂ��ł���̂��낤���B
�i�R�j�����v���ɁA�u����Ȃ�����Ȃ��A�܂��A�ȒP�ɂ͓����邱�Ƃ̂ł��Ȃ��A���A�댯�Ȏ���͂��Ȃ��ʼn������v�Ƃ����̂��A�ł��������Ȃ̂ł��邪�A���̂悤�ȉ͎���҂ɂ���āu���ہv�ƕ��ނ���邩�����ꂸ�A�L���҂Ɉ���ۂ�^����댯����������̂ł���B�܂����Ƃ������ɑ[�u���ꂽ�Ƃ��Ă��A�u�ǂ���Ƃ������Ȃ��v�ɕ��ނ����̂������ł��낤�B�������u����ւ̈ӌ��v�Ɓu�ǂ���Ƃ������Ȃ��v�́A�������Ⴄ�̂ł���B����������Ɉ������Ƃɂ́A�u�ǂ���Ƃ������Ȃ��v�Ƃ������̂��A�u�v���[���v�̌���ł͂Ȃ��A�u�D�_�s�f�v�Ǝ��ꂩ�˂Ȃ��Ǝv����̂ł������B
�@ ���͂��̃A���P�[�g�́u����I������Ȃ��v�̗��R���l���悤�Ƃ��A�k�J���ɏP����̂ł��������A�Ƃɂ��������͐������Ȃ��Ɛ�ɐi�߂Ȃ��ƍl���A��L�̂悤�ɂ��̂Ƃ����������Ƃ������Ă݂��̂ł���B���������̐悪����̂ł������B
�i�P�j���Ƃ������ł����u���V�A�v�Ƃ́A��Ɏv�킸�u�����ւ̐e���݁v�Ɨv�Ă��܂����悤�ɁA���������Ɂu���v�̂��ƂȂ̂ł��낤���B���邢�́u���V�A�l�v�̂��ƂȂ̂ł��낤���B
�i�Q�j�܂����ꂪ�u���v�ł���ꍇ�A����͐����̐����w���Ă���̂ł��낤���A���邢�͗��j�╶���̂��Ƃ���Ɏw���Ă���̂��낤���B
�i�R�j�܂��u�e���݁v�̑Ώۂ��u���V�A�l�v�܂�u�l�ԁv�ł���ꍇ�A����͑��l�ł���ꍇ������A�m�l�E�F�l�ł���ꍇ������ł��낤�B
�@�������A���Ƃ��u�G�J�e���[�i�Q�����D���v�u�j�W���X�L�[���D���v�u�G���c�B�����D���v������u���V�A���D���v�ƂȂ����ꍇ�A����͗��j�╶������Ɋւ�邱�Ƃł��邩��A�u�l�ԁv�ł͂Ȃ��A�u���ɐe���݂����v�̈ꕔ���\�����邱�ƂɂȂ�͂��ł���B���������u�l�ԁv�Ƃ́A�l�ł�����W�c�ł�����̂ł������B�Ƃ���Ɓu�e���݁v�����Ώۂ��i�P�j�̂悤�Ɂu���v�Ɓu�l�ԁv�ɕʂ��čl�����̂������������Ƃ������ƂɁA�܂�U��o���ɖ߂��Ă��܂��̂ł���B
�@�܂��u�e���݁v�������肪���āA���ꂪ�m�l�E�F�l�ł���ꍇ�ɂ��Ă��A���Ƃ����̗���]�����āA�܂胍�V�A�l�ł���`���u���{�ɐe���݂������Ă���v�ꍇ�ŁA���̗��R�́u���{�l�̗F�l�a�����邩��v�ł������ꍇ���l���Ă݂�ɁA���̗F�l�a���A���{�E�Ό��E�������̋ɉE�����Ǝx���҂ł������ꍇ�ƁA�����ɉE�����Ƃɑ��đ����݂����l���ł������ꍇ�ł́A�`���u�e���݂����v���R���傫������Ă���̂ł͂Ȃ����낤���i�܂聛�Ƃ����L���͉��������Ă���Ȃ��̂ł���j�B
�@���͍ŋ߁A�w�̉Ԃ̉��x�i�i�n�ɑ��Y�j�Ƃ����{��ǂ݁A�]�ˎ���̏��l�E���c���Õ��q�ƃ��V�A�C�R�R�l�E���R���h�Ƃ́A1812�N�����N�Ԃɂ킽��𗬂ƁA��l�̊ԂɈ�܂ꂽ�F���M����悤�ɂȂ����҂ł���B�܂����R���h���g���������Ƃ����u�i���{�ɂ́j������Ӗ��Ől�ԂƂ��������Ȗ��ŌĂԂɓK�͂����l�X�i������j�v�Ƃ������͂��A�f���ȋC�����œǂ݂������̂ł���B�������A���R���h�ƍ��c���Õ��q���A���R���h�̌R�F�E�S���[�j����������邽�߂ɋꓬ���Ȃ���Ȃ�Ȃ���������́A�]�˖��{�Ƃ����u���v�������̂ł���B���R���h�͂͂����āA�u���{�ɐe���݂�����v�Ɂ��ȂǂƂ����L���������ł��낤���B���Ƃ������ɂ��Ă��A��������ʕs�����ɂ����Ȃ܂��̂ł͂Ȃ����낤���B
�@����Ɏ��͎v���̂ł������B���͂��܁u���{�l�v�Ƃ��u���V�A�l�v�Ƃ������Ă������A���̈Ӗ������܂�[���͍l�����Ɏg���Ă���̂ł���B��ʓI�ɂ͂���́A���ꂼ��̍��Еێ��҂̂��Ƃ��Ӗ����Ă͂��邾�낤�B���������Ђ͐l�X���O���[�v������B��̕��@�ł͂Ȃ��A�u�A���u�l�v��u�N���h�l�v�Ƃ������������Ȃ����̂ł������B�����炽�Ƃ��Ύ����T�n�����ʼn�b�����킵���l�X���u���V�A�l�v�ƌĂԂƂ��Ă��A���ꂪ��G�c�����邱�Ƃ͊m���Ȃ̂ł���B
�@���s����A���ēǂA��p���V�Ƃ����l�̑�w���Ƙ_���w�T�n�������N�l�������ɂ��āx�ɂ��A�T�n�����ɂ͑����̒��N�l�������A�ȉ��̂悤�ȗ��j���o�čݏZ���Ă���̂ł������B�����ł����u���N�l�v�Ƃ́A1910�N�̓��{���ɂ��؍������ɂ���āu���{�l�v�ɂ�����ꂽ�l�X���т��̎q���Ƃ����Ӗ��ł��낤�B
�@
�i�P�j1938�N4���@���{���u���Ƒ������@�v����B
�i�Q�j1939�N7���@�u���N�l�J���ҁv�̈ړ��J�n�B
�i�R�j1944�N9�� �u�������p�߁v�̒��N�ւ̓K�p�J�n�B
�i�S�j�呠�Ȃ̎����ɂ��A1939�N����1943�N6���܂ł́A��T�n
�@�@�����ւ̒��N�l�����l���́A1��6,113�l�i���̖�3����2���Y�z
�@�@�J���j�B
�i�T�j���{�~�����̓�T�n�����̐l����40���l���B���̓��A���N�l��
�@�@2��5,300�l����4��3,000�l�i���ɖk���N���痈���J���҂���
�@�@�邽�߁A���m�Ȑ��͕s���j�B
�i�U�j1946�N12���́u�ă\����v�ɂ��A�u���{�l�ߗ��v�Ɓu��ʓ�
�@�@�{�l�v�̈����g�����n�܂邪�i1949�N7���I���j�A���́u���{�l�v
�@�@���璩�N�l�͏��O�����i�u���N�l�̓��{���Бr���v���K�肳���@�@
�@�@�̂́u�T���t�����V�X�R���a�i�u�a�j���v��������1952�N�ł�
�@�@��ɂ�������炸�j�B
�@�@�q�������F������1947�N5���́u�O���l�o�^�߁v�́A�u���N�l
�@�@�@�́A�����̊Ԃ�����O���l�Ƃ݂Ȃ��v�ȂǂƂ��Ă���r
�i�V�j2000�N�A�؍��ɉi�Z�A���җp�A�p�[�g���������A900�l������
�@�@�i�u1945�N�ȑO���܂�v�u2�l1�g�ł̋A���A�����v�̏�������
�@�@�@��j�B
�@
�@�u���N�l���v�Ɛ��������Ă����A�C�X�N���[������̒��N�����A���ւ��p�̃u���]����������̐e�q�A���O���X�g�����œ����Ă����E�F�C�g���X�A�p�ꂪ���ӂ������{���̒��w���A�����Ŕ��ɉa�����Ȃ���A�u�A�C�S�[�v�u�A�C�S�[�v�Ɖ��x�����������Ă����V�w�l�����B�ނ�ޏ���̒��ɂ́A��������u�����v���ꂽ���N�l�J���҂̉Ƒ���q���������͂��Ȃ̂ł���B
�@���́A2010�N�V������W���ɂ����ė��s�����k�C���ƃT�n�����ɂ��āu���s�L�v���������Ǝv�����������̂́A������߂Ă����̂ł������B�����������͂����̊ό����s�҂ł���A�K�C�h�u�b�N�ɂ��łɏ����Ă��邱�Ƃ��\�肵�A������Ƃ��������⊴�z��t�������邱�Ƃ����ł��Ȃ��B����Ȃ��̂ɉ��l������Ƃ͎v���Ȃ��̂ł������B���̏�A�L�^�͂��납���L�������Ȃ��ӑĂ��������āA�����⊴�z��t��������ɂ��Ă��L���ɗ��邵���Ȃ��A�܂����̋L�������łɞB���Ȃ��̂ɂȂ��Ă���̂ł������B���ꂪ���܁A�������ĂȂ�Ƃ������n�߂Ă���̂͐�̐V���L�������������ł���A�ނ���E�C��^���Ă��ꂽ�̂ł���B
�@���͂���ȁu�Ă��Ɓ[�v�ȃA���P�[�g�������Ă����̂��낤���A�Ǝv�����B�����āA���������ɋߏ��̐H���ŏE���ǂ݂����Y�o�V���̑I���֘A�_���̂��Ƃ��v�������B�����ł́A�����咣����Ă����̂ł���B�܂�A����̏O�c�@�I���̑��_�́A�����ł�����łł��s�o�o�ł��Ȃ��A��t���ł���Ƃ����̂ł���B�������A�ɉE���ւ̓��[���Ăт����Ă���̂ł��낤�B�����V���͂��̂悤�Ȏ咣�͂��Ă��Ȃ������B���������̃A���P�[�g�́u�Ă��Ɓ[�v���́A���Ƃ������A�����̂Ȃ��ɂ���u�D��I�C���v�ɂ����˂邩�̂悤�ł���A�쌛�E���a���͂ɂ͕s���ɓ����Ă���ƒ������ꂽ�̂ł������B�����Ď��ۂɁA�u���h�R�v�u�����@�����v�u���@�����v�u�����@�\��ς���v�u�ƍفv�Ȃǂ����Ԑ��͂����������̂ł���B���́A�u�Ă��Ɓ[�v���u����I�C���v�̗��s�L�Ȃ珑����悤�ȋC�������B����u�e���݂�����v�ɑS����d�ۂ����A���R�͒P�Ɂu�s�������Ƃ����邩��i�k���N�͂Ȃ�����ǁj�v�Ƃ������\�ȐU�镑�����������̂ł���B
�@
�@�t�����珑�����F�l�ւ̎莆
�@
�@�X�i��i�g�c��Y�j�Ɂu�����Ȃ��v�Ɖ̂��āA�n���̐l�����𗧂Ă��ƕ������ݏ֖��ɂ͗��h�Ȏ{�݂������Ă��āA����ς�ł��ӂ��ꂽ�̂�����ǁA�����ƉI舂������̂́A���{��̗��s�̃v���i�����j�����łɂ��̒n��K��Ă������Ƃł����āA�����������̓꒣�肾�Ƃł��������̂悤�ɁA����̒Z�̂�\��t���Ă���̂ł������B���܂�ɂ����������̂Ŏv�킸���w���Ă��܂��A�L�^���Ƃ�Ȃ������̂�����܂��B
�@�Ƃ����̂͂��ܒt���ɂ��āA�ό��o�X�ŖK�ꂽ����̌����ŁA���s�̃v�����̃v���i���j���u��l�̉����v�ɑ��ĉr�Ƃ����̔����������Ȃ̂ł������i�u��l�̉����v�����̓\�A�ɂ�銒���N�U���ɁA�ʐM�Ɩ���S��������Ɏ��������Ƃ����j�B���킭�u�����ɖ������Ă�������߂̐S���v���ނ˂��܂肭��v�ł���A����ɂ��̔�ׂ̗ɂ͒��a50�Z���`�قǂ̒��F�����̂��ݒu����Ă���A�Ȃ�Ƃ���͂��̍�҂̗܂�\���Ă���Ƃ����̂��B
�@�x����A���ꂾ�˂��B�ό��o�X�Ƃ����̂͐b������@�ւ̈����ˁB���Ƃ�������A�����̓��A�[���z���́u�k���̓y�Ԋ҉^���v�̍Ő�[�ł�����̂�����ǁA�u1789�N�v�̂��Ƃ��ƃK�C�h���ꂽ�u�N�i�V���E���i�V�̐킢�v�ŁA�A�C�k���������Y���ꂽ�C�݂�ʂ��Č���������͋������_�ЁB�����Ă���́i�����̒��W�������j���c���Õ��q�ɂ���āu����3�N�v�Ɍ������ꂽ�Ɛ��������̂��B
�@�u����͐���ł����Ɖ��N�ł����v�Ǝ��₵���̂����A�����ɂ͓����Ă��炦�Ȃ������B�����́u1806�N�v�B�������ė��j�͂Ԃ�ɂ����i����Ƃ���A���̓����̃A�C�k�́u�܂����{�l�ł͂Ȃ��v����A����Ȃ̂��낤�j�B
�@��̒��F���{�[���̘b������Ⴂ�K�C�h���畷�����Ƃ��A�v�킸�ςȐ����o�Ă��܂�������A���̊ό��q����s�R�̖ڂŌ���ꂽ���������B�u��l���̂��т����v�̎v���o�̈�ɂ��Ƃ��܂��B
�@�������܂Łu�t���݂ȂƓ�ɍՂ�v�̂������ɂ����B�t���ɂȂ���ɂ��B�T�����̌��Ȃ���Ƃ������Ƃ��������A���e�͖Y�ꂽ�B��Â̔��Ց��x��������B�k���x���ɉ�Ô˂���������Ă����Ƃ̂��ƁB��20�`�[��1000�l�Q���́u�Ă���x��v�R���e�X�g�͌����������������A���R�݂ǂ�Ƃ���70���߂��Ă���͂��̉̎肪�A����1000�l�̂��߂Ɂw��ɗx��x�Ƃ������g�̉̂��A���Ԃ�8��A���ʼn̂����̂ɂ́A���������B�����āc�c�A��̃R���e�X�g�̌��ʔ��\���Ō�ɂ����āA�D���`�[���́A�q�q���ł������B
�@
�@�����ݏ֖��́u���̊فv�Ō����A���s�̃v���i�����j�̉̂́A���̂悤�Ȃ��̂������̂ł���B
�@�u���������ԊC���ɑς����������i�N�i�Ȃ��Ƃ��j�����Đl���Ăʁv�i���m2006�N�j
�@�����ċ{�����̉���ɂ��A�u���É��ɂ́A�ݏ֖��̗Ή����Ƃɂ��āA����5�N�̒����X�ѕ�����҂Ƃ̂��b�����_�@�ɁA���S���Ă���ꂽ���A����9���A�k�C���s�K�[�̋@��ɂ��̒n�����K��ɂȂ�A�Ή����Ə]���҂��炻�̘J����������ɂȂ��Ă�����v�Ƃ̂��Ƃł���B
�@�������ׂ��Ƃ���ɂ��A���̗Ή����ƂƂ����̂�1953�N������g�܂�Ă������̂ŁA���̓������łɋݏ֖��͍��������Ă����̂��Ƃ����B�����ېV�ȍ~�̓��A�҂ɂ��X�є��̂����̌����ł���A�������y���𐁂��r�炵�A�C�Y����S�ł����Ă����̂ł���B
�@�����Ă܂����́A�{����������ɂ���u�s�K�[�i���傤���������j�v�Ƃ�����������Ȃ����t�ɂ��Ă��A���炽�߂Ē��ׂĂ݂��̂ł������B���́A����́u�v���̂��闷�s�v�̂��Ƃ��ƒP���ɉ��߂��Ă����̂ł��������A�L�����ɂ��A�������́u�s�K�[�v���u�s�K�ƍs�[�v�ł���A�u�s�K�v���u�V�c���O�o���邱�Ɓv�A�u�s�[�v���u���c���@�E�c���@�E�c�@�E�c���q�E�c���q�܂Ȃǂ��O�o���邱�Ɓv�������ł���A�u�s�K�[�v�Ƃ����̂́u�v���̉Ƒ����s�v�̂��Ƃł���B
�@�̐l�E�䑺�O�́w�Z�̗̂F�l�x�ɂ��A�̐l�́A���W�������̐l�̒Z�̂́u�ǂ݁v�ɂ́A���銴�o�̌��@����������̂Ȃ̂��Ƃ����B�����Ă��̊��o�Ƃ́A�u�̂Ƃ������̂͊�{�I�ɂЂƂ̂��̂���������ς��Ă��邾���v�Ƃ������o�ł���A���́u�ЂƂ̂��́v�Ƃ́A�u���v�́u���̂��������̂Ȃ��v�ł���̂��Ƃ����B���́w�Z�̗̂F�l�x���y�����ǂ��A�Ƃ��ɂ��̕����́A�悭�������Ă��ꂽ�Ǝv���A������ۂɎc���Ă���̂ł������B���̏�ŁA��̉̂͂ǂ��ł��낤���B
�@�܂�����ؗF�́A�w���̉̂́A�u�����r���C���ɑς��鍕�����A���N�����Đl�X�͈�Ă��Ȃ��`�v�Ƃ������Ƃ��̂��Ă���x�̂��Ƌ������Ă��ꂽ�̂ł��������A�������ł���B�����u�����������Ɓv���̂��Ă���Ƃ����v���Ȃ��̂ł͂��������A���́u���������v�́A�䑺�O�������Ƃ���́u�ЂƂ́u�����v���r�����ƂɊւ��Ă͖��ӔC�ł�����v�Ƃ������ԂɑΉ����Ă�����̂ł��낤�B���������\�Ȏ��́A�ŏ��̊��z�ł���u���܂�ɂ��������v�ɁA�u�������v��t�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł���B
�@���������A�u�A���Ձv���Ƃ��u�C�̂Ȃ�v���Ƃ������āA�V�c���e�n�ɗ��s���A�V�c�Ǝ��R�ی�����т���C���[�W���삪�u�i�N�����āv�s���Ă��邪�i�V�c�̍������R�̍��Ɍ����͂���Ȃ��A�Ƃ����������h������̂ł���j�A���Ƃ��ΐA���ՂƂ����̂́A����̎����܂����čL��⓹�H�����A���̏�œV�c��1�{�̕c��A����Ƃ������ԂȂ̂ł���B
�@����ɂ��Ă��A�Ƃ�킯����ɏ��̂́u�l��v�Ƃ����P��ł͂Ȃ����낤���B�u���v�́u���������̂Ȃ��v�ǂ��납�A�l���͂ЂƂ̏W���Ƃ��Ĉ����Ă���̂ł���B�u���W�������v�̐l�ɂ킩��₷������������Ȃ�u�l��v���u���獑���v�ƂȂ�ł��낤�B���������͎v���̂ł���B�u�l��v�́A�{������������ɘA�˂��Ă���u�ɂ́v�u���b���v�u���S���Ă����v�u���K��v�u�������ɂȂ��Ă�����v�Ȃ�u�����J��v�ƁA�u���Ə]���ҁv�Ȃ�@���p��I�E�@�B�p��I�P��Ƃ̍��ʓI�Δ�ɂ́A�v�킸������Ƃ������Ă悢�͂��Ȃ̂ł���B�u���Ə]���҂̊F����v���炢��������ǂ����H�Ǝv���̂́A�������Ȃ̂ł��낤���B
�@�����Ď��͂܂��A���̂��Ƃ��w�E���Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł���B�܂肱�́u�l��v�́A���鉹�Ƃ҂�����ł���A����V�������A���X���I�A���邢�̓T�u���~�i�����ʓI�e�N�j�b�N����g����Ă��邩�̂悤�ł��邱�Ƃ��A�ł���B���邢�͂���́A�u�b�V���i���q�j���t�r�`�哝�̂��A�u�C���^�[�i�V���i���v�ƌ������Ƃ��āu�C���^�[�R���`�l���^���v�ƌ����Ⴆ�邽�тɁA���̐[�w�S���ɐ[�����t�����u�嗤�Ԓe���~�T�C���v��I�悵�Ă��܂��̂Ɠ����l����悵�Ă���̂ł��낤���B�����������肢���������ł��낤�B���ɂ́A�u�l��v�́u�q�g���[�v�ɕ�������̂ł���B���邢�̓u�b�V�����Ɠ����l����悵�Ă���̂́A���̕��ł��낤���B���邢�͂����������u���W�������v����̓ǂ݈Ⴂ�ł���A���̉̂���́A�Y�傩�s���Aꡂ��Ȃ�i���ł���厩�R�ƁA�R���L���Ȑ����������ɐ�����l�ԂƂ̑Δ��ʂ��ĕ\�������u���̂��������̂Ȃ��v�������Ƃ�Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł��낤���B
�@�t���������ɂ���u���a�V�c�s�K�[�L�O��i�J���S�N�L�O���T1968�N�j�v�ɍ��܂�Ă����A�v�����̃v���i���j�́u�����܂肭��v�Ɏ����ẮA�u�J���������ǂ���Ȃ��v�Ƃ����ׂ��ł��낤�B���̐l���́A�s�킪����I�ƂȂ��Ă���1945�N7�����_�Ɏ����Ă��A�u�ɐ��ƔM�c�̐_��������̎茳�ɒu���A�^�������ɂ���v�Ȃǂƌ����A���쌧����i�܂���j�Ɍ��ݒ��̒n����{�c�ւ̈ڏZ�����S����̂ł��������A���1947�N�ɓ������u���K�v�����ۂɂ́A�������������Ă���̂ł���B�u���̕ӂɐ펞�����ʂȌ����@�����Ƃ��낪����Ƃ������A�ǂ̂ւH�v�ł���A���������s���Ă������]���́u�É��͏����{�c�̂��Ƃ��I���ɂȂ��Ă��珉�߂Ă��m��ɂȂ����v�Ƃ����u�R�t���v�ł���B���͐�ɂ��A�N���o�b�g�ȉ��߁A�܂�u�l��v���u�q�g���[�v�Ɠǂ̂ł��邪�A���̂��Ƃ�\���Y���Ă��������̂ł���B��{�c�̈ړ]��ɒ��쌧���I�ꂽ���R�̂ЂƂ́A�u�M�B�͐_�B�ɒʂ���v�ł������̂ł���B
�@�܂����̐l����1946�N�A�}�b�J�[�T�[�Ɖ�k�����ۂɁA�����̂ĂȂ�Ȃ��\����f���Ă���̂ł������B���킭�u�i���{�����́j��]�ɐ����|������̂̓X�g���C�L�ł���܂��B�c�c���{�l�̋��{�����ɒႭ���@���S������Ȃ����݁A�č��ɍs����X�g���C�L�����āA������s���Ζ����`���ƂɂȂ�邩�Ǝv���悤�Ȏ҂����Ȃ��炸�i����j�v�ł���B�u�J���������ǂ���Ȃ��v�Ƃ�����g�\���̓K�p�K�ؗ�������ɋɂ܂��Ă���A�u�u���b�N�W���[�N�v��ꡂ��ɗ��킵�A����ɕC�G���钼�g�́A�V���w�R���́u�u���b�N�z�[���̂悤�ȁv���炢�ł��邾�낤�B�������g����ΐ_�ł��������́u���Ɛ_���v�Ƃ����@���͂ǂ��ւ������̂��H �u�����̂�����߁v�͂��̏@���̐M�ҁE�]���҂ł͂Ȃ��������B���̐l������ΐ_�ł���Ƃ���́u���́v����邽�߂ɁA�푈�͌p������đ���̎��҂��o�����̂ł͂Ȃ��������B
�@�����Z�̂�������̂ŁA��I�������Ǝv���̂ł���B
�u���_�����z�������q�g�琶�����тĐM�i�L�g�l�烒�o�t�v�Ȃ̂ł���B������́A�u�z���v�Ɂu�@��v�Ɓu�R�v�̗��`����^���Ă���̂ł���B�܂��u�������тāi���������J�^�J�i�Ȃ��j�v�́A��O�E���̐ؒf���_�u8��15���v���ے����Ă������Ȃ̂ł��邪�A����ɂ͒��߂��K�v�ł��낤�B�u�|�c�_���錾�v�����8��14���A�u�~�������v�����9��2���ł���A�u8��15���v�͑ΊO�I�ɂ͉��̈Ӗ����Ȃ��̂ł���B���̓��͂������A�V�c�����W�I�����������Đb���ɑ��u���̂܂ܐԎq�����ɐ₦��ƁA�c�c�c�@�ɂ��l�т��o���Ȃ��v����푈����߂�ƍ����A�u���ꂩ��������̌����ʂ�ɂ���i�Ȃb������悭�����ӂ�̂���j�v�Ɛ錾�������ł��邪�A�������͐������ł͂Ȃ��A���R�[�h�̍Đ��������čs��ꂽ�̂ł���A���̘^���͑O��14���ł���B�܂�8��16���ȍ~�̐V���ɂ́A�ʉ�������q�����ċ�������A���邢�͓y�������ĎӍ߂���u�l��v�̎ʐ^���������f�ڂ��ꂽ�̂ł��邪�A�����́u�����Z�v��u�n��v���������Ƃ��������Ă���̂ł���B���łɂ������肢���������ł��낤�B�����u�������тāv�̂��ƂɍĂѕ���ƃJ�^�J�i��p���Ă���̂́A�u�������сv���̂��l�������łȂ��A�u���́v�ł����邱�Ƃ��������Ă���̂ł���B
�@���́A�u�����v���u���v���l����n���ɂ��Ă���Ǝv���҂ł��邪�A�u���v�ɂ��Ă͋^��̗]�n���Ȃ��ł��낤�B���������āu�����v�ɂ��Ă�����A�؋�����Ă��������̂ł���B
�@�u�Z�\�N�i�ނ��Ƃ��j�����l�i���ɂтƁj�̂��ߐs���ꂵ�N�̏j�Ђɉ��W�ւ�v�i2006�N�^�C�������É����ʘZ�\�N�L�O���T�j
�@�q����18�N6���A���É��̓^�C�������É��䑦��60�N�L�O���T�ɁA�e���̍�������щ����̕��X�ȂǂƂ��ꏏ�ɂ�������ɂȂ�A�o���R�N�̎��T�ɂ��Q��ɂȂ����B(�{����)�r�@
�@���Ă���͂ǂ��ł��낤�B���͌��^�C�������u���l�̂��߂ɐs�͂��Ă������v�ǂ�����m��Ȃ��B�^�C�ɂ��Ēm���Ă��邱�ƂƂ����A�ȉ����炢�Ȃ��̂ł���B
�i�P�j1782�N�A�`���b�N���[���R�Ƃ����l���A�O���������Y���A�u��
�@�@�[�}1���v�Ƃ��đ��ʂ������Ɓi�������͂��̎q���̃��[�}9����
�@�@����j�B
�i�Q�j13���I�ɕ���������������A�����͑m���̒��_�����˂Ă��邱
�@�@�ƁB
�i�R�j200�ȏ゠��Ƃ��������̂����A�d�v�ȁu4���v������A���̒�
�@�@�́u�ω��v�́u�����ƉR�������Ɓv�ł���A���̉������^
�@�@�C�����E�́u�W���v�����\�����Ă���悤�ŋ����[�����ƁB
�i�S�j�^�C�Ƃ����A���{�R��1942�N����1943�N�ɂ����Č��݂����S
�@�@��415�L���ɋy�ԁu�זɓS���v�i�^�C�`�r���}�i���~�����}�[�j�j
�@�@�ł���A�A���R�ߗ�6���l�ȏ�i��1��2��l�����S�j�A�A�W�A�l
�@�@�J����7���l�`20���l�i��3��3��l�`9���l�����S�j����������
�@�@�����ƁB
�i�T�j�����[��6���ɂ͍��̂���������A�����~�܂��ĉ̂����Ƃ�����
�@�@���Ă��邱�Ɓi���ۂɌ�������ł���l���A���Ƒ�������j�B
�i�U�j�ԐF�̕��𒅂��l�����i�^�N�V���h�j�Ɖ��F�����𒅂��l����
�@�@�i�����h�j�̓����Ƃ�������Փ˂��A�ߔN�A�e���r����Ă���
�@�@�@���ƁB
�@�v���������Ƃ������_���ɏ����A�˂Ă��܂������A�����ł͂��̂悤�Ȏ����⊴�z�͕K�v���Ȃ��̂�������Ȃ��B���̍�i�ɂ͂�������̈Ӑ}�������Ă���A����͔�_���I�ȘA�z�ւƓǎ҂����̂�����Ȃ̂ł���B�����č�҂͂��ꂪ��������Ǝv���Ă���̂ł���B���Ȃ킿�A���̒Z�̂��Ӑ}�����_���I�W�J�Ƃ́A�u�^�C�̍����͍����v���v�{�u���͓V�c�v���u���������v���v�ł���B
�i�P�j���R�̂��Ƃł��邪�A���Ɂu�^�C�̍����������v���v�ł�������
�@�@���Ă��A����́u���������v���v�ł��邱�Ƃ��Ӗ����Ȃ��B
�i�Q�j�u���ׂĂ̍����͍����v���v���^�ŁA�u���͍����v���^�̂Ƃ�
�@�@�́A�u���͍����v���v�͐^�ł��邪�A���̑O��̐����͂��Ȃ�
�@�@����ł���B
�i�R�j�������A�����̍�����J�ߏ̂�����Łu�N����v�i���㊴�o
�@�@�ł́j���Ă���̂�����A��҂��u�̂��l�v�ɈႢ�Ȃ��ƁA�Ȃ��
�@�@�Ȃ��v���Ă���B
�i�S�j�����Ă܂����ɂ́A�����ō�҂́u�N����v���ߘ_���Ɍ�������
�@�@���Ă���̂��Ǝv���Ă���̂ł���B
�@�u�N����v�̉̎��̈Ӗ��A�܂�Ƃ���u�N�v�������w�����ɂ��ẮA1999�N�́u�������̖@�v���莞�ɂ��A���{���قɍ���������A�ŏI�I�ɂ́u�ے��V�c�v���w���Ƃ������Ƃɗ����������ƋL�����邪�A�u�N�v���u�F�l�v�ł���̂��u�N�v���u�N��v�ł���̂��ɂ��ẮA�_�����������̂ł���B�܂肱���ō�҂́A�u�N�v���u�F�l�v���u�����i�N��j�v�Ƃ��������������Ă���ƌ�����ł��낤�B���������āu�N����v�́u�F�l�̎��オ�i���ɑ����悤�Ɋ肤�́v�ł���Ɖ��߂��Ă������̂����A���́u�F�l�v�́u�����v���Ƃ������ƂȂ̂ł���B�A�W�A�̌N��A�Ђ��Ă͐��E�̌N���ڎw���Ă��Ȃ������A�u���̂��������̂Ȃ��v�������Ƃ���Ƃ����ׂ��ł��낤���B
�@���́A1�����قǂ̖k�C�����s�ɂ���āA��L��Ȃ����O�̒Z�̂��w�̂ł��������A���V�A�Ƃ̊W���v���Ƃ��A�܂��ʂ̒P�ꂪ�v���o�����̂ł������B����́A������L�����B���Ő\����Ȃ��̂ł��邪�A�t���̖k���L�O�قɂ͌f������Ă���A�[���z���̖k���قɂ��f������Ă����͂��́A���I�W�N�\�ɋL�ڂ���Ă����u�����v�Ƃ��������Ȃ̂ł���B����́A�O���Ȕ��s�w2009�N�ł���̖k���̓y�x�̒��ɂ����Ă��A�u�|�[�c�}�X���ɂ���āA�����̖k��50�x����̕��������V�A�������܂����v�Ƃ���̂�����A���ƓI�ɓ��ꂳ�ꂽ�����g�p�ł���ƌ�����ł��낤�B�܂�䂪���́A���I�푈��́u�슒����������v�̂ł��邪�A�����m�푈��ɂ́u�k���̓y�v���u��̂���v�A�����u�s�@�ɐ苒���ꑱ���Ă���v�̂ł���B���́A�����ނ荇���̂Ƃ�Ȃ��\�����ȂƎv���A���Ȃ�̔N�\������Ă݂��̂ł������B
�@
1855�N�@ ���I�ʍD��𑨁i�G�g���t�j���ƃE���b�v���̊Ԃɍ�
�@�@�@�@�@�����������i�T�n�����ɂ͍����݂����j�B
1869�N�@ �������{�A�ڈΒn���u�k�C���v�Ɩ����B�ːЍ쐬���A�C�k
�@�@�@�@�@���u���y�l�v�ƕ��ށB
1875�N�@ �瓇����������瓇����{�̂Ƃ��A�T�n��������
�@�@�@�@�@�V�A�̂Ƃ���B
�@�@�@�@�@���{���A�����A�C�k�̖�3����1�i841�l�j��Ί�i��
�@�@�@�@�@������E�D�y�ߍx�j�����ڏZ�����邪�i�c��3����2��
�@�@�@�@�@�c����I���j�A�����V�R���ȂǂŎ��S�B
�@�@�@�@�@���V�A�A�k�瓇�̏��Ȃ��Ƃ�84�l�̐�Z�������J���`��
�@�@�@�@�@�b�J�ɋ����ڏZ������B
�@�@�@�@�@���̌�A1884�N�A���{���́A�k�瓇�A�C�k�i���V�A�����A
�@�@�@�@�@�����k�������j��F�O�������ڏZ�B
1877�N�@ �n�����s��߁��A�C�k��L�n���u����n�v�Ƃ��č��L�n�ɁB
�@�@�@�@�@���̌�A���̒�����u�䗿�n�v���c�����Y�������i�S
�@�@�@�@�@����2�����̖ʐρj�B
1904�N2���A���I�푈�n�܂�B���{�R�A����i���\�E���j�𐧈��B
1905�N1���A���{���{�u�|���v�̕ғ����t�c����B
�@�@�y6��1���A���{�A�č��ɍu�a�������˗��B
�@�@�@6��9���A��A�u�a���J�n�������B
�@�@�@6��10���A���{�A����B
�@�@�@6��12���A���V�A�A����B
�@�@�@6��15���A���{�A������팈��B
�@�@�@6��17���A���{�A�o�����߂��o���B
�@�@�@7��7���A���{�R�A��T�n�����ɐN�U�B
�@�@�@7��24���A���{�R�A�k�T�n�����㗤�B
�@�@�@7��31���A���V�A�~���B
�@�@�@8��10���A�|�[�c�}�X�u�a��c�n�܂�B���{�̓�T�n��������
�@�@�@�@�@�@�@�v���ɑ��A���V�A�́u1875�N���v�𗝗R�ɒ�R�B
�@�@�@�@�@�@�@���������Y�S���́u�푈�̌��ʂ��v�Ǝ咣�B
�@�@�@9��5���A�|�[�c�}�X��슒���̓��{�ғ��B�z
�@�@�@11���@���{�A�؍���ی썑���B
1918�N�`22�N�@���{�A�V�x���A�ɏo���B��������������7��2��l
�@�@�@�@�i�\�A�E���V�A�ł́u�V�x���A�푈�v�ƌĂԁj�B���C�B�A�A��
�@�@�@�@�@�[���B�A�U�o�C�J���B�i�o�C�J���ΐ��݂̃C���N�[�c�N��
�@�@�@�@�@�ށj���́B���̌�p���`�U���̔����ɂ���ċ��B
1920�N�@ ���{�A�U�o�C�J������P�ނ��A�k�T�n�������́i1925�N��
�@�@�@�@�@�Łj�B
1925�N�@ �T�n�����ɂ�����1905�N�̗̓y���Ċm�聁���{�A�k�T�n��
�@�@�@�@�@���̐Ζ��E�ΒY�̗�����B
�@
�@1905�N�A�č��́u�u�a���J�n�����v�����V�A�����������ɁA���{�R���T�n�����ɐN�U���Ă��邱�ƂɁA�ڂ�������͂��Ȃ��ł��낤���B���̌��ʊl�������̓y���A���{��ł́u������v�ƕ\������̂ł���B���������̃T�n�����N�U�ɂ�����́A�w�V�x���A�o���x�i�����V�j�ɂ��A���̂悤�ł������Ƃ����B�u�k�����܂ޑS���œ��{�R���O��I�ɗ��D���ق����܂܂ɂ������ƁA���{������Ƒ��ƍ��Y����낤�Ƃ������߂ɎE���ꂽ�Z�����������ƁA�啔���̈ڏZ���Ɣ_�������ꕶ�ɂȂ��đΊ݃f�J�X�g���n��ɕ������ꂽ���Ƃ͋^�����Ƃ̂Ȃ������ł���v�B
�@�Ȃ��A�����Łu�ڏZ���v�Ƃ���̂́A�T�n������1881�N�ȍ~�A���V�A�̗��Y�n�ł���������ł���A1897�N�̋L�^�ɂ��A�����̐l���́A���l2��3,251�l�A���V�A�l���A��1��1,997�l�A��Z����4,151�l�Ƃ̂��Ƃł���B
�@
1945�N2���@ �����^�i�閧�j����i�ĉp�\�j���Q��̌��Ԃ�Ƃ��āA
�@�@�@�@�@�@�\�A�ɓ슒����Ԋ҂��A�瓇�������n���B
�@8��8���@�\�A�A��������j�������z���B
�@8��11���@�\�A�R�A�슒���ɐN�U�B
�@8��14���@���{�A�|�c�_���錾�̎��������A�ʍ��B
�@�@�@�u���{���̎匠�͖{�B�A�k�C���A��B�y�юl���Ȃ�тɉ�X�̌�
�@�@�@�@�肷�鏔�����Ɍ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�i�|�c�_���錾�j
�@8��16���@��{�c�A�y�u���q�퓬�������������v�z�߂��邪�A
�@�@�@�@�@�@�e�n�Ő퓬�����B
�@8��17���@�č��A�\�A�̐瓇��̂ɓ��ӁB
�@8��18���@���i�V�����V���j���̐퓬�i8��21���A���{�R�~���j�B
�@�@�@�@�@�@�y��5���ʌR�i�i�ߕ��E�D�y�A���n��͖k�C���E�����E
�@�@�@�@�@�@�@�瓇�j�A�u�퓬��~�E���q�퓬�Ɉڍs�v�̖��߂��o
�@�@�@�@�@�@�@���B�z
�@8��20���A�^���X�֓d�M�ǎ����i�u��l�̂�����߁v�������j�B
�@8��25���A�\�A�R�A�슒����́B
�@8��28���`9��1���@�𑨁E����E�F�O�����́B
�@9��2���A�~����������B
�@�@�@�@�@�@�A�����ō��i�ߊ��u��ʖ��ߑ�P���v�i���B�A�k��38�x
�@�@�@�@�@�@���Ȗk�̒��N�A�슒���E�瓇�����ɍ݂���{����C�w����
�@�@�@�@�@�@�Ȃ�тɈ�̗���A�C��A�q��y�⏕�����̓\���B�G�g
�@�@�@�@�@�@�ɓ��R�ō��i�ߊ��ɍ~�����ׂ��j
�@9��4���@�\�A�R�A�����Q�����́B
1950�N6���@���N�푈�n�܂�B
1951�N�@�T���t�����V�X�R���a�������i�\�A�A�����͒����j�B
�@�@�@�@�@���슒���E�瓇������B����͕č��̎{�������ɁB
�@�@�@�@�@���{���{�͍���Łu����E�𑨂́i���������j�瓇�Ɋ܂�
�@�@�@�@�@���v�Ɛ����B
1955�N�@���\�������J�n�B�\�A�A�u�F�O�E����2���Ԋҁv��
�@�@�@�@�@��镽�a�����������āB���{���{����������B
�@�@�@�@�@�_���X�č����������u����Ȃ牫���Ԋ҂��Ȃ��v�Ɯ����B
�@�@�@�@�@���{���{�A�u����E�𑨂͐瓇�Ɂy�܂܂�Ȃ��z�v�ɕω��B
1956�N�@���\�����錾�i�����j�B�u���a��������̎����Q���E
�@�@�@�@�@�F�O���Ԋҁv�L�B
1957�N�@�č��A�y�܂܂�Ȃ��z�ɑԓx��ς���B
1960�N�@���Ĉ��ۏ������B�\�A�A�ԓx���d���B�u�Ē����R�̓P�ށv
�@�@�@�@�@��2���Ԋ҂̏����ɉ�����B
1961�N�@���{�u4���ꊇ�Ԋҁv���u���a���v�����̏����ɁB
1964�N�@�O�������ʒB���u��瓇�v�̌ď̂��g���̂���߂āu�k��
�@�@�@�@�@�̓y�v�Ƃ����ď̂��g�����ƁB
1965�N�@�u�k���̓y�Ԋ҉^���v�����s�Ŏn�܂�B
�@
�@�u�����v�̍s���́A���{���\�A��������������ł͂Ȃ����낤���A�Ǝ��͎v�����̂ł������B����́u�u�a���J�n�����v�̎���ł���A�����́u�~���v�̎���ł���̂�����A�����̏d�݂̂���u����v�ł͂Ȃ��ɂ��Ă��A�ł���B�J��Ԃ��ɂȂ邪�A���I�푈���ɂ�������{���́u�u�a���J�n�����v�肪�u����v������ɁA�N�U���𗧂āA�������̂��Ă���̂ł���B�܂��A�Ђ�u�u�a�������v�i�b�������j�ɂ���Ċ��������肳�ꂽ���Ƃ������āu������v�ƕ\�����A�Ђ₢�܂��u���a���v����������Ă��Ȃ��i�b���������I����Ă��Ȃ��j���Ƃ������āu���܂��s�@�苒����Ă���v�ƕ\�����Ă�����̂Ǝv����̂ł��邪�A���a���̒����́A���Ȃ��Ƃ��o�����ɖڎw���Ă͂���̂ł���B
�@����ɂ��Ă��A1945�N8��16���̑�{�c�u���q�퓬�������������v���߂�A8��18���ɏo���ꂽ��5���ʌR�́u�퓬��~�E���q�퓬�Ɉڍs�v���߂Ƃ́A���ۂɉ�������Ƃ������߂ł���̂��낤���B���{�R�R�l�́A�ߗ��ɂȂ邱�Ƃ��ւ����Ă����̂�����A�����ɐ퓬���~������͂��������Ȃ������̂ł͂Ȃ����A�Ǝv����̂ł���B
�@1974�N�ɐ��삳��A���㎩�q���̐�Ԃ��o�����Ă���Ƃ��A�܂��\�A�̈��͂ɂ���f��������ꂽ�Ƃ�������A�^���X�ǎ�����`�����f��w�X��̖�x�ɂ����Ă��A�O�g�N�Y�����錻�n�R�Q�d���́A�S�������^��ɂ����āA�u����͂��������ǂ������Ӗ����I�v�Ƌ��Ԃ̂ł��������A���̖��߂��Ӗ�����Ƃ���́A�u�O����͐퓬���~���邱�Ƃɂ��邪�A�Ƃɂ����\�A�̓쉺��j�~���邽�߂ɁA�����̔��f�Ő퓬����v�Ƃ������Ƃł������̂��낤�B
�@���́A���I�W�N�\�����Ȃ���A�Ƃ��ɋC�ɂȂ����������y�@�z�ň͂����̂ł��������A���̍Ō��1�y�܂܂�Ȃ��z���A�u�k���̓y���v��m���ŏd�v�Ǝv����̂ł������B���̓_�Ɋւ���ꕶ���w����̖k���̓y�x���甲���o���A�u�ߋ��̗����ԂŒ������ꂽ�d�v�ȏ��ɏƂ炵�āA�k���̓y���T���t�����V�X�R���a���œ��{�����������瓇�Ɋ܂܂�Ȃ��͖̂����v�Ƃ������ƂɂȂ�̂ł���B�܂茾��������A�u�瓇�v�Ƃ́u�E���b�v���Ȗk�̓��X�v�̂��Ƃł���A�܂����́u��`�v�́A�u�ߋ��̏d�v�ȏ��v�A�܂�u1855�N���I�ʍD���v�Ɓu1875�N�瓇�����������v�ɏ�����Ă���Ƃ������ƂȂ̂ł���B�J��Ԃ��Đ�������A���̂悤�ɂȂ�ł��낤�B
�i�P�j1855�N�ɁA�𑨓��ƃE���b�v���̊Ԃɍ������������B
�i�Q�j1875�N�ɁA�����S���Ɓu�瓇�v�����������B
�i�R�j�u�瓇���N���������v�Ƃ́A�u�E���b�v������V�����V���i���j���܂ł̓��X�v�̂��Ƃł���B
�@�������A���́u��`�v�̔w�i�ɂ́A�w�k���̓y�����l����x�i�a�c�t���j�y�сw�k���̓y���x�i����j�������������Ă���悤�ɁA�l�X�Ȏ�����肷����̂ł������B
�@
�i�P�j�܂����ɁA���V�A���́A���㓇�Ƒ𑨓����u�N���������v�Ɂu�܂܂��v�ƈ�т��Ē�`���Ă���̂ł���i�������Ƃ͕ʂɁj�B
�i�@�j�w����̖k���̓y�x���g�����́y�����P�z�ɂ����āA�w�j�R���C1���̃v�`���[�`������P�߁i1853�N�j�x�i�������m����ɂ������Ă̎w�߁j���f�ڂ��Ă��邪�A�����ɂ́A�u�N���������̂����A���V�A�ɑ�����œ�[�̓E���b�v���ł���A�c�c�v�Ƃ���A�u�N���������̂����v�Ƃ������m�ȕ\�����Ȃ���Ă���B
�i�A�j�܂��y�������Q�z�ɂ���w�ʍD���x�̕����́A�u�G�g���v�S���͓��{�ɑ����A�E���b�v�S���v���k�̕��N���������͘I�����ɑ����v�ł���A���`����������悤�Ɍ�����B
�@�������A���̏��ɂ́A���V�A���A�I�����_���A���{���A����������A���V�A���i���V�A�쐬�j���I�����_���i���{�ɒj�������Ɠ��{���i���{���쐬�j�Ƃ����i�K��ō쐬���ꂽ�炵���A����̓I�����_���Ɗ����ł���Ƃ����B
�@�����Ă��̊����́A�u�U�z�S���y���k���v�����������I�����v�œ��{���Ɠ��`�A���������V�A���͂Ƃ����ƁA�u�C�g���t�S���͓��{�ɑ����A�܂��E���b�v�S���Ƃ��̑��̖k�̕��̃N���������̓��V�A�ɑ�����v�ł���A�I�����_��������Ɠ��`�������ł���B
�@�a�c�t�����ɂ��A�����ٓ��́A��쐬�ߒ��ɂ����āu���v�Ƃ��������������������߂ɐ������Ƃ̂��Ƃł���A�����ł���́A�y�����P�z�Ɠ����悤�Ɂu�N���������̂����̃E���b�v�Ƃ��̑��̖k���ɂ��铇�X�����V�A�̂ɂ���v�Ɠǂނ̂����R�Ǝv����̂ł���i�u���v�Ƃ������t���B��������������Ƃ͎v���Ȃ����̂́j�B����Ƃ��O���Ȃ́A����1853�N����55�N�܂ł�2�N�̊ԂɁA���V�A���u�N���������v�̒�`��ύX�����ƌ����̂��낤���B�@
�i�B�j����Ɂy�������R�z�́w�����瓇�������x���f�ڂ��Ă���A�u��`�v�����ɂ͎��̂悤�ɏ�����Ă���B
�@�u�u�N�����v�Q��������1�u�V�����V���v���c�c�c��18���u�E���b�v�v
�@�@�����v18���́c�c�v�B
�@����͂܂��Ɂu��`���̂��́v�ł���B���������́A���̏��̐����̓t�����X���݂̂ł���A�����Ɍf�ڂ���Ă���̂́A�u�Q�l���v�ɂ����Ȃ��Ƃ������ƂȂ̂ł���i�u�w���g�ޖ�x�Ƃ���a���Q�l�̈ו��f����v���{�O����W�����߁j�B
�@�ł͂��̃t�����X���͂Ƃ����ƁA����́A1946�N�ɊO���Ȏ��g���p�Ă���A�u�Q�l���v�́u�����v�ɓ����镔�����A�u�c�cthe said group of Kuriles shall belong to the Empire of Japan. This group comprises the eighteen ialands named below :�i1�jShumushu�c�c�v�Ə����Ă���̂ł���B���������̂��uKuriles�v�S���ł���Ȃ�A�uthe said�i���V�A�c�鏊�L���w���jgroup�v�ȂǂƏ����͂��͂Ȃ��A�u�N�����Q���̂��̃O���[�v�v���A�|�{���g�i���g�Ƃ��ă��V�A�ƌ��j�ɂ���āu�N�����Q���i�̑S���j�v�ւƁu�Ӗ�v���ꂽ�Ƃ����ׂ��ł��낤�B����́A�����Ɓu�k�瓇�v�����������̂ł͂Ȃ��A�����Ɓu�S�瓇�v�����������̂��Ɛ�`���邽�߂́A���������̕��͂Ȃ̂ł���B
�@
�i�Q�j�܂����{�����g���u�암�瓇�v�u��瓇�v�Ƃ����p���p���A���Ȃ��Ƃ����㓇�Ƒ𑨓��ɂ��Ắi�Ƃ��ɂ͐F�O�����j�A�u��瓇�v�܂�u�瓇�v�̈ꕔ�Ƒ����Ă����̂ł������B
�i�@�j1884�N�A����܂ł́u�������v�Ɋ܂߂Ă����F�O�����u�瓇���v�ɕғ��B
�i�A�j�w�瓇�T���x�i�k�C����1934�N�j�́u�암�瓇�ɑ�������̍��㓇�A�𑨓��A�F�O���̂R���c�c�v�Ə����Ă���B
�i�B�j1946�N11���A�u�a�Ɍ����ĕč��ɒ�o���������ɂ́A�u�i1875�N�̏��Łj���{�̓T�n�������ł̌��������S�ɕ������A����ɃN���������̖k�� the northern portion of the Kuriles ��������v�Ɩ��m�ɏ����Ă���i�O���Ȃ͂��̎��������݂Ɏ���܂Ō��J���Ă��Ȃ��Ƃ����j�B
�i�C�j1951�N�̃T���t�����V�X�R���a����y����ɂ�������ǒ�����ق́A�u���ɂ���瓇�͈̔͂ɂ��ẮA�k�瓇�Ɠ�瓇�̗��҂��܂ނƍl���Ă���܂��v�ł���B
�i�D�j��1951�N�u�a��c�ŁA�g�c�Α�\�i�j�́u���{�J�������A�瓇�암��2���A�𑨁A���オ���{�̂ł��邱�Ƃɂ��ẮA�鐭���V�A���Ȃ��ً̈c�����܂Ȃ������̂ł���܂��B�����E���b�v�Ȗk�̖k�瓇�����Ɗ����암�́c�c�v�Əq�ׂĂ���B
�@�܂��A�w����̖k���̓y�x�́A�T���t�����V�X�R���a���ɂ́u�瓇�v�̒�`���Ȃ���Ă��Ȃ��ƁA���ꎩ�̂͐�������������Ă��邪�A�g�c��\���܂ߒ������u���㓇�A�𑨓��A�c�c��瓇�v���u�瓇�v�ƔF�����Ă������Ƃ͊ԈႢ�Ȃ������ł���B
�i�E�j1952�N7���A�O�c�@�͕��a����ɔ����A�c��̓y���̉����𐭕{�ɗv�]���錈�c���̑��������A����A���}�������ƂƂ��ɂ�����ꂽ�̂́u�����v�Ɓu�F�O�v�݂̂ł���B
�@
�@�ȏ�i�P�j�Ɓi�Q�j���番���邱�Ƃ́A���{���{��1955�N�́u���\�������v�����Ɂu��`�v��ύX�����Ƃ������Ƃł���A1855�N���́u���{���v��1875�N���́u�Q�l���v���u�V��`�v�̍����ɂ��Ă���Ƃ������ƂȂ̂ł������i���ۂɃ\�A���炻�����_����Ă��Ă���j�B
�@�܂�����͉�����1992�N�A�O���Ȃ̓��V�A��p���t���b�g�w���{�̖k���̓y�x�����V�A���������ɔz�z���邪�A�����ł͎��̂悤�ɏ����Ă���̂��Ƃ����B�u�����̓��V�A�̎s�����X�^�[�����̂��̍s�ׁi4���̕����j�Ɍ����Ȕ��f���������Ɗ��҂��܂��v�u�S�̎�`�̐��̂��ƂŁA�c�c�����̎s���ɂ͂����̓����\�A�̓y�ł���Ƃ̌�����ӌ������܂�܂����v�ƁB
�@�����āA���㓇�Ƒ𑨓����u�N���������Ɋ܂܂�Ȃ��v���Ƃ��������߂ɁA1855�N���ɂ��āA���V�A�����̂��̂�I�����_������̖|����g���̂ł͂Ȃ��A�킴�킴�u���{���v�����V�A��ɖ��������̂��u��v�Ƃ��Čf�ڂ��Ă���Ƃ̂��ƂȂ̂ł���B
�@���́A����ȁu���܂����v���肵�Ă���悤�ł͘b�������͐i�܂Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���A�������܂��A���{���{���g�����́u��`�v�������I�ł͂Ȃ����Ƃ́A�\���Ɏ��o���Ă���Ƃ����@����̂ł������B�Ƃ����̂����{���{�́A�u�瓇�̒�`��e�ɒu�����Ƃ��Ă��v�Ƃ����Ӗ��������������邩�̂悤�ɁA�܂�A�����2��u���a�I�ɒ������ꂽ�v���Ƃ𗝗R�ɁA�u�S���͓��{�̌ŗL�̗̓y�v���Ǝ咣���Ă��邩��Ȃ̂ł���B
�@�������Ȃ���A����ɑ���\�A�E���V�A�̔��_�͎��̂悤�Ȃ��̂Ȃ̂ł������B�u1904�N�̃��V�A�U���A�|�[�c�}�X���ɂ�郍�V�A�̓y�D��ɂ��A���{��1855�N�A1875�N�̗����Ɍ��y���錠�����������v�B���I�푈���A���{�̐N���ł������̂��A���V�A�̐N���ł������̂��A���邢�͓��I�ɂ�钩�N�̒D�������ł������̂��A�Ƃ��������f����������e�ɒu���āA�����Ŏ咣����Ă��邱�Ƃ���ʉ�����A�u������H�̎���ɁA�푈�ɕ����Ă���A���a�Ȏ���̏��������o���̂͂��������v�Ƃ������Ƃł��낤�B
�@�����Ď��͎v���̂ł������B���{�̗L���҂͂����v���Ă���̂ł͂Ȃ����낤���ƁB�\�A���邢�̓��V�A�Ƃ������́A�Ȃ�Ɩ�ȍ��Ȃ̂ł��낤�A������u�e���݁v�����ĂȂ��̂��ƁB��������̔��_���A�\�A�E���V�A�̍D��I���i�����ɋA����Ƃ�����A����͌������Ɍ�����ԓx�ł���悤�Ɏv����̂ł���B�Ƃ����̂������Ŏ咣����Ă��邱�Ƃ́A1905�N�̃|�[�c�}�X�����ɂ����āA�u���a�I�ɒ������ꂽ�v1875�N���𗝗R�ɁA���V�A���슒���̊������������Ƃ����̂ɑ��āA���{���̎����o�����_���A�u�푈�̌��ʂ�����d���Ȃ��ł͂Ȃ����v�Ɠ����Ȃ̂ł���B
�@�����Ď��͂܂��A���̂悤�Ɏv�����̂ł������B���{���O���Ȃ͏������u�����v�łȂ����Ƃ��u�����v�ł���Ə����A�܂��u������v�u�s�@�苒�v�Ƃ����Δ�̍ۗ��\����p���邱�ƂŁA�����̓G���S���������A���ʁu�e���݁v�����Ă��A���ʁA�b���������i�܂��A�����Ă��̌��ʁu�s�@�苒�v�������A�Ƃ������X����������N�����Ă���̂ł͂Ȃ����낤���ƁB�����Ď��͂���ЂƂ̂��ƂɁA���̓��X����͋N�����Ă���̂ł͂Ȃ����낤���ƁB
�@��̃��V�A��p���t���b�g�z�z�ɑ���A���郍�V�A�V���ǎ҂̓��e�ɂ́A���̂悤�ɏ�����Ă����Ƃ����B�u���{�l���V�c�̂��Ƃ���X���悭�m���Ă���悤�ɁA��X�͓��{�l�����X�^�[�����̍߂��悭�m���Ă���v�ƁB���{�l�́A���́u�V�c�̂��Ɓv���A�悭�͒m��Ȃ��̂ł���B
�@
�@���W�m�T�n�����X�N�ƃz�����X�N
�@
�@5������10���ɂ����ďT��2�֏o�Ă���t�����R���T�R�t�i�T�n������[�̍`���j�A���t�F���[�́A�n�����w�����@�J�x�ɂ��A1�N������1���~�̐Ԏ����o�Ă���炵���A���̑�������Ԃ܂�Ă���Ƃ������Ƃł��������A���̓��̑D���́A���Ȃɂ͒������ɂ��Ă��A�ՎU�Ƃ��Ă���킯�ł͂Ȃ������B���w�Z�̎Љ�ȋ����Ƃ��ڂ����\�����̏W�c���A2���D���̈�p���߂Ă����B�𗬍s�����J�Â����炵�������B
�@���͑O���̃A���R�[�����c���Ă��āA�T���Ԕ��̑D�����قƂ�lj��ɂȂ邩�A�����ĉ߂������B���H�ɔz�z���ꂽ���̓��ٓ��͂Ȃ�Ƃ��H�ׂ��B�t���ň���ł����̂̓y�`�J�Ƃ������V�A�����̓X�ŁA�T�n�������痈�Ă������w���̃o���[�{�[���`�[���̑��ʉ�s���Ă����B���̓X�Łu�В��v�ƌĂ�Ă���l����Î҂Łi���ۂɖf�Չ�Ђ̎В��炵�������j�A��������t���E�T�n�����Ԃ̌𗬂ɑ傫�Ȗ������ʂ����Ă���悤�������B�u�В��v�̓t�F���[�̌�����ɂ����Ă��āA���ɂ����������Ă��ꂽ�B
�@�R���T�R�t�̓����R����ɂ͑�����2�����Ȃ��A�����s�����Ă����B�����ł����Ƃ��ɂ́A�[���̂U�����߂��Ă����悤�Ɏv���B�������̌サ�Ȃ���Ȃ�Ȃ������̂́A�Ŋ��̃o�X�◯����T�����Ƃ������B���̒◯�����烆�W�m�T�n�����X�N�s���̃o�X���o�Ă������ɏ��A���ꂪ�Ȃ���A�o�X�^�[�~�i���܂ł�������s���ď��p���̂ł���B�B�s�E���W�m�T�n�����X�N�܂�1���Ԃ�����Ƃ̂��Ƃ������B
�@�u�݂�ȃ]���]�������Ă����܂�����A�o�X��͂����킩��܂���v�ƁA���s�Ђ̒S���҂͌����Ă������A�����R�����I�����l�X�̓^�[�~�i���̏o�����������ɂ��ނ낵�Ă��邾���ŁA����ɕ����n�߂悤�Ƃ��Ȃ��B�}���̎Ԃ�҂炵�������B���V�A�͊ό����s�ɂ��r�U���K�v�ŁA�r�U�擾�̂��߂ɂ͏h����̏ؖ����K�v�������B���́A�z�e���Ɩ�s��Ԃ̗\��A�r�U�̎擾�����V�A���̗��s�ЂɈ˗����A���łɂ��낢��Ǝ��₵�Ă����̂������B
�@����炵�������ւƕ����čs���ƍL��ɏo�āA�o�X��ɂ��ǂ�����Ƃ��ł����B�����������\�炵�����̂͌������炸�A�ړ��Ẵo�X������̂����Ȃ��̂�������Ȃ��B�����ɂ������G�ݓX�̒���`������ł݂�ƁA����l�Ɩڂ��������B�u���݂܂���B���W�m�T�n�����X�N�ɍs�������v�ƌ����Ă݂��B��l�́u������Ƒ҂��Ă�v�Ƃ����悤�ȑf�U��������ĉ��ւƎp�������A�߂��ė���ƁA�u�o�X�^�[�~�i���֍s���v�Ƃ����Ӗ��̂��Ƃ������Ă��ꂽ�B�����\�͓X���ɂ͂���悤�������B�u�^�[�~�i���v�� ���V�A��Łu���@�O�U�[���v�Ƃ����B���́A�n�ʂ��w�����A�����āu���@�O�U�[���H�v�ƌ�����グ�Ȃ��琅�������Ɏw���������B�u�_�[�v�Ƃ��������Ԃ��Ă��āA�����ő҂Ă������Ƃ��킩�����B���͂��܁A�u���@�O�U�[���v�Ƃ����P����o���Ă������̂悤�ɏ����Ă��邪�A���́w���̎w������b���x�������o���Ă��āA�v���o���Ȃ��珑���Ă���̂ł���B
�@�H���o�X�͂����ɂ���Ă��āA���x�͏����ԏ��Ɂu���@�O�U�[���ɍs�������v�ƌ����āA�^�������B���́A���K�������Ă��邱�Ƃ̍K�^���v�����B���s��Ђ̎��Ј��́A��N�̉Ăɍs���ė������肾�ƌ����A�t�F���[�̒��ł����ւł���Ǝv�����A�`�ɗ��֏�������Ɛ������������A���ۂɂ́A�t�F���[�ł̂���͔p�~����Ă��āA�`�ɂ����֏��͂Ȃ��A���ǑO�̍L��ɋ�s�͂��������A�����s��̂��Ƃł͉c�Ǝ��Ԃ��߂��Ă��܂��̂ł���B���͓��{�ŗ��ւ���炩�͂��Ă������A���������R�ɏ��K�܂Ŏ�ɓ���Ă����̂������B
�@���炭����Ə����ԏ����ߊ���Ă��āA���������~���ׂ��ł��邱�Ƃ������Ă��ꂽ�B�u�X���F�[�h�c�c�v�Ƃ�������������ꂽ�悤�ȋC�������B��������ܒ��ׂ�Ɓu�X���F�[�h�D���V�B�[�v�Łu���v�Ƃ����Ӗ��ł���B
�@�A�t�^���@�O�U�[���́A�o�X�^�[�~�i���Ƃ����ɂ͂ƂĂ������Ȃ��̂ŁA�����Ă�����Ă��Ȃ���Βʂ�߂�������������Ȃ������B�₪�ĘH���o�X���͂��傫�߂́A��͂肩�Ȃ�N�㕨�̃o�X������Ă����B���̐��ʂɄ_�G�N�O �R�@�V�@�L�I�N�R�K�Ƃ����������f�����Ă���̂��m�F���A�\�l�قǂ̏�q�����Ə�荞�B
�@���́A���̂Ƃ��̂悤�ȁA�������o�X�ɏ���Ă��鎞�Ԃ��D����������Ȃ��A�Ǝv���B�ړI�n�Ɍ������Ċm���ɐi��ł���Ƃ������S���B�����͉��ł���ȏ��ɂ���낤�Ƃ����A�Ȃ�Ƃ͂Ȃ��̎��ȁB�����A�S�ׂ����䂦�ɁA�����Ƃ������݂͊m���ɂ���ȁ`�Ƃ������G�B����Ȋ��o�������荇���āA�ڂ���ƕ��i�߂Ă���B�ʐ^���B��̂���̐l��A慉r�o������l�Ȃ�Ⴄ�̂�������Ȃ����A�������i�ɂ��Ă͂قƂ�lj����v���o���Ȃ��B
�@���W�m�T�n�����X�N�w�O�ɓ����������ɂ́A������������������Ă��āA����ɉJ���~��o���Ă����B���́A�w�O�L�ꂩ��܂������ɐL�тĂ����ʂ������o�����B15����20�����炢�Ńz�e���E���[�_�ɒ�����͂��������B�t���́u�В��v����́u�Ȃ�ł܂����[�_�ȂɁB�z�e���E�T�b�|�����悩�����̂Ɂv�ƌ���ꂽ���A�r�U�̕K�v�����ɂȂ��Ă��邽�߂ɁA�T�n�����̏h����͊ό��q�ɂ͂��Ȃ荂�z�Ȃ̂ł���B�T�b�|���ƃ��[�_�ł�1��������5��~���̈Ⴂ������A���́A���̃z�e���Ɩ�s��Ԃ̗��p�ɂ��h����̐ߖ���v�������̂������B����ɁA�z�e���E�T�b�|���́u�������ى�Ђɂ������ς݁v�ł���A���[�_�̕��́u�\�A����ɂ͋��Y�}�̒��c�ł������v�Ə����Ă���̂�ǂ̂������B���������̊O�����s�A�u���{�̃r�V�l�X�z�e���Ƃقړ����ݔ��������Ă���v���́A�u�\�A����̖ʉe���c���Ă���v�����ʔ����͂��Ȃ̂ł���B���́A�z�e���E�T�b�|��������炵���������E��Ɍ��ă��[�j���ʂ��n��i���܂܂��K�C�h�u�b�N�����Ȃ��珑���Ă���j�A���̌�`�F�[�z�t�ʂ�����f���Ă����A���V�A���������Ƃ��ڂ��������̎�O�܂ōs���āA�傫�Ȍ����_�����ւƋȂ������B20���ȏ�͂��������Ǝv���B�X�H�͔��Â��A�����Ԃ͑����Ă������A�l�͂قƂ�Ǖ����Ă��Ȃ������B
�@�z�e���̃��r�[�ɂ����������낵�ĎP�������݁A���s�Ђ��������Ă����o�E�`���[�����o�����Ƃ��Ă���ƁA�t�����g����u�~�X�^�[�E�^�i�J�H�v�Ɛ���������ꂽ�B���̑��ɍ���`�F�b�N�C��������{�l������悤�������B���r�[���t�����g���G���x�[�^�[���������ꂽ����ŁA�Ƃ��ɃG���x�[�^�[�͋ߖ����I�Ƃ�������f�U�C�����������A�����ɓ����Ă��̗����ɋ������B�u�\�A����̖ʉe�v���c���Ă����B�V�����[�̂����͂������Ɏg���邱�Ƃ��m�F���Ĉ��g�����B
�@�[�H�͂܂��Ƃ��Ă��Ȃ������B�t�F���[���~��鎞�ɁA���u����Ă����ٓ��̗]����J�o���ɓ���Ă������Ƃ��A���̂Ƃ��ɂȂ��Ďv���o�����B�����Ă�����ʂ�̗l�q����݂āA���܂���H���ɍs���̂͑�d���ɂ������Ȃ��A�t�F���[��Ђ́u�C�����v�����肪�����v�����B�x�b�h�ɉ��ɂȂ�Ɖ����g�����݂���ł��܂����B�}�b�g���X���߂����Ă݂�ƁA�x�b�h�̏��ɂȂ�͂��̔��������͂���Ă���̂������B���͂����ݒu�����������A���������炸�A���ǂ���ɂ͂Ȃ�Ȃ������B�t�����g�ɓd�b���ĕ�����ւ��Ă��炤�]�͂͂����c���Ă��Ȃ������B
�@���̓����́A�܂��͉��������Ă��A���������Ȃ���ƌ��S���A�t�����g�܂ō~��čs�����̂ł���B���̃T�n��������́A��̏W���U���ɂ��炳��A�����̔s�k�ɏI����Ă����B���r�����Ȃ�܂������A��Ԏh����Ă͂����Ȃ����̗����h����A��Ȃ������B�����ڎ���������͑����̑�Ԃ�Ȃ��̂ł��������A�����̓V��͍������A�d���͈Â����A���Ă��邵�ŁA�ߎE���邱�Ƃ͂ł��Ȃ������̂ł���B�����āA�^�i�J����ɏo������B�c������́A�t�����g�W��̏���2�l��ɉ������Ƃ肵�Ă������A��b�̓X���[�Y�ɂ͂�����ł��Ȃ��悤�������B���ւ̂ł����s�̏ꏊ���Ă���炵�������B��s�́A������������Ă�����ʂ�E�R�~���j�X�g��ʂ艈���ɂ���Ƃ������Ƃ������B
�@���c�����H�ŗ����c������́A�T�n������`�ŗ��ւ��o�����u1���[�u���v�Ȃ��A�o�X�ɏ�邱�Ƃ��o�����A�Y�������ό��ē������烉�[�_�ɓd�b�����Ă��炢�A�}���𗊂��f���A���ǁA���̈ē����̌W���̎��Ɨp�ԂŁA20�h�����đ����Ă�������̂ł���B
�@���̓��͓c������ƃz�����X�N�i�^���j�ɍs�����ƂɂȂ����B�o�X��2���ԁA�O���̉J�œ��H�̏��X�������Ȑ�̂悤�ɂȂ��Ă����B�u��l�̉����v�����������X�ǂ�T���Ă݂����A���̌����������Ȃ̂��낤���A�Ƃ��������Ƃ����킩��Ȃ������B�^���_�АՂ̐Βi�́A����Ƃ킩��B�_�Ђ̖{�a�����������ɂ́A�ʑ��̂悤�ȁA���邢�͌������̂悤�Ȃ��̂������Ă����B���q�����H��Ղ͂�≓�����猩���낷���Ƃ��ł����B���\�A����ɂȂ��Ă�����A���炭�͉ғ����Ă����Ƃ����B
�@���2�l�ŗ[�H��H�ׁA�������B�K�C�h�u�b�N���Љ�Ă��郍�V�A�����X�B���{�̏��Ј��̏W�c�������B�c�������30��B���郁�[�J�[�̎����E���B�C�O���s�͂���2�A3�N���̎�ŁA����̓E���W�I�X�g�N�ɂ��s���Ƃ����B�u�T���L���[����ʂ��ĂȂ��悤�ȋC�������ł��v�u����قǂƂ́A�v���ւ����ȁ`�v�u���V�A��ł͂ǂ�������ł����v�u�X�p�V�[�o�v�B 2�l�ł���ƋC���傫���Ȃ�B�����Ԉ��݁A�����Ď��͉�������̂��Ƃ��A��������Y��Ă����̂ł������B
�@��̂��Ƃ��uKomar�R�}�[���i�����Ƃ��Ă̓J�}�[�����H�j�v�ƌ������Ƃ͂悭�o���Ă���B����́u���܁[��v�Ƃ��ċL������Ă���̂ł���B���̓����́A�H���i�X��G�ݓX�A�s���V�L�����������W�܂��Ă���V���R�s��܂ŁA���������T���ɍs�����̂ł������i��������R�ɔs�k�ł��������A�A���R�[���̂������U���͂���Ɏ��X�ł������j�B�����Ԃ������������̂́A����炵�����̂�X���Ɍ����邱�Ƃ��ł��Ȃ��������́A������p�i�X�ɑ_�����߂ė����~�܂����̂ł���B�����Ď蒠�̐V�����y�[�W�ɍ��{�[���y����KOMAR�Ə����A���̕����̏�ɐԂ��o�c����������̂��������̂ł������B�������Ď��́A���V�A���x�[�v�}�b�g�i�R���Z���g���j���w�������̂ł���B
�@�u�V�[�c���������Ă��������v���u�I�u���j���C�e �v���X�`�j�v�ƌ������Ƃ́A���̂Ƃ��g���Ă����蒠�ɏ�����Ă����B��̎��̓V�[�c�ł������B�Ђ������Ă��Ȃ��������Ƃ��v�������A����͂Ȃ�Ƃ������A���ȂтĂ������A��������������Ă��Ȃ��悤�Ɏv��ꂽ�B���͂�����t�����g�Ɍ�������ō앶�����̂��������A�������o�����ɏo������|���W�̘V�w�l�Ɍ����Ă݂��̂������B�����������Ƃ͂����ɒʂ����炵���A�V�w�l�͌�����̂悤�ȁA�J�茾�̂悤�Ȃ��Ƃ���������ׂ����B�����ɘb���Ă���悤�ȑf�U�肪�������������B���̓��A�V�[�c�͌�������Ă������A���܂肩���f���͂��Ȃ������B
�@���W�m�T�n�����X�N�i�L���j�ő�̌��w�ꏊ�́A���y�����قł���B����͓��{���������1937�N�Ɍ��Ă�ꂽ��s���̌������������قŁA�W�����e������Ȃ�ɏ[�����Ă����Ǝv���B��������ɒu����Ă����W�i�e�̖�͂����܂�Ă���j����{����̐����p�i���W������Ă����B�����Ă��̔����ّO�̌����ł́A��������̎ʐ^�B�e���s���Ă��āA�R�~���j�X�g��ʂ��ʂ邽�тɁA���g���̃J�b�v���߂邱�Ƃ��ł���B
�@�`�F�[�z�t�ʂ�A�`�F�[�z�t�L�O���w�فA�`�F�[�z�t�L�O����ƁA���̍�Ƃ̖���������{�݂������̂́A��Ƃ��A1890�N�ɃV�x���A�����f���Ă��̒n��K��Ă��邩�炾�낤�B�`�F�[�z�t�͂��̃T�n�����ŁA���Y������̕�����蒲�������Ă��邪�i���w�I����̂��߂̎������W�Ə̂��āj�A�w�`�F�[�z�t�S�W12�x�i�����ܕ��Ɂj�̉�����ɂ��A�����ƂƐڐG���Ȃ��悤�������Ď�����Ȃ�����A�u�ǂݏ����̂ł��闬�Y���v��u�C�܂܂ȕ������������Y���v���܂ށA7800���ȏ���́u�Ζʒ����J�[�h�v���c���Ă���Ƃ����B
�@�u���Ă̕ɂł͂Ȃ����v�Ƃ���鏬���ȊO�͉����c���Ă��Ȃ������_�АՂɂ��s���Ă݂��B�����̒����O�L��́A���݂́u�h���L��v�ƌĂ�Ă��āA�폟�L�O�肪���Ă��Ă���B ����ɂ��Ă��A�T�n�����ό��ɂ�����ۂ����������́A�e�n�̌����Ƃ��āu�_�АՁv���������Ă��邱�Ƃ��낤�B�K�C�h�u�b�N�w���[���h�K�C�h�E�T�n�����x�ł́A60�y�[�W�قǂ̒��ɁA6�J���̐_�Ђ��ʐ^����ŏЉ��Ă���̂ł���B����́A�ό����������ɖR�����Ƃ����ȏ�ɁA1905�N����1945�N�܂�40�N�ԁA���̒n�����{�̂ł��������Ƃ�z�N������[�I�Ȉ�Ղł��邩�炾�낤�B
�@�����������̐_�Ђ́A�ڏZ�҂̖��ԐM�ɂ���Č��Ă�ꂽ���̂ł́A�������Ȃ��̂ł���B�����_�Ђ́A���Ƃ��w���[���h�K�C�h�E�T�n�����x�������̒��u�E�O���S���X�N�i�b�{�悦���Ƃ�j�v�Ɍf�ڂ��Ă���u��3�����w�Z�ՂɎc�����a�v�i��^�e���V�c�̎ʐ^�Ƌ��璺���[�߂錚���j�ȂǂƓ����悤�ɁA����ɂ���Č��݂��ꂽ���̂Ȃ̂ł���B127�Ђ��������Ƃ����T�n�����̂���́A�܂�1910�N�Ɋ�����ЁE�����_�Ђ�����A���̌�1917�N�Ɍ��ЁE�b�{��_�ЁA1921�N�Ɍ��ЁE�L���_�ЂƂ�����ɁA����Β��_�̕��������Ă���A���̓_�͑��̓��{�̂Ɣ�r���āA�傫�ȓ����������Ă���悤�ł���B
�@���́A�K�C�h�u�b�N�w���[���h�K�C�h�x���A �b�{��_�АՂɂ��āu���D����������v�Ə����Ă���̂ɂ��A�܂��A�K�C�h�u�b�N�w�n���̕������x���A���Ă̊����_�Ђ̎ʐ^�Ɂu�݂肵���̊����_�Ёv�ƓY���Ă���̂ɂ��A�^���������������Ȃ��̂ł������B�����ʐ^�́A�L�^�Ƃ��ċM�d�Ȃ̂ł���i�f�l�Ӓ�ł͂��邪�A�����_�Ђ̒����́A�p�ъۑ�2���^�������_�Ќ^�ł���A�b�{��_�Ђ����^�ł���j�A����́u�݂肵�����Âԁv���߂̂��̂ł͂Ȃ��A�������{�������������Ɛ_�����ė����Ȃ��悤�ɂ��邽�߂̋��ނłȂ���Ȃ�Ȃ��̂ł���B
�@�u��l�̉����v�����́A����a��ʂ邽�тɂ����V���������A�V���߁i�V�c�a�����j�⑲�Ǝ��Ȃǂ̋V���ɂ����ẮA�Z���ɂ�鋳�璺��̕�ǂ��A�����s���œ��𐂂�A�@���������邱�Ƃ������ꂸ�ɕ�������A�u�N����v���̂킳��A�����Đ^���_�ЂɎQ�q�������A��ΐ_�̂��߂ɖ��𓊂��o���悤��Ă�ꂽ�̂ł͂Ȃ��������낤���B
�@�u���n�v�O�̓��{�̓y�ɂ������_�Ђ́A��ʂɂ́u�C�O�_�Ёv�ƌĂ�Ă��邻���ł��邪�A�ŏ��̊C�O�_�Ђ́A1901�N�Ɍ��݂��ꂽ������ЁE��p�_�Ђł���i���A�Ӊ�͂�����M�o�q���}���邽�߂̚��R��ѓX���O�����h�z�e���ɉ��z�j�B
�@�����Ă��̐_�Ђł́A�k����{�\�v�i�������炩��݂̂�悵�Ђ��j�Ƃ����c�����Ր_��1�ɂȂ��Ă��邪�A����͂��̐l�����A�����푈��́u���֏��v�i1895�N�j�ɂ���āu�������ꂽ�v��p�͒������邽�߂Ɏt�c���Ƃ��ďo���i�u������v�̂ɕ��͒������Ȃ���Ȃ�Ȃ������̂ł���j�A�}�����A�ɜ늳���A���S��������Ȃ̂ł������B1896�N�Ɍ��c���ꂽ�M���@�́u����������đ�p�ɐ_�Ђ����z�āv�̕��������A���̐l���́u��a���v�́A�u���₩�ɋ����𐪕����A�킪�c���̈Ж]�i���c�c�킪�V�Ő}�̗̗L�����łɂ��A�킪�b���̎m�C�����N�����v�Ƃ������ƂȂ̂ł���B�Ȃ����{�����t�ɂ��u��t�v�̗L�̊t�c�����1895�N�ł������B
�@�����Ă�����̑�p�_�Ђ́A�u�i��p�l�́j�c�����_�̓O���}��v���߂̒��S�{�݂Ƃ��Ă̖������ʂ����čs���̂ł������B�܂��p��Z�����猩��A���������𐪕����ɗ����R���̑�����_�Ɛ��߂�@���{�݂ւ̎Q�q���A���Ƃ��邽�тɋ��v����邱�ƂɂȂ����̂ł���i��p�ɍ��ꂽ�_�Ђ̂قƂ�ǂ��\�v���Ր_�Ƃ��Ă��邻���ł���j�B
�@���Ɛ_���ɂ�����_�Ђ̏���́A�u�ɐ���_�{�v�u�_�{�v�u��Ёv�u�{�v�u�_�Ёv�u�Ёv�ł���炵�����A�C�O�_�Ђ̑����́A�u��p�_�{�v�i��p�_�Ђ����̌㏸�i�j�ȉ��A700�ЂƂ�1500�ЂƂ������Ă���̂ł���i���Ɛ_�����p�������_�Ж{���́A�����̌��J�ɐϋɓI�łȂ������ł���j�B
�@
�@���͎v�����̂ł������B�k�C���ݏZ�̃A�C�k�����́A1869�N�Ɂu���y�l�v�Ƃ��ČːЂɕғ�����Ă���B�Ƃ������Ƃ́A�_�ЎQ�q�������Ă������Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��ł��낤�B�ł̓T�n�����̃A�C�k�i�����A�C�k�j�͂ǂ��������̂��낤���B�܂����̃T�n������Z���A�j�u�t��E�B���^�����͂ǂ��������̂ł��낤�B�����������́A�u���I2���ɂ��̗L�v���o�āA1875�N����̃��V�A�́A1905�N����̓��{�́A1945�N����̃\�A�̂ƕω����Ă�����T�n�����ɂ����āA��Z���������ǂ̂悤�ɕ�炵�Ă����̂��A�悭�������Ă��Ȃ������̂ł���B���͂��̕��͂������n�߂Ă���A�w�Ӌ����璭�߂�x�i�e�b�T�E���[���X�E�X�Y�L�j�Ƃ������������邱�Ƃ�m��A���̖�������A1905�N�ȍ~�̐�Z�����������̂悤�Ɉ����Ă������Ƃ�m�����̂ł������B
�i�P�j1875�N���ɑΊ�ɈڏZ������ꂽ�A�C�k�̓��̐����҂́A�슒��
�@�@�ɖ߂�i�ق�30�N�Ԃ�Ƃ������ƂɂȂ邾�낤�j�A���{�̌ːЂ�
�@�@�ĕғ������B
�i�Q�j1875�N�ȍ~���T�n�����Ɏc���Ă����A�C�k�i1500�l�ȏゾ�낤
�@�@���j�y�уj�u�t�ƃE�B���^�i���킹��500�l�ȏ�j�́A���̂܂ܕ�
�@�@�u�����i���_��̓��V�A���Ђ̂܂܁j�B
�i�R�j1912�N�ȍ~�A�����A�C�k�����́A9�̑��i43���������������j
�@�@�ւƋ����ڏZ�������A�_�Ə]�����u�M�S�ɐ����v�����B
�@�@�w�Z��3�́u�y�l�w�Z�v�ɕ�������Ă����A����K��̑��́u��
�@�@���I�Z���v�̈琬�ł���B
�i�S�j1925�N�A���V�A�́u���V�A���Еێ���]�ޓ�T�n�������Z�҂͓o
�@�@�^����v�Ƃ̖@�߂��o�����A���m�͂���Ȃ������Ǝv����i�u�V
�@�@�x���A�o���v���W���Ă���̂ł͂Ȃ����낤���j�B
�i�T�j1927�N�ȍ~�A�j�u�t�ƃE�B���^�����́A�I�^�X�Ƃ���1�̑�
�@�@�ֈڏZ�������A��͂�_�Ə]�����u�M�S�ɐ����v�����B1930
�@�@�N�ɃI�^�X�Ɋw�Z�������A�u�_���ɂ��ƂÂ��_�b�⍑�j�v�̋�
�@�@��ɏd�_���������B
�i�U�j1930�N��ȍ~�A�������̒ʂ�X�ђn�тɍa�Ƌn������A
�@�@�ߗ����́A�e�މ��ҁA�Ƃ��ɉƑ��̐������������������B
�i�V�j1932�N�A�A�C�k�͂��ׂČːЂɕғ������i�u���B���ρv�ȍ~��
�@�@�����S���g�ɊW���Ă���Ƃ̂��Ƃł���j�B�܂��A�j�u�t�ƃE�B
�@�@���^�́u�y�l����v�ɓo�^�����i�����͖��L����Ă��Ȃ�����
�@�@���A�����炭�́A���̍��ł͂Ȃ����낤���j�B
�@�܂�A1945�N�܂ł́u���{�l�v�ɂ��Ă܂Ƃ߂�A����͎��̂悤�ȃO���[�v����\������Ă����̂ł���B�i�P�j���n�b���A�i�Q�j�u�O�n�ːЁv�������N�E��p�̐A���n�b���A�i�R�j�u���y�l�v�i�A�C�k�j�A�i�S�j�u�y�l�v�i�A�C�k�ȊO�̐�Z���B�ːЂ��������A���{�̌Y�@�E���@�ɕی삳��Ȃ��j�B
�@�����Ď��͂܂��A�܂����Ă����s�̃v���i���j�ɐ�z����Ă��邱�Ƃ��A���̏����ɂ���Ēm�����̂ł������B�܂��c���q�ł�����1925�N�ɁA�u���v�̓T�n������K��Ă����̂ł���A�����ł̔ނ́u�`���I�ȃA�C�k���y�̉��t�v��u�E�B���^�ɂ��g�i�J�C�����̔�I�v�ɂ���Č}�����A�A�C�X�N���[����H�ׁA�r�[����t���b�v�E�\�[�_�����݁A�g�i�J�C��A�U���V�̓����H�ׂ��̂��Ƃ����B
�@�j�u�t�A�E�B���^�������_�ЎQ�q�������Ă����m�͓����Ȃ��������A�A�C�k�ɂ��ẮA���Ȃ��Ƃ�1932�N�ȍ~�́A�S������������Ă����Ǝv����̂ł������B�܂��A�j�u�t�ƃE�B���^�ɑ���1930�N�ȑO�̋���ɂ��Ă��m�肦�Ȃ��������A�v����1925�N�ɗ��s�ł��邮�炢�ł���̂�����A�u�_�b�v�̐Z���͐}���Ă����̂ł��낤�B
�@�����Ă�����Z�������́A1945�N�̓��{�s��ɂ���āA�ӂ����ю��̂悤�ȏɂ��炳��邱�ƂɂȂ����̂��Ƃ����B�A�C�k�����i�ːЏ����j�́u�����g���v�D�ɏ��A���̂قƂ�ǂ��k�C���ɈڏZ�B�j�u�t�A�E�B���^�́u�ːЕs�����v�̂��߁i������u�鍑�b���v�Ƃ݂Ȃ��悤���炳��Ă������j�A�u�����g���v�ł����A�Ⴂ�j���̑唼�́u�����v�𗝗R�ɁA�������e���֑���ꂽ�Ƃ����B������1950�N��ɂȂ�A�����̐����҂Ƃ��̉Ƒ��ɓ��{�ւ̈ڏZ���F�߂�ꂽ���A���̗��R�́A���鍑�b���Ƃ��āu�L�`�̓��{�l�v�ł���u���{����������{�l�v�Ɠ����ːЂւ̓o�^���F�߂���A�Ƃ������Ƃł������B
�@
�@����ɂ��Ă��A�u���{�l�v�u�O�n�ːГ��{�l�v�u���y�l�v�u�y�l�v�u�L�`�̓��{�l�v�u���{����������{�l�v�ł���B���������u���{�l�v�͉�����C���ςނ̂ł��낤���A�Ǝv���͎̂������ł��낤���B�����āu���y�l�v�Ɓu�y�l�v�ɑ���u�_�Ə]���ւ̔M�S�Ȑ����v�ł���B
�@���́A�i�n�ɑ��Y�́w�̉Ԃ̉��x���v���Ԃ����ɂ͂����Ȃ��̂ł������B���̒��ҏ����́A���R�ɃA�C�k�Ɋւ���L�q�𐔑����܂�ł���A��Ƃ́A���ɂ�����ϓ_����т��Ď����Ă�������Ȃ̂ł���B
�i�P�j�w�Î��L�x��w���{���I�x�ɏo�Ă���ڈ̒��ɃA�C�k�̑c�ł�
�@�@��l�������������A�ڈ͐l��_�I�T�O�ƌ���ׂ��ł͂Ȃ��A����
�@�@�������i�߂�퐶���̈��_�k�ɂȂ��܂��A �`���I�ȕ�炵���ł�
�@�@��̏W��������ȂɈێ����Ă���l�X�ƌ���ׂ��ł���B
�i�Q�j�Â�����̖k�C���́A�킴�킴�_�k�����Ƃ��̏W�����ŐH�ׂĂ�
�@�@���铇�ł���������A�_�Ƃ͔��B�����A���x�̋��@�����B���Ȃ���
�@�@���B
�i�R�j�_�Ƃ����B���Ȃ���A���������͔��B���ɂ����B
�i�S�j�]�ˊ��A���O�˂̃A�C�k���͐��܂������̂ł������i���ۂɎ�
�@�@�������Ă����̂́u�ꏊ�v�𐿂������Ă������l�����ł���j�B
�i�T�j1799�N����̈ꎞ���A���{���������čs�����A�ڈΒn�o�c��A�C
�@�@�k�̐������P�͐ϋɓI�ɕ]���ł���i���̓_�ō��c���Õ��q���ɂ�
�@�@�đ傫�Ȗ������ʂ������j�B
�@���́A��l���E���c���Õ��q�̐������܂ɑł���ĂƂ��Ɋ��܂��A�܂���Ҏ��g�́u�̓y�_�ɂ�鍑�ƊԂ̕����قNj��Ȃ��̂͂Ȃ��v�Ƃ���������A�u�v����Ƀ��V�A�Ɠ��{�́A渂ƃ��b�R�A�j�V����ǂ����߁A���ʁA�y�n���̂��̂�̓y�ɂ����v�Ƃ����w�E�������Ȃ���A���̏�����ǂ̂ł������B�����Ă��܂������_�ɂ��ẮA�������ȂЂ���������������A�قڎ��R�Ȃ��̂Ƃ��Ď���Ă����̂ł���B���������́A�w�Ӌ����璭�߂�x�ɂ���āu�A�C�k�̔_�Ɓv�ɂ��ċ������A�����āu���{�l�������ς��v�ɂȂ������R�̈�[��������ꂽ�̂ł������B����2�͐[���֘A���Ă����̂ł���B
�@���������A�u�A�C�k�Љ�̔_�Ƃ͖��J�Ȃ܂܂ł������v�Ƃ����L�����z���Ă���Ƃ��ڂ����F���ɂ́A�����̎������������Ă���悤�Ȃ̂ł���B�A�C�k�͎��ۂɂ́A�����R�V�A�L�r�A���A����k�삵�Ă���A���̔_�ƌ`�Ԃ́A18���I�㔼�܂ł̓��{�̗l�X�Ȓn���ōs���Ă������̂ƁA�قƂ�Ǖς��Ȃ������Ƃ����i1780�N�̍ŏ㓿���ɂ��A�a�l���A�҂������A�C�k�Ɠ����Ă����_�Ƃ��s���Ă������A����͂��Ƃ����n���Ɠ������̂ł������j�B�܂�A�C�k�����́A����̕�炷�C������ɓK�����_�Ƃ��c��ł����̂ł���B�ł͂Ȃ��A�u�A�C�k�Љ�ɂ͂قƂ�ǔ_�Ƃ��Ȃ������v�悤�Ɍ�����̂��B���́A����́u�Ȃ������v�̂ł͂Ȃ��A�u�Ȃ��Ȃ������D��ꂽ�v�̂ł������B
�@�]�ˎ��㒆���̑�\�I�ȏ��i�앨�ł���ؖȂ̐��Y����́A�엿�̗��p�ɂ��Ƃ��낪�傫���A����́u����v�Ƃ�����ꂽ�����j�V���ł������i�u�j�V���v���A�u�G�g���t�v�u�N�i�V���v�u�V�R�^���v�u�n�o�}�C�v�Ɠ������A�C�k��ł���j�B�a�l���l�́A���͂������ăA�C�k��z��I�J���i���Ɖ��H�j�ɋ�肽�āA����Y�����̂ł���i���̓_�͎i�n�ɑ��Y���������Ă���j�B
�@�W�H���̕S���o�g�ł��������c���Õ��q�́A���̗D�ꂽ�l�i�ƍˊo�ɂ���Ĉꗬ�̉��D�Ǝ҂ƂȂ����̂ł��邪�A���̌㖋�{�Ɍ���āA���ʂ̋��_�Ƃ��Ă̔��ق��J���A�܂��𑨓��ɑ����̋�����J���A�A�C�k�������ق��Čo�c�i�����ɂ��A�z��I�J���ł͂Ȃ��u�����J���҂Ƃ��āv�j�A��ʂɎ��n���鋙�@�������A�����̌���ɂ��s�͂����Ƃ����i�_�Ƃ��������Ə�����Ă����j�B
�@�������A���c���Õ��q�̌o�c�������ɗ��h�Ȃ��̂ł������ɂ���A���{�ƃA�C�k�̊W���l�����ł́A�u�_�Ƃ����Ȃ������v�̂ł͂Ȃ��A�j�V���H��̘J���҂ɂ�����ꂽ�����߂Ɂi���{�̒����o�c�͂�����������Ȃ��������낤���j�A�_�Ƃ��o���Ȃ��Ȃ����Ƃ����F���́i���n���Ɠ����x�Łu���x�v�ł͂Ȃ������ɂ���j�A���d�v�Ǝv����̂ł������B�u�A�C�k�Љ����̏W�Љ�Ƃ��čč\�z�����̂́A���{�̋ߑ㔭�W�ߒ��ɂق��Ȃ�ȁv�������̂ł���B
�@�e�b�T�E���[���X�E�X�Y�L�ɂ��A�]�ˊ��̐������̕����ɃA�C�k�̔_�Ƃɂ��Ă̌��y������Ƃ����B���́A�u�A�C�k�Љ�ɂ͔_�Ƃ��قƂ�ǂȂ������v�Ɓw�̉Ԃ̉��x��ǂޑO����v������ł����̂ł���B�����āA�֘A�����אs�����A�ŏ㓿����ԋ{�ё��̋Ɛт͂��Ƃ��A���̐l�ƂȂ�܂ł������ɕ`���i�n�ɑ��Y�����A�A�C�k�ɂ��ẮA�u�e���Ȕ_�k�ƌÑ�I�ȍ̏W�����v�u�O�ꂵ���̏W�����ҁv�Ƃ��������t������Ԃ��Ă���̂ł������B
�@���������͂��́A�u�i�̏W�����ŐH�ׂĂ���������j�`���I�ȕ�炵���ێ����Ă����v�Ƃ����ꌩ�����I�Ȍ����́A����܂��i�n���������Ă��������̊ϓ_�A�܂�u�ڈ�l��_�I�Ɍ���ׂ��ł͂Ȃ��v�Ɛ[���ւ���Ă����̂ł���B
�@�v���Ύ��́A�i�n���́u�l��v�Ƃ������t�Â����ɁA�Ђ���������o���Ă͂����̂ł������B�����Đ�́i�P�j�Ɉ��p�����u�l��_�v�Ƃ����p��ɂ́A���{�̊w�҂����̍s���Ă��������ɑ���ᔻ���܂܂�Ă���̂�������Ȃ��A�ƍl���������̂ł���B�܂茤���҂����́A�A�C�k�́u�l��I�����v�����邱�ƂɌ������グ�A��������Đl�������W���A�e��v���̕W�{�Ƃ��Č������ɕ��u���Ă�������Ȃ̂ł���i���߂č������Ȃ��ꂽ�̂�1980�N�ł���A�w�̉Ԃ̉��x�̎��M�����Əd�Ȃ��Ă���j�B
�@����������͂Ƃ������A��́i�P�j�̕��������������ڂ����܂Ƃ߂�Ǝ��̂悤�ɂȂ�̂ł������B
�i�P�j�w�Î��L�x�w���{���I�x�ɏo�Ă���ڈ́u���c�_�k�����Ȃ�
�@�@�l�X�v�Ƃ����Ӗ��ł���B
�@�q�`�����c�k��ҁ����݂̓��{�l�̎嗬�A�a���c�k��ҁr
�i�Q�j�����������܂łɁA���{�͒Ìy�܂ł����c�k��Љ�ɂȂ���
�@�@���A���̊ԁA�������s���A�ڈ����݂̓��{�l�̑c��̈�h�ɂ�
�@�@�����B���{�l���A���N�����ɔ�ׂđ��тȐl�������̂͂����ʂ�
�@�@�v����i�u���c�k�삪���N��������炳�ꂽ�v�ƍl�����邱��
�@�@����A��Ƃ͒��N�����Ɣ�r���Ă���̂ł���j�B
�i�R�j����ł����c�k��Љ�ɓ��邱�Ƃ��D�܂Ȃ������l�X���ڈΒn��
�@�@�n�����Ƒz���ł���B
�@�q�a���a�P�i���c�k��ҁj�Ƃa�Q�i�c�k��ҁj�ɕʂ�A�w���`��
�@�@�a�P����т��́u�����v�����݂̓��{�l�A�a�Q���A�C�k�̑c�ł�
�@�@��r
�@�i�n���́i�Q�j�ɂ����āu���тȐl�������v�Ə����Ă���̂ł���A�`�Ƃa�ɂȂɂ�����́u�l��I���ق�����v���Ǝ��͔̂ے肵�Ă��Ȃ��̂ł���B�����Ă܂��ʂ̂Ƃ���ł́A�Õ��q�̖ڂ�ʂ��Ăł͂��邪�A�u�ڈΐl�̊�̓����v���u���ڂ��|�A�Z�����A�D�F�ɋ߂������畆�v�Ə����Ă���̂ł������B
�@���������͎��̂悤�Ɏv���̂ł���B
�i�P�j���Ƃ��ΏW���`�ƏW���a�ɂ�����u�̖і��x�v���z�ׂ邱�Ƃ��\�ł������Ƃ��Ă��A����͐��K���z�ɂȂ�ł��낤���A����2�̎R�^�Ȑ��́A�قƂ�Lj�v����̂ł͂Ȃ����낤���B
�i�Q�j�܂��A2�̎R�^�Ȑ��ɂ��ꂪ�������Ƃ��Ă��A�u�̖і��x���p�[�Z���g�ȉ��͂`�ł���A�ȏ�͂a�ł���v�Ƃ����悤�ȁu��v��ݒ肷�邱�Ƃ͍���ł͂Ȃ����낤���i�R�^�Ȑ����d�Ȃ��Ă������A�̂̔�r�ɂ����Ắu���тł���`�̐l�v�Ɓu���тłȂ��a�̐l�v�Ƃ����t�]���N����̂ł���j�B
�i�R�j���������āA��萳�m�ȁu�����v����낤�Ƃ���ƁA�u���|�̐[���v��u���̐F�v�Ȃǂ��K�v�ƂȂ�̂ł���A�܂�Õ��q�̂���́A�u�̖т������v���u���|���[���v���u�����D�F�ɋ߂����v�i�o���p���q�j���A�a�̓����Ƃ������ƂȂ̂ł���B
�i�S�j�������Ȃ���A���̂悤�ȁu�����v�́A���������s�����Ȃ��̂ł͂Ȃ����낤���B�Ȃ��Ȃ炻��́A�u�o����p�v�i�̖т͑��������|�͐j��u�p����q�v�ȂǁA�u�o���p���q�v�łȂ����̂��ׂĂ��A�Ȃ����`�̕��Ɋ܂߂Ă��܂��Ă��邩��ł���B
�i�T�j�W���w�ƏW���a�Q�ɂ��Č����A�i�S�j�̑ԓx�͎��R�Ɍ����邩������Ȃ��i�w�͂a�P���܂݁u�L���v�̂�����j�B�������i�P�j����i�R�j�ɂ�����u�葱���v�́A�܂��܂������Ȃ��̂ɂȂ��Ă��܂����낤�i�u�o���p���q�v�ł���w�̐l�͂a�P�ɕ��ނ����̂ł��낤���j�B
�@���́A�k�C���E���V�ɂ���u�A�C�k���������فv�Ō����������x�̌�����ɁA���̂悤�ȏ�ʂɏo���킵���̂ł������B����ό��q�����������̐E���ɑ��Ă����b�������Ă����̂ł���B�u���o�����Ă����l�����̑����̓A�C�k�ł͂Ȃ��̂ł͂Ȃ����v�ƁB���̐l�́A�o���҂����̑������u�o���p���q�v�łȂ��������Ƃ��s���������̂ł���B
�@�܂����͂���Ƃ��A�ߏ��̌����قōs���Ă����s���u���w�y�����p��b�x�ɎQ�����Ă݂��̂ł��������A�����ł͎��̂悤�Ȗⓚ�����̂ł������i�u�t�Ǝ�u�҂����́A���n�č��l�`����̂���Ƀz�[���X�e�C���Ă����Ƃ������Ƃł������j�B
�@�u�t�u�`����̊�́A���{�l�̊�Ƃǂ��ƂȂ��Ⴄ�悤�Ɋ����܂���ł������H�v�B��u�������u���������A���{�l�ɂ��������܂���ł����v�B
�@�����v���ɂ��̎��₪�Ӑ}���Ă����̂́A���{��Ɖp��ł͂��̔����ɂ����Č��O���ӂ̋ؓ��̎g�������Ⴄ�Ƃ����w�E�ł���i�u������p��̔����͓���̂ł���v�Ɛ������邽�߁j�A�Ȃ�قǁA�p����肵��ׂ��Ă����玄�̊�����ς���Ă����̂��낤���ƁA��ۂɎc�����̂ł͂������i�����Ă��v���ɂ��̎���́A�u���{�l�̊�v�Ƃ������́u���{�����ł悭���������̕\��v�Ƃ̔�r�����߂Ă����̂ł��낤�j�B
�@����������͂Ƃ��������́A�u���{�l�̊�v�Ƃ����̂͂��������ǂ�Ȋ�̂��Ƃ������̂ł��낤���A�Ǝv�����̂ł���B�u�T�^�I���{�l��v�ȂǑ��݂���̂ł��낤���ƁB����Ƃ����̍\���v�f�́A�u�ڂ��ׂ��v�u�@�͂���قǍ����͂Ȃ����Ⴍ���Ȃ��A���������A�������Ƀ��V�^�v�u��O�������O�̕���������v�u���V�ɂȂ�Ɣ������ڗ��v���X�Ȃ̂ł��낤���B
�@�����Ď��͂܂��A��u�������̉�����̈Ӑ}�����ݎ���Ă��Ȃ����肩�A���M�����Ղ�ł��������ƂɖʐH������̂ł������i�ނ��뎩�M���Ӑ}���������悤�ł������j�B���̎��M�͂��������ǂ����痈��̂ł��낤���ƁB���������v���ɂ���́A�u�`����̊�͕č��l�̊�ɂ͌����Ȃ��v�Ƃ������Ƃł͂Ȃ��������Ǝv����̂ł���B���̏ꍇ�A��u�������͎��O�Ɂu���n�v�ƕ����Ă����̂ł���������A�����́u2��1�v�̂悤�ł���A�u���{�l�Ɍ�����v�Ɓu�č��l�ɂ͌����Ȃ��v�͘_���I�ɓ��l�̂悤�Ɍ����āA���������́u������v�ł��邩��ɂ́A�����́u�������Ɓv�ł͂Ȃ������̂ł���B�܂�A�č��l�̊������Â��鉽�����܂��͑O��Ă��āA�`����̊�ɂ͂��ꂪ��������Ȃ������Ƃ������ƂȂ̂ł���A������́u�����v���A���M�̂��Ƃł������̂ł���i���邢�͂�����������ł��낤�B�u�č��l�v�͍��ЊT�O�ł���A�`����ɕč��l��̓�����T���Ă�������Ȃ������͓̂��R�������̂ł���j�B�@
�@�܂�͂����������Ƃł͂Ȃ����낤���B�������́A�������́u�l��I�����v�ɂ��ẮA������ɂ��Ȃ��ɂ�������炸�i���{�l��̓����Ȃnj����Ȃ��̂ł���j�A���҂́u�����v�ɂ��Ă͂��ꂱ�ꌾ���Ă͂���Ȃ��̂ł���B
�@�����Ă܂����́A���郉�e���A�����J�l�̂��Ƃ��v���o���̂ł������B�ނ́u�����l�ɐe���݂������Ă��Ȃ��v�炵���A�ނɂ��Β����l�̖ڂ́u��オ���Ă���v���炷���ɂ킩��Ƃ̂��Ƃł������̂ł���B�Ƃ��낪������A����u�ڂ���オ���Ă���l�v�Ƙb�����ۂɑ��肪�u�����l�łȂ��v�ƒm���A����ȍ~�A���̐l�̖ڂ́u��オ���Ă���v�悤�ɂ͌����Ȃ��Ȃ����̂ł���c�c�B
�@�i�n�ɑ��Y���́A�u�ڈ͐l��_�I�T�O�ƌ���ׂ��ł͂Ȃ��v�Ə����A�܂��u���c�_�k�����Ȃ��A�Ƃ������Ƃɂ����Ȃ��v�Ə������i�܂��u�e�Ղɒf�肵�������v�ȂǐT�d�Ȍ�����p���Ȃ�����j�A�u���сv���̑��̓����������Ă���̂ł������B���́A�i�n���̌����u����ׂ��łȂ��v�̈Ӗ�������Ƃ킩�����C������̂ł���B�܂肱���ł̎i�n���́A�u�A�C�k�͎������Ƃ͈Ⴄ�v�ƍl���Ă���ǎ҂�z�肵�A�u�l��I���ق͂��邪�l��_�I�Ɍ���ׂ��łȂ��v���u�������Ɠ����ƌ���ׂ����v�Ƌ������Ă���̂ł���i�a�̂����̂a�P�́u�������v���\�����Ă���̂ł��邩��A�a�Q�������u����ׂ��v�Ȃ̂ł���j�B
�@�������A���́u�������Ɠ����v�ɂ́A���ۂɂ́A���̂悤�ȏ����W���ł͕\�����Ƃ̂ł��Ȃ����G�Ȗ�肪�܂܂�Ă����̂ł���A����͎��Ȃ�ɐ�������Ύ��̂悤�ɂȂ�̂ł���B
�i�P�j���V�A�Ƃ̑R��A�A�C�k�͓��{�l�łȂ���Ȃ�Ȃ��i1855
�@�@�N���̌��ɂ����Ă��u�����A�C�k�̏Z�ޏ��͓��{�́v�Ǝ咣
�@�@������j�B
�@�@�q���̏ꍇ�̓��{�l�����{���̍\�����i���Еێ��҂̂悤�Ȃ�
�@�@�@�́j�r
�i�Q�j�������A�A�C�k�͌���E���K����݂Ęa�l�Ɠ����ł͂Ȃ��B
�@�@�q�a�l���A�C�k�Ƃ͕ʂ̖�������a���������{����������{�l�r
�i�R�j�������A���{�́u���������Ƃł͂Ȃ������{�l�����̍��v�ł���
�@�@����A�A�C�k�͓������Ȃ���Ȃ�Ȃ����A�o����͂����B
�@�@�q���̏ꍇ�̓��{�l���_�b�I���{�l�̂悤�Ȃ��́r
�i�S�j�������A�ق�Ƃ��ɓ����͉\�Ȃ̂��H�@�A�C�k�Ɓu�������v
�@�@�́A�ǂ��Ⴄ�̂��H
�@�@�q���������a�l�Ɛ_�b�I���{�l���ӑR��̂ƂȂ��������B�܂�
�@�@�u�������v��a�l�Ƃ���A�A�C�k�́u�������łȂ��v���A�u��
�@�@�����v���u�_�b�I���{�l�v�Ƃ���A�A�C�k���u�������ł���v�r
�@�����Ă��̕��G�Ȗ��ɓ����邽�߂ɓ������ꂽ�̂��A���́A���Ԏ��ł������̂ł���B�����Ԃɂ�����������Ԃʼn������悤�Ƃ����̂ł������B�܂�A�A�C�k�́u�������ł���v�Ɠ����Ɂu�������łȂ��v�̂ł͂Ȃ��A����́u�u�ߋ��̎������v�Ƃ��čĒ�`�v�i�e�b�T�E���[���X�E�X�Y�L�j����邱�ƂɂȂ����̂ł������i�u���ق͂��邪�����ƌ���ׂ��v�Ƃ����v���̕��������A�a��a�P��a�Q�Ƃ������W���T�O��������̂ł͂Ȃ��������낤���j�B
�@�u�ڈΒn�Ƃ�����c�ɂɂ������߂ɒx��Ă���̂��v�ƁA���c���Õ��q�̃A�C�k�ς��i�n���͏����Ă���̂ł������B�����āA�Õ��q�́u�����̐l�ԂƂ��ăA�C�k�����邱�Ƃ��ł����v�����߂ɁA�u�Ί펞��̓��{�l�v�Ƃ����u�l���Ǝ����l���v�������Ƃ��ł����A�Ƃ����Ӗ��̂��Ƃ������Ă���̂ł������B�������A���̃A�C�k�ς��������Ă������̂́A������܂��i�n�����g�������Ă���悤�ɁA�u�A�C�k�Ƃ͐l��I�ɂǂ������ЂƂтƂł��邩�Ƃ������Ƃ��c�_����v�������ȍ~�̂��ƂȂ̂ł���i�����č�Ƃ́A�Ȃ�����ȋc�_���K�v�ɂȂ����̂��ɂ��ẮA�q�ׂĂ͂��Ȃ��̂ł���j�B
�@�u�A�C�k�Љ�ɂ͔_�Ƃ��Ȃ������v�̂ł͂Ȃ��A����́u�Ȃ��Ȃ������D��ꂽ�v�̂ł������i�]�ˊ��j�B�����āu���{�l�v���߂����₪�u�`���I�ȕ�炵�����ێ����Ă���l�X���ߋ��̎������v�Ƃ����u����v�������炵�i�����ȍ~�j�A���́u����v�ɂ���āA�u���{�l�������ς��v�ɂȂ邱�Ƃ��ł����̂ł���B�@�@
�@���͂܂��A���̂��Ƃ��������Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł���B���́A�u�A�C�k�ɂ͒b��̋Z�p���Ȃ��A�S��Y���Ă��Ȃ������B�����͌��Ղɂ���Ă����炳�ꂽ�v�ƐM���Ă����̂ł���i�������̏����ɏ�����Ă����Ǝv���j�B���́A����s�����قł����ے肷�鎑���A�܂�������H�i���o�y���Ă���Ƃ����W����ڂɂ����Ƃ��ɂ��A�u�܂��ʓI�ɏ��Ȃ��A������܂łɂ͎����Ă��Ȃ��v�Ƃ����ӂ��Ɋ������̂ł������B�ӂ����сw�Ӌ����璭�߂�x�ɂ��A �ԋ{�ё��́A�A�C�k�̒b��Z�p�ɂ��ċL�^���Ă���Ƃ����B �A�C�k�̋������H�i�́A���{���i�̈ړ��ƂƂ��Ɏ���ɏ��ł��Ă������̂ł������B
�@�i�n�ɑ��Y���̒���̑����s�����́A�y��1�����Ă���Ƃ����B�ǂ݂₷�����́A����ɂ킽����j���ۂ̉���Ƃ��̊Ȍ��ȗv��A���������Ƃ����l�����`�A�u�c�c�Ƃ������Ƃ͂��łɏq�ׂ��v�Ƃ����`�œK�X���肩�������u���K�v�B�u��l�̋��ȏ��v�Ƃ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ����̉e���͂��v���Ƃ��A�Ǐ��ɋ��߂���T�d�����v�킴������Ȃ��̂ł������B�����Ď��́A���̂悤�Ɍ��������Փ��ɋ���A�Փ��ɕ����Č����Ă��܂��̂ł���B���͂�͂�u�l�灁����b���v�������̂ł���c�c�B
�@���V�A���x�[�v�}�b�g�͂悭�����A�V�[�c�͌�������A�S�g���߂ɌX���Ă��܂��x�b�h���C�ɂȂ�Ȃ��Ȃ�A���͂��邱�Ƃ��Ȃ��Ȃ����̂ł������B��͂���{����̌��z���ł���B�����p�فi���k�C����B��s�j�͋x�فB�`�F�[�z�t�L�O����́A�������������������J�Â���Ă��Ȃ��悤�ł������B���́A���Ȃ�傫�Ȍ����ł���K�K�[�����L�O���������i���L�������j���Ԃ���A�q�ǂ��S���ɏ��A�i���������ĂɃr�[���ƃE�H�b�J�����݁A�ʂ̎��R�s��ŏ㒅���A�y�Y�����Łu�N�����g�̓��V�A�̉�Ɓv���x���ꂻ���ɂȂ�A�J�W�m�ɓ��낤�Ƃ��Ďv���Ƃǂ܂�A�{����`���ĉ߂������̂ł������B
�@
�@�m�O���L
�@
�@���͎P���Ȃ������̂ł���B���}�n���Y�l�b�g�V���b�v�ōw�������܂肽���ݎ����s�p�P���A�������~�肽�^�N�V�[�̒��ɂ����Y�ꂽ�̂ł������B���́A�T�n�����k���ɂ���m�O���L�Ƃ������̃z�e���Ƀ`�F�b�N�C����������ł��������A���̎��������������Ƃ́A�C���X�^���g�R�[�q�[�����Ƃł���i�K���Ȃ��Ƃɓ��������|�b�g�������ɂ������j�A���̌サ�Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ́A���̒��̗B��̌����ł���k�����������ق܂ōs���Ă݂邱�ƂȂ̂ł������B���������̉J�͎~�݂����ɂȂ��A�P�͂ǂ����Ă��K�v�Ȃ̂ł���B
�@���W�m�T�n�����X�N����k�ւƌ������Q���Ԃɏ�邱��16���ԁA�I���w�ɂ��ƌ������J���~�肵�����Ă����B��q�����́A����ɖk�ւƌ������o�X�ɏ�荞��ōs�����l�����������āA���\�l���w�ɂɂ��ނ낵�Ă������A�Ƃ��������ė���Ƒ����d�����Ԃ炵���l�̎ԂɃ|�c�|�c�Ə�荞��ł��������ŁA���̐l�����́A��͂�N���̌}�����A���̒��S���ւƘA������H���o�X��҂��Ă���͂��ł������B
�@�u�͂��ł������v�Ƃ����̂́A �������̘H���o�X��҂��Ă͂���̂ł��������A�����\�炵�����̂���͂茩�����炸�A�܂��A�܂�8�����Ƃ����̂ɁA�Ђ���Ƒł����Ă���J�ɋC�����܂ŎՂ��Ă���悤�Ȉz�ŁA�u���܂ł̃o�X�͂�����̂��v�ƒN���ɕ������߂̍앶������C�ɂ��Ȃꂸ�A�^�o�R������z���Ă��邩��Łi���̂��тɉw�ɂ��o�ĎP���������j�A������������H���o�X�Ƃ������̂͑��݂��Ȃ����i�w�n���̕������x�ɂ́u1���Ԃ�1?2�{�v�Ə����Ă������j�A���̎����ɂ͉^�s���Ȃ����ł����āA���̕��Â��ȏ�q�����́A���̒��S�܂œk��40�����x�ƁA��͂�w�n���̕������x�ɏ����Ă��������̂������n�߂邽�߂ɁA�J���~�ނ̂�҂��Ă���̂�������Ȃ������B
�@�����Ď��͉��{�ڂ��̃^�o�R�ɉ��������ɖڌ������̂ł���B����Ƃ͂�����킩��^�N�V�[���w�ɋ߂��ɓ�������₢�Ȃ�A�V�v�w�Ƃ��ڂ���2�l�������ɋ삯����荞���Ǝv���ƁA�u���Ԃɂ���͓D�����͂ˏグ�Ȃ��瑖�苎���čs�����̂ł������B
�@������������͌��S�����̂ł���B���邩���Ȃ���������ʘH���o�X��҂̂͂�߂āA���ɗ����^�N�V�[�ɏ��̂ł���B��������u�C�Y�r�j�[�`�F�i���݂܂���j�Ɓu�X�p�V�[�o�v�̊ԂɌ����ׂ��̐S�̕��͂��앶���Ȃ��Ă��ނ̂ł���B
�@����ɂ��Ă��A���̘V�v�w�̔N��Ɍ�����ʂ�������������݂�ɁA�����͕����̂��̂ł͂Ȃ��悤�ł������B�܂��^�N�V�[���A�w�ɂ̑O�܂ł͗����A25���[�g���͗��ꂽ�Ƃ���ɒ�Ԃ����̂́A�܂�ł��̐�w�������y����ł��邩�̂悤�ł���B�܂����͂������A����炵���Ԃ��������H���炱����ւƋȂ����ė��鎞�ɂ��A�����ƂƂ����ɑ̂��������A�X�^�[�g�̒x������߂��ׂ��P��������ő���o�����Ƃ������̂́A�����������ɂ͒��y�ʒ����^���p�i�͈����ɂ������̂ŁA�u�|�`�v�̉������݂Ɏ�Ԃǂ��Ă��邤���ɁA���͂�މ�̍��͖��炩�Ȃ̂ł������B
�@���������͗L���ȃX�^�[�g���C���Ă����̂ł���B�Ƃ����̂��A�����^�o�R���z���Ă���ꏊ�͉w�ɂ̊O����������ł���A�d���ȃK���X���h�A�ɎՂ�ꂽ�n����������ɁA�^�N�V�[���ł���\���͍����A�܂��S�[���܂ł̋������Z�������̂ł���B
�@�����Ď��ۂɁA���ɗ����^�N�V�[�ɏ�荞�ނ��Ƃ��ł����̂��A���R�Ƃ����Γ��R�̐���s���������̂ł���B���͌㕔���Ȃɍ������낷�Ȃ�A�u�h�u���E�W�F�[�j�i����ɂ���j�A�m�O���L�E�A�e�[���A�p�W�����X�^�i�m�O���L�E�z�e���A���肢�j�v�ƌ����A�u�Ӂ`�v�Ƌ��̂Ȃ��ő����p�����̂ł��������A����o���Ă܂��Ȃ��A�������͉���������������Ă����^�]�肪���x�͂͂�����Ƃ�����������āA�u×××�c�c�v�ƕ����Ă�����̂�����A����ɑ����́A���ӂ́u�l�E�p�j�}�[���E�p���[�X�L�[�i���V�A��͕�����܂���j�v���J��o�����̂ł���B
�@����ƁA�^�]��͖����@�����o���ĉ����m�F���A�₨��t�^�[�����n�߂�̂ł������B�����ĉw�܂Ŗ߂����^�N�V�[�ɋ삯����Ă����̂́A2�l�A��̒��N�w�l�������̂ł���A�ޏ���͑傫�Ȑ����������ĉ^�]��ƌ��t�����킵�Ȃ����荞��ŗ����̂ł���B���͂��̎��ɂȂ��Ă���Ɨ��������̂ł������B��ɘV�v�w����荞��ōs�����^�N�V�[���A����������Ă��邱�̃^�N�V�[���A�d�b��������ʂ��ČĂяo���ꂽ���̂������̂ł���B
�@���̌�^�N�V�[�͉������Ȃ����̒��S���ւƌ������A����ꏊ��1�l�̕w�l���~�낵�A�܂��ʂ̏ꏊ�ł���1�l�̕w�l���~�낵�A�����čŌ�Ƀz�e���E�m�O���L�ɓ��������̂ł������B���́u�X�p�V�[�o�B�X�p�V�[�o�B�{���V���C�i�傫���j�A�X�p�V�[�o�v�ƌJ��Ԃ��A���芨�ƂȂ������߂Ɍ��ʓI�Ɋi���ƂȂ����������x�������̂ł������B�����āA�P��Y�ꂽ�̂ł���B
�@���V�A�ł͂��ꂪ��ʓI�Ȃ̂ł��낤���A���邢�̓T�n�����̓����Ȃ̂ł��낤���A�Ƃɂ����T�n�����ł́A���X�g������{�����̑��̓X�܂̃h�A����~���[����ł��邱�Ƃ������A�X���̗l�q���`���Ȃ��悤�ɂȂ��Ă���̂ł���B���̏�A�X�܂̏ꍇ�ɂ́A���i�͔���̔w��̒I�ɒ�Ă���̂��ʏ�̌`�Ԃł����āA����͂���������Ɏ�Ɏ�邱�Ƃ��ł��Ȃ��V�X�e���A�܂茾�t�̏o���Ȃ��O���l���s�҂ɂ́A���X����ǂ��V�X�e���Ȃ̂ł������B
�@�����o�}�����̂́A���̐��ʂɂ��炦��ꂽ�J�E���^�[�̌������ɕ��сA�G�k�𒆒f����Ă�����Ɉ�ĂɐU�������ꂽ3�l�̏����̊፷���ł������B�u�h�u���E�W�F�[�j�B���[�A���[�A���[�A�]�[���`�N�i�P�j�v�ƌ����Ȃ��王�����j�����ɁA�P�͂���ɂ͂������̂ł��������A����͐܂肽���ݎ��ł͂Ȃ��A�܂����Ȃ�傫�����̂ŁA�����u�܂肽���ݎ����~�����v�Ƃ����ꕶ���́u�܂肽���ݎ��v�Ƃ����A�o�Ă���͂��̂Ȃ����V�A��P��ɓ������点�Ă��邤���ɁA�����炩�猩�č��[�̓X���`�͂������Ɏ��A�傫���J���Č�����̂ł������B�����悤�₭�u�}�[�����L�[�i�������j�A�}�[�����L�[�i�������j�v�ƌ����Ȃ���p���g�}�C�����Ă݂���ƁA�u���[���v�Ƃ��������ł��Ȃ������`�́A���܊J�����P�������ލ�Ƃ�^�̓X���a�ɔC���Ă��炱����ɔw�������ċ��ݍ��݁A�܂肽���ݎP�����o���āA�ĂъJ���Č�����̂ł������B�����u�_�[�C�`�F�E�G�[�^�i����E����j�v�ƌ����Ƃ`�͍Ăт�����a�Ɏ�n���A�����ɐ�̎P������Č��̒�ꏊ�ɖ߂��A�����Đ܂肽���ݎP�������a�́A�E�[�̓X���b�Ɏ�n���̂ł������B�b�̓��W�W�Ȃ̂ł���A�m�F�������z��ł����d������Ɍ����A�P���a�ɕԂ��B���̌�A���͂b�Ɏ�����n���A�b�̓��W�ɑł����݂��s���A���͂a����P��������̂ł������B���N�ɂ킽���Ă��������i��������ď��i��̔����Ă����̂ł��낤���B�R�l�̘A�g��Ƃ͂܂��������ʂ̂Ȃ��X���[�Y���ŗ����悤�ɐi�̂ł��������A���������́A��������Əd���A�^�N�V�[�̒��ɒu���Y�ꂽ���}�n���Y���̂T�{�̏d�ʂ͂���悤�Ɏv����̂ł������B
�@���́A���s�ו��̑��d�ʍ팸�ɂƂ����邽���Ȃ̂ł������B���Ƃ��Ύ���3�T�Ԃ̗��s�̏ꍇ�A�����̃p���c3�����J�o���ɂ߂�̂ł��������A�����g�ɂ��Ă����ȑf�ރg�����N�X����80�O�����ł���̂ɑ��A���j�N���ɂĔ��������X�[�p�[�V���L�[�g�����N�X�͉���40�O�����B���Ȃ킿���d�ʂ�120�O�����̍팸�ɂȂ�̂ł���B�������������ł���B�C��1������������40�O�����A�s�V���c����͂蔖��̑������Ŗ�100�O�����A�Ƃ�������ł���B��������Đ��S�O�����̍팸�����������͂��Ȃ̂ł��������A���̓w�͂���C�ɖ��ʂɂ����v�Z�ɂȂ�̂ł������B
�@���̓z�e������̂قڈ�{�����A�k�����������ق�ڎw���ĕ����n�߂��B���炭�s���Ə����ȃ��X�g�������ЂƂ��������A�c�Ƃ͒��炭���Ă��Ȃ��悤�ŁA�ܑ����H�������Ős����ƁA�D���ɂȂ����B�����Ԃ͕p�ɂɒʂ�߂��čs���A�g���b�N�̒��˂�����D��������邽�߂ɁA���݂͎֍s����������Ȃ������B���ꂪ��Z�����̏Z�����Ɖ����Ō�������̌��������Ԉ�悪���������A���������o���Ă���̂͋����̎Ⴂ�����ŁA�K�₵�Ă����N2�l�ƃp�[�e�B�[�������̑��k�����Ă���悤�Ɍ������B
�@�u���[�[�C�i�����فj�H�v�Ɛ���������ƁA���𓊂��o���i�D�ň֎q�ɍ��|���A�^�o�R���z���Ă����j�̊�ɏ݂��L����A�����Ɨ����オ�����Y��ȐU�镑�����������B�u�K�C�h�͕K�v���v�Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ��ꂽ�Ǝv�����A�悭������Ȃ��܂ܓ��ꗿ�����B�o�}���Ă��ꂽ�̂́A��i�Ȋ痧���̏����ȏ����������B30���炢���낤�B�j�u�t�̓������Ƃ�͂艽���ɏ����Ă������A�A�U���V�������̊v�ō��Ƃ����A����Ԃ��܂ł��ތC�𗚂��Ă����B���������ɂ́A�j�u�t�ƃE�B���^�̋�ʂȂǂł��Ȃ��̂ł���B�F�N�₩�ȃZ�[�^�[�𒅂Ă����Ǝv���B
�@�����ȓW�����B�Z���P���Y���Ȃ���W�����̂P�P�ւƈē����Ă��ꂽ���A��������܂߂Č��t�͂قƂ�lj��������ł��Ȃ������B����ł��K�ȋ�����u���ĕt���Y���Ă���邱�̐l�ɁA���͍D�����������B�u�F�Ղ�v���s�����Ƃ̓A�C�k�Ƌ��ʂ���悤�ł������B�u�S�b�h�v�u�x�A�[�v�u�Z�C���v�Ƃ������p�P��Ɓu�A�C�k�v�Ƃ����P��������Ă݂��Ǝv���B���w�҂͎���l�������B�Ⴂ��e�������ȑ��q��A��ē����Ă������A�Ȃ��������ɏo�čs���Ă��܂����B���炭����ƁA�����̂������N������擪�Ɋw�|���炵���l�X�����āA�����K�C�h���Ă��������̕\�������n�܂�炵�������B
�@���́A�ԑ��ɂ���k�����������قŁA2�A3�{�̒Z���r�f�I�e�[�v�����������ŁA�\�A�E���V�A�ɂ������Z�����̕�炵�ɂ��ẮA���̒m�����������킹�Ă��Ȃ������B�r�f�I�Ɏ��߂��Ă����C���^�r���[�ł́A���ƃR���z�[�Y�̘J���҂Ƃ��ē����Ă��邪�A�Ǝ��̕��K�������ăA�C�f���e�B�e�B�[���ۂĂ��A�A���R�[���ˑ��ǂɊׂ�l�������A�Ƃ��������Ƃ�����Ă����Ǝv���B���͂ނ��낻�̔����قł́A�T�[�~�Ƃ����k�������̐l�X�����ɏo��Ƃ��̃_�C�i�~�b�N�ȑ̂���A�C�k�C�b�g�̂��Ղ�ŁA�����ɕ������������_����Ŋۑ���@���p�ɖڂ�D���Ă����B
�@
�@���́A�\�A�ɂ������Z�����̗��j�̈�[�ɂ��Ă��܂��A�w�Ӌ����璭�߂�x�ɂ���ċ�����ꂽ�̂ł���B
�i�P�j�u�������A�����Ɓv�Ǝ�����`����\�A�ł́A���V�A�l�Ə���
�@�@�����Ƃ́u�����I�Ȃ���v�����ɂ���邱�Ƃ͂Ȃ������B����
�@�@�̍\���҂́u�Љ��`�ւ̐i���Ƃ����ڕW�����L��������v�ł�
�@�@��A�u��Z�����Љ�́A�K�Ȏw��������A���i�K����Љ��`
�@�@�i�K�Ɉڍs�ł���v�ƍl����ꂽ�B
�i�Q�j1925�N�A�T�n�����ɐ�Z���i�j�u�t�A�E�B���^�A�G���F���L�j
�@�@�w�Z������Ă���B�܂����[�j���O���[�h��w�ł́A�����e�n��
�@�@���Z�����̊w�����W�߁A�G���[�g�i��Z���w�Z�̋��t�j���琬��
�@�@����g�݂��i�߂�ꂽ�B������1931�N�ɂ́A������13�̐�Z��
�@�@������̂��߂̃A���t�@�x�b�g������Ă���B
�i�R�j�������A�u�i���v�Ɓu���V�A���v�̍����͔������Ȃ������B��
�@�@��1920�N��㔼�ȍ~�Ɏn�߂�ꂽ��K�͊J���ɂƂ��Ȃ��A���A��
�@�@�����傷��ɂ��������āA��Z���̎����E�����͂Ȃ�������ɂ���
�@�@�Ă����B�����ăR���z�[�Y�ɂ�����W�c�J���́A���ɉ�������Z
�@�@���̐�����j�Ă������B
�i�S�j1930�N��A�T�n�����̐�Z���R���z�[�Y�̂������́A�_�Ƃւ�
�@�@�]�������߂��Ă���B
�i�T�j1930�N�㔼�Έȍ~�A���傫�ȑ��ւ̋����ڏZ�ƃR���z�[�Y�̍�
�@�@�����n�܂�B1962�N����1986�N�ɂ����ẮA�T�n�����ɂ����鑺
�@�@�̑������̂���1000����329�Ɍ����B�j�u�t�̑啔���̓m�O���L
�@�@�ƃl�N���\���Ƃ���2�̑��ɏW�Z��������B��K�͉������V��
�@�@�m�O���L�́A�Z��ݔ����s�K�Ȃ��̂ŁA�u�ނ�ɍs���̂ɂ�18
�@�@�L���������Ȃ��Ắv�Ȃ�Ȃ������Ƃ����B
�@���������������ق܂ł̓��A��������ł�������̉Ɖ��B�������Ƀg�D�~��߂��ɊJ����Ă����Ƃ͂����A�����A���ꂪ��Z���j�u�t�̑����ƒP���Ɏv������ł��������́A�u�V���v�ɂ����Č��݂��ꂽ���̂ł������̂��낤�B
�@
�@�z�e���߂��̌����܂Ŗ߂�A�^�o�R���z�����B���V�A�����̏����ȋ�����������A�N�₩������Ɣ��̕ǂ́A�e�[�}�p�[�N���v�킹���B���Ǝ҂炵�����N�̒j���x���`�ɍ��荞��ł������A�^�o�R������Ƃ͌����Ă��Ȃ������B����Ԃɗc�����悹����e�������ɍs���Ă��܂����B
�@�[�H�̓z�e���̐H���łƂ邵���Ȃ������B����ɏ����Ȃ����������̃��j���[����́A�����ǂݎ��Ȃ������B�u���[�Y�v�Ƃ����P��������Ă݂��Ǝv���B�E�F�C�g���X���w�����������ɖڂ��Â炷�ƁA�m���ɂ��������Ă���悤�Ɏv�����B�e�ȋC�����ł������Ă��ꂽ�̂��낤�B�܂�20��O���Ƃ��ڂ����E�F�C�g���X�́A���ꂪ�Ă��ǂ������������̂ł��邩��������Ă��ꂽ���A�u�`�L���v�Ƃ����p�P�ꂾ����������ꂽ�B���́u�`�L���H�v�ƕ����Ԃ��Ȃ���A�{�̉H���Ɍ����Ă�������q���q�������A�u�_�[�C�`�F�E�G�[�^�v�ƌ������B�E�F�C�g���X�́A����Ԃ��Č������֕����n�߂����Ǝv���ƁA���̌{�`�Ԗ͎ʂ��ɍČ����Č����A�}��悤�ȏ��������Ă��B���̑ԓx�Ɏ��͐e���݂������Ȃ������B
�@�r�[�����^��ł����̂́A������Ⴂ�E�F�C�^�[�������B�ނ͂����܂�����Ă��āA��Ԃ�Ȋ����������̑O�ɍ����o�����B�T�[�r�X���Ƃ������Ƃ͂킩�����B�j�����̊�������������d�����������悤�ȋC������̂́A�ނɐe���݂��o�������炾�낤�B���͋��̖��O���m��Ȃ��B���������5�{���炢�̑傫���̂���͗₦���Ă��āA���L�����������A������T������Ŋ���t���A�r�[���ŗ������B�g�̂��₦���Ă����B�E�H�b�J�ɂ���悩�����ƌ���������A���͂Ƃ����Ɂu�s�[���@�v�Ƃ����P�ꂪ������o�Ă��܂��̂��B���ꂪ�Z���P���ŁA�K���ʂ���P�ꂾ���炾�낤�B
�@���V�A��̖����ɂ́A�j���E�����E�����̋�ʂ�����A���̋�ʂɉ����Č`�e�������łȂ��A�����́u�P�v��u�Q�v���ω�����B���Ƃ��u�Q�v�́u�h���@�i�j���E�����j�v�u�h���F�i�����j�v�ŁA�u���@�_�[�i���j�v�͏�������������A�~�l�����E�H�[�^�[���Q�{�~�����Ƃ��A�u�Q�̐��v�́u�h���F�E���@�_�[ �v�ƂȂ�i�{���́u���@�_�[�v������ɕω�����͂�������ɕ����Ȃ��j�B���ꂪ�ȒP�ɂ͊o�����Ȃ��B�L�I�X�N�i�G�ݓX�j�Łu�h���@�E���@�_�[�v�ƌ����āA�u�h���F�v���ƒ������ꂽ�Ƃ����b�������Ƃ��A�u����Ȃ�A�c�[�E�H�[�^�[�ł�����Ƃ��Ⴄ�v�Ƃ���F�l�Ɍ���ꂽ���A�����Ă͂��Ȃ��̂Ŏ��M�͂Ȃ����A�T�n�����ł͒ʂ��ɂ����Ǝv���B����Ɏ��́A�p��̕K�v���͒Ɋ����Ȃ�����A�����ɂ����A�ʂ��Ăق����Ȃ��Ƃ��v���Ă���̂������B
�@���̒��A���H�`�P�b�g�������Ăӂ����ѐH���ɍs���ƁA�H���W����̋���ɂ������B�u�����X���v�ƌ����Ă���炵���A�`�P�b�g�ɋL����Ă��鎞�ԑт������Ē�R�������A���◝�R�̐����͑����Ă���悤�������B�u�K�X�{���x����ɂȂ����v�Ƃ��u�H�ނ��Ȃ��Ȃ����v�Ƃ������Ă���悤�ȋC���������A���ׂĈӖ�ɂ��Ȃ��Ă��Ȃ����Ă����ۂ��ł���B
�@���Ȃ�̎��ԁA����I�ɂ���ׂ��Ă����Ǝv���B�w�ォ����傫�Ȑ����|����ꂽ���Ǝv���ƁA��q�̒j�������̎M�������o���Ă���̂ł������B �����āu���̂�H�ׂ�v�ƁA����͂͂�����ƈӖ�ł��錾�t�������Ă����̂ł���B�M�̏�ɂ̓s�U�g�[�X�g�̍Ō�̈�ꂪ�c���Ă���A���H�̃��j���[�͂���ł���炵�������B�j���͕v�l��A��Ă��Ă����B���́A�u�X�p�V�[�o�A�c�c�o�b�g�A�m�[�A�T���L���[�v�ƌ������悤�Ɏv���B���̂��Ƃ�����Ă������낤���B���̂܂ɂ��~�[�ɍs���Ă����H���W�������ȎM�������ċA���Ă��āA�����ɂ͍��H�ׂ��`�L�����C�X���킸���ɍڂ����Ă���̂������B�u����ł��������H�v�Ƃ������Ƃ炵�������B���́u�_�[�A�_�[�v�ƌ����A���܂�����s����������Ă���Ă���j���ɂ�����x��������A�Ȃɂ����B�o�Ă����̂́A���̃`�L�����C�X�Ƃ��������߂�ꂽ�s�U�g�[�X�g�ł������B���́A�����N�������̂������ł��Ȃ��������A�s�U�g�[�X�g�͒g�����A�����������B
�@
�@���́A���̕��͂������n�߂Ă���w�Ӌ����璭�߂�x�̑��݂�m�����̂ł���A���́u���s�L�̂悤�Ȃ��́v���A�r������͂��́u�Љ�̂悤�Ȃ��́v�ɕω����Ă��܂��Ă���̂ł������B�Ƃ��낪���̏����̍Ō�̏͂́A�����Â���ӗ~���������킹���˂Ȃ����̂������̂ł���B�Ƃ����̂��A�u�I�̓T�n��������z����v�́A���̂悤�ɏ����o����Ă�������Ȃ̂ł���B�u�T�n�����Ɍ������t�F���[�̒��ŁA�c�c���킽���͓ǂ�ł����v�B�u���s�L�v�͂��łɏ�����Ă��܂��Ă����̂ł���B
�@�t�����R���T�R�t����q�H�����������̂�1995�N�B�e�b�T�E���[���X�E�X�Y�L�́A���̗��N�ɃT�n������K��Ă���̂ł������B�����Ă������̂��ƁA���O�ɒt���̖k���L�O�ق�K��A���̌��z�l������W�����e�܂ł������ɏ����Ƃ߁A���͂������Ă���̂ł���i���͂Ƃ����A�u������v�Ɓu���F���{�[���v�����o���Ă��Ȃ��̂ł������j�B
�@�����ăt�F���[�̒��ł́A�u�i�L�������ɂ����������j�ǂ�ł����v�����ł͂Ȃ��A���悵�Ă������T�n�����ݏZ�̘V�l��������b���A���̋L���Ɏv�����߂��点�A������肩�A�݃T�n�������N�n�Z�l��j�u�t�A�E�B���^�̐l�����Ƃ���b�����킵�Ă���i���͓�������ŐQ�Ă��������ł���j�B
�@�����Ă܂����R�̂��ƂȂ���A���W�m�T�n�����X�N�̋��y�����ق�K�ꂽ�e�b�T�E���[���X�E�X�Y�L�́A�t���Ɠ��l�ɂ��̓W�����e�J�ɂ��ǂ�A���̏�ŁA���̗��҂������������ɂ��ďq�ׂĂ���̂ł������B
�@���̗��҂ɋ��ʂ��Ă����̂́A�u�T���҂̖ڂ�ʂ��Đ�Z��������v�Ƃ����p���ƁA���ꂼ��̍�������z���ׂ��u�����I����v�̒掦�������̂ł���B�Q�̔����ق́A����������̓W�������ɂ����āA�u���̒n��̒T���j�v������n�߂�̂ł���A�Â��āu��Z�����Ɋւ���W���v�ւƌ��w�҂�U�����Ă����̂ł������B�����āA�W�����e�̏I���_�́A�t���ɂ����Ắu��l�̉����v�ł���i���{�R�͎̏ۂ���Ă���j�A�T�n�����ɂ����Ắu�p���`�U���ɂ��c���h�q�v��u�g�i�J�C�W�c�q��ɂ�鐶�Y�̌���v�ƂȂ�ł��낤�B
�@���͂��̕��͂������Ȃ���A������x�u���v�������C���ɂ��Ȃ��Ă���̂������B�w�Ӌ����璭�߂�x�̒��҂��ǎ҂�U�������ƍl����u���v�Ƃ́A�u���j�␢�E�j���������������ĖK���闷�v�Ȃ̂ł���B���͂悫���s�҂ł����������M�͂Ȃ����A�Ƃ��������ǂݏI�����̂ł���A���̕��͂��I���ɋ߂Â��Ă���̂ł���B
�@
�@�R���T�R�t
�@
�@�ӂ����і�s��Ԃɏ��A���W�m�T�n�����X�N���炻�̂܂ܒ������o�X�ɏ��p���A�R���T�R�t�܂Ŗ߂��Ă����̂������B�Ō��2���Ԃ��߂����̂ł���B������̏h���{�݂ł���z�e���E�A���t�@�́A���Y��ȃy���V�������ŁA�����ȎᏗ���Ƃ��������͋C�̏������Ί�ŏo�}���Ă��ꂽ�B
�@�����ł̊ό��ꏊ�́A���j���y�����فA���k�C����B��s�唑�x�X�A�����ċ�����i���ɂ�j�_�АՐΒi�ł���B���́A�_�Ђ̐Βi����������ƁA���j���y�����قւƌ��������B�d���͂��Ă��Ȃ��������A�ق��Ă���킯�ł͂Ȃ��A����҂����邽�тɓ_������̂ł���B���́A���ꂪ�����I�Ȃ̂��ƁA���̂Ƃ��ɂ͎v����悤�ɂȂ��Ă����B���Ƃ����W�m�T�n�����X�N�̃`�F�[�z�t�L�O���w�ق́A���̏������ō\������Ă���A�w�|���͌��w�҂��G�X�R�[�g���Ȃ���A���������Ƃɓ_���E�������J��Ԃ��Ă����̂ł���B�z�e���E���[�_�̔��X�ł́A�^���Âȕ����̉��ɔ̔��������肱��ł���̂ɋC�Â��A�v�킸������Ƃ����̂ł���������ǂ��B
�@���j���y�����ق͂ƂĂ������Ȃ��̂ł��������A�W������Ă����ꖇ�̎ʐ^����ۂɎc���Ă���A�����Ă���𐳊m�ɍČ��ł��Ȃ����Ƃ���͂��Ȃ��̂ł���B���̎ʐ^�́A1945�N�ɂ����R���T�R�t�ŎB�e���ꂽ���̂ŁA����G�݉��������̓X�܂̑O�ɏW���������N�l�����ƁA���̓X�܂̊Ŕɑ傫���f����ꂽ�u�\���B�G�g�v�̕������L�^���Ă���̂ł������B���̈ꖇ�́A���{�������̃T�n�����ɂ����āA�鍑��`����̉�����Ă����l�X�����݂��Ă������ƁA������1945�N�̃\�A�ɂ���̂́A���̊肢������������̂ł��������Ƃ������Ă���̂ł���B
�@���́A���{�������ɂ�����T�n�����ŁA�ǂ̂悤�Ȋ������s���Ă������ɂ��āA����m�����Ȃ��B���̎ʐ^�́A�\�A���Y�}�̃v���p�K���_�̐����������炩�͊܂�ł��邾�낤���A�s���ʐ^�ł���\������ے�ł��Ȃ���������Ȃ��B����������ł��A2��5��l�ȏア�����N�l�J���҂̒��ɁA�\���B�G�g�����ɂ����������Ă����l���F���ł������Ƒz�肷�邱�Ƃ́A����ȏ�ɂł��Ȃ��Ǝv����̂ł���B
�@���́A���W�m�T�n�����X�N�̋��y�����قŁA1918�N�̃E���W�I�X�g�N�㗤����n�܂�u�V�x���A�o���v�𓌕�����̍��������ŕ\���A1941�N����n�܂�i�`�X�h�C�c�̐N�U���A�ӂ����э��x�͐�������̍��������ŕ\���i1939�N�Ƀi�`�X�ƍs�����|�[�����h�����͎̏ۂ���Ă���j�A�����N�������ނ��Č��݂̃��V�A���Ƃ��ۂ���Ă���Ƃ����W���������悤�ȋC������B���{�Ō����Ƃ���́u�V�x���A�o���v���A�\�A�E���V�A����́u�N���v�Ƒ������Ă��邱�Ƃ̏؋��Ƃ��āA��ۂɎc�����̂ł������B����ǂ����́A���s��ł̔����Ƃ����Ӗ��ŁA���̈ꖇ�̎ʐ^���v���o���̂ł���B
�@���ɂ́A�ʐ^���B��Ƃ����K�����Ȃ��BI take pictures in my mind.�ȂǂƁA�����in�ł͂Ȃ�on��������Ȃ��Ǝv���Ȃ���A�Ӓn�ɂ��Ȃ��Ă���̂ł������B���������́u�����Ǝv���v�u�C������v�ȂǂƂ��菑���Ă���̂ł���A�������̈ӌŒn�ɂ����邱�������A�C�����ׂ��Ȃ̂�������Ȃ��Ǝv��������̂ł���B�@
�@���́A����B��s�O�̒ʂ���A�j���p��������Ƃ���܂ŕ����A�`�߂��́u�y���M���o�[�v�ɓ������B�����Ă����̂悤�Ƀs�[���@�𗊂��ƃ��j���[�Ɗi�����Ă��鎄�ɁA�{���V�`��r�[�t�X�g���K�m�t��M�S�Ɋ��߂Ă��ꂽ�̂́A�{�f�B�R�����o�[�X�[�c�E�p���N�t�@�b�V�����ɐg���E�F�C�g���X�������B�ޏ��́A�w���̎w������b���x�ɕ`���ꂽ�����̊G�ƃ��j���[�̕�����1��1�Ή������āA���ǂ܂ł��Ă��ꂽ�̂ł���B�ޏ��ړ��ĂƂ��ڂ������₶����������������݂ɗ��Ă����̂��A���R�̂��ƂƂ����悤�B
�@�z�e���̒��H�́A�����͂�̏�����Ɋ؍��X�[�v�ƃL���`�A�����ăT���[�N���[���������Ղ肩����������ȃP�[�L�������B���Ɉ�i��������������Ȃ����Y�ꂽ�B���̓��͎��R�s���`���Ă݂����A�~�������͉̂����Ȃ������B�s�ǒ��w����2�l�g���A�g�ѓd�b��Ȃ����Ɛ��������Ă����B �C���^�[�l�b�g�J�t�F�ł͏��N�������Q�[���ɔM�����Ă����B �s�U���ɓ���Ƃ�͂胉�o�[�X�[�c�E�{�f�B�R���E�p���N���E�F�C�g���X�����Ă����B���w�Z�������̒��N��������l�ŐÂ��ɃR�[�q�[������ł����B��ʂ�ɉ�����o���Ă����N���X�i�y���r�[���̂悤�ȒY�_�h�����N�j���A�����ɍs�����B��������̔����a������ł����B�����Ď��́A�b�̐s���邱�Ƃ�m��Ȃ��V�l�����̐����Ȃ���A�������Ԃ��߂������B
�@�A��̃t�F���[�͋Ă��āA���V�A�l�̃c�A�[�O���[�v���ڗ����Ă����B���w�����炢�̎q�ǂ���A�ꂽ�������̉Ƒ��������B�ߌ�1�����A�t�����B���͎D�y�܂ł̃o�X�ɏ�邱�Ƃɂ��A���Ԃ܂ł̑҂����Ԃ��A�X�ɂ܂ŏo�āA�R�C�������h���[�Ő�������Ȃ���߂������B�o�X�^�[�~�i���܂Ŗ߂�ƁA�t�F���[�ňꏏ���������V�A�l�c�A�[�̐l�X�łقƂ�ǖ��Ȃ������B�t�F���[����Ŏ��Ԃ�ׂ��A�����������Ă����̂������B�T�[�r�X�G���A�ɒ������тɁA�q�ǂ��B�͂悭�V�сA�͂��Ⴂ���B�������肭���т�͂Ă����A�D�y�ɒ������B���V�A�l�c�A�[�̐l�������A�ǂ����̃o�X��ō~��A��ɂ܂���Ă������B
�@
�@
�q�Q�l���r
�w�Z�̗̂F�l�x�i�䑺�O�E�͏o���Ɂj
�w2009�N�ł���̖k���̓y�x�i�O���ȁj
�w�k���̓y�����l����x�i�a�c�t���E��g���X�j
�w�k���̓y���x�i�a�c�t���E�����o�ŎЁj
�w�V�x���A�o���x�i�����V�E�}�����[�j
�w�V�c���̐N���ӔC�Ɛ��ӔC�x�i��{�G���E�؏��X�j
�w�����{�c�x�i�؍F���E�V���{�o�ŎЁj
�w�����\�ܓ��̐_�b�x�i������ȁE�����ܐV���j
�w�זɓS���Ɠ��{�̐푈�ӔC�x�i���C���q���E���Ώ��X�j
�w���[���h�K�C�h�E�T�n�����x�i���c�k��E�i�s�a�j
�w�n���̕������E�V�x���A�S���ƃT�n�����x�i�_�C�������h�Ёj
�w���̎w������b���E���V�A�x�i���Z���^�[�o�ŋǁj
�w�`�F�[�z�t�S�W12�x�i�����ܕ��Ɂj
�w�Ӌ����璭�߂�x�i�e�b�T�E���[���X����E�݂������[�j
�w�̉Ԃ̉��x�i�i�n�ɑ��Y�E���t���Ɂj
�w�N���_�Ёx�i�Ҏq���E�V���Ёj
���v���t�B�[����
���������Y�i���Ƃ��E���傤���낤�j�B
Web�]�_���u�R�[���v26���i2015.08.15�j
�����s�L���i���������Y�j
Copyright(c) SOUGETUSYOBOU�@2015 All Rights Reserved.
|
| �\���i�ڎ��j�� |