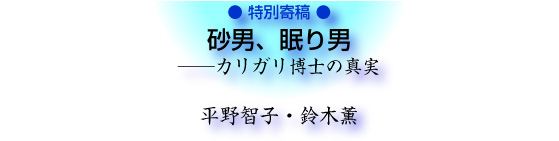|
|
|
Web評論誌「コーラ」 |
|
■創刊の辞 ■本誌の表紙(目次)へ ■本誌のバックナンバー ■読者の頁/ご意見・感想 ■投稿規定 ■関係者のWebサイト ■プライバシーポリシー |
|
<本誌の関連ページ> |
|
■「カルチャー・レヴュー」のバックナンバー ■評論紙「La Vue」の総目次 |
Copyright (c)SOUGETUSYOBOU |
|
|
|
はしがき
筆者らの一人(平野)がたまたまDVDで『カリガリ博士』“Das Cabinet des Dr. Caligari” ロベルト・ヴィーネ監督、1919年製作、20年公開)を見たことから本稿は書かれた。平野はこの映画に強い印象を受けたのだが、調べてみても、映画史上に名高いこのサイレント・フィルムを論じた文章で、平野が見たものについて触れている例は一つも無かった。それどころか、「あらすじ」と称するものさえ、およそまともに書けているものは見当たらなかったのである。もう一人の著者である鈴木は、遥か昔にどこであったかもう正確には思い出せない複数の上映会場のスクリーンでこの映画を見ており、一度はメモを取っているが、その内容は――眠り男”チェザーレは語り手フランシスの分身で、恋敵を殺し、恋する女を寝室から攫って逃げる、彼の欲望の代行者であり、それと知らずにフランシスは、外界の事件として可視化された自らの欲望の上演に立ち会っている。彼の内面の出来事であるために徹底的に人工的なセットの内部、すなわち「カリガリ博士のキャビネットの中」で一切が生起する――といったものであった(と回想される)。鈴木だけではそれ以上の認識に至らなかったろうが、例によって平野がこれ以上ないほどあざやかに作品を分析してみせたため、以下の論証を共同で行なうことになった。主要な解釈は平野のものであるが、言ってみれば、平野の脚本(あるいはスコア)を鈴木が自分なりに撮影(演奏)したということになろうか。
『カリガリ博士』について論じる過程で、私たちは必然的に、これまでなぜ、この有名なフィルムについて、まともな批評がなされてこなかったのかを考察することになった。そして、その結果として、既存の批評の主に次の二つの立場に、異議を唱え、反対することになった(なお、この二つの立場からの批評は、『カリガリ博士』論に限らず、今なお広く行なわれているものであることを言いそえておこう)。一つは、芸術作品を論じる際に、「性的なもの」と「知的なもの」を結びつけることができない――前者を、矮小化、局所化するために――立場であり、もう一つは(一つめと関連するが)、あらかじめ作り上げた物語=歴史に、植民地化したジャンル(ここでは映画)の作品を取り込んで利用する――作品を単純に時代を反映するものと見なして、もっともらしい文化史を捏造する――立場である。
本稿で対象としたのは、英語とその日本語訳字幕付DVD『カリガリ博士』(IVCベスト・セレクション)(A)*と、YouTubeに上げられたそれより長い英語字幕ヴァージョン(B)http://www.youtube.com/watch?v=ALqnSUMHPrAである。(B)は画像が鮮明で、字幕もあらたまっており、英訳のヴァリエーションという以上の異同が見られる(ただし、物語の大筋に影響はない)。傷みの激しいヴァージョンhttp://www.youtube.com/watch?v=xrg73BUxJLI&feature=relateもYouTubeには存在し、これは英語字幕は(A)と同じだが、(A)(B)からはカットされたと思われる古いクレジット・タイトル(英語)が本篇の前に流れ、その最後には「この話は十一世紀の伝説のカリガリ博士の、現在への再びの出現を語る」といった趣旨の文章が読まれる。この「伝説のカリガリ」の年代については、病院長室のキャビネットから見つかった本のページ(としてインサートされる映像)が、内容も含めて(A)と(B)では異なっており、たとえば(A)ではカリガリは「十一世紀の修道僧くずれ」、(B)では「十八世紀の神秘主義者」である。
映画の内容や字幕について、必要と思われる際は(A)(B)どちらのヴァージョンかを文中で示したが、煩雑になるのを嫌って断らなかった場合もある。(A)の字幕を引用するのに日本語字幕の訳には必ずしも従わなかった。ドイツ語字幕版はウェブ上には見つからなかった。

(★Bヴァージョンのトップ画面)
*(A)もYouTubeで見られる。
一 探偵の仕事
観客にゆだねられた“解決”
『カリガリ博士』はドイツ表現主義映画の傑作であり、歪んだ書割めいた(実際、書割なのだが)特徴的なセット美術でも有名云々といった説明なら、あらためてここで試みるまでもなく、映画ファンならとうに御存じであろう。そうでなくても、山高帽に丸メガネ、マントを着て杖を持った小柄な老人と、その傍に直立する棺のような箱の中の“眠り男”の、あるいは、気絶した女を脇に抱え奇妙なセットの中を逃げてゆく黒ずくめの怪人のスチール写真なら、目にしたことがある方も多いかもしれない。「カリガリ博士」というそれ自体印象的な名前をどこかで聞いた覚えがあるという方はさらに多かろう。最近では、「ホラー映画の元祖」だの、「最古の妄想オチ映画」だのと言われもするらしい(トールキンをRPGの祖というたぐいか)。カリガリ博士という無気味な老人が夢遊病者チェザーレ(“眠り男”)を操って起こした殺人事件が回想として語られるが、実は語り手フランシスは狂人で、回想部分は妄想であり、カリガリ博士はフランシスが入院している精神病院の院長だった――ごくごくかいつまんで筋を追えばこんなところであろうか。
しかし、それ以上に長い「あらすじ」となると、研究書やウェブで探してみても、まず、例外なく、重要なシーンを落したり、逆に勝手に補足して話を「作って」しまっていたりする。たぶんそれは偶然ではない――細部が軽視され、〈物語〉に還元されがちであるとは映画一般について言いうることであるが、特にこのフィルムの場合、物語自体に一種の推理小説的なトリックが仕掛けられている。最初から疑わしい人物は犯人ではないという定石通り、あからさまに怪しいカリガリ博士なる殺人者は存在しなかったことが最後に判明するが、明示的に探偵役が謎を解いてみせるような親切な作りではないので、大半の観客には仕掛けの存在すら気づかれまい。観客はまさに探偵のように、手がかりとしての細部に注目しなくてはならないのだが、何が重要かさえ初見では認識不可能だから、少なくとも二度見なければわかるまい。記憶を頼りにするしかなかった時代の観客が構造を理解できなくても、あるいは無理はなかったかもしれない。だが、読者がこの文章を読んでいるPC上で、パブリック・ドメインとして置かれたファイルに今すぐ接続して確かめることも可能な今日でさえ、それまで観客が見てきたもの、すなわちフランシスの回想として語られた部分が実は語り手の妄想であったという結末は、「ただの妄想で全ては無意味だった」と受け取られるか、さもなければ、「本当に妄想だったのか」という点に注意が集中してしまいがちであるようだ。
まず押えておくべきは、妄想だったことが明かされたからといって、それまでの回想部分が無意味になる訳でも、否定される訳でもないということである。それどころか、回想として語られた(演じられた)部分は、「現実」として提示される部分との関連において、新たな光の下に照らし出されることになる[☆1]。夢遊病者を操って殺人を犯すカリガリをフランシスが追いつめるという設定は架空のものであった。それは、犯人があらかじめ置いた偽の手がかりに、無能な警察がうまうまと釣られて描いた筋書きのようなものであったのだ。しかし、こんなものはまだ“真相”ではない。この映画の場合、言ってみれば真相が明かされる手前で話が終わっているのである。
事実のレヴェルでは、院長はカリガリ博士ではなかった。しかし、フランシスが彼をカリガリ博士と思い込んだことには“意味”がある。ラスト・シーンで院長は、彼を「カリガリ博士」(とは、しかし、何か?)と呼んで暴れたフランシスを診察して、「彼の偏執病がどんなものなのか理解できた。彼は私を伝説のカリガリだと思っているのだ。しかしこれで彼をどうやって治せばいいかわかった」と言う。奇妙な同語反復の印象を与える幕切れ――だが、これは要するに、院長が、「カリガリとは何であるのか、なぜフランシスが院長をカリガリだと思い込むに至ったのか、それを解き明かせ」と観客に言っているのだ。この時、院長の考えぶかげな眼差し(妄想部分でカリガリ博士に扮していた時とは別人のようだ)は、部下の二人の医師をさしおいて、キャメラの方、つまり私たちに向けられている。
ホームズ/フロイト
『カリガリ博士』という映画には――映画というものは一般にそうであるが――目に見えるものとは別に、どこか深いところに意味がひそんでいる訳ではない。全ては表層に、観客の目に見えるところに隠されているのだが、物語を性急に追う眼差しはそれを通り過ぎてしまうのである。探偵にとってと同様、一見重要ではない物、人目をひかない、見過ごされるようなディテールにこそ手がかりがある。と言っても、それは見落すのが当然と思われるような“細部”とは限らず、物理的に意外に大きな部分を占めていることもある。今回平野が見つけたある手がかりもそうで、本稿を最後までお読みになられた方は、ご自分の目にもそれが間違いなく映っていたことをお認めになるだろう。
原題の「カリガリ博士の箱(キャビネット)」とは、チェザーレを入れた吸血鬼の寝床めいた箱であり、それが置かれたカリガリ博士と名乗る香具師の見世物小屋であり、カリガリ博士と同一視された院長の宰領する精神病院という(城や僧院のように)閉ざされた空間であり、そこにある院長の部屋であり、その中に備え付けられたキャビネットでもあろう[☆2]。さらには、キャビネットから見つかった(それ自体が妄想の一部なのだが)『夢遊病者』なる古い書物も箱の一種と見なされよう――「カリガリ博士の箱」と題された章が、ここにはさらに入れ子になっている。〈中心紋〉的合わせ鏡の中で見出されるページには、十八世紀のイタリアでカリガリ博士と名乗る神秘主義者が、箱の中で眠る夢遊病者チェザーレを見世物にして各地の市(いち)を回りながら、彼を操って殺人を繰り返し(疑いをそらすためにはチェザーレそっくりのダミー人形を箱に入れておき)、町々を恐慌に陥れたという記事が読まれる[☆3]。
しかし、院長はカリガリの生まれかわりでも模倣者でもなく、この名前の一致は、フランシスが本の内容を見つける前から知っていた――自分の頭の中にすでにあるものを外部に“発見”した――ということしか意味しない。院長がカリガリである証拠をフランシスが見出したと信じる場所もまた彼の内部なのだ。「内面」と呼ばれるものも映画では通常、外部にあらわれるのであり、いわゆる回想シーンは俳優によって実際に演じられ、事実上、空想と現実の別は無い。フランシスの内面もそうやって外化されていた――舞台装置としての異化された外界とはフランシスの歪んだ内面であり、そこに彼の妄想が投射されるスクリーンであった。彼の回想と思われたのは、過去にあった出来事(フランシスの狂気の原因になった事件)が著しく変形されたものであったのだ。フランシスが語り終わった時、その場所がまさに精神病院の中であることが判明する。
それよりもある意味さらに衝撃的なのは、回想の中に登場した人々が、実は病院の患者であったことだ。フランシスの過去に彼らはいなかった。病院に来てから出会った院長と患者たちを彼が(勝手に)キャスティングして、過去の事実として語り、上演したのが、フランシスの回想だったのである。それに立ち会う観客が身を置く内部空間もまた、カリガリ博士のキャビネット(映画館という見世物小屋?)に他なるまい。
映画産業の草創期であり、精神分析の草創期でもあった時代に、「心の世界」と「映画」の類似はすでに人々の関心を引きつけたようだ。『心の不思議』(1926年)なる精神分析医が協力した映画も作られたが、そこではいわば映画が夢を再現しようと努めている(ちなみに主演はカリガリ博士役のヴェルナー・クラウスである)。映画を知った人々の夢は映画に似かよいもしたことであろう(私たちの夢は、多かれ少なかれ映画のように編集されているのではないか)。浸透する夢と映画。「夢は一つの投影、すなわち内的過程のある一つの表出である」と書いたフロイトを受けて、「芸術作品もまた内的な動揺を終結させる「投射」なのであり、夢のように、欲望の幻覚的な充足を可能にする」とサラ・コフマンは言う(『芸術の幼年期』)。「だから、芸術作品もまた、幻覚性のパラノイア精神病に似ているのである」とコフマンが続ける時、その「芸術作品」とは何よりもまず映画を思わせよう。実際、フランシスが(回想という名の下に)私たちに見せる“映画”は、まさしく「幻覚性のパラノイア精神病」の結果と呼べそうなものだったと判明する。『映画――想像のなかの人間』で、エドガール・モランは夢と映画をあえて混同しようとした諸家の言葉を引いている――「映画とは夢である」(ミシェル・ダール)、「映画は人工の夢」(テオ・ヴァルレ)、「夢もまた映画ではないか」(ポール・ヴァレリー)、「私は眠りにつくときに、映画を見にいく」(モーリス・アンリ)、「私たちに対し、夢の可視化を可能とするために動く映像がとくに発明されたように思われる」(ジャン・テデスコ)。もう忘れられてしまったかもしれないが、カラー映像があたりまえのものとなる以前には、夢は映画と同じく色彩が無いと信じられたり、色つきの夢は狂人が見るものという説がまかり通ったりした。
フランシスの妄想は、(一般的にはフロイトが明らかにしたように)夢、空想、神経症の症状、さらには小説や映画のテクストと、その組成において基本的に異なるものではない。フランシスの“狂気”も物語にとってはたんなる口実――それも恰好の――である。表現とはそもそもストレートに語ることではなく、歪曲のうちに隠蔽しつつ、ある条件の下で可能性を汲み尽くすことであるからだ。外部の痕跡をたどって探偵が見かけとは異なる真実に達するように、フランシスの「内面」として仮構されたものもまた、症状として表出されたものの意味を読みとることによって明らかにされるはずである。私たちにゆだねられたのはまさにそうした作業であり、夢を外見上統一している不思議な筋書き、夢から覚めた人が無防備に他人に喋って面白がられる(あるいは退屈される)あの奇妙なシナリオから、夢分析はその本当の意味、当人にも自覚されない「潜在思考」を引き出す。フランシスの夢=妄想とは、そのようにして解読されるべきものではなかったか。この映画が作られて九十年以上が経つが、その作業はどうやらなされぬままであったようだ。
スクリーンの夢魔
むろん、映画と夢には大きな違いがあるのであり、映画が映画館の他の観客たちにも同時に見られているのに対し、
謎の解決は先送りされたものの、夜の窓にあらわれて、閉ざされた室内に入り込み、ベッドで眠る美女に近づく夢魔の黒い影――この原型的なイメージが、二十世紀の無意識のスクリーンに忘れ難く刻印されたことだけは確かなようだ。種村季弘はその若書きの映画論で美女と野獣(ここでは美女を攫う野獣)のテーマについていささか荒っぽく総括する中で、「この種の物語の白眉といえば、やはり『モルグ街の殺人』にとどめをさす。大都会の場末を月光を浴びながらさまよい歩く、孤独で兇暴なオランウータンと美女掠奪のテーマは、のちの『キングコング』、『コンガ』、『コンゴリラ』のような、摩天楼の彼方に全裸の美女を掠奪して消える反文明的な夢想の怪物を、つぎつぎにスクリーンに登場させる原型的発想となった」(「怪物のユートピア」)と記し、マリリン・モンローのイメージを使ったケネス・アンガーのコラージュ作品を経て、「巨大なロボットが金星か月のような世界の上で眠れる美女を抱きかかえて棒立ちになっている」アメリカのSF雑誌にまで説き及んでいるが、この、(脱線気味の)ポオ解釈にはじまる系譜の中に、われらが(通俗的に理解された)“眠り男”も位置づけられよう。この種のモチーフをめぐって、種村はさらに「狼人」との近縁性を主張して次のように述べる。
若き種村の面目躍如と言うべき風呂敷の広げ方で、奇怪なセットの切妻屋根や山道の尾根を美女を横抱きにして渡ってゆく(そして転落する)“眠り男”が入っていないのがむしろ不思議に思われるが、どう見ても濡れ衣のオランウータンはともかく、ここにハイド氏やドラキュラの名があるのは興味深い(そういえばブラム・ストーカーの原作では、ドラキュラも城の垂直の外壁を自在に這い降りている)。ホームズものの一つにも「這う人」というのがあったし、ハイドの毛深い手や体つきもそうだが、こうした先祖返り的形象には進化論というトピックが少なからず影を落してもいよう。しかし、ここで注目したいのはそうしたことではない。ほとんど強迫的にスクリーンに回帰してくることになったハイドやドラキュラ、彼らは本来、女を襲う能動的で攻撃的なヘテロセクシュアルの男性主体とは言い難く、にもかかわらずそう誤認されてきたという点で、チェザーレと共通するものがあるのである。
ドラキュラは、女を独占する、息子たちが打ち倒すべき〈恐しい父〉と見なされがちだが、ブラム・ストーカーの原作を読めば、ドラキュラが女吸血鬼と争い、彼女たちにからかわれながら、ジョナサン・ハーカーを懸命に己がものとしようとしていることがわかるだろう。かの伯爵は映画などで強調される、犠牲者を魅了する女蕩しからはほど遠く、女吸血鬼たちもドラキュラの情婦などではありえない。エレイン・ショウォールターは、『ドラキュラ』においてトランシルヴァニアとは「セクシュアリティが流動する地」であり、「ハーカーのトランシルヴァニアへの旅はレオとホリーのコールへの旅なのだ」と言っている。『洞窟の女王』(原題は“She”)のアフリカへの旅が、不死の女神を探しに行くかに見えて実はコールの洞窟の〈彼女〉を殺し、ホリーとレオが女にわずらわされずに生きる道を開くものであったように、トランシルヴァニアとは異性愛規範がゆるがされる「オリエント」であるのだ。(「オリエント」については『“父子愛”と囮としてのヘテロセクシュアル・プロット』(「コーラ」10号)の第三章でも書いた。)ロンドンに舞台が移ってからの、ドラキュラによって“淫乱”にされた女たちをホモソーシャルな男たちが救済/絶滅させる話とは一線を画す、トランシルヴァニアでのパートのたぶん最も重要な部分は、作者自身によって『ドラキュラ』の本篇から切り離され、歿後にストーカー夫人の手で短篇集に収められた「ドラキュラの客」である[☆4]。伯爵の城を訪ねる旅の途中、道に迷ったハーカーを狙った女吸血鬼は雷に打たれて焼死(誰の差し金かは明らかだ)、意識が混濁したまま雪の中に放置されたハーカーは、大きな狼にのしかかられ、喉をなめられていることに気づく(もともとドラキュラは「狼人」なのである)。救出に来た兵士たちによって「突き通っていない」と判断される喉の傷を負ったハーカーは、自分を招いた「ドラキュラ」(この固有名詞はストーカーの小説によって有名になったのだから、むろん彼はその正体を知る由もない)の指示による「神秘的な形の庇護の下」に置かれていたことを知るが、そこで彼を襲う深刻な心身の動揺に合理的説明が与えられているとは言い難い。物語はここで終っているが、このまま行けば、狼と伯爵の同一性が明かされ、雪原では未遂に終った行為がドラキュラの城で成就されるしかなかったろう。しかし、そうする代りに、ストーカーはこの部分を削除して、現在見られるような、ドラキュラに魅入られた罪ある女が滅び、無垢の女が救われ、ハーカーが幸福な結婚生活を送るというプロットを完成させたのである。
『ドラキュラ』にも二つながら出てくるように、そもそも催眠術と夢遊病は世紀末において人に知られた現象であった。ルーシーは夢遊病になってさまよい出ている間に吸血鬼となるのだし、ドラキュラも、ヴァンパイア・キラーのヴァン・ヘルシング博士も催眠術を使う。『ドラキュラ【完訳注釈版】』の註に見る通り、メスメリズムのいかがわしさを催眠術から払拭したのは、ヒステリーの女性患者に催眠術を施して劇的な発作を起こしてみせたシャルコーであった(フロイトがパリでこれを見学したのは有名な話だ)。フロイトは第一次大戦中に行なった一般向けの講演で、自らを理性的な主体と疑わない聴衆に対し、「夢遊状態」にされた人が、覚醒後、はじめは何も覚えていないと主張するにもかかわらず、催眠状態に置かれた間の出来事を思い出すという例を反証として挙げている。「彼は自分が知っていることを知らず、その出来事を知らないと信じていたのです。ところで、私たちが夢をみた人について推測した事実も、これとそっくりといえます」(『精神分析学入門』)。周知の通りフロイトは催眠療法を廃して自由連想法をはじめたが、医師への患者の惚れ込みが転移の結果であることを悟り、ひるがえって催眠暗示が治療効果を上げる際にもリビドーが働いていた(フロイトがパリで師事したベルネイムは知らなかった)ことに気づいた[懸田克躬の同書解説による]。
しかし、その名も「催眠術師とあやつり人形」という論考で種村が使っている、ヒステリー発作を起こす世紀末の女性患者が影をひそめたのち、催眠暗示にかかりやすいのは小市民となり、「表現派映画に登場するあのおびただしいあやつり人形たちは、かくてプレファシズム時代の小市民的現実の正確な反映にほかならなかったのである」とか、「ヒトラー以前に、ドイツ小市民はすでに夢遊病者だったのである」といった、クラカウアー(『カリガリからヒトラーへ』)写しのレトリックは煽りとしても感心しない[☆5]。種村は医師を装った男が女性患者に催眠暗示をかけたハイデルベルク事件を挙げ、また、「夢遊者の反犯罪」と題するエッセーでは、これは下って五十年代の話だが、男が男に催眠術をかけて銀行に押し入らせたコペンハーゲンの事件を紹介しているが(『失楽園測量地図』)、集団心理学もどきよりこうした個別的事象の方が、例としては適切であろう。いずれの場合も催眠術師は被施術者と性的関係を結んでいた。
フィギュア/分身
しかし、カリガリ博士とチェザーレは、上記のごとき「催眠術師とあやつり人形」の関係にある訳ではない。『カリガリ博士』の、社会的地位のある行ない澄ました紳士(医師)が実は犯罪者だったという表のストーリーは、『ジキル博士とハイド氏の奇妙な事件』のあからさまな流用であろう[☆6]。類似はそれだけにとどまらない。スティーヴンソンの小説の場合も、殺人を含むハイドへの疑惑は「表のストーリー」であり、「裏のストーリー」は伏せられている。いや、近年の研究を見ると、それは隠されていた訳では全くなく、『性のアナーキー』の著者エレイン・ショウォールターによれば、スティーヴンソンの周囲では暗黙の了解があった上、この小説が刊行されたのは英国で男性間の性行為を犯罪化する法律が施行されたのと同年同月(1886年1月)であり、冒頭に出てくる「ゆすり」という語は、それだけで当時の読者には同性愛を連想させうるものだったという(ちなみに、『性のアナーキー』のこの章は「ジキル博士のクローゼット」と題されている)。つまり、殺人という表面上の嫌疑の下に、当時ドイツでも英国でも実際に刑法に触れる犯罪であった同性愛の主題が潜んでいるという点も含めて、『カリガリ博士』は『ジキル博士とハイド氏』を“粉本”として使っている――つまり、ここには、『ジキル博士とハイド氏』をそういうものとして理解しえていた「作者」(あるいは作者たち)の意図が働いていたと思われるのだ。
スティーヴンソンの小説でハイドの“悪徳”の正体――女の子を踏みつけたり老紳士を殴り殺したりは、たまたま表面に出た事例であり、彼が夜中に出歩いて耽っていたらしい、恐るべき(と、ほのめかされる)“悪徳”が何かは語られない――は最後まで不明のままだが、カリガリ博士がチェザーレに殺人を教唆した直接の証拠も、実はない。見世物の許可を願い出たカリガリが役所で高圧的な役人に横柄な扱いを受ける、カリガリが市で見世物の口上を述べる、件の役人が殺された現場が映し出されるという三つのシークェンスをつなぐだけで偽の因果関係が生じ、カリガリが恨みからチェザーレを使って殺人を犯したと、私たちがたやすく信じてしまうだけだ。殺人の命令に限らず、カリガリ博士がチェザーレに何らかの具体的な悪事を指示する場面はもちろん、催眠術をかけるシーンすら存在しないのである。
それではカリガリは何をしているのか。
フランシスの回想の終り近く、彼が先頭に立って院長室に乗り込み、運び込まれたチェザーレの遺体を前に院長が錯乱するシーンがある。これを指してクラカウアーは、「フランシスは、院長に、その犯罪を認めさせるべく、彼の道具である夢遊病者の死体を見せた。この怪物はツェザーレが死んだと認めるや否や、荒れ狂いだした」と書いている。しかし、先入見のない目で見れば、これは殺人が露見したからではもとよりなく、愛する者を失った悲しみのあまりであろう。
これに先立つ、眠ったままの夢遊病患者として院長室に運ばれてきたチェザーレをはじめて見るシーンでの、彼の喜びようにしても、
チェザーレの遺体が見つかったからといって、連続殺人の犯人としての院長の正体が暴かれた訳ではない。それは彼の殺人への関与はもちろん、チェザーレのそれさえ証しはしない――フランシスの友人アラン殺害のシーンで私たちが見るのは、襲われたアランの恐怖の表情と壁に映った影ばかりである。「万事休すだ、カリガリ博士」と、遺体を運んできたフランシスは言うが、それは何を意味するのだろう。どういう意味で、彼はカリガリを追いつめたと思っているのだろう?
虚心に見るなら、院長室に踏み込んだ人々によって暴かれた院長の罪――人目をはばかるものであり、暴かれることで破滅に至るほどの行い――とは、チェザーレを手に入れた時にそうしていたような、同性に対する“愛”の行為としか思えない。チェザーレを手に入れ、衆人環視の中で――人払いをしても観客がいる――彼を愛撫する院長。もしチェザーレが美青年ではなく美少女であったなら、彼が何をしているかは一目でわかってしまっただろうに、女を男にするというただ一点の変更だけで、かくも大胆な行動に出ても観客(と検閲)は気がつくまいと製作者は思ったのであろうか[☆7]。
結論から先に言うなら、夢遊病者チェザーレとは、フランシスの潜在意識が生み出した、スクリーンに映る影さながらの分身である。チェザーレの行為はフランシスの「行動の射程の外で生じている」から、フランシスは彼のすることを他人事[ひとごと]としか思わずにいられる。といっても、チェザーレは、フランシスの“生き霊”として”恋敵”をベッドで刺殺した訳ではないし、女の窓から忍び込み、眠っている女に襲いかかって、失神した女を抱えて逃げる、フランシスの抑圧された欲望の代行者でもない。いや、確かに彼はフランシスの欲望のインカーネートしたものであるのだが、九十年ものあいだ、その欲望の性質は見誤られてきたのである。
傷口にしてナイフ
フロイトは論文「無気味なもの」でホフマンの『砂男』について論じながら、主人公ナタナエルが恋する自動人形オリンピアは、子供時代の彼の「父親に対する女性的態度を物質化したもの」であり、自己愛の投影であると述べている。人形を男に変えれば、それはそのまま、〈父〉(同性)に受動的に愛される男性主体という、本来の――そして男性主体にとっての最大のタブーである――形に戻るだろう。『カリガリ博士』でジェーンが誘拐された夜、箱の中にずっといたと思われていたチェザーレが、実はダミーの人形だったとわかるシーンがある。巧みに表の筋と関連づけられているが、これは伊達に人形とすり替えられる訳ではなく、むしろチェザーレが本質的に人形であることを表わしていよう。
『カリガリ博士』には、『砂男』のモチーフと、『ジキル博士とハイド氏』から採られたモチーフが、巧みに組み合わされている。前者から由来するものは二つあり、一つは主体によって否認された結果、“人形”として外在化、物質化された「父に対する女性的態度」、そしてもう一つは、伝承のキャラクターに投影された、人形を弄ぶ「悪い父」だ。フランシスが院長をカリガリだと思うのは、幼い頃、子供の眼をえぐり出す「砂男」だと信じていた恐しいコッペリウスが、眼鏡売りコッポラとして再来したとナタナエルが思うようなものである[☆8]。『砂男』では女の自動人形だったオリンピアが、『カリガリ』では青年の生き人形になっている。実はそれこそがオリンピアの正体なのだが。ナタナエルの幼年時のトラウマになったコッペリウスは、覗き見していた子供の眼に、「焔のなかから真っ赤に燃えた砂粒をつかみ出して」投げ入れようとした。ナタナエルの父の懇願によって眼だけは容赦した代り、彼はナタナエルの「肉体をがっきと鷲づかみにし、手足をねじ切ってそれをまたあちこち嵌め換え」た。要するに少年は人形として扱われたのである[☆9]。
スパランツァーニ教授の娘、実は自動人形オリンピアのガラスの目玉は、眼鏡売りコッポラが提供したものだった。二人は、かつていまわしいプロジェクトに携わっていたナタナエルの父とコッペリウスの反復である。カリガリ博士に連れられたチェザーレとは、スパランツァーニ教授に伴われたオリンピアであろう。スパランツァーニの娘ではなく息子としての自動人形。オリンピアが女であるのは文字通り形ばかりのことである。
『砂男』と『ジキル博士とハイド氏』を、ともに『カリガリ博士』の発想源と仮定するとき、両者に共通するのが“分身”のモチーフであることはたやすく見てとれよう。すでに述べたように『砂男』では、分身とは「〈父〉に愛される受動的な存在としての、主人公の分身」である。後者の場合は、少々複雑だ。表面上の筋では、院長=ジキル、カリガリ=ハイドのようだが、実は『カリガリ博士』においては、フランシスとチェザーレの分身関係こそが本質的であろうと思われるからだ。この場合、分身とは、「犯罪の実行者でないかと疑われる、主人公の分身」となる。つまり、チェザーレは、「犯罪の実行者」と「受動的な存在」を一人で受け持っている訳だ。
荒俣宏の『ホラー小説講義』には、種村季弘のいわゆる野獣による美女掠奪のテーマを思いきりエグく発展させたパルプ雑誌の表紙絵の数々が載っている。これだけまとめて見せられると、想像しうるかぎりの醜悪さ(と滑稽さ)をもって描かれた怪物(というより化け者。動物もいるし、ゾンビやミイラ男もいれば、修道僧、食人植物、怪しい中国人やマッド・サイエンティストもいる)たちが囚われの美女にさまざまに強要しているものが、単なる異性間性交の置き換えとはとても思えなくなってくる。何かされそうな気配に脅える客体として提示された彼女たちが、性別を越えた受動性の化身であることは誰にでもわかるだろう。荒俣は面白いことを言っている。「巨大な獣の手に掴まれた美女。/――このイメージにこそ、恐怖のあらゆる要素がたたみこまれている。わたしたちの心は、絶叫するだけしか身をまもる手段のない弱々しい美女にすぎない。恐怖は、ときに猛々しい野獣として、ときに甘美な性の誘いとして、さらに人知れず空気感染していく疫病としてわたしたちを掴みとめる。」
そして「ときに」は、「猛々しい野獣」は同時に「甘美な誘い」でもあるだろう――すでに触れたストーカーの短篇「ドラキュラの客」のの場合がまさしくそれで、そのとき犠牲者は「がっきと鷲づかみに」された子供さながら、絶対的な力に蹂躙されており(「ドラキュラの客」の主人公は「まるで巨人の手でがっしりと捕えられたかんじで」とか、「私はまたもや巨人に掴まれ、引きずられていくような気がした」[桂千穂訳]と語る)、しかも、「神秘的な形の庇護の下に」身を置いているとも感じている。「ドラキュラの客」はほとんど合理的に説明のつく話ではない。むろん、死後も生き続ける“不死者”を扱っているからというのではなく――実際、この主題はまだ明確に表われてはいない――「ミュンヘンを馬車で出発したとき、太陽は空にキラキラ輝き、大気は初夏の喜びにあふれていた」という書き出しが、数ページ後には「いまや雪はふかぶかとふりつもり、私のまわりに勢いよく渦巻いているので、ほとんど目をあけていられない」となる気候の激変、それ以前に馬車を返してしまうこと、馭者が降りて行くのを拒んだ谷間へ下って「何時間もそのあたりを時間とか距離の観念を忘れてさまよっていた」ことなど、ほとんど夢の中の出来事であり、語り手自身が「肉体的な悪夢」と呼ぶ、「全世界があたかも眠り込んでいるか、死んでいるかのように思える、空漠とした静寂」の中での、「私の上に横たわり、私の喉をなめている」獣との遭遇を実現させるための口実としか思えないからだ。ジョナサン・ハーカーのエロティックな受動性の夢は、刊行された『ドラキュラ』では、ドラキュラの城で女吸血鬼たちが彼にキスしかけた(これは婉曲な言い方)のに、激怒して割って入った老伯爵が、「この男は私のものだ」と宣言する場面にかろうじて残っている。「われは傷口にしてナイフ、犠牲者であり死刑執行人」(ボードレール)。「犯罪の実行者」は同時に「受動的な存在」でもあり、前者は「ときに」後者の夢想に他ならない[☆10]。
キャビネットの中の“悪徳”
『ジキル博士とハイド氏』の、明言されないハイドの悪徳が同性愛と考えられることはすでに述べたが、ショウォールターはジキルの友人で弁護士のアタスンについて、彼が「ハイドの謎の虜になったのは、おそらく自分自身の生活が抑圧と空想にどっぷりと浸かっていたためであろう」と言う。アタスンはジキルと(最初は彼の囲い者かと疑われた)ハイドの謎を追及し、最後にはジキルの執事プールと二人で、ジキルの書斎のドアを破って侵入することで、ジキルに戻れなくなっていたハイドを結果的に自殺に追い込む。ショウォールターに言わせると、アタスンは自らを厳しく律し、「空想的なものに怯え、無秩序な想像力の領域を怖れている」。しかし、それゆえ彼は、「顏のない人影がジキルが眠っているドアへ続くドアを開け、ベッドのカーテンを寄せ、ジキルを起き上がらせて彼の意のままにするレイプ幻想を見るようになる」のである。
杖と斧でドアを破ってジキルの書斎に入ったアタスンとプールは、直前に服毒自殺を遂げたハイドとキャビネットの中の姿見を発見する。ショウォールターは、姿見が見つかったことは彼らにとってそこにハイドがいたことに匹敵するショッキングな事実であり、「鏡は、ジキルのスキャンダラスにも男にあるまじきナルシシズムを明らかにするばかりでなく、同性愛を扱った文学において鏡を強迫的な象徴としてきた、仮面と「他者」の意味をも明らかにしている」と述べている。彼女によれば、アタスンはこの時、「彼自身の鏡に映った顏を、杖と斧でも粉砕できない酷く抑圧された欲望のイメージを見る」のである。「分身」の表向きの犯罪(殺人)を追求することが、キャビネットの中の秘密を暴き出す。カリガリ博士のキャビネット(ないしクローゼット)に隠されていた秘密もまたこの種のものであったと思われる(院長を追いつめたと信じて院長室に入ってきたフランシスの台詞は、(B)では「仮面を外せ、カリガリ博士」だ)。フランシスと医師たちが院長室を捜索するのは、アタスンとプールがジキルの部屋に押し入るのに相当し、そこで見つけるもの(まさにキャビネットの中から取り出される)は、アタスンがジキルの部屋で発見する遺書や、それに従って開封することになる書類と同様、秘密の告白である手記なのである。
ジキルとハイドをめぐる話は、カリガリとチェザーレの話とは違って(フィクションの水準では)紛れもない事実であるが、それをアタスンの妄想に変えた結果が、いわばフランシスというキャラクターであると言えよう。いや、『ジキル博士とハイド氏』にあっても、犯人の“悪徳”とは探偵の願望の投影に他ならなかった――事実であり、しかも投影なのだ。『ジキル博士とハイド氏』の長年にわたる映画化、TVドラマ化のうち、ただの一つも「この話をスティーヴンソンが書いたとおりに――つまり、、男同士の関係についての物語として描いたものはないのである」とショウォールターは言うが、『ジキル博士とハイド氏』の変形としての『カリガリ博士』は、それを実現しているのではないか? しかし、『カリガリ博士』と『ジキル博士とハイド氏』には大きな違いがある。後者では、あえてその名を言わぬ秘密は、ひたすらおぞましく、忌避されるべき、破滅と死を招く(実際、秘密を知ったラニョン博士は死に至っている)何ものかであった。ハイドに対して人々が理屈抜きの嫌悪と恐怖を示すことにそれは象徴されている。“悪徳”は明かされないものの、書斎の中で見つかったハイドの醜い死体として人目にさらされることになる。
だが、『カリガリ博士』では、扉の向うにいるのはハイドではなく、箱に入れられた美青年であり、フランシスの分身にしてカリガリの愛の対象である。
今や、「チェザーレ」の担う核心的な意味が、能動的な殺人者もしくは誘拐者としてのそれではなく、カリガリ博士に愛される、受動的、女性的な存在であることであるのは明らかであろう。ハイド氏の見かけ上の能動性、攻撃性にも、実は本質的な受動性、女性性が隠れていた。ゲイル・マーシャルは、男性的で暴力的に見えるハイドが、身体が小さい、神経質、ヒステリー発作を起こすといった、通常「女性的」と見なされる特質を示していることを指摘している。『宝島』とH・R・ハガードの『ソロモン王の宝窟』について論じながらマーシャルは、このような男性的な物語によって抑圧されたものの回帰こそハイドであると、『ジキル博士とハイド氏』は、「ジキルの、抑圧された先祖返り的性本能、女性化された本能の、ハイドというペルソナへの回帰」の探求であると述べる(“Victorian Fiction”)。言うまでもなく「女性性」とは女性に固有のものではなく、男が男になるために排除したもののことだ。恐らくハイドとは、ヘンリー・ジキルの肉体における女性性の抑えのきかない表出なのであろう。
しかし、父に愛される彼自身が少女人形の姿で現われたナタナエルと違い、ジキルの(否定された)女性性は、忌まわしく、病的なハイドに体現される。ジキルにとってハイドとは、父に認められない(ゆえに)醜い自分なのだ。彼は本物の父がいなくなった後に、父に代わって自分自身の父になっており、この父にハイドが息子として(あるいは息子がハイドとして)反抗しているのである。しかし、ジキルは父の価値観を内面化しており、父によって悪とされたものを自分の一部と認めることはけっしてできない。ハイド(になった時のジキル)は父から受け継いだ蔵書に冒涜の言葉を書き込み、父の手紙を焼き、父の肖像を傷つけている。ジキルの回想の中で、幼い彼は父と手をつないで歩いているが、ショウォールターに言わせると、これはジキルが「父権社会の規範と抑制を表わす」父の右手right hand、 すなわち「正しい手」を受け継いだことを意味する(「ハイドはまるでジキルの無気味な左手のようだ」と彼女は言う)。しかしジキルは現実には父になった訳ではなく、妻もなく、『ジキル博士とハイド氏』のロンドンは、〈愛〉のない独身者たちが秘密と抑圧を抱えて互いを訪問しあう灰色の世界なのである。
一方、ナタナエルやフランシスの場合、彼らが〈男〉になるために自らに禁じた、父(同性)から受動的に愛されたいという抑圧された願望は、自己の外に物質化され、二重人格ではなく二重身(しかし、瓜二つのドッペルゲンガーではないので、見たところそれと知られない)の形を取った。カリガリ博士が一人でいる時、チェザーレを愛撫しているというのは、(アタスンのそれにも似た)フランシスの妄想であり、欲望をチェザーレという人形に投射することではじめて見ることができた夢なのだ。その証拠に、拘束され、隔離室に入れられたフランシスは、彼がカリガリと信じている院長からチェザーレと同じように“愛撫”されると、穏やかな表情になって眠ってしまう。幼いナタナエルでさえ、最悪の瞬間には、炉にかがみ込んだ父親が「悪魔の顏」になり、いやらしい「コッペリウスそっくり」になったのを見たものだ。自らが「チェザーレ」であることを否認している時のフランシスは、院長を「カリガリ! カリガリ! カリガリ!」と呼んで糾弾し、あまっさえその首を締め上げようとした。フロイトによれば、ナタナエルは悪しき父コッペリウスの死を願うが、彼の場合、それは「コッペリウスのせいで死ぬ良い父親として実現されて」しまったのである。
ナタナエルの思い出の中の父は「パイプをくゆらしながら大きなグラスでビールを飲」み、「いろいろ不思議な物語を話してくれた」し、その際、パイプの火が消えてしまうと、「ぼくが火のついた紙を差し出してまた火をつけてやらなければならなかった」。結局のところ、「悪い父」に「肉体をがっきと鷲づかみに」され、受け身に蹂躙された記憶は、「不思議な物語」で頭をいっぱいにしたナタナエルの想像の産物(フランシスの妄想のような)であったのだろう。焔の上に身をかがめて怪しげな作業にふける父は、コッペリウスであったのだろう(院長がカリガリであるとフランシスが発見したように)。恐しいコッペリウスと愛してくれた父はついに統合されず、ナタナエルは悲劇的な最期を遂げるが、フランシスの場合は、「良い父」すなわち良い砂男の下で、彼は反抗を止め安らかな眠りを与えられた。彼はついに、自らがそうであることを否認し、そうなることを恐れていた、そして何よりもそうなりたいと思っていた「チェザーレ」になったのだ。
カリガリ博士の“罪”
それでは「カリガリ」とは何であるのか。すでに述べたように、「カリガリ博士」の(作中での)出典ははっきりしている。精神病院の院長と見世物小屋の香具師が同一人であることが発見された後、院長が別棟で眠っている間に、フランシスと彼に説得された医師たちは院長室の捜索をするが、そこで見つけた古い書物にカリガリについての記述が見つかる。このシークェンスは、眠る院長の映像が挿入されることで、それ自体が院長の悪夢のような印象を与える。実際、このあたりに(これ以前から)通常のリアリティはもはやない。医師たちの協力が得られるというのはありそうにないことだし、時間経過も不明である(これはいつ行なわれている捜索なのか?) いや、箱の中のチェザーレが人形と判明してカリガリが逃げ出した時、警官たちもその場にいたのに、カリガリを追って精神病院にたどり着いたのがフランシスだけというのがすでにおかしい。本と日記が院長の正体を明らかにしたちょうどその時、眠り男が谷底で死んでいたという報せが届いて、フランシスと医師たちは現場へ向かう。しかし、これは不可能な展開である。チェザーレを追跡した人々がフランシスの居場所を知るはずはないので、そもそもチェザーレの死体発見の報せがそこに届くなどということはありえない。
フランシスのケースは、フロイトが記述している、同性愛に対する男性の防衛機制の一つに酷似している。パラノイア患者とされた元判事シュレーバーの手記を検討したフロイトは、「私は彼を愛している」という文が、抑圧の結果、「私は彼を愛していない――私は彼を憎んでいる――私が彼を憎むのは彼が私を迫害しているからだ」と変形されて、自分が入院している精神病院の院長シュレヒジッヒ博士から迫害されているというパラノイアックな妄想を患者が抱くことになったと解釈した(『著作集』9)。しかも、その迫害とは、自分の身体が〈神〉=シュレヒジッヒによって女性化されている――〈神〉によって女にされ、愛人にされてしまう――というものだったのである[☆11]。
件の本を開くと、「夢遊病者」というタイトルや、「ウプサラ大学 1726年」という出版元や出版年の表示が見える。医者の一人が「これは院長の特別研究だ」と言う中、フランシスは次々とページを繰る。「The Cabinet of Dr.Caligari」という章が現われ、すでに述べたようなカリガリとチェザーレについての文章が読み取れる。さらに院長の日記――(A)では「臨床記録」――が発見されると、待ち望んだ夢遊病者をついに病院に迎えた日のことが記されており、院長の喜びのさま(日記の内容)が映像として示される。
本で読んだ「カリガリ博士」の話に魅了された院長が、夢遊病の患者を手に入れ、市に見世物小屋を出してカリガリ博士になりきって連続殺人を行なっていたというのが、フランシスの妄想の表の筋である(チェザーレを迎えて喜ぶ院長の映像とは、言うまでもなくフランシスの空想だ)。この時はじめて見つけたように描かれているが、すでに知っていた物語を院長に投影したというのが、本来の順序であろう。「カリガリ博士」なる人物はフランシス以外の人々にも伝説として知られている――生きた人間としては実在しなくても外部の情報としては存在する。つまり、作品内の現実世界では、「カリガリ博士」とは「砂男」のようなもの、つまり、誰でも知っている伝承のキャラクターであるようだ。だからこそ院長は、「彼は私を伝説のカリガリ博士だと思っている。これで彼を治せることがわかった」と断言しえたのである。
しかし、院長の知っているカリガリとは、夢遊病者を使った連続殺人犯であり、それ以上のものではない。なぜなら、院長は、私たちと一緒にフランシスの回想としての映画を見てきた訳ではないからだ。「院長はカリガリ博士だ」とフランシスが叫ぶ時、彼は、院長は“カリガリ博士の罪”を犯していると言っている訳だが、その罪とは何であろう。殺人とは表向きのそれに過ぎず、カリガリの隠された――いや、実のところ隠されてなどいないのだが――罪はすでに見た通りである。院長はまだ知らないが、「彼がカリガリだ」とフランシスが言う時、その妄想の中での“カリガリ博士の罪”とは、男の患者を受動的な存在として“愛する”ことなのである。
ところで、院長は本当に「知らない」のだろうか。知っている――それも、観客以上に――のではないか? イタリアが舞台であることの意味については註3でも触れたが、書物の中に見出される原カリガリとチェザーレの旅する世界は、フランシスを惹きつける「オリエント性」をそなえているのであろう。彼が妄想の中で見出した本として私たちに提示されるものは、自己検閲されている(彼自身に対して、また実際の検閲に対して)のではあるまいか。歴史上のカリガリは貴種流離譚の主人公で、修道僧くずれの医師、錬金術師、魔術師であり(ちょっとユルスナルの小説の主人公のようだ)、ゴシック・ロマンス的背景を持つ、今は見世物で日銭を稼ぐ流れ者だが、夢遊病者と称する若者を伴侶としており、男色を疑われた――くらいの設定が少なくともあったのではないか(そうであればこそ、院長は確信を持ってフランシスの妄想を見抜けたと断言できたのではないか)。もしそうなら、院長から観客へ向けられる眼差しは、そのような「削除部分」をも含めて読み取れと要請していると言えよう。
長尺版(B)で、フランシスは医師たちに「あんたたちは僕を狂人だと思っているだろうが、本当の狂人は院長なのだ」と主張する。
院長=カリガリ博士
院長=狂人
フランシスはそう言っている訳だが、彼にとって「カリガリ博士」とは「“カリガリ博士の罪”を犯している者」のことなのだから、これは要するに、彼が「狂人」と呼んでいるのは、通常そう呼ばれている者のことではなくて、「“カリガリ博士の罪”を犯している者」だということだ。フランシスは、「“カリガリ博士の罪”を犯している者は自分ではない、院長だ」と訴えているのである。
「あんたたちは僕を狂人だと思っているだろうが、本当の狂人は院長なのだ」というフランシスの台詞はそのまま、「あんたたちは僕を同性愛者だと思っているだろうが、本当の同性愛者は院長なのだ」と読みかえられる。そうであれば、この映画で(少なくともフランシスの妄想の中で)病気ないし狂気とされている者とは同性愛者であり、狂気とはその言いかえであるということになる。
フランシスが知らなかったのは、彼の妄想の中で「本当の狂人は院長」であったとしても、彼もまた「狂人」だったということだ。彼はそれをどのように抑圧したのか。その事情は彼の夢=妄想に隠されて/表われている。そこにうかがわれる「実際に起こった事件」について、次章では映画の初めに戻って、表面にあらわれているものに注目しながら検討することにしよう。
註
☆1 『カリガリ博士』について、このことはかねてから誤解されてきた。オリジナル脚本は「衝撃的」だったのに、監督が枠物語に変えたためにそれが損われたかのように言われてきた。「なぜこんなふうにしたかというと、オットー・フリードリッヒによれば、はじめの物語ではあまりに時代との相似性がなまなましすぎるからで、ヴィーネはそれを避けるために、はじめの物語をそっくり狂人の話という枠組にはめこんで、この映画が時代を批判しているのだという責任を逃れたのだという」(海野弘「暗箱のなかの都市」)。しかし、こうした見方は浅薄なものであり、「はじめの物語をそっくり」「はめこんだ」というのも、「時代との相似性」も、「時代を批判」も、ジークフリート・クラカウアーが言い出したガセネタだ。オリジナル脚本が「衝撃的」だったとはとうてい考えられないことを含め、これについては後述する。「箱の中に閉じ込められているはずのツェザーレは箱を抜け出して街に出没して殺人を重ねる」(海野)――しかし、「箱」の外にあるのはなおも映画であり、それを現実の「街」と混同し、映画内での「妄想」と「現実」の関係を見ない結果が、映画が映画館の外の街を反映しておりカリガリがヒトラーにまで発展したという、クラカウアーが言い立てた目的論的でアナクロニックな認識である。
☆2 原題がDas Cabinetであってドイツ語Das Kabinettでないのは、『ワイマール映画研究』の著者田中雄次によれば、「ドイツ語が本来持っている意味のほかに、英語、フランス語が含み持つ意味も込められていると見ることができる」、つまり、チェザーレが入っている「箱」、見世物が行なわれる「賭け小屋」、部屋、診察室、戸棚等を意味しえているのだという。
☆3 「はしがき」で述べたようにこの設定には異同があるが、北イタリアであることは変わらない。なぜ、イタリアなのだろう?(脚本家の一人がカリガリというイタリア人名をスタンダールの書簡集で見つけた時はまだ偶然に過ぎなかった。)荒俣宏は、『オトラント城奇譚』以来の、英国のゴシック・ロマンスについてこう書いている。「オリエンタルを含めた異国的なものへの憧れは、早くもウォルポールの『オトラント城』にさえ潜んでいた。かれは、『オトラント城』の舞台を、イギリスではなくイタリアに求めたし、ラドクリフやマチュー・ルイスやマチューリンのゴシック小説もまた、イギリスだけの舞台に満足などしなかった」(『ホラー小説講義』強調は原著者)。マチュー・ルイスの『マンク』下巻「月報10」で、荒俣は英国へのドイツ文学紹介者、翻訳者としてのルイスについて書いているが(“「マンク」とドイツ的情熱”)、逆にホフマンの『悪魔の霊薬』は『マンク』が粉本であるという(『マンク』上巻「月報9」石川実“「マンク」とドイツ恐怖小説”による)。修道僧(マンク)という伝説のカリガリの設定は、このようなインターテクスチュアリティの結果なのかもしれない。ホフマンにとってイタリアは特別な場所であり、この映画が明らかに“粉本”にしている『砂男』後半の重要登場人物コッポラとスパランツァーニは、名前からもわかるようにイタリア人である。なお、こうした理由から、本稿ではチェザーレという名をイタリア式の読みで表記した。
☆4 「ドラキュラの客」には『書物の王国12 吸血鬼』所収の桂千穂訳(短篇集『ドラキュラの客』も国書刊行会から出ている)と、『ドラキュラ』完訳詳注版の二種の邦訳があり、引用には日本語としてこなれていると思われる桂千穂訳を使った。なお、『ドラキュラの客』の訳者あとがきには、「ドラキュラの客」は未定稿であり、『ドラキュラ』人気にあやかろうと短篇集に入れられたもので本来なら収録を見合わせられるべきものだったとあるが、私たちは本文で述べた理由から断じてこれに賛同せず、「ドラキュラの客」は「夫の最高傑作とされる作品を愛する読者の方々には、興味深く思われることでしょう」と序文に記したフロレンス・ブラム・ストーカーの心情を文字通り受け取りたいと思う。「ドラキュラの客」は文学史上にそれだけがぽつんと残されていたとしたら未定稿かもしれないが、人口に膾炙した本篇『ドラキュラ』の存在が、今では「ドラキュラの客」を余すところなく理解できるものにしており、同時に、本篇から独立した一箇の佳品たらしめている。
☆5 60年代初出のこのエッセーで、種村は「『カリガリ博士』を頂点とするドイツ表現派映画に氾濫したあやつり人形たちに、のちにジークフリート・クラカウエルがナチス胎動の影を見たのはあまりにも有名だが」云々と述べている。“クラカウエル”の名は澁澤龍彦の著作にも散見され、『カリガリ博士』のリメイクであるアメリカ映画『怪人カリガリ博士』評でも、オリジナル版への言及はジョルジュ・サドゥール経由のクラカウアーに依拠している(「カリガリ博士あるいは精神分析のイロニー」『澁澤龍彦集成』7)。澁澤が『カリガリからヒトラーへ』を実際に読んでいないのは明らかで、オリジナルの『カリガリ』自体は以前見たきりで覚えていないにしても(戦後に見たと書いている。ちなみにクラカウアーは、ウィキぺディア英語版の“The Cabinet of Dr. Caligari”の項目によれば、執筆時を遡ること二十年前に見たきりだったらしい)、サドゥールを鵜呑みにして“「この映画がニューヨークで熱狂的に迎えられた原因は、一に公式主義との妥協にあった」と[サドゥールは]述べているが、卓見というべきであろう。”などと何の疑問も抱かないのは情けない。「そもそも芸術は危険な「無意味」を志向するものであり、「有意味」に終る芸術は、人道主義のお説教にすぎないことを誰もが知っている」なぞと書いているが、映画を「お説教」にしているのはクラカウアーである。映画評自体の趣旨は、夢と神経症と芸術を現実よりも上位に置こうとするものだから、およそクラカウアーとは相容れないというか、そもそも関係がない。つまり全く噛み合っていないのだが、しかし、彼らにとっても言及(参照ではないにしても)すべき権威の位置をクラカウアーが占めていたことをうかがわせる記述ではある。
☆6 周知の通りこの小説は繰り返し映画化されているが、『カリガリ博士』が公開された1920年には、チェザーレを演じたコンラート・ファイトの主演によるF・W・ムルナウ監督作品も公開されている(現存せず)。また、ファイトは、世界で初めて明示的な同性愛者を描いたと言われる、マグヌス・ヒルシュフェルト博士肝煎りのプロパガンダ映画『他の人たちと違って』(“Anders als die Andern”)の主演者でもあるが、これも1919年の作である。『他の人たちと違って』については後述する。
☆7 『カリガリ博士』を誰が作ったかについては、必ずしも明確でない入り組んだ話がある(詳しくは第三章で扱う)。脚本家としてクレジットされた二人組による最初のシナリオはひどいもので、フリッツ・ラングが手直ししたと伝えられるが(最初に予定されていた監督もラングであった)、回想形式の枠物語に改悪されたとクラカウアーが中傷し、長いことそれが事実のように言われてきた。しかし、実際に見ればわかるとおり、これは枠物語であることをも含め、間然するところのない脚本である。観客に解決をゆだねたこの筋書きを作ったのはラングなのだろうか? 最終的にはラングに代って撮ることになったヴィーネの意向が反映されての演出だったと想像されるが、真相を知る手立てはない。いずれにしても私たちの関心は(当然のことながら)作家の無意識の秘密や創造の源にではなく、非人称の装置としての映画が今なお生産し続けている“意味”にある。
☆8 ホフマンの影響についてはつとに指摘されてきたようだ。『カリガリ博士』のオリジナル脚本をクラカウアーは「E・T・A・ホフマンの精神をうけついだこの恐怖物語」と呼ぶが、むろん書いているものを見れば何もわかっていないことは明らかだ。田中雄次は『カリガリ博士』について「夢遊病者や自動人形やドッペルゲンガーといった特異な世界を創造したロマン派の作家、とりわけホフマンの影響が認められる」と言い、『砂男』の名まで出しながら、「二重性」の例をあげようとして、「『砂男』に登場する弁護士コッペリウスと眼鏡売りのコッポラは同一人物である。砂男はあるときは子供の眼をえぐりとり、あるときは生命のない物体にすぎない眼鏡を生きた眼に変えるのである」と無意味な記述をしている。また、本国で公開された翌年に逸早く『カリガリ博士』を見た谷崎潤一郎と佐藤春夫もホフマンの名を出しており、佐藤は「話の筋は、観てゐ乍ら考へたことだが、アマデス・ホフマンの「砂売」と云ふ奴に大分似てゐる」と書いている[『佐藤春夫全集』19巻。「砂売」とは「砂男」のフランスでの呼び名]。いったいどういう点についてそう「考へた」のかは興味のあるところだ。
☆9 大人になったナタナエルが、ふたたび自分が人形でしかないのを悟った瞬間――スパランツァーニ教授にガラスの目玉を投げつけられた瞬間――その「肉体をがっきと鷲づかみに」するものは狂気である――「この瞬間、ナタナエルは狂気の灼きつくような鈎爪にがっしとばかりつかまれた」。「フイ――フイ――フイ――火の輪よ――火の輪――火の輪は回れ(...)」と言いながら、彼は教授の首を締め上げる――「カリガリ! カリガリ! カリガリ!」と叫びながらフランシスが院長の首を締めるように。「大勢がよってたかって床に転がして縛り上げ、ようやく狂人を押え込むのに成功した。(...)こうしてむごたらしい狂気のうちに暴れ回りながら彼は精神病院に運ばれて行ったのである。」フランシスが取り押えられて隔離室に入れられるのと全く同じ展開と言えよう。
☆10 『ドラキュラ』の起源であり、核心である、実際に見た夢の中の台詞だという「この男は私のものだ」という文句を、ストーカーは創作ノートに繰り返し書きつけている。ロンドンでドラキュラの標的にされる女たちは、その後、自らドラキュラに襲われることを夢見る〈女〉(=受動性の化身〉として、男性の異性愛的ファンタジーの登場人物になりはしたが、ハーカーがそうであるような夢見る主体ではない。
二 夢の仕事
アラン
『カリガリ博士』は明確な(夢と幻想が混じり合ったりしない)、かつ巧みな枠物語である。冬枯れの庭とおぼしき場所で、青年フランシスが老人と二人でベンチに腰を下ろしており、後者が焦点の合わない目を見開いたまま、「われわれを取り巻いている霊に憑かれたために、私は健康も妻子のいる家庭も失ってしまった」と話すところからフィルムははじまる。美しい若い女が小道の奥から白衣をまとった幽霊のように近づいてきて、彼らの前を通り過ぎるのを目で追いながら、「僕の婚約者だ」と青年は口走る。女は彼らには目もくれず宙を見つめて行ってしまう。
すでにここだけで、出てきた三人がひとり残らずまともではないことが了解される演出である。もっとも、彼女と自分が経験したのは老人の話したのよりずっと恐しい出来事だと言って青年が語り出すと、観客はその内容に引き込まれて――夢見る人が夢であることを自覚しながら、いつしかそれを忘れるように――彼が「信用できない語り手」でありうることをすみやかに忘れてしまうだろう。
だからこそ、チェザーレの死体を見せられた院長が傍の医師に食ってかかって取り押えられ、拘束衣を着せられて、隔離室らしき場所に連れ込まれてベッドに寝かされ、なおも暴れるうちに扉が閉まり、扉の手前に立つフランシスをしばしキャメラが映した後、冒頭の庭に戻って、フランシスが老人に「その日から彼は狂人として鎖に繋がれたままだ」と語り終え、二人が立ち上がって場面が切り替わった直後、そこが回想に出てきた本当の精神病院の庭であることを知って私たちが受ける衝撃は大きい。回想の中では無人だった放射状の模様の広場が、今は異様な人々で一杯になっている。それぞれが抱える妄想に応じた身ぶりを繰り返す人たちの中に、フランシスの「婚約者」や、死んだはずのチェザーレがいる。チェザーレを見つけたフランシスは、彼に未来を尋ねると死ぬぞ、と言うが、チェザーレはどこか女性的な感じのする若い男で、白い花を大切そうに手にしている。「婚約者」は頭におもちゃのティアラを載き、玉座のような立派な椅子に掛けていて、フランシスが「愛してるよジェーン、いつ結婚してくれるんだい?」と話しかけても、あらぬ方向に目をそらし、「王族である私たちに勝手な真似は許されないわ」と言ったきり、ふたたび宙を凝視する。
この女性は「ジェーン」――この名前が明らかにされるのはこの時が初めてだ――でさえなかったのであり、フランシスが勝手に彼女を起用して回想シーンを作っていたのだ。チェザーレもまた「チェザーレ」ではない。女を襲って攫った怪物ではない。観客がそう悟ったところに、あのカリガリ博士までが建物の中から姿を見せる。いや、妄想の中のカリガリと違い、無帽の彼は髭を綺麗に剃り、髪も小ざっぱりと調えて、メガネも、その下でギョロギョロしていた目も、ホクロもシミもなく、温和な表情をした病院長だ。それまで偉そうに演説をしていた男性患者も、彼に声をかけられると挙手の礼で見送る。ここは、入院後のフランシスに、妄想のための材料としての役者たちを供給していた楽屋とも呼べそうな場所だったのだ。
しかし、そこに重要な役者がひとり欠けていることに観客は気づくだろう。「顕在夢」における連続殺人で二人目の犠牲者となった、フランシスの友人アランである。彼は精神病院にはいない――フランシスを除けば、彼が、ただ彼のみが過去において本当に存在したのであり、また、彼のみが本当に死んだのだ。フランシスの恋人ないし婚約者(どちらの呼び名も、妄想の中でさえ正しくない)すら存在しなかったのにアランは存在する。アランが――映画のはじまりの方で殺されて姿を消す友人が――かくも重要な人物であることに、観客はもっと驚いてよいのではないか。もとより彼は、カリガリ博士に操られた夢遊病者チェザーレに殺されたのではない。そんな事件はけっして起こらなかったのであり、本当にあったことが変形されたのがあのシーンなのである。それは本当に起こったことを見えなくしていると同時に、真実へ至る唯一の通路なのだ。もう一度言うが、私たちはフランシスの回想(=妄想)としてスクリーンに提示されたものを頼りに、「本当に起こったこと」に迫らなければならないのである。
「友達のアランだ」という字幕(フランシスによる傍の老人への、そしてむろん観客への紹介)とともにアランは現われる。明るい室内で立ったまま本を読んでいるアラン。彼は本を読みながら歩き回り、中央に置かれた椅子の、梯子のように高い――デザインも梯子に似て、伏せた細い半月状の横木が数本、水平に渡っている――背もたれの上に腕を置いてよりかかりながら読み続け、本から顔を上げて高窓に視線を移し、窓辺へ歩み寄りながら本をテーブルに置く。窓の内側の壁の厚みに手をかけて外を覗き、笑顔を見せて振り向くと、
愛情をこめてアランに向けられたこの眼差しを覚えておこう。冒頭の庭で「僕の婚約者だ」と呼ばれた若い女は、けっしてこのように遇されることはなかった。回想の中で名指されることもなければ、このあとフランシスの部屋を訪ねたアランが、途中で受け取った市のチラシを示して熱心に誘う時の、じゃれ合うような仲の良さに匹敵するものが、彼女とフランシスの間に生じることもない。アランはフランシスの肩に抱きつくようにして腕を引っぱり、「フランシス、一緒に市へ行こう」と、回想の中での最初の台詞を口にする(つまり、字幕が入る。これで語り手の名がフランシスであることがわかる)。字幕から元の画面に戻った時も、アランはフランシスの腕を引っぱっており、フランシスは笑顔でチラシを見ている。二人は笑いながら顔を見合わせ、なおもしばらくじゃれ合っている。
回想の中のアランとフランシスの名は登場とほぼ同時に提示されるのに対し、「婚約者」(実際はその設定はない)が終始、〈彼女〉としか呼ばれていないことに、もう一度注意を促しておきたい。なぜなら、市からの帰り道、二人が〈彼女〉に出会って、三人で歩きながら話をする短いショットのあと、ふたたび二人きりになった時、いささか唐突にフランシスは、「アラン、僕達は二人とも彼女を愛している。どちらを選ぶかは彼女に任せよう。だが、どういう結果になったとしても僕達は友達でいよう」と、回想の中での彼のはじめての台詞を発するが、たぶん過去においてそのような事実はなく、このままの台詞が二人のあいだで交わされたことは無かったと思われるからだ。そもそも彼らがともに「愛している」女は全く存在しなかった。そう推定できるのは、〈彼女〉の登場自体がたんにこの台詞の口実であったと思われ、この台詞以外にフランシスの〈彼女〉への特別な感情はうかがわれず、むろん、言葉による表明も(最初と最後の精神病院の庭以外では)一切無く、一貫して親密さを、台詞よりもむしろ映像で示される、彼とアランの関係とは対照的であるからだ。ここでは二人をライヴァル関係にする〈女〉を、たんに形式的に提示できればそれでよかったのだろう。アランはフランシスの手を取り、二人は握手を交わして別れる[☆12]。
しかし、この台詞一つで、観客はフランシスの愛情の対象を誤認することになる。これは驚くほど効果的なカムフラージュであって、男二人の親密さは忘れられ、たいていの場合、〈彼女〉をめぐる恋敵、カリガリの犠牲者の一人としてしかアランは記憶されず、記述されない。このあとに語られる「顕在夢」もまた、アランを排除してジェーンを所有したいというフランシスの欲望が、言葉とは裏腹にチェザーレという形を取ってアランを襲ったものだと解釈されることになるだろう。夜行する“夢魔”としての分身=影のイメージが、影の本体(夢見る者/語り手)がフランシスであることを示唆するように思えるからだ。しかし、事件は本当に、口実として導入された〈彼女〉への欲望から起きたように描かれているだろうか?
「Night」―夜―という字幕が示され、ベッドで眠るアランに壁に映った影が忍び寄り、目覚めたアランは恐怖の表情を浮かべる。影が刃物らしきものを振りかざし、抵抗するアランの両手をつかみ、最後は襟首をつかんで締め上げながら刃物を振り下ろす瞬間までが、シルエットとして示される。
翌朝、アランの死を知り、警察へ赴いたフランシスは、アランが殺害されていた状況について説明しているらしく、喉を押え、刃物を振り下ろす身ぶりをする。二人の警官は、何かに憑かれたようなフランシスの後ろで顔を見合わせるが、フランシスは「私はこの恐しい犯罪を解決するまで休みはしない!」と言い放つ。警官の一人がいったん部屋を出て行き、上司らしいマントの男を連れて戻ってくるまでの間も、三人が何やら話し合い出しても、フランシスは異様な表情で正面を向いたままだ。
フランシスの身ぶりは、壁に映るシルエットだけの殺人者によって、アランがまさにそうやって殺されたことを私たちが見たばかりであるからいっそう異様であるのだが、これは別に彼が犯人であってアランを襲った時の動作を強迫的に反復しているという訳ではないだろう。これは、アランは何者かによってこのように殺された――フランシス自身によってではなく、理由なき連続殺人以外の何らかの原因や手段によってではなしに――と確認しようとする身ぶり、すなわち彼がアランを殺した(象徴的に)ことの否認、その激烈な行動化なのである。彼は実際、拘束衣を着せられ、隔離室に入れられて、院長の手に触れられるまで「休みはしない」だろう。その時、「この恐しい犯罪」はどのように解決されていたか? そもそも、そのように変形される前の「恐しい犯罪」の本来の姿とは、いったいどのようなものであったのか。アランはどうして/どうやって死んだのか。フランシスの妄想に覆い隠され、その部分を復元することは難しい。しかし、直接表現されないものも、夢(妄想)という迂路を通って形をとるのであり、それがこの映画では、市で二人の青年が入ってゆく、カリガリ博士の見世物小屋でのシーンとして上演されているのである。
チェザーレ
見世物小屋のシーンは、明るすぎるライトのように強烈な情動で充たされている。これは、「本当にあったこと」――表には直接あらわれていないそれ――が圧倒的な力を振るっているからだ。情動においてはリアルで、昼の光のように鮮烈だが、そもそもこの出来事は現実の――現実にあった(ありうる)――ものなのだろうか。ウィキペディアの「カリガリ博士」の項には、見世物小屋で「アランが悪戯心で自分の寿命を尋ねた」(強調は引用者)とあるが、本当だろうか。むしろアランは、何かに突き動かされるように、強迫的に質問しているように見える。そしてフランシスは、それを懸命に止めようとしているではないか。
とはいえ、そこで起こることの現実性は、一見、疑う余地がないように思われる。これが一場の夢だという、また、夢と同じようにかたちづくられた妄想であるなどという可能性は、見ている観客の胸を一瞬たりともかすめはしないだろう。逆に、回想が終ってそれまでの話がフランシスの妄想であるとひとたび判明してしまえば、公然と妄想であるとされたものの現実性をあらためて問題にする者は誰もいまい。
しかし、そこで、見世物小屋での挿話として語られているものこそ、『カリガリ博士』の核心にある事件なのだ。フランシスが自分にすら隠している出来事、アランの死の原因になり、ひいては彼に正気を失わせるにまで至る何かがそこで起こったのである。フランシス自身の検閲のため元の形は見きわめられないが、それでもなおそこに戻って、何が起こっているかを確かめてみよう。
――さあお立会い。当年二十三になる夢遊病者チェザーレのお目見え!
――二十三年間、昼も夜も眠り続けてきた驚異のチェザーレ!
――今日、チェザーレがその死のような眠りから目覚めるのを見られるよ。さあ、お立会い......
カリガリ博士の口上に惹かれたらしいアランが、気の進まない様子のフランシスを連れ込むようにして見世物小屋に入って行く。舞台の幕が上がり、カリガリ博士が、直立した箱の観音開きの扉を左右に開くと、中には絵姿と同じ、目の下に隈取りをし、黒く塗られた唇の男が立ったまま眠っている。
カリガリ博士は男に呼びかける。「チェザーレ! 私の声が聞こえるか? 私――カリガリ博士――お前の支配者が命じる! お前の暗夜から目覚めよ......」
目覚めたチェザーレはそのまま前に歩み出て、舞台の縁まで来て立ち止まる。客席では他の観客とともに、フランシスとアランがこの光景を見つめている。アランは特に目を奪われているようだ。カリガリ博士は客席に向かって、「夢遊病者チェザーレはあなたが知りたいあらゆる質問に答えることができる。チェザーレはあらゆる秘密を知っている。過去を知り、未来を見通す」と言う。
するとアランが、不意に、懸命に制止しようとするフランシスを振り切って、チェザーレとカリガリ博士の立つ舞台に近寄って、傍でうろたえるフランシスを尻目に「僕はどれだけ生きられる?」と訊いてしまう。チェザーレは「夜明けまで」と答え、アランは衝撃を受けた様子で、虚脱したように笑い出す。傍のフランシスはしばし呆然としているが、灰色の墓石やがてアランをいたわりながら二人でその場を去る。
ここで重要なのは、まず、アランが積極的に天幕に入ろうとしており、予言を聞きたがったのもアランであり、フランシスはそれを止めようとしていることだ。そもそも市に誘ったのもアランである。ここには、「起こったこと」はアランが進んで招き寄せたものであり、自分のせいではない(と思いたい)という、フランシスの潜在的思考が表われていよう。
次に、アランが質問をする場面での彼ら二人の振舞いの不自然さだ。アランはなぜ、むきになってそんなことを聞きたがったのか。また、フランシスはなぜそんなに必死になって止めたのか。たかが市の余興ではないか。アランが何を訊くのか、前もって知っていた訳でもないのに。
いや、彼は知っていたのだ――「夜明けまで」という答えもむろん知っていた。考えてみればあたりまえのことである。全ては起こってしまったのであり、アランは彼のせいで夜明けが来る前に死んだのであり、フランシスは取り返しのつかない過去を、本来の姿のままでは近づけないほど自分から切り離されてしまった事件を、別な形で想起しているのである。だからこそ、フランシスは、懸命にその実現を阻止しようと(同時に、自分の関与を否定しようと)しているのだ。
ここで使われているのは、夢におけるのと同様の置き換えの手法に他ならない。アランの質問は何か別のものであり、チェザーレの答えも別のものであって、それに付随する情動だけが本物、すなわち過去において本当に体験されたものであったのだ。精神病院で回想される過去の世界にカリガリはいなかった(アランの死後、フランシスが入院してから、院長を素材に捏造した人物だった)。当然、カリガリ博士の見世物などというものも実際にはなかった。アランの質問もチェザーレの予言もなかった。そしてチェザーレもジェーンも、病院にうわつらだけのモデルがいるのみの存在なのだから、現実の過去の世界にいたのはフランシスとアランだけである。「カリガリ博士のキャビネット」にいたのもフランシスとアランだけであり、アランが質問し、チェザーレが答えるとは、実際に交わされた(そしてアランの死の原因を作った )フランシスとアランの会話がそのように偽装されているのである[☆13]。
チェザーレが、フランシスの抑圧された願望が形を取った分身と考えられることはすでに述べた。アランとフランシスが入って行った「カリガリ博士のキャビネット」とは、いわばフランシスの頭の中であり、であればチェザーレがあらゆる秘密を――むろんこれはフランシスのあらゆる秘密である――知っているのは当然であろう。見世物小屋での出来事は、彼ら二人のあいだに起こった、強い情動を伴った別のことの置き換えなのだ。二十三年間眠り続けたチェザーレが今日目覚めるとは、これまでの全人生でフランシスが抑圧してきたものが明らかになるという意味であろう。アランは訊いてはいけないことを訊き、チェザーレ(つまりフランシスの代理人)は言ってはならないこと、つまり、言えばアランの死を招くようなことを言ってしまったのである。「夜明けまでしか生きられない」とは、その発言がもたらした「結果」を端的に表現するものであった。見世物小屋での問答という見かけに隠された出来事とは、おおよそこのようなものだったと考えられる。
モンタージュ
見世物小屋での挿話のあと、場面は夕方の広場に移り、他の通行人たちと一緒にフランシスとアランが連れ立ってやって来る。(A)ではこの後すぐにジェーンが現われるが、(B)では、二人は、殺人事件の情報提供に千マルクの賞金が懸けられたポスターが貼られているのを見つける。アランは一瞬にして表情をこわばらせ、ポスターに見入った後、ひどく不安げな顔でフランシスを見返る。フランシスは脅えるアランの手首を握る。
アランのこの反応は、彼の不安を殺人事件に前もって結びつけようとする印象操作に他ならない(同時に、二人の親しさを駄目押し的に強調しもする)。回想のはじまりからここまでは、実はアランとフランシスについての話とカリガリの話がカットバックされて、両者にことさら関連があるかのように見せている。わざわざ小間切れにしてつなぎあわせているのである。
回想シーンはそもそもカリガリの登場からはじまっていた。正確には、立ち並ぶ市の天幕のセットが映され、ベンチで語るフランシスと傍の老人が一瞬映ったあと、「彼だ!」という字幕が入って、帽子の下のぼさぼさの白髪と髭、丸いメガネの小柄な老人が登場し、見世物小屋の列の前を杖を突いてゆっくり通り過ぎる。この直後に、すでに述べた、「友人のアランだ」の字幕に続いての、アランの登場となるのである。これに続く流れを順に書き出してみよう。
(1)街路に出たアランがチラシを受け取り、フランシスを訪ねて市に誘う。
(2)老人が役所に見世物の許可を申請しようとして、忙しい役人に横柄に扱われる(この時、彼が出す名刺で、老人が「カリガリ博士」であることが判る)。
(3)カリガリ博士が市の入口の、オルガンと猿の見世物の前を通り過ぎる。
(4)自分の見世物小屋の前で口上を述べ、客寄せをするカリガリ博士。
(5)「その夜から奇怪な連続殺人が始まった」という字幕。
山高帽にマントの刑事と制服警官二人が、縦に置かれたベッドを覗き込んでいるショット。
「町役場の職員は鋭利な刃物の一刺しで殺されていた」という字幕。
(6)(3)と全く同じ構図で、同じ見世物の前をフランシスとアランが通り過ぎる。
(7)カリガリ博士が客寄せをしているところに、フランシスとアランがやって来る。
(2)〜(5)はカリガリを連続殺人に結びつける操作であるが、時系列が少なからず混乱しており、「あらすじ」を作ろうとする者たちを途惑わせ、彼らは多かれ少なかれ、話を適当に刈り込んだり、つけ加えたりして辻褄を合わせている。そもそもアランを連続殺人の第二の犠牲者に見せるつもりなら、(1)を最初に持ってくるのはうまいやり方ではあるまい。市役所での出来事の結果 横柄な役人が殺されたとしたいのなら、(5)はむしろ(2)の直後に置くべきだろう。わかりにくさを避けるには、カリガリ博士が町にやって来る→役場で邪険な扱いを受ける→役人が殺されるというプロセスを提示したあとに、アランとフランシスを登場させれば問題ないはずである(実際、たいていの「あらすじ」はそのように書かれるか、役所での出来事をあとから説明してカリガリの犯行を暗示するかしている)。(3)と(6)では同じ背景の前(舞台のようにキャメラは固定されたまま動かない)を、カリガリとアランがそれぞれ左から右へ通り過ぎるが、これが同じ日に起こったことなのか、それとも何日も続いた(続いたとして)市の別の一日に起こったことなのか、観客には知りようがない。
しかし、過去に存在したものとして回想されているのは、実はアランとフランシスが市に出かけた一日だけであり、全てはその日に起こったのである。過去の世界にカリガリは存在しないのだから、彼らがカリガリ博士の見世物小屋に入ることも、まして予言を聞くこともあったはずがない。確実にあったと言えるのは(1)と(6)だけであり、それ以外のことは多かれ少なかれ、圧縮と置き換えによって変形されている。チラシやポスター、本や日記のページといった文字のインサートは、本当にあったものの想起(引用)の可能性が高い。殺人事件はあるいは実際にあったかもしれないが(夢=妄想に取り込まれて連続殺人を形成したかもしれないが)、アランの死に直接関係はないと思われる。
夜のあいだにアランが殺されるシーンについてはすでに述べた。翌朝フランシスは、アランの家政婦らしい中年女性の訪問を受け、アランが殺されたと聞いて部屋に駆けつける。フランシスが下手から部屋に入ってきた時、画面右端に縦に置かれたベッドは、この部屋が最初に映された時よりは多くフレームに入っているものの、役人の時と同じく、遺体は見えない。しかし、フランシスには見えたらしく、不意に帽子を取り落す。しばらく身を震わせていた彼は突然顔を上げ、「夢遊病者の予言だ!」と言う。
このシーンは、ベッドの向きや、遺体を直接見せない点で(5)の反復であり、二つの殺人の連続性(連続殺人の可能性)を視覚的にも示すものだ。むろん、このわかりやすさは囮である。このシーンの本当の手がかりは、部屋の奥、ベッドヘッドの傍にさりげなく――しかし、フランシスを左に配し、遺体はフレームの外だから実は画面の中央に――置かれた、例の高い背もたれを持つ椅子である。
ジェーンの誘拐は完全なダミーであり、チェザーレに代行されるフランシスの欲望をヘテロセクシュアルなそれに見せかけるものであり、「顕在夢」のクライマックスを形作るものであり、広く流通しているイメージでもある(だが、真のクライマックスはすでに述べた見世物小屋でのシーンであろう)。これに先立ち、フランシスがジェーンの父オルセン博士の協力を得て、カリガリ博士とチェザーレの住まいである箱型の馬車を調べる挿話がある。先に述べたような警察での出来事のあと、警察署の階段をよろよろと降りてきたフランシスが片腕で顔を覆って泣き出すシーンに続いて、彼はアラン殺害をジェーンの家に報せに行き、話を聞いたオルセン博士から「私がその夢遊病者を調べるために警察から許可を貰おう」と言われる(たぶんこれも全部無かったことで、オルセン博士の娘は実在したかもしれないが、フランシスともアランとも恋仲ではあるまい。オルセン博士にフランシスの言い分がまともに受け取られたかもあやしいものだ)。とまれオルセンとフランシスはカリガリのもとへ向かうが、合い間には、事件を模倣した殺人未遂犯逮捕の話が挿入される。これも小間切れだが、しかしこちらはまぎれもなく並行して起こっている。二人はカリガリを追求し、チェザーレを目覚めさせるよう迫って押し問答になるが、そこへ「犯人逮捕」の号外を持った男がやって来たのでその場を去る。
このすぐあと、「彼女は父の帰りが遅いのを不安に思っていた」という字幕と、自宅の居間で父の帰りを待ちわびるジェーンのショットが入り、フランシスとオルセン博士が警察で容疑者の取り調べに立ち会っているシーンに変わる。いかにも悪党づらの髭の容疑者は、自分は例の事件に便乗しようとしたに過ぎず、前の二つの殺人とは無関係だと主張する。再びジェーンの姿が映り、彼女は人のいなくなった市の会場にやって来る。カリガリ博士の天幕の前まで来ると中からカリガリ博士が出てきて、ジェーンは父のことを尋ねるが、カリガリは彼女を招き入れ、直立した箱の中のチェザーレを示し、彼に目を開けさせたので、ジェーンは脅えて逃げ出す。
これは要するに、あとで誘拐された時にジェーンが犯人をチェザーレだったと証言できるよう、前もってチェザーレを見せておいたのである(表の筋では逆でチェザーレに彼女を見せたということになろうが)。「葬儀の後――」という字幕が入り、墓地の門らしきところから、フランシス、ジェーン、オルセン博士の三人が出てくる。たぶんこれは本当にあったことだ――アランは本当に死んだのだから。そしてこれは正気のフランシスが出てくる最後のシーンでもある。このあとはもう、ジェーンを攫ったチェザーレを操っていると彼が信じるカリガリを追って、フランシスは精神病院に至る――現に自分がいる場所へ戻ってくるだけなのだから。
夜
ジェーンが攫われるのに先立って、「Night again...」―ふたたび夜―という字幕が挿入され、人気のない夜の市へ入って行くフランシスの姿が映る。フランシスはカリガリ博士の見世物小屋を覗くが、誰もいなかったらしく、今度は家馬車のところにやって来て窓から様子を窺う。馬車の中には椅子に掛けたカリガリ博士と、横たえられ、蓋が開かれた状態の箱の中で眠るチェザーレが見える。
寝室で眠るジェーンのショット。彼女の家の外の塀に貼りつくようにして、チェザーレが戸口から家の中へ入り込む。ジェーンの窓にチェザーレが現われ、ガラスを破って侵入する。そしてジェーンの枕許に忍び寄り、刃物を振りかざす。だが、寝顔を見つめるうちに刃物を取り落し、そのまま見入っているとジェーンが目を覚ます。
黒く塗られた唇で歯をむき出してチェザーレは笑い、悲鳴を上げるジェーンを抱え上げて、窓から外へ逃げようとする。オルセン博士や使用人たちが目を覚まし、皆はジェーンが連れ去られた後の寝室にやって来て、窓が割られているのに気づく。割られた窓から外を見た人々は、ぐったりしたジェーンを抱えて屋根の上を逃げてゆくチェザーレを見る。
ここで、フランシス視点でカリガリと箱の中のチェザーレを見た、窓越しのショットが入る。後でわかるが、このチェザーレはダミー人形なのである。一方、人々はジェーンを抱えたチェザーレを追って行き、町外れの山道らしきところで、チェザーレは追いつかれそうになってジェーンをその場に放置して逃げる。オルセン博士らは彼女を連れ帰り、他の者たちはそのままチェザーレを追う。
山の中でよろめいて倒れ、谷間へ転げ落ちるチェザーレ。
カリガリの馬車を覗くフランシスのショット。一晩中何もなかったのを確かめたフランシスはジェーンの家へ向かうが、そこでは連れ帰られたジェーンがオルセン博士に介抱されていた。われに返ったジェーンは、「チェザーレ!」と叫ぶ。フランシスは、「チェザーレのはずがない。僕は彼が箱の中で眠っているのを何時間も見張っていた」と言うが、ジェーンは譲らない。フランシスは外へ出て行き、それを見送ったジェーンとオルセン博士は顔を見合わせる。
警察署に行って模倣犯が独房につながれていることを確かめたフランシスは、例のマントの刑事と警官二人とともに、ふたたびカリガリ博士の馬車を訪ねる。カリガリの懇願を振り切って、彼らはチェザーレの入った箱を外に運び出す。フランシスが箱の中のチェザーレを抱え上げ、それが人形であると判った瞬間、カリガリ博士はその場から走って逃げ出す。
「夜」――それはアラン殺害に先立って挿入された字幕に他ならず、「ふたたび夜」とは、第一の夜が逃れ難く強迫的に繰り返されることを意味するものであろう。それはまた、二つの夜の同一性をも、異なる二つのものに見えながらそうでないことをも表わすだろう。
最初の犠牲者はアランであった。今回狙われたのは〈彼女〉である。フランシスの欲望、第一の夜では殺しという形でしか表現できなかった欲望が、ここでは〈女〉というダミーを得て、明示的に性的な意味を帯びるに至った。窓を破って侵入し、横たわる女にナイフを振り上げるチェザーレとは、(当時のコードでは直接的に描くことを許されなかった)性的攻撃の暗喩でもあろう。しかし、それに先立つアランへの攻撃もまたそうだったのであり、私たちが見せられた、影と、恐怖の表情と、抵抗する手と、乱れるシーツと、どぎつい照明によって演じられた息づまる光景もまた、(文字通り)一種のベッド・シーンに他ならなかったことを、私たちは遡行的に理解された原光景のように知る。
〈夜〉とは、昼のあいだは抑えられていた欲望があらわれ出る時であり、灰色の墓石に押えつけられていた蓋が開いて、伏せられていた真実が立ち上がる時だ。語り手の悪夢こそが箱の中に眠るものであり、それは夜行する分身として本質的に〈夜〉のものなのだ。それが動き出さないよう、フランシスは眠らずに馬車の窓から一晩中見張っていたのだが、悪夢はダミーを置いて彼の知らないところで欲望を実行していたのである。「夜」と「ふたたび夜」との間にあった隔たりは消え、二つの夜は同じものとなり、第一の夜が明らかにしえなかったものを、真実の追求という表向きの意図に潜んだ彼の欲望――〈女〉への欲望に偽装されたアランへの欲望――を、隠蔽しつつあらわにする。
チェザーレがジェーンを誘拐するシーンの合い間にカリガリの映像が挿入されれば、観客はカリガリがチェザーレを操っていることの示唆として受け取るだろう。しかし、チェザーレが傍の箱の中にいるためそれは成り立たなかった。箱の中身が人形と判明してわかったこと、それは、一晩中眠らずにチェザーレを操り、チェザーレに己が欲望を代行させていたのは、分身としてのチェザーレを〈夜〉の中に解き放っていたのは、カリガリでなくフランシスだったということだ。チェザーレが箱の中にとどまっているのをこの目で確認し続けていたというのはフランシス自身のアリバイであり、フランシスがジェーンに「チェザーレのはずがない! 僕は彼が箱の中で眠っているのを何時間も見張っていた」と言うのは、「僕のはずがない!」と言っているのだ。しかしそれはフランシスなのである。
見世物小屋での問答に変形された「本当にあったこと」とは何であったか。たぶん、アランは、フランシスを市に誘って、そこで彼への愛を告白したのであろう。それこそ、チェザーレに置き換えられたフランシスに対し、アランがしてはならなかった質問否ステイトメントであり、フランシスはそれに対して、「お前は死ぬしかない」と言うに等しい答えを返してしまったのだろう。
それというのも、「質問」はフランシスがそれまで――二十三年間――隠し続けていた「秘密」にかかわるものであったからだ。ありていに言えば、フランシスもまたアランと同じ欲望を持っていた。フランシスもアランを愛していた。だからこそ、それを否認する必要があった。
アランはその夜、自ら命を断ったと思われる。ジキル博士のキャビネットの中で見つかった鏡のように、「カリガリ博士のキャビネット」の中で起こった出来事もまた、フランシスに彼自身の、鏡に映った顏を見せてしまった。そこから連れ出してくれるかもしれない者こそアランだったのに、その愛を拒み、あまっさえ彼を死に追いやってしまった。こうしてフランシスは、あまりに辛い真実を意識下に葬って、許されないもう一つの顏を持つ邪悪な父カリガリに院長を仕立て上げ(その意味では、彼は院長にも自分を投影しており、院長もまた別な意味で彼の分身なのだ)、そのカリガリがチェザーレを使ってアランを殺したと信ずるに至ったのだろう。
ナタナエル
これまで見てきたように、フランシスの“ケース”は、フロイトのシュレーバー症例や、同じく同性愛からの防衛としての他の症例の分析との共通性を持っている。入院したフランシスは、院長が患者である自分を〈女〉にしようとしているという妄想を抱き、また、院長(フランシスから見れば「カリガリ博士」に同一化した狂人)は彼にとって、運命を見通す支配者=神=父をも意味することになった。アランの死が自分のせいであり、愛する者を自らの手で殺したに等しいことにフランシスは堪えられなかった。カリガリに全ての責任があり、夢遊病者に予言させた通りにアランを殺させた、いや、むしろ、彼が運命を最初から握っていてアランの死は避けられなかったと信じることによってのみ、フランシスはその苦しみから逃れられたのだ。フランシスは患者たちに向かって、「愚か者たちよ この男は僕たちの運命を操っている!(You fools, this man is plotting our doom!)僕たちの命は夜明けまでだ」と言い、「彼がカリガリだ!」と叫んで院長につかみかかる。plottingしている――妄想の筋書きを作っている――のはカリガリではなく、彼自身――カリガリに操られているチェザーレからジェーンを救い、院長の仮面を剥いだ、異性愛のヒーローとしての自分を生きることで、アランを死なせた罪と自身の女性化をともに回避しようとする彼自身――なのだが。
フランシスの妄想は、フロイトがシュレーバーの手記に見出したのと同様の、「私が彼を愛している」という命題の否定として読み解ける。つまり、最初の命題は「私は彼を愛していない――私は彼を憎んでいる――それは彼が私を迫害するからだ」と変形され、院長と同一視されたカリガリ博士に固着した「迫害妄想」を形成するに至ったのだ。彼とアランには共通の知り合いである〈彼女〉がいて、三角関係だったという作り話も、註12で指摘した、同性愛に対する防衛としての「嫉妬妄想」のヴァリエーションとして理解できる。「私がアランを愛しているのではない――〈彼女〉がアランを愛しているのだ」および「アランは私を愛しているのではない――アランは〈彼女〉を愛しているのだ」という認識は、「私はアランを愛している」/「アランは私を愛している」という二つの命題の否認の結果生じたのである。
入院したフランシスは、父親のような院長に対して転移を起こし、伝説のカリガリ博士と彼の伴侶のチェザーレという素材を使って、院長の意のままにされたいという自分自身の欲望を、同じ患者である女性的な若い男に投影した。「院長に〈女〉のように受動的に愛されているのは自分ではなく、すでに女性的な彼である。だから自分はまだ〈女〉にされてはいないのだ」という、受動性の否認と外在化である。ここでフランシスとアランの「友情」を危うくした要素が、そのままカリガリ博士の“悪徳”に、また、カリガリ博士とチェザーレの関係に置き換えられているのに注目されたい。回想の中の「友情」は、かくして無傷のまま保たれ、〈彼女〉をめぐるライヴァル関係という偽の問題を介在させることで真の問題は忘れられ、死を予言されて不安がるアランをいたわり、友達でいようと誓った場面ばかりが事実として思い出され、フランシスにとってアランは純粋にその死を悲しんだ「友達」のままでいられるのである。
前述したようにフランシスが院長をカリガリ博士と思い込んだというのは、『砂男』の主人公ナタナエルがコッペリウスを砂男だと思ったようなものである。幼年時のナタナエルは、深夜、コッペリウスと父が怪しげな実験にふけるところを覗き見る――「そこら中にいくつも人間の顏が見えるようだった。だが、どの顏もどの顏も眼がないのだ――眼のあるべきところに気持の悪い真っ黒な穴がぽっかりあいているのだ」。ナタナエルがカーテンの後ろからかいまみた男二人による〈原光景〉は、女を交えずに人間を造り出そうとする呪われた所業であった。「眼をよこせ、目玉をよこせえ!」というコッペリウスの声にナタナエルは悲鳴を上げて倒れる。
大人になったナタナエルに、呪われた二人組はスパランツァーニ教授と眼鏡売りのコッポラとして再来する。スパランツァーニの娘という触れ込みのオリンピアに結婚を申し込もうとして、彼は二人の“父”の喧嘩のシーンに遭遇する。「まるっきり話が違うじゃないか――目玉は、目玉はおれが作ったんだ――ゼンマイ仕掛を作ったのはこっちだ。」二人は「女の形をしたもの」を奪い合っており、ついに実験用のガラス器具の並ぶ机の上にコッポラが教授を投げ飛ばす。「オリンピアのぶざまにだらんと垂れ下がった両足」を、木の階段の縁にガタンガタンとぶつけながら、眼鏡売りは木でできている人形を持ち去るが、その顏に眼がなく、真っ黒な穴が二つあいているのをナタナエルは見てしまう。この黒い穴は――フロイトの言うような去勢象徴であると同時に―― 直接的には髑髏[しゃれこうべ]のうつろな眼窩であって、言うまでもなく死を意味する。
すでにスパランツァーニの舞踏会でオリンピアにダンスを申し込んで手を取った時、その氷のような冷たさに、ナタナエルは「むごたらしい死の悪寒にぞっと刺し貫かれ」(強調は引用者)ていた。さらに、「ナタナエルの燃える唇を迎えたのは氷のような唇ではないか!――オリンピアの冷たい手に触れた時、彼は腹の底からゾッとして、突然、死せる花嫁の伝説を思い浮べた」と、見紛いようもなく死が指し示されていたのだった。「それは死―あるいは死んだ女」(ネルヴァル)。見世物小屋の前でのカリガリの口上――「死のような眠りからチェザーレが目覚める」(B)――もこのヴァリエーションとして読める。
「コッペリウスめ――コッペリウスめが、生命より大切なわしの自動人形を盗みおったな。(...)ゼンマイ仕掛――言葉――動作――わしのものだ――目玉――目玉を盗った。呪われた――地獄の亡者め。」こうわめきちらしながらスパランツァーニは、コッペリウス(ママ)を追いかけるようナタナエルに言い、床の上からナタナエルを見つめていた二つの目玉を彼の胸に投げつける。眼のあるべきところに真っ黒な穴だけがあいた人形、血だらけの目玉――ナタナエルの目撃したのは、幼年時のオブセッションにまみれた彼自身の死体だったのである[☆14]。
フロイトも指摘するように、ここには「良い父」と「悪い父」がいる。『砂男』では、死んでしまう実父以外はおおむね「悪い父」であるが、フランシスの妄想の中のカリガリは、「悪い父」に見えて実は「良い父」だ。カリガリ博士は、乳母が幼いナタナエルに話した砂男のように、また砂男と同一視されたコッペリウスのように、熱せられた砂粒を子供の眼に入れたり、眠らない子供の眼を飛び出させて、血まみれの眼球を自分の巣へ運んだりしない。優しいその手でチェザーレを眠らせ、ついにはフランシスをも眠らすのである。
『カリガリ博士』、『砂男』、そして『ジキル博士とハイド氏』は、科学者(ないし魔術師)の実験による女性的/同性愛的分身の誕生という、共通したモチーフを持つ。『砂男』の場合は、機械工学技師(コッポラの前身コッペリウスは錬金術師)と言うべき二人の〈父〉が、女の人形(実は彼らの〈息子〉)としての主人公の分身を製作し、『ジキル博士とハイド氏』の場合は、医師であるジキル博士自身が、自ら調合した飲み薬で自分を作りかえる。つまり、自身を素材に、「“罪”=同性愛を平然と実行できる“悪”の分身」を作り出すが、この“悪”とは彼の中の「女性性」でもあった。そして『カリガリ博士』では、やはり医師であるカリガリ博士の生き人形としてのチェザーレの物語が語られ、実はそれは主人公の現状の投影=分身なのである。
澁澤龍彦は「悪魔の創造」(『思考の紋章学』所収)と題するエッセーで、『未来のイヴ』のエディソンと、『砂男』のスパランツァーニとコッポラ/コッペリウスを、「母の協力なしに娘(自動人形)を造っている、いずれも往古の連金術師めいた相貌の男たち」と呼び、これに、自動人形ではないが、幼い頃から毒を与えられて身体組織を変えられた「父によって造られた一種の人造人間、一種の人形」と言うべき娘たちを持つ『ラパチーニの娘』(ホーソン)のラパチーニと『毒の園』(ソログープ)の植物学者を加えて、「魔術師めいた父のイメージ」と呼んでいる。彼は、『砂男』の、人形を愛する青年と人形の同一性を指摘したフロイトに「まったく不服はないけれども、ただ、もう一つだけ、ここに父娘テーマを付け加えてほしかったと思っている。あえて言えば、父娘相姦のテーマである」と言う。
しかし、女の姿をした自動人形と青年の同一性が証明されたのであれば、これはむしろ「父子テーマ」と呼ぶべきではないか。「フロイトは現実生活で、まさに愛娘の父親という立場にあったから、ひょっとすると、このことを書くのに筆が鈍ったのではないかと勘ぐりたくなるほどである」と彼は書くが、私たちは澁澤に何も勘ぐる気はなくて、ただ、父娘萌えなので“父子”には気が回らなかったのだなと思うだけだ。だが、「人形を愛する者のナルシシズム的陶酔は、人形に対する狂気の恋愛によって破滅する青年の立場と、超絶的な力によって人形を支配する父の立場、この二つの立場を我がものとすることによって、初めて完全なものになるのではないかと私は思う」と言われると、少なくとも『砂男』は――そして『カリガリ』は――そうではあるまいと思えてくる[☆15]。
しばしば誤解されていることだが、『砂男』の“父たち”はナタナエルの対象選択[恋愛]に干渉して彼を操ろうとする訳ではない。父の愛(と迫害)の対象を、大人になった主人公は、最初、自分と関係のない〈父の娘〉と見誤り、カタストロフの中でそれが自分自身だったと知るのである。フランシスの場合も、カリガリの連れている“息子”チェザーレ(ここでは〈娘〉ではなく、はっきり男の人形)は、フランシスにとって、自分であることが意識されないままの、「女性的/同性愛的分身」の「物質化」なのである。
「オリンピアとマリア―ホフマンの『砂男』とフリッツ・ラングの『メトロポリス』」と題する論文で識名章喜は、澁澤同様、フロイトの「無気味なもの」を参照しつつ、コッペリウスに関節をはめ直されるナタナエルの語りを引用して、自動人形を「受動的存在の隠喩」であると指摘しながらも、「自らの不安と激情に翻弄されるまま主人公が人造美女オリンピアに求めたものは、他者としての女性ではなく自己の鏡像である」と、ナタナエルが対象としての女を求めそこなった(異性愛に失敗した)結果、自己の鏡像しか見出さなかったかのように論じている。しかし、フロイトが示唆するものは(「終りある分析と終りなき分析」を併せ読めばよりはっきりするが)、オリンピアが「美女」であるのは見せかけであり、父に対象として愛される(性的対象にされる)自己が女性の形を取っているに過ぎないということだ。ドラキュラについても触れたことだが、異性愛中心主義とホモフォビアが、ここでも視野を偏らせ、判断を誤らせている。ベクトルが全く逆なのであり、「父に対する女性的態度」とは男性のホモセクシュアルな欲望の一部なのである(ただし、最大の禁忌であるがゆえに至高の享楽――〈女〉の享楽――であると幻想されるものである以上、この欲望は普遍的なものであり、その欲望を持つ主体は「男性同性愛者」に限られる訳ではない)[☆16]。
註
☆12 ここでもまたフロイトの記述が有効であろう。同性愛衝動に対する「防衛策」としての「妄想的な嫉妬」において、「僕は彼を愛している」の否認の結果生じるフレーズはこうだ――「僕が彼を愛してるんじゃない、彼女が彼を愛しているんだ!」(強調は引用者による)(“On Psychopathology”「嫉妬、パラノイア、同性愛に関する二、三の神経症的機制について」)
☆13 見世物小屋には他にも大勢の客が入っていたようだが、「大勢の人」というのは「類型夢」の一つであるから、その意味はフロイト博士に訊いてみるといいかもしれない――「夢の中で「たくさんの他人」に会うのが何を意味するかご存知ですか。たとえば裸の夢などではしばしばそういうことが起こって実に恥ずかしい思いをしますね。その意味するところは他でもない――秘密ということです。つまりそれは反対のものによって表現されているのです」(『著作集』6「隠蔽記憶について」)
☆14 このスパランツァーニの台詞についてフロイトが、「眼鏡売りがナタナエルの目玉を盗んでオリンピアにはめ込んだという(…)スパランツァーニの申し立て」と書いているのを、フロイトの思い違いであり、ナタナエルの目玉は無事で、ここでスパランツァーニは、ゼンマイ仕掛の人形はコッポラに盗られたがこっちは相手の作った目玉を盗ってやったと言っているのだとマックス・ミルネールは指摘しており、これはその通りである。しかしフロイトの解釈も「精神分析学的に見れば正しい」というミルネールの議論にはここでは立ち入らないことにする。ミルネールは、ナタナエルからでなければこれらの目玉はどこから取ってこられたかという点に拘泥しているが、ここで重要なのは、ナタナエルに強迫的に取り憑いて離れないシーンが実現してしまったことであり、“父たち”の大喧嘩の結果、割れたガラスで負傷した(「血が噴水のように勢いよく噴き出した」)スパランツァーニの血が偶然付着したにすぎない目玉(彼が「怪我をしていないほうの手で」それをナタナエルに投げつけたと、ホフマンはわざわざ書いている)の与える心理的効果だけで、読者に対してもナタナエルに対しても十分であり、また、フロイトの言う「ナタナエルとオリンピアの同一性の証左」にもなりえており、何よりもこのスラップスティック的場面にふさわしい十分な馬鹿馬鹿しさがそなわっていると思われるからだ。
☆15 ヴィリエ・ド・リラダンの小説も別の意味でそうではない。「この恋人の肉体のみを忠実に模した魂のない人形は、エワルド卿の頭のなかだけで生まれた理想の女、幻想の女でしかなく、いかに科学の粋をこらしても、ついに「独身者の機械」以上のものではあり得なかったのだ」(「人形愛あるいはデカルト・コンプレックス」『幻想の画廊』所収)と澁澤は言うが、これはハダリーの「魂」たるソワナの存在を考慮に入れない議論(そうでないものはまず無い)である。ソワナの存在は“人造美女”が男の幻想の中で完結することを妨げる(それゆえ無視されてきた)ものであり、『未来のイヴ』を類書からはっきりと分けるものである。
☆16 識名はホフマンについて、「人造美女の関連で留意すべきは、人形愛の他に、二次元的な肖像や鏡像を通して恋に目覚めたり、憧れの女性への思いを深めたりする趣向の作品が実に多い点だろう」と言い、「アニメ・キャラに感情移入するアキバ系オタク」の情熱を引き合いに出して、「こういう「萌え」をドイツ・ロマン派で先駆けたのが他ならぬホフマンだったのではないか。人形を愛でる一八世紀の独身者の精神は、確実に秋葉原につながっている」と主張するが、これには全く賛成できない。男が受動性を自身のものとしては認められず、女という対象として確保せずにはいられないという点を考慮に入れていないからというだけではない。ロマン派の「美女」がしばしば人間ならざる化け物で、死と至高の愛と超越的な美と芸術に結びつき、破滅と隣り合わせであったのに対し、今日びの秋葉原にそんな心配は全くないからである。
三 同性愛映画?
プロパガンダ映画
『カリガリ博士』に先立つ1919年に公開された、チェザーレ役のコンラート・ファイト主演の映画がある。初上映時、性科学者のマグヌス・ヒルシュフェルト博士は次のように挨拶した。
これは『セルロイド・クローゼット』にあるヴィト・ルッソの引用から写したものだ。「戦前のベルリンで花開いた性的啓蒙の時代」が生んだ、ヒルシュフェルト率いる「最初のゲイ解放運動」について、ルッソは次のように書いている。
ルッソの記述からもわかるように、この時代を、クラカウアーがそう思わせたがっているような、ヒトラー出現の予兆に満ちた暗い抑圧された不安な時代と一概に呼ぶことはできない。むしろそれは帝政が終った後の新しい自由な時代であり、戦前(第一次大戦前)から、いや、前世紀から「科学人道委員会」を作って活動していたヒルシュフェルトも、だからこそこの時期(『カリガリ』が作られたのと同じ1919年)、「性科学研究所」を設立することができたのである。あとで引くようにこの映画についての感想を書き残しているクリストファー・イシャウッドや、W・H・オーデン、スティーヴン・スペンダーといった英国人にとって、「ベルリンはホモセクシャルの解放区のように見えた」(海野弘『ホモセクシャルの世界史』)。「ベルリンはホモセクシャルの自由を解放するとともに、一九ニ八年から一九三二年までの間に、英国の若い芸術家たちがベルリンに出かけ、政治に目覚め、労働者階級と連帯しようとした」(同)。『カリガリ博士』が作られたのはこれに先立つ、ヒトラーの影などまだどこにも差さぬ時期であった。だが、先の引用にもある通り、ドイツにおいて男性同性愛が刑法で罰せられる犯罪であったことも事実である(刑法175条は1871年に規定されて、実に東西ドイツ統一後の1994年に至るまで――実際の運用はともかく――存続した)。ファイト演じるヴァイオリニストは結局自殺するのだが、ルッソは彼を、その後映画の中で同じように同性愛者であるために死んだ者たちの點鬼簿に載せ、実際、ファイトの演じた役はスクリーンに登場した最初の同性愛者とされている。
「第三の性」という言葉に象徴されるように、ヒルシュフェルトの主張は同性愛者を一つの種族として認めよというものだった。イヴ・コゾフスキー・セジウィックの分類に従えば、同性愛の「マイノリティ化」(「普遍化」ではなしに)である。こう言っただけで、「生得説」とか「本質主義」とか「生物学的要因」とかいう言葉がいちどきに群らがり寄ってくることになる。その場合に生じる問題も、萌芽としてであれ、すでにこの時に出そろっているようだ。「第三の性」を「中間形態」と呼んだことでもわかるように、ヒルシュフェルトが想定した「同性愛者」とは男女の中間的存在であった。男であれば女性的、女であれば男性的ということになるが、実のところ、こうした言説の女性への適用は、男女の非対称性を隠蔽するものであり、ユングの「アニマ」「アニムス」概念と同種の眉唾である。「男性の身体に閉じ込められた女性の魂」というカール・ハインリヒ・ウルリクスの自己規定も、ヒルシュフェルトの「中間形態」も、それが前提とする“女性性”の本質化は、生物学的女性にとっては、女という身分の強化――よりいっそうそこに繋ぎとめられること――をしか意味しない。自分は完全に男だと主張して女性性を外在化するのも、自らのうちなる女性性をうっとり愛撫するのも、ともに男の特権であって、女にはこれに相当するものはない。
周知の通り、「科学が誤りに、正義が不正に、人類愛が人間の憎悪と無知に打ち勝つ日」の代りに、「まもなく」(1933年)やって来たのはナチス政権であった。同性愛者の「人種化」は、そのまま差別と排斥の理由になりえた。付け加えるなら、これは、ユダヤ人だけでなく同性愛者もまた収容所に送られたということではない。もともとユダヤ人は女性性及び同性愛と分かち難い観念連合の中にあったのである。
言うまでもなく、ナチスの政権掌握が映画界に与えた影響ははかり知れない。『カリガリ博士』の脚本の(その程度は不明ながら)事実上の作者だったかもしれないフリッツ・ラングはアメリカに渡り、そこで撮った『死刑執行人もまた死す』には、『カリガリ』でアランを演じたハンス・ハインリヒ・フォン・トワルドフスキーが敵役のナチス将校役で出ているし、妻がユダヤ人だったファイトも、亡命して英米の映画(『カサブランカ』ではナチスの少佐としてボギーに射殺される)に出演した。『カリガリ博士』の評価にもそれは影響を及ぼすことになった。『カリガリ』は『他の人たちとは違って』のようにフィルムを焼却されるような憂き目は見なかったにしても、戦後になってクラカウアーの妄説に利用されることになったのである。
『他の人たちとは違って』は、本質的には、麻薬中毒や売春について社会に訴えたり、妊娠中絶の権利を主張するといった、同時代の「啓蒙映画」のジャンルに属する作品であったようだ。「オスヴァルトの映画は、当時の、妊娠中絶、近親姦、性教育、性病を扱った映画と同様、プロパガンダの手法を用いており、ヒルシュフェルト自身も専門家として登場する」とルッソは言う。劇場だけでなく、映画の中でもヒルシュフェルトはスピーチした。イシャウッドの『クリストファーとその仲間たち』には、作家が実際に見たこの映画についての記述があり、ルッソはその一節を紹介している。
『他の人たちとは違って』は、現在では、発見された一部のフィルムから復元されたものがDVDになっていて、抜粋をYouTubeで見ることができた。一見して驚くのは(『セルロイド・クローゼット』に載ったスチール写真で見ていたとはいえ)、コンラート・ファイトの、『カリガリ』と同時期とはとても思えない老け方とやつれ方だ。社会的犠牲者としての同性愛者を描こうとしての演出ででもあるのだろうか、骸骨のように頬骨が浮き出して見え、最後の方は眼をギラギラさせ憔悴しきった芥川という感じで、自殺するまでもなく肺病か何かで息を引き取りそうである。著名なヴァイオリニストである彼に憧れて個人教授を受け、恋人になる若者も、どうしてこの男優を選んだのか首をひねらざるを得なかった(『カリガリ博士』において、主要な役を演じた俳優が、どれもこれ以外にはないと思われるのと対照的だ)。同性愛者をどうしても美しく描かなければならないという訳ではもちろんないが、同時代の映画で男女の恋人なら間違いなく美男美女に決まっているのに、彼らの恋愛を魅力的に見せる気が製作者になかったようなのは、要するに政治的な正しさとステレオタイプな説明以上のものを作る意図も手腕も持ちあわせなかったということだろうか[☆17]。
横たわる男と椅子
試みに、自殺したヴァイオリニストの遺体が背景に横たわっていたという先のシーンを、同様に「ファイトの遺体」を横たわらせての『カリガリ』の終りに近い一場面と、さらに、その変奏である二つのシーンと較べてみよう。ジェーンを攫う〈怪物〉のメーキャップを取ったファイトは、いずれのシーンでも美しい寝顔を見せている。
(一)運び込まれた担架の毛布をフランシスが剥ぎ取り、チェザーレの死体を院長に見せると、院長は驚愕の表情を浮かべて震えながら歩み寄り、チェザーレの死体に取りすがる。しかし、やがてゆっくりと顔を上げて、そばにいた医者の一人につかみかかり、取り押えられて拘束服を着せられる。フランシス一人が離れて立っているが、なおも暴れるカリガリと揉み合いながら全員が院長室の外へ移動してしまったので、手を差し伸べながら後を追い、チェザーレの死体だけが残される。この間、カメラは固定されたままで、チェザーレも(死体であるから当然だが)動かず、画面の手前に顏を向けたまま安らかな表情をしている。
(二)(一)は、チェザーレを手に入れた院長が、医師たちを部屋の外に追いやると、全身で押え切れない喜びをあらわし、笑みを浮かべながらチェザーレの首に腕を回し、胸に頬をよせたりするシーンである(二)に先行されている。院長はいったん机の方に駆け寄って、本を取り上げ、ページを繰りながら、ページとチェザーレの顔を交互に眺め、最後には本を二つに引き裂いて、もう一度チェザーレの頬をなでるようにして顔を抱える。チェザーレは車椅子のようなものに乗せられており、やはり人形のように安らかに目を閉じたまま動かない。
(三)フランシスが取り押えられ、回想(妄想)の中で「カリガリ博士」が連れて行かれたのと同じ隔離室に入れられると、院長は「カリガリ博士」がかけていたのと同じメガネを取り出して、フランシスを診察する[☆18]。フランシスは目を見張って院長の顏を注視し、脅えているようだが、「カリガリ博士」がチェザーレにしていたように、額や頬に触っていたわるように検分するうち、徐々に落ち着きを取り戻す(最後まで暴れていたカリガリとは対照的だ)。院長がそっと彼を横たわらせると、フランシスは目を閉じて眠りにつく。
ここまで“描かれて”いても、名づけられていなければわからなかったのである。『カリガリ博士』より『他の人たちとは違って』の方が公開は早かったかもしれないが、『カリガリ博士』は、少なくとも、“啓蒙”というエクスキューズ抜きのものとしては、「世界初の同性愛映画」であったと言えよう。『セルロイド・クローゼット』も、人目を騙しおおせた例としてこの映画を入れる(そしてチェザーレに扮したファイトの美しい写真を――別人のようなヴァイオニリスト役のではなく――載せる)べきであった。
それでも、本当に製作側にそのような意識があったのかと、なおも疑う人があるかもしれない。それならば、明らかに作者によって置かれたはっきりした手がかりをお教えしよう。上記(一)のシーンにそれは見出される。
(一)でチェザーレの遺体はスクリーンの下方に、頭を右に、顏を観客に向けて、台の上に横たわっている(台の頭の方がゆるやかに高くなっており、寝心地はよさそうである)。そして彼の後ろの右方に、背もたれの高い椅子がある。実は彼の遺体は、前にアランの部屋で、フランシスに帽子を取り落させながら、私たちには見せられなかった遺体の代りにそこにあるのだ。
あの時、アランのベッドの傍に置かれていた椅子を覚えておいでだろうか。後方に見えているのはあれと同じ椅子である(一輪挿しは無いが)。なんでアランの椅子が院長室に? この椅子は最初にアランが紹介された時にも、画面手前に大きく映っており(本を読みながらアランはその背もたれに腕を乗せたが、腰掛けはしなかった)、アランが本を置いて歩み寄る窓の下の机の前にも同じものがもう一脚あった。アランが殺されるシーンにも、翌朝フランシスが駆けつけた時にもあった、いわばアランの換喩である。後方では医師たちがカリガリを取り押えようとしているので観客の目はそこに集中するだろうが、この椅子は背景で起きていることに劣らず重要だ。回想の最初でアランが室内を歩き回っていた時も、私たちは当然のことながら紹介された彼ばかり見ていたが、固定されたキャメラは最初から最後まで(左手にアランが消えた後もしばらく)椅子を見つめていたのである、
折から――フランシスひとりが騒ぎを傍観する中――この椅子が、争っている男たちが接触したはずみにガタンと動く。それまでも院長室がスクリーンに収まる際、つねにこの椅子は映っていた。院長の机を中央に、骨格標本が左に立ち、椅子は右に立っていた。誰もそこに掛けたりはせず、客に勧める椅子とも思えず、オブジェか何かのようだった(それでも骨格標本の方が目立つし、傍には中から本や日記が見つかるキャビネットもあるから、当然、観客の注意はそちらに向かうだろう)。ストーリーからは外れて、それでも確かに存在した。染みのように視野の一部を占めていた。しかし、観客の視線はそれを通り抜けてしまっていた。
椅子が動いたのは、明らかに作者から観客への目配せである。ここに椅子があると。前にこれをどこで見たか思い出せと。
フランシスは思い出せない。目の前で起こっていることが他人事[ひとごと]としてしか感じられない。本来彼は、ここでカリガリに感情移入してしかるべきだったのである。愛の対象に死なれ、その遺体を目のあたりにしたカリガリに。それはかつてアランの部屋で起こったことの再現であったのだから。しかし彼は、自分の見ているものから解離しており――見世物小屋での予言の場面が強い情動を帯びていたのと対照的に――映画を見る人のように身じろぎもせず、何も感じることができない。愛する者の死によって錯乱し、取り押えられ、拘束衣を着せられて、連れて行かれるのは彼自身でもあったのに。ここまで熱心にカリガリを追ってきた彼は、その主張が全面的に認められて医師たちがカリガリを捕えようと奮闘するこの時、ひとり手出しをせずに見つめている。私は狂人ではない。院長が狂人なのだ。このあとフランシスは空しくそう主張することになるだろう。カリガリをようやく取り押えた男たちがもつれるようにして行ってしまうと、フランシスはしばしチェザーレと二人きりになる。
愛の対象を失った者としてフランシスはカリガリであり、チェザーレはアランである。そしてフランシスはチェザーレでもある。チェザーレはフランシスの分身であり、ナタナエルにとってのオリンピアであるからだ(だが、オリンピアの喜劇的かつ残酷な“死”と、この美しい死体の静謐さの隔たりは大きい)。ナタナエルと違って、フランシスは、自分がそこに死んで横たわっていることを知らない。だが、やがて、カリガリに替わって彼自身が拘束衣を着せられて横たわる時、彼はチェザーレに――“眠り男”に――なるだろう。受動性そのものとなり、人形のように愛撫されながら目を閉じるだろう。
アランの遺体は画面には映らなかった。フランシスと彼の場合には、その“意味”が隠されていたからである。カリガリとチェザーレの場合へ置き換えられて、隠された意味は文字通り目に見えるものとなり、フランシスがアランの部屋で見た血まみれの遺体でも、ナタナエルが見た無残に壊された人形としての彼自身でもない、欠けるところなき美しい人形として横たわる。同様に愛する者を失くした男が遺体の傍で嘆く構図とは言い条、『他の人たちと違って』の社会的偏見の哀れな犠牲者を示して寛大さと科学的認識を懇願するという憐れむべき単純さは、『カリガリ博士』の一シーンの持つ意味の重層性と豊かさに及ぶべくもない。
フランシスの狂気の原因はアランの死であった。そのことは直接的には明かされなかったが、チェザーレの死を知ったカリガリが直ちに狂気に陥ることで、見間違いようもなく示された。この後に控えるどんでん返しに先駆けて、単なるどんでん返し以上に手の込んだ仕掛けがここにはある。『カリガリ博士』なら見たという方ももう一度見直してみて頂きたい。九十年経ってもなお、椅子がひそやかな合図を送ってよこすのが見られるはずである。
一度も存在しなかった過去
クラカウアーは近年ようやく否定的に扱われるようになったらしいが、脚本家の一人であるヤノヴィッツの愚にもつかない内輪話を、「このように私は、今まで知られないでいた真の内幕話の上に『カリガリ博士』に対する私の解釈を基礎づけることができるのである」と得々と引用するような男が主張した、「集団心理学」なるものに目を曇らされてきた人たちに同情する気にはなれない。この著者は、スクリーンにあらわれているものを見るよりも、自分で勝手に(では実はなく、時代のドクサに合わせて)作った筋書きに映画をあてはめることに熱心だった。クラカウアーの“『カリガリ』はヒトラーの予兆だった”説は、早い話が、発表時点に近い過去の重要な政治的歴史的事件――第二次世界大戦やナチスの支配――についての「政治的に正しく見える意見」を、それ以前の作品にアナクロニックに投影したものである[☆19]。
『カリガリ博士』の脚本家としてクレジットされているハンス・ヤノヴィッツとカール・マイヤーの最初の構想と称して、現行のストーリーから最初と最後を省いただけの、つまり院長が殺人者のカリガリと同一人物である狂人と判明して監禁されるまでのあらすじを紹介した後で、クラカウアーは、「E・T・A・ホフマンの精神をうけついだこの恐怖物語は、明らかに革命的なストーリーであった」と脚本家たちを賞賛し、最初予定されていたラングに替わって監督になったヴィーネがプロローグとエピローグを加えて回想形式にしたせいで、オリジナル脚本の革命性が失われたと非難している。「オリジナル・ストーリーが権威の本質的な狂気を暴露したのに対して、ヴィーネの『カリガリ博士』は、権威を讃美し、その狂気の反対者を罪に陥し入れていた。革命的な意味をもった映画は、このようにして従来の型にはまった映画となってしまった――正常だがやっかいな個人を気が狂っていると宣告し、精神病院に送りこんでしまうという使い古された型に従いながら。」
「革命」という語は、その後、価値をすっかり下落させてしまったが(「心の東京革命」という気持ち悪い言葉があるくらいだ)、政治犯を精神病院に送り込むというのは今でもありうることだ。だが、ヴィーネが「権威を讃美し」ているとまで言われると、誰でも首をかしげるのではないか。しかも、それが、「商業主義映画」が「大衆の欲望に応えることを要請されている」ことにヴィーネが「本能的に服従」したためであるとか(最初の脚本がつまらなかっただけだろう)、変更前の脚本は「インテリの特徴的な感情を表現して」いたのに、変更後は、「インテリよりも教養の低い者たちが感じたり好んでいるものと調和をとることを想定した映画にすぎなくなっていた」とか(クラカウアーの頭には調和しなかったとみえる――複雑すぎて)、「たとえ、『カリガリ博士』が従来の形式にとらわれた映画になってしまったにせよ、この作品は、革命的な意味をもつストーリー――ある狂人の空想として――を保存し、強調していた」とか、オリジナル・ストーリーを回想形式という「一つの箱の中へ入れることによって」、大戦後のドイツ人一般の外界からの「引きこもりをより忠実に反映」させることになったとか、「ドイツ人は革命的な行動から遠ざかってしまった。しかも同時に、心理的革命は、集合的魂の奥底で準備されたように思われる。映画は、カリガリの権威が勝利を収めた現実を、同じ権威が打倒された幻覚と一緒にすることによって、ドイツ人の生活の二面性を反映している」とか言われては、訳の生硬さは別にしても、どうやらこれは映画の冒頭でフランシスに語りかけていた老人の話に劣らぬたわごとではないかと思えてこよう。
しかし、語るに落ちるクラカウアーの供述からは、彼の思惑を越えた別の情報が読み取れる。ヤノヴィッツが、実際に起こったレイプ殺人から想像をたくましくしたこと(ハンブルクの「市」で目をつけた若い女を追って夜の公園へ行き、その女が茂みへ男を誘い込むのを見たが、男が立ち去るのと入れ替わりに茂みに隠れていた別な人影が現われて闇に消えた。翌日新聞で事件を知って被害者は彼女ではないかと思って葬儀に行くと、件の人影と思われる男も来ており「彼は突然、まだ逮捕されていない殺人犯人を発見したような気がした」――と、ほとんど妄想である)、マイヤーが、戦争中、精神状態を疑われ、治療を受けさせられたために、軍医(精神分析医であったという)を憎んでいたこと。最初の脚本は、全く共通点のないこの二つの体験談を政治的な主張でつなぎ合わせた、およそ洗練を欠いた生な願望充足と自己正当化から成っていたとおぼしいことが見えてくるのだ。
むろん、ヤノヴィッツの話――それを普遍化するだけの腕が脚本家になければ、個人的な性的妄想としか言いようがない――が、専制君主がどうしたというクラカウアーの主張に使える訳がない。だから彼は、権威への叛逆という政治的な主張に利用できるマイヤーの体験と脚本との関連を強調し、ヤノヴィッツの話については事実を記すだけですませている。一方、マイヤーの個人的動機の方は、「このストーリーの革命的な意味は、カリガリが精神病医であることを暴露するラストにおいて、まぎれもなく明らかにされている。すなわち、理性が無分別な力に打ち勝ち、気狂いじみた権威は象徴的に廃止されるのである」と、最大限に持ち上げられる。クラカウアーは最初と最後を除いた中間部分がそのままオリジナル脚本だったと言っているが、この点は実際に映画を見れば誰でも疑問に思うだろう。精神病院での「現在」の部分は単純につけかえのきくようなものではなく、フランシスの妄想と分かち難く結びついているのだから。
元の脚本が枠物語でなかったという主張も事実とは異なることが今日では判明している。クラカウアーの主張を無批判に繰り返す田中雄次もこれについては詳細に報告している――「ベルリンのドイッチェ・キネマテークが買い上げたW. クラウスの遺品のオリジナル脚本のタイプ原稿によると、ヤノウィッツ、マイアーの草稿でも、〈枠組み〉が構想されていたことがうかがえる。冒頭に登場するのは、田舎の屋敷に住む裕福なフランシス博士である。彼は友人たちとパンチを飲みながら、20年前に自分が巻き込まれたカリガリと夢遊病者の物語を語る。話を聞く人たちの中には、いまはフランシスと結ばれ、幸せな結婚生活を送るジェーンの姿もある。この移動市にやってきたジプシーたちを見たことから呼びおこされる物語は、前後の挿話を現在の時制にし、〈内側の部分〉を叙事的な過去時制で表現しており、そこには実際の映画に見るような現実と非現実との間の曖昧さといったものはない。草稿はまた、カリガリの同情的な弟子を登場させ、カリガリは精神の錯乱した、憐れむべき悲劇的な科学者であったことを観客に見せようともしている」。
この単純で葛藤のない勧善懲悪的筋書きと、語り手のアイデンティティを脅やかすことなどあるはずもない安定したパースペクティヴを持つ語りから、現在のフィルムに見られる、複雑な構成と錯綜した分身関係が生まれたとはとても思えない。「E・T・A・ホフマンの精神をうけついだ」というなら、完成したフィルムこそがまさにそうなのであり(クラカウアーに『砂男』との類似などわかる訳がないが)、最初の脚本にそうした要素は全くなかったのである。こうした事実から判明するのは、外枠部分は、無かったものが付け加えられたのではなく、内側の物語と巧みに関連づけて書き替えられたのであり、ヴィーネかラングかはわからないが、それだけで(フランシスとジェーンの結婚生活のように凡庸で退屈だったと思われる)内側の物語が救われるほどの、手だれによる改稿だったということだ。フリッツ・ラングの研究書で明石正紀は「ラングがやったのは少々手を加えてわかりやすくしたといった程度だとの説もある」と書いているが、「少々手を加えて」ここまでになることもあるということだ。準備期間がそうあったはずはないのに、ここまで素晴しい作品に仕上がったことには驚かされる。
ヤノヴィッツの見聞きした猟奇的事件の記憶は、ジェーンの寝室に忍び寄るチェザーレに遠いこだまを響かせているのであろう。彼が被害者(?)の女性に目をつけたのは「ハンブルクの定期市」であり、事件は「ホルステンヴァル」で起こった。ベルリンで彼とマイヤーはしばしば天幕の並ぶ「定期市」に足を向け、ある夜、「あたかも催眠術をかけられているかのごとく演じて」いる「力持ちの男」が、「意味ありげな予言者のように、固唾をのんで見守る観客を感動させてしまう話しぶりで、すばらしい芸をやってのける」のを見たという。カリガリがマイヤーの仇敵の軍医であることも、チェザーレが「力持ちの男」から出発したことも、さして不思議な話ではない。ボヴァリー夫人もそもそもは田舎医者の妻の自殺を報じる三面記事であった。「カリガリ」という名はヤノヴィッツがスタンダールの本から見つけ出した。
こうした話が私たちの興味を引くのは、誰かの手の中で石ころが、あるとき魔法のように宝石に変えられたればこそである。二人の脚本家の最初のアイディアが貴重だからではなく、その逆である。私たちが本稿で考察してきた、主人公の妄想の起源にあったと想定される出来事は、脚本家たちの経験から生まれたものではなく、そもそもオリジナル・ストーリーが書かれた時点では存在しなかった。オリジナル・ストーリーにあったのは退屈な回想だったとしても、「信用できない語り手」による妄想ではなかった。起源の出来事はラングとヴィーネの手が加わることでいわば「事後的に」構築されたのであり、功なり名遂げた中年男が得々と語る思い出話だった「オリジナル・ストーリー」が、一度も存在したことのない過去の再演に作りかえられたのだ。
自分は「子種をうえつけた父親で、マイヤーはそれを宿し、育て上げた母親である」とヤノヴィッツが言っているとクラカウアーは書いているが、このヘテロセクシュアルな再生産の比喩が醜悪なのは、彼らが、異質な血を排除して、彼らの意図に忠実な、自分にそっくりな真正の子供であることを作品に要求しているからだ。彼らの脚本に対してヴィーネが提示した変更に、二人は「激しく抗議した」という。だがそれは、彼らの意図から切断され、思いがけないものと結びつき、フレームの外との関係によって意味づけをすっかり変えられることによってのみ、彼らの下品さの再生産からまぬかれた傑作たりえたのである[☆20]。そこに働いているのは、クラカウアーが言うような「ドイツ人の集団的魂」や「民衆の生活のゆっくりと動いている基礎から生じ、時には真のヴィジョンを生じさせるあの暗い衝動」などでは断じてない。(やはりクラカウアーの世迷い言は、『カリガリ』の冒頭で例の患者が“われわれを取り巻いている霊”について話しているのに近いようだ。)彼の作る寓話には、「専制君主」「専制君主に反抗する告発者」「専制君主に操られる民衆」という、三通りのキャラクターしか存在しない。彼はそれを『カリガリ博士』に適用するという恥知らずなこじつけをやってのけたのである。
クラカウアーとヒルシュフェルト
同時代との関連を言うなら、たとえば「催眠術」や「夢遊病」が一般にどう受け取られていたかをクラカウアーは問題にすべきであったろう。映画の中に現われるそれらは、人々が抱いていたイメージの引用であるのだから。いやしくも「ホフマンの精神を受け継いだ」と言うなら、彼はまず『カリガリ博士』がホフマンのどの作品とどのように似ており、ホフマンをどう変形しているかについて述べるべきであったろう。作品は過去の作品から作られるのであり、作家の個人的動機もそれと同列の引用対象に過ぎないのだから。むろん、そんなことがクラカウアーにできたはずはない。能力の問題もあるが、それ以上に、彼にとっては政治的に価値があるかどうかが全てだからだ。作者の意図が立派であれば誉め称えるに足ると思っているのだが、あいにく、そんなものは、(幸いにして)複数の「作者たち」の手さばきの中に消え去ってしまった。クラカウアーはそれを非難するが、それは、彼が革命的な政治的意図(それ自体多分に思い込みの)に固執するばかりで、出来上がった映画を見ようとしないからだ。
彼のターゲットは『カリガリ』ばかりではなかったから、ムルナウの吸血鬼、世界ではじめて陽に曝されて塵と化したノスフェラトゥまでが、「血に飢え、血を吸う、専制君主の映像」呼ばわりされている。クラカウアーのような男は、〈父〉と聞けば自動的に「反抗」という言葉が浮かび、病院長は狂気の専制君主の象徴で、打倒のため雄々しく立ち上がるべきだと思っており(あるいは、そういう態度をとれば、ほめられ、受け入れられると知っており)、受動性を理解しない。彼はあまりにも男らしいので、フランシスがカリガリに愛されたいと思っているなどとは夢想だにしないのである。
クラカウアーの説は、同性愛はもちろん、およそ美的なことは何一つ理解できず、「この脚本家たちが取り憑かれた専制政治のテーマは、はじめから終りまでスクリーンにしみわたっている」と宣言する、自分こそ何かに取り憑かれ、政治的なものをタバコの脂[やに]のようにしみつかせた男性的批評家の営為であった。ヒルシュフェルトが同性愛と女性性及び芸術の関係に拘泥した訳も、クラカウアーを脇に置くと理解しやすくなるのではないか。しかし、実のところ、ヒルシュフェルトはクラカウアーを補完する存在なのである。政治的なものしか理解しない男らしい男がいてこそ、そこから自らを分かつ、男でありながら女性性とそれに結びついた芸術的資質を有する、彼ら「第三の性」が成り立つのであるから。一方、「男らしい男」にとっては、そうやって別種族と名乗ってくれるのは願ってもない話であり、そうした男女[おとこおんな]に(そして自らの抑圧した女性性に)それ以上わずらわされることも脅やかされることもなくなるだろう。
人は一般に、衝撃的な歴史的事件が起きると、それに合わせて「それ以前」の歴史の解釈を変えてしまうものである。ある意味、その状態は、次の衝撃的事件によって塗り替えられるまで続く(しかも、いったん変化が起こると、人々が以前にはそう信じていたという事実すら、すみやかに忘れられる)。しかし、過去の出来事はそれ以前の出来事の結果として起こったのであり、実証的な因果関係を無視して、現在そう主張するのが正しいと思われているものを無批判に投影してよいようなものではない。ヤノヴィッツは、彼とマイヤーは元のシナリオで「国家の権威が一般的な徴兵と宣戦布告の中にその万能ぶりを発揮することを非難した」と主張しているとクラカウアーは書いている。だが、クラカウアーも承知していたはずだが、ヤノヴィッツが言っているのは直前の最初の世界大戦についての話であり、マイヤーがひどい目にあった軍医同様、過去の怨みであっても予兆ではない。これは映画作者たちの営為とは似て非なる、存在しなかった過去の捏造というべきである。
ちなみに「ナチスの予兆」とは、もっともらしさをかもし出すのに今なお便利に使われている符丁らしく、本稿を書きながら新聞の映画評にまさかの実例を見つけた。今年(2011年)封切られたあるドイツ映画を紹介しながら、「誰しもそこにナチス台頭の予兆を見るに違いない」とその評者は言うのである――物語は1913年、つまり第一次大戦前の設定であるのだが。
「それ以前」の事実について少々触れておきたい。帝政期末期には、オスカー・ワイルド裁判に匹敵するような同性愛スキャンダルであり、「ホモセクシュアリティ」という概念が広く知られるきっかけにもなったと言われる「オイレンブルク事件」が起こっている。同性愛の噂でヴィルへルム二世の宮廷は揺れ、皇帝の側近だったオイレンブルク侯爵とモルトケ伯爵は名誉棄損で告発者を訴えた。1908年、スキャンダルは政治的事件に発展し、オイレンブルクと性的関係を持ったという下層階級の証人の出現で、彼はついに失脚する(この展開もワイルドの場合に似る)。海野弘によれば、皇帝に平和政策をすすめていたオイレンブルクは政敵や外務省から狙われていたのであり、彼の影響がなくなったので政府は軍備を進め、戦争突入に至った――つまり、この同性愛スキャンダルは第一次世界大戦の一因にすらなったのである。
この裁判の際、ヒルシュフェルトは証人として出廷し、「第三の性」としての同性愛者を擁護している。だが、彼の主張した、階級を横断する「ホモセクシュアル」概念は、彼が擁護したはずのオイレンブルクやモルトケからは理解すらされなかった。オイレンブルクについて海野は、「たとえ、若い兵士や農夫と遊んだとしても、それは二次的なもので、貴族としての本質にはまったく関係がない、というのだ。いかにも貴族らしい考えである」と書いている。自身がヴィルへルム二世と愛人関係にあったオイレンブルクにとって、そうした行為は、自らのアイデンティティに関わらない、また、特権として見逃されてしかるべき事柄だったのである。彼らはまたそのように考えることのできた最後の時代を生きた人々であった。ヒルシュフェルトは同性愛概念をも巻き込んだある種の「民主化」の申し子であったと言えよう。
今日ではヒルシュフェルトの主張のうち、「第三の性」のような“女性性”の実体化や、それと不可分の、同性愛と芸術的資質の関係を主張することは、「政治的に正しく」なくなったためにかえりみられなくなってしまった。しかし、本質化による同性愛擁護という形式自体は、脳や遺伝子その他へ鞍替えしながら今日まで続いている。それは(女性性や芸術といった)内実を伴わない空疎な形式であるが、「同性愛」と呼ばれるカテゴリーにはあくまで固執しながらその文化的意味を問わない(「異性愛」についても同様であるが)点において、たとえ生物学的でなくとも本質主義的である。
性科学対精神分析
もしもフロイトが同性愛についてヒルシュフェルトのように考えていたとしたら、私たちが本稿でかくもたびたびフロイトに言及することはなかっただろう。しばしば誤解されていることだが、フロイトの方法は全く還元主義的ではない。彼の同性愛理解は、ヒルシュフェルトのように同性愛と芸術的資質に関係があるというのとは全く違う意味において、必然的に文学や芸術にも関わるものであったため(そして、彼が教養とセンスと、人間に対すると同様、作品に対しても細部に向ける注意深い目を持っていたため)、今なお、性的なものと知的なものの結びつきを考える際の、基本的な、そして汲めども尽きぬ参照先なのである。それは作品に対して、隠された何かの表現だと決めつけるのではなく、たんにそれがどのように構成されているかを言うのである。フロイトは女性性を本質化しなかったように、芸術的資質の本質化もしなかった。夢も白昼夢も神経症も芸術も同じ構造を持つ以上、「病人」と「健常者」、「同性愛者」と「普通人」の区別が不可能なように、「芸術家」の人種化も不可能なのだ。しかし、フロイトの思想はそのポピュラリティにもかかわらず、二十世紀の続くあいだずっと誤解され続け、その通俗的理解は今なお終っていない。ヒルシュフェルトはといえば、もともと通俗的なのである。
ヒルシュフェルトの言う「科学的根拠」とは、文化的な意味を問うことなく「自然」に理由を求めるものであった。同性愛者という「他の人たちとは違って」いる種族として認めろという主張は、「他の人たち」、つまり「普通の人たち」とは何かを問わないため、波風を立てないですませられるので、以来、現在に至るまで、この形式は説明内容を入れ替えながら存続している。先に、ヒルシュフェルトのような同性愛者の「種族化」は、そのまま逆転してナチスによる迫害の理由になりえたと述べたが、これは彼らの主張がたまたま悪用されたというようなものではない。ナチスは、少なくとも彼らと同程度には、「民主的」であり「科学的」であったのである。誰でも犯しうる、ある場合は罪とされるものの身分によっては全く問題にならない「行為」から、階級を横断し、個人を超えたところで個体を規定する生物学的特質へ。ヒルシュフェルトが依拠したものは、実のところ、政治的主張が先にあってそれに見合う(偏見に満ちた)証拠固めをするナチスの優生学と同様、疑似科学であった。
ヒルシュフェルトはフロイトの同時代人であり、彼の著作に少なからずその名が引かれているのを今でも見ることができるが、それは参照のためであり(もはや実際には参照されないにしても)、必ずしも批判のためではない。しかし、ヒルシュフェルト的な人種化・属人化した「同性愛者」概念については、フロイトははっきりと反対の立場を取っている(彼らが間違っていることを知っている)。「レオナルド・ダ・ヴィンチの幼年期の記憶に関する一考察」(『著作集』3)に付けた註で、フロイトは、精神分析の研究が明らかにした「同性愛の理解のために疑問の余地なき二つの事実」として、第一に母親への固着を挙げ、そしてもう一つを次のように述べている。
フロイトは本文で、「これらの説明が同性愛の代弁者の公的な理論に真向から対立することは間違いない、しかしこれらの説明が、問題を決定的に解決するほどに包括的なものでないこともわかっている」とも言っている。彼は同性愛にただ一つの本質を認めはしなかった。それは、人が「異性愛者」になるのが自明のことだとは思っていなかったからであり、なぜ多くの人間が異性愛に向かうのかもまた、説明を必要とする事柄だと考えていたからだ[☆21]。「実際的な諸理由から同性愛と呼ばれているものは、種々さまざまの心理的・性的抑制の過程から生じてきたものであろうし、またわれわれの認識した経過は、単に多くの経過のうちのひとつにすぎず、単に「同性愛」のひとつの型にしかあてはまらない」(前出の註より。強調は引用者による)。
フロイトが「第一の事実」として挙げている、母親への性的固着から息子が同性愛になるという言説は、「ひとつの型」という限定つきであってさえ、現在では即座に強力な反発を引き起こそう(もっとも、その型に属するとフロイトが認定したレオナルドのケースについての考察の多くは、芸術的才能に乏しい――つまり大多数の――同性愛者にはあまり関係がないだろう。芸術家という人種はいないにしても才能の有無はある)。セクシュアリティが「種々さまざまの心理的・性的抑制の過程から生じてきた」というのは、特に同性愛に限らず、いわゆる正常な異性愛の場合についても言えよう。また、こうした議論は言うまでもなく男性についてのものである。以上の留保の上で、フロイトの見解が今なお古びていないのは、同性愛者の「マイノリティ化」に真向から反対するこの立場ゆえにだと言っておこう。
ふたたび夜
『カリガリ博士』においては、いったい誰と誰が「同性愛者」なのか。アランを演じたトワルドフスキーはウィキペディア英語版の彼自身の項目によれば本当にhomosexualであり、そのためアメリカに亡命したというが、彼は自分の演じた役(佐藤春夫に言わせると「如何にも近代的な意志薄弱なデカダン」)の正体を知っていたのだろうか。クラカウアーのような人が信じたところでは、カリガリは恐しい父であり、専制君主であり、善良な庶民を操って殺人者にする催眠術師であり、ヒトラーを予告するものであった。しかし、私たちの発見したところでは、「カリガリ博士」はヒトラーどころか、もし(フランシスの妄想でなしに)実在すれば、ピンクの三角形をつけられて収容所送りにされたであろう側の人間である。
『ナチ娯楽映画の世界』の著者瀬川裕司は、戦後の西ドイツの知識人が、強迫的に(それが正しいことであり、社会的要請であったがゆえの)ナチスの否定に取り憑かれていて、ナチス時代に作られた大量の「娯楽映画」をプロパガンダと頭から決めつけてきた事実について論じており(それらの映画でさえ、単純にまた都合よく時代を「反映」したりはしない)、クラカウアーについても、「クラカウアー的な、最初期からのドイツ映画の全体がナチズム的なものを直截に志向していたとする〈呪われた映画史観〉」と言っている。クラカウアーもそのような“総懺悔”的「正しさ」の虜だったのだとしても、あの下らないおしゃべりが権威になってしまったというのはどうにも解せない(読まずに有難がられたのかもしれないが)。いずれにせよ、彼はスクリーンを見なかった。カリガリ博士が本当は何をしているのかを見なかった。そして、外から貼り付けたレッテルだけで理解するという点で、レッテルは違えど“クラカウアー”は掃いても捨て切れないほどいたし今でもいる[☆22]。
夢を分析するのにフロイトが使った用語「検閲」とは、見るからに時代がかった比喩のようであるが、実は「検閲」の本質は外部の権力を超えたところにある。というのも、芸術はラベリングを嫌うからで、そうでなければ詩人が修辞に身を削ることもなく、言葉と物は一対一対応になるだろう――しかし、言語とは比喩であること(類似物の類似物であること)を本質とし、その一点で詩作と夢の仕事は同じものなのだ。フランシスが実演してみせた、過去を歪曲しながら反復するというのは、実は作品の営為そのものである。フロイトは神経症やヒステリーの症状を芸術の戯画化と呼んだが、『カリガリ博士』は、いわば「普通人」フランシスのホモセクシュアルな夢を、芸術として描き出してみせたのだ。サラ・コフマンの『芸術の幼年期』の訳者は、「芸術の真理」に迫ろうとしたフロイトについて、「精神分析は、解釈するというより、構築するのであり、その言説はある意味で妄想の構築物と変わらない、ということをフロイトははっきりと語るようになるだろう」と述べている。「精神分析が芸術の本質を明かすというより、芸術が、精神分析的言説の本質的なありように光をあてるのである」(赤羽研三「訳者あとがき」)。『カリガリ博士』はこの意味で、精神分析の手法を取り入れたと称して単純な絵解きに終始する(方法的に『他の人たちと違って』と変わらない)凡百の映画とは異なる、真の「フロイト的映画」とも言えよう。
万人に理解させることを目論んで作られた“啓蒙”作品である『他の人たちとは違って』は「同性愛者」を「同性愛者」と呼び、その同語反復に疑問を持たなかったが、『カリガリ博士』はその言葉だけは使わないまま、伝達の道具であるよりはむしろ謎としての映像を繰り広げることになった。明快なスピーチに対する、イメージの必然的に多重決定的な意味作用。外部の権力から本物の検閲に遭って前者は破壊されたが、『カリガリ博士』は映画というメディアの特性を存分に利用しながら、“自己検閲”のメカニズムそのものを構造的に組み込んだ作品であった。したがって馬鹿には最初からわからず、外部からの検閲は基本的に成り立たない。
『カリガリ博士』の幕切れでフランシスが眠り込むのは、『ドグラ・マグラ』の最後で主人公がふたたび混迷に陥るようなものである。ただし、悪夢の無限ループの中にいる呉一郎と違って、フランシスは院長に「治す方法がわかった」と言われている(「わかったかな?」と院長は観客に向かって言っている)。フランシスはその眠りと夢からいつ覚めるのだろう? 彼の回想の中でただ一人本当に生き、本当に死んだ、アランの最期の真相は解明されることのないまま長い時が過ぎた。
「そのあいだに、ポルトガルのリスボン市が地震によって破壊され、七年戦争が過ぎ去り、皇帝フランシス一世が歿し、イエズス会が解散させられ、ポーランドが分割され、女帝マリア・テレジアが歿し……」とは、「ファルンの鉱山」の題でホフマンやフーゴー・フォン・ホフマンスタールも小説化した綺譚――スウェーデンのファルン銅山で「一人の若い坑夫が岩の割れ目に落ち、緑礬水のなかに漬ったまま、五十年後の一七一九年に事故当時そのままの、美しく若い屍体で発見されたという実在の事件」(種村季弘「鉱物の花嫁」)――を素材にしたヨーハン・ペーター・へーベルの「思いがけない再会」の一節(種村の引用による)であるが、これに倣えば、さしづめ、「そのあいだに、性科学研究所はナチスに破壊されて焚書に遭い、ヒルシュフェルトはドイツに帰国できないまま客死し、ナチスがオーストリアに侵攻してフロイトはロンドンに逃れ、『カリガリ博士』の関係者も多くが国外に出て、ベルリンは陥落し、第三帝国もヒトラーも終焉を迎え、ドイツは東西に分断され、ベルリンの壁が築かれ、トワルドフスキーはニューヨークで、ラングとファイトはロサンジェルスで歿し、『他の人たちとは違って』のフィルム断片が見つかって西ベルリンのゲイ映画祭で復元上映され、ソ連が崩壊し、冷戦は終り、ドイツは再統一され……」といったところであろうか。「地上では全てが時間に腐蝕されて変形して行く」(種村)。まことに如何なる小説家の想像力も及ばぬ転変である。「だが、地下の坑夫は微動だにせず、若い肉体に少しも毀損の痕をとどめずに、義眼のような眼を見開いて、全てから自由に、だが全てに接触を禁じられて、しかも全てを観ているのである」(同)。眠り男のガラスの眼、否、みずみずしい花のような目は、フィルムが映写機にかけられて単調な機械音が響くごとに、〈夜〉の中であまたたび開かれることを繰り返した。作者たちも日々も過ぎ去り、多くの記憶と多くの希望が滅び去ったあとまでも、一条の光にすら堪え得ぬ〈夜〉の中で唯一生きのびた物質がかたちづくるむなしい影は、意識の執拗な明るみに似て、理解する者のないまま意味を産出し続けた。
フィルムが破棄されようがされまいが、『他の人たちとは違って』は、その手法、その啓蒙、そのプロパガンダ、そのイデオロギーは、検閲を行なった権力ともども過去のものになってしまった。『カリガリ博士』はどうか。むろん、それは、揺らぐことのない一定の評価を受けてきたように見える。しかし、『カリガリ博士』の真実が私たちがここで論じてきたようなものであるとすれば、それは理解されることなく尊重されているのだ――骨董品のように。表現主義美術の成果に注目したり、文化的遺産として歴史の中に位置づけたりすることは、それ自体としては悪いことではない。しかし、『他の人たちとは違って』とは異なり、『カリガリ博士』は過ぎ去ってしまった訳ではない。世界の転変にもかかわらず作品は変わらなかった――それはなおもあまりにも現在なのである。
ヒルシュフェルトは科学的根拠なるものを示せば世界が変わると思っていた。だが、実のところ世界は、ヒルシュフェルトのように考える人々が今なお多数を占めているがゆえに変わらないのだ。それは、私たちがいまだに“クラカウアー”と“ヒルシュフェルト”が補完しあう図式のうちに生きているということでもある。『カリガリ博士』が理解されなかったのはけっして偶然ではない。それはフロイトがかくも長い無理解[☆23]の下にあることと軌を一にするものだ。『カリガリ博士』はついぞ本来の価値を見出されることがなかったのであり、その点は第二次大戦後、自我心理学としてアメリカで栄えることになったフロイト理論にとっても同様である。カリガリ博士の真実が見出され、真のテーマが見出される時、人はすでに「今」がその時はじまっていたことに、そしてかくも長い時を経ても世界が変わっていなかったことに気づくだろう。
註
☆17 本稿をほぼ書き上げてから、ウェブ上のグーグル・ビデオで“Anders als die Andern”の英語版“Different from the Others”(51分)が見られることを知った。失われた部分は字幕であらすじを補われており、想像を超えてプロパガンダ映画であった。興味のある方には一見をお勧めする。プロパガンダとしては全く古びていない。偏見の部分ではなく啓蒙の部分が今でも通用しそうだ(ほとんどカリカチュアである)。少々紹介を試みると、自分が他の人たちと違うことに悩んだファイトは最初に効果のない催眠療法を受け、次にヒルシュフェルト博士を訪ねて同性愛に問題はないのだと納得。両親から富裕な未亡人との縁談を勧められると、彼らをヒルシュフェルトのもとにやる。両親納得。若い恋人を得て、その妹からも恋されたファイトは慌てて彼女をヒルシュフェルトの講演会に行かせる。妹納得。そればかりか、忠実な友以上のものにはならずに献身することを誓う。しかし、彼が脅迫を受けている事実を知ったショックで恋人は失踪、バイト先で店主の娘に言い寄られ、拒むと逆に店主に告げ口されて失職(女は例の未亡人も含め性的な誘惑者か、天使のような良き協力者のどちらかという訳だ)。脅迫者が捕まって被害者のファイトも罪に問われる。ヒルシュフェルト出廷して擁護の演説をぶつが、ファイトは有罪判決の上、社会的に葬られて服毒。新聞でそれを知った恋人は遺体にすがって泣きくずれ、自分も死にたいと思うが、そこでヒルシュフェルトの御宣托がまた響く(つまり、字幕が出る。ここでイシャウッドの記憶のようにヒルシュフェルト登場なのにフィルムが失われているのか、それとも、それ以前のシーンと混同されているのかは不明)。残念ながら今回、こうした具体的内容を本稿に反映させることはできなかった。
☆18 クラカウアーはこのシーンについて、「院長が鼈甲縁の眼鏡をかけると、彼の容貌は一変してしまう。すなわち、疲れきったフランシスを診察しているのはカリガリであるように思えるのである」と書いているが、そのような事実はない。たんに院長が眼鏡をかけただけである
☆19 ザビーネ・ハーケは「批評家たちは、ヴァイマル映画を前ファシズム映画とみなすクラカウアーの目的論的解釈に対して、その主張のいくらかを修正したり、問題視したりするような、数多くの歴史的研究によって反応してきた」として90年代以降の研究書を挙げ、「ヴァイマル映画を、戦後映画として規定される数多くの特徴を同時に考慮しないで、前ファシズム映画として記述するのはもはや不可能なのである」と述べているが、この程度では批判として生ぬるい上、批判対象の教条主義とセンスの無さをそのまま受け継いでいるようだ。
☆20 ベルリンでの公開から数年後、遥か極東でヴィーネのフィルムは、関係者のむろん知る由もない奇蹟的な出会いを遂げる。東京の銀座で杉山泰道という青年が『カリガリ博士』を見たのである。『ドグラ・マグラ』は『カリガリ』なしではありえなかったが、『カリガリ』は“思いがけないもの”と結びついて生まれたこの鬼子を絶対に予見できなかったであろう。フランシスは本当に父(たち)の操り人形になり、フランシスの見出す本と日記は、患者の手記と大量の「一件書類」に変わり、「再び現われる伝説のカリガリ」は先祖の記憶を甦らせる主人公となった。夢野久作が『カリガリ博士』を見て『ドグラ・マグラ』を書きはじめたとは、ほとんどありえないことが現実に起こってしまったのである。
☆21 「男性の関心がもっぱら女性にだけ向けられるということは解明を必要とする問題であり、化学的な牽引力がその根底をなしているというような自明のものではない」( 『著作集』5「性欲論三篇」註)
☆22 本稿を九分通り書き上げたところで、ウェブ上で『カリガリからヒトラーへ』を扱った近年の論文を見つけた。それによれば、クラカウアーらには以下のような“事情”があったという。「ここまで見てきたうち、原作からの改変に関しては、クラカウアーは個人的に参照することを許されたヤノヴィッツの手記をそのまま受け入れて論じている。しかし近年の研究によれば、ヤノヴィッツの記述は彼の革命性と功績を誇張し過ぎているという。具体的には、既に原作の時点で物語は映画とは違って形においてではあるが枠付けられていたこと、原作者たちも映画での変更を了承していたであろうことなどが、脚本や契約書から明らかにされている。ヤノヴィッツが「カリガリ博士」成立の経緯をこのように改変したのは,彼がクラカウアーと同じくアメリカへの亡命者であり,自分の政治的正しさや能力を証明する必要があったからであろう」(荻野雄「クラカウアーの『カリガリからヒトラーへ』」)。もし、この論文(それ自体はクラカウアー批判を目的とするものではない)を先に読んでいたとしたら、私たちはクラカウアーにここまで紙幅を割かなかったかもしれない。もともと彼の書いたものは映画論とは言い難く、政治的主張だけでは自立できない(友人だったと言われるベンヤミンの文学的才気もアドルノの理論性も持たない)物書きが、映画をネタに(植民地化して)、うらみつらみと功名心から、世渡りのために反ナチ的意図をあらわにした、それこそ単純に時代の反映であったのだろう。とはいえ、『カリガリ博士』についてはいまだにそれを鵜呑みにした、時代背景を考えるとよくわかるといったたぐいのコピペが氾濫しているのだから、また、テーマは違えどクラカウアーを知らずして反復している頭の悪い著作があとを絶たないのだから、ショボい左翼親爺とわかっても叩いておく意味はあるだろう。
☆23 ウィキペディア日本語版「精神分析学」の項目にその一形態が見られる。
参照文献
Freud, Sigmund “On Psychopathology”, The Pelican Freud Library vol.10 1972[『フロイト著作集』6]
Marshall, Gail “Victorian Fiction”, Arnold Publication 2002
Russo, Vito “The Celrroid Closet: Homosexuality in the Movies”, Harper & Row 1981
Showalter, Elaine “Sexual Anarchy: Gender and Culture at Fin de Siecle”, Penguin Books 1990/エレイン・ショウォールター『性のアナーキー―世紀末のジェンダーと文化』富山、永富、上野、坂梨訳、みすず書房 2000年
明石正紀『フリッツ・ラングまたは伯林[ベルリン]=聖林[ハリウッド]』アルファベータ 2002年
荒俣宏『ホラー小説講義』角川書店 1999年
海野弘「暗箱のなかの都市―ベルリン・一九二〇年代」『カイエ』四月号所収、冬樹社 1979年
海野弘『ホモセクシャルの世界史』文春文庫 2006年
荻野雄「クラカウアーの『カリガリからヒトラーへ』」(1)(2)京都教育大学紀要No.111 2007年
ジークフリート・クラカウアー『カリガリからヒトラーへ』丸尾定訳、みすず書房 1995年
サラ・コフマン『芸術の幼年期―フロイト美学の一考察』赤羽研三訳、水声社 1994年
識名章喜「オリンピアとマリア」巽孝之・荻野アンナ編『人造美女は可能か?』所収、慶應義塾大学出版会 2006年
澁澤龍彦『幻想の画廊から』美術出版社 1967年
澁澤龍彦『思考の紋章学』河出書房新社 1977年
『澁澤龍彦集成』7「文明論・芸術論」桃源社 1970年
ブラム・ストーカー『ドラキュラ』[完訳詳注版]新妻昭彦・丹治愛訳+注釈 水声社 2000年
ブラム・ストーカー「ドラキュラの客」桂千穂訳、須永朝彦編『書物の王国12 吸血鬼』所収、国書刊行会 1998年
瀬川裕司『ナチ娯楽映画の世界』平凡社 2000年
田中雄次『ワイマール映画研究―ドイツ国民映画の展開と変容』熊本出版文化会館 2008年
種村季弘『怪物のユートピア』西澤書店 1974年
種村季弘「鉱物の花嫁」『ユリイカ』総特集 オカルティズム 1974年7月増刊号[『怪物の解剖学』所収]
種村季弘『失楽園測量地図』イザラ書房 1974年
ザビーネ・ハーケ『ドイツ映画』山本佳樹訳、鳥影社 2010年
フロイト「精神分析入門」『世界の名著』60、懸田克躬訳、中央公論社 1978年
『フロイト著作集』3「文化・芸術論」高橋義孝他訳、人文書院 1969年
『フロイト著作集』5「性欲論 症例研究」懸田・高橋他訳、人文書院 1969年
『フロイト著作集』6「自我論・不安本能論」井村・小此木他訳、人文書院 1980年
『フロイト著作集』9「技法・症例編」小此木圭吾訳、人文書院 1983年
ホフマン フロイト『砂男 無気味なもの』種村季弘訳、河出文庫 1995年
マックス・ミルネール『ファンタスマゴリア―光学と幻想文学』川口・篠崎・森永訳、ありな書房 1994年
エドガール・モラン『映画―想像のなかの人間』杉山光信訳、みすず書房 1980年
M・G・ルイス『マンク』上・下巻、井上一夫訳、国書刊行会 1976年
★プロフィール★
平野智子(ひらの・ともこ)
今回も共著でしたが、できれば次の機会には、やはりDVDで見た『カサブランカ』について単独で書いてみたいと思っています。以前載せていただいたトールキンについての論考『“父子愛”と囮としてのヘテロセクシュアル・プロット』(「コーラ」10号)も、今回の『カリガリ博士』論も、明示的に描かれていない同性愛の主題を作品から読み取る(だけではありませんが)というものでしたが、『カサブランカ』論はそれとは違う──むしろその逆というか、そういうことをしているつもりになってデタラメを書いている、ある具体的な批評に反対する試みになるはずです。私たちがやっているような批評はありもしないエロティックな要素を妄想的に深読みしているかのように非難されかねない一方で、「クィアー・リーディング」としてはすでに制度的に認められているものです(私は別にそういう訓練を受けている訳ではなく、たんに自分が読み取るものが人と違うことに、しばしば驚かされ、当惑するのですが)。しかし、後者が人と場合によっては、まずは作品そのものを予断を排して分析するという当たり前の手順をないがしろにし、あらかじめ党派的に定められている政治的な正しさの枠組みに従って作品を裁断する事を批評と称していることもあるという事実を、最近、『カサブランカ』について書かれたある文章──その文章の場合は、非性的な男同士の絆を性的なもののように誇張し、明示的な男女の関係をきちんと読み解こうとしないというものでした──を読んであらためて認識しました。加えて、私が見た『カサブランカ』のヘテロセクシュアル・プロットは、一般に言われているような、ハンフリー・ボガードが昔の恋人イングリッド・バーグマンをなおも愛しつづけながらもそれゆえに別れるというメロドラマとは全く別のものでした。来るべき『カサブランカ』論ではそれについて語りつつ、先に述べた実例を批判することになるでしょう。
鈴木薫(すずき・かおる)
『“父子愛”と囮としてのヘテロセクシュアル・プロット』について一箇所マイナーな訂正を。トールキンの『失われた道』の登場人物アルボインをオックスフォードの教授としたのはは誤りでした。どこであるかはわかりませんが、オックスフォード以外の大学の教授ですね。
『他の人たちとは違って』がいろいろな意味で面白すぎたので、これを使って、ずっと休んでいた「読書会」(今回はヴィジュアル版)を再開しようかと思いつきました。本文で書いたようにネット上で見られますので、集まって感想や意見の交換をしませんか? 五月以降に、東京のたぶん東銀座か本郷で週末の夜あたり。ブログでお知らせしますので、その時は参加希望の方ご連絡下さい。ブログ「ロワジール館別館」
Web評論誌「コーラ」13号(2011.04.15)
特別寄稿:砂男、眠り男――カリガリ博士の真実(平野智子・鈴木薫)
Copyright(c) SOUGETUSYOBOU 2011 All Rights Reserved.
|
| 表紙(目次)へ |