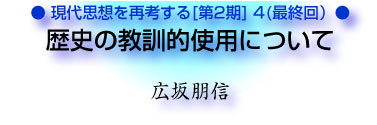|
|
|
Web評論誌「コーラ」 |
|
■創刊の辞 ■本誌の表紙(目次)へ ■本誌のバックナンバー ■読者の頁/ご意見・感想 ■投稿規定 ■関係者のWebサイト ■プライバシーポリシー |
|
<本誌の関連ページ> |
|
■「カルチャー・レヴュー」のバックナンバー ■評論紙「La Vue」の総目次 |
Copyright (c)SOUGETUSYOBOU |
|
|
|
まえおき
カントをもじって「歴史の教訓的使用」と題したからには、マルクスから「一度は偉大な悲劇として、もう一度はみじめな笑劇として」の名文句を引いてその出典について蘊蓄をひとくさりしつつ、おもむろにハーバーマス「歴史の公的使用について」(『過ぎ去ろうとしない過去』)を引っぱり出して歴史修正主義について論じるといった「遊び」が必要だというのが、このリレーエッセイで私が主張してきたことの一つである。
白か黒か短兵急に決着をつけたがる議論は危い。せめて結論のない蘊蓄をひとくさりするくらいの「遊び」がないと、考えることが苦痛になる。それは裏返せば、思想が恫喝の道具になりかねないということだ。さあ考えろ、結論はこれだ、というわけだ。来年あたりから小中学校で実行されようとしている教科としての道徳教育とはそうした恐喝に、きっとなる。
教科としての道徳教育は、思考に対する恐喝の道具となる。なぜそう言えるかというと、受験科目のようになるからだ。戦前の修身科がそうだった。修身科は正規の教科であるから試験もあれば受験参考書まであった。国を挙げて道徳教育に熱心に取り組んだから、当然、政府や軍の幹部は教科としての道徳においても優等生だったはずである。そして、にもかかわらずというべきか、だからこそというべきか、「無責任の体系」と評されるような社会が出来上がったのだった。
余裕のない思考は、思索するものをとんでもないところに連れてゆきかねない。あらぬ方角へわき目もふらずに駆け出して迷子になるよりは、多少不まじめでも道草を食いながら遊び歩く方がましなのではないか。
思想を論じるとは、どこか占いに似たところがある。現実が混とんとしている時にそれは意味がある。このリレーエッセイ「現代思想再考」を始めたとき(2011)には東日本大震災があり、翌年(2012)には政権交代があった。私の目には時代状況は混とんとしたものに映っていた。そこで、今、私たちはどこにいるのか、これからどうなるのか、いくらかの不安とともに模索するうえで、あえて直近の現実から一歩身を引いて80年代ごろのいわゆる現代思想を再考することは、過去の偉大な魔法使いたちの予言の精度を確かめつつ、身の振り方を考える準備をすることでもあった。ところが昨年(2013)から世間の雲行きが怪しくなった。
本当は、歴史の終わり論争やハイデガーとナチ論争も取り上げたかったし、広松渉のような大家や、時代の寵児であった浅田彰や中沢新一、さらには蓮實重彦、栗本慎一郎ら、80年代ごろの思想誌の目次を飾った論客たちについても、岡田さんの胸を借りて、かみあいそうでかみあわない議論をずるずると続けていられれば、どんなに楽しかったことだろう。
それに、前々回、岡田さんが柄谷行人『世界史の構造』を取り上げてくれた。本来なら私はこれを受けて、最近、刊行された柄谷の柳田国男論を取り上げるべきだったろう。実際、前回で私が歴史観に話を持って行こうとしたのは、ある程度までは「遊び」を意識しながら体系的思考を再検討する噺のマクラにしようとの心づもりもなかったわけではない。しかし、ご時勢の急進展にせき立てられるように、柄にもなく結論を急いだのであった。
1
前回、私は次のように述べた。
「決意のためのノモス」とはハンス・ヨーナスのグノーシス論(『生命の哲学』所収)からとった言葉だが、私の頭のなかではすでにヨーナスの文脈を離れている。道徳規範のことだと思ってもらっていい。倫理ではなく個人道徳、ひらたく言えば人生論や処世術のことだ。学問としての哲学だの倫理学だのは専門の研究者にお任せする。一市民として今の時代をどう生きるかだけが当座の私の関心である。
一方で、一市民として今の時代をどう生きるかというテーマは、学者さんの手の出せるものではない。大学であろうが文科省であろうが、人の人生に責任を負うことはできない。学校や役所にそんなことを期待する方がどうかしている。逆に、たかが研究者や教育者や官僚や政治家が他人様の人生に指図しようとするなら、そんな無責任なことを素面で言えるのは馬鹿か詐欺師かのどちらかだと疑った方がいい。
ではどうすればよいか。結論から言えば、歴史に学ぶほかはないのである。どのような状況で、どのような人間がどのようにふるまい、その結果どうなったかを知ることは、後世の人間にとって我が身のふり方を考える上で最も参考になる。私たちが自らの生き方について、それに問いかけるような歴史を規範的歴史像と呼んでおこう。しかし、その規範的歴史像は私たちに共有されていない。
現代社会の特徴をポストモダンと呼ぶ場合があるが、何をもってポストモダンの特徴とするか? 私の印象では規範的歴史像が共有されないということだと思う。共有が期待される範例的歴史像がないと言い換えてもよい。それを強引に共同化しようとするのが、いわゆる歴史修正主義である。共同化というより私有化と言った方がよいかもしれない。
しかし、規範的歴史像は共有されていないが、それと歴史の本体は別である。だから歴史の教訓的使用のためには、私たち一人一人が、各人の身の振り方について、それぞれの固有の関心から歴史に問いかけ、自らの責任で範例を探り当て、指針を見出すほかはない。ほとんど実存主義だが、歴史を媒介にするという一点で「決意のためのノモスを欠いたままのたんに形式的な決意性」に陥ることを避けられる。
歴史学あるいは歴史研究は実証的な学問であって、道徳ではないとの反論もあるだろう。それはその通りである。実証的でない歴史叙述はよくいえば神話・伝説であり、悪くいえばただの空想妄想だ。その上、そもそも歴史自体は道徳的ではない。人間の基準から見て道徳的であろうがなかろうが、その時そうなってしまったことの積み重ねである。他に選択肢がなく、やむにやまれずそうしてしまった場合もあるだろうし、ただなんとなくそうした場合もあるだろう。人の行為の動機は様々でも結果は変えられない。変えられない結果の連鎖として歴史をとらえれば歴史の展開は必然であり、必然の連鎖として歴史を叙述するのが歴史学である。そこに「もし」や「たら・れば」の付けいる余地はない。
しかし、歴史の評価は別だ。そもそも人間が歴史を記録しておこうとした動機は、後世への教訓の材料としてではなかったか。司馬遷『史記』には、過去の人物の事績を書き留めた後に「太史公曰く」云々と寸評が付されている。例えば「李斯列伝」では、始皇帝の中華統一を補佐し、法家の理論を実践して秦帝国の行政に辣腕をふるった李斯という人物について次のように言う。
帝国の屋台骨が揺らぐようになってから軌道修正しようとしたが時すでに遅く、政敵によって無実の罪で極刑に処せられたため世間では悲運の忠臣のように言うが、司馬遷はそうではないと手厳しい。しかし、もしそうでなかったら、李斯の功績は周公や召公に列するものなのに、とも言う。周公と召公は儒教的政治観からは最高級の賛辞を寄せられる政治家で、司馬遷も『史記世家』で誉めちぎっている。もし、李斯が道を誤らなければ、最高級の政治家の一人となっただろうと司馬遷は言っているのだ。
このように司馬遷は歴史上の人物を評価する際に「もし」や「たら・れば」を持ちこんでいる。そうすることによって、李斯という人物の事績から教訓を導き出している。これは司馬遷が古代の歴史家だからなのだろうか。次に現代の歴史学者のケースを見てみよう。
2
私は歴史の評価に「もし」や「たら・れば」を持ちこむことを可とした。むしろ、それを持ちこむことで、歴史に問いかけ、対話することを可能にしてくれるツールとして「もし」や「たら・れば」を考えている。現代の歴史学者はどうだろうか。
加藤陽子『それでも日本人は「戦争」を選んだ』(朝日出版社)を読んでいくと、一か所、はっきりと仮定を持ちこむことである歴史的事件を評価しているところがあった。
加藤は「このとき、斎藤首相と天皇の考えのとおりになっていれば、日本の歴史はまた別の道を歩んだかもしれない」と仮定を持ちこむことで、熱河作戦を歴史の分岐点としている。熱河作戦が歴史の分岐点の一つだとするのが妥当かどうかを史実に即して検証することは、本稿の関心と私の能力の範囲外なので省略する。ここでは必然の連鎖のように語られる歴史に、仮定を持ちこむことで歴史上の事件を評価すること、言い換えれば教訓として解釈することが可能になることを見ていきたい。
まず、昭和八年(一九三三)の熱河作戦という事件をクローズアップしたところが面白い。前年には帝国の傀儡国家である満州国建国があり、同年には国際連盟脱退、翌年にはワシントン条約破棄、続く昭和十年に天皇機関説事件、昭和十一年に二二六事件と、大事件が目白押しの一九三〇年代の日本史で、熱河作戦は今ひとつ目立たない。
三三年一月、満州と中国の国境付近の熱河省山海関で軍閥・張学良軍と日本軍が武力衝突する。日本は張学良軍を追討するために、二月に中国・熱河省に出兵した。この作戦は事前に閣議決定を受け、天皇の裁可も得ていた。日本側の主観ではシンプルな自衛行動のつもりだった。ところがこれに先立つ満州事変と上海事件について、中国は日本を国際連盟に提訴しており、国際連盟はリットン調査団を派遣するなどして両国の紛争を調停している真っ最中だった。加藤は国際連盟規約第一六条に注目する。
ここから、熱河作戦を止められるかどうかが当時の日本外交の針路を左右するものとなり、結果としては、日本が国際的に孤立し、国際連盟脱退、太平洋戦争、敗戦へといたる流れの分岐点になった。けれども、もし、天皇と首相が別の決断を下していれば、歴史は別様でもあったろうと考えられるのはまさにこの時だったというのが、加藤の見立てである。
別のポイントを挙げる歴史学者もいる。中山隆志は張作霖爆殺事件(1928)の事後処理を挙げる。
こうした見立てからどのような教訓を引き出すべきかは、加藤や中山の課題であって私の課題ではない。ここでは、現代の歴史学者も歴史の教訓的使用を行っており、それにあたって仮定をさしはさむということをしていることが確認されればよい。
3
古代の歴史家・司馬遷も現代の歴史学者も、歴史を教訓的に使用するにあたり、歴史に「もし」や「たら・れば」を持ちこんでいた。もちろん、それは過去を自分に都合よく改変するためではなく、歴史の解釈や評価のためであり、むしろ、苦い経験から学ぶための操作である。あの時、もし何々していればこうなってはいなかっただろうに、と嘆くのは、単なる詠嘆のためではなく、もしまた似たような状況に立たされたら、別の選択をするべきだという教訓へ導くためである。
しかし、似たような状況は同じ状況ではない。歴史は繰り返すというが、厳密にはまったく同じ状況が繰り返されることはない。それでも歴史は繰り返す(ように見える)、それは歴史が繰り返すのではなく私たち人間が過去の範例を繰り返し演じるからである。ただし「一度は偉大な悲劇として、もう一度はみじめな笑劇として」。だから、歴史をなぞって処世の範とすることは茶番を演じることだという自覚がないと、それこそ「みじめな笑劇」、笑えないコントになってしまう。これが歴史の教訓的使用にあたった注意すべき第一のことである。
歴史から教訓を導き出すこと、これはある意味で危険な道である。加藤陽子は次のように指摘している。
このケースの実例として加藤はE・H・カー『歴史とは何か』(岩波新書)からトロツキー失脚を挙げる。トロツキーの失脚については、このリレーエッセイの初めの頃に取り上げた山口昌男『歴史・祝祭・神話』の、トリックスター的両義性を持つがゆえにスケープゴートにされたとの仮説があったが、加藤が紹介するカーは違う説を立てる。トロツキーが失脚したのは、当時のロシア人が歴史の教訓に学ぼうとしたからだというのだ。
軍事的リーダーシップとカリスマ性のあるトロツキーに、当時のロシア人はナポレオンのイメージを重ね合わせた。レーニンの後継者として「ナポレオンのような軍事的なカリスマを選んでしまうと、フランス革命の終末がそうだったように、革命が変質してしまう。ならばということで、レーニンが死んだとき、軍事的なカリスマ性を持っていたトロツキーではなく、国内に向けた支配をきっちりやりそうな人、ということでスターリンを後継者として選んでしまうのです」(加藤、前掲書)。フランス革命の教訓から学ぼうとした結果が「犠牲者は数百万人ともいわれる」スターリンの大粛清だったのはご存知の通り。
それでは、現代の歴史学者は歴史から教訓を導くことに消極的かと言うとそうでもない。むしろ、加藤は歴史から正しく教訓を得るためにこそ「歴史の誤用」を避ける工夫をしておくべきだと言っている。歴史の教訓的使用が適切になされるかどうかは「いかに広い範囲から、いかに真実に近い解釈で、過去の教訓を持ってこられるかが、歴史を正しい教訓として使えるかどうかの分かれ道になるはずです」(加藤、前掲書)という。
イブン=ハルドゥーンも「歴史学は、無数の資料とさまざまな知識を必要とする」と言っている(『歴史序説(一)』岩波文庫)。ただし、私のような専門の歴史研究者ではない一般市民にとって、膨大な史書のなかから適切な例は何かを探し当てるのは至難の業である。したがって、歴史の誤用、「みじめな笑劇」を演じる可能性は払拭できない。だからこそ、茶番を演じる覚悟が必要になる。それは、歴史を誤用したにせよ、せめて悲惨な愚行ではなく、笑ってすませられる程度の茶番にとどめておく工夫でもある。
もう一つの注意点は、信長禁止令である。私たちは必ずしも歴史上の偉人や英雄ではない。この点で、司馬遷の例も加藤の例も直接には私たち、少なくとも私の参考にはならない。私は始皇帝の宰相でも、大日本帝国の天皇や首相でもない。歴史の流れを左右する立場にないどころか、むしろ、歴史の流れに右往左往する側にいる。それを忘れて例えば、俺が信長(のようなリーダー)ならと風呂敷を広げるのは、娯楽の範囲を超えると有害である。
信長ごっこが格好悪くて恥ずかしいだけでなく有害でもあるのはなぜか。英雄史観において自らを英雄になぞらえるのは、自分を歴史の主催者に位置に置くことであり、それは陰謀史観と似てくるからだ。これはスポーツファンの監督ごっこに似ている。ほんとうは「似ている」ではなく「構造的に同一である」と言い切ってしまいたいのだが、強い表現を使って証明を求められたら面倒なので逃げをうっておく。
スポーツ、特に野球やサッカーのファンのなかには、ごひいきのチームの監督になったつもりで、俺が監督ならエースは温存するとか、このタイミングで代打を出すとか、監督の采配を批評して悦に入る御仁が多い。これもまたスポーツ観戦の楽しみ方の一つで、私は否定するつもりはない。映画・演劇ファンにも、この芝居でこの配役はないだろうとか、あの場面の演出はこうあるべきだとか、監督・演出家気取りで口角泡を飛ばす人もいる(何を隠そう私もそのひとり)。そして、気の大きい人のなかには、俺が総理大臣だったら…と勝手に組閣したりする人もいる。
政治にも芸能的側面がある以上、こうしたごっこ遊びを否定するべきではないどころか、政治的判断力を養う上で有益である。ただし、あくまでも「ごっこ遊び」である自覚を忘れてはならない。
これに関連して、『戦国自衛隊』の法則を導入したい。半村良の歴史SFの傑作『戦国自衛隊』は、戦国時代にタイムスリップした自衛隊員たちが、近代化された兵器を使って、戦国時代の人々から見れば超人的な活躍をして天下統一をなしとげる痛快活劇である。しかし、物語の結末で主人公の伊庭三尉は、自分たちが織田信長の役割を演じていたに過ぎなかったことを悟る。
たとえ「もし」や「たら・れば」を持ちこんでも、歴史は大きな変化を受け付けない。個々の当事者としては変化をもたらすつもりで行動しても、歴史はそれを吸収して軌道修正に利用してしまう。
似たようなアイデアを描くものとして、山田太一『終わりに見た街』(小学館文庫)がある。この小説では、昭和十九年の日本にタイムスリップしたシナリオ・ライターが歴史の知識を用いて、東京大空襲から一人でも多くの人を救おうと奔走する。しかし、一市民にできることは限られており、ついに主人公は歴史の裏をかくことはできなかった。
戦国時代の人々にとって現代の兵器は鬼神の力のように見える、また、これから先、何月何日に何が起こるかを知っているのは神の如き予言者のようだろう。それでも歴史の大筋は変わらない。変えられるのは、歴史の進行に大きな影響を与えない偶発的な側面だけである。
タイムスリップという設定は荒唐無稽に感じられるかもしれないので、ノンフィクションも挙げておこう。かつて、すぐれたノンフィクション作家であった猪瀬直樹は、『日本人はなぜ戦争をしたか 昭和16年の敗戦』(小学館)で、「昭和十六年十二月八日の開戦よりわずか四カ月前の八月十六日、平均年齢三十三歳の内閣総力戦研究所研究生で組織された模擬内閣は、日米戦争日本必敗の結論に」至っていたことを描く。日本政府は、日米開戦前に陸海軍・各省庁と民間から選りすぐりの若手エリートを集めて、対米戦争のシミュレーションをやらせていた。これを指示したのは近衛文麿首相で、どうにも勝ち目はないとの報告を受けたのは東条英機首相だった。それでも開戦にふみきった。
こうした実例を見ると、タイムスリップとは、総勢三十数名の内閣総力戦研究所研究生による十一カ月にわたる調査と討議という手間を省くための小道具でしかなかった。歴史に詳しいシナリオ・ライターが現代から訪れなくても、勝ち目のない戦争だということは知っている人は知っていたのである。
こうした歴史の安定性を、必然性とか、ましてや宿命などと呼んではならない。あくまでも相対的な安定性である。歴史自体は、まさしく必然的な自然界の運動から、気まぐれに移り変わる私の気分にいたるまで、世界中のすべての出来事が陰に陽に影響を及ぼしあって変化する。
だから、歴史自体にとっては、人間的な基準での、必然も偶然も、進歩も循環もない。それなのに、なぜ、あたかも歴史が繰り返しているかのように見えるかといえば、人間は未来を演じることができないからだ。未来を作るつもりでいてもシナリオは過去の歴史を参考にするほかないからだ。
現代の保守政治は復古革命をめざしている。それは「とりもどす」という表現からも明らかである。彼らの主観レベルでは今はその革命の渦中にある。少なくともイデオロギーレベルでは彼らの主観的革命の規範となっているのは明治維新のはずだ。しかし、実際に行なわれている復古革命は、昭和初期の軍や官僚が主体となった体制内改革運動によく似ている。あるいは彼らにとっては、明治維新そのものよりも、明治維新に範を仰いだ昭和維新こそが敗戦によって中断された革命だと位置づけられていて、その再開を期しているつもりなのかもしれない。
最近の政治が昭和初期に似ていることは、既に多くの人が指摘しているし、それもなんだか出来すぎた話のようで口に出すのも気恥ずかしいが事実である。もちろん、似ているのであって同じではない。例えば、改正教育基本法は教育勅語的な道徳教育の復活を意図してなされたが、教育勅語のように学校教育の場で生徒たちが暗唱することはないだろう(ただし、教員採用試験受験者は暗記するだろうが)。特定秘密保護法にしても、それだけで治安維持法のような威力を発揮できるわけではない。ただし、共謀罪が成立し、自民党改憲案に添って憲法改正がなされればその限りではない。
改憲案はしょせん改憲案にすぎないではないかと言う人もいるだろう。しかし、それは間違っている。改憲を公約とし、かつそれに強い意志をもつ勢力が国会の多数を占めて政権を握っている今は、長い目で見れば改憲の作業はすでに始まっているととらえなければならない。それが完遂されるか挫折に終わるのかは、まだわからないが。
***
冒頭でふれました通り、2011年から、勝手気ままに続けさせていただいてきたこのシリーズですが、私の一存で、今回でいったん打ち切りとさせていただきたく存じます。企画当初と社会状況が大きく変わり、現代思想を(70年代80年代を中心に)再検討するという作業の意味を考え直さなければならないと痛感したからです。
この『コーラ』という場をお貸しくださった山本編集長、また、私のムチャぶりにつきあってくださった岡田有生さんとS.T.さんに、心からの感謝と、お詫びを申し上げます。もちろん、読んでくださった方々にも、篤く御礼を申し上げます。(広坂朋信)
★プロフィール★
広坂朋信(ひろさか・とものぶ)1963年、東京生れ。編集者・ライター。著書に『実録四谷怪談 現代語訳『四ッ谷雑談集』』、『東京怪談ディテクション』、『怪談の解釈学』など。ブログ「恐妻家の献立表」 Web評論誌「コーラ」22号(2014.04.15)
<現代思想を再考する>第4回[第2期]:歴史の教訓的使用について(広坂朋信)
Copyright(c) SOUGETUSYOBOU 2014 All Rights Reserved.
|
| 表紙(目次)へ |