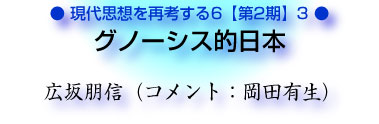|
|
|
Web評論誌「コーラ」 |
|
■創刊の辞 ■本誌の表紙(目次)へ ■本誌のバックナンバー ■読者の頁/ご意見・感想 ■投稿規定 ■関係者のWebサイト ■プライバシーポリシー |
|
<本誌の関連ページ> |
|
■「カルチャー・レヴュー」のバックナンバー ■評論紙「La Vue」の総目次 |
Copyright (c)SOUGETUSYOBOU |
|
|
|
1.柄谷行人の今村社会哲学評
柄谷行人は、朝日新聞2005年04月17日付けの書評欄で、今村仁司の『抗争する人間』(講談社)を取り上げた。その記事で柄谷は「本書は、社会哲学者として知られた著者の、これまでの仕事を集大成するような力作である」と儀礼的に評価しながら、今村の議論を次のように要約している。
これは『抗争する人間』だけのことではなく『排除の構造』ほか、『暴力のオントロジー』以降の今村の著作のここかしこに見て取れる社会観を要約したものである。こうした今村の社会観・人間観について柄谷は、旧ソ連を念頭において「このような認識は、理想主義が強かった時代においては意味があったと私は思う。なぜなら理想主義がうらはらに残酷な社会体制を作り出すケースが各所に見られたからである」と評したうえで、「だが、ソ連邦が崩壊し、一切の理念をあざ笑うシニシズムが蔓延したのちに、さらに国家が露骨な暴力性を示している時期に、このような主張は何を意味するのだろうか」と問う。
今村のいう「覚醒倫理」とは宗教的救済に近い。柄谷はそのことを指摘して記事を結ぶ。
宗教的救済が「根本的には保守派の議論」なのかどうか、私には疑問があるが、ここでは保留しておく。問題は宗教的かどうかではなく、現実に対する絶望の仕方にあると思う。
柄谷は「自己意識から出発する理論は、そのような解決(解決不能)しか見いだせない」と一刀両断にして恰好いいが、少し今村を弁護すれば、『抗争する人間』において「覚醒倫理」は最終章で持ち出されていて、その一つ前の章ではベンヤミンが『暴力批判論』で、言語を「暴力がまったく近寄れないほどに非暴力的な人間的合意の一領域」としていることをヒントに「非暴力的言語的交通」、「論議過程」に希望を見いだしている。
こうした論議過程の実現する場を今村は「純粋言語空間」とも表現していて、それはロールズ『正義論』の有名な「無知のヴェール」を連想させるが、実はロールズ以上に現実的でもある。ロールズの無知のヴェールは自分の立場を棚上げにすることだが、今村は、いわば負荷ある自己を前提にしていて、論議の参加者たちの負荷、つまり各人の立場や経歴や主張・信条による偏見(自己確信の迷妄)が論議過程のなかで洗い出され、訂正されていくことを期待している。あらかじめ無知のヴェールでおめかししておかなければいけないロールズの会議よりも、普段着のまま(偏見丸出し)で結構というのだから、今村の談義の方がよほど気楽でいい。
哲学的な概念をちりばめた今村自身の文章を読んでいると、論議過程とは理想的な言論空間が成立していなければあり得ないような高遠な理念のように思えてしまうが、深遠そうなレトリックをはずして文意をながめれば、これは民主主義の基本である。そんな当たり前のことを今さら説くのかと思わないでもないが、そんな当たり前のことすら実現できていない社会の現実があるから今村の絶望も深いというわけだ。
ともあれ、論議過程について今村の言っていることはそんなにトンデモなこととは私には思えない。ところがどこでどう間違えたのか(そのあらさがしは筆者の関心の範囲外)、『抗争する人間』最終章で「覚醒倫理」を言い出すあたりになると、柄谷が書評で指摘するとおり、煩悩にまみれた常人には不可能な、一種のエリート主義である。
2.覚醒倫理の危うさ
覚醒倫理とは何か。今村自身は次のように言っている。
平たく言えば、煩悩を滅却して涅槃寂静の境地に至ることであり、いわば聖人君子の心がけである。それ自体はまことに尊いことであって、欲望にまみれた私なんかもかくありたいと思わないでもない。しかし、この倫理は中庸を欠くと他人に自己犠牲や沈黙を強いることになる(中庸以外の言い方を今は思いつかないのがもどかしい)。覚醒倫理はあくまで自らに問いかけるものであって、これを世俗倫理の徳目のように他人に課すようになるとあやうい。往々にして「自己変容を目指すことなしには倫理はありえない」は「自己変容を達成することなしには倫理はありえない」と読み替えられ、そうなれば倫理の主体は倫理的エリートに限られ、それ以外のものには沈黙が強要されてしまうからだ。
実際、今村が自らの先駆者として称揚した清沢満之の主宰していた雑誌「精神界」には、足尾鉱毒事件について目を疑うような記事が載せられていた(近藤俊太郎『天皇制国家と「精神主義」―清沢満之とその門下』法蔵館参照)。その記事は、鉱毒の被害者たちのために奔走する田中正造に対して、被災地の人民に権利思想を吹き込んだのはいらぬお世話で、被災地人民は権利思想を捨てよ服従せよ、と説いた挙げ句、人民の苦しみの原因は足尾銅山にあるのではなく人民の心の中にある、という趣旨のことが書かれていた。ずいぶんな覚醒倫理である。これなら覚醒するより居眠りをしていた方がマシというものではないか。
このような覚醒倫理が論議過程の条件とされるならば、民主主義とは聖人の集まりでしか実現されない。愚民はひたすら服従するのみである。
ただし、エリート主義的だから即ダメというわけでもない。聖人または賢者による政治とはプラトン『国家』を持ち出すまでもなく、近代以前ではよくある政治形態だった。洋の東西を問わず、統治者層には程度の差はあれ、また実態はどうあれ、なにがしかの徳が要請された。そもそもプラトンが『国家』で哲人王による政治を理想としたのも、アテネの民主主義が衆愚政治に陥ったことを憂いてのことだったのだから、民主主義の機能不全が当の民主主義のシステム内では解決不能であるかのようなイメージが社会に広がれば、賢者による徳治への期待が生じることもあるだろう。
そもそも議会制民主主義を建前とする日本でも、代議士たちを「選良」と呼ぶことがある。あれはまさにエリートのことだ。問題は、日本の選良がもっぱら人気投票的な基準で選ばれていることだ。日本では芸能的基準と政治の基準が近い。これはアイドルグループの人気投票を総選挙と呼ぶことに違和感を抱く人の少ないことを挙げるまでもない。
確かに政治と芸能には相通ずる側面がある。これは政治体制がどうであるかにかかわらず観測される現象である。政治家の言動をパフォーマンスに過ぎないと切って捨てたつもりになっている人がいるが、とんでもない。政治家たるもの、公の場での言動はすべてパフォーマンスであるとの自覚がないようでは困る。
3.佐倉義民伝
しばらく前のことだが、園遊会に出席した山本太郎参院議員が天皇に「手紙」を渡した騒動について、文部科学大臣が「田中正造のようでけしからん」という趣旨のコメントを発した。本当だとしたら実に嘆かわしい話で、こういう場合に日本の歴史に照らして真っ先に思い出されるべきは佐倉惣五郎(佐倉宗吾)であろう。そもそも田中正造自身が明治天皇に直訴に及ぶ際に佐倉惣五郎を意識していたはずである。下総国の名主佐倉惣五郎が将軍に直訴したというのは史実ではなく、講釈師や歌舞伎作者が伝説に取材して作りあげた虚像だとされているが、それならなおのこと、歴史オンチの大臣はさておき、役者であった山本議員にはこれを意識してほしかった。
いわゆる佐倉義民伝は史実ではないが、江戸時代では特に政治がらみのことをリアルに描写することは禁じられていたので、芝居の観客も講釈の聴衆も、この物語が事実そのままだと思って受けとめたはずがない。しかし、決して荒唐無稽な話ではなく、いかにもありそうな物語として受けとめていたはずである。実際、物語の描く義民惣五郎は、江戸時代後期の一揆指導者の行動のモデルとなったし、その傾向は明治の自由民権運動、そして田中正造にまで引き継がれた。
佐倉義民伝が、なぜそれだけの説得力を持ちえたのか。惣五郎伝説はもともとは一揆や越訴とは結びつけられていなかった。比較的早い時期の記録の一つとして馬場文耕『当時珍説要秘録』(1756)に「堀田相模守領知佐倉宗吾の宮建立の事」がある。それによると「大佐倉町の庄屋大友宗吾といふ者」が領主堀田上総介(上野介正信)の家臣と争論になり、「宗吾不届きなり」として、一族とともに将門山で磔の刑に処せられた。その祟りで堀田上総介は乱心して領地没収となった。その後、上総介の遠戚にあたる堀田相模守(正亮)が佐倉の領主に任ぜられたとき、宗吾の霊を弔うために立派な社を建てた、「さもおそろしき事也」、とこれだけの話である(引用は『叢書江戸文庫12馬場文耕集』国書刊行会より)。
つまり、惣五郎伝説の原型は下総国佐倉に伝わっていた怨霊伝説であった。現在知られている佐倉義民伝は、この怨霊伝説に各地の一揆の指導者たちの事績を結びつけて物語化したものだろう。重税に苦しんだ佐倉領民がはじめは粘り強い順法闘争でのぞんだものの埒があかないどころか藩は弾圧によって不満を押さえこもうとした。ついには各村の名主たちが集まり、一揆か越訴かと熟議を重ねたすえ、一人でも犠牲は少ない方がよいと公津村の名主惣五郎が立って佐倉領民の願いを背に江戸へ旅立つ。一見するとリアルなこのストーリーの方が後世の付け足しであって、史実に近いのは御霊信仰に根ざした怨霊伝説の方なのである。しかし、佐倉義民伝の説得力は、後から追加されたリアルなフィクションによるものであることは間違いない。代表越訴による闘争の一つの典型例を描いているからだ。
田中正造は明治天皇への直訴というパフォーマンスを成功させるべく、幸徳秋水らと事前に協議し、直訴状を新聞で公表して世論に訴える手はずも整えたうえで決行した。これは佐倉惣五郎の将軍直訴が突発的な単独行動ではなく、佐倉領の名主たちと熟議を重ねたうえでだったことに通ずる。山本議員の場合は「手紙」のにせものがネットに出回ってからあわてて訂正する始末で、パフォーマンスというよりアクシデントになってしまった。
もちろん、政治を見物する基準はパフォーマンスの良し悪しのみではない。それは政治という舞台を構成する一側面にすぎないのであって、政治エリートと芸能エリートを同一視して、政治家のパフォーマンスにだけ気を取られているととんでもないことになりかねない。同じ脱原発というメッセージでも、小泉純一郎元首相が言えばもてはやすのに、他の人が言うのには冷めるというのは、見物の側がどうかしている。
芝居ならご贔屓の役者の演技に夢中になっても害はないが、政治においては見物席にいるつもりの人間も実は共演者である。テレビスタジオに動員された観客のように、演出サイドの合図にあわせて拍手喝采したりブーイングしたりしているようでは、眼の肥えた見物とは言えない。
4.覚醒倫理のもたらすもの
閑話休題。今村仁司の覚醒倫理にはどこかグノーシス主義を連想させるところがある。グノーシス主義といっても歴史上の古代キリスト教の異端思想のことではなく、ハンス・ヨーナスによってハイデガー哲学に近付けて解釈された思想のモデルのことである。このグノーシス主義とは何か。中村雄二郎『悪の哲学ノート』(岩波書店)からさわりだけ引いておく。
このような世界観をもつグノーシス主義者にとって、現世の諸権力によって隠された真の神についての知識を得ることが重要になる。救済とは、苦しみに満ちたこの世を創った悪しき造物主によって隠されている真の神を知ることによって可能になる。知による救済という点で一種の覚醒倫理である。この真の神の知識(グノーシス)が、グノーシス派という名付けの由来であることは言うまでもない。
ハンス・ヨーナスによれば、グノーシス的世界観からは二つの態度が生じるという。『生命の哲学』(法政大学出版局)に収められたグノーシス論から引く。
つまり、この現世は偽の世界であり堕落しているという認識を前提にするならば、今村のように暴力の連鎖に覆われた現実を禁欲主義的に観想し覚醒をめざすか、あるいはドストエフスキーの描くロシアのニヒリストたちのように「神がなければすべてが許される」(『カラマーゾフの兄弟』)として個の自由の実現をめざすか。いずれにせよ脱俗的なエリート主義の傾向を持つ。こうした宗教的な(善悪・正邪・聖俗)二元論的世界観と、今村の覚醒倫理が似ていることは注目すべきことである。
5.グノーシス主義の社会的背景
学生時代にハイデガーのもとで学び、グノーシス主義の研究をしていたヨーナスは、当初、研究対象のグノーシス主義に対して実存主義のカテゴリーが「あたかもあつらえて作られていたかのように、ぴったりだった」のは、実存主義が「あらゆる人間的「実存」の解釈に有効」な「普遍的な鍵」であることの証明だと思っていたそうだ。しかし、「普遍的な鍵というものに対する信頼を放棄したあとで、ようやく私はなぜその鍵がその特定の事例にあれほどうまく当てはまったのかと問い始めた。私はまさに適切な鍵を適切な錠に差し込んだのではないか?」とヨーナスは自らの研究を問い直した。
なお、ここで言う「実存主義」とはハイデガー『存在と時間』の現存在分析が想定されていることはヨーナスも明言している。フッサールとハイデガーの薫陶を受けたこの哲学者は、自らの方法論的視点でもあったハイデガー流「実存主義」の方法について、それが歴史的に特殊なものであると言っている。そこで、もしグノーシス主義についての「実存主義的」な読解が成功したのであれば、両者の間には類似の歴史的状況があったのだろうという仮説を立てて、それを検証しようとした。
ヨーナスはグノーシス主義の「徹底的な二元論的気分」は、「人間と世界の不和という内在的な体験」を「経験的な基盤」とするのだとしてその歴史社会的文脈に言及する。それでは「人間と世界の不和」が始まる以前はどうだったのか。
ここではアテネやスパルタに代表される古代ギリシアの都市国家(ポリス)が想定されている。ところが、アレクサンドロスのマケドニア、その後はローマによる世界帝国が実現し、部分と全体、個人と国家の有機的な結びつきは牧歌的な思い出になりはじめたわけだ。そして「都市国家が政治的に後退してゆくことによって、ポリスの市民階級はその本質的な機能と精神的な位置を喪失した。新たに生まれた大国家は、それに比肩しうる関係に自らをゆだねることを拒んだ」。
ポリスというのは、例えばアテネの場合、ソクラテス裁判に見られるように、女性や未成年、奴隷や異邦人は排除されたとはいえ、市民権を持つ市民が全員、議場に集まって評決に参加できる程度の規模である。現代でいえば、「国家」というより、ある地方のコミュニティといった方がよさそうな規模の社会だ。だから、「親和的なコスモスという理念の喪失による人間と世界の疎外関係」という形而上学的な表現には、ポリス的コミュニティが帝国に包括されたことによって、その地位を相対的に下落させた、ということが含まれてくるわけだ。
ポリスの市民にとって、社会の全体は身近なものだったし、全体における自らの位置も手応えのあるものだった。けれども、「世界帝国のアトム化された新たな大衆」にとって「部分は全体に対して意味をもたず、全体はその部分に疎遠」になった。
グノーシス主義の歴史社会的背景についての、このヨーナスの描写が、歴史上のグノーシス主義にどこまで適合するのかは歴史家ではない私にはわからない。ただ、この指摘は、親和的なコミュニティがより巨大なシステムに呑みこまれ解体されたときの、旧コミュニティの成員の反応を描いたものとして読めば、それなりに今でも妥当するような気もする。おそらくヨーナスは、ナチス台頭直前のドイツ社会の雰囲気を回想しながら考えているのではないかと推測する。
6.グノーシス的王権
山本議員の天皇直訴騒動の話に戻すと、天皇の政治利用ということを問題視する向きもあるが、天皇はもともと政治的な存在である。天皇についての議論には文化天皇論と分類される傾向のものがあり、天皇を非政治的権威と位置づける主張がみられるが、歴史をふり返れば天皇という地位からまったく政治性を抜き去ることはとてもできそうにない。
古代の天皇はまさしく為政者であったわけだし、中世でも後白河法皇とか後醍醐天皇のような強烈な政治家がいた。徳川幕府によって政治的実権をきびしく制約されていた江戸時代でさえ、当の幕府の政治的正統性を保証する役割を担っていた。幕末の維新と呼ばれるクーデターの際に倒幕派がかつぎだしたのもその象徴レベルでの政治性を期待してのことである。明治新政府こそ天皇を政治にフル活用したのだ。その後、戦後憲法では「日本国の象徴であり日本国民統合の象徴」とされたが、これも日本の占領統治を円滑にすすめたいアメリカの意図による政治利用である。
こうした天皇観は事柄の一側面を拡大解釈したものとしてすらも単純にすぎると思われるだろう。だが、天皇制について歴史・社会・文化などの次元を総合してとらえようとするとかえってわかりづらくなる。昭和の終わりに天皇論がさかんに議論され、網野善彦(歴史学)・上野千鶴子(社会学)・宮田登(民俗学)による共同討議『日本王権論』(春秋社)や山口昌男『天皇制の文化人類学』(岩波書店)のようなすぐれた成果も生まれた。いずれも第一級の知識人による天皇論だが、古代から近代までを統一的にとらえようとしたために、近代天皇制の政治性があまり注目されなかった。
天皇の政治利用が問題視されるのは近代の天皇に政治的実権がなく、ふつうの意味での政治にはかかわらなかったからだろう。大日本帝国憲法では天皇は統治者と定義されていたが、昭和天皇が君主として自覚的に国政に対する実権をふるった唯一の例は、ポツダム宣言の受諾、いわゆる「ご聖断」だった。その理由は政府が決定できず天皇に判断を求めたからだとされる。昭和天皇の主観的理由としてはそうだったのだろうと思う。「国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ」という条文を昭和天皇は立憲君主制と理解していたからである。それは天皇機関説事件についての昭和天皇の感想とも一致する。
しかし一方で、明治新政府は発足当初、祭政一致の神権政治を掲げていたから、明治憲法には「神聖ニシテ侵スヘカラス」の一句が入った。憲法学上はあるいは国家主権の神聖不可侵を言ったものとの解釈もありうるかもしれないが、大多数の国民にとってはこの条文は天皇が神であることを言ったものと理解されただろう。権現様(徳川家康)だって神様なんだから、京都からやって来た天子様を神様とするのはそんなに違和感がなかったはずである。そして、もとはといえばこれまた天皇の政治利用にすぎなかった統帥権干犯問題から、軍部を中心に天皇神格化の傾向が強まり、天皇機関説排撃、国体明徴運動へとつながっていった。結果として大日本帝国の天皇は神聖帝国の君主となった。たとえ天皇自身が主観的には立憲君主たらんとしても、その地位についた人間は神として扱われ、人とのあいだには越えられない距離が設定された。
神聖帝国の君主と現実政治の関係は、あたかもグノーシス主義の世界観の描く隠れた真の神と現実世界のように見えないだろうか。グノーシス主義においては、もちろん神はいるが、われわれ人間は偽の神たる創造神デミウルゴスの支配下にあって、真の神は世界を完全に超越している。この超越は、この世界の中にあって、あるいはこの世界に関わるものとして、比較にならないくらいに優れているという意味ではなく、全く世界と関わらないという意味での超越である。このグノーシス的世界観は、神聖君主である天皇と世俗権力である政府との二本立てであった帝国の政治秩序とよく似ているように思う。
天皇直訴は超越者にこの世の悲惨を訴えるようなものだが、超越者は決してそれに応えない。二二六事件の青年将校たちが期待した天皇親政など望むべくもない。戦後に三島由紀夫が二二六事件をモデルに描いた小説『英霊の聲』が応答しない超越神への呼びかけに似ているのも、青年将校と彼らに共鳴した三島にとって天皇は神であるべきだったからだ(「などてすめろぎは人間となりたまいし」)。
田中正造の天皇直訴はそれに似ているようであっても実は違う。田中がしたことは、佐倉義民伝という当時広く共有されていた範型的ドラマの枠組みを採用することによって世間の人々に訴えることだった。当時の人々は明治天皇の馬車に訴状を差し出す田中正造の姿に将軍の駕籠に越訴する芝居の佐倉宗吾を重ね合わせて受けとめただろう。その結果として足尾鉱毒事件の情報はイメージ豊かに伝えられて世論を喚起した。田中正造の天皇直訴というパフォーマンスは、天皇にではなく民衆に向けられていたのである。
あいにくと現代ではこの手は使えない。もちろん、佐倉義民伝のような広く大衆に共有されている世直しの物語がないからだが、それだけではない。天皇について民衆の持つイメージが変わった。神聖皇帝であった昭和天皇が敗戦後「人間宣言」をして、晩年にはついに無垢な聖老人にそのイメージを変容させた(大塚英志『少女たちの「かわいい」天皇』角川文庫)。無垢という点で聖性を維持しているが、君主としての威力は大きく減じた。だから、仮に佐倉義民伝に代わる物語があったとしても、天皇直訴は政治的パフォーマンスとしては残念な結果に終わる。それではどうすればよいか。
7.それではどうすればよいか
それではどうすればよいか。山本議員がどうすればよかったかは関知するところではない。私たちが、いや、選良でも人気者でもないこの私がどうすればよいか、そう自問して、焦燥と朦朧のあいだで立ち止まる。
久野収編『中井正一 美と集団の論理』(中央公論社、1962)には「中井正一が週刊新聞『土曜日』のために、巻頭言として無署名で執筆した時事評論」が再録されており、これに同書の編者久野収による「『土曜日』について」と題された文章が寄せられている。『土曜日』とは「昭和十一年(一九三六年)七月から昭和十二年十一月まで、京都でつづけられた反ファシズムの同人グループ的文化新聞」で、発行当初は3000部だったが昭和十二年(1937)には7000部に達したというから、現在の出版事情に照らしても堂々たる成果である。
しかし時はすでにあまりにもおそく、もはやどうすることもできなかった。将来、こんな回顧をしないですむようにしたいものだが、まだまにあうのか、もう遅すぎるのか、見極めの難しい状況である。
ひとつ、確かに言えることは、岐路に立たされたときに自信過剰は禁物だ、ということだ。
ヨーナスのグノーシス主義論では、グノーシス主義に、ナチスが台頭した時期のドイツ社会の風潮と、ナチスに加担したハイデガーに重ね合わされていた。
グノーシス的な世界観を背景にしたニヒリズムは法や規範を越えた放縦主義的人間を生み出す。これをヨーナスは「いかなる秩序にも属さないプネウマティコス(精神的人間)」と呼び、それは「法を超えており、善悪の彼岸にある。自らの「知」のもつ力によって彼自身が法なのである」と言う。「自らの「知」のもつ力によって彼自身が法」であるような「彼自身」とはハイデガーを暗示している。ヨーナスのハイデガー批判の眼目は、このプネウマティコスの傍若無人さに向けられている。
ヨーナスの批判が、ハイデガーの哲学に即して妥当かどうかは棚上げにしておく。ただ、ハイデガーに同情的な木田元も『ハイデガーの思想』(岩波新書)では、彼のナチス加担について「思いあがり」ということを挙げている。
精神的人間の傲慢さは何に由来するのか。ヨーナスは、グノーシス主義とハイデガーに共通する反コスモス的・反ノモス的自由は「被投性」というハイデガー哲学の人間観に由来する、とヨーナスは捉えている。「すなわち、生命は世界のなかへ、光は闇のなかへ、魂は肉体のなかへ投げ入れられている」。このように投げ捨てられた存在にとって、現在(現実)には意味も価値も、コスモスもノモスもない。現在(いま・ここ)には「私が従うべき法」はないからである。ヨーナスは「決意のためのノモスを欠いたままのたんに形式的な決意性は、無から無へと向かう先駆となる」という辛辣な言葉で、旧師ハイデガーとの訣別を宣言した。
それではどうすればよいか。ハイデガーがどうすればよかったかは私の関心の範囲外である。ノモス、つまり何らかの規範が必要であることだけはわかる。ヨーナスの議論に従うならば、「決意のためのノモス」とは、コスモスとの連続性を保ったものでなければならないだろう。ヨーナスが有機的自然観の復権を唱えるようになるのは、こうした省察があってのことだったのだろう。しかし、現代の日本では「自然」という語には過剰なイデオロギーが読み込まれかねない心配があるので、私としてはその途はとらない。
それではどうすればよいか。もはや紙幅も〆切も限界をとうに超えているので、ごく簡単に、かつ乱暴に見通しだけを述べる。「決意のためのノモス」として採用できるのは、歴史ということになるだろう。歴史を読みなおし、語りなおすこと。歴史修正主義の提唱と思ってもらっていい。歴史学に「もし」や「たら・れば」は禁句だとされるが、そこにあえて「もし」や「たら・れば」を持ちこむのが私の歴史修正主義である。もしあの時こうだったら、こうしていれば、その後の結果はどうなったろうか、と問いをはさみながら歴史を読みなおしてみること、空想歴史小説の構想である。古い言葉でいえば実録小説が念頭にある。佐倉義民伝もそうしたもののひとつである。
しかし、歴史物語は既成のものだけでも莫大な数にのぼる。将来を考えれば無限に思える量の歴史物語のなかから、現在の自分の置かれた状況と引き比べるのにふさわしいものは何か。それもまた「決意のためのノモスを欠いたままのたんに形式的な決意性」にゆだねるわけにはいかないだろう。
【コメント】】えげつない企み
広坂さんは、論考の最後で、ノモスの復権の必要を訴え、そのための具体的方法として、歴史に「もし」や「たら・れば」を導入する「私の歴史修正主義」を提唱している。
これは、なかなかに挑発的な発言だ。
しかし、よく考えると、この修正主義が、いま新自由主義と新国家主義の隆盛のもとで猖獗を極めている本物の(?)歴史修正主義とは、似て非なるものであることは明らかだ。なぜなら、ここで言われている修正主義とは、歴史に「もし」や「たら・れば」を持ち込むということ、つまり、それが嘘であることを自認しつつ、あえて歴史のなかに自己の想像力を投げ込んで、もう一つの歴史を構成し、そこから現在の自分自身を問い返すというような、積極的・肯定的態度のことを意味していると思えるからだ。「私が言っていることは嘘である」と言いながら「史実」を主張する(修正する)歴史修正主義者を考えることなど出来ないだろう。
歴史はわれわれにとって、おそらくは「事実」の次元以外のところで、変更することも否認することも不可能な重みを持つという実感に基づいているからこそ、「もし」や「たら・れば」を導入する「私の歴史修正主義」は、ノモスの新たな構築という難事への道を開くのである。この「実感」に基づいたノモスの新たな構築こそ、広坂さんの目指すところであろうと思う。
***
ヨーナスは、コスモスの解体という危機に関係するグノーシス的態度から生じる二つの傾向を、放縦主義と禁欲主義と名付けたのだという。前者が、ファシズムに代表される「力への崇拝」と深い結びつきがあることは明らかだろう。
そして、この態度と、今村が「覚醒倫理」と呼んだ、禁欲主義的・あるいは倫理主義的な態度との間に同根性を見出したことが、ヨーナスの認識の重要性の一つなのだろう。それらはいずれも、人々の生をコスモスの構築へと結びつけるような「実感」の領域を、押し潰してしまうものだと思えるのである。
広坂さんが提唱する方向は、おそらく、それらの誘惑や抑圧に抗して、人々の生を歴史の形成という、実践的であると同時にコスモロジカルな行為へと、(再び)接続させようとするものである。
***
歴史修正主義は、人々を歴史という実践から切り離す。むしろ、その切断こそ、歴史修正主義という技術が生み出された理由であろう。
歴史修正主義は、やはりファシズムに似ている。
それらは、抑圧的な社会を変革し、歴史的・社会的実践と個々人の生との結びつきを回復しようとする、それ自体は真っ当な願望に関わって生じているのであるが、その願望が国家や権力によってすっかり骨抜きにされ、システムの維持に都合のいいように変質させられたなれの果てが、ファシズムであり歴史修正主義者なのである。
カール・マンハイムは、行動主義的政治運動としてのファシズムが持つ、新たな社会の形成に通じる力を高く評価しながらも、それが結局は人間の表面的な部分にしか働きかけることが出来ないことに、その限界を見出していた。
マンハイムはそこから、「計画」による人間社会の根本的な改変という、しかしやや平板なファシズム超克の見通しを示したのだが、広坂さんの「超克」の方法は、おそらくもっと根底的である(大阪弁でいえば、えげつない)。
つまり、それはファシズムが危機の時代に生きる人々を引きつける、その根本的な力を国家から奪いとって(あるいは奪回して)、実践的でコスモロジカルな生の次元を社会形成の土台として作り上げることに動員しようとする企みであるように、僕には思えるのだ。この奪回への道筋の模索に関わるのが、冒頭に近いところで語られている、今村(ベンヤミン)の「論議過程」のアイデアなのではないかと思う。
ロールズを読んだこともない僕には、イメージの掴みにくい箇所なのだが、おそらくここで述べられている「普段着のまま」の論議過程から成立してくる民主主義の姿と、生の「実感」を歴史的実践に接続させようとする「私の歴史修正主義」の提唱の大胆さとは、強いつながりを持っているのだろうと思う。
それは、時には偏見や嘘を含んでも、人が生きていることの実感に基づいた「言葉」のぶつかりあい、つむぎ合いのなかで、はじめて形成されていくような社会の土台のイメージだと思える。
嘘を虚言から区別し、人の心を傷つけないために述べられる「嘘」(秘密、と言ってもよいが)の価値を擁護しようとしたのは、ルソーだった。民主主義の根幹を、国家の支配に対する、この私的な領域の小さな「秘密」「嘘」の守護にこそ見出すその視点を、やはりベンヤミンも継承しているのである。
広坂さんの語る「私の歴史修正主義」は、この「嘘」や「言語」の力にこそ関わっている。
繰り返すがそれは、いわゆる歴史修正主義とは、まったくの反対物である。
歴史修正主義やファシズムにも、それらが出現する以前の社会システムにも、同じものが欠けている。それは、人々の生の「実感」を、歴史的実践へと接続するコスモロジカルな力である。むしろその接続を切断するところに、それらの(芳しくない)成立の重要な要件があるのではないかと思われる。
歴史に「もし」や「たら・れば」を導入する試み(戯れ)とは、この力の奪回を目指すことだ、と僕は勝手に理解している。
奪い返す当の相手とは、もちろん、「この」国家である。
Web評論誌「コーラ」21号(2013.12.15)
<現代思想を再考する>第3回[第2期]:グノーシス的日本(広坂朋信)
Copyright(c) SOUGETUSYOBOU 2013 All Rights Reserved.
|
| 表紙(目次)へ |