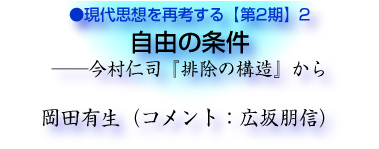|
|
|
Web評論誌「コーラ」 |
|
■創刊の辞 ■本誌の表紙(目次)へ ■本誌のバックナンバー ■読者の頁/ご意見・感想 ■投稿規定 ■関係者のWebサイト ■プライバシーポリシー |
|
<本誌の関連ページ> |
|
■「カルチャー・レヴュー」のバックナンバー ■評論紙「La Vue」の総目次 |
Copyright (c)SOUGETUSYOBOU |
|
|
|
はじめの頃(『コーラ』16号)に今村仁司の80年代の仕事について書いたことがあったが、そこでは最も有名な著作『排除の構造』については論じることが出来なかった。
今回は1989年に単行本が出版されたこの本の内容について考え、現在の社会状況との関わりを探ってみたい。(以下、引用文のページ付は1992年出版のちくま学芸文庫版のもの)
Ⅰ 承認欲望と模倣欲望
論の糸口としたいのは、同書の最後の章「Ⅵ 排除の構造」である。
今村はこの中で、彼が「未開社会から近代社会までを貫く、社会形成の論理」(p199)として提示する、いわゆる第三項排除効果を形成する、幾つかの契機を挙げて順次論じている。
第三項排除効果とは、根源的な暴力のカオスの状態から何らかの「第三項」を析出し排除することで、秩序や体系といった社会的な安定性が形成される作用のことだ。それは、排除によるシステムの形成・維持という面を持つと同時に、運動としてシステムの閉鎖の不可能性を示し、その解体と乗り越えとの道を開くという、二重の働きをするものだとされる。
第三項排除は、不可視の、また唯一の働きであり、この働きのなか以外のところに解放の現実的な条件を見出すことはできない、というのが今村の論なのである。
また、本書の考察できわめて重要なことは、近代資本は貨幣という形で第三項排除を社会に「全般化」した、とする考えだ。
この考察は、現在の政治と社会の状況を考える上でも、重要な手掛かりを与えてくれるものだと思う。だがここでは、まず、今村が語る「承認欲望」と「模倣欲望」との違いというテーマに注目したい。
今村は、人間の社会的な欲望のうち、「基本的には意識的な欲望である」(p206)であるところの承認欲望を、第三項排除効果の最も重要な生命力にして原動力であるとして重視する(p208)。他者に承認されたいという欲望こそ、人間の社会関係の、また文化の、あるいは人間が人間として生きることの根底をなす力であり、第三項の排除による安定的な社会関係の形成も、この欲望の力があるからこそ遂行されるのだ、というのである。
これに対して、共同体内に生じるカオスの原因ともなる模倣欲望とは、人間が無意識的に互いに模倣し合ってしまう傾向を指す概念であろうが、これは特定の局面においてのみ登場するもの、承認欲望の転化形態でしかないものと考えられている。「条件つき承認欲望、それが模倣欲望である」(p209)。
ヘーゲルにならって承認欲望を重視する今村が、ここで批判的に言及するのは、ジラールの模倣欲望論だ。
未開社会における供犠から近代文学の内的構成まで、あらゆる現象を模倣欲望という観点から分析し、説明するジラールの文化論的思考は、承認欲望の存在を否認し、追放しようとするものであると、今村は述べる。
つまり今村が言っていることは、ジラールは承認欲望と闘争とによって示される社会的な次元を否認し追放したがために、本来は一種の社会的行為に他ならない模倣欲望というものを主観主義化・心理主義化させてしまった、ということである。
社会的・闘争的な次元を追放してしまったがゆえに、ジラールの「欲望の現象学」は、いわば脱歴史化され、心理主義的次元に閉ざされることになった。このように今村は、ジラールの模倣欲望論を批判するわけである。
また今村は、ジラールの模倣欲望論の意義を、プラトンが模倣(ミメーシス)という行為のなかに直感していた暴力性を、その思想の中で明示したことにあるとする。
そして、こう書く。
ここでは、社会的な欲望の「病的」な要素は、模倣欲望に専一的に結びつくものとされ、承認や闘争というものは、それ自体では「健康」なものとして肯定されている。模倣欲望は、社会の「危機」の、そしてそれをもたらす(「傷つけられた」ことに起因する)ルサンチマンの感情の唯一の母胎だということになる。
ここで気がつくのは、今村の議論では、模倣欲望がまるで承認欲望や闘争の影のようなものとして捉えられていること、純粋なものとして取り出された社会発展のプロセスの剰余であるところの、閉鎖的な表象として描かれているということだ。
今村の文章は次のように続く。
ここで、社会的暴力の制御不可能なまでの拡大、「危機」の際限のない膨張が、模倣欲望と不可分なものとして描き出されている。
今村はさらに続いて、暴力の相互模倣による社会の危機(カオス)の状態を、共同体のメンバー全員が互いに互いの「分身」となる状況として捉え、それを「群集」化という現象と結びつける。模倣欲望によって社会に生じる相互暴力状態は、「分身」と「群集」という二つのモメントによって特徴づけられる、とされるのである(後で詳しく触れる)。
* * *
今村はこの後、第三項排除効果による社会形成において、この第三項(の排除)を社会に内面化させるためには日常での「儀礼」的な実践が重要だということを指摘し、その点では近代以後の資本主義的な社会も、それ以前の社会と何ら変わらないことが強調される。現在では、たとえば貨幣という第三項の使用という「儀礼」を通して、第三項排除はわれわれの社会に内面化されていくと考えられるからである。ヴィトゲンシュタインがフレーザーに関して述べたように、近代社会もまた魔術的・呪術的なのであり、それは「合理化された」儀礼的実践によって形成・維持されているのである。
さらに今村は、排除の行為における「視線」の重要性を強調し、「排除の視線」を、対象を物化・石化する「メデューサ効果」という言葉によって説明する。われわれは相手を対象化することによって社会生活を送っているといえるが、対象化とは認知そのもののことなのだから、対象化の視線自体は排除とは呼べず、対象化が物化に転じたときにそれは排除の視線となるのだと、今村は述べている。
このあたりについても、よく考えてみたいところだが、先に進もう。
Ⅱ 変身と分身
さて、今村は、この「排除の視線」との関係において、排除されるもの(第三項・犠牲者)の「変身」(メタモルフォーゼ)という、大変興味深い論点に言及していく。
ここで今村が強調するのは、排除されるものに生じる変身は、排除する共同体の側による強制の結果にほかならない、ということである。第三項は強制的に変身せしめられ、日常の儀礼的実践を通して、イデオロギー的に、それは「第三項であるがゆえに」排除された(される)のだと思いなされるに到る。今村は、排除・差別の自明化・内面化のメカニズムを、マルクスによる貨幣のフェティシズム分析と、アルチュセールのイデオロギー論の枠組みのなかに見出しているのである。
ここも詳しく見たいところであるが、先に進もう。ただ、このくだりでは、第三項が「聖性」と「アブジェクト性」(被差別性)という正負二つの属性を有するものとして、魅惑的で、また絶対性を帯びたものとして表象されること、またそれは第三項に共同体が加えた排除の暴力の反映のようなものでもあることが指摘されていることを、特に書いておく。
さて、今村はここで再び「分身」のテーマに言及し、変身と分身とは根本的に区別されるべきものだ、ということを強調する。分身は、先に書いたように模倣欲望の産物である。共同体の成員が同質化し、相互に「兄弟/敵」となることによって、「分身性」が社会に現出する。それが危機とカオスの状態を到来させる、とされる。
つまり分身は、危機状態にある共同体の成員にのみ関わる現象だが、それに対して変身は第三項排除に関わる。第三項が排除されるような場においてだけ変身は生じるのだ。
ここでの今村は、承認欲望(排除・闘争)が関係するような社会性の領域を、模倣欲望が支配するカオス的な場から区別して救出し、そこに意識を持った主体が関わる社会の「正当」な発展と解放の可能性を見出したいのではないかと思う。
事実、この直後に今村は、歴史上の変身は、たいていは強制的変身であるが、変身には「自由な変身」の可能性もある、と述べるのだ。そのことは、第三項排除効果の、「こういってよければ、「ユートピア的」契機である。」(p237)とされる。
ここに、第三項排除効果による歴史の進展を、根源的な「力」(暴力)の働きとして捉える今村の史観の、未来への希望が託されていることは確かだろう。排除の効果の一つとして生じる変身が、自由なものであり得る余地があるのならば、この歴史の論理への肯定が支配のメカニズムからの解放へと帰結する道が開かれ得るはずである。
こうした、「自由な変身」を重視する今村の意図は、次の文章によく示されている。
承認欲望を模倣欲望から切り離して、歴史の意識的な進行過程を「自由」へと接続する(解放する)こと。そのための契機として、「自由な変身」が重視されている。共同体による強制ではなく、諸個人による自由な行為としての変身が可能となるならば、それこそが非同一的な社会を、すなわち第三項排除という装置を必要としないような社会を可能にするはずだ。ここでの今村は、そのように語っている。
このような「自由な変身」の萌芽でありうるものとして今村が注目するのが、「暴力を避けるための変身」、すなわち「防御変身」と呼ばれるものだ。
ここで、防御変身というかたちをとった、排除される第三項の「自由な変身」が、「魔術・手品・詐欺・ペテン」の形態をとりうるものであると述べられていることには、特に注意したい。繰り返して言えば、今村の理論における第三項とは魅惑するものであり、時には暴力的なもの、また絶対性を帯びて出現するものでもあるありうるのである。
Ⅲ 群集化
さて、以上のように論述を進めてきた今村が最後に取り組むのは、19世紀以降に出現した「群集化」社会に、どう対処するかというテーマである。
今村によれば、群集現象の原動力となるものは、模倣欲望である。危機や不安に直面した共同体のメンバーたちが模倣欲望の虜となり、同質化へと突き進もうとするとき、諸個人の群集化が生じる。歴史の中で群集化が生じることは、社会や秩序の危機の兆候であるといえる。
この流動的な状況が、第三項排除と相関的な「全員一致」によって解消されるとき、秩序は表面上回復されて日常が再び現出するのだが、この日常はもちろん、日々遂行される排除の暴力と、その痕跡を抹消する儀礼的実践によって維持されるわけである。そうした日常を生きる人たちは、もはや「流動性群集」ではないが、管理され馴化された「固定性群集」である、とされる。
今村の近現代社会分析は、この群集化の二つの局面を射程におさめて展開されたものといえるだろう。貨幣と資本という「全般化」する第三項排除を中心にした社会の展開(資本主義経済)は、個の解放ということをただちにもたらすわけではなく、一方では、伝統的秩序の破壊によって群集化という状況(流動性であれ固定性であれ)を生じさせる。つまり、そこにはつねに模倣欲望の力による反動化の危険が口を開いているのである。
このように今村は、群集化という概念によって現代社会の危機的・暴力的な性格を見事に捉えているのだが、ここでやはり気になることは、この群集化の危険があくまで模倣欲望という共同体的・無意識的な、つまりは社会の意識的な発展にとっては副次的な領域に結びついた事柄として考えられていることである。
つまり、「力」を原動力とし相互承認を通して解放に向かって進むべき人間社会の論理
にとっては、副次的・偶有的なものでしかない模倣欲望という無意識的な領域の磁力に、なぜか引き寄せられてしまうことによって、諸個人は群集化に向かう、という構図になっているといえるだろう。
この観点によってでは、群集化をめぐる問題を、社会形成や資本の運動の総体にとって、あくまで偶有的な現象としてしか見出すことが出来ないのではないか、と思われるのだ。
Ⅳ ファルマコンと力の形而上化
ところで、この本、『排除の構造』の前半部では、プラトンのテクストに登場する「ファルマコン」という概念をめぐって、たいへん興味深い考察が展開されている。
ファルマコンというのは、毒でもあれば薬でもありうるような両義性をはらんだものを指す概念らしいのだが、プラトンはこのファルマコン(の要素)を呪術や魔術に結びつけ、哲学や法律、公共性の領域から追放してしまったのだと、今村は書いている。全体主義的な性格をもつプラトンの思想の根底にあるものは、ファルマコンの伝染性や誘惑力に対する怖れなのだ、というのである。
今村の論では、ファルマコンこそ公共空間(秩序)や論理的思考から排除される第三項の表象であり、それは排除されることによって現実の社会のひそかな動力になっていると、考えられている。
こうしたファルマコンとしての第三項の力についての考察は、特に第三項が近代社会においては貨幣と資本の運動という形で全般的にあらわれ、社会全体の群集化を招いたという観点に到ることによって、ファシズムが産み出される過程のすぐれた洞察たりえていると言えるだろう。
しかし問題は、今村のこうした思考自体が、「力」(暴力)から余剰な要素を切り捨てて実体化する「力の形而上化」とも呼べる枠組みのもとで成立しており、したがって呪術的な魅力をもつこの危険な「力」の働きを、十分に対象化することが出来ていない点にあると思われる。
このいわば形而上化された「力」(ファルマコン)について、今村はベンヤミンやデリダに触れながら、このように語るのである。
このように、潜在的にはポジティブな意義を持つもの、というよりも解放をもたらしうる唯一の力として考えられたファルマコンが、歴史の現実のなかに出現する姿を描いたのが、先に引いた「防御変身」をめぐる文章だ。引用部分を拡大して、もう一度引こう。
ここでは、ファルマコンである「自由な変身」の萌芽としての防御変身が「魔術・手品・詐欺・ペテン」として立ち現われて、権力的・攻撃的・暴力的な相を帯びるのは、「特定の条件の下」に限られるとされている。
逆にいえば、ファルマコン(自由変身)の危険性は、本質的なものではなく、特定の条件の下でのみ生じる偶有的な性質へと、いわば低減されているのである。
このことによって救済されているのは、ファルマコンの潜在的意義であるとともに、「狡智と策略」という性格をもつ「自由な変身」というものの純粋性、未来を切り拓くものとしての無垢な性格のようなものだといえるだろう。
だがわれわれは、いかなる変身をなすことにも全能の権限を持つとされる、この「自由」の地位をこそ、再審に付すべきではないか。そのことは、ファシズムのみならず、新自由主義下の生存のあり方の問題にも関わる。
Ⅴ ファシズム再考と力への屈服
ここで、今村の卓越した考察の助けを借りて、歴史上のファシズムと資本主義経済(経済的自由主義)との関係を考え直しておきたい。
19世紀以降の世界は、産業資本主義の発達と結びついた諸大国による帝国主義的競争の時代に入ったが、このうち英米仏などの先発資本主義国は、第一次大戦の勝利を機にそのヘゲモニーを正当化して確立させる。これが一面では自由主義経済体制と呼ばれ、また他方ではワシントン・ベルサイユ体制とも呼ばれる「強者の論理」の支配である。敗戦国ドイツのワイマール体制は、ドイツ国民にとっては、この「強者の論理」の押し付けと受け取られたのであり、やがてファシストたちは、そのような後発資本主義国の国民の心情(ルサンチマン)に沿うような方向に自らの政治的主張を形成し、その勢力を拡大していったのだと考えられる。
今村の群集化の議論は、支配的諸国によって体現された自由主義経済の論理が、共同体の伝統や秩序を破壊することで、後発資本主義国の人々をファシズムという相互暴力状態へと追いやる過程をよく説明するものだが、大事なことを取り逃していると思う。
それは、人々を模倣欲望と相互暴力の状態においやる力は、共同体のなかだけに由来するのではなく、むしろもっぱら国際的な資本主義の運動のなかにあるものだ、ということである。ファシズムは、流動化状態に陥った人々が「力」を希求し信奉することであるが、そうした魔術性・呪術性は、まさしく資本の運動を支える原理である。自由主義的体制という名のもとに形成された秩序は、そうした「力への信奉」「力の支配」を、いわば正当化して、敗戦国民をはじめ世界中の人々に突きつけた。ルサンチマンがファシズムへと流れ込んでいった過程は、そのことと無縁ではない。
敗戦国ドイツに襲いかかった国際的な資本の力は、たんに伝統的な生活や秩序を破壊したのではなく、むしろ人々の中にあった「力への渇望」を解き放ったのだ。
同様のことは、ワシントン体制下の日本に関しても言えるだろう。
このように考えれば、ファシズムとは、資本の運動のひとつの様態であることが分かる。国際的な資本の運動は、ある条件下では、ファシズムのような政治状況を成立させることによって、その発展と支配を遂行するのである。
このような「力への渇望」という時代の特徴を、いち早く、また最も見事に思想の形に結実させたのは、もちろんニーチェだろう。自由主義的体制が実際には奴隷的な「勝者の論理」に基づくことを告発することで、ファシズムの援護になったともされる彼の思想が、新自由主義が胎動を始めた70年代以後の欧州や80年代の日本で大きな関心を集めたのは、この点から考えても至極当然のことだ。
* * *
ニーチェは『道徳の系譜』において、歴史を、生命力や精神的強者に向けられる民衆のルサンチマンが、それを統治・管理する制度の姿をとって人間の生を抑圧する過程として描いたといえる。生を抑圧する支配的なシステムは、人々の心の無意識的な部分と別に存在しているわけではない。近代史にあてはめて言えば、「勝者の論理」である自由主義的体制(ベルサイユ体制)は、それが力(貨幣・資本)に魅了されたものである限りで、ファシズムへの希求に帰結したドイツ民衆のルサンチマンと同じ質の運動としてあるのだ。
問題は、この「力=システム」の支配に対して、イエスというかノーというかである。
ニーチェは、彼が「禁欲主義的理想」と名付けた、巧妙な道徳的内面化の装置を、ルサンチマンの統治・管理の、一つのモードとして捉えている。人間の暴力性や模倣欲望といったものは、内面化、言い換えれば意識化の過程を通して処理(管理)することもできるが、時にはそのような過程を経ることなく処理される場合もある。
意識化の過程を経る場合には、それは主体の承認欲望と「健康な」社会秩序に関わり、それを経ない場合には、共同体的な自我の模倣欲望と相互暴力状態に関わるといえるだろう。いわば、市民社会とファシズムだが、それらはいずれもルサンチマンの現実態とも呼ぶべきシステムの力による、生の抑圧の形態なのである。
ニーチェがこのような観点に立つことが出来たことは、彼の思考が、生(力、権力)の非意識的・非主体的な層に定位するものだったことを示している。それ故に彼の思想は、「力の形而上化」によって承認願望の次元を模倣願望から分離したものとして捉えることなく、生の社会的な過程をその無意識的次元を含んだ総合的なものとして掴むことができたのである。
今村とは違ってニーチェは、「力」の展開としての歴史を、非主体的・無意識的な次元を含むものとして捉えたのであり、そこから「資本」の運動の問題と、共同体のルサンチマンやファシズムというような、いわば「ネーション」の問題とを、一続きのものとして捉える思想への道が開ける。その道だけが、秩序の形をとるばかりでなく、時には相互暴力状態という姿をとることもあるシステムの支配からの、解放の可能性に通じているはずである。
* * *
『排除の構造』が出版された当時、日本でもてはやされていたフランスのいわゆるポストモダン系の思想家、ドゥルーズやフーコーといった人たちは、ニーチェの思想、とくにその「遊戯」というテーマに注目していたのだが、今村における「ファルマコン」への注目も、そうした同時代的な趨勢のなかに位置づけられるのではないかと思われる。
そうした趨勢は、真理による一義的な支配を逃れて、「自由な変身」を目指そうとするような態度に関わっている。彼らに共通するのは、全体主義的体制・思考や、管理社会のテクノロジーに抗して、力や欲望として表象される人間の生の自由を守護していこうとする姿勢だった、と言っていいだろう。
ファルマコンに注目して社会の動きを捉える今村の考察は、資本主義社会がはらむ危険性と可能性について、たしかに重要な示唆を与えてくれるものだが、ただ問題は、そこではファルマコンとして現われる「自由」の表象が、全能なもの、本質(純粋形態)においては批判の余地のないものとして示されていることから、支配的なファルマコンである貨幣の運動としての現代資本主義の展開も、基本的にはあくまで肯定されるべきものとして捉えられる、という点だ(この点は、ドゥルーズたちの場合も同じだが、ただ彼らの思想においては、システムの支配的な様態としての主体概念への対峙が徹底的である)。
これはつまり、ここでは社会形成の動力としての「力」(暴力)が、その純粋な形態においては「解放」をもたらす唯一の可能性であるような、絶対的原理として立てられている、ということである。
純粋なものとして考えられた「力」は、意識をもった個の自由と完全に重ねられ、その個によって追求され展開される運動としての資本主義を根本において批判しうる契機は、この思想にはないのである。つまりそれは、この思想が「力への屈服」の教義になっている、ということだ。
こうした今村の思想の特徴は、先に述べたように、「力の形而上化」ということに由来する。「力」から余剰の要素を切り捨てて、個の「自由」と完全に重なり合うようなものとしてそれが表象されたときに、この思想は、力を見据える思想であることをやめて、力の支配に奉仕する思想となるのである。
Ⅵ 力の外部性
では、ここで切り捨てられた、力の余剰な要素とは、果たして何か?それは一言でいえば、「力の外部性」であると思う。
以下の文章を、ここであらためて引く。
ここからうかがえることは、今村の暴力論においては、暴力の非主体的な要素、ないしは非意識的な要素が、本質的でないものとされていることである。ここに、ニーチェが切り開いた可能性との、見えにくいが決定的な隔たりがある。
実際には、力(暴力)は、それが働くとき、行使する主体(の自由)にのみ関わるわけではない。今村も論じているように、それは暴力によって排除される他者にも深く関わっているのだ。ところが今村の論理では、この力の非主体的な要素は、「ヴァルネラビリティ」という言葉によって非本質化され、あるいは「強制」という語によって否定的に意味づけられて、歴史を形成するとされる「自由」の概念の肯定性から裁断されてしまうのである。
つまり、今村の語る「力=自由」には、この暴力(排除)を被る他者の存在、またその他者との関わりにおける個というものが考慮される余地はない。そこでは「力」は、その外部性を切り落とされて、自由な個のなかに、まったく内部化されてしまっている。
これは視点を変えて言えば、今村の力の思想が、他者が被る(被った)暴力の記憶を意識から消し去ろうとする、現代資本主義の欲望に同化され、その装置として働いてしまっている、ということである。それは、「力=自由」として捉えられたこの欲望を肯定することで、新自由主義の原理に屈服し続けるしかない。今村の議論は、「力」に魅了されるままになる人間の「自由」を無批判に認めてしまうので、システム批判(解放への契機)の核心というべき、「力への抵抗」という要素を持つことが出来ないのだ。
そして、ファルマコン(貨幣)の魔力への信仰に奉仕する思想であることをやめないがゆえに、この思想はまた、資本主義の運動のひとつの様態としてのファシズムの魔力にも抗しえないのである。
実際には、解放の方途としての「自由な変身」を可能にするのは、暴力にはらまれた他者に関する記憶であり、あるいは、他者からの強制を介してのみ自由に達しうるような、微細な、動物的な、非意識的な存在である自己の発見という出来事である。
ニーチェが切り開いたシステム批判・主体批判の可能性は、こうした方向、つまり主体の自由に重ねられた「力」の支配を解体する方向において、継承されるべきだろうと思う(この、自由と力との分離という意味では、ドゥルーズやフーコーの思想にも、欠けている部分があると思う)。
自由を、悪しき力から解き放つこと。
ドゥルーズとガタリが、動物やマイノリティへの生成変化を語るとき、そこでは個はむしろ変化することを他者に強いられている。そこで述べられている「力」とは、本当は、私の制度的な個の解体を強いる、このような微細なものたちの記憶と存在を表現する概念なのだ。その記憶だけが、「自由な変身」の権能を、私に与える。
それだけが、システムとファルマコンのあらゆる支配から、私たちを脱却させる手掛かりとなるだろう。倫理的な力だけが、自由をもたらすのだ。
そこから開かれてくるのは、非意識的な相互承認の可能性、意識を有する主体を単位としないような脱暴力的な関係性構築への道だろう。暴力の介在は不可避であろうけれども、暴力に関わる他者の存在と記憶とに対して絶えず身を開くことによって、力の論理への屈服を拒み続けるような、開かれていく共同性。
そのかすかな展望を手放さずに進むことによってしか、われわれが力の支配を脱却する道は開かれないはずである。
【コメント】「不気味な時代」
広坂朋信
「七月二一日の参院選は、大方の予想通り自民党の圧勝に終わった」。この書き出しは、実は本誌「コーラ」編集長から「ギリギリまで待ってやるから予定稿を用意しておけ」と言われて参院選前に書いておいたものだ。そして実際にその通りになってしまった。民主党の議席が激減し、共産党が政権批判票を吸収して議席を若干増やすだろうということまでマスコミの予想通りだった。まるで、人々は新聞の予測記事を読んで、そのシナリオにそって投票したかのような結果となり、参院選翌日の大新聞各紙の朝刊などはすべて予定稿で、記者たちは久しぶりの休日を楽しんでいたのではないかと勘ぐりたくなるほどであった。
さて、岡田さんの論考で取り上げられた今村仁司『排除の構造』には、今回の選挙結果とそれを受けた政局を無責任に見物するにあたって役に立つキーワードがたくさんある。例えば、「群集化」。
とくに解釈する必要もないだろう。今や目の前の事態を見ていれば、今村の言っていたことがよくわかる時代になった。あえて屋上屋を架すならば、群集化した現代社会に市民はもういないということだ。近代市民社会の市民どころか「よき古き庶民や常民の理念も現実も、とうの昔に消え去った」(今村、p247)というから、お先真っ暗である。そして今村は市民なき近代社会の行く末を次のように描き出す。
分身とか模倣とか独特の概念が並んでいるが、岡田さんの論考で一通りの解説はなされているし、今村自身のロジックは明快であるから付け加えることは一つだけ、80年代の終わりに書かれたこの文章がその後の三十年の日本社会をよく見とおしているということだ。「自由主義デモクラシーの政治的理想も超越論的主観性の哲学的理想も、群集社会で溺死したがゆえに、回顧的に復活する」というくだりなど、アーレントやカントがもてはやされたころを髣髴とさせる。そして今、無意識と催眠による「ウンハイムリッヒ」な時代、不気味な時代が到来したというわけだ。これは市民なき時代の行く末だと言ったが、既に過去にお手本がある。この後で今村は「ウンハイムリッヒ」な時代の思想家としてハイデガーを挙げている。市民なき時代の不気味さとはファシズム到来の予感だったわけだ。現代の日本の場合、アベノミクスの破たん後、政治・経済の混乱の原因として現行憲法がスケープゴートにされることになるのかどうかが、一つの分岐点となるだろう。
今村理論は選挙後のドタバタを見物するのにも役立つ。惨敗した海江田民主党は菅直人元首相に離党を勧告した。これはスケープゴートの典型である。小沢一郎、鳩山由紀夫両氏に次いで創業時のリーダーを粛清してどうしようというのか。老害を追放して中堅・若手によって党が再生される? そんな期待をもっている人はよほどのとんまだ。そしてそのとんまの集団が現在の民主党である。
スケープゴートによって組織が再生されるには条件があるのだ。とにかくなんでもいいから生け贄を差しだしたり、異端者に負の遺産を背負わせて排除したりすればどうにかなるというものではない。それですむなら古代の王国はすべて生き残っている。殷の紂王なんてずいぶん熱心に人身御供を捧げたが、それがもとで人心の離反を招いて滅んだという説もある。『悪霊』のシャートフ殺しのモデルとなったネチャーエフ事件も、結局は犯罪が露顕して組織は崩壊した。
今村仁司『排除の構造』から引こう。
民主党執行部がとんまのは「儀礼(とその実践)」を忘れていることである。聖性の契機、ある種の宗教性といってもいい。もっとくだけて言えば田舎芝居である。自民党はこれが上手だ。野党時代の自民党を懸命に支えた谷垣禎一前総裁を切って安倍新総裁をかつぎ政権復帰したが、不義理の埋め合わせをするように谷垣氏を法務大臣につけた。民主党に政権を奪われたときの敗軍の将・麻生元首相も今は副総理格の財務大臣である。大の虫を生かすために小の虫を殺しますが、大の虫が栄えれば死んでもらった小の虫も厚遇しますよという田舎芝居を情緒たっぷりに演じてみせる。
その点、民主党は創業者の首を次から次へと切って、次はどうするつもりなのか。あの党にはリーダーを支える力もなければ、結党時の功労者に報いる情もないと、もとからの支持者に見限られるだけだろう。いや、もう見限られているからこのざまか。つまりは新撰組なのである。粛清に次ぐ粛清で純化路線を取った挙げ句、人材は底をつき、いざというときに薩長を足止めする役にも立たなかった不忠者である。もっとも「排除の論理」は1996年の民主党結党時からあったのだと言ってしまえばそれまでだが。
* * *
岡田さんは、今村の議論では第三項排除効果、つまりは暴力のシステムを追認していることになるとおかんむりだが、ある事柄の特徴を描きだすとは、それを後から(追って)認識することに他ならないのだから、あまり責めるのも気の毒だ。しかし、もちろん、岡田さんの指摘は正しい。まさに後知恵で言えば、今村はこの『排除の構造』発表後も近代社会における暴力のシステムの分析を精力的に続け、断ち切ることの出来ない暴力の連鎖をひたすら凝視し、ついにはそこに人間の業、原罪のようなものを見てとって、ある種の宗教的な諦念に至ったのである。岡田さんの言う「力の形而上化」の到達点は今村晩年の『清沢満之の思想』(岩波書店)に読み取れるだろう。
今村理論は田辺元『懺悔道の哲学』と似たタイプの思想なのである。田辺の『懺悔道』が敗戦の反省に立ったものではなく、実はすでに戦時中から唱えられていたものであることを考えあわせると、このタイプの思想が、岡田さんの言葉を使えば「力への屈服」の教義になってしまうのも当然なのであった。
どうしてそうなってしまうのか? 私見では、人類史的課題を一挙に解決しようとするからである。それはできない。たとえ理論上のことであるにせよ、神ならぬ身の人に完全な仕事はできない。あれが足りない、ここが拙い、ああ、もっとやりようはあったのにと反省するのは、不完全であっても何かをなし遂げた場合のことであって、それが人間の常である。優秀な人、熱心な人、己に厳しい人ほどしばしばこのことを忘れる。
できることからコツコツと、そんなことは今村も百も承知だったはずである。それがわかっている人でなければあれだけの業績をあげることはできない。ところが、優秀な人が熱心にコツコツやっていると、愚公移山の譬えよろしく、あと少しで不可能なことに感じられた何かに到達してしまうのではないかと思わせられる境地に至る。しかし課題は暴力のシステムからの解放という遠大な理想である。一個人、一世代でなしうるものではない。ここで欲をかいてしまうと無駄に絶望してしまう。ここが思案のしどころ、ということで今回はここまでにいたしとうございます。
Web評論誌「コーラ」20号(2013.08.15)
<現代思想を再考する>第2回[第2期]:自由の条件─―今村仁司『排除の構造』から(岡田有生)
Copyright(c) SOUGETUSYOBOU 2013 All Rights Reserved.
|
| 表紙(目次)へ |