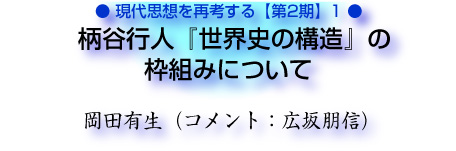|
|
|
Web�]�_���u�R�[���v |
|
���n���̎� ���{���̕\���i�ڎ��j�� ���{���̃o�b�N�i���o�[ ���ǎ҂̕Ł^���ӌ��E���z �����e�K�� ���W�҂�Web�T�C�g ���v���C�o�V�[�|���V�[ |
|
���{���̊֘A�y�[�W�� |
|
���u�J���`���[�E�������[�v�̃o�b�N�i���o�[ ���]�_���u�k�� Vue�v�̑��ڎ� |
Copyright (c)SOUGETUSYOBOU |
|
|
|
���J�̑ԓx�ύX�E��]����̌n��
�@80�N��Ȍ�̓��{���\�����]�ƁE�v�z�Ƃł��长�J�s�l�̒���w���E�j�̍\���x���o�ł��ꂽ�̂́A2010�N6���̂��Ƃ��B���̎��A�����D���A�v�z�D���̐l�̊Ԃł́A���̖{�͑傫�Șb��ɂȂ����Ǝv���̂����A�l��80�N�O�ォ��̈��ǎ҂ł���Ȃ���A���̖{������܂œǂ܂��ɂ����B�����A���J�ɑ���S���A�������炩�������蔖��Ă������߂ł���B
�@�����A���̑��̊T�v�̂悤�Ȃ��Ƃ�������Ă���w���E���a���ցx�Ƃ����{���A2006�N�Ɋ�g�V������o����A������̕��͓ǂB������A���҂̎咣�̑�g�͒m���Ă����킯�����A���̓����Ƃ������A�v�z�̒����̂悤�Ȃ��Ƃɂ��ẮA���̖{��ǂ�ł͂��߂Ēm�邱�ƂɂȂ����ƌ����Ă����Ǝv���B
�@���ɂ���������ۂ������R�́A���ʂ̑傫�������ł͂Ȃ��āA���́w���E�j�̍\���x�̏����̂Ȃ��ɁA���̂悤�Ȃ��Ƃ�������Ă��邩��ł���(�ȉ��A���p���́A���ɏ����̕\�L���Ȃ��ꍇ�́w���E�j�̍\���x��g���X�A2010�N����)�B
�@�ŏ��Ɂu���̂悤�ȃI�v�e�B�~�Y����ƌĂ�Ă���̂́A���҂�����܂ŁA1999�N�̃V�A�g���̔��O���[�o���[�[�V�����^���ɏے������悤�ȁA�u���{�ƍ��Ƃւ̑R�^���v���A����Ύ��R�ɍ������z���ĘA�т��Ȃ���W�J�����ʂ������Ă������낤�ƁA�u���R�Ɓv�l���Ă������Ƃ��w���Ă���B
�@����2001�N�́u�X�E�P�P�v���_�@�Ƃ��ē˂�����ꂽ�̂́A�����͂��̂悤�ɂ͓W�J���Ȃ����̂��Ƃ������ƁA�R�^�������̃��x�����z����ƁA���{�ƍ��Ƃ͂��̌��͐��������炳�܂ɂ��āA�^���f������A���邢�͗͂����ʼn���������ł��܂��B
�@�܂��A�l�[�V�����̗͂������ɓ��������B����́A�X�E�P�P����̃A�����J�Љ�̋����Ԃ���v���o���Ă����炩���낤�B���҂����̖{�̒��Ŏ������Ă���悤�ɁA�������z�������R�ȘA�тƂ����悤�Ȃ��̂́A��@�ɍۂ��Ĕ�������鍑�Ƃƃl�[�V�����̍�p(�푈�ւ̈ӎu�j�ɑ��ẮA���܂�ɖ��͂Ȃ̂ł���B���ہA19���I�̒鍑��`�̎���ɂ����Ă��A20���I�̓�x�̐��E���ɂ����Ă��A�J���҂̃C���^�[�i�V���i���Y���ƌĂꂽ���̂́A���Ƃ̘_���ƃi�V���i���Y���̕����̑O�ɁA�J��Ԃ��ł��ӂ���Ă����B
�@�X�E�P�P�ɂ����ĕ��J�́A�u��k�v�̊ԂɎ��݂��Ă���i���{�⍑�Ƃɂ��j�u�T��v�̐[���ƁA��@�ɍۂ��Ă͂����炳�܂Ɏp������킵�āA�R�^�����₷�₷�ƕ��f�����͉����Ă��܂����Ƃ̎��͂Ƃ������́A�܂��l�[�V�����̍R����З́A�������������ɒ��ʂ��āA�v�z�̍��{�I�ȑԓx�ύX�̂悤�Ȃ��̂�������ꂽ�B�����������Ƃ��A�����ɏ����Ă���̂��B
�@�����ɒ��ʂ������ƂŁA�����̂���܂ł̍l���ɕs�\���Ȃ��̂����������Ƃ𗦒��ɔF�߁A����܂łƂ͍��{�I�ɈقȂ����d���Ŏv�z���\�z���悤�Ƃ���B����Ȑ錾����������ǂ܂��ꂽ��A�Â�����̈��ǎ҂̈�l�Ƃ��āA����͂���Ύ������g������悤�Ȃ��Ƃł�����̂ŁA���������ēǂ܂�������Ȃ��B
�@���̖{�Łu�v�z�̒����v���͂��߂Ēm�����A�Ə������̂͂��������Ӗ��ł���B
�@�Ƃ���ł��̑ԓx�ύX�Ƃ́A�ǂ̂悤�Ȃ��̂ł��������B��L�̈��p���̏I���̕��Łu�i�����j�v�ƂȂ��Ă��镔�����牺���A�ꕔ�J��Ԃ��ɂȂ邪���p���Ă݂�B
�@���J�́A����܂ł́u��]�Ɓv�I�ȑԓx�A�}���N�X��J���g�̒�����e�N�X�g�Ƃ��ēǂނ��ƂŌ����ɉ�����Ă����Ƃ����ԓx�̌��E�����o���āA��������߁A���_�I�̌n��n�邱�Ƃ����ӂ����Ƃ����̂ł���B
�@���́u���͍��{�I�ɕ��w��]�Ƃł���v�Ƃ������ȋK����A�͂��Ƃ�������Ƃ��낪����B�����ł́u���w�v���u��]�v���A�ʂɔے�I�ȈӖ��ŗp�����Ă錾�t�ł͂Ȃ����낤�B�����A�����ɂ͓��R�Ȃ�����E������B�����ŁA�����݂̍�l�ƁA���̂Ȃ��ɑ��݂��Ă��鎩���̎p�Ƃ��A�V���ɖ��炩�ƂȂ������́A�ʂ̕��@�A�u�����Ă������A�܂����ł��������v���@���Ƃ邱�Ƃɂ����B�����q�ׂ��Ă���B
�@�]���̔�]�ƓI�ȑԓx�A���Ē��Ҏ��g�����y���Ă������{�̎v�z�j�̗���ɂ����Ă͍]�˂̒��ߊw�ɂȂ�����̂Ƃ��l������Ǝv�����A��������ĂāA�}���N�X�������Ȃ����悤�ȎЉ�\���ɂ��Ắu���_�I�̌n�����v�d���ɐi�ށB���̑ԓx�ύX���Ӗ����Ă�����͉̂����낤�B
������
�@���̗��R�́A�����Ŗ����Ȑ������Ȃ���Ă���B
�@�{���ɂ����镪�͂̏d�v�Șg�g�݂ł���u���{���l�[�V�������X�e�[�g�v�Ƃ����V�X�e���́A�O���w�g�����X�N���e�B�[�N�x�i��]��ԁA2001�N�j�ɂ����Ă�����Ă������̂����A���J�ɂ��A���́u�I���ȃV�X�e���v���ŏ��ɖ��m��(�������ϔO�_�I��)�������Ƃ�������̂́A�w�[�Q���ɂ�闝�_�I�̌n�ł������B���Ƀ}���N�X�́A���̃w�[�Q���̑̌n��������B���_�̗��ꂩ��ᔻ���āA���Y�l���ɂ��ƂÂ���(����������\���Ƃ���)���E�j�̉𖾂Ƃ������Ƃ��s�����B���J�͂��̃}���N�X�̕��͂ɂ��ƂÂ��A���̃e�N�X�g���u��]����v�Ƃ����d���ł���܂Ŏd�������Ă����킯�����A�X�E�P�P�̎��Ԃ����āA�����Ɍ��E��������������Ȃ����ƂɂȂ����B
�@����͏�L�̂悤�ɁA���Ƃ�l�[�V�������A�}���N�X�������悤�Ȃ���Ȃ�u�㕔�\���v�ł���Ƃ����Ă��܂����Ȃ��悤�Ȍ����I�ȗ͂ł��邱�Ƃ�˂�����ꂽ���炾�B
�}���N�X���w�[�Q���̑̌n�I�v�z�����̂Ă������A�܂�u���{�v�݂̂Ȃ炸�A�u�l�[�V�����v��u�X�e�[�g�v�ɂ��A���̂��̗B���_�I�ȍ���������ƍl����������Ȃ��B
�@����炨�̂��̂̍������A���炩�̌`�ŋ��łɘA�ւ���悤�ȃV�X�e���Ƃ��āA�Љ�I������c������K�v������Ƃ������Ƃ��B�����ŁA�}���N�X�����Y�l���������\���Ƃ������ƂɊ����āA���J�͐V���ɁA�����l���Ƃ����T�O�������\��(����)�Ƃ��Đ��E�j���𖾂���悤�ȗ��_�I�̌n���\�z���邱�ƂɂȂ����̂ł���B
�@�ȏオ�A����̌n����邱�Ƃɓ��݂����R�ł���B
�@�����A����ɕ��J�ɂ��A�w�g�����X�N���e�B�[�N�x�Ɩ{���Ƃ̍��ق͂������ł͂Ȃ��B�傫�ȈႢ�́A�{���ɂ����ẮA�w�[�Q�����s�����悤��(�u���{���l�[�V�������X�e�[�g�v�Ƃ���)�V�X�e���̂���Ȃ�L�q�Ƃ������Ƃ��z���āA���̃V�X�e�������z���铹�����Ƃ����p�����A��薾�m�ɂ���Ă��邱�Ƃ��B����́A�w�[�Q���I�Ȏv�z�̂�����ɂ���ẮA�V�X�e���̊�����������Ώ̗g���邱�Ƃ͂ł��Ă��A��������z����\���́A�ނ��������Ă��܂��Ƃ������Ƃ��Ӗ����邾�낤�B
�@�l�����̖{��ǂݎn�߂āA�܂��ŏ��ɋ��������Ƃ́A���J������܂ł܂������ᒆ�ɒu���Ă��Ȃ��Ƃ�����ŏ���Ɏv���Ă����w�[�Q���̎v�z���A�����̖`������A�傫�ȈӖ��������Č���Ă��邱�Ƃ������B����܂ŁA���́w�R�[���x�ł̘A�ڂ̂Ȃ��ŁA���J�����̑�\�i�ɂ����āA�W�O�N��Ȍ�̓��{�̂�����u����v�z�v�̑傫�ȓ������邢�͌��_�ł�����̂��u�w�[�Q���̕s�݁v�Ɩ��w���Ă����Ǝv�����A���̖{�ł͂��̕��J���w�[�Q���̎v�z�̏d�v����͐����Ă���B����͂܂������l�̕s���̂������Ƃ���ŁA���J�͂���܂Ŗ��O�͓��ɏo�����Ƃ��A�w�[�Q���̎v�z�̏d�v�ȓ_��������ƒ͂�ł����̂ł��낤�B����A���O���o���ĂȂ������Ƃ����̂́A����Ȃ�l�̎v���Ⴂ�ŁA�����}���N�X��J���g��t���C�g�قǂɂ͑�������邱�Ƃ��Ȃ������A�Ƃ������Ƃ����m��Ȃ��B
�@�����A�{���Ńw�[�Q���̖������ɂ������Ă���̂ɂ́A���ɂ��傫�ȗ��R������Ǝv����B����́A���̂X�E�P�P���߂��鎖�ԂɊ֘A�������Ƃł���B���Ȃ킿�A�L���ȃw�[�Q���w�҂ł���R�W�F�[���̒�q�A�t�����V�X�E�t�N���}���͂��߂Ƃ����l�I�R���̃C�f�I���[�O�������A�X�E�P�P���ċN����������C���N�푈(�A�����J�ɂ��C���N�N��)�ɍۂ��Ď����o�����̂��w�[�Q���̗��j�N�w�ł���A�Ȃ����u���j�̏I���v�ƌĂ��l�����������Ƃ��B
�@���̕����ł́A�w�[�Q���̎v�z�A���J�̌��t���g���u���{���l�[�V�������X�e�[�g�v�Ƃ����V�X�e���̍I�������L�q�������̑̌n�́A�V�X�e���̊��������u�̗g�v���A�������瓦��o�邱�Ƃ̕s�\����ǂގ҂Ɏv���m�点��A���s�I�ȓ����������Ă��܂��B
�@���J�͖{���ɂ����āA���̃w�[�Q���̎v�z�A���邢�͗D�ꂽ�̌n�I�Ȏv�z��ʂ����A������ύX���悤�Ƃ���l�X�̈ӗ~��}�����ނ悤�ȓ����ɑR���悤�Ƃ����̂��Ƃ����悤�B���̂��߂ɂ��炽�߂ď�������邱�ƂɂȂ�̂��A�J���g�Ȃ̂ł���B
������
�@�����A���̃w�[�Q���̑̌n�I�v�z�ƃJ���g�̎v�z�Ƃ́A���J�ɂ�����W���ɂ��Ă͌�قǏ������Ƃɂ��āA�����ł́A�{���ɂ����长�J�̑ԓx�ύX�A�܂��]����̌n�ւƂ����v�z�̂�����̕ύX�����Ӗ��ɂ��āA���������l���Ă݂����B
�@�����𗝘_�I�ɐ����������悤�ȑ̌n�����Ƃ������Ƃ́A�����Ɍ����Ă��錻����c�����Ă���ɑR������悤�ȁA��̍\�z�������グ�悤�Ƃ���c�݂��낤�B�����A���ꂪ�^�Ɍ����̐��E��I�m�ɑ����Ă�����̂Ȃ�A���̔F���́A�v�l���鎩�����g�̑��݂����A���̐��E�̃V�X�e���̂��Ȃ��ɑ��݂��Ă�����̂Ƃ��Ē͂�ł���͂��ł���B
�@�܂�́A���_�I�̌n�̍\�z�Ƃ́A�������������`�����Ă���V�X�e��(���J�ɂ��u���{���l�[�V�������X�e�[�g�v)�̈ꕔ�ł��邱�Ƃ��A�v�l���铖�l�������Ƃ������Ƃ��Ӗ����Ă���̂��B���������āA�������c�����ᔻ����V�X�e���̂Ȃ��ɁA������\������ꕔ�Ƃ��Ď��Ȃ��m���ɑ��݂��邱�Ƃ��A�v�z�Ƃ��ӔC�������Ĉ�����ӎu���A�̌n�̍\�z�Ƃ����s�ׂɂ͍��߂��Ă���͂��ł���B�����ɁA�v�z�̑ԓx�ύX�Ƃ������Ƃ̈Ӗ�������B
�@���̕��͂̂͂��߂ɁA�l�͂��Ĉ��ǂ��Ă������J�̎v�z�ɁA���鎞������S�����ĂȂ��Ȃ������Ƃ��������B�������������A�Ȃ��l�͔ނ̏������t�┭���ɂ���قǎ䂩��Ă����̂��낤���B���܍l���Ă݂�ƁA����͂܂��������J�������悤�ɁA�ނ̎v�z���u��]�v�I�Ȃ��̂��������炾�Ǝv���B���猻�����������悤�ȗ��_�I�̌n��ł����Ă�̂ł͂Ȃ��A�����̉��炩�̑̌n��v�z���]����Ƃ����d���Ō�����_���悤�Ƃ���B��������a����ďo�Ă���̂́A�����������̏��ΏۂƓ����ʒu�ɗ����ƂȂ��A���S�ȍ��݂��炻���������낵�čْf���Ă������̂悤�ȑS�\�����A�ǂގ҂Ɋ��������镶�͂������̂ł���B���̊��o���A�l�ɂ͂ƂĂ��S�n�悩�����B����́A���������̌����Ώ�(���E)�Ɠ�����̒��ɂ������ɑ��݂������Ă���Ƃ����ꂵ�����A�Y�ꂳ���Ă����悤�ȑ̌����������炾�B
�@���������A����Β��z�I�ȕ��J�v�z�̖��͂́A�ނ�NAM�Ȃǂ̉^�����H�ɓ��荞�ނ悤�ɂȂ����̂��_�@�ɁA�l�̒��ł͋}���ɔ���Ă������B�l���g�̐g�ӂ̕ω������낤���A���J�̕��͂┭���ɂ��܂�S�������Ȃ��Ȃ������R�́A���̂��Ƃ��傫���Ǝv���B
�@���������^�����H�ւ̎Q�����A���J�̂Ȃ��łǂ������Ӗ����������̂��͕�����Ȃ����A�X�E�P�P�̏Ռ����o�ĐU��Ԃ�ƁA�����܂ł̎��g�̎v�l�̂�����S�̂��A�ނɂ́u���w��]�Ɓv�I�Ȃ��̂��Ɗ�����ꂽ�悤�ł���B���̂��Ƃ́A���g�̎v�l�����܂������̏��ΏۂƓ�����ɑ��݂�����̂��Ƃ��������������Ă��Ȃ����Ƃւ̎��o�A����������A�����ɑ��Đ^�ɗL���ȑR�I�v�z�ƂȂ肦�Ă��Ȃ��Ƃ������o���Ӗ�����̂ł͂Ȃ���(����́A�̌n�I�v�l�Ɣ�]�I�v�l�̂ǂ��炪�D�ʂ��邢�͗L�����A�Ƃ��������ƂƂ͕ʂł���)�B
�@�l�́A���J�����̖{�ő̌n���u�����Ƃ������Ƃ́A�X�E�P�P�Ƃ����o����������v�z��̏Ռ����Ƃ߁A���̐V���Ɍ��o���ꂽ�����̂��Ȃ��ŁA�R�I�Ȏv�z���`�Â����Ă������Ƃ���ӎu�̌����Ƃ��đ�����ׂ����Ǝv���B���̐V���Ȍ����̑��e�Ƃ́A�Ƃ�킯���Ƃ�l�[�V�����̋�̓I�Ȏ��݁A���́u�\���I�Ȏ�́v�Ƃ��Ă̈З͂Ƃ������Ƃł���B
�@�u���{�����Ɓ��l�[�V�����v��T���猩�o���Ă���͂�����u��]�v����̂łȂ��A�ނ��낻�̃V�X�e�������Ă��錻���I�Ȉꕔ�Ƃ��Ď����̑��݂Ǝv�l�����o���A���̔F���̂��ƂɑR�I�Ȏv�z��z�����Ƃ��邱�ƁB���ꂪ���_�I�̌n�̌`���Ƃ������Ƃł���A����͂���Ό����̃V�X�e���̂��Ȃ��ɁA���̃V�X�e���̌����ɉ����A���̃V�X�e���̍\���ɑ�������悤�Ȃ��̂Ƃ��Ĉ�̑R�I�\�z�������グ�悤�Ƃ����A���o�I�ȁu���v�̎p��(���Ȃ̐������E���͐��̎��o)�Ƃ��Ăׂ�悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ����B
�@�w�[�Q���̐��k�ȓN�w���A���܂Ȃ����͂ȈӋ`�Ɨ͂����Ƃ����̂��A���ꂪ���Ȃ̌��͐��̎��o�̂��ƂɁA�V�X�e���̎��p�Ƃ��Ď��g�̍\�������グ�Ă��邱�ƂɁA���R������̂��낤�B���_�A���̎��Ȃ̈�(���͐��E������)�ւ̎��o��������Ƃ��A���̈Ӌ`�Ɨ͂́A�l�I�R���ɂ�����悤�ɒP�ɐl�X��}��������̂ւƕς���̂����B
�@�����Ċ��ɏ������Ƃ���A���J�̏ꍇ�́A���̑̌n�ւ̈ӎu�Ƃ��������I�ȗ͂��A�̌n(�V�X�e��)�̗}����Ŕj���邽�߂ɂ����g�p���悤�Ƃ���̂ł���B
�@�Ƃ���ł��̂��߂ɂ́A�w�[�Q���̂悤�ȊϔO�_�I�̌n�ł͂Ȃ��A�}���N�X�̂悤�ȗB���_�I�ȕ��@���Ƃ邱�Ƃ�����Ƃ��K�v�ƂȂ�B���̕��@�������A�����I�E�����I�����̐l�Ԏ��g�ɂ����ς̓����������邩�炾�B�������J�ɂ��A���̗B���_�ɂ͌��E���������B����͍��Ƃ�l�[�V�����̎��ݐ��ɂ��ēI�m�ɔc���o���Ȃ��悤�Ȃ��̂ł��邵�A�݂̂Ȃ炸���{�Ɋւ��Ă��ݕ���M�p�Ƃ������́u�㕔�\���v�I�ȑ��ʂɂ��Ă͏\���ȗ������o���Ȃ����̂�����ł���B���̓_�ł́A�}���N�X�����@��̗��R���炠���Đ�̂Ă�(�ƕ��J�����Ȃ�)�w�[�Q���̑̌n�I�E�����I�Ȑ��E�F���̏d�v���ɁA���炽�߂Ē��ڂ���K�v������B
�@�����ŁA���E�̍\�����u���{���l�[�V�������X�e�[�g�v�̃V�X�e���Ƃ��ēI�m�Ɍ���߂��w�[�Q���̓��@���A�����̃}���N�X��`�̂悤�ȒP���ȉ����\���̗���(���Y�l���ɂ��ƂÂ���)�ɂ���Ă͑������Ȃ������̑S�̑���c������_���Ƃ��ďd�����Ȃ���A����ɐV���ȈӖ��ł̗B���_�I�ȍ���(�����l��)��^����悤�ȐV���ȑ̌n��n��o�����Ƃɂ���āA���̊����Ɏv����V�X�e������̒E�p(���)�ւ̓���_���I�Ɏ������Ƃ��A�{���̊�}�ƂȂ�̂ł���B
�@
�l�̌����l���̐���
�@���J���u���{���l�[�V�������X�e�[�g�v����̉���̓����������߂ɏ������Ă���̂́A��q�����悤�ɁA�w�[�Q���ɑ���ᔻ�҂Ƃ��ẴJ���g�̎v�z���Ƃ�����̂����A���̂��Ƃ������O�ɁA�����̓ǎ҂ɂ͎��m�̂��Ƃ��낤���A�{���Ō���Ă���u���E�j�̍\���v�̊�{�I�Ȑ}���A�l�̌����l���̊W�ɂ��ĊȒP�ɐ������Ă����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B
�@���J�́A���E�j���`�����鉺���\��(�y��ƂȂ�d�g��)���AA(�ݏV)�AB(����ƍĕ��z)�AC(���i����)�AD(X)�Ƃ����l�̌����l���Ƃ��čl���Ă���BD��X�Ƃ���Ă���̂́A�ǂ������Ăѕ������Ă�������������炾�Ə����Ă��邪�A���ꂪ�ނ��u���O�v�Ƃ��Ē��Ă���A�ڎw�����ׂ������l��(�Љ�I�E�����I�W��)�̂�������ƌ����Ă������낤�B
�@���j�I�ȋL�q�ɂ����ẮA�����Љ�ɂ����Ă�A���x�z�I�Ȍ����l���ł���A���Ƃ��`�������悤�ɂȂ��B���x�z�I�ƂȂ�A����Ɏ��{���Љ�ɂȂ��C���x�z�I�ƂȂ�A�Ƃ������Ɉڍs����B������D�ɂ��ẮA����͎x�z�I�ȗ͂Ƃ��Ď��݂�����̂ł͂Ȃ��A���Տ@����Љ��`�ɂ�����悤�ɂ����܂Łu���O�v�Ƃ����p�ŗ��j�ɉe����^����A�Ƃ����킯�����A�厖�Ȃ��Ƃ́A���j�̂ǂ̒i�K�ɂ����Ă��A�����l�͕����I�ɕ�������ƍl�����Ă��邱�Ƃł���B
�@���Ƃ��Ε����Љ�Ƃ����Ă��A���Ƃ�ݕ��o�ς̖G��̂悤�Ȃ��̂͂��łɂ��邵�A����Љ�ł��ݏV�������S���������Ă��܂�(����Ȃ�i�V���i���Y���̐����̍������Ȃ��Ȃ�)�Ƃ������Ƃ͂Ȃ��A�܂����R�s��̊g��ɂ���č��Ƃ����ł����萊�ނ��Ă��܂��ȂǂƂ������Ԃ����ۂɂ͐����Ă��Ȃ��̂��݂�A���̂��Ƃ͂悭�����ł��悤�B
�@��������l���́A���j�̐i�s�ɂ��������ė}�������Ƃ������Ƃ͂��邪�A����͏��ł��邱�Ƃ͂Ȃ��A�`��ς��đ�������̂ł���A�܂�����ꍇ�ɂ́u��A����v�Ƃ����d���Ō����ɓ���������Ƃ����B���ꂪ���J���_�̔��ɏd�v�ȃ|�C���g���B
�@���Ƃ��A�����Љ�̌���������A(�ݏV)�́A�x�z�I�ȗl���ƂȂ������Ƃ̑̐��̓����ł��@�\���āA���Ƃ⋤���̂̂������l�X�ɋK�肷��Ƃ����B�Ȃ��ł����ڂ���Ă���̂́A���ꂪ���j�̊e�i�K�ŏW���I���Ƃ�ꐧ���Ƃ̌`����W����@�\���ʂ��Ă����Ƃ��������ł���B
�@�܂��A���{���Љ�ł���u�ߑ�Љ�v(���݂������Ɋ܂܂��)�ł����A��q�́u���{���l�[�V�������X�e�[�g�v�̂����AA(�ݏV)�̓l�[�V�����ɁAB(����ƍĕ��z)�̓X�e�[�g(����)�ɁAC(���i����)�͎��{�ɁA���ꂼ��Ή�����̂ł���A�w�[�Q�������@�����悤�ɁA���̎O�͑��ݕ⊮�I�ȉ~���`�����Ă���B���Ƃ��A���{��`�o�ς̔��B�ɂ���Đ��������u���W���A�Љ��ߑ㍑�Ƃ��݂Ă��A�����ł͌����l��B�������Ȃ��Ă��܂����킯�ł͂Ȃ��A�����u����ƍĕ��z�v����u�[�łƍĕ��z�v�ւƍ��Ƃ̎x�z�`�Ԃ��ό`���������ł���B�܂����l�ɁA���{��`�o�ς̔��B�͏@�������̂Ȃǂ̓`���I�����̂�j�Ă��܂����A���ꂪ�������ăl�[�V�����Ƃ����ߑ���L�́u�z���̋����́v�ݏo�������ɂȂ�̂ł���B�����Ƌ�̓I�Ɍ����Ȃ�A���R�s��̐N�P�I�Ȋg��Ƃ����C���[�W�́A(���R�s�ꉻ�Ƃ͎��͍��Ƃ̌��͂ɂ���ĉ\�ɂȂ��Ă�����̂ł���ɂ��ւ�炸)���Ƃɑ���l�X�̋A�˂̍��܂�ƃi�V���i���Y���̕����Ƃ����`�ŁA�u���{���l�[�V�������X�e�[�g�v�V�X�e���ւ̑R�^���f�E������Ă��܂��̂��B
�@����ɑ��Č����l��D�́A���E�j�̓W�J�̏�ł��A�����܂Łu���O�v�Ƃ��Ă��̓��������o��������̂Ƃ��Ę_�����Ă���B����(�����)�o���̌����́A�t���C�g�̂����u�}�����ꂽ���̂̉�A�v�ł���B��͂菘���̂Ȃ��ɁA��������B
�@�܂������ɂ����ẮA�����q�ׂ��Ă���B
�@D�́u��A�v�Ƃ������Ƃ́A���_�I�̌n�ɂ���Ĕc������鐢�E�j�̃V�X�e���̂Ȃ��ŕK�R�I�ł���B���̕K�R���́A�u���{���l�[�V���������Ɓv�́u�g���v�������̖ڕW�Ƃ��Čf�����邱�Ƃ������Â��邾�낤�B���E�V�X�e���͂������Ɋ��������A���̊��������w�������Ă���̂́A���̃V�X�e���́u�g���v��ڎw�����Ƃ̏d�v���ƕs�����ɑ��Ȃ�Ȃ��A�Ƃ����킯�ł���B
�@�����Ŗژ_�܂�Ă���̂��A�l�I�R���ɂ���Ďg�p���ꂽ�w�[�Q���̑̌n�I�v�z�̗}���I�ȈӖ��������t�]�����邱�Ƃł���͖̂��炩���낤�B�w�[�Q�����ϔO�_�̌`�Ȃ��猩�o�����A���̌����̃V�X�e���̂������(�ߋ��̃}���N�X��`�҂̗\���ɔ�����)�����ƌĂԂ����Ȃ����̂Ȃ̂����A���̊����ȃV�X�e���̓����ɂ́A���ꂪ�u�g���v����Ă��������A���Ȃ킿�u�}�����ꂽ���̂̉�A�v�̕K�R������߂��Ă���B����ނ���A���̌����̃V�X�e���̘_��(�̌n)�̂Ȃ��ȊO�ɁA���́u�g���v�ւ̓����J�����͑��݂��Ȃ��Ƃ����̂��A���J�̌����Ƃ���Ƃ���ł��낤�B
�@
�J���g�����̈Ӗ��E���O�ƌo��
�@�Ƃ�����A�u�����l��A(�ݏV��)�̍������ɂ�����v�Ƃ��Ă̌����l��D�������A�ߑ㐢�E�ɂ����Ċ������ꂽ�u���{���l�[�V�������X�e�[�g�v�ɂ��O�ʈ�̂̃V�X�e������̉���̌����ł���B���̌����l���͖��m�ɁA�u���^�̗́v�ɂ���Č`�������ƌ���Ă���(���S�R�Ȃ�)�A����͏d�v�Ȗ����͂��ł���Ǝv���̂����A���̏��_�ł͂���ɂ͏ڂ����G����Ȃ��B
�@�����ő厖�Ȃ̂�(�����ł���Ƙb�̖{�ɖ߂��̂���)�A�u�}�����ꂽ���̂̉�A�v�Ƃ��Ă̌����l��D�A�����̃V�X�e������̉���̌����ł��邻�̑��݂��A�J���g�I�ȈӖ��ł́u���O�v(�����I���O)�Ƃ��Č���Ă��邱�Ƃ��B
�@��ɂ��q�ׂ��悤�ɕ��J�́A�����������̂Ƃ��ẴJ���g�̎v�z���A�w�[�Q���I�Ȏv�z�̂�����ւ̔ᔻ�Ƃ��Č��o���Ă���B��͂菘����������B
�L����M
�@�w�[�Q���̑̌n�ɂ����ẮA����(���j)�͊���������̎��ݕ��Ƃ��āA���łɊ������Ă�����̂Ƃ��Č��o����Ă���B����͊����������j�̑���`�����A���̗��j�́A������łɏI��������̂Ȃ̂ł���B����ɑ��ăJ���g�̎v�z�́A���j������ꂪ���S�Ɍ��ʂ��f�肷�邱�Ƃ��o���Ȃ��A�����̎����Ƃ��đ����Ă���A�Ƃ����킯�ł���B
�@���̕��J�ɂ�����A�w�[�Q���ƃJ���g�̑Δ�́A�����̂��Ƃ��l��������B
�@�Ƃ���ŏ�̕����Ɂu���z�_�I�v�Ƃ������t���o�Ă���B����͕��J���ȑO����悭�p���Ă���J���g�̌��t�����A���J���g�́A���̌���J���g���g���Ă����̂Ƃ͈قȂ�A�Ǝ��̈Ӗ������������Ďg���Ă���ƁA�J��Ԃ��q�ׂĂ����Ǝv���B���������ł́A�Ƃ肠�����J���g�ɂ����邱�̌�̈Ӗ��ׂĂ݂悤�B
�@���́w�R�[���x�̓������ɍڂ���ST����̘_�l�ɂ��A�w���������ᔻ�x����J���g���g�ɂ�閾�m�Ȃ��̐�����������Ă���͂������A�����ł͌F�쏃�F���w���m�N�w�j�x(��g�V��)�́A���L�̉�����Q�Ƃ���B
�@�܂�u���z�_�I�v�Ƃ́A�o�����\�ƂȂ�����ɂ��ĔF�����悤�Ƃ���ԓx���Ƃ������Ƃ��B�o���́A���ꎩ�̂ɂ���Ă����ł͕��ՓI�ȔF���ɒB���邱�Ƃ͏o���Ȃ��ƁA�J���g�͍l�����B�o���ɂ́A�����ł͏��z���邱�Ƃ̏o���Ȃ��A���̏���(���E)�Ƃ������̂�����B����͌���������ƁA�����l�Ԃ����ՓI�ȔF�����Ƃ�����̂́A���͂ǂ��܂ł����E�t����ꂽ���̂ł������肦�Ȃ��A�Ƃ������Ƃ��낤�B
�@�u���z�_�I�v�ȗ���Ƃ́A���������l�������������̂ł���A�J���g�͂��̗���ɗ����Ƃɂ���āA�����̌o���z����悤�ȑ��݂̗̈���m�ۂ��悤�Ƃ����̂��ƍl������B
�@���̑��݂��A�_�ƌĂԂ��Ƃ��o���邵�A�܂����O�ƌĂԂ��Ƃ��ł��悤�B����́A�����l�Ԃ������̒��Ɏ��݂Ƃ��Č��o�����Ƃ͌����ďo���Ȃ����A�����̗������̂��̂������Â��A������^����悤�Ȃ��̂Ƃ��Ċm���ɓ����Ă��鉽���ł���B
�@���̂悤�ɑ�����Ȃ�A���J�ɂ��u���z�_�I�v�Ƃ�����̗p�������́A�J���g�ɂ����邻��ƁA��͂肻��Ȃɑ傫���u���������̂ł͂Ȃ��Ǝv����B
�@����́A����ꂪ(���j�̒���)���݂Ƃ��Č��o��(�o������)���Ƃ͏o���Ȃ�����ǂ��A�����̗��j�����E�t���A�܂����̕�������m��ʊԂɗ^����悤�Ȃ��̂Ƃ��ē����Ă���悤�ȁA���鑶�݂Ȃ����͂�z�肷��Ƃ����ԓx�ł���B���̑ԓx�́A�o�����Ƃ���悤�ȑԓx�Ƃَ͈��Ȃ̂��B
�@���ɓ����{����A�J���g�́u���O�v�ɂ��ď����ꂽ������������Ă݂悤�B
�@�u�����I�v�ƁA���J�̎g���Ă���u�����I�v�Ƃ́A�����Ӗ��̖��Ȃ̂��낤�B�l�ɂ͓���ȕ��͂����A�u���O�v�́A�o���ɂ͑ΏۂƂ��ď\���F���ł��Ȃ����̂ł���ɂ��ւ�炸�A�o��������d���ŋK�肷��悤�ȑ��݂��A�Ƃ����Ӗ��̂��Ƃ������Ă���悤���B
�@���Ƃ���ƁA���́u�ΏۂƂ��ĔF���ł��Ȃ��v�Ƃ������Ƃ��A�t���C�g�I�ȗ}���̈Ӗ��ɂƂ�ƁA����͂܂������u�}�����ꂽ���̂̉�A�v�Ƃ��ė��j�ɓ���������悤�ȗ́A�܂�͕��J�̂����u�����l��D�v�̂��Ƃ��Ƃ��������邾�낤�B
�@���̂悤�ɁA���J�́A�J���g���p�����u���O�v�Ƃ������t���A�o�����z������̂ł����āA�����Ɍo���ɓ��������ĕ������K�肷��悤�Ȃ��̂Ƃ����Ӗ��ŗp���Ă���Ǝv����̂����A����͕��J�̗B���_�I�Ș_���ɂ����ẮA�u�_�v�̂悤�ȑ��݂ł͂Ȃ��A�t���C�g�I�Ȗ��ӎ��̃��J�j�Y���Ƃ��ċL�q����Ă���̂��Ƃ����悤(�����Ƃ��A�t���C�g�̎v�z���̂��A�J���g����e�����Ă��Ȃ��͂��͂Ȃ��̂�����A�t���C�g��ڑ������邱�Ƃŕ��J���J���g�̍l���̘g�g�݂���傫���O�ꂽ�Ƃ͂����Ȃ���������Ȃ�)�B
�@�Ƃ�����A���J�����́w���E�j�̍\���x�ł��p���Ă���u���z�_�I�v�Ƃ��u���O�v�Ƃ������t���A�J���g�͌��X�A�o�����Ƃ���悤�ȍl�����A�o���݂̂ɂ���ĕ��ՓI�ȔF�����\�ł���Ƃ���l�����ւ̔����Ƃ��������ɂ����ėp�����Ƃ������Ƃ́A��͂�d�v���Ǝv���B
�@���̂��Ƃ́A�N�w�j�I�ɂ͖��_�A�q���[���̌o���_�ɑ���J���g�̔ᔻ�A�Ƃ������ƂȂ̂ł��낤�B�������J�́A���̃J���g�̔ᔻ�̘g�g�݂��A�ނ�����ɏo�Ă����w�[�Q���̑̌n�I�v�z�ɑ���ᔻ�̍ޗ��Ƃ��ėp���Ă���킯�ł���B���̂��Ƃ��A�ǂ��l���邩�B
������
�@�����ŁA��Ⓜ�˂����A��ɏq�ׂ��u��]�Ƒ̌n�v�Ƃ����^�[�����v���o���Ă������������B
�@�X�E�P�P�ɒ��ʂ��ė��_�I�̌n�̍\�z���u���悤�ɂȂ�܂ŁA���J���Ƃ��Ă����v�z�̑ԓx�́A��]�ƂƂ��Ă̂���ł������Ƃ����B�����āA�{���I�ɔ�]�Ƃ������Ƃ������J�́A�̌n�I�v�l�����ł���A�܂�����������Ă����Ƃ����̂ł���B
�@�l�̋L���ł͕��J�́A�h�D���[�Y�̒���̒��ł͏����̃q���[���_���ł��D���Ȃ��̂Ƃ��ċ����Ă������A�܂����g�̒���ł��A���Θ_�Ȃǔ�r�I�����̘_�l�ł̓q���[���̎v�z���d�����Ă����Ƃ�����ۂ�����B��]�I�Ƃ����A�X�E�P�P�ȑO�̕��J�̎v�z�̃X�^�C���́A�q���[���I�ȁA�o���_�I�ȗ���ɏd�˂���̂ł͂Ȃ����Ǝv���B
�@��������ƁA�@�X�E�P�P�ȑO�̔�]�I�Ȏv�z�̂�����̓q���[��(�o���_)�I�Ȃ��́A�A�X�E�P�P�Ȍ�ɂ��̏d�v�����ĔF�������̌n�I�Ȏv�z�̂�����̓w�[�Q���I�Ȃ��́A�����āA�B���̃w�[�Q���I�ȑ̌n�̎v�z�̕��Q��Ŕj���邽�߂ɏ��҂����V���Ȏv�z�̂�������J���g�I�Ȃ��̂ƁA�ꉞ�A���������ł���̂ł͂Ȃ����H
�@�@�ƇB�́A��������l�I�R�����咣����悤�ȑ̌n�I�v�l�ɑΗ�������̂Ȃ̂ŁA�ꌩ�����悤�ł��邪�A�B�͇@�Ƃ͈���āA�A�̏d�v�����\������������ŁA���̑̌n������Γ��ݓI�ɔᔻ(�E�p)����悤�Ș_���Ƃ��đ������Ă���Ƃ������ƂɂȂ�B���ہA�{���ɂ�����J���g�̎v�z(���E�j�ɂ��Ă̍l����)�̈ʒu�Â��́A�����������̂ɂȂ��Ă���Ƃ�����(�ŏI�́u���E���a���ցv�E��q)�B
�@�������łɏq�ׂ��悤�ɁA�A���A�w�[�Q�����g�̎v�z�ɂ����ẮA���X�͎��Ȃ́u���v(���͐�)�����o����Ƃ����A���Ȃ̌��E�ɑ���ӎ��A���Ȃ킿�u���z�_�I�v�_�@��L���Ă����Ƃ����̂��A�l�̍l���ł���B���ꂪ����ꂽ�Ƃ��ɁA�A�̓l�I�R���ɂ�����悤�ȗ}���I�ȑ̌n�I�v�z(�C�f�I���M�[)�ւƕς����̂ł���B
�@���̊ϓ_�ɗ��ƁA�@�̌o���_�I�A��]�I�Ȏv�z�̂�����ƁA�A�̂����̃l�I�R���I�E�����w�[�Q����`�I�Ȏv�z�̂�����Ƃ́A���ɒ��z�_�I���i�A�܂莩�Ȃ̌��E�⌠�͐��ɑ��鎩�o�������Ă���Ƃ����Ӗ��ł́A���͎��Ă���Ƃ������Ƃ�������B
�@�{���w���E�j�̍\���x�ŁA�w�[�Q���̑̌n�I�Ȏv�z�̈Ӌ`���d�����Ȃ���A�����Ƀl�I�R���I�ȃw�[�Q���̗}���I�g�p�ɍR���āA�J���g�����邱�ƂŃw�[�Q���I�ȃV�X�e���ւ̑̌n�I�c����̐��ϊv�ׂ̈̎v�z�ւƕς��悤�Ƃ��长�J�̊�}�́A�܂������ɁA���݃w�Q���j�[�������Ă���o����`�I�Ȏv�l���L����v���O�I�Ȑ��i�ɑ���ᔻ�Ƃ����Ӗ����������Ă���̂ł��낤�Ƃ����̂��A�l�̌����ł���B
�@�����v���̂́A���̎Љ�ł́A�u���O�v�̈Ӌ`��F�߂��A�o���̐ςݏd�˂�W�ς����ŕ��ՓI�Ȃ��̂ɓ��B�ł���Ƃ���A�ߓx�Ɍo����`�I�ȍl�������A���ۂɂ̓l�I�R���̑����w�[�Q����`�Ɠ��l�ɁA�V�X�e�����쎝���邽�߂̃C�f�I���M�[�Ƃ��ċ@�\���Ă���ɈႢ�Ȃ��Ǝv�����炾�B(���P�@�����ł����ЂƂC�����̂́A�̌n�I�v�l�ɑ���ᔻ�Ƃ����Ӗ��Ō����ƁA�@�̌o���_�I�E��]�I�ȗ���́A�����B�i�X�ɂ��S�̐��ᔻ�Ɏ��Ă���̂ł͂Ȃ����A�Ƃ������Ƃ��B���ăf���_�́u�\�͂ƌ`����w�v�̂Ȃ��ŁA�����B�i�X�̗p��ł���u�`����w�v(���ʂ̈Ӗ��ł́u�`����w��ᔻ������́v�ɂ�����Ǝv����)�@���w���āA����͎��͌o���_�ł���Ə����Ă������A����͂��̈Ӗ��������̂ł͂Ȃ����B�����B�i�X�͂��̌�A���̃f���_�̔ᔻ���Ďv�z��ω������Ă������͂��ł��邪�A����͏�L�̇@����A���邢�͇B�ւƂ����A���J�̎v�z�̕��݂Ǝ��Ă���̂��ǂ��Ȃ̂��B
�@���̂��ƂɊS�����̂́A�����B�i�X�̗ϗ��I�Ȏv�z�A�Ƃ�킯���{�ʼn��߂���ĂX�O�N�㍠����L���e���͂����悤�ɂȂ������ꂪ�A�X�E�P�P�ȑO�ɂ����长�J�̔�]�ƓI�Ǝ��̂����v�z(�@)�Ɠ��l�ɁA�V�X�e���⍑�Ƃ̈�����ݓI�Ȃ��̂Ƃ��đ�����ӎ�����Ɍ����Ă���悤�Ɏv���邩��ł���B
�@�܂肱�̎v�z�́A�ϗ��I�ł��鎩�Ȏ��g�̐������E���͐����\���Ɏ��o���Ă��Ȃ��߂�����B���邢�́A��������o�����ɍς܂��邱�Ƃ��A���̏d�v�Ȑ��i�Ƃ��Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv����Ƃ��낪����̂��B�����ŁA�����B�i�X�̒���̃^�C�g���ł����A�u�S�̐��v�Ƃ����ᔻ����_�@�Ƃ��Ắu�����v(����)�Ƃ��A���͖{���ɑΗ�������̑��肦�Ă���̂��Ƃ����^�����o�Ă���B�f���_�ɂ�邩�Ă̔ᔻ�́A���̂��ƂɊւ����̂������̂ł͂Ȃ����H���̈Ӌ`�́A����̓��{�̎v�z�̂Ȃ��Ŏp����Ă���̂��낤���B)
�@
�{���̘g�g�݂ւ̍m��I�]��
�@���̂悤�ɁA�{���w���E�j�̍\���x�ŕ��J�s�l�́A�w�[�Q�������̊ϔO�_�I�̌n�ɂ����Ĕc�����Ă����u���{���l�[�V�������X�e�[�g�v�Ƃ����ߑ㐢�E�V�X�e������̉���̉\�����A�J���g�N�w�ɂ�����u���O�v�̌����ɑ��铭���̂����Ɍ��o�����Ƃ��Ă���B���̓����Ƃ́A���J�Ǝ��̗B���_�I�̌n�̗p��ł����A�����l��A(�ݏV�I����)�̍������ɂ������(�u�}�����ꂽ���̂̉�A�v)�Ƃ��ẮA�����l��D�̏o���Ƃ������Ƃł���B
�@�����l��D�́A���j�̂Ȃ��ł́A���Տ@����Љ��`�A�A�i�[�L�Y���A�A�\�V�G�[�V���j�Y���Ƃ��������`�Ԃ�������B�܂��l�[�V�������A���`�I�ł��邪�A��ʂł͍��ƂƎ��{�̎x�z�ɑ���v���e�X�g�Ƃ������ʂ������Ă���Ƃ����(���R�R�O)�B�����͂�������A���E�j�̂Ȃ��ŁA�Ƃ�킯�ߑ㐢�E�̂Ȃ��ŗ}������Ă����ݏV�I�����̌������A�u���O�v�Ƃ����������ʼn�A���Ă������ʂ��Ƃ����̂ł���B����炪�`��ς��āA�J��Ԃ����j�̂Ȃ��Ɏp�����킵������̂́A�u�}�����ꂽ���̂̉�A�v�Ƃ������ۂ��A�t���C�g���������悤�ɋ����I�A�K�R�I�A���ߓI�Ȃ��̂ł��邩�炾�B
�@���́u���O�v�̖��߂́A���J�̑̌n����������悤�ɁA�B���_�I�ȍ��������ȏ�́A���Ƃ⎑�{�ɂ��x�z��⊮����z���I�ȉ�(�l�[�V�����̂悤��)����ɂƂǂ܂�̂ł͂Ȃ��A�����Ɏ��������ׂ����̂ł���B����܂ł́u���O�v�̐��́w�������Ă�܂Ȃ��̂ł���x(��351)�B
�@�����āA���̎����̂��߂ɕs���Ȃ��̂Ƃ��ĕ��J�������Ă���̂́A�e���ɂ�����R�^���Ƌ��ɁA�u���A�v�̖����ł���B
�@�u���{���l�[�V�������X�e�[�g�v�̌����̗͂��l����Ȃ�A�u���E�����v���v(���ꂪ�����́u�v���v�̐�ΓI�ȏ����ł���)�̎��R�����I�Ȑ����͂��肦�Ȃ��B�V�X�e���̌����̂Ȃ��ł́u���O�v�̑Q�i�I�Ȏ����Ƃ��Ă̍��A�̑��݂�y��Ƃ��A��������v���Ă������Ƃ����Ƃɂ���Ă����A����͖K��Ȃ��B
�@�u���{���l�[�V���������Ƃ̗g���͐V���Ȑ��E�V�X�e���Ƃ��Ă̂ݎ��������v(��43)�Ɛ�ɏq�ׂ��Ă����̂́A���������Ӗ��������̂ł���B
�@���ꂪ�A���̖{�ł̕��J�̗B���_�I�̌n�ɂ��ƂÂ��l�@�́A���H��̌��_���ƌ����Ă������낤�B����́A�V�X�e���̏��z����̔F���̂����ɗ������A���ۖ����`�ƌĂׂ���̂ɂ��v����B
�@���ǁA���J�����Ă���̂́A�V�X�e����ے肷�邱�ƂŒE�p����悤�ȓ��ł͂Ȃ��A�V�X�e���̕ϗe��ʂ��č��Ƃ⎑�{����̉������������v�������Ƃ������ƂɂȂ낤�B
������
�@�ȏ�̂悤�ȁA�w���E�j�̍\���x�̋c�_�̘g�g�݂��A�ǂ������邩�B
�@�܂������邱�Ƃ́A���J���J���g�I�ȁu���O�v(�����I���O)���������Ƃ́A���j�ɑΛ����Č��������グ�Ă����s�ׂ̂Ȃ��ɁA���O�I�Ȃ��̂����悤�Ƃ���A�ЂƂ̎��݂ł��낤�A�Ƃ������Ƃ��B
�@����̌o����`�̎x�z���v���O�̌X���������Ă���Ƃ��������łȂ��A�l�I�R�����p����悤�ȁu���j�̏I���v�̋c�_���A���͖v���O�I�Ȃ��́A����������A�V�j�V�Y��(��Ύ�`)�ɖ��������̂ł���B��������́A�w�[�Q���ɑ�\�����悤�ȋߑ�I�ȗ��j�̗��O��(�\���I���O�H)���͂��ł���ے�I�Ȃ��̂̌��ʂł���Ƃ��l������B���O�����̓I�Ɍf���������̕ϊv�́A���ǃV�X�e���̗͂̑O�ɔj�ꂴ������Ȃ��B�u�ǂ̕���v�Ƃ����悤�Ȍ��ۂ����łȂ��A���{��`�͂��Ƃ��Љ��`�̐����܂���l�ԓI�ł���Ƃ����F���̍L�܂肪�l�X�ɂ����炵�����̂́A���������V�j�J���Ȋ���ł͂Ȃ��������B
�@����ɑ��ĕ��J�́A�������邱�Ƃ̏o���Ȃ�(X�Ƃ������w���Ȃ�)�����I���O�Ƃ����d���ŁA���j�F���̂Ȃ��ɗ��O���A����������Ζ����ւ̈ӎu���A���������悤�Ƃ��Ă���̂��ƍl������B
�@���J�́A���̂悤�ɏq�ׂĂ���B
�@
�ϓ_�ւ̋^��E���R�Ƌ]��
�@���J�̎��݂̈Ӗ����A�ЂƂ܂����̂悤�ɍm��I�ɑ�������ŁA�����Ŗ{���̊ϓ_(�܂Ȃ���)�ɑ����̋^�����Ă��������B����́A�����ł̕��J�̋c�_�ɂ�����A�w�[�Q���ƃJ���g�̗��j�ς̑Δ�Ɋւ���Ă���B
�@������������A���J�́A��x�̑����o�č��A�̌`���ւƎ������ߒ��́A�J���g�̂��������Ƃ��u���R���m�v�ɂ���Ď�������Ă������̂ƍl������Ȃ����̂��Əq�ׁA�J���g�̊፷���ɂ́u�w�[�Q���̃��A���Y�������A�����Ǝc���ȃ��A���Y�����Ђ���ł���v(��455)�ƋL���Ă���B
�@�J���g�̗p��ł���u���Љ�I�Љ�v�Ƃ́A�U�����ƌ����������錾�t���Ǝv�����A�U�����ɂ���Ă����A�܂��푈��ʂ��Ă����A�i�����a�Ƃ������z�A�u���O�v��������n�_�ɏ��X�ɋ߂Â��Ă����̂��Ƃ����A�J���g�́u���R�j�v�I�Ȏv�z�������Ō���Ă���Ƃ����邾�낤�B���ꂪ�A���J���{���Ńl�I�R���I�ȗ��j�ςɑ��Ē����A�R�I�Ȑ��E�j���߂̌������Ƃ����Ă悢�B
�@�܂��m�F���Ă��������̂́A���ꂪ�A�푈�̑̌��������ɂ����炷���a�ւ̗��O�̎����I�ȏd������������Ӑ}����������肾�낤�Ƃ������Ƃł���B�J���g�́u�i�����a�v�̗��O�́A�����ċȗ��z��`�̂悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ��A�푈�Ƃ����ߍ��Ȍ����̂Ȃ�����s��I(�K�R�I)�ɔ������Ă���A�m���Ȃ��̂ł���A����͐l�Ԃ����������Y�p���ĉ߂����J��Ԃ��Ƃ��Ă��A���X�ɉ�A���Ă��ď����Â^�̎����ɋ߂Â��Ă����B���ہA���j�͂������ڂ��Ă����A�ƌ����Ă���̂��B
�@�������������̌����ɂ́A�٘_�����邾�낤�B�푈��A�������̂Ȃǂ̐l�דI�Ȕj��̋K�͂́A���j�̐i�W�ƂƂ��ɁA�ނ���s�\�Ȃقǂɐr��Ȃ��̂ɂȂ��Ă��Ă���B�ƂĂ������ɑ��āA����Ȋ�]�I�ȋC�����ɂ͂Ȃ�Ȃ��Ƃ����v���́A�l�ɂ�����B�������J�́A�����Ŋ�]������Ă���̂ł͂Ȃ��A���j�̕K�R���ɂ��Č���Ă���̂ł���A���̂Ȃ��Ő����čs����������̎w�j�Ƃ��Ă̗��O�Ƃ������̂ɂ��āA�����������Ă���Ƃ������Ƃ��낤�B��]�����Ƃ�����]���悤���A�����͗��O�̗͂ɔ����ė��j���`�����邱�Ƃ͏o���Ȃ��B�����������Ƃ��낤�B
������
�@�Ƃ���Ŗl�́A�����ɏo�Ă���u���R�v�Ƃ������t�ɒ��ӂ��������B�{���w���E�j�̍\���x�ł́A�����̂Ƃ���ŁA���x���u���R�j�v�Ƃ������t���o�Ă���B����́A�}���N�X��A���̐�s�҂ł��郂�[�[�X�E�w�X�̎v�z�A�Ƃ��Ɍ��(����)�T�O�Ɋւ��A����̊����A�G�R���W�[�̉^���ɂȂ����Ă���A�l�ԂƎ��R�Ƃ���ӂɂ����Č���悤�ȍl�����Ƃ��Ăł���B
�@���͂��̖{��ǂ݂͂��߂��Ƃ��A���R�j�Ƃ������t���A���̂悤�ȈӖ������ʼn����ϋɓI�Ɍ���Ă��邱�ƂɌ˘f�����B�l�̓��̂Ȃ��ɂ́A�ߋ��ɕ��J�������Ό���Ă����A��L�̕��͂ɏo�Ă���悤�ȃJ���g�I(�����Ƀt���C�g�I)�ȁA�����̎c������тт��u���R(�j)�v�̃C���[�W�����Ȃ���������ł���B
�@�����l���Ă݂�ƁA���̓�̎��R�j�́A�܂������ʂ̂��̂��Ƃ͌����Ȃ��B�l�Ԃ����R�Ƃ̕������(���Ԍn)�̂Ȃ��ɂ����đ�����Ƃ������Ƃ́A�P���Ȑl�Ԓ��S��`�ƌĂׂ�悤�Ȋϓ_���猩��Ȃ�A�c���ɉf�邾�낤�B
�@�{���̓��b�u�Ȃ߂Ƃ��R�̌F�v�ł́A��l���̗t���A����܂Ŏ�ɂ���ĎE�����ƂŎ����̐����𐬂藧�����Ă������݂ł���F�ɏP���āA���͎������H�ׂ��鑤�ɉ��ׂ����Ǝv���Ă�����Őg�𓊂��o���̂����A�����ł͐l�Ԃ̎��́A�H���A���̈���Ȃ����̂Ƃ��āA����ΗL�@�I�ɈӖ��Â����Ă���킯�ł���B
�@����́A�w�[�Q���̍��Ɗς̂悤�ɁA�l�ƍ��Ƃ̊W���A�זE�ƌ̑S�̂Ƃ̊W�̂悤�Ȃ��̂ƍl���A�l�̎����A���ƑS�̂Ƃ����L�@�̂̈ێ��̂��߂̂��̂Ƃ��ĈӖ��Â���^�C�v�́A�]���̐������̎v�z�Ƃ͂��قȂ邪�A�ʂ̃^�C�v�̋]���̐������̎v�z�A����S�̖̂��ɂ����ĈӖ��Â��Ă��܂��v�z�ɂȂ肤����̂ł͂Ȃ����H
�@���̕ʂ̃^�C�v���A����Ӗ��ł̎��R��`�A���邢�͐����w��`(��L�̂悤�ɁA�w�[�Q���̂���������w�Ɩ����ł͂Ȃ��Ǝv����)�ƌĂ�ł�����������Ȃ��B
�@�J���g���ˋ����Ă��鎩�R�j�Ƃ����T�O�ɂ́A���̂悤�Ȑ����w��`�̊댯������Ƃ������Ƃ́A�j�[�`�F�Ȍ�̗��j�������Ă��邱�Ƃł����邾�낤�B���J���A�����m��Ȃ��͂��͂Ȃ��B��������ł��A�ނ��J���g�I�ȁu���R�v�̈Ӌ`���̗g����̂́A���ꂪ�u�����v���̂��̂Ƃ���w�[�Q����`�I�ȗ��j��(�u�������m�v)��ᔻ������̂Ƃ��ďd�v���ƍl���Ă��邩�炾�낤�B�������̂��߂ɁA���J�͎��R�j�Ƃ����l���������A�����w��`�̊댯�����y�����錋�ʂɂȂ��Ă���̂ł͂Ȃ����B(���Q�@���J�́A�l�ԂƎ��R�Ƃ̊W���Љ�\������藣���čl�������ȃG�R���W�[�I�Ȏv�z�̌��E�ɂ��ẮA�{���̂Ȃ��Œ��ӂ𑣂��Ă��邪�B��31�`32)�B
�@�u�푈�v�ɂ��l�X�̎����A�u���O�v�̎����̂��߂̕s���̉ߒ��Ƃ��đ����长�J�̎��R�j�I�ȍl�����́A�������ɁA�i���̕��a�Ƃ������O���A�U������푈�Ƃ��������ɍ����������I�Ȃ��̂ł��邱�Ƃ�\������d�v�Ȏv�z�Ȃ̂����A���̔��ʂŁA����d���Łu�푈�v��u�]���v��e�F����悤�Ș_���ɉ����肷��댯���͂��ł���̂ł͂Ȃ����Ǝv���̂��B
�@���̈Ӗ��ŁA���J�̎v�z�ɂ́A�l�����Ę_����(�w�R�[���x�P�U���u����v�z���čl����@�R�v)�A�����m�i�̎v�z�Ƃ����ʂ���A�����ɂ����鐶�Ǝ��ւ́u���O�v�̂悤�Ȃ��̂��A��͂芴������Ƃ������Ƃ��A�Ƃ��ɏ����Ă��������B��������́A�u�����\���J(�����Č���)�v�ɋ��ʂ��郍�[�J���Ȏv�z�̌X�������l���邱�Ƃ��o���悤�B
�@�܂�A�}���N�X�Ƌ��Ƀw�[�Q�����d�����������̎v�z�̐��i���A�ُؖ@�I�A�����E�Љ�\���_�I�A������`�I�A�ߑ�I�ȋ]���̎v�z(��O���r��)�ւ̐��F�Ƒ�����Ȃ�A����Ƃ͈قȂ�A��ُؖ@�I�A���R(�����w)�I�A�����Ė��ӎ��I�A�O�ߑ�I�ƌĂׂ�悤�ȋ]���̎v�z�ւ̐��F�̋C�����A���J�̘_�ɂ͌��o����悤�Ɏv���̂ł���B
�@�����ŖY��ĂȂ�Ȃ����Ƃ́A�w�[�Q���́u�������m�v�̎v�z�ƁA�J���g�́u���R���m�v�̎v�z�Ƃ́A�����Č����ɂ��Ă̈قȂ���߂����������̂ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃ��B�u���R���m�v�Ƃ��ĕ`����錻���̎p�́A���́u�������m�v�Ƃ��ĕ`����錻���̎p���A���̕����I�E�Љ�I�ȑ�����E���̂ĂāA���ڂɘI�悵�����̂ɂ����Ȃ��̂ł���B
�@����������Ȃ�A�w�[�Q���������̎����ɂ����đ����������̑����A�J���g�͖��ӎ��̎����ɂ����đ����ĕ`���Ă��邾�����Ƃ������Ƃł���B����͂�����ɂ���A�������̗����̕���(�L���X�g���I�ȁH)�Ɉˋ����������̉��߂ɉ߂��Ȃ��̂ł����āA���̌���ł́A�w�[�Q���̋L�q�Ɣ�ׂăJ���g�̂��ꂪ�Ƃ��ɗϗ��I�ł���Ƃ������Ƃł͂Ȃ��B
�@�����(�w�[�Q���̎v�z�ɂ���A�J���g�̎v�z�ɂ���)�́A����Ȃ镶���ˋ��I�Ȍ����ł��邱�ƂɂƂǂ܂����A�����̔ߎS��(�l�̎���\�͂Ȃ�)���Ӗ��Â��ɂ���ĉB�����Ă��܂��A�V�X�e���̂��߂̎v�z�ł���ɂƂǂ܂�B�܂�A�]���̘_���̊e�o�[�W�������Ȃ��ɉ߂��Ȃ��Ƃ������Ƃ��B
�@�v�z���A�����Ƃ��ɂ́A�܂�V�X�e���̈ێ��̂��߂̌����ł��邱�Ƃ���߁A�ϗ������Ɋւ��v�z�ƂȂ邽�߂ɂ́A�����ăJ���g�̌��p����A�����ɐ^�̈Ӗ��̒��z�_������������˂Ȃ�Ȃ��B�܂�A�����炩��G�c�Ȍ������������Ă��������Ȃ�A�����̉��߂��߂��鎩���̌��͐����Ǝ˂���悤�ȁA���l�̌����������܂�˂Ȃ�Ȃ��̂ł���B
�@���̂��Ƃɂ���Ă͂��߂āA�v�z�͐l�X�̐����̌������ƁA������x�z���Ǘ����Ă���V�X�e���̗͂ƂɌ����������Ƃ��o����͂��Ȃ̂��B
�@�����A���傤�Ǎ������w�[�Q���ُؖ̕@�I�ȋ]���̘_���Ɂu���O�v�������Ă��������Ȃ������悤�ɁA���J�͂����ŁA�J���g���`���o���Ă���悤�Ȗ��ӎ��̎����ɂ�����]���̘_��(�\�͂̐������̍\��)�ɁA�\���ɍR�����Ă��Ȃ��悤�Ɏv����B�܂�A�����ł̕��J�̎v�z�́A�J���g�̎v�z�������Ă���l�Ԃ̗��j�̖��ӎ��I�Ȏ����̖\�͐��Ƃ������̂ɁA�����̌��͐���\���o�����l�̌��𓊂������邱�Ƃɂ���āA�V�X�e���̌���̊O�ł����c������ɂ͎����Ă��Ȃ��B
�@����́A���܂�Љ�╶���̑�����E���̂āA�����炳�܂ɂȂ����\�͂�(�V�X�e���ɂ��)�����I���p�Ɣ×��Ƃ��������ɂ������āA���J�̋c�_���A�\���R��������̂ɂȂ��Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃ��Ӗ����Ă��邾�낤�B���̂��Ƃ́A�t���C�g�̗p���p����Ȃ�A�G�X�̒��ړI�Ȑ����I���p�Ƃ������{(���邢�͐��E)�̐����̌���ɑ��āA���J�̕��͂����z����悤�ȁA�ǂ�ȑR�̎d�����\�Ȃ̂��Ƃ����₢���A���炽�߂Ă����ɓ˂������ɂ͂��Ȃ��̂ł���B(���R�@�t�@�V�Y���Ƃ̊֘A���l����A�J���g�����O���`�e����̂Ɂu�����I�v�Ƃ������t�������Ƃ́A�Ӗ��[����������Ȃ��B)
�@
���R�ƌ���
�@��L�̖₢�ɑ��āA�l�ɓ�������킯�ł͂Ȃ��̂����A���̎�|��邽�߂ɂ��A
�����ōĂсA�{���̑傫�Șg�g�݁A�܂蕿�J�̗B���_�I�̌n�ƁA�J���g�ɂ��w�[�Q���̏��z���A�Ƃ������ɖ߂��čl���������߂悤�B
�@�܂����J�̗B���_�I�̌n�̓����́A�}���N�X�����Y�l������b�ɂ��ĎЉ�Ɨ��j�̍\���𑨂��悤�Ƃ����̂Ɋ����āA�����l������b�ɂ��ĐV���ȗB���_�I�ȑ̌n����낤�Ƃ�����̂��Ƃ������Ƃ������B������u�������R�́A���̕��@�ɂ��Ȃ���A�w�[�Q�����ϔO�_�I�ɑ����Ă����悤�ȃV�X�e���̌����I���̂�c�������邱�Ƃ��o���Ȃ��ƍl����ꂽ����ł���B
�@����Ή����\��������(�W)�Ɍ��o���Ƃ����l�������̂́A�}���N�X��`��ُؖ@�I�v�z�̗��j�A�Ƃ�킯���{�̂���̂Ȃ��ł͓��ʂɒ��������̂ł͂Ȃ����낤���A���J�̖{���ł̎��݂̏d�v�ȈӋ`�́A���Ƃ�l�[�V����(����Ɏ��{�̊ϔO�I����)���������I�E�����I�ȁu�́v�̍������𖾂��悤�Ƃ������Ƃɂ���ƌ����邾�낤�B�{���̒��ŕ��J�́A�����̂̓����̐��x�ł���u�\���v�ɑ��āA�����̊Ԃ̌����ɂ����ē������̂Ƃ��Ắu�́v�m�ɋ�ʂ��Ă���(���V�S)���A�{���̑S�̂��т��Ă���̂��A���́u�́v�̓����𑨂��悤�Ƃ���p�����Ƃ�����B����́A����܂Ŏ����Ƃ��ꂽ�ߑ�I�ȎЉ�̎d�g�݂��������A�u�́v�̘_�����I�悵����悤�Ɍ����邱�̎���ɑ��������v�z�̑ԓx�ƌ����邩������Ȃ��B�J���g�ƃt���C�g�Ƃ�����l�̎v�z�Ƃւ̒��ڂ��A�U������ӎ����̗~�]���Љ�̕\�ʂɘI�悵�Ă���悤�ȁA���݂̎Љ�Ɍ������Ă���Ƃ��l������̂ł���B
�@�����J��Ԃ����A���j�𑨂���̌n�̊�b�Ƃ��Č����l���������o���ꂽ�Ƃ������Ƃ̈Ӗ��́A�w�[�Q���I�Ȍ����c����B���_������Ƃ������Ƃł���B�Ƃ������Ƃ́A�w�[�Q���ȑO�ɂ́A���̂悤�ȔF���͎v�z�j��ɑ��݂��Ă��Ȃ������ƍl������A�Ƃ������Ƃł�����B
�@�Ƃ���ƁA�J���g�ɂ���ăw�[�Q�������z����Ƃ����A�{���̊�}���̂��̂��������v���Ă���̂��B���J�̘_�ł����ƁA�J���g�̓N�w�ɂ͊��Ƀw�[�Q���I�ȔF�����A���ۏ����ق���Ă������̂悤�Ȉ�ۂ���̂����A�ق�Ƃ��ɂ����������Ƃł����̂ł��낤���H
�@�b��U��o���ɖ߂��悤�ł͂��邪�A��͂肻�����悭�l����ׂ��ł͂Ȃ����Ǝv���̂��B�J���g�̏ꍇ���A�������ɕ��J���Q�Ƃ���u���R�j�v��u���E�j�v�Ɍ�����悤�ɁA�l�ԎЉ�̗��j�̂�����ɑ���[�����@���s�Ȃ����l�ł���Ǝv����B�����A�ނ̌����Љ�́A���ǁA�u��Љ�I�Љ�v�Ƃ������ƁA�܂�U�����̗��j�Ƃ������ƈȊO�̂��̂ł͂Ȃ��̂ł͂Ȃ���(���J�̎Q�Ƃ̎d�����������ł́A�����v����)�H�w�[�Q���̗��j�ς��A������l�ԓI�������Ƃ����a��`�I�������ȂǂƂ́A�ƂĂ������Ȃ����낤���A����ł���͂�w�[�Q���̂悤�ȈӖ��ł̎Љ�(�W)�̔c���̎d���Ƃ́A����͍��{�I�ɈقȂ������̂ł͂Ȃ��̂��H�v����ɁA�J���g�́u���R���m�v�Ƃ͌��ǁA�{���Ȃ�Љ�I���݂ł���l�Ԃ�������ׂ��������A���ׂāu���R�v�Ɉς˂Ă��܂����Ƃ��������̂��Ƃł͂Ȃ��̂��H
�@�{���̓��e�ɑ����āA���̂��Ƃ��l���Ă݂悤�B����́A���J�������Ō���Ă���u���R�v��u�v�Ƃ����T�O�̓��e�Ɋւ���Ă�����Ȃ̂ł���B
�@�{���̋c�_�ň�ۓI�Ȃ̂́A�����l��D�̏o���̏����Ƃ��āA�ߑ㐢�E�ɂ����Ďx�z�I�ȗ͂����ɂ���������l��C(���i����)�̓����̕s��������������Ă��邱�Ƃł���B
�@�����l��C�̓����̏d�v���́A���ꂪ�l�������̂���藣���āA���҂Ƃ̎��R�ȊW���̂Ȃ��ɒu���Ƃ������Ƃł���B�l�͋����̂ɂ��S������藣���ꂽ�Ƃ��A�͂��߂Ď��R�ŒP�ƓI�ȑ��݂Ƃ��đ��҂Ƃ̗ϗ��I�ȊW�ɓ��邱�Ƃ��o����B�����l�����Ă���B
�@���̂悤�ɁA�����l��C(���i����)�ɂ���Ă����炳���悤�Ȏ��R�́A�����̂���̎��R�ł��邪�A���ꂱ�������҂Ƃ̊W�̂Ȃ��ɐ^�̌ݏV��(���^)����������ł���Ƃ���Ă���̂ł���B���^�Ə��i�����́A�����Ƃ����Ă��������i�̂��̂ł͂Ȃ��̂����A�O�҂��\�ɂ�������͌�҂ɂق��Ȃ�Ȃ��B
�@���ہA���i����(���Ƃ������ɂ�錈��)�Ƃ����_�@��ے肵�āA�����̓I�Ș_�������ŎЉ�����c�����Ƃ���Ȃ�A�S���I�ȍ��W���̂��������Ă��āA���܂��܂ȂƂ���ő����̋]���������邱�Ƃ͊m�����낤�B���i�����̘_���́A�������ɐl�������̂ɂ��]���������������A���҂Ƃ̗ϗ��I�ȊW�̏��������グ����̂ł��낤�Ǝv���B
�@�������A�����ōl�������̂́A���Ƃ��Ύ��̂悤�ɏ�������́u���R�v�́A�ʂ����ē������̂��Ƃ������Ƃ��B
�@���J�̘_�ł����ƁA�O�҂Ō���Ă���A���Տ@�����_�@�Ƃ��Ă����炳���悤�Ȍl�ƌl�Ƃ̊W�́A����ʓI�ɂ́A��҂ɂ�����悤�Ȏ��{���o�ω���(���x�I��)���������l�̎��R�������Ƃ��ĉ\�ƂȂ�A�Ƃ������ƂɂȂ�Ǝv���B
�@�������������l���́A���R��Ƃ������̂̂�������A���܂�ɏk�����đ����Ă��邱�ƂɂȂ�Ȃ����낤���B�����l��C�ɏd����u�����J�̎��R�̊T�O�Ƃ́A���Ƃ��Ύ��̂悤�Ɍ������̂Ȃ̂ł���B
�@���{���o�ω��Ŏ����������͕ۏ����悤�Ȏ��R����ՂƂ����A���J�̐l�ԓ��m�̌���(���)�̊T�O�́A�����ɐl�Ԃ������Ă��邠������A���������Ă���Ǝv���B����́A���i�����Ƃ����`���ɁA�l�̑��݂̂��ׂĂ������悤�ȉߏ�ȈӖ���^���Ă��邩�A�������͋t�ɁA���i�����Ƃ������̂̈Ӗ��������ߓx�ɋ����ݒ肵�������ŋc�_��i�߂Ă��邽�߂ɂ����Ŏ����E�ۏ����ׂ����̂̎����𑨂�����Ă��Ȃ����́A�ǂ��炩���Ƃ������Ƃ��B�v����ɁA���J���_���Ă���u���R�v�̊T�O�́A���܂�Ɍ���I�Ȃ��̂ł���B
�@�����������J�̋c�_�ɂ����ẮA���^��`�͂����ς����(���R�Ȍɂ����鑊�ݓI�ȊW)�ɂ������݂���̂ł����āA�����̓��I�Ȑ��`�Ƃ������́A�܂蕪�z�I���`�́A���̈Ӌ`��ے肳���Ƃ������ƂɂȂ�B�{���̓����I�Ȏ咣�̂ЂƂ́A���z�I���`�̈Ӌ`���ے肳��A�����I���`�̏d�v����������������Ă��邱�Ƃ��B�܂蕿�J�́A���z�E�ĕ��z�Ƃ����s�ׂɐ��`�②�^��������\�����A�����I�ɂ͔F�߂Ă��Ȃ��B�ĕ��z�Ƃ͌��ǁA���Ƃɂ��x�z�̈�`�Ԃ��Ƃ����f��ŏI����Ă��܂��̂ł���B
�@�����l�́A���{���I�ȈӖ��ł̎��R�Ȍl�ł���Ɠ����ɁA�ʂȗ̈�ɂ����鎩�R�ɂ��ւ�邱�ƂŐ����Ă��鑶�݂ł͂Ȃ��̂��B���̌����(���{���o�ςɂ���Đ�������悤��)�����̓��I�Ȑ��`�̘_���A�܂�(��)���z�I���`�̒Nj��Ƃ������Ƃ��A��͂茻���ɂ����Ă͏d�v�ł���Ƃ����̂��A�l�̍l�����B
�@���̖��́A�����炭���J�̋c�_�ɂ�����u���^�v�Ƃ������̂̐��i�ɂ��ւ���Ă��鎖���ł͂Ȃ����Ǝv���B�����́A���܂�ɂ��k�����ꂽ�̋K���O��ɂ��Ă��āA���͂��ł���Љ��W�c�����\���Ɏ˒��Ɏ��߂Ă��Ȃ��Ǝv����̂ł���B
�@�ȏ�̂悤�ȁA���J�ɂ�����u���R�v��u�v�̋����Ƃ����������A�J���g�ƃw�[�Q���̎v�z��̍��قɌ��т��Ă悢�̂��ǂ����A�l�ɂ͕�����Ȃ��B���������ɂ́A(�Y�Ǝ��{��`��V���R��`�Ƃ������X�p���ɂƂǂ܂炸)���R�ƎЉ�Ƃ̊W���ǂ������邩�Ƃ����A���낵���������j�I�w�i���������₢���܂܂�Ă���悤�ł�����B
�@�����l��(�W)�Ɋ�b��u���Ƃ������z�̏d�v����F�߂Ȃ�����ނ̑̌n�ɉ����l���g�̉��l�ςƑ��e��Ȃ����̂�����Ƃ���A����͂�͂肻�̌����l���_�̒����A�Ƃ�킯�A���̋N�_���Ȃ��ׂ��⎩�R�Ƃ������̂̈ʒu�Â��ɂ���Ǝv����̂ł���B
������
�@�܂Ƃ߂ɓ��낤�B
�@������(��͂蓂�˂���)��قǂ́A�u���O�v�����j�̂Ȃ��ōŏI�I�Ɏ��������ߒ��ł́u���A�v�̏d�v�������ꂽ��߂��A������x�����Ă݂����B
�@���炽�߂čl���Ă݂�ƁA���́w�������z���Ď��R�ɂȂ���x�Ƃ������Ƃ́A���J�̑O���̑薼(�w�g�����X�N���e�B�[�N�x)�ɂ��p�����Ă���A�g�����X(�z����)�Ƃ������Ƃł���A���̌�ɂ͂܂����z�Ƃ����Ӗ�������B
�@���A�̂悤�ȁA�V�X�e���ɓ��݂������̍��ƂƂȂ����Ă���悤�ȋ@�\�̉�݂��o�邱�ƂȂ��A���R�����I�ɍ������z���ĂȂ��邱�Ƃ��ł���Ƃ����l�����A�܂�g�����X(���z)�̔��z�Ȃ̂ł���A����͌o�������ꂾ���Œ��ڂɕ��ՓI�Ȃ��̂ɓ��B�ł���Ƃ����l���ɓ������B
�@�܂肻��́A����ꂪ���ۂɂ̓V�X�e���ɂ������葨�����Đ����Ă���A���Ƃ�l�[�V�����̗͂ɋK�肳��đ��݂���ق��Ȃ����̂��Ƃ����A�����̌������ւ̒��ʂ��������v�z�̑ԓx���B���J�͂��̖{�̏����ɂ����āA���������ԓx���A��]�I�ƌĂ킯�ł���B
�@�u���z�_�I�v�Ƃ́A���������A���z�����Ղɉ\�ł���ƍl����v�l�ɑ��āA���̏��z���邱�Ƃ̏o���Ȃ��O�����A�܂荑�Ƃ�l�[�V�����⎑�{�̌����I�ȗ�(�B���_��)��˂�����悤�Ȏv�z�̑ԓx�Ȃ̂��Ǝv���B
�@���Ƃ���ƁA�{���ŕ��J�����o���Ă��鍑�Ƃ�l�[�V�����̌������́A�}���N�X�́u���Y�l���v�ɕς���āA�ނ��V���ȗB���_���Ƃ��Ē���u�����l���v�Ȃ���̂́A���̓����ɊW���Ă���Ƃ������Ƃł��낤�B
�@���Ȃ킿�A�ނ̗�����������l���̐��i������̃V�X�e���ɓ����I�ł���Ƃ��A���o����鍑�Ƃ�l�[�V�����̑����A�܂����������ĉ���ւ̓���(�v����)���A��͂�ǂ����V�X�e���ɓ����I�ł���Ƃ������ƂɂȂ�B
�@�l�̍l���́A���J�̌���(���)�l���ɂ��Ă̍l���́A���̌����̒P�ʂ���̊T�O���A���j�I�Ȍ���(�k��)����������Ă��邪�̂ɁA���E�̌���ɑ���\���ȑR�ƁA����̓��̓K�Ȓ��o���Ȃ��Ȃ��Ă���̂ł͂Ȃ����A�Ƃ������Ƃ��B
�@�������ɕ��J�����Ă���J���g(�����ăt���C�g)�I�ȗ��j�ւ̂܂Ȃ����́A���͂�u�Љ�I�v�ł��肦�Ȃ��Ȃ������̐��E�̌�����A�I�m�ɑ����Ă�����̂��Ǝv���B��������́A���g�̂܂Ȃ����̗��j�I���萫���^��ɕt���悤�ȁu���l�̌��v���\���ɑттĂ��Ȃ����߂ɁA���܂��V�X�e���̗̏g�A�����I�Ș_�q�Ƃ������̂Ɏ~�܂��Ă���Ǝv����̂ł���B
�@���̌��E���z���āA�u�v��u���R�v�̓��e���ĐR�ɕt���������ŁA�V���Ȍ����l���̑̌n���\�z���邱�Ƃ��ł������A�����͏��߂āA�ډ��̊�@�ɑΛ�������B���_�����l���ł���̂ł͂Ȃ����낤���B
�@
�y�R�����g�z
�@
�@���c���ɂ�邱�̕��J�_�������āA�������̎��݂̑����̎n�܂�Ƃ������B����ɂ��Ă��A����Ȗ{�i�I�ȕ]�_�ɃR�����g����͎̂���̖}�f�����Ȃ݂ċC���Ђ��邪�A�ǂ݂Ȃ���A�z�������Ƃ��������߂Ă����B
�@
��A������j�ɂ���
�@���c�ȎO�Ɂu���̋c�_�̑O��v�Ƃ������͂�����i�w���_�j�I�l�@�x�A���}�Џ����j�B���̕��͂����ŋ߂܂Ŏ��͒m��Ȃ������B����ǂ��납�A�p�������Ȃ��瓡�c�ȎO�Ƃ����l�ɂقƂ�NJS�������Ă��Ȃ������B�Ƃ��낪�A���́u�R�[���v�̑O���Ɋ�e�����Ă��炢�A���̉ߒ��ŁA�����Έ����Ă����u����j�I�ȁu�����v�̗��_�Ƃ����v�i���J�j�̗��_�̎�_�Ƃ��āA�t�@�V�Y����S�̎�`�𑨂�����Ȃ��A�ނ���A����ɋ߂Â����Ƃ���ƑΏۂƓ������Ă��܂����˂Ȃ����ƂɋC�����A����Ăē��c�ȎO�w�S�̎�`�̎���o���x�i�݂������[�j��ǂ݁A���̌d��Ɋ��Q��������ł���B��������҂̎������ɂт����肵�����́u�R�[���v�O���f�ڂٍ̐e���������������Ƃ��āA���ڂ������̂́w���_�j�I�l�@�x�����́u���̋c�_�̑O��v�ł���B�����Ɂu����v�z���čl����v�Ƃ������̍čl�̎d���ɂ��Ẵq���g������Ǝv������ł���B
�@���āA�u���̋c�_�̑O��v�œ��c�́u���̎v�l�̑O��͌o���ł������v�ƌ����Ă����B���ꂪ�����Ȃ�o����������O�ɁA���c�̌����u���v���A�ӂ��R�Ǝg���Ă�����Ƃ����敪�A���Ȃ킿�A���{������E���ɔs�킵�Ă���Ȍ�Ƃ����c�����́A�����ƌ���I�ł��邱�Ƃɒ��ӂ������B1981�N�Ɂw�v�z�̉Ȋw�E�掵���n�����x�Ɍf�ڂ���A82�N�ɒP�s�{�w���_�j�I�l�@�x�i���}�Ёj�Ɏ��߂�ꂽ���̕��͂c�́u�Ƃ�킯�A�u���x�����v���o�ĎЉ�̍\�������ꂩ��ϖe���ė����������v�Ƃ�������F���ɗ����ď����Ă���̂ŁA���c�̌������Ƃ͔s���̕���������60�N�㏉�߂��炢�܂ł̂��Ƃł͂Ȃ����Ƒz�������B
�@���̂��Ƃ�O���ɂ����āA���c�̌������̎v�l�̑O��Ƃ��Ă̌o���������Ȃ���̂ł��邩�����Ă������B
�@���̎v�l�̑O��ƂȂ�o���͎O�������Ă���B
�P�D���Ɓi�@�\�j�̖v�����s�v�c�ɂ����邳���܂�ł���Ƃ������̔���
�Q�D���ׂĂ̂��̂����`���̂ӂ���݂������Ă��邱�Ƃ̎��o
�R�D�u������̐�O�v�A�u�B���ꂽ��O�v�̔����ł���A�����Ɂu������̐��E�j�I�����v�̔���
�@���̎O�̂����A�P�͂킩��₷���B���̓����̂��Ƃ������Ɍo�����Ă��Ȃ��Ă��A����̔s�킪���{�Љ�ɗ��j�I�ɑ傫�ȕω��������炵�����Ƃ͂킩��B�s��Ƃ͋��J�Ǝ��ӂ̌o���ł��������낤����ǂ��A�����ɏ����ɂƂ��Ă͑S�̎�`�̐�����̊J���������炵���킯�ŁA���Ƃ̖v�����s�v�c�ɂ����邳���܂�ł����Ƃ����̂��A�Ⴆ�Κ��h�w��\�l�̓��x�̑�ΐ搶�̊��S���ˎ����w���̍ԁx���v�������ׂȂ���z�����邱�Ƃ͂ł���B
�@�Q�́A�P�̂����ɂ��łɊ܂܂�Ă������ʂ���肾���ēW�J�������̂ƌ����邾�낤�B�Â��o���ł���͂��̍��Ƃ̖v���ɖ��邳���܂܂�Ă����Ƃ����̂����`���̌o���̈���낤�B��O�E�풆�Ɏ嗬���������l�ς��v�����A�����ɏꍇ�ɂ���Ă͑������邱�Ƃ�����悤�ȐV���ȉ��l���N���オ���Ă����Ƃ������Ƃ����邾�낤�B
�@�R�́A���I�ȐV���ȉ��l�ƌ��������̂��A���͐�O�ɉ\���Ƃ��Ă������i���푈�̐��ɂ���ė}������Ă����j���̂��A���ɂȂ��ĕ\����ɂ����ꂽ���̂ł��������Ƃ̔����Ƃ��l������B��̗�Ƃ��ẮA�I�[���h�E���x�����X�g�Ƃ��ē쌴�ɁA�}���N�X��`�҂Ƃ��ċ��Y�}�̐�㏉���̎w���ҁA���w�҂Ƃ��Ă͒Ŗ��َO���u������̐�O�v�̓T�^�Ƃ��ċ������Ă����B���Ƃ�����ЂƂ̉��l���Љ�̑O�ʂɉ����o�����Ƃ��ɁA����܂ŋ����E�������Ă������̏����l�͎����ɒǂ�����A���̒S����͏ꍇ�ɂ���Ă͖��E�����B����ǂ��A���̍��Ƃ��v������Η}������Ă��������l�̂��������炩�͑��𐁂��Ԃ��Љ�ɉ�A���Ă���B���̂悤�ȉ��l�̐��Ԃc�͎w�E�����̂��낤�B
�@�Ƃ���ŁA�Q�̗��`���̎��o�ɂ��Ă͋C�ɂȂ邱�Ƃ�����B���c�́u���̌o���̊j�S�Ƃ��ẮA�v���Ɩ��邳�A���R�ƃt�@���^�W�[�A�ߎS�ƃ��[���A�A���ׂƃ��[�g�s�A���X�̗��`���̓T�^�I�������܂��u���v���������҂̒��ɂ����݂����v�ƌ����A�u�����́u���v�̗L�肳�܂�`���Ďv�z���ɂ܂Ŏd�グ����i�v�Ƃ��āA�ΐ�~�w�ĐՂ̃C�G�X�x�i1946�j�A�������w���s�x�i1946�j�A�ԓc���P�̕]�_�Ȃǂ������āA�ΐ�~�w�ĐՂ̃C�G�X�x�̕`�����E�ɂ��Ắu�J�[�j�o���v�Ƃ������t���g���Ă���B
�@���c�̉�ڂ����オ�J�[�j���@���I�i�j�ՓI�j��Ԃ������Ƃ���ƁA���c�̎���F���͖ؑ��q�̘g�g�݂ɂȂ��炦��u�Ղ̌�v�A���Ȃ킿�|�X�g�E�t�F�X�g�D���I�ӎ��ɗ����Ă��邱�ƂɂȂ�i�ؑ��q�̘g�g�݂ɂ��Ă͑O��ٍe�Q�Ɓj�B����͒P�ɉ��ÓI�ӎ��Ƃ��������ł͂Ȃ��B�ؑ��q�́w���ԂƎ��ȁx�i�����V���A1982�j�ŁA�l�Ԃ̎��Ԉӎ����j�Ղ��L�[�^�[���Ƃ��āA�O��ՓI�ȃA���e�E�t�F�X�g�D���A��̍ՓI�ȃ|�X�g�E�t�F�X�g�D���A�u�Ղ̂��Ȃ��v���Ӗ�����u�C���g�D���E�t�F�X�g�D���v�ɕ��ނ��A�|�X�g�E�t�F�X�g�D���I�ӎ��͟T�a�ɐe�a�I�i�������R���[�e�a�I�j���Ƃ����B���͉����p�g�O���t�B�[�̂܂˂��Ƃ����悤�Ƃ����̂ł͂Ȃ��B�����A������ڂ��铡�c�̎���F�����Ձi�J�[�j���@���j�̌�ł��邱�Ƃ���A�|�X�g�E�t�F�X�g�D���I�ӎ����炭����Ƃł��������̂�����A����ɒ��ӂ��Ă��������������B
�@�ؑ��q�ɂ��A���݂��u�Ղ̌�v�Ɗ�����|�X�g�E�t�F�X�g�D���I�ӎ��́A�P�Ȃ�m�X�^���W�[�ł͂Ȃ��A�u���͂���Ԃ������Ȃ��v�Ƃ����ӎ����Ă��邱�Ƃ��Ƃ����B���c�̎v�l�ɁA���̃|�X�g�E�t�F�X�g�D���I�ӎ��ɗR�������������Ƃ�����A����́A���́u���̋c�_�̑O��v���M���̓��c�ɂƂ��Ă̌��݁i1981�N�j���₪�Ă͉ߋ��ɂȂ�Ƃ������Ƃ��l�����킳��Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃ��낤�B���c�ɂƂ��Ắu���v�͂�����x�̌o���Ƃ��ē���������Ă���B�������A����E���ȑO�ɂ��푈�͂��������A������Ȃ��Ƃ͌���Ȃ��B�ߋ����Ȃ݂�Ƃ��A��ڂ��鎋�_�͌��݂ɂ���킯�����A���̌��݂��܂����j�̂Ȃ��œ�������B
�@�������Ă݂�ƁA�u������̐�O�v�A�u�B���ꂽ��O�v�̉�A�����Ƃ͌���Ȃ��B���݂��ߋ��Ɛؒf���ꂽ�܂������V��������Ƃ��Č�������A���߂̉ߋ��ɂ����Ă͂Ȃɂ��̗��R�ɂ���Ď�������Ȃ�����������̉ߋ������݂̗v�f�ƂȂ��Ă���ƌ����Ă邱�Ƃ��ł���̂ł͂Ȃ����B
�@���x�o�ϐ����̎����A���{�Љ�͕�����g��Ȃ��푈�����Ă����̂��Ƃ�������B�P�ɎY�ƊE�����ۋ����ɏ����������߂�����ȑ����������Ƃ��������łȂ��A�����I�ɂ���ʐ푈��푈�Ƃ������t���g��ꂽ�B���Q�������������B���ێЉ�ł̌o�ϋ����ɏ����������߂ɁA�p�������ʎ��́A�ߔM��������A���Q�̎S�ЂȂǂ̋]���������ɋ���������ł��������킯���B
�@���̈Ӗ��ŁA�|�X�g���x�����̎���A70�N��㔼����o�u������܂ł́A������̐��̂悤�Ȏ����������Ƃ�������B�������Ƃ��Ă݂�ƁA�R�W�F�[�u�̃w�[�Q���u�`�̓��{�ɂ��Ă̒��ŁA���{�Љ���X�m�r�Y���ƕ]�����̂����{�����ł͍D�ӓI�ɎƂ߂�ꂽ�̂��[���������B��ɋ{��^�i�ɂ���āu�I���Ȃ�����v�ƌ���������ꂽ�A���j�̏I���̌����X�m�r�Y���A����̓|�X�g���x�����̎���̓��{�Љ�ɂƂ��Ă������肭��]���������̂ł͂Ȃ����B�u���j�̏I���v�u�[����{��ɐ�삯�ďI���Ȃ�����������ɕ\�������̂��A�A�j���[�V�����f��w���鐯���Q�@�r���[�e�B�t���E�h���[�}�[�x�i�����ēA1984�N���J�j�ł������B������A����t���̒��ҏ����w���E�̏I��ƃn�[�h�{�C���h�E�����_�[�����h�x�i1985�N�A�V���Ёj�������Ă��������B
�@�w���^���ł��u�O���ڂ̗[�z�v�ł��Ȃ��A�������60�N��A���肦����������Ȃ��ʂ̐��ւ̖G�肪�A�|�X�g���x�����̎���ɉ�A���Ă����̂�������Ȃ��B���x�o�ϐ����ɂ���Ď���ꂽ���̕ʂ̉\���Ƃ��Ă����Ɏv�������Ԃ̂́A�a�ғN�Y�炪�句�����������ƘH���ł���B���ہA�s���A������b�������V���S�̈˗��ō�������N���������������_�́A70�N��Ɂw���҂����l�ԑ��x�i�����R���\�̕t�ѕ����j�Ƃ��ĐV���Ȃ鑕���ƂƂ��ɍēo�ꂵ���B�������������́u���s�w�h�̕����v�ƌĂꂽ���Ƃ����邪�A�P���Ȑ�O��A�Ƃ݂Ȃ������A���x�������ȑO�̐��̉�A�ƌ����������Ԃɋ߂��̂ł͂Ȃ����B
�@����ł́A�|�X�g���x�o�ϐ����̎���̌o���Ƃ͉��������̂��B����܂����c�̌��t�����Ȃ�A����͂����炭�u�r���̌o���v���낤�i�u����r���̌o���v���c�A�O�f�������j�B�������������A�������܂ꂽ���A�����A��������ꂽ���A�����Y���ꂽ���ɒ��ڂ��Ă��̎���̒m�I�c�݂̊T���}�߂Ă݂�ƁA�����ȓ��������邱�ƂɋC�Â��B������`�̕s�݂ł���B
�@
�u�v�Ɓu���R�v�̍ĐR�ɂ���
�@���\�N��ɓ��{�v�z�E�̃`�����s�I���Ɩڂ��ꂽ�����Y��Y�Ɂw���c�N�w�̒E�\�z�x�i��g���X�A1987�j������B�����̐��c�_�̓|�X�g���_���̗��ꂩ�琼�c�N�w���m��I�ɕ]���������̂ƕ]���ꂽ���Ƃ����������A���́w���c�N�w�̒E�\�z�x�ł͐��c�̌��E�ɂ��āu���������S��`�̕\���ɑ��Ă��܂����v�Ǝ茵�����B�w�[�Q���Ɛ��c�N�w�̑Δ����Ƃ���u�I�́@���c�����Y�̏@���_�Ɨ��j�_�v�ɂ����ẮA���c���w�[�Q���A�}���N�X�A�L���P�S�[����ُؖ̕@�ƑΌ����A���̏��z�����͂��������Ƃ�`�ʂ��Ȃ���A���c������́u�ꏊ�I�ُؖ@���w�[�Q���A�}���N�X�̉ߒ��I�ُؖ@���܂ނ��̂��Ƃ��Ă���v���Ƃɂ��āu���̂悤�Ȑ��c�̌������ɂ͖���������A�\���ɍ����Â����Ă��Ȃ��v�Ǝa��̂Ă���ŁA�u���c�̏ꏊ�I�ُؖ@�̂�����傫�Ȗ��́A�����Ƀw�[�Q���|�}���N�X���ُؖ̕@�̊j�S�I�����Ƃ������ׂ����a�O�I�q�̉����⁃���ۉ����̘_�����A�������ɂ���Ċ܂݂��܂�Ă��邱�Ƃł���v�Ɛh煂ɔ�]���Ă���B
�@�܂�A�w�[�Q���̌��t�ł����u�q�ϓI���_�v�̈ʑ��ɂ��Ă̓��@�����c�ɂ͌����Ă���ƒ����͌����Ă���킯���B
�@�����́A���c�̕s�������z���鎎�݂Ƃ��āA�w�����ƘJ���x�A�w�����I���E�x�A�w���c�����Y�̐��E�x�Ȃǂŋ����N�w�������؋��ƁA�����Ƃ����������ɓ��ݓI�ᔻ�w���c�N�w�̍��{���x���A���́u<�푢�����n����>�̐_�w�v���`�Â�������Ȃ������Ă���B���҂Ƃ������N�w�I�v���Ɏ�����u���A�@���i��͕����A���̓L���X�g���j�ƃ}���N�X��`�Ƃ������ݒ�ŋc�_��W�J�����v�z�E�ɃC���p�N�g��^�����B�����A���������c�_�\�������\�N�㓖���A�����̖���N�͂��̘g�g�ݎ��̂��Âт����̂Ƃ݂Ȃ���āA���܂蒍�ڂ���Ȃ������悤�ɋL�����Ă���B���ꂩ��O�\�N�߂����������A�Y�p���p�����������@��͂߂����Ă���̂��낤���B
�@����Y�ꋎ��ꂽ�܂܂ł��闝�R�̈�Ƃ��āA������`�̒���������B�����I�ȊS���̂͌��݂ł�����Ɍ���Ă���B�ꎞ�͍ĕ]���u�[���ƂȂ����A�[�����g���n�C�f�K�[�ƃ��X�p�[�X�̈���q�ł���B�Ƃ��낪�A�u���^�����f���k�v���ɋ��������`�̎�����`�̑�\�҂̂����A�{�[���H���[���̓t�F�~�j�Y���̐��҂̂ЂƂ�Ƃ��āA�������]�|���e�B�͒m�o��g�̂̌��ۊw�҂Ƃ��Čڂ݂��邱�Ƃ͂����Ă��A������`�҂Ƃ��čĕ]������邱�Ƃ͂Ȃ��B�����ċɂ߂��̓T���g���ł���B1980�N�A�T���g���̎��́A���̏I�����ے�����悤�Ȏ��Ƃ��đ�X�I�ɒǓ�����A�����Ă����ɖY�ꋎ��ꂽ�B����A�Y���ꂽ�Ƃ�����薕�����ꂽ�ƌ����������߂��B���E���̐S�����͂��炢�Ă����̂ł͂Ȃ����Ɗ��J�肽���Ȃ邭�炢�̖Y����Ղ�ł���B���̌�A�T���g���{�l�Ɛ�ʈ����̂��郌���B�i�X�̎����_�I�N�w�����Ă͂₳�ꂽ�̂ɁA���܁A�T���g�����������v�z���̐V�����قƂ�nj������Ȃ��Ȃ����B���ɃA���o�����X�Ȍ��i�ł���B
�@���̉����ۂ̐����̈�Ƃ��čl������̂́A������`���̂��̂̐��ݗ͂����ނ����̂ł͂Ȃ��A������`�ƃ}���N�X��`�Ƃْ̋��W�Ƃ�����������ꂽ�̂��Ƃ������̂��B���{�̐����v�́A������A�����J�̎哱�ɂ���Ă����Ȃ�ꂽ�B�������A����ȊO�̉\�Ȑ��Ƃ������̂����@�[�`�����ɂ͂��肦���͂��ŁA�Ď哱�ɑR����ʃR�[�X�̐��̗��O���v�z�̃��x���ŒS�����̂��}���N�X��`�Ǝ�����`�ł������ƌ����Ă邱�Ƃ��ł���i�Ď哱�ɑR����v�z�͑��ɂ����肦�����낤���A�����ɉe���͂��������̂̓}���N�X��`�Ǝ�����`�������j�B�����ŁA����������炿�Ȃ��瑊����ʂƂ����������̎v�z�ْ̋��W����g�ɑ̌��������̂悤�ȃT���g���͐��v�z�E�̃X�^�[�Ɩڂ��ꂽ�B�������A���\�A�̐��ނƂƂ��Ƀ}���N�X��`�������I�ȑI�����Ƃ݂Ȃ���Ȃ��Ȃ�ƃT���g���l�C�������肪�����n�߂�B�܂�A���ނ����͎̂�����`�ł͂Ȃ��A�}���N�X��`�Ǝ�����`�ْ̋��W�Ƃ������ݒ�̕��������B
�@�������A���ۏ�̕ω��ɂ���Ė��̘g�g�݂ւ̊S�����ꂽ�Ƃ͂����A�ނ�̎v�z�I�c�ׂ̓}���N�X��`�Ǝ�����`�ْ̋��W���ǂ��������邩�Ƃ������Ƃɐs������̂ł͂Ȃ��B�\�c�ꗍ���ɖY�ꋎ��ɂ͐ɂ�����Y�ł���B�L���P�S�[���̓w�[�Q���̓N�w�̌n�Ƃ̑Ό��Œm���邪�A�ނ̓����͗��_�ʂɌ���ꂽ���̂ł͂Ȃ��A����Ƃ��������̃V�X�e���Ƃ̓����ł��������B�u�v��u���R�v�̓��e���ĐR���悤�Ƃ���Ƃ��A�L�`�̎�����`���ǂ��p�����邩����̃|�C���g�ɂȂ�̂ł͂Ȃ����Ǝv���B
�@
Web�]�_���u�R�[���v19���i2013.04.15�j
������v�z���čl���遄��P��[��Q��]�F���J�s�l�w���E�j�̍\���x�̘g�g�݂ɂ��āi���c�L���j
Copyright(c) SOUGETUSYOBOU�@2013 All Rights Reserved.
|
| �\���i�ڎ��j�� |