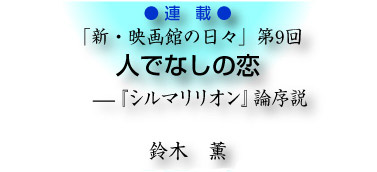|
|
|
Web評論誌「コーラ」 |
|
■創刊の辞 ■本誌の表紙(目次)へ ■本誌のバックナンバー ■読者の頁/ご意見・感想 ■投稿規定 ■関係者のWebサイト ■プライバシーポリシー |
|
<本誌の関連ページ> |
|
■「カルチャー・レヴュー」のバックナンバー ■評論紙「La Vue」の総目次 |
Copyright (c)SOUGETUSYOBOU |
|
|
J・R・R・トールキンはいまだ発見されていない未来の作家である。『指輪物語』があれだけ評判を取ったのは、何かの間違いだろう。いや、あれに(あるいは映画化されたものに)惹きつけられ、ファンになったというのなら、それはそれでいい。『指輪物語』は確かに「快楽の装置」[☆1]であって、『シルマリリオン』(邦訳『シルマリルの物語』[☆2])を知らなくとも十分に楽しめるものであるから。驚くべきは、少なからぬプロの書き手が、賞賛すべき『指輪物語』の作者トールキンの作であるという理由で、やむをえず(としか思えない)これに言及する際、それが彼らにとっての「快楽の装置」として機能しないため、これは『指輪』のための舞台を準備したものにすぎないと言いくるめて、おのれの不能ぶりを糊塗し、また、自らの理解力のなさを棚に上げて、『シルマリリオン』を“難解”と呼んではばからないことだ。
『指輪物語』は実のところ『シルマリリオン』から派生したものであり、いかに長大であれ、また、切り離してそれだけで読めるにせよ、その副産物でしかない。職業的小説家ではなかったトールキンの生涯をかけた“主著”は、どう見ても『シルマリリオン』である。『シルマリリオン』に作者が入念にほどこした仕掛けが見分けられなければ、『シルマリリオン』と『指輪物語』がどう繋がっているのかもわかりようがないはずだ。
トールキンが「同時代の大多数の鑑賞者」の目に信を置いていなかったことは、『シルマリリオン』の次の一節にも見て取れよう――「太陽が作られる以前に世を去り、今は世の終わりを待つマンドスの館に坐して、同族の許にはもはや帰らぬフェアノールが戻ってくる日まで、太陽が消滅し、月が落ちるその日まで、シルマリルがいかなる物質で作られたかは知る術もない」(強調引用者)
シルマリルとは、エルフのフェアノールが、人間がまだ存在しなかった時代、西方の楽園ヴァリノールにおいて、「密やかな、長い時間をかけ」、「持てる知識と力と精妙なる技のすべてを尽くし」て造り上げた三つの宝石である――こんなふうに説明したところで、何がわかるというのだろう。『指輪物語』の「一つの指輪」は、その廃棄という、物語のエンド(結末=目的)にしっかり結びつけられていたし、他の指輪もそれなりに実際的な効用を持っていた。しかし、シルマリルは――あれが何であるのか、何の役に立つのか、さらに言えば、シンゴルがあれほど執着したのはなぜか(手に入れたシルマリルを、彼は昼も夜も身につけていたいと望んだのだ)、納得できる答えを出した人がいるだろうか。「太陽が消滅し、月が落ちるその日まで」とは、酔狂で書かれた文句ではないのだ。
シルマリルは、楽園ヴァリノールの聖なる二本の木が放つ「始原の光」を閉じ込めて造られ、二本の木が堕天使(と、とりあえず呼んでおこう)メルコールの襲撃に遭って破壊されたのちは、楽園の光はシルマリルの中にしか存在しない――そんなふうにシルマリルの重大さを強調したとて、そうした設定が何を意味するのかを知らなければナンセンスでしかない(このナンセンスが公然とまかり通っている)[☆3]。なぜシルマリルは三つあるのか。楽園の「始原の光」とは、なぜそんなに貴重なのか。答えられる者はまずいまいが、それも無理もないことだ。なぜなら、シルマリルという物の由来が、言いくるめられ、誤魔化され、すりかえられて、ついに完全に隠蔽されるに至るまでを語ったものこそ、シルマリリオン(シルマリルの物語)であるから。
フェアノールがシルマリルを造ったとき、ヴァラール(トールキン世界における神々のようなもの――と言っておこう)の一人であり、運命を司る〈神〉マンドスは、「シルマリルには、アルダの運命、大地、海、空気が閉じ込められている」と言った(アルダとはこの世界での地球の呼び名)。作中の誰も異議を唱えず、不審に思いもしないようで、それ以上説明されることもないが、被造物の手になる一作品に与えられるにしては、これはまた恐しく過分な言葉ではあるまいか。しかも、『シルマリリオン』を最後まで読んでもマンドスの言葉に対応するような記述は無いのだから、やはり『シルマリリオン』はわけがわからない――のではなく、これはわけがわからないように書かれているのである。
「シルマリルには、アルダの運命、大地、海、空気が閉じ込められている」とはどういうことか。たんにそう考えたとて、答えなど出てくるはずがない。いかに技に優れているとはいえ、エルフの一工人が作ったにすぎない宝石に、なぜ世界のすべてが含まれているのだろうと首をひねるのはやめて、逆に、「アルダの運命、大地、海、空気が閉じ込められている」のはいったいどこかと問うてみよう。そういう場所は一つしかない――『シルマリリオン』という小説自体だ。だからここでは、「シルマリル」に『シルマリリオン』が重ねられ、シルマリルの作者フェアノールに、『シルマリリオン』の作者トールキンが重ねられているのである。 つまり、シルマリルにことよせて、ここでトールキンは、「密やかな、長い時間をかけ」――なにしろ、生きているうちはついに完成を見なかった――「持てる知識と力と精妙なる技のすべてを尽くし」た自分の『シルマリリオン』もまた、はるかな未来に至るまで(太陽が消滅し、月が落ちるその日まで)、理解されることはない、まして君たち、同時代の読者にはわかるまいと、はっきり宣言しているのだ。「かれと似た者は二度と再びアルダには現われなかった」という、フェアノールについて書かれた文句は、芸術家としてのトールキンの自己言及として読まれるべきだ。彼がハイ・ファンタジーの祖だなどというのは作り話で、彼の衣鉢を継いだり、彼を父祖として仰いだりして書いていると称しうる作家など、ただの一人もいるはずはないのである。
『シルマリリオン』はわけがわからないように書かれている。では、「わからないように書かれている」ものとは何か。端的に言って、それは性的なものである。それも主流のヘテロセクシュアリティとはおよそかけ離れている――(“児童文学研究者”の目を必然的にすり抜けることはこれだけでも察しがつこう)。といっても、出回っているポートレートではいささか気味の悪い目つきでこちらを見返している禿げ頭のC・S・ルイスとトールキンの「同性愛的」関係だの、女を締め出した「インクリングズ」で、オックスフォードに奉職する男どもが築いていたホモソーシャル空間だとかの話ではないし、第一次大戦時のトールキンと彼の従卒がモデルだという、フロドとサムのカップルにすら、ほとんど関係がない(フロドとサムについて何か言うなら、少なくとも『指輪物語』の追補篇まで読んでからにすべきだろう)。トールキンが〈異世界〉を創造したと、人はあまりにも軽々しく口にしてきた。それが彼らの想像もつかぬ〈異世界〉だとも気づかずに(本当に『シルマリリオン』を動かしている原理を知ったら、彼らは腰を抜かすだろう)。
ウラジーミル・ナボコフについてなされた若島正のこの指摘は、まるで『シルマリリオン』について言われたかのようだ(作品内の細部の照応が読み取れなければ、こと『シルマリリオン』に関しては、外部から持ち込んだ見当はずれのことを――世の終りまで――言い続けるしかあるまい)。若島はこうも述べている。「文学は教えることのできないものだという考え方がある。文学の勘所は、いわばあうんの呼吸で会得すべきものであり、それがわからなければしょせんは文学に無縁な衆生だと一蹴される。しかし、ナボコフの小説では、読み方のルールさえ心得ていれば、本当は誰が読んでも同じ答えが出てくるような側面がたしかにある。本書では、できるかぎりそういう側面を取り上げて解説する。つまり、ここにこの駒が配置されているのはどういう意味だろうか、という考え方を好んでする」(強調引用者)。
たとえばナボコフを読むようにして、トールキンは読まれなければならない(それがわからないから、駒の配置の仕方が美しいとか、トールキンの実人生に似ているとか、ざれ言を並べて研究と称するのだ)。その気になれば、トールキンにはいくらでも普通の小説らしいものを書くことができたのは、『指輪物語』なり、未完の断片なりを見れば了解されよう。また、彼は、「ホビットの冒険」や「農夫ジャイルズの冒険」に見られるように、ユーモアあふれるストーリー・テリングの技も持っていた。だが、そのやり方では、「主題の実現」は不可能だった。いろいろ試みた結果(ルイスにはSF三部作があり、彼にも未完の時間旅行ものがある。そういう方法もあることを、彼は知らなかったわけではない)、どうやらある方法でなら、書けるとわかった。その結果として私たちの前にあるのが『シルマリリオン』で、これは二十世紀の直前から後半まで生きた一人の英国人のペン先から生まれたよく統御された構築物でこそあれ(『ベンドシニスター』の幕切れのようなあざとさは彼の流儀ではないとはいえ、イルーヴァタールという“唯一神”は、たとえばナボコフのあの小説に現われる書斎の〈作家〉を思わせないだろうか)、神韻縹渺たる太古の昔を髣髴とさせるとかなんとかいうのは(仮にそれが本当だとして)テクストの効果であるのだから、あれこれ起源探しをして、神話だの原型だの(あるいはカトリシズムだの)にトールキン作品を還元するのは大概にするがいい。全体主義を逃れての亡命者の実存にナボコフを還元できないのと同じことだ。
瀬田貞二訳の『指輪物語』は、学生の頃に赤いクロス装のハードカバーで読んだ(その後、O先生によるOn Fairy Storiesの講読に、英文科の女子学生に混じって出席した)が、『シルマリリオン』を読んだのは今年に入ってからのことでしかない。友人の平野智子が『シルマリリオン』を読み、しきりにこれについて話してきかせるので、手に取ることになったのだ。彼女に導かれることなく読んだとして、果たしてどれだけわかったか、実を言えば心もとない。とはいえ、『シルマリリオン』について活字になったものに目を通すに至って、いくら何でも彼らの読めなさはただごとでないと知った。平野の鋭い読みには及びもつかないにしても、こんなにはっきり表に出ているものを、なんで専門家たちは全く気づかず、的はずれなことばかり言っているのか。平野の読みのレヴェルの高さは、そこまで読み得ている――細部の照応や小説全体の組み立て方の驚くほどの緻密さを含めて――のは世界中で二人といまいと(けっして誇張でなく)思われるほどだが、感嘆する私に、先入観抜きで読めばそれ以外には読めないという意味のことを彼女は言った。確かに、本当は誰が読んでも同じ答えが出てくるはずなのだ。書かせてくれないかと筆者は申し出た――その無謀さに気づかずに。
その時はまだ、書くだけの材料は手のうちにすっかりそろっているかに思われた。だが、発見はそれでは終らなかった。『シルマリリオン』における「細部の照応や小説全体の組み立て方の緻密さ」は、半端ではなかったのだ。ナボコフの『青白い炎』を、メアリイ・マッカーシーは「自分でしあげる組立部品」と呼び、「ばらばらな部品を製造業者の指示に従ってよせ集め、さまざまな手掛りや相互参照の助けをかりて組立てると、いくつもの層からなる一箇の小説作品が現われてくる」(「晴天の霹靂」加藤光也訳)と言っていて、これもそのまま『シルマリリオン』にあてはまるのだけれど、トールキンの場合、さすが一生をかけただけのことはあり、組み立てに時間がかかるのはやむをえまい。平野は「製造業者の指示」をこつこつ読み解いているが、ここでは筆者は対象を『シルマリリオン』の先行作品であるトールキンの物語詩「領主と妖精の物語[レー]」(「ユリイカ」1992年7月号に掲載された辺見葉子訳)に限って、ささやかな解釈を試みることにする。
ちなみに、性的なものを無視することは、同じトールキン特集に別の研究者によって訳出されている未完の物語断片『失われた道』に付された解説にも顕著である。父が息子の裸体を想像したり、実際に見入ったりする描写に読者は驚かされ、トールキン研究者である訳者がどのようにこれを評しているか、ぜひ読みたいと思うだろうが、期待は完全に裏切られる。御本人が訳した本文を見れば(訳して紹介してくれたこと自体は非常にありがたいが)一目瞭然なものを、完全に無視してなかったことにするかのように、ポイントをはずしたお喋りが続くのだ。「本書はフィクションの形態を採ってはいるものの」、トールキンの「人工言語構築の具体的プロセスを間接的に記述している」と訳者は言うが、通常のエディプス・コンプレックスの成立しない〈異世界〉におけるエルフ語のデフォルト会話は、他ならぬ父子相聞のそれである(「アタラニャ、テェ=メラーネ、父上、汝を愛します――それは耳慣れぬ、しかし甘美な言葉としてエレンディルの耳に響き、かれの胸を衝いた。「ア・コニャ・イニェ・テェ=メーラ、吾もまたそなたを愛している」かれは言ったが、その一語一語が耳慣れぬものながら麗しいものに響いた」)。父の胸をときめかす甘美さ、麗しさが、音の響きからのみ来ると聞き違える者はまさかいまい[☆4]。
トールキンは「作家」としてまともに論じられてこなかった。伝記的には敬虔なカトリックであったことが二言目には持ち出され、あたかも個人的動機や同時代の文学の影響など全くなしに、現実に存在する神話(ギリシア神話や北欧神話といった)と同列の「神話」を独力で書こうとしたかに語られる。児童文学者にせよ、いわゆる「ファンタジー」の研究家にせよ、人工言語を作ろうとした言語学者として注目するにせよ、トールキンをトータルに論じることはなく、多くは自分の関心に引きつけて、毒にも薬にもならないことを書きつけるだけだ。『シルマリリオン』の同性愛的な読みとは、言うまでもないことながら、ありもしないものをそこに読み込むことではない。はじめから存在しながらかえりみられることがなかったもの、本来それなしには成立しないはずのものを見て取ることだ。そして、それを読み取るのに、当人の性別も、性的志向も、本来、関係がないことは論をまたない。トールキンのケースは、ホモフォビア/セックスフォビアが、批評の質を救い難いまでに低下させている典型であろう。
ところで、『指輪物語』の映画化以来、トールキン作品については、いわゆる“二次創作”が盛んに行なわれるようになった。興味深いことに、『シルマリリオン』についてこれをやっている女性たちは、ウェブで見るかぎり、実のところ研究者たちよりも、はるかに細部に即した、正鵠を射た読み方をしている(平野が見出したような構造には触れえないにしても)。しかし、残念なことに、こうした読みを実践している女性たちの多くは、自分のしていることを自分で信じていないようだ。一方に、お行儀の良い公式の「解釈」があり、他方に彼女たちの「妄想」があると思って、前者には無条件で敬意を払わなくてはならず、自分には発言権がないと感じているのだ(言うまでもなく、この最悪の形態は、自分が貞淑な女であることを証明するため、同性を無意識に抑圧する側に回ることだ)。こうしたメンタリティは、要するに、彼女らが女――「男にとっての女であること」以外に、そのセクシュアリティを認められたことが一度もない存在――であることの結果である。「やおい」 を論ずるフェミニズム研究(と呼ぶにふさわしいもの)があるとしたら、それは、所詮男との関係において女を規定するものである、異性愛の変形だの、同等な関係を求めて男同士に仮託しているだのといった頭の悪い無害な議論ではなく[☆5]、“本物の同性愛”は差別してはならないが、女による“二次創作”なら揶揄や攻撃の対象にしてよいといった了解の蔓延する、この腐り切った状況に対する批判的考察をおいてはありえまい。
*
人でなしの恋■はじめに
「ユリイカ」の1992年7月号(トールキン生誕百年特集)には、同特集のために物語詩「領主と奥方の物語[レー]」(The Lay of Aotrou and Itroun)を訳出した辺見葉子の、解説を兼ねた論文「ブロセリアンドの森の伝承――トールキンのブルトン・レー その背景と典拠」が載っている。それによれば、原題のAotrouおよび Itrounとは、LordおよびLadyに相当するブルトン語で、もともとレー(Lay)とは、ブリタニー(ブルターニュ)に住むケルト人、すなわち「ブルトン人がその伝承譚をもとに作り、歌った作品のこと」だそうだ。「しかしブルトン人が歌ったレーは現存しないので、その性質は今となっては、十二世紀半ばのマリー・ド・フランスなどの言及をもとに推測されるのみである。」
ブルトン語作者の手を離れたレーは古フランス語で、さらに中英語によって書かれ、辺見によれば、後代の模作に他ならないトールキンの物語詩は、「まさに正統なブルトン・レーと呼んでいい」特徴をそなえている。マリー・ド・フランスが自作についてブルトン語のレーに典拠があると主張したのに倣い、レーの作者がそう述べることは、「以後のブルトン・レーの常套文句となった」。だが、前述のとおり、ブルトン人のレーは現存しないのでこれは形式的なものだったようだ。しかし、トールキンの「領主と奥方」の場合、挿入された「ブルトン人の竪琴弾きが今なお語り継ぐように」という文句の裏づけとなる、「典拠作品と限定することが可能なブルトン語の作品が存在する」と辺見は言い、ブリタニーのバラッド「領主ナンとコリガン」を特定している。
「領主ナンとコリガン」は研究者により「ブルトンD」と呼ばれるとのことで、本稿でもこれに倣う。辺見は「ブルトンD」および他の類似作品とトールキン作品の異同について詳述しているので、以下、この論文の助けを借りながら、テクストの細部を見てゆくことにする。また、ここでの議論は辺見の翻訳と解説なしにはありえず、多くの恩恵を受けているが、トールキンの作品についての辺見の解釈には疑問があるため、順次それをも述べてゆく。なお、「エピローグ――無垢な女」のコンセプトは、平野智子に特に多くを負っている。
■蒼白い水と聖なる水
この物語詩は、領主である人間の男が、超自然的な水の魔女――セイレーン、ウンディーネ、ローレライといったファム・ファタール的水妖を想起されたい――のために身を滅ぼすという結構を持っている。最初、彼が魔女のもとへ行くのは、以下に述べられるとおり、妻に子ができないためだ。
求愛し、指輪を与えて娶った妻は
暮らしを愛溢れるものにしてくれた。だが、
領土と剣を受け継ぐ嫡子がいないのでは、
誇りは空しく、財宝もまた虚しかったのだ。
「心の冷えるような手立てを選んだ」ことを自覚しながら、領主は魔女の住処へ馬を進める。
人里離れた丘の間の、魔女の虚ろな谷、
その底は黒く、縁は薄暗い。
ひっそりと、洞穴の前の石の座に魔女は一人座っていた。
領主の頼みを了解して洞穴の中へ入って行った魔女は、再び姿を現わすと、「さえざえと美しい玻璃の瓶」を彼に手渡す。
瓶の中の秘薬は
霜凍るような岩間の泉からほとばしり
灰白色の洞穴の、窪んだ淵へと流れ込む
薄い灰色の水に似て、うっすらと蒼味を帯びていた。
玻璃の瓶を持ち帰った領主は妻に、魔女に会ったことを黙っており、明らかにそのことを後ろめたく思っている。館へ戻った翌朝には「見せかけの喜びをその身に纏い、うれしそうな振舞でその心を覆い隠した」とあるし、奥方に未来への希望にあふれた言葉をかけるくだりでは、「彼は厳かに語った、偽りの誠実そうな眼差しで」と言われる。
しかし、何と言っても領主の最大の裏切りは、葡萄酒に混ぜた魔女の秘薬を、そうと知らせることなしに、奥方に飲ませたことだろう。この結果、彼女は男女の双子を産む。ブルトンDには秘薬は出てこず、また、「結婚して一年目の領主と奥方に双子が誕生」するところから物語がはじまるそうであるから、これがトールキン作品の典拠と判断される理由の一つが「双子の誕生」という細部の存在であるとはいえ、魔女の薬による妊娠とは、トールキン独自のアイディアであるようだ。領主はもう一度コリガンを訪ね、三度目には熱にうなされてその姿を幻視するが、その度ごとに彼女の見かけは異なっている。最初に秘薬を与えるときは老婆であり、最後の時もやはりそうだが、二度目の時は黄金の櫛で髪を梳く水の妖精の姿で領主を誘惑する。
辺見によれば、「一人の水の女神が同時に豊饒女神であり、醜い老婆であり、猛々しい戦いの女神であるという多面性を持っていることは、ケルトの伝承としてはごく自然なことであった」というから、コリガンが老婆の姿をとること自体はさほど不思議ではないのだろう。彼女は、薬の謝礼に領主が「震えながら」差し出す黄金を受け取らず、「いや、必ずやまた逢うことになろう。効果があったとわかるまで謝礼はお預けとしておこう」と、「笑いながら嗄れ声で」言う。
二度目に領主がコリガンのもとに赴くのは、少なくとも意識的には自らの意思によるのではない。子を持つという願いが叶った奥方に、もう望みはないか、言わずにいる願いはないかと問うて、「どうしたことか、心の悩みと痛みが癒された今、/また激しい渇望がしばしば襲って来るのです。」と告げられるのだ。
「殿、」と奥方は言った。「本当なのです、
夢の中で激しく身を刺すような願いを抱いていたのは、
ひんやりとした澄んだ水
そして緑なす森の鹿の肉、
水晶のような透明な冷たい水
そしてこの世の森にはいない鹿。
そして目覚めてもまだ、この愚かな願いが襲ってきて
私を思い煩わせるのです。
でもあなたを今日もこれから先も、決して
私のそばから離れて行かせたりはいたしません。」
それでも彼は、妻の願いを叶えるため、進んでほの暗い森へ入り込む。
森を縁取り、ひさしのように延びた枝の葉陰、
一頭の白い雌鹿がびくっと跳ねた。
雌鹿は陽光の下で妖しくきらめいた。」
辺見によれば、白い雌鹿とはブリタニーの水の妖精がしばしば化身する動物で、「トールキンのレーに登場する白い雌鹿ももちろんこのたぐいであり、ブロセリアンドの森に棲む水の妖精コリガンが、領主をおびき寄せるためにとった姿である」。領主は「森の中の幽かな笑い声」をも気に留めず、雌鹿を追って馬を駆る。
彼は苛まれていたのだ、
美しく恐れ気もなくさまよう鹿、
人間が捕って食べることのできないその獣の肉、
そして聖なる泉からはけっして湧き出ることのない
水晶のように澄んだ冷たい水への不思議な渇望に。」
奥方の願いとされていたものが、実は自らを欺く口実であったかのように、鹿を追う彼自身の「渇望」に他ならなかったことが、ここでは明らかにされている。ここで魔女の泉から湧き出る水と対立させられた「聖なる泉」は、先へ行って出てくる領主の科白と最終節では、はっきり「キリスト教徒の聖なる水」と呼ばれており、この渇望自体がキリスト教下では罪であることを物語る。
日が沈むと同時に、領主は求めるものを見出す。
日は暮れ、緑はことごとく灰色になった。
と、妖精の泉がきらめいた。
洞穴の前、銀色の砂の上
ブロセリアンドの暗い枝の下で。
泉を取り巻く草は柔らかく、その水は澄んでいた。
領主はひんやりと冷たい水で顏を洗った。
そして魔女があらわれる。
彼女を見たのはその時、洞穴の前の
銀の椅子の上に。髪は蒼白く
口には薄ら笑いを浮かべ、そしてブロセリアンドの森で
手招きしているその手は白い。
辺見は書いている。「こうして領主をおびき寄せたコリガンは、典型的な水の妖精のしぐさで領主を迎える。月の光に輝く長い髪を、黄金の櫛で梳いているのだ。[...]まさにセイレーンや人魚の誘惑の場面なのだが、トールキンの描くコリガンは、官能的な魅力で男たちを虜にし破滅させる典型的な水の妖精とは少し様子がちがう。金色のはずの髪は蒼白く、その髪をコリガンは一房一房引き抜いては、はらりと落として見せるのだ」。
上のようにパラフレーズされた部分は、トールキンの詩句を直接引くなら、「黄金の櫛をすべらせ/一房、一房、髪を引き抜くと、あたかも谷間に流れ落ちる湧き水のように/それは落ちゆくのだった。」である。ここでコリガンの髪が金色ではなく、月の光と同質のpalenessを持つことは、『シルマリリオン』における「髪の色」の重要性を思えば見逃すことのできぬ細部であるが、髪の房が落ちる際の直喩も、それに劣らず重要である。なぜなら、領主に与えられた秘薬は「霜凍るような岩間の泉からほとばしり/灰白色の洞穴の、窪んだ淵へと流れ込む/薄い灰色の水」に喩えられ、奥方が葡萄酒に混じたそれを飲み乾すときもなお、「灰白色の洞穴にある窪んだ淵の/薄く凍るような水に似て、うっすらと蒼味を帯びている」とされていたのであり、ここに至って、コリガンの「流れ落ちる」「蒼白い」髪と、妖精の泉からほとばしり、窪んだ淵に流れ入る冷たい湧き水、そしてその水に喩えられる秘薬は、相通じるものであることが明らかにされたからである。
それかあらぬか、秘薬の代償としての愛を拒まれた妖精は、「それならば、よくも私の蒼白い水を/こんなに乱しておきながら、私に顔向けができたものです。少なくともこの代償は請求しましょう」と言う。このとき、「私の蒼白い水」とは「私の蒼白い髪」の謂でもあろう。
■「おまえの暗闇に包まれた洞穴」
そもそも領主とコリガンはどのような関係にあるのか。領主が子のできぬ悩みを抱いて彼女を訪ねたとき、二人は初対面であったのか。テクストが語るのは、領主が「重く緩慢な足取りで」「ためらいがちに/石の座へと向か」い、「彼の言葉は弱々しく風に震え」、「言葉はほとんど要らなかった」こと、「彼の名前を老婆は知っていた、彼の用件も、思惑も、彼をここまで駆り立てた、ある渇望のことさえも」――ということだけである。
これについて、辺見は、ブルトンDおよびヨーロッパ各地に分布する類似作品を挙げてトールキン作品と比較しているが、それによれば、あるバラッド(「イギリスのヴァージョン」)では、主人公の相手は人魚であり、「人魚と主人公とは偶然出会ったわけではなく、以前から交渉があったらしく、人魚の愛人を捨て人間の妻を選んだために、人魚の復讐を受けて、命を奪われるという展開になっている」。そしてブルトンDでは、「領主はコリガンの泉の水を乱したことを責められ、コリガンと結婚するか、または人間の妻を選びその結果死ぬかという選択を迫られるが、コリガンと以前に関係を持っていた様子はない」。これに対し、「トールキンのコリガンの描写が伝統的な水の妖精と異なることについては既に触れたとおりだが、水の妖精によって破滅に導かれる理由も、トールキンのレーの場合は独自のものである」と辺見は主張し、その独自性を論ずるにあたって、「イギリスのヴァージョン」との違いを次のようにまとめている。
そうだろうか。私たちには、領主とコリガンの過去の――詩の始まる以前の――「交渉」は、十分に性的なものであって、領主をコリガンのもとへ駆り立てた「渇望」もまた、コリガンの与える「この世のものならぬ官能の悦び」(「この世の森にはいない鹿」「人間が捕って食べることのできないその獣の肉、/そして聖なる泉からはけっして湧き出ることのない/水晶のように澄んだ冷たい水」)を再び追い求めるものであるように思われる。コリガンの洞穴の前で、柔らかい草に囲まれた「ひんやりと冷たい水」を乱したとき、領主はすでに罪を犯していたのではないか。
私たちには、トールキンのレーは、ブルトンDと「イギリスのバラッド」を巧みに組み合わせたもののように見える。領主は、「イギリスのバラッド」の、人魚の愛人を捨てた男のように、一度はコリガンを去って人間の女を娶った。しかし、子を授からないため、思いあぐんだ末、別れた愛人の魔力を借りに行ったのだろう(この部分が、トールキンの「改変」/「独創」ということになる)。コリガンは老婆の姿でこれを迎え、その場では復縁を求めないが、薬の効果があらわれる「その曉にこそ高い謝礼を払ってもらおう/何でも私の望むものを」と言い放つ。双子誕生後、ブルトンDと同様、領主は白い雌鹿を狩ってコリガンの下に至るが、まるで自分が、それが魔女とのはじめての出逢いであるブルトンDの主人公であるかのように、「おまえなど知らない、おまえなど知らない、/おまえの暗闇に包まれた洞穴も見たことがない、/ああ、コリガン、おまえのためではない、/ここへは気の向くままに狩りをしてやって来たのだ。」と言いつのる。
だが、これはいかにもしらじらしい言い逃れであり、彼の言葉はすべて逆転されるべきで、以前から領主は彼女を、その「暗闇に包まれた洞穴」を知り、「人間が与り知らない深い恍惚」、人間が食べることのできない鹿の肉を味わっていたのであり、それを再び求めてやってきたとしか思えない。最初の訪れのとき、老婆に身をやつしたコリガンが、領主の名前も「用件も、思惑も、彼をここまで駆り立てた、ある渇望のことさえも」知っていたのは、彼女の魔法の力によるばかりではなく、人魚とその情人同様、二人が旧知の仲であったからではないだろうか。
黄金の櫛で髪を梳いていたコリガンは領主に言う。
「また巡り逢えました、待ったすえ、苦しんだすえに。
殿よ、あなたはこうして戻っていらした――
もしかしたら私に好意を抱いて下さったのでしょうか。
殿よ、こんなにはるばる逢いに来て下さって、
何を私に下さるのでしょう?」
もしも領主が、玻璃の瓶を渡されたときの老婆としてのコリガンしか知らず、真の姿をそれ以前に見ていなかったとしたら、「もしかしたら私に好意を抱いて下さったのでしょうか」と、このときコリガンが言うわけがない。
領主が先の否定で応えると、コリガンは泉の水を乱したことの償いを求め、次のように、強烈な性的快楽を約束する。
「それならば、よくも私の蒼白い水を
こんなに乱しておきながら、私に顔向けができたものです。
少なくともこの代償は請求しましょう、
もし仮に、ただ気ままにさまよっていただけだとしても。
ここで私に愛をもって償いをするのです、
なぜならここでは夜は長く甘美なのだから。
素晴しい性愛を味わうことでしょう、
人間が与り知らぬ深い恍惚を。」
ここではもう、領主に子を得させたことの代償は問題になっておらず、「コリガンの泉の水を乱したことを責められ、コリガンと結婚するか、または人間の妻を選びその結果死ぬかという選択を迫られる」というブルトンDの領主ナンと、トールキンの領主は、ほとんど見分けがつかなくなっている。しかし、これに続く、「愛など約束しなかった。私の愛は妻のもの」というトールキンの領主の返答は、魔女とは初対面の領主ナンの場合とは異なり、最初の訪問のとき、秘薬の代償として愛など約束しなかったというのと、それ以前の「交渉」においても愛の約束などしなかったという、二重の意味を響かせていよう。
果たしてコリガンの「顏から笑みが消え、ゆっくりと彼女は言った、/「おまえの妻のことは忘れるのだ。なぜならおまえは/私とあらたに結婚するのだから、さもなくば/石のように動けずに、生気を失い孤独に萎びてゆくのだ。/ブロセリアンドの泉水の傍らに立つ/忘れられた石のように。」
領主がこれを否定し、自分の家へ、「キリスト教徒の聖なる水のもとへ」帰ると宣言すると、魔女は、たとえ戻っても三日後には、領主は棺台に横たわっているであろうと予言する。館に辿りついた領主はそのまま床につき、コリガンが「意地の悪い目付きであざ笑」うのを幻視する。
「さあ願いが叶った以上は報酬を持って来てもらおう、」
と声は言った、「私の報酬を持って来てもらおう。」
今や萎びて老いたコリガンは、
冷たく流れ落ちる泉の傍らに
腰を下ろして歌っている。彼女の鈎爪のある手の中に
領主が見たのは、骨で出来た櫛の歯、
彼女はそれで灰色の長い髪を梳いていた、
しかしもう片方の手には、
苦い泉からこぼれ出た水で満たされた
玻璃の瓶が握られていた。
三度目に、そして最後にあらわれるコリガンは再び老婆に変じているが、その姿は前にもまして異様である。鈎爪のある指を持つ怪物となったコリガンは、かつて領主をさし招いた白い手に握られていた黄金の櫛の代りに、骨の櫛で灰色の髪を梳いているのだ。 「トールキンの描くコリガンは、官能的な魅力で男たちを虜にし破滅させる典型的な水の妖精とは少し様子がちがう」と指摘していた辺見は、その違いとして、彼女が金色ではなく「蒼白い」髪を持つこと以外に、「あらがい難く蠱惑的なはずのその声」が「冷え冷えとして」いること、また、「トールキンのコリガンは終始一貫して蒼白さ、ほの暗さ、冷たさ、虚ろさ、闇などと結び付けられ、死の不吉なイメージで描かれている」ことを挙げており、私たちもそれには同意するが、その声の冷たさが、「コリガンが人間には計り知れない、太古に遡る力を秘めた存在であることを伝えている」という太古の神話世界の作り手トールキンといった“神話”に依拠した、一般化された解釈、また、トールキン作品における「水の妖精が持つ、人間の運命を狂わせ没落させる危険な魅力は、コリガン自身ではなく、まがまがしい妖しさを湛え、暗いブロセリアンドの森できらめく、美しい玻璃の瓶が担っているようだ」という解釈には異議を唱えたい。
■激しい渇望の対象
私たちはすでに、トールキンのレーでコリガンが約束する「この世のものならぬ官能の悦び」は「領主をコリガンのもとへと駆り立てた「渇望」とは係わりない」という、辺見の解釈に反駁してきた。「領主が破滅するのは水の妖精の魅力の虜になってしまったからではない」とし、「水の妖精によって破滅に導かれる理由も、トールキンのレーの場合は独自のものである」と言う辺見は、では、何が「領主をコリガンのもとへと駆り立てた」としているのであろうか。典拠となるブルトンDと比較して、「トールキン独自の作品主題」、「領主の没落の本当の原因」は、次のようなものであると辺見は述べる。
「領主は世継ぎを残さずに「死」を迎えること、言い換えるなら現世で彼が所有していた富を他人に渡すことを拒んだのだ。そして「孤独な老年と死」への恐れと絶望から、運命に刃向かい、コリガンの秘薬の助けを求めることになったのである。コリガンは死からの逃避願望と、現世の富への執着心を満たす手段として求められ、その「心の渇望」を叶えたかに見えて、かえってその「心の渇望」で領主と奥方の身も心も焼きつくし破滅させるのである、既に述べたようにこの「渇望」は、コリガンの化身である白い雌鹿と、コリガンの泉の水への渇望として表現されている。そして彼らは「心の願望」であったはずの子供たちの成長を見ることもなく、空しく死んでしまう。」(強調引用者)
ここでは幾つかの要素が混同されている。確かに領主は、世継ぎがないため、「眠れぬ夜」に、その心が「暗く翳り、孤独な老年と死が/幻影となって浮かび来る」のを体験し、「墓は荒れるがままにされ、彼の代わりに/見知らぬ名前と楯を持った者たちが、広間と領土の主になっている」のを見て、「暗い幻影の果てに」、「心の冷えるような手立てを選」ぶことになる。しかし、正式な夫婦の間で嫡出の子供を持ちたいという願望が、キリスト教徒に許されないような性質のものではない以上、それは、「聖なる泉からはけっして湧き出ることのない/水晶のように澄んだ冷たい水」への、非合法の「渇望」とはなりえない。最初にコリガンを訪ねるくだりで、「彼の名前を老婆は知っていた、彼の用件も、思惑も、/彼をここまで駆り立てた、ある渇望のことさえも。」と語られるのは、子供を望んでそこへ行ったという、彼が自らを騙している口実以上の、隠された「渇望」さえ、魔女には見抜かれていたということではないか。
領主は子を得て、自らの欠如感の正体に、子供では満たされない渇望にあらためて気づいたのだろう。水の妖精を捨て、人間の女と結婚した彼は、しばらくはその虚しさを、子供のいないせいにできた。しかし、皮肉なことにコリガンの助けで子が生まれると、それまで抑圧していた真の「渇望」が浮上してくることになったのだ。コリガンは領主の〈「心の渇望」を叶えたかに見えて、かえってその「心の渇望」で領主と奥方の身も心も焼きつくし破滅させ〉ようとしたのではない。領主の表面上の願望を叶えることで、かえって、隠れていた「渇望」をあらわにさせたのだ。その「渇望」は奥方にも感染する。いや、むしろ、彼は自らの「渇望」を彼女に投射し、最大の願いが叶ったばかりの産褥の妻に、さらに望みはないかと尋ねるのである。
「さあ、これで私には希望と祈りが
共に叶えられたことになる。そなたはどうか?
とうとう心の願いが叶ったとは、
素晴しく甘美なことではないか。
しかしもし、そなたの心にまだ何か
切望しているものがあるならば、
またはどんなささいな願いでも
言わずにいることがあるのなら、
それを見つけ出して持って来よう、
たとえそのために陸や海を駆け巡ることになろうとも。」
ここではむしろ、「希望と祈りが共に叶えられ」たはずなのに、なぜか不満な(そなたはどうか?)領主が、「とうとう心の願いが叶ったとは、素晴しく甘美なことではないか」と自らに言いきかせながら、それでも「まだ何か切望しているもの」があるので、それを奥方の願望であるかのように、また、自分が、妻の「どんなささいな願いでも」叶えてやる優しい夫であるかのように、錯覚し、自らを欺きながら、実は生まれたばかりの子供たちと奥方のもとにとどまるよりも「陸や海を駆け巡る」ほうを望んでいるかのようである。
領主の問いに応えて「激しい渇望」を口にし、しかし、「私のそばから離れてあなたを駆け巡らせるようなことはいたしません」ときっぱりと言う奥方に、領主はしかしいっそうの告白を促す。
「いや、奥方よ、もし何か不思議な渇きや飢えを覚え
それがそなたを苛むのなら、」と領主は微笑んだ、
「地上を徘徊する鳥獣でも、
葡萄酒でも、あるいは人知れぬ泉や谷間に湧く水でも
かまわない、さあ、早く言いなさい。
黄金や珍しい宝石を凌ぐもの、
おそらくは緑なす森の淡茶色の鹿か
あるいは湖の浅瀬に泳ぐ水鳥か、
そなたが切に望むとあれば
それを捕って持って来よう、
たとえ陸地や草原を狩りに奔走することになろうとも。
(...)」
これは領主が、「何か不思議な渇きや飢え」を自らおぼえ、それに苛まれているために、妻子を置いて「陸地や草原」――あるいは森――を「狩りに奔走」できる口実を、妻からもぎ取ろうとして、しつこく尋ねているのだ。それにしても、「鳥獣」、「葡萄酒」(魔女の薬を入れて妻に飲ませた)、「人知れぬ泉や谷間に湧く水」、「黄金や珍しい宝石を凌ぐもの」(黄金はコリガンの受け取らなかったものだ)、「緑なす森の淡茶色の鹿」に「湖の浅瀬に泳ぐ水鳥」とは、また、ずいぶん、あやういというか、図太いというか、語るに落ちる修辞ではないか。「渇望」が、「コリガンの化身である白い雌鹿と、コリガンの泉の水への渇望として表現されている」(辺見)のではない、「コリガンの化身である白い雌鹿」や「泉の水」はそれ自体が「渇望」の対象なのだ(雌鹿がコリガン自身であるとトールキンのテクストでは明示されていないことは、かえって効果をあげていよう)。「その底は黒く、縁は薄暗い」谷間、見たことがないと言い張った「暗闇に包まれた洞穴」、領主がその蒼白い水を乱した「柔らかい草に囲まれた」泉等が、何の暗喩であるかは言うまでもあるまい。コリガンは「手段」などではない、「目的」なのだ。
■〈異世界〉としてのブロセリアンド
しかし、なぜ、トールキンのレーの特異な水の妖精は、辺見が指摘するように、「官能的な魅力で男たちを虜にし破滅させる」力において、「あらがい難く蠱惑的なはずのその声」において、「人間の運命を狂わせ没落させる危険な魅力」において、劣るとは言わぬまでも、「様子がちがう」と感じられる存在なのだろう。そうした魅力を、「コリガン自身ではなく、まがまがしい妖しさを湛え、暗いブロセリアンドの森できらめく、美しい玻璃の瓶が担っている」と言ってみたところで、気のきいた(と錯覚する)レトリックにしかならないだろう。最後に領主が見た、骨の櫛で灰色の髪を梳いていない方の手で彼女が持つ「苦い泉からこぼれ出た水で満たされた玻璃の瓶」が、辺見の言うように「危険な魅力」にきらめいていたとして、それはいったいどのような危険であろう。すでに見たように、瓶に入れられた秘薬とは、どうやらコリガンの身体の一部のようなのだが。
トールキンのコリガンの描写に、美貌や声やなまめかしい姿態で男たちを抗い難く虜にする水の妖精らしさが欠けていたとしても、さほど驚くようなことではあるまい。およそトールキンの作品に、そういう女が出てきたためしがあったろうか。ファム・ファタールめいた女が出てこないことこそ、そもそもトールキン作品の特徴ではなかったか。
『シルマリリオン』の読者にこの「レー」を読んでもらい、この魔女が『シルマリリオン』の登場人物の誰かの前身だとしたら、それは誰だと思うかと尋ねたなら、たぶんその人はメリアンと答えるだろう[☆6]。彼女こそ、セイレーン並みに――なにしろナイチンゲールの歌の師匠である――美しい歌声でシンゴルをおびき寄せ、虜にした精霊に他ならないが、しかし少しも色っぽくなく、そもそもどんな顏をしているのかも――目や髪の色さえ――わからない。美しいと書かれているので美しいのだろうと思うまでだ。
だが、コリガンは、メリアンよりも遥かに複雑な――複合的な――存在である。メリアンも本来は形を持たないのが、シンゴルへの「愛ゆえに」現し身をそなえたと言われるが、老婆1、老婆2(鈎爪と骨の櫛付き)、蒼白い髪の妖精、白い雌鹿と、自在に姿を変えるコリガンはどうなのだろう。そもそも彼女は本当に女なのだろうか。コリガンは金色のはずの髪が「蒼白い」、つまり、月の徴を持つ者だと言える。トールキンの作品世界では金色=太陽=人間=異性愛であるので、それに対する月の蒼白さとは、両性具有のエルフと同性愛を暗示する[☆7]。玻璃の瓶に入れられたのは、彼/彼女の流れる髪であり、その「苦い泉からこぼれ出た水」であったが、それを領主の奥方に飲ませたとは何を意味しているのか。もしかして生まれた双子はコリガンの胤であったのだろうか。あるいは、自分では産めない領主の子を、代りに奥方に産ませたのだろうか。「様子がちがう」のは、女ではなく、しかも女であるからではないか。
辺見論文には、双子を得ながら、元愛人でもない魔女に夫が因縁をつけられるブルトンDの夫婦について、「領主と奥方の幸福な生活はコリガンの唐突な呪いによって壊され、二人とも死んでしまうが、二人の墓からは樫の木が生えいで、その梢には二羽の白い鳥がとまって歌をさえずり、天へ向かって飛び立って行ったという結末になっている」ことが紹介され、「このように恋人または夫婦の愛を讚えた結末をもつ作品と、トールキンのレーとでは、主題の相違が明白である」とある。それはそのとおりなのだが、主題の相違とは、「レーの始まりの部分にあった「誇りは儚く、財宝も虚しかったのだ」という詩句と対応するように、領主の柩の描写のくだりが「領主の誇りはついに尽きた、財宝も虚しかった」と結ばれ、「死」からの逃避の企てが無に帰したことを印象づけている」ことなどではないだろう。すでに引用したように、「誇りは儚く、財宝も虚しかったのだ」というフレーズには、「領土と剣を受け継ぐ嫡子がいないのでは」という一句が先立てられている。つまり、「領主の誇りはついに尽きた、財宝も虚しかった」とは、領主個人の死を嘆くものでこそあれ、はじまりにおける、子供ができなかったときの苦悩とは意味が変わっているのだ。ここは、領主が熱望していた子供を二人も――「心の冷えるような手立てで」――得たものの、自らは命を落したという、運命の皮肉をこそ読むべき箇所だろう。
「恋人または夫婦の愛を讚えた結末をもつ作品と、トールキンのレー」との「主題の相違」とは、辺見の主張するようなところにあるのではなく、トールキンの「Lord and Ladyのレー」のLadyが、むしろコリガンであるところにあろう。もちろん、「領主と奥方について、これですべてが語られた。/神よ、今や亡き彼らの魂を休めさせたまえ。」とはじまる最終節が示すように、表向きはあくまで、夫婦である領主と奥方が主題である(トールキン自身が、夫婦愛の権化のように取沙汰される墓に葬られているように)。「神よ、希望と祈りのうちのわれらを/誘惑や絶望より守りたまえ。/キリスト教徒の聖なる水のもとに住まわしめたまえ、/清く汚れ亡き聖母マリアが/女王であられる天国の/喜びへとわれらがついに赴く日まで。」という結びは、むしろブルトンDの、二羽の鳥が天へ向かって飛び立って行く話の(あるいはトールキン自身の比翼塚の)仲間であろう。キリスト教(と異性愛)の紋切型が真実を覆いかくすのだ
一方的な被害者だったブルトンDの領主と違って、トールキンの領主は、コリガンとの関係において絶えざる葛藤の中にあった。だが、そのことは隠されており、彼をブルトンDの領主に近く、イノセントに見せていた――詩のはじまりにおける、領主と魔女が初対面でなかったことの隠蔽、二度目におびき寄せられたのが自ら望んだものではなかったかのごとき偽装、そして、表面上の筋書においては魔女の誘惑をしりぞけたように見えること(だが、実は、物語がはじまる以前に、彼はコリガンと関係を持っていたと考えられる)。
『領主と奥方のレー』の、領主と魔女が相知っていたとは書かない、つまり、積極的な嘘は言わないが真実も言わないという叙述の仕方は、『シルマリリオン』の語りにも特徴的なものである。しかし、『領主と奥方のレー』と『シルマリリオン』には、一つ大きな違いがある。領主を苦しめていた葛藤が後者には存在しないのだ。
『領主と奥方のレー』は、『領主とコリガンのレー』と称するわけにはいかなかった。妖精の泉からほとばしる冷たい水は、「キリスト教徒の聖なる水」とはけっして相容れぬものであったから。しかし、『シルマリリオン』において、トールキンは「聖なる水」を干上がらせ、命取りの(mortal)洞窟の女王――「不死の女」(immortal she)がいない代りに、どう転んでもキリスト教徒ではありえない、キリスト教徒から見れば人でなしの、「不死のエルフ」がいる世界を創造した。キリスト教とともに葛藤を切り捨てたとき、『シルマリリオン』の世界が可能になったのだ。
辺見は、『領主と奥方のレー』で描かれているのが、『シルマリリオン』の遥かな後代としてトールキンが設定した中世だと主張する。確かにトールキンはブロセリアンドというブルターニュの実際の地名を、『シルマリリオン』の先駆けとなる作品で使っているが(最終的にはべレリアンドと呼ばれることになる)、辺見はそこから、「トールキンの神々の時代における妖精の王国の面影が、遥に遠く時代を経て人間の世となった中世のブロセリアンドにも映されていることが見て取れる」、「トールキンにとって『領主と奥方のレー』のブロセリアンドの森、及びそこに出没する妖精は、たわいもなく儚い空想の産物としての現代のフェアリーのイメージとはほど遠く、自らの神話世界の妖精の王国の面影が残る森であったことがわかる」という解釈を引き出す。そして、「『領主と奥方のレー』は中世に時代設定されているが、ここでは、人間はコリガンの住み処であるブロセリアンドの森に象徴される、太古からの妖精の力の前にあっては、無力にも滅ぼされていく様子が描かれている」というのだが、もうこれはトールキンとは何の関係もない話である。トールキンの著作のどこにそんな“妖精”が書かれているというのだろう。
コリガンはエルフの裔ではない。むしろエルフがコリガンの裔なのだ。トールキンは過去から未来へ展開する、そのような予定調和的な歴史のうちに彼の物語を置きはしなかった。むしろトールキンは、『領主と奥方のレー』の束縛から逃れ、天国も地獄もないそれ以前――と言っても、キリスト教以前の異教世界というわけではない――へ向かったのだ。「自らの神話世界の妖精の王国」などという、囲い込まれた甘やかな〈内部〉は彼にはなかった。閉じこもって模型造りに熱中できるような場所はどこにもなかった。彼が二つとない〈異世界〉を発明したのは友ひとりなく風吹きすさぶ過酷な〈外部〉においてであり、残りの人生の続くあいだ、彼はそこで誰にも真似のできないやり方で、「愛の再発明」(ランボー)の孤独で困難な企てに従事したのである[☆8]。
エピローグ――無垢な女
トールキンが『シルマリリオン』に登場するエルフの王女「ルーシエン」の名を、妻の墓碑に本名と並べて彫らせ、その死後、彼自身の名前にはルーシエンの伴侶「ベレン」の名が添えられたというのは、しばしば写真を添えて紹介される有名な話である。しかし、メルコールに奪われたシルマリルの一つを取り戻した英雄であると不正確に紹介されるのがつねであるベレンの実際の行動を、『シルマリリオン』で読んでなお、トールキンが専ら彼に自らを投影しているなど本気で信じうる者がいるとはとても考えられない[☆9]。「二人の墓からは樫の木が生えいで、その梢には二羽の白い鳥がとまって歌をさえずり、天へ向かって飛び立って行ったという結末」は、確かに、トールキンが、表向きそのように見なされるのを望んだものかもしれない。しかし、真実を曲げる必要のない唯一の場所である作品の中では、次に示すとおり別な結末が語られている。
『シルマリリオン』には、それだけが切り離しても読まれうる(と信じられているが、むろん、それらもまた、いまだ全体との繋りとの中で読まれていないにすぎない)物語が含まれ、その一つが、人間であるフーリンの子ら、すなわち兄妹と知らずに結婚するトゥーリンとニエノールの悲劇である。近親姦の話は、しかし、一番外側の(トールキン夫妻の墓のように)安んじて見せびらかすことのできる層でしかない。はじまりにおいて直接語りえなかったシルマリルをめぐるコアの話が、ここでは(構造変換された上で)最初の物語のいわば註釈として展開されている。ニエノールに出会う以前、トゥーリンの話の前半部では、彼の愛(相愛)の対象は男のエルフ、ベレグであった。ベレグは誤ってトゥーリンの手にかかって死ぬが、その際凶器となったベレグ自身の〈黒の剣〉は最後までトゥーリンとともにあって、〈黒の剣〉とはトゥーリン自身の通り名ともなり、妻が妹であると知ったとき、この剣でトゥーリンは自害して、砕けた剣はともに埋葬されることになる。
〈黒の剣〉は、それを携えているだけで素性を知られてしまう、断ち切ろうとしても断ち切れない、影のようにつきまとう運命の象徴であったが、また、最愛の同性を手にかけてしまった武器であり、相手の形見でもあるという男同士の絆の象徴でもあった。断崖から川に身を投げたニエノールの名と自分の名が並べて刻まれた墓碑の下に、トゥーリンはその破片とともに眠る。この剣が隕鉄を鍛えたものである、つまり、もともとは〈星〉であったという事実は、〈黒の剣〉を星で(も)あるシルマリルに結びつけるものだ(シルマリルの一つは、最後には星になって天にのぼるが、そのようにして誰の目にも明らかに見えるところに、本来の素性を隠したとも言えよう)――名指されうる罪であるニエノールとの近親姦以前の、(実はその遠因でもある)名指されない罪の象徴たるシルマリルに。
トゥーリンと出会ったとき、ニエノールは龍グラウルングによって記憶を封じられ、自らの名も思い出せない状態にあった。運命から逃れるためフーリンの子であることを隠し、複数の偽名を使った、すなわち自らへの名づけをやめなかったトゥーリンと違い、ニエノールは仮の名さえ、自分からは名乗ることがない。トゥーリンが与えた「ニーニエル」の名を従順に受け入れて妻になるのは、自らの意思で過去と本名を隠そうとし、自らの意思で新たな名を名乗ったトゥーリンとは対照的な無垢性をあらわすもので、つまり「女に本当の罪は無い」ということだが、これは当然「愛も無い」ことを意味している。
瀕死のグラウルングの口から自らの素性を教えられ、記憶を取り戻したニエノールは妊娠していた。身籠ったまま死を選ぶ他ない、紛れもない「愛の結晶」でありながら日の目を見させてはならない――太陽が消滅し、月が落ちるその日まで――許されざる「罪の証」は、芸術によらず、悪をなす意識を経ずして、無垢な(愛を知らない)女のうちに宿った、シルマリルに封じられた〈秘密〉の異性愛的等価物でもあろう。同性愛が名指されることがないのに対し、彼らの〈罪〉は、墓石に刻まれたニエノールの二重の名前――「ニエノール‐ニーニエル」――のように(あるいはトールキン夫妻の墓碑銘のように)、何ぴとの目にも明らかに読み取られうる。だが、彼らの運命を語る章は、急流が運び去ったニエノールが「そこにはいない 」ことを強調して終る[☆10]――あたかも名指されたものは真の罪ではなく、人が認識していると信じるとき、すでにそこに見ているものは幻にすぎないかのように。
註
☆1 「快楽の装置」および後出の「同時代の批評」については、「コーラ」4号掲載の拙稿「私たちは「表象の横奪論をほってはおかない」4章の、ボッティチェルリの贋作についての話(http://sakura.canvas.ne.jp/spr/lunakb/eiga-4.html)を参照されたい。
☆2 田中明子訳。以下、テクストの引用は田中訳によるが、一部改変したところがある。
☆3 「楽園」に「二本の木」が生えており、その花の発する光を内臓する三つの宝石が作られ、宝石が奪われて二本の木が破壊されたのち、エルフたちが「楽園」を出る――表の筋書が“キリスト教神話を下敷きにしているのは歴然としているが、アダムとイヴによるのではないこの時の〈事件〉は――本当は何があったのかは――目の前で起こっていながら研究者たち(既成の神話のなかに起源探しを好んでする)の眼には映らないようだ。
☆4 二代にわたって妻にあっさり先立たれ 息子と水入らずになる御都合主義(最初のボヴァリー夫人を殺したフロベールも顔負け、ナボコフだってシャーロット・ヘイズを片づけるのにもうちょっと手間をかけたのに)の話を自分で訳しておきながら、どうして訳者は『シルマリリオン』におけるミーリエルの〈死〉と残された者たちの場合に言及しないですませられるのか不思議である。
☆5 むろん、無害なのは男にとってであり、少なからぬ同性に対しては害をなす結果となっている。
☆6 ちなみに、正答は別にある。
☆7 これについての論証は省略する。
☆8 ここで詳述する余裕はないが、「○○の子、△△」という名乗りが一般的な『シルマリリオン』(および『指輪物語』)の世界は、一見そうと思われがちな通常の父権制社会とは全く異なっている。
☆9 ルーシエンについては、「シンゴルとメリアンの愛から、イルーヴァタールの子らの中でもかつて存在したこともないほど、またこれからも存在しないだろうほど美しいものが、この世に生まれ出たのである」と語られている。彼女は人間の男ベレンを愛し、自分との結婚の代償として父シンゴルがベレンに要求したシルマリル一顆を、彼を助けて(実際は「従えて」とでも言いたくなる展開であるが)モルゴスの王冠から奪い取る。さらに、死んだベレンを甦らせるため、自らが死すべきものとなる運命を選択する。「その結果、エルダリエ[エルフの意。「エルダール」も同様]の中でただかの女のみが、本当に死に、遠い昔にこの世を去ったのである。しかしながら、かの女の選択によって二つの種族は結ばれ、かの女を祖とする多くの者の中に、全世界が変わってしまった今もなお、エルダールは、かれらが失った愛するルーシエンに生き写しの者たちを見るのである」――この美しい一節は、フェアノールについての「かれと似た者は二度と再びアルダには現われなかった」という文句と、対にして読まれるべきだろう。異性愛の結果が、再生産される(美しくはあっても)似たような子供たちであるのに対し、フェアノールの場合は「芸術家」の唯一性が強調されている。そして、言うまでもなく「芸術」とは反生殖的な領域に属するものであり、これは、「楽園」の「二本の木」の「果実」たる三つのシルマリルが、直接木に“
☆10 「しかし、かの女はそこにはいなかった。テイグリンの冷たい水がかの女をどこに運び去ったか、それさえも分からなかったのである。」
★プロフィール★
鈴木薫(すずき・かおる)本稿を書き上げたあとで、内容だけは入門書か何かで知っていたのだが、レヴィ=ストロースがある講演の中でロートレアモンの例の「ミシンと洋傘」(“une table de dissection”の上の)を、《互いに相手の逆転的メタフォアへ変形》させてみせているのを読んだ(「構造主義再考」『構造・神話・労働』(みすず書房)所収)。彼の言う「対立と対比」を二つだけあげれば、ミシンは縫うため(pour)の、傘は雨に対抗する(contre)もので、傘は弾力を持ったドームの上で尖った先が上を向き、ミシンは尖った針先が《丸いドームならぬ角ばった腕木の下端(上端でなく)に下向きに位置している。》[ちなみにこの対立は私にとって、今のコンパクトなものと違って下半身があった母のミシンと、羽ぼうきや薄く削いだ消しゴムと一緒に、切り出しナイフで細くけずった先を上向けた鉛筆が何本も垂直に立てられた紺のピース罐が置かれていた父の製図板を思い起こさせるものだ。父と母それぞれの固有の領域であることが幼い私に鋭く意識されていたこれらの道具には“テーブル”という共通項があり、外光の入るガラス戸に面したミシンの折りたたみ式のなめらかな板の上ををしなやかな布地がすばやくすべる一方、電気スタンドが光を投げる製図板には、四隅を画鋲で留められ、折り目もしわも知らない磨りガラス色のブーブーがみ(切れ端を唇にあて音を出して遊ぶのでトレシング・ペーパーをそう呼んでいた)がぴんと張られていた。]むろんこれは〈こじつけ〉だ(レヴィ=ストロース自身、「楽しみ」「息抜き」と呼んでいる)。だが、そう思った瞬間、文化とはすべて〈こじつけ〉であると知るだろう(たぶん、良い――よくできた――こじつけと箸にも棒にもかからないこじつけがあるのだ)。《そもそも、次のような問い方をすることもできたはずです。「ミシンとは一体何であるか」、「洋傘とは一体何であるか」、「解剖台とは一体何を言うのか」、そして、このような問いを個別に発しているかぎり、そこからは何もでてこないでしょう。》この教えをトールキンの〈企て〉にどう応用すべきかは言うまでもない。
ブログ「ロワジール館別館」
Web評論誌「コーラ」09号(2009.12.15)
「新・映画館の日々」第9回:人でなしの恋――『シルマリリオン』論序説(鈴木 薫)
Copyright(c) SOUGETUSYOBOU 2009 All Rights Reserved. |
| 表紙(目次)へ |