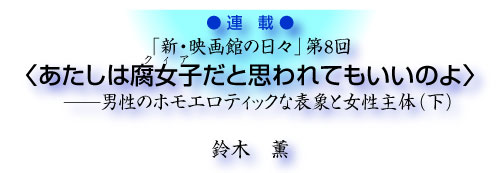|
|
|
Web評論誌「コーラ」 |
|
■創刊の辞 ■本誌の表紙(目次)へ ■本誌のバックナンバー ■読者の頁/ご意見・感想 ■投稿規定 ■関係者のWebサイト ■プライバシーポリシー |
|
<本誌の関連ページ> |
|
■「カルチャー・レヴュー」のバックナンバー ■評論紙「La Vue」の総目次 |
Copyright (c)SOUGETUSYOBOU |
|
|
|
2 やおいとその外部(承前)
流用について
『ユリイカ』の2007年12月臨時増刊号「総特集BLスタディーズ」に載った石田仁の二つ目の論文、「『ほっといてください』という表明をめぐって やおい/BLの自律性と表象の横奪」[石田2と表記し、最初の論文は、以下、石田1とする]で、石田は〈表象の横奪〉(appropriation of representation)という概念を導入する。そして、腐女子は、ゲイ男性という〈他者〉を表象し、これはファンタジーだから現実のゲイには関係ない、だからほっといてくださいと言うが、やおい/BLが「ホモ/ゲイ」という言葉を使っている以上、それは現実のゲイを「すでに・つねに参照している」、ゆえに「『やおい/BLはファンタジー、フィクションだから』無関係とする主張は誤りであろう」と主張する(石田2; 116)。
まず、appropriationの訳語を、収奪、搾取を連想させる〈横奪〉とし、ことさら簒奪者として、のみならず、「宗主国」という語まで使って腐女子を表象することの暴力性を指摘しておかねばなるまい――権力関係を隠蔽するという暴力。女のセクシュアリティがいかに社会的に認められていないかについてはすでに述べた。「リアルゲイ」の側はつねに自分を真正と、やおいのゲイ表象(と腐女子の欲望)を偽物と――極端な場合には作品を見さえせずに――断じられる立場にあるのに対し、女は、自らの欲望が、“参照の淵源”として尊重されることの絶望的なありえなさを知っている。
次に、ここで言う〈表象の横奪〉とは、明らかに、男性による「女性性の流用(横奪)」(appropriation of femininity)概念をそのまま逆転させたものであるが、何度も言うように女は男の女版ではない。「女性性の流用」なら、エロスを論じるにあたって女性キャラをわざわざ作り、妊娠・出産の比喩をもって語らせた(しかも最初から最後まで男同士のエロスの話である)プラトンにまで遡れる(デイヴィッド・M・ハルプリン「ディオティマは存在したか」参照)。「『他者』として切り分けた存在を、「私」との関係で非対称に配当し、お決まりのパタンでくり返しイメージした後に葬送する」(石田2; 118)という説明は、こちらにこそふさわしかろう。
前回触れた最初の論文「ゲイに共感する女性たち」冒頭で、「リアルゲイ」という言葉を聞いて、現実のゲイの方が「有徴」にされてしまったことに衝撃を受けたという話をしたとき、石田は有徴の例として次の語を挙げていた――女相撲、女棋士、女性議員、女性天皇。すべて女の有徴化である。周知のとおり、大相撲では女は土俵に上れない。優勝力士の幼い息子は土俵上に抱き上げられても、娘であれば土俵下で見上げるだけだ。それがわかっているときに、「『相撲』は、男同士の取り組みがスタンダードである(らしい)。「女」相撲という有徴化がそれを物語る」(石田1、強調は引用者)とは随分なおとぼけである。
「リアル厨房」を引き合いに出して、「ゲイたちが、「リアルゲイ」という有徴化の語句をまとって「スタンダードならざるゲイ」として指し示されるようになった」と石田は主張していた。だが、「リアルゲイ」と呼ぶのはそちらさまが本物ですという意味、ウェブ掲示板の住人と中学生は、腐女子とゲイ男性のような関係には置かれていないのだから、「リアル厨房」と「リアルゲイ」の類似は形式上のものにすぎない。腐女子から「リアルゲイ」と呼ばれたとは、女より優位の〈男〉、ファンタジーごときの及ばぬ正真正銘の男と認められたということでもある(ジェンダー間の権力関係とはそういうものだ)。リタ・フェルスキは、(現代の男性哲学者の唱える)“becoming woman”は「リアル・ウーマン」には不可能らしいと辛辣に言うが(“The Gender of Modernity”)、「リアルゲイ」にそういったことは起こりえないから心配には及ばない。
石田の言う「リアルゲイ」とは何か。テクストに即して答えを探すなら、「現実に生きる「ホモ」およびその社会的イメージ」(石田2; p116)ということになろう。「現実に生きる『ホモ』」とは「ホモ」の
筆者は、「やおい/BL」のゲイ表象が、現実のゲイ男性と「無関係」に存在するとはむろん思わない。社会的なものである言語に意味を気ままに付与するのは不可能という当然の理由のみならず、前章で概観したように、男性のホモエロティックな表象の歴史的蓄積の上にやおいは成立し、「完全に内的で唯官能的な欲動の『経験』」としての「萌え」などというものは幻想にすぎないからだ。しかし、だからこそ、ここで石田の言う「リアルゲイ」が、腐女子が「すでに・つねに参照」している起源であると、優先的に見なされねばならない理由はないのである。
文化の中には無数の参照先があり、「物語の理解可能性」はそれらによって「担保」される(ロラン・バルトが『S/Z』で実演してみせたように)。「あなたのホモは私のホモと違う」と言えるような、複数の同性愛がそこではありうる。石田の言う「ホモの社会的イメージ」を特権的「起源」としたのでは、「青年の家裁判」で、事件当時、同性愛に関しては現代用語辞典の酷い定義しかなく、「アカー」会員を差別したのはやむをえなかったと主張した、東京都側の証人を笑えまい(「女性向け」の男性同性愛表象がすでに広く知られていたはず、と原告側が反論しなかったのが惜しまれる)。
腐女子が使った「ホモ」という語が、(たとえば)上記東京都側証人のようなメンタリティの持主に、「悪しきイメージ」(バルトに言わせれば冗語であろう)を喚起しても、「それは私のホモとは違う」と彼女は言いうる(「ホモ」という語の使用の是非とは別の話である、念のため)。
あるいは石田は、「ホモ/ゲイ」という言葉を使う以上、現実に生きる「ホモ」のイメージに影響があると腐女子を啓蒙したいのだろうか。しかし、男の描く女性像が本質化され、たやすく人々に信じられるのに対し、あえてその名を言ってさえ、(たかが)BLに登場する「ホモ/ゲイ」が真正と見なされようか。「BLに登場するゲイは本当のゲイではなく、ゲイに対する差別になる」とか「男性同士の行為を見世物にすることによって、男性を性の商品化し、憂さを晴らそうというフェミニスト的ルサンチマンも意図されています」(☆1)くらいのことは、今時、バックラッシャーでも(流用的に)言う。フェミニズムの本なのかもしれない『身体とアイデンティティ・トラブル』(明石書店)にも、「漫画の主人公の少年がそこでは存分に性的にいたぶられる。常に心のどこかに“強姦される恐怖”を抱えている少女たちは、ギャ――ッと叫んで犯される少年たちに胸のすく思いをする」(三橋修)とあるのだから、もうどっちがどっちかわからない。
ファンタジーやフィクションだから現実と関係ないという主張が誤りなのは、ファンタジーが現実に影響を及ぼすからではない。(石田が腐女子に突きつけようとする)現実もまた、ファンタジーであるからだ。実際、男性同性愛に関してこの社会で猛威をふるう、もっとも広範に共有されているファンタジーは、「ホモ」を周知の差別的「
「やおい/BL」は「一角獣のような幻の存在として」ゲイを描くという批判があったが(石田2; 116)、あるものを「何ものかとして」表象することそれ自体はありふれている。問題は、ゲイ表象がいかなる意味を生産できるかということであり、それが関連づけられている特定の「意味内容」を確認しつづけることではないだろう。ちなみに、ブラム・ダイクストラの『倒錯の偶像』(パピルス)を開けば、女を蛇や猫や吸血鬼として描いた図版が満載だ。いや、筆者はなにも、一角獣と蛇ではどっちが差別的(あるいは魅力的)かとか、(石田が女性の側からの反論として想定する)「異性愛男性こそが女性イメージを圧倒的に性的な存在としてパタン化し領有してきたことは論を待たない」(石田2; 118)とか言いたいのではない。そうではなく、同性愛男性もまた、女性イメージを、圧倒的に性的な存在としてパタン化し領有(appropriate)してきたと言いたいのだ。文学においては、ゲイ男性を〈女〉として表象することで、非異性愛者の男性作家は、伝統的に高い芸術的効果を挙げてきた。女性性の流用と男性同性愛には、本来、(それに対するミソジニックな否定も含め)深い結びつきがある。女によるゲイ表象横奪説とは、その何食わぬ顔をした転倒にほかならない。
仮託について
女による性的な表現は、いや、性的表現をする女は、しばしば彼女自身が性的に有徴な存在として異性愛男性の関心を惹く。むろん、彼らに理解可能な範囲で--彼らの目には彼らの理解できる範囲しか映らず、真に他者である女ではなく、自己の欲望の投影しか見ないのだが。だから、石田が正しく指摘するように、腐女子の性的植民地化はすでにはじまっている。彼が例として挙げる『僕たちの気になる腐女子』(オークラ出版)は、同じ『ユリイカ』12月臨時増刊号に書いている吉本たいまつの表現を借りるなら、「『腐女子』を見つけ出し、カミングアウトさせ、男性が主導権を握る形でセックスし、そして「腐女子」を「卒業」させる方法を具体的にレクチャーしていく」本で、「もともとエロいから妄想するわけで」(石田による本文の引用)、「楽にヤレそう」、「いろんなセックスを試すことができそう」(吉本による引用)といった調子で腐女子が表象されているそうだ。以前、コミケの参加者から聞いたところでは、男女ものを描/書く女性は、性的なことを(話)しかけてもいい女と思った勘違い男にハラスメントされる恐れがあるが、男同士の話だと安全ということだったけれど、もはやその限りではないらしい。
石田が主題化している「『ほっといてください』という表明」にしても、こうした事情と無関係ではありえまい。石田は、腐女子による「『ほっといてください』という表明に」「関連づけられた」、「やおい論は迷惑だ」という主張を、「やおい/BLを批判的・分析的に言及するすべての論は、大好きな対象を汚辱にまみれさせる我慢ならない営みであり「やおい論は迷惑だ」ということになる」(石田2; 118)と解釈しているが、問題はそんなことでは全くあるまい。何よりも、男性(ゲイ、ストレートを問わない)に理解しやすく、かつ、都合のいい話(やおいはゲイ差別というのもその一つ)に還元されてしまうのが迷惑――そして、そうなるのがわかりきっているからこその、「ほっといてください」――なのだ。女がそれに反論するのは難しい。石田論文に限らず、どう見ても間違っている言説に対してさえ沈黙するのは、女の性的な自己はそれ自体が「汚辱にまみれ」ており、まして、やおい/BLに対する嗜好は言い訳できないと、少なからぬ女が思っているからだ。迷惑などという生やさしいものではない。マジョリティに対して自分を正当/正統化する可能性すら考えられない。だから閉じる。かつてのレズビアン/ゲイと同じである。
石田の第二のテクストは、終りに近づくにつれ批判が難しくなる。突飛な思いつきや恣意的な観念連合が多過ぎるからだ。石田は次のように主張するが、あなたにはこの意味がわかるだろうか。「私が考えるに、「やおい/BL」における女性の、「ゲイ/男性」に向けるまなざしは、日本がスペインなどに向けるまなざしに近い」(石田2; 121)。たとえこれに先立って、「現地のイメージを一方的に創出‐蕩尽する」植民地的開発が、腐女子の所業に重ね合わされ、スペインがかかる「現地」の一つとして名指されていても、である。ともあれ、やおいのゲイとかけてスペインと解く、その心は「引き裂かれたイメージ」である(のだそうだ)。「スペイン」は「知性と荒々しさを兼ねそなえた引き裂かれたイメージ」へ還元され、次いで異性愛ポルノにおける女性の「引き裂かれたイメージ」(聖母と娼婦)へ変換される。そして「引き裂かれた」女二人は、なぜか、「やおい/BL」において「つねに同時に二人立て」られる「引き裂かれた男性」カップル(対照的な)に重ね合わされ、そして「お人形」にされたこの「ゲイ/男性」を使って「両者の
「周知のように、異性愛男性向けポルノにおいて、女性は引き裂かれたイメージ(典型的には聖母と娼婦だ)でとらえられてきた。だがやおい/BLにおけるゲイ/男性は、単なるそれの反転図式ではない」と石田は断言するのだが、どうしてここで「聖母と娼婦」が出てくるのか。「異性愛男性向けポルノ」の「単なる反転」がやおい/BLであるという定説でもあるのだろうか。もともと無関係なのだから「反転図式ではない」のはあたりまえだ。
石田の連想ゲームはまだ続く。ゲイ・ブーム期のゲイ像、すなわち、女性にとって「新しい男性としてのゲイ」と、やはり女性にとって「身を委ねられる女性としてのゲイ」の対がまたぞろ引っ張り出され、「ありうべき自己」と「現実の自己」にそれぞれ重ね合わされる(雑誌記事のゲイ像が、直接、BLの〈物語の範型〉に反映しているというわけだ)。「少女文化から派生したやおい/BLで求められた物語の
だが、そもそも分身とはロマン派お気に入りのテーマであり、愛と憎しみに引き裂かれ/結ばれたアルター・エゴなら、伝統的に同性愛の表象とも近いところにある。古典的な例を一つ。『ジキル博士とハイド氏の奇妙な事件』の場合、形式的には「多(二)重人格」であるが、「理想の、他人の期待を投影された自分=『ありうべき自己』と「あるがままの自分=『現実の自己』」の「分裂と葛藤というテーマ」という記述を、ほぼそのまま適用できる。「ジキルは自分を分裂させ、分身のエドワード・ハイドを唯一の友とする」とE・ショウォールターは書いている。「ジキルはひとりでいながら相棒がいるのであり、独身でいながら二人で暮らしているのだ」。ジキルの挙動不審は、最初、友人たちから、若い男(ハイド)を囲っているのではないかと疑われる。
このようなホモフォビアからもっとも遠いところにいるのが日本の〈腐女子〉であるのは言うまでもなかろう(☆3)。
男性のホモエロティックな表象についての豊かな文化的蓄積も知らぬげに、ゲイ・ブーム期の雑誌記事から取ったという図式を、石田が後生大事にリファレンスにするのは理解しかねるが、それだけならまだ、勝手におやんなさいと言えば済む。だが、安易な図式化を「やおい/BL」全体へパラノイアックに拡大されるのは、現実に生きている女にとってはっきり迷惑だ。やおいと腐女子を、研究者の自律したファンタズム展開に恰好な材料と思っているのでなければ、澁澤的「自由な結合」(アンドレ・ブルトン)ならぬ「恣意的和合」によるペダンティックな植民地化は止めるべきだ。
「植民的介入」(石田2; 118)とは、「やおい/BLを批判的に検討する」、あるいは「彼女たちを分析的な知の俎上に載せる」ことそのものではない。そうではなく、対象を忘れて自らの夢を語り、自らの権力性を忘れて対象を領有(appropriate)しながら、研究者としての科学性、普遍性を言いつのるさまが、「植民的介入」ないし〈善導〉の可否について頭を悩ますメタ位置に立ちうるかに装うところまで含め、自己正当化を図る植民地主義者の醜悪な身ぶりそのものなのだ。
「「横奪」を「仮託」と呼んだらどうか」(121)と石田は言うが、ひょっとしたら「横奪」よりこれは悪いのではないか。というのは、仮託には、「仮」ならざる、本物のセクシュアリティがあることが、必然的に前提となるからだ。“本物”“現実”“自然”とは、女のセクシュアリティが語られるとき、もっとも警戒せねばならぬ反動的なレヴェルである。しかも、〈横奪〉であるとの主張も手放さないというのだから、参照先としての「起源」はあくまで〈ゲイ/男性〉の側にあることになる。
ゲイ・セクシュアリティと真正性がここまで親和的になったのは、いうまでもなく最近のことである。『薔薇の木 にせの恋人たち』とは一九六四年に出た高橋睦郎の詩集だが、恋人たちが「にせ」なのは男同士であるからだ。これは同性愛を貶めてのことではない。「にせ」の方が価値があり、誇るべきことなのだ。〈自然〉である女は、腹が減れば食べたが、さかりがつけばされたがる(ボードレール『火箭』)、自己保存と生殖がすべての忌わしい存在であり、オスであることの余剰が文化を作る。
先に引用した、「少なくとも一九八〇年代初めまで、同性愛を理想化して描くことは反俗的な美意識の表明で」あり、中井、塚本、足穂といった人々の伝える「男性同性愛はそのまま美的な別世界への扉と受け取られて」いたという高原英理の言葉は、アクティヴィズム以前のホモエロティックな表象と、それに正式に参入する資格を持たないまま魅惑されていた女性主体との関係の記述でもありうる(高原自身は女性ではないが)。女性たちにとっても、「美的な別世界」はそのままで異性愛のオルタナティヴでありえたのだ。燦然と(月下に)輝くこの世界に近づくとき、しかし女は、自分があらかじめ排除されていることを知るばかりではない。自分に無縁とされた領域での、男性芸術家(有徴化ではなく冗語)による女性性の占有[appropriation]を目のあたりにするのである。
「反俗的な美意識」は忘れられてすでに久しいとはいえ、この構造がたやすく変わるはずもない。リタ・フェルスキの次の文章は十九世紀後半についてのものだが、“必要な訂正を加えて”読めば、まるでゲイと女の共感可能性を謳った〈ゲイ・ブーム〉への警鐘のようではないか。
十九世紀後半という進歩主義と実利主義の時代のオルタナティヴ(これは高度経済成長期における澁澤龍彦の位置にも似ている)としての、教養ある男性による女性性の流用は、彼女によれば、実のところ〈本物〉の女を置き去りにするものであった。男性が流用した場合には賞賛(時には非難)の対象となる特性は、女性に所属する場合、「たんに、彼女が自らの自然的条件から逃れられないことの確証であるだけ」なのだ。
現代の「逸脱した男性性に対するフェミニズムの肯定」にも、フェルスキは疑いの目を向ける。「女性的なものへの男性の同一化が、必然的に父権制の特権の転覆であると仮定するのは、たぶん仮定し過ぎであろう。」[強調は原著者]次に引く一節で彼女が言及しているのは、ドゥルーズによるマゾヒズム論の「フェミニズム研究者、とりわけ映画理論家による流用[appropriation]において注目される、逸脱的な男性主体性」のことである。
実は私自身、こうした男性主体性には、やおいの女性読者がそこに同一化することで「流用された」女性性を楽しめる「ウケ」の男性主体との類似という点で、ずっと関心を持ってきた。“Becoming woman”についてのフェルスキの醒めた視線はすでに紹介した。だが、女は、女になった男になって楽しむことができる。女性性は男が流用すると、女が体現している場合とは別の意味を生む。それを再流用することができるのだ。
ゲイ表象への「仮託」説について、筆者は先に否定的な意見を述べた。だが、仮託を、帰るところなき仮託、何から何まで偽物である私たちのセクシュアリティの、表象への仮の宿りと考えるなら話は別だ。「セクシュアリティはマゾヒズムとして生まれる」としたレオ・ベルサーニによれば、「私たちは何よりも先に、自我によって作り出された心的統一性なしにオートエロティシズムを持つ」(“The Culture of Redemption”)。その後に自我が生じるのだが、それは、「自らの解体という待ち望まれる快楽によって必要とされた」ものである。「最初の心的統一性は、統一性を打ち砕きたいという欲望によって構成されたのであろう」。「快く打ち砕かれる」(ベルサーニ)ためには何かに仮託しなければならないが、その同一化の対象が男性主体性[male subjectivity]なのだ。
これ以上詳述する余裕はないが、いずれにせよ筆者のこうした議論は、思春期以後の男女関係をもとにやおいを論じる人々とは根本的に異なる立場から、やおいについて考えようとするものである。
おわりに
「『女ではない他者』のイメージをパタン化し領有するやおい/BL」(石田2; 118、強調は引用者)とは不思議な表現だ。男が女を他者化してこの世界は成り立っている。そのどんな「反転図式」がありえよう。ストレートの男がゲイの男の優位に立とうとも、その力を、女――異性愛の男を補完する異性愛の女であると信じられている女――がわかち持つことはありえない。
女とは、男にとって〈他〉とされたものの集積場である。だからこそ、ストレートだろうとゲイだろうと、男はそこに好きなものを投影できる。欲しいものは何でもある宝箱。何でも出てくる魔法の箱。男が(男であるために)自らに禁じた/認めたくないものすべてを放り込んだ実はゴミ箱。女にとって禁じられているものは何もない。禁止されること自体から疎外されているからだ。女が入れない領域はある。理由は女だから、ただそれだけ。この理不尽な理由を、女が内面化し、自己規制することはあろう。多くの女がそうしている。だが、男のように、それを本気で信じることはけっしてない。
禁止を受けていないことで女は羨望される。権利のない場所を横奪=領有して好き勝手をやっていると見なされる。何も禁じられていないというのはすごいことだ。多くの男がその前で思考停止する、「友情」という言葉も女には効き目がない。何の抵抗もなく、そこにセクシュアルなものを読み込んでゆく。
だがそれは女の深い疎外のしるしなのだ。
腐女子の弱い立場についてはすでに述べた。だが、弱者とはまた、いくらでも卑屈になりうるものでもある。科学的中立性と学問的晦渋さの外見を備えた石田の書くものを、規範意識の高い良い現地人=腐女子の、心得として読む者もいる(だが、どうしてゲイ表象とは、このような特別な顧慮の対象にならなくてはならないのか。それも女が近づく場合に限って)。
さすがに石田は、腐女子を教化する神父にはならない。ゲイを正しく表象せよとは言わない。だが、女たちは、容易に修道女になる。腐女子という自意識を持つ者の中には、実に女らしいことに自らの分をわきまえた者たちがいて、彼自身に自覚がなくとも、そうした女たちにとって石田は絶対的に参照すべき位置にいる。
「こういったものでも、権威ある学者のいうこととしてひとり歩きしてゆくわけです」(☆4)。そのような「権威」では自分たちはない、ただ、黙々と自らの研究に打ち込んでいるだけだと、『ユリイカ』の特集の若い寄稿者たちは言うかもしれない。だが、周知のとおり、権威と権力はどんな場にもそれなりに生じ、時にはパロディ的に作用する。他の女を裁かなければ自分が罪ある者に落されるという恐怖にとらえられたとき、女が女に何をするか。あたかも昔ながらの「貞淑さ」が、たんに「政治的な正しさ」に置き替わったにすぎないかのように。どこから思いついたのか、立論のためのアイテムとして「聖母と娼婦への分割」をこともなげに持ち出す石田は、その意味するものを少しでも考えたことがあるのだろうか。それは女にとっては連想をつなぐ便利なチェーンなどではない、アクチュアルきわまりないものだ。
『ユリイカ』の特集に書いている若い女性研究者たちは、上に述べた一部腐女子と違い、欲望を肯定し、反動的言説に対抗する、プライドある立場にいるのではないかと愚考する。しかし、「石田仁の論文が提起する、やおいの表象暴力という問題は、現在、やおいをめぐる言説空間の最新にして最大の論点となりつつある[…]ぜひ石田論文を参照してもらいたい」(金田淳子「やおい論、明日のためにその2。」)[『ユリイカ』2007年12月臨時増刊号]などと持ち上げていたのでは、自己植民地化(と他の女に対する抑圧)への道があるばかりだろう(思えばこの一点において、上野千鶴子は偉かった。男に媚び、同性を売り、抑圧に加担することだけはしていないからだ。少女マンガややおいについて見当外れを書くことなど、この際、問題ではない)(☆5)。石田を批判する勇気がないとすれば、他の女性研究者も同様だ。
それにしても、女の話でなければ、石田もここまで根拠の薄い立論は避けたろう。女は(女研究者も)批判しない(特に男を)。そして相も変わらず性的搾取(間接的、学問的な)の対象にされ、男を都合よく補完する者へ、女研究者は女研究者なりにまた一歩近づくのだ。
最後に──「やおいの表象暴力」(☆6)という
註
☆1「フェミナチ監視掲示板」過去ログ。
☆2 むろん個々の作家は差別的な表現をする可能性に対しても開かれているが、これはBLに限った話ではない。なぜ「やおい」について、それが取り立てて問題にされるのかが問題にされねばならないだろう。
☆3 これは皮肉でも誇張でもない。かつて小説や映画に「男同士の関係についての物語」を読み取ることは、ゲイの作家、芸術家の特権であった。そうした美意識と教養を持つゲイ男性が地を払った今、〈腐女子〉がそれをやっているのだ。
☆4 小熊英二「神話をこわす知」(『知のモラル』東京大学出版会)より。
☆5 上野はかつて、ゲイ・アクティヴィスト/研究者たちとのシンポジウムで、ミソジニーを持たないゲイとなら共闘できると述べた。この発言には批判があるようだが、これは別に、他の者には要求しないことをゲイ男性にだけ要求したのではない。要するに、(お前ら〈男〉なんだぞ、それを忘れるな)と言ったのだ。(そして実際、彼らは忘れ、女たちは男/ゲイに迎合していることを忘れる。時代が変われば、「媚び」「迎合」の内実も変わってくるのは当然だ。)このとき、聴衆の一人であった筆者は、さすがにパイオニアは凄みがあると感じ入った。ぬるま湯の中で育った彼女の弟子たち(直接の弟子とは限らない)は無防備過ぎる。上野もそこだけは伝えそこなったのかもしれない。
☆6 『ユリイカ』の「総特集BLスタディーズ」において、この語は女性研究者の論文の、次のような、きまじめで素直な女子学生風注記の中にも見出される(88ページ)。「JUNEややおいやBLの中には「表象暴力」の問題が出てくる、という具体的な指摘は、今年八月のおたくやおい部のMLおよび部会を通して知った。」
引用元
石田仁
・石田1「ゲイに共感する女性たち」『ユリイカ』2007年6月臨時増刊号「総特集腐女子マンガ大系」
・石田2「『ほっといてください』という表明をめぐって やおい/BLの自律性と表象の横奪」『ユリイカ』2007年12月臨時増刊号「総特集BLスタディーズ」
★プロフィール★
鈴木薫(すずき・かおる)イギリスのSF作家ジョージ・グレアム・バラードとラジオで言い(JはJojiのJ?)、「若くして夭折した悲劇の詩人ボードレール」と書いた大学の先生はどの程度恥ずかしいのだろう?「今やマンガは真剣に読まれ論じられる対象であるし、それに疑念を投げかける者こそ見識を疑われるだろう」と断言する一方で、三島由紀夫はその気になれば特攻隊に加われたはず(昭和二十年に)と信じている大学の先生はどの程度恥ずかしいのだろう? 『血と薔薇』を男性アングラ文化と表現した大学の先生と、それを書評にコピぺした大学の先生は、どの程度見識を疑われるのだろう?
次回は『密やかな教育 〈やおい・ボーイズラブ前史〉』について書きます(たぶん)。
ブログ「ロワジール館別館」
Web評論誌「コーラ」08号(2009.08.15)
「新・映画館の日々」第8回:〈あたしは
Copyright(c) SOUGETUSYOBOU 2009 All Rights Reserved. |
| 表紙(目次)へ |